|
ルール崩壊
公務員の労働争議権を剥奪する代わりに、人事院の勧告にもとづき給与など公務員の労働条件を確立する制度が設けられている。いわゆる「人事院勧告」というものである。この人事院勧告にそって東京都の人事委員会が東京都の実態に即した勧告を行ない、都内の各自治体ではこの勧告にもとづき職員団体と自治体側の協議が行なわれ、労働条件の見直し等がすすめられている。
この勧告にそった議案が12月議会に小金井市から提案された。中心内容は、職員の期末・勤勉手当の年間支給額を0.1カ月、再任用職員については0.05カ月、それぞれ引き上げるというものである。
ところがこの議案が21日(水)の総務企画委員会で賛成少数で否決され、関連する予算も否決されてしまった。従来、職員団体と自治体側が合意した給与関係議案に、さまざまな思いはあっても賛成してきた自民党と公明党が反対する側に回ったからである。翌日の本会議でも否決されることは必至となっている。主な理由は「今後の市財政の見通しが示されていないなかでの給与アップは賛成できない」というものである。
しかしこの言い分にはムリがある。この間、駅前開発を積極的に推進し、何億もの財源を毎年投入することに賛成してきたのは、ほかならぬ自民党、公明党である。駅前開発が今後の市財政に重くのしかかることや市民に負担を求めることになる、と日本共産党などが指摘してきたことにはいっさい耳をかたむけなかったではないか。逆に「行革」を求め、値上げや負担導入、施策の切り下げを容認してきたのである。
議会のなかには、人事院勧告であっても職員の給与等の引上げには頭から問題視する勢力がいる。理由は「市民のくらしが大変」というもの。たしかに、市民のくらしは深刻である。アベノミクスは格差をいっそう拡大し、若者の半数が非正規雇用に追いやられ、低賃金・長時間労働が横行、年金削減、医療・介護の改悪、負担増が目白押しである。
しかし、だからといって、人事院勧告による給与等の引上げを問題視してよいのか?。先述のように人事院勧告は労働争議権剥奪の代償措置であり、制度として確立され、このことによって労働条件の改善等が保証されているのである。この措置が問題だと言うならば、公務員にも諸外国と同様に労働争議権を付与し、人間らしく働くためのたたかう権利を保障すべきである。それとも、公務員には人間らしく働く権利はないとでもいうのであろうか。
今日、公務員バッシングが大手を振って歩いている。生活保護受給者に対するバッシングも見受けられる。くらしが大変になっているからであり、自分より楽をしていると思える部分に怒りの矛先が向くからである。しかし、くらしを大変にしている元凶は、一般の公務員でもなければ生活保護受給者でもない。富めるものはますます富み、貧しいものはどんどん貧しくなり、世界第3位の経済大国でありながら、庶民にそれにふさわしい暮らしを保証しない自民党・公明党の政治である。そのことに目を向けることこそ、なによりも求められているのではないだろうか。公務員や生活保護受給者に矛先を向けても、悪政の元凶をすすめる安倍内閣には何の痛みも届かないばかりか、悪政を押し付けられている者同士の中でのいがみあいに終始してしまうであろう。
同時に、小金井市側にも一言いいたい。公務員は住民の公僕とならなければならない。国が福祉・医療の改悪を行ない、教育分野でもさまざまな課題を押し付けてくるもとで、市民への負担や押し付けに対する防波堤になることが行政に求められていると私は思う。なのに国の動きに歩調を合わせ、国が示したそのままに負担増、サービス見直しを持ち込み、税金の取り立てに奔走すれば、市民は職員に怒りこそ持っても、心を寄せることにはけっしてならない。市民と職員の間に隙間風のみが吹きつけることになるであろう。
西岡市長の公約は「市民との対話」である。対話ができる環境づくりの一つに、市民のくらしに寄り添う市政運営があると私は思う。自民党や公明党の今回の対応の一因に、市民の気分感情があることは否めない。西岡市長の市政運営のありかたが問われていると言っても過言ではないであろう。
(2016年12月22日付)
制服が一新されるということは
創立40周年を迎えた小金井市立南中学校は、来年4月の新1年生を皮切りにオリジナルの制服に一新する。子どもたちにとって制服が新しくなることは、心踊る出来事である。しかし、手放しで悦べないのが親の側。過日の市議会本会議の一般質問では、このことが取り沙汰された。
質問者の問題意識は「制服の一新は、経済的に苦しい家庭にとっては大変。なんらかの対応策が必要」というもの。現行の制服であれば、兄や姉のいる家庭ならばお下がりが可能であり、知人から譲り受けることもできる。しかし一新となればお下がりはなく、買う以外にすべはない。買えない家庭が出てくるのではないか・・・。質問者の懸念は当然である。
ところが教育委員会の答弁は、負担のことなどどこ吹く風。「新しくなる制服の値段はいくらなのか」の問いに、「教育委員会では、各学校の制服の金額は把握していない」と耳を疑う内容。そのうえで「男子生徒の制服は、従来のものより1,500円から1,700円、5.3%のアップ。女子生徒の制服は従来のものより600円、1.5%程度のアップと聞いている」と、「把握していない」と言いつつ説明した。この数値をもとに計算すると、男子生徒の新たな制服は32,000円余、女子生徒は40,000円余となる。経済的に苦しい家庭でなくとも厳しい金額である。
小金井市は今年度から、就学援助の認定基準の引下げを強行した。引き下げる代わりに、新1年生の就学援助世帯に支給する入学時学用品費を3年間で3,000円アップするという。
その入学時学用品費。南中学校の制服が一新する来年度は2万5,550円(中学1年生)となる。しかし一新される制服は、男子が32,000円余、女子は40,000円余。制服代のほうが支給される金額よりもはるかに高い。
入学にあたって必要となるのは制服だけではない。カバンや上履き、体操着など様々あ
る。しかも小金井市の場合、入学時学用品費の2万5,550円は7月下旬に支給される。それまでの間、保護者は建て替えなければならない。このことを教育委員会は、どうとらえているのであろうか。しかし、教育委員会の答弁や説明からは、痛みに対する理解の言葉は聞こえては来なかった。
いままで述べてきたことは、就学援助の「準要保護」世帯に対するものである。では、生活保護世帯(「要保護」世帯)はどうであろうか。
生活保護世帯に対しても、準要保護世帯の入学時学用品費と同様に「入学準備金」というものが支給される。支給日は入学前の3月。よって、準要保護世帯のような立て替え払いはしなくてすむ。しかし支給額は、昨年も今年も「小学1年生が40,600円以内、中学1年生は47,400円以内」。
仮に、中学1年生の「入学準備金」を限度額の「47,400円」とした場合、南中学校の新1年生の家庭はどうなるであろうか。保護者は47,400円の中から、男子生徒の場合は32,000円余を、女子生徒の場合には40,000円余の制服代を支払う。手元に残るのは、男子生徒が15,400円弱、女子生徒が7,400円弱。ここからさらにカバンや上履き、体操着などを購入しなければならない。到底、足りる額ではない。
「47,400円」というのは通常の入学の際に必要とされる金額である。しかし来年度の南中学校は通常とは異なる。制服が一新する。お下がりもリサイクルもない。「47,400円」から制服代をまるまる支出しなければならないのである。このことを教育委員会や小金井市はどう考えているのであろうか。議会での答弁や説明からは、なんら語られるものはない。恐るべきことである。
制服を一新するのであれば、経済的に困難な家庭への対策をとるべきである。生活保護世帯へは制服を支給し、就学援助世帯に対しては入学時学用品費に制服代を上乗せするなど。そのことに目が行かぬ教育委員会であるならば、子どもの成長発展を語る資格などはない。
(2016年12月12日付)
下水道事業イメージキャラクター
 |
| イラストは小金井市職員が作成 |
「ゆるキャラ」と呼ばれるイメージキャラクターが、多くの自治体で活躍している。全国大会に出場して「ゆるキャラ」チャンピオンに輝き、その名を全国に知らしめるモノまで出るほどに。この私でさえも「ひこにゃん」とか「くまモン」「ふなっしー」という名前が頭に浮かぶ。
小金井市の「ゆるキャラ」はなんだろうか。イメージキャラクターは「こきんちゃん」。しかし彼は、コンテストのような場所には出ない。プライドが許さないらしい。では、ごみ対策課の「くるカメくん」?。「ゆるキャラ」にむいているとは思うが、小金井市の代表となると、「こきんちゃん」の勤務先である企画政策課がその位置を「くるカメくん」に譲るとは思えない。ということは、小金井市には「ゆるキャラ」は存在しないのであろうか。
そんな矢先、市役所内で慌ただしい動きが出てきた。新たなイメージキャラクター擁立の動きである。震源地は下水道課。11月10日の市議会建設環境委員会にイラストが示され、これから市民に愛称を募るというのである。ゆくゆくは「こきんちゃん」や「くるカメくん」と同様に、市民の前に姿を見せたいという。
なぜ下水道課が名乗りをあげたのか。関係者いわく、「水は水道の蛇口を開けばすぐに出てきて、誰の目にも入ってきやすい。けれども下水道は地面の中に埋まり、あまり人々の関心にはのぼらない」。だから「イメージキャラクターを擁立し、下水道の存在を世間にアピールしたい」「縁の下の力持ちがいることを、知ってほしい」というのである。私の目には、エキストラではなく、ごみ対策課や企画政策課のように、下水道課も主役の座に躍り出たいというふうに見える。
名前を付けてほしいという。何がいいだろうか。ちなみに東京都下水道局のイメージキャラクターは「アースくん」。地球という意味である。その「アースくん」に負けない名前が求められる。
ああだこうだと悩みながらも、私の乏しい頭脳はようやく一つの名前を見つけ出した。「がんばるくん」。下水道は地面の下にあり、誰もが認める縁の下の力持ち。しかし九州の博多駅前の道路陥没のように、あのような出来事でもないかぎり、その存在を理解してもらう機会は出てこない。しかし、下水道は日常生活に欠かせない。日の目のあたらないところでも精一杯頑張っている。よって「がんばるくん」。市役所第2庁舎4階の下水道課職員の姿に生き写しである。
「がんばるくん」。言葉の響きは悪くない。力強さもあると思う。下水道課職員のみなさん。「がんばるくん」でどうか。「こきんちゃん」や「くるカメくん」を脅かす存在になること疑いなし!。決定ですな。
(2016年11月17日付)
6施設複合化をゼロベースで見直し
9月定例市議会最終日の10月4日、西岡真一郎市長は、昨年12月市長選挙の中心公約である「6施設複合化」を「ゼロベースで見直す」と表明した。「ゼロベース」とは、「白紙」状態にして、最初から考え直すというもの。
「見直す」こととなった発端は、今年8月31日に示された「6施設複合化プロジェクトチーム」からの「6施設複合化(本庁舎・第二庁舎・福祉会館・図書館・前原暫定集会施設・本町暫定庁舎)の実現に向けた調査、検討」の最終報告書である。この「プロジェクトチーム 」は、西岡市長の指示を受けて結成された庁内組織で、「6施設」にかかわる課長、館長からなる総勢11人の組織。西岡市長が市長選挙で掲げた「6施設複合化」の公約が実現可能なのかどうかを調査・検討することを目的に設置されたもので、いわば市長の附属機関のようなもの。この「プロジェクトチーム」から、市長の公約である「6施設複合化」は“市長が述べているような金額では到底、無理ですよ。他にも待ったなしの事業があるなかで、自分の公約に固執していてはいけませんよ”と告げられたのである。つまり市長の足元から「ダメ」と突きつけられたわけである。
「最終報告書」でそう告げられたとしても、市長は市政のトップである。“6施設複合化が無理だというのならば、このやり方はどうだ?”“複合化する施設数を減らしてはどうか”などの対案を示していくのが、本来のあり方だと思う。ところが西岡市長は「ゼロベース」つまり「白紙」に戻して、一から考え直すというのである。
「公約違反」「有権者を騙した」との指摘が、本会議の質疑で西岡市長に浴びせられた。しかし西岡市長は「3月議会の施政方針で述べた『ジャノメ跡地に庁舎建設』『庁舎建設後にはリース庁舎は所有者に返還』は堅持しているので、『公約違反』『有権者を騙した』の指摘はあたらない」と突っぱねた。しかし、その言い分は通用しない。市長選挙時に西岡市長はどのような公約を行なったのか―――。
西岡真一郎氏の公約は「(1)老朽化した本庁舎、(2)前原暫定集会施設、(3)老朽化した本町暫定庁舎、(4)第二庁舎(リース庁舎)の4施設をジャノメ跡地に移し、(5)老朽化した福祉会館、(6)老朽化した図書館本館もジャノメ跡地に持ってくる」というもので、そのことによって「各施設の改修費、維持管理費が削減され、新たな財源が生まれ、新たな市民サービスも可能」としている。そのうえで、この6施設を集約した「複合新庁舎」の建設費を「約67億円」と試算し、現行の施設をジャノメ跡地に集約することによって市有地の売却が可能となり、「起債(借金)はしますが、市民への新たな負担はありません」とうたっているのである。そして西岡真一郎氏は「子育て環境日本一」を真正面に掲げて、有権者の支持を集めたのである。
この「6施設複合化」を取りやめ、「ゼロベース」「白紙」にするというのは、「公約違反」にあたらないのか?。「6施設複合化は約67億円」で可能と試算しているが、市長の附属機関である「プロジェクトチーム」からは「約109億円」、つまり市長が述べている金額の1.63倍が必要だと指摘している。この点も「ごめんなさい」ですむことなのか。しかも西岡真一郎氏は「市民への新たな負担はありません」「新たな財源が生まれ、新たな市民サービスも可能」と訴えてきた。「だから子育て環境日本一が可能なんだ」と。
おおもとから崩れ落ちた西岡市長の選挙公約。加えて西岡市長は、今年4月から就学援助の認定基準の引き下げを強行し、来年4月からは認可保育料の値上げを行なう。このどこが「子育て環境日本一」だというのであろうか。「有権者を騙した」という指摘は、当然であろう。本会議の質疑では「市長は辞職すべき」と述べる議員もいた。
市長の指示のもとで設置された「6施設複合化プロジェクトチーム」は、16回の会合を開いたという。もし私がプロジェクトチームの一員だったら、こう思うだろう。「なぜ市長の選挙公約を、俺たちが調査・検討しなければならないのか。そんなことは、公約をつくる時点で自らが行なうもの」「市長が6施設複合化を公約に掲げたのであれば、そのための計画案作成を部下に指示し、できあがった計画案が市長の思惑と大きく異なったとしても、それが現実だと受け止めるべき」と。
「ゼロベース」「白紙」とは、どういうことであろうか。私から見れば、「選挙中の公約は全面的に間違っていました。降参します」と見て取れる。「6施設複合化で新たな財源が生まれ、新たな市民サービスも可能」も、全面降服によって、空手形となってしまった。「市長は辞職すべき」の声は当然であろう。
「ゼロベース」「白紙」に対する質疑は昼食休憩や夕食休憩、答弁調整などをはさみながら、実に9時間45分にもおよんだ。この長時間にわたる質疑を経てもなお、私には理解できない部分が残る。なぜ西岡市長は「ゼロベース」「白紙」へといっきに向かってしまったのか。
最終報告書が示された8月31日は、9月定例市議会の3日目である。9月1日からは一般質問が始まり、定例市議会の終盤には決算委員会も控えている。だから「最終報告書に対する見解や新たな方針を示すには時間的余裕がないので、もう少し時間がほしい」という選択もあったはずである。なぜバンザイしてしまったのか。バンザイせざるをえないほどに自身の公約に甘さがあったということなのか、それとも考えるだけの余裕はもはやなく、バンザイしたほうが気が楽、肩の荷が下りると判断したのか。あるいは別の理由が存在するのか。いずれにしても、「ゼロベース」「白紙」は想定外の展開であった。
置き去りにされたのは市民である。なかでも福祉会館の建設を待ち望む方々にとっては、一からのやり直しとなった。稲葉前市長の時には、まがりなりにも本町暫定庁舎敷地に福祉会館の建設という目標があり、スケジュールも示されていた。いまは「白紙」である。だから、市長を応援した民進党含めて、議会が全員一致で「新福祉会館と新庁舎の早期建設を求める決議」を西岡市長に突きつけたのは当然である。
(2016年10月6日付)
就学援助費支給条例を議員提案
子どもの貧困が大きな社会問題となっています。昨年、政府が発表した2012年の最新数値によると、日本の子どもの貧困率は16.3%、6人に1人の割合となっており、年々増加しているとのこと。今年の3月1日に、山形大学の戸室健作準教授が独自に公表した2012年の「子どもの貧困率」調査では、東京都全体では10.3%とされており、全国水準よりは多くないものの、それでも10人に1人は「最低生活費以下の収入しか得ていない世帯」で暮らしていることになります。
そのことから今年の4月6日、参議院の地方消費者問題に関する特別委員会で答弁に立った石破茂地方創生担当大臣は、子どもの貧困が「貧困の連鎖・拡大を生みかねない大問題である」と認め、都道府県において傾向を把握して対策をとること、地方創生の観点から厚生労働省と連携して対応していくことに言及しました。
私は6月議会の一般質問でこのことを紹介するとともに、子どもの貧困対策の取り組み充実の観点から、「こども食堂」など、こどもの居場所づくりの取り組みに対する支援を求めました。また、今年4月から小金井市が、小中学校児童・生徒の就学援助の認定基準の段階的引き下げに着手しはじめたことに対して、引き下げの中止を求め、小金井市独自の施策「給付型奨学資金制度」の充実を求めました。
「こども食堂」に対する支援については、「他自治体の取り組み状況を調べたい」との答弁があり、「給付型奨学資金制度」に対しては「充実」の言及には至らなかったものの、現行制度を守る意思を担当部長が表明しました。しかし、就学援助の認定基準引き下げに対しては、方針どおりに引き下げる答弁に終始しました。
そのことから、9月議会で日本共産党市議団は、就学援助の認定基準引き下げをやめさせ、制度の改善・充実を行なうための条例提案を準備。あわせて、条例提案を視野に入れた一般質問を私が担当しました。
条例案の準備作業は、議会事務局の悲鳴に近い協力のもとですすめられ、9月21日の本会議で、他会派と共同で「就学援助費支給条例(案)」を上程。10月24日(月)の厚生文教委員会で質疑されることとなりました。
9月21日の本会議での条例提案説明は私が担当。数日前に条例案が完成し、本会議前日に、条例案を準備された担当部局から条例案の構成についてレクチャーを受け、その夜に、翌日の本会議提案に向けた原稿を作成するという急ピッチの作業となりました。以下は、本会議で条例案を提案した際に読み上げた原稿です。
就学援助費支給条例(案)の提案説明書
就学援助費支給条例の提案説明を行ないます。
提案理由は、条例に明記されていますように「低所得世帯の就学児童または生徒の保護者に対し支援を拡充するため」との理由からです。御存知のように、2014年1月17日に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が施行されました。法律の趣旨は「子供の将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子供が健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子供の貧困対策を総合的に推進すること」とされています。その趣旨に沿って、就学援助制度の充実をはかるというのが、今回の条例提案の中心的な眼目です。
条例の基本は、現行の小金井市の就学援助費支給要綱をもとに作成し、条例化するにあたって、一定の整理を行なっています。
それでは、わかりやすくするために、現行の「要綱」と今回の「条例」との異なる点を述べさせていただきます。
第1に、就学援助費支給対象世帯であり、四月から小学1年および中学1年になろうとする児童・生徒に対して、入学する前に、就学に必要な学用品や通学用品にかかる費用を支給するというものです。その額は、小学1年、中学1年ともに現行の支給額よりも1万5千円、上乗せを行ないます。その金額が最後の部分の「別表第3」第4条関係の表、「入学時学用品・通学用品費」の部分の「準要保護者」の小学生3万6,470円、中学生の3万9,550円というものです。金額を引き上げる理由は、現行の支給額と最低限必要とされる額との間に、小学1年生では1万3,500円程度、中学1年生では3万6,500円程度もの開きがあるからです。しかも、入学時学用品・通学用品費の対象費目には、購入費が合計で1万円にものぼる体育着と水泳用品が明記されていません。よって、上乗せを行なうものです。
現行の「要綱」では、「準要保護」の場合、就学に必要な学用品や通学用品にかかる費用は7月下旬に支給されます。つまり、経済的に苦しい家庭でありながら、入学前に保護者側でお金を工面しなければならない事態となっています。今回の条例は、保護者側が一時的にでも負担せざるをえない状況ををなくそうというものです。文部科学省は昨年8月24日付で「通知」を出して、一時的に負担せざるをえない状況をなくすことを求めています。この「通知」に沿った支給方法に改めるということです。
第2に、今年度から「準要保護」の生活扶助の認定基準が段階的に引き下げられ、昨年度までは「1.8」 だったものが、今年度は「1.7」となりました。「1.7」に引き下げられたものを「1.8」に戻すというものです。2年半前に施行された「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の趣旨に沿った対応を行なうというものです。
第3に、学校納付金である「クラブ活動費」「生徒会費」「PTA会費」を、「準要保護」の就学援助費の支給対象項目に加えるといものです。その額は「実費」、つまり、納付すべき額を支給するというものです。2010年度から「クラブ活動費、生徒会費、PTA会費」が生活保護の補助費目に追加されました。「準要保護」に対しても、就学援助の支給費目に加えるというのが、文部科学省の「通知」文の趣旨となっています。その趣旨に沿った措置を行なうというものです。
以上、述べた点が、条例の第2条から順次、反映されています。なお、「別表第1」と「別表第2」のそれぞれの「住宅扶助」について、現行の「要綱」では「知事承認額を限度とし、その実費」と明記されていますが、条例化にあたって、わかりやすくするために、金額を明示しました。
条例の施行日は「規則で定める日」としています。条例が可決されれば、就学援助費支給のためのシステム変更が必要となりますが、システム変更は4月1日を基準としていますので、入学する前に、就学に必要な学用品や通学用品にかかる費用を支給する規定は、今年度末時点ではシステム上、間に合いません。よって、早くても2018年4月に入学する児童・生徒を対象とした施行日が設けられることになります。
最後になりますが、条例化で就学援助制度の充実を予定していますが、現行の就学援助費支給額とくらべて、973万円の予算増が必要になると試算しています。内訳は、新入学予定児童・生徒への就学援助費上乗せ分で234万円、「準要保護」の生活扶助の認定基準を 「1.8」に戻すことで594万円、学校納付金の「クラブ活動費、生徒会費、PTA会費」で145万円です。
以上、ざっぱくではありますが、提案説明を終わらせていただきます。「子育て環境日本一」にふさわしい本条例に、多くの皆様方がご賛同いただけますよう、心からお願い申しあげます。
以上。
私は本会議で、この原稿を脇目もふらずに読み上げました。ところが最後の段落、「以上、ざっぱくではありますが、」の文字を何をどう思ったのか、「以上、ざっくばらんではありますが、」と音読。脇に居並ぶ共同提案の面々(全員女性)からは「ざっぱく!」の声が一斉に飛び、議場内は、議員側も部局側も大爆笑。「へっ?・・・」。歳をとるとはこういうものなのか。原稿すらまともに読めない身になってしまったと、「57歳」をしみじみと感じる年頃となりました。おかげで議場内の雰囲気は和らぎ、本会議質疑はなく、資料要求を受けるのみとなりました。
考えてみれば、「ざっぱく」という言葉を私は使ったためしはなく、逆に「ざっくばらん」は、私の存在そのもの。使い慣れない言葉は使うものではないと、あらためて思う今日この頃です。
(2016年10月3日付)
年間予算が成立
5月24日未明の臨時市議会本会議で、小金井市の2016年度予算が賛成多数で可決・成立した。賛成12人、反対11人の僅差での成立である。可決・成立した年間予算は3月定例市議会で否決された内容に加えて、社会福祉協議会事務所の移転経費への補助金が上乗せされただけのものである。だから、これだけで見るならば、3月定例市議会と同じく、大差で否決されるのは当然といえるものである。ところが、そうはならなかった。自民党と公明党が賛成の側に回ったからである。
前日23日の午前10時から、年間予算への質疑は始まった。いち早く質問に立ったのは、自民党の中山議員である。彼はいきなりこう切り出した。「庁舎と福祉会館の2施設複合化であれば、ジャノメ跡地に早期建設できるのではないか。福祉会館を早期に建設すべき」。この質問を受けて西岡市長は、「答弁調整のため、休憩を」と発言。出だしから休憩となってしまった。しかし、このやりとりを見て、議場に居合わせた者は誰もが、シナリオが事前に作られた出来レースだと感じ取った。案の定、再開された本会議で西岡市長は「6施設複合化の早期実現は困難。庁舎と福祉会館の2施設複合化を優先的にすすめる」と発言した。
西岡市長は「2施設複合化」(正確には、福祉会館、本庁舎、第二庁舎、本町暫定庁舎の4施設複合化)に方針転換した理由として、熊本地震を受けて新庁舎の早期建設が求められていること、福祉会館の早期建設が求められていることを挙げた。しかし、新庁舎を早期に建設し、耐震化がされていない本庁舎の使用を一日も早く終えることは、熊本地震を待たずとも、稲葉市長時代に実施した本庁舎の耐震診断結果から明白となっており、福祉会館の早期建設についても今年1月の市議会全員協議会や3月定例市議会で、議会側から再三再四、求められていたことである。西岡市長の「理由」は付け足しでしかない。
だれもが思ったことは、年間予算に賛成する条件として自民党側が、(1)「6施設複合化」を断念すること、(2)福祉会館をジャノメ跡地に早期建設すること、を持ち出してきたのではないかということ。一方、なんとしても年間予算を可決させたい西岡市長は、自身の方針にそぐわないものであったとしても、自民党側からのアプローチになんらかの形で応えたい―――。つまり、手詰まり状態であった西岡市長に対して、渡りに舟の自民党側からの呼びかけであったといえる。
この点を私なりに推察すると、以下のようになる。自民党と西岡市長の支持母体に、大きな開きはない。前市長・稲葉氏の支持母体の一定部分が昨年12月の市長選挙で西岡陣営に回ったために、稲葉市長の後継者であった五十嵐氏は落選してしまった。稲葉氏の支持母体の一定部分が西岡市長側に付いたとはいえ、西岡市長の本体は民主党(民進党)であることから、自民党や公明党は背を向けざるをえない。その結果が3月定例市議会での年間予算否決となった。しかし今回の臨時議会を前に、自民党や稲葉前市長の支持母体であり西岡市長の支持母体でもある関係団体が、自民党に予算に賛成しろとの圧力をかけてきた。しかし、自民党としてもそう簡単に「わかりました」とは言えない。だから、西岡市長の公約の中心となっている「6施設複合化」の断念を迫り、「公約履行は不可能」を世間に知らしめたい―――。
この場合に西岡市長に迫る「交換条件」は、西岡市長が乗れるものでなければならない。もし西岡市長に拒否されたら、自民党は予算賛成に回ることができなくなるからである。だから、市役所内部で可能性として取り沙汰されている「ジャノメ跡地での庁舎と福祉会館の複合化」であれば、西岡市長の公約と矛盾するものでもなく、西岡市長は首を縦に振るのではないか。
一方、西岡市長としても「6施設複合化」を「断念する」とは言えない。「断念する」と言ったとたん、「公約違反」「不可能な公約を掲げた」と攻撃されるのは目に見えているからである。だから西岡市長は次のように答弁した。「6施設複合化の一括整備については、早期の実現は困難な状況だと考え、いったん立ち止まって整理することにいたします。これまで検討した経過を踏まえ、福祉会館機能と、新たな防災拠点となる庁舎の複合化を優先してまいります」。
「早期の実現は困難」との言葉を入れることによって、「6施設複合化」は「早期」は難しいが「時間をかければ可能」との位置に座らせ、「優先して」の一言を加えることによって、残る施設を加えた「6施設複合化」は公約どおりに進めますよとの意思表示を示すものとなったのである。
自民党の中山議員は「明らかな方針転換ではないか」と、西岡市長に詰め寄る。しかし西岡市長は「方針の一部変更」と述べ、あの手この手の質問を受けても、「方針転換」と受け止められる表現はなんとしても避けなければとの固い決意をにじませていた。しかし西岡市長の次の一言は、自身の心の揺れを表すものでもあった。「『方針の一部変更』、これを各議員がどのように受け止めるかは自由」。中山議員は、西岡市長が必死に踏ん張る言葉「方針の一部変更」を前に、刀を鞘に納めざるをえなかった。
自民党と公明党が賛成に回った。しかし、3月議会で両党が否決する側に立った内容とどこがどう違うというのであろうか。両党の言い分はおおよそ次のようなものである。公明党は「本町暫定庁舎敷地での福祉会館建設に向けた取り組みがされておらず、3月議会と変わるものではない。しかし、暫定予算によって生じた市民生活への影響を回避する必要があるため、賛成する」。市民生活を考えて、やむなく賛成するというものである。一方、自民党は違う。「2施設複合化は我が党が早くから主張していたもの。それを市長が受け入れたことから、賛成する」。この発言には驚いた。3月議会で自民党は、稲葉市長時代の「本町暫定庁舎敷地での早期の福祉会館建設」を求めていたではないか。だから、3月定例会ではそのことを前提とした福祉会館建設に向けた市民検討委員会設置の条例提案を日本共産党と公明党、自民党の共同提案で行なったのである。予算に賛成するための理由付けとはいえ、ここまでくると「呆れ返る」の一言である。公明党が述べる理由の方が、実に正直だと私は思う。
年間予算が可決されたあと、自民党から「付帯決議」なるものが提出された。年間予算に対する付帯決議である。しかし、そこで明記された内容は、すでに西岡市長のもとで実施に移されているもの、あるいは西岡市長が「行ないます」と答弁している内容の羅列であり、新たなものは何一つ明記されていない。いったいこの決議はなんなのか?と、議場の面々はいぶかしげに、あるいは半ば呆れ返る思いで眺めた。
この場合の「付帯決議」とは、年間予算に賛成する代わりに、ここで明記する内容を実施せよと市長に迫るものである。いわば、賛成するための「条件」を示したものとなる。しかるに、すでに「実施します」「実施しています」と答弁しているものを明記しても意味はない。なのに、なぜかこのような意味を持たない付帯決議を、自民党が提出したのである。
さらに滑稽なのは、この付帯決議が賛成少数で否決された。公明党が反対したからである。公明党は、いっかんして「本町暫定庁舎敷地での福祉会館の早期建設」を主張している。しかし示された付帯決議は、ジャノメ跡地での2施設複合化を前提としている。公明党の主張とは相いれないのである。輪をかけて滑稽なのは、この付帯決議に民主党が賛成したということ。自分たちの支える西岡市長が提案した年間予算は、不十分だというのであろうか。付帯決議に賛成するとはどういうことなのか。民主党議員はそのことを考えたことがないのであろう。付帯決議が否決されたことから、自民党は立つ瀬を無くしてしまった。
年間予算が成立した。自民党と公明党が態度を一変させたからである。西岡市長は安堵しているが、しかしこれからが西岡市長の真の意味での正念場となる。なぜなら、自民党と公明党の応援なしには、予算が通らない事実を痛いほど知ることとなったからである。
西岡市長の政策と稲葉前市長時代の政策は、基本的には変わらない。だから、自民党と公明党が許容する政策を打ち出すことになる。しかし、自民党も公明党も、民主党が支える西岡市長を、そうやすやすと応援するということにはならない。なんらかの揺さぶりをかけてくることは必定である。西岡市長のこれからは、自民党と公明党の顔色をうかがいながらの市政運営になっていく。
(2016年5月25日付)
西岡市長の行革は市民意向調査をどのように扱うのか
西岡市長は今年の秋に、新たな行財政改革大綱を発表しようとしている。通常の流れであれば「第4次行財政改革大綱」と呼ぶべきところであるが、稲葉市政から西岡市政に変わり、西岡市長の公約に沿った施策を打ち出す必要があることから、新たな角度での取り組みがすすめられようとしている。その骨格案(たたき台)が5月13日の市議会行財政改革調査特別委員会に示された。
名称は「今後の小金井市行財政改革」。2016年度から2020年度までの5年間を予定し、2016年度と2017年度を「緊急対策」の期間に、2018年度から2020年度までを「経営改革」の期間に、計画期間終了後の2021年度からは「魅力向上」の期間に位置付け、この3段階を経たあかつきには、小金井市の「自治体経営新時代」を迎えるという。
では、「自治体経営新時代」へと突き進むために西岡市政はどのような「行財政改革」を取り組むというのであろうか。この日、示された骨格案(たたき台)には「窓口改革の推進」や「民間活力活用・市民協働」「受益者負担の原則徹底」「市民サービスのコスト管理」など、稲葉市政時代に見られた文字が踊っており、どこがどう違うのかと言いたい。
庁内の担当者は、新たな行財政改革大綱を策定するにあたり、2015年3月27日に市長の諮問機関である行財政改革市民会議が当時の稲葉市長に提出した『答申書』を「参考にする」、稲葉市政時代の2015年3月下旬に実施した第4次行財政改革大綱策定にともなう『市民意向調査』を「活用したい」と述べている。つまり、『答申書』や『市民意向調査』が、西岡市長の「行革」方針の基礎部分になるというわけである。だから、稲葉市政時代に見られた文字が骨格案にも登場してくるのである。
行財政改革市民会議の『答申書』は、市民への負担増や有料化、市民団体等の補助金・交付金の見直し(削減)、保育園・学童保育所・図書館本館の委託化・民営化などに加えて、市民が利用する集会施設の統廃合を打ち出している。これを小金井市は「参考にする」と言うのである。一方、「活用したい」という『市民意向調査』は、設問の仕方も回答項目の記述の仕方も、莫大な財源を投入し借金を背負う大型開発を不問にし、“市財政は限られているのだから、ガマンするか負担増か。事業の見直しや委託化もやむなし”の方向に導く意図的な構成となっている。全体の流れは、行革市民会議の『答申書』に沿うものとなっているのである。
しかし、この『市民意向調査』は見方によっては、さまざまな判断・考え方に立つことができるものになっている。たとえば、「市が実施している事務や事業の見直しを推進」「不必要な事業は廃止し、必要な事業を重点化する」に、回答者の支持が集まっているが、「不必要な事業」とは何なのか?、「必要な事業」とは何なのか?、見直すべき「事務や事業」とは何のことを指すのか 小金井市が実施した『市民意向調査』には、対象となる事務や事業の説明文が一切、示されていない。だから、回答者によっては、駅前大型開発や都市計画道路整備が「見直すべき事業」「不必要な事業」だと思っているかもしれないし、あるいは稲葉前市長が企図していた保育園や学童保育所、児童館の業務が「見直すべき事業」だと考えて回答した人がいるのかもしれない。いずれにしても、行革市民会議の『答申書』に沿った『市民意向調査』の回答状況だとは、どこをどうみても言い切れないのである。
5月13日の行財政改革調査特別委員会でそのことを指摘したところ、担当課長はそのことを認め、「『聖域なしの見直し』としているので、見直すべき事務・事業が具体的にどれなのかと言えるものではない」と答弁。「不必要な事業」「必要な事業」についても、「個別には答えられるものではない」と述べた。
しかし小金井市は「見直すべき事務・事業が具体的にどれなのかと言えるものではない」と述べる『市民意向調査』を「活用する」としている。西岡市長のもとで、莫大な財源を投入し借金を背負う大型開発や都市計画道路整備を不問にし、市民負担増・有料化、施設の委託化・民営化、集会施設の統廃合を中心とした「行財政改革大綱」が打ち出される事態となれば、結局は、市長の公約と行革市民会議の『答申書』に重きを置いたものと指摘されるであろう。そうなれば、『市民意向調査』はいったいなんだったのかと、私は激怒さぜるをえない。
担当課長は「骨格案をもとに庁内で検討し、7月14日の行革市民会議に計画案を提示する」と言う。「計画案」に明示されるであろう「見直し対象となる事務・事業」をどのような根拠で選択したのか、そのことを明確にする責任が担当課には求められる。
(2016年5月18日付)
※PDFファイルで「『市民意向調査』の設問項目と回答項目概要」掲載
管理職者の大幅移動
拝啓、西岡市長殿。4月1日の小金井市役所の管理職者の大量人事異動に、私は正直、驚いています。部長職者は半数が、課長職者は8割程度が異動したのではないでしょうか。一般的には、市長が代われば管理職者の異動も多くなると言われます。しかし、これほどまでに動かすのは、行き過ぎなのではないでしょうか。
たしかに、あなたがやりやすいように、旧政権時に形成された体制を組み直したいというのはわかります。しかし、程度と時期というものを考えるべきだと思うのです。
管理職者の多くは、西岡市長が誕生したことから、4月の人事異動はある程度は避けられないと考えていたと思います。ですから、慣れ親しんだ部署から離れることを覚悟していた人もいるでしょう。しかし、程度というものがあります。あなたが発令した人事異動は、あまりにも激しすぎると思うのです。就任してわずか1年で異動というのもあれば、同じ部署の部長と課長がともに異動というのもあります。ひどいのは、課長が異動し、その下で働いていた係長も異動というところもあるということです。これでは、業務自体が滞ってしまうのではないでしょうか。
よく言われているのは、人事異動は部長や課長を先に決めて、その下で働いている係長や主任は、上司の異動状況を見て判断すべきというものです。これが、日常業務に支障が起きないようにするための鉄則だというのです。しかし西岡市長のもとで行なわれた人事異動は、この鉄則がふまえられていないように思います。
西岡市長殿。なぜ、このような無理筋な人事異動を行なったのですか。西岡市長自らがこの配置を考えたのですか。それとも、天からの指示があったのですか。議会サイドからは、まさかとは思いますが、3月定例市議会での福祉会館建替え問題にかかわっての報復人事という声が囁かれていますし、行革を推進するための体制づくりとも言われています。いずれにしても今回の人事異動は、評判がかんばしくはありません。
「人は城、人は石垣」と言います。職員の適材適所を見極め、能力・技術を発揮させることができるかどうかが、どんな部署や職場においてもカギとなります。そのカギを握っているのが、西岡市長、あなたなのです。しかし、職員の中から漏れ聞く声は、「人は城、人は石垣」とはほど遠いものとなっています。これでは、職員のモチベーションも下がっていくのではないでしょうか。
西岡市長殿。いまのあなたには、まったくゆとりが感じられません。議会が少数与党ということもありましょうし、市長に就任してそんなに経っていないということもありましょう。加えて、職員のなかに気心しれた人がいないというのもあるでしょう。だとしたら、まずは職員の心をつかむことからはじめるべきだったのではないでしょうか。私が市長だったら、人事異動は最小限に抑え、すくなくとも半年間は動かさずに、職員が安心して同一場所で働けるように心がけます。
西岡市長殿。あなたが小金井市の市議会議員だった時は、つねに笑顔がありましたね。議会野球部ではサードを守り、ピッチャーの私の投げる一球ごとに守るポジションを移動させ、たえずマウンドの私とコンタクトをとっていましたね。けれどもいまのあなたには、コンタクトどころか目を合わせることさえ見受けられません。あの頃のあなたは、どこへ行ってしまったのですか。
新年度予算が暫定予算になってしまいました。笑顔を取り戻し、心にゆとりを持つためには、猪突猛進ではなく周囲の声に耳を傾け、時には自身の考えを改める勇気が必要です。そうすれば、おのずと人心が集まり、議会運営もスムーズにいくようになると思うのです。ただし、私みたいな優柔不断な人間にはならないでくださいね。市長は大きな権限を持ち、その一挙手一投足が市役所を左右するものとなるのですから。
(2016年4月2日付)
6施設複合化は断念せよ
拝啓、西岡市長殿。あなたがまっすぐ進む人であることは、十分に存じあげております。けれども時には立ち止まり、周囲を見渡すことも必要なのではないでしょうか。公約を掲げて市長に当選し、一途にその公約のもと突き進もうとする気持ちは理解できます。けれども「6施設複合化方針」は、ちょっと考えものです。あまりにも無理すぎます。 すでに多くの方々が指摘するように、ジャノメ跡地での複合化計画は、実現の時期がいっこうに見えません。リサイクル事業所など既存施設の移転が不可欠であり、貫井北町の中間処理場の建替えスケジュールに合わせざるをえないからです。
なによりも、市役所庁舎に加えて図書館本館や福祉会館を合築することが、現行の容積率や用途地域で可能なのでしょうか。予算委員会での担当課の答弁では、変更するためには、地区計画を立てることが必要とのこと。そのためには近隣住民への説明や理解など、それ相応の準備と労力が必要になります。そのための時間も必要ということを、あなたは理解されているのでしょうか。
予算委員会の質疑では、新たな事実が明らかになりました。ジャノメ跡地の複合施設には、公民館本館も含まれるというのです。生涯学習施設の本拠地となるわけですから、当然にいくつかの学習室も併設されることでしょう。そのスペースも確保しなければなりません。予定する施設をすべて複合化したら、全体でどれくらいの床面積になるのでしょうか。見当もつきません。
さらに驚いたのは、公民館本町分館は「廃止」ではなく、「休止」だというのです。ジャノメ跡地に複合施設が完成し、公民館本館がそちらへ移ったあかつきには、公民館本町分館が復活するというのです。でも、ちょっと待ってください。今定例会に「本町分館廃止」の議案が提案されているのですよ。本会議の説明でも、「廃止」と明確に言っていたではありませんか。さらに驚いたのは、「廃止」の議案を議会に上程しておきながら、公民館のあり方を議論する公民館運営審議会には諮問していないというのです。西岡市長、公民館運営審議会はなんのためにあるのですか。分館の「廃止」は、公民館事業の一大事ではないのですか。運営審議会委員の存在を無視しているとは思わないのですか。
複合施設化は、社会福祉協議会にもしわ寄せがきています。福祉会館が3月末で閉館となるのは、いたしかたないことです。だから、社会福祉協議会は閉館後に移転の準備を行ない、6月からは別の場所で事業を再開することになります。
そのため、社会福祉協議会は移転先を探しています。民間ビルの空き室を一所懸命、探し歩いています。ところがなぜか、社会福祉協議会とは関係のない部分も、社会福祉協議会に探させているというのです。「悠々クラブ連合会事務室」「集会室」です。なぜ、これらの部分まで探させているのでしょうか。3月14日の予算委員会での担当課長の説明はおおよそ次のようなものです。「複合施設化の方針によって、『仮移転』ではなく『本格移転』の様相となり、民間ビルの空き室に入れるべき施設が増えてきた」「ミニ福祉会館的様相に変わってきている」。私は言いたいのです。社会福祉協議会が探すのではなく、小金井市が探すべきではないですか。
私は、担当課から議会に提出された資料「社会福祉協議会運営補助金の内訳」を見て、腑に落ちない部分に直面しました。この資料は、社会福祉協議会に今年度支払う補助金の内訳ですが、なぜか、民間ビルの一室に移るための経費が入っていないのです。3月14日に質問しました。「入っていないのではないか」。これに対して担当課長は入っていないことを認め、「当初予算で組んでいる運営補助金のなかで対応してもらい、6月の補正予算で対応する」と言うのです。
ちょっと待ってください。「6月補正で対応する」と言いますが、補正予算を執行するのは7月からですよ。5月末で福祉会館を撤収するのに、移転費用は7月にならないと出ないというのでは、6月はどうするのですか。「運営補助金のなかで対応してもらう」と言いますが、補助金の95%は人件費ですよ。どうやって移転費用を工面しろというのですか。あまりにも無茶苦茶です。小金井市が契約し、契約金額と移転費用を小金井市が工面すべきです。
図書館協議会は現在、中長期の計画を議論し、中央図書館構想も議論しています。けれども西岡市長の方針は、ジャノメ跡地の複合施設に図書館本館を入れるというものになっています。当然に、複合施設のなかに図書館本館を入れることが可能なのかどうかを、図書館協議会は議論することになります。となると、この間議論してきた中長期計画や中央図書館構想は、どうなるのでしょうか。ジャノメ跡地の複合施設に図書館本館を入れることが、中長期計画の中心課題になっていくのではないでしょうか。中央図書館構想は、どうなるのでしょうか。しかも、新年度の図書館協議会の予算は4回分しかないのです。どうやって複合施設化の議論をすすめろというのでしょうか。
公民館運営審議会や図書館協議会、それに福祉会館の閉館など、これまで検討してきた計画・スケジュールのなかに、突如割り込んできた「6施設複合化方針」。いま、関係する部署はテンヤワンヤの状態です。それが一因かどうかはわかりませんが、新年度から小金井市は就学援助の支給基準を市長・副市長・教育長の理事者判断で、引き下げようとしていました。この引き下げによって、新年度は70人前後が支給対象から外されるというのです。ところが、支給基準の引き下げを教育委員会に諮問していないことが発覚しました。なんということでしょう。公民館本町分館を「廃止」する議案も、公民館運営審議会には諮られていません。小金井市の行政運営の歯車が、狂いはじめています。
ジャノメ跡地での「6施設複合化」が可能かどうかを8月末まで「検証」するとのことですが、どうやって「検証」するというのですか。「検証」は10人の課長によるプロジェクトチームで行なうとされていますが、各施設の規模が出揃うまでに相当な期間が必要ですし、各施設それぞれに役割や開館曜日・時間が異なるなかで、どのようにして施設を合築させればよいのかなど、検討しなければならない要素はあまりにも多いのではありませんか。しかも私の目からすれば、施設の複合化に精通した専門家は建築営繕課長くらいだと思うのです。なのに「検証」期間が8月末までとは、極端に短すぎます。とはいっても、時間がかかればかかるほど、困るのは市民です。
ところで、「検証」の結果「不可能」となった場合、どうなるのでしょうか。ジャノメ跡地に市役所を建てることはハッキリしていますので、「6施設」ではなく、「2施設」あるいは「3施設」くらいに舵取りを変えるのでしょうか。それとも、市役所単独でいくのでしょうか。ふりだしに戻るようなことにでもなれば、たんなる時間の浪費と見られますよ。
西岡市長殿、小金井市の行政運営がギクシャクしています。市役所のだれもが、この先どのようになっていくのか不安のなかで仕事をしています。たしかにあなたは「6施設複合化」を公約に掲げて市長に当選しました。その公約を実行に移すのは当然でしょう。しかし、この公約はあまりにも行政運営の柱を揺さぶるものとなっています。柱のブレが大きければ大きいほど、被害も広範囲に及んでいきます。私は懸念するのです。市長の手足となるべき職員や部課長の気持ちが沈んでいくことを。行政運営の歯車が、さらにおかしくなっていくことを。
西岡市長殿、「6施設複合化方針」を断念すべきではありませんか。8月末までの6カ月間で、どのような「検証」ができるというのですか。部課長の声に静かに耳を傾けるべきではありませんか。立ち止まって回りを眺めるべきではありませんか。それこそがいま、あなたに求められているものだと私は思うのです。
(2016年3月22日付)
都市計画道路問題への推論
都市計画道路というものがある。五十年以上も前に、お偉い人が地図上に勝手に線を引いて決めた道路築造計画である。この道路築造計画を10年以内に推進させるという計画を東京都が決めようとしている。「東京における都市計画道路の整備方針」=「第四次事業化計画」と呼ばれるものである。この「第四次事業化計画」に、小金井市内を通過する2つの路線が明示された。
一つは「3・4・1号線」。国分寺崖線を斜めに横断し、小金井市のウリにもなっているハケの緑や坂道をなぎ倒していく路線である。そしてもう一つが「3・4・11号線」。国分寺崖線の坂上から坂下へと南北に計画線が引かれている路線である。こちらもハケの緑をなぎ倒し、公園の緑地や景観を破壊するものとなっている。
この2つの路線の道路築造を“10年以内に優先的に行なう”という「第四次事業化計画」(案)が公表されたのは昨年の12月18日。西岡市長が市長に就任して間もない時期である。公表されるや、当該の住民は言うに及ばず、小金井市の自然をこよなく愛する多くの市民が「エライコッチャ」と立ち上がり、市長へ要望書を提出し、市議会にも計画見直しや中止を求める陳情書・要望書を提出する事態となった。ところが、なぜか西岡市長の態度が煮え切らない。「計画反対」とは言ってくれないのである。
折しも西岡市長は、自身の選挙公約である「蛇の目跡地での市役所庁舎、福祉会館、図書館本館の複合施設化」が実現可能なのか、福祉会館の建替え計画はどうなるのかなど、議会側から説明を求める申し入れがあり、それへの対応に迫られるとともに、さわらび学童保育所の委託化失敗の善後策にも追われるというドタバタのなかでもあった。新年度予算編成の締め切り段階とも重なり、就任したての西岡市長にとっては、頭の中が真っ白状態ではなかったろうか。もしかすると、都市計画道路どころではなかったのかもしれない。しかし市民としては、市長に明確な態度をとってもらいたいのである。
3月定例市議会の施政方針質疑や一般質問で都市計画道路問題が取り上げられ、質問者は西岡市長の見解を何度も問いただした。ところが西岡市長は「市民や議会からいただいた意見は適切に東京都に伝えていきたい」と述べるのみで、なんら見解を述べることはしない。述べることを避けているように見えるのである。なぜそうなるのであろうか。
小金井市は、東京都からの今回の「第四次事業化計画」に『市施行』で入れるべき路線があるか?との問い合わせに対して、「該当ありません」と答えている(昨年10月15日)。ところが東京都が昨年11月11日の第6回市町検討部会合同会議に提示した「第四次事業化計画」(案)には、小金井市が「該当ありません」と回答しているにもかかわらず、なぜか「3・4・1号線」と「3・4・11号線」が登場している。それも『都施行』という位置づけで。都市整備部長は3月3日の百瀬議員の一般質問に対して、「3・4・1号線」は『地域の安全性の向上』から、「3・4・11号線」は『自動車交通の円滑化』を理由に「優先整備路線に入れたと聞いている」と述べる。しかも「聞いている」という他人事のような言い方で。
なぜ、東京都は優先整備路線に2つの路線を入れたのであろうか。しかも小金井市が「該当ありません」と回答しているのに。私は思う。2014年7月18日付で小金井市の都市計画課が各課に調査依頼し、各課から寄せられた意見のなかに「3・4・1号線」と「3・4・11号線」の整備を求めるものがあったからではないか。
小金井市の都市計画課は2014年7月18日付で、「次期優先整備路線の選定において、市が優先して整備する都市計画道路の選定の参考にするため」に、市役所の各課あてに、小金井市内の道路事情を把握するための調査を依頼した(「次期優先整備路線」とは「東京における都市計画道路の整備方針」=「第四次事業化計画」のこと)。この調査依頼によって各課から意見が寄せられ、そのなかに今回の「第四次事業化計画」に登場している「3・4・1号線」と「3・4・11号線」の記述が出てくるのである。
「3・4・1号線」に対しては、「交通量が多いなか、白線のみの歩道を歩いて通学するのが危険であるという意見が、保護者からでている」(教育委員会学務課)。「連雀通りの歩道が狭く、歩道も途切れてしまう箇所があり、危険を感じている、との声が市民から複数件寄せられている」(広報広聴課)。一方、「3・4・11号線」に対しては、「都道3・4・11号線の東側にある市道573号線については、東八道路への抜け道となっており、以前より通行量や走行スピード等による近隣住民からの苦情が絶えない箇所となっている。今後、都道3・4・11号線が東八道路まで拡張されることにより、上記の課題が解消され、また、市内全域の円滑な交通機能を確保できることが期待できる」(交通対策課)。「連雀通りから二枚橋へ抜ける道が狭隘している。車のすれ違いはもちろん、自転車で対向車とすれ違う際も、生垣にもぶつかるし、非常に危険な状況があるとの指摘が、町会から上がってきている」(広報広聴課)。「連雀通りからの入口で、時間帯で車両規制を行なっているが、交通誘導員の配置も、権限がなくあまり意味がない。抜本的な解決ができないか、との要望が町会から上がってきている」(広報広聴課)というものである。
小金井市の都市計画課は、このように各課から寄せられた意見を「都市計画課の意見も加えたうえで、理事者等の内部調整を経て、8月末に小金井市施行の優先整備路線の仮候補といたします」と記している。つまり2014年8月末には「小金井市施行の優先整備路線の仮候補」にしているのである。そのうえで小金井市は、この「仮候補」をもとに、「2014年度末から2015年度の上半期に、文書等にて都へ市道の優先整備路線の要望の正式な回答を行なう」と、2014年8月7日付の「起案書」添付文書で述べている。
では、その「正式な回答」では、どのような記述をしたのか―――建設環境委員会でただすと、この「正式な回答」が、昨年10月15日に東京都に提出した、「市施行」では「該当ありません」と記した回答書だと、課長補佐は言うのである。ではなぜ、都への正式回答で「該当ありません」と記しておきながら、2つの路線が「都施行」となって登場してきているのであろうか。
カギとなるのは、資料が他にもあるのではないかという点と、東京都を交えた都市計画道路関係の合同部会の会議録がつくられていないという点にある。
日本共産党市議団はこの間、小金井市に対して、関係する文書の情報公開請求を行なってきた。しかし「小金井市施行の優先整備路線の仮候補」の資料は手元に届いていない。この「仮候補」が「正式な回答」という形ではなく、別の形で、例えば「非公式」という形で東京都の担当部署に渡たっているのではないか。あるいは、「仮候補」に仕上げるには至らなかったが、合同部会などで、小金井市の意思が東京都に伝えられていたのではないか。例えば「『市施行』では無理だけれど、『都施行』ならばいいですよ」という具合に。
いずれにしても、「該当ありません」と回答したにもかかわらず、東京都は2つの路線を「都施行」という形で計画に明示した。「なぜ、計画に入れたのですか」と、私だったら東京都に聞くであろう。しかし課長補佐は「都施行だったので意見は述べていない」と言う。では、「該当ありません」という昨年10月15日付の東京都への回答そのものについては、どう考えているのか。西岡市長は「市施行路線としては、当時と同じ考え」と述べ、「市施行ならば『該当するものはない』」というのが、今日の西岡市政においても同じだというのである。逆にいえば「都施行ならば、話は別だよ」と言っているようにも聞こえる。
ではなぜ「市施行」ならば「該当ありません」なのであろうか。「市財政では対応できないからではないのか」とただすと、川上副市長は、そのことも一つの要因であることを認めた。ようするに「小金井市はカネがないから、市施行では対応できない。しかし東京都で事業化したいというのならば、おまかせしたい」というのが小金井市の本心であり、都施行ならば、小金井市が住民の矢面に立たなくても済むという考えなのではないか。だから「都施行なので、市が判断する立場にない」との西岡市長の答弁になり、昨年11月11日に東京都から(案)が示されても、「何故?」と意見を述べる意思を持ち得ないのである。しかし市民から様々な意見が寄せられているので、それくらいは東京都に届けましょうとなるのである。
ここまで独自の推論を展開してきた。推論であるから、まったくの的外れであるかもしれない。しかし、いずれにしても、市民は西岡市長が明確な意思を示してくれることを望んでいる。
それにしても、なぜ西岡市長は明確な意思を示そうとはしないのであろうか。私が推論するように、「都施行ならば、お願いしたい」という思いがあるからなのか。それとも自身の応援団のなかに、この計画を進めてほしいという勢力がいるからなのか。はたまた少数与党であるがために、自民党・公明党の顔色をうかがっているのであろうか。3月8日の市議会建設環境委員会では、傍聴席を埋めつくした人々の間から、西岡市長の答弁に対する驚きや失望の声が渦巻いた。西岡市長、あなたは東京都の側に身を置くのか、それとも市民の側に置くのか―――そのことがいま、あなたに問われている。
(2016年3月14日付)
『福祉会館建設問題』全員協議会開かれる
新しい福祉会館のお目見えが、いつになるかはまったく不明―――1月27日(水)に開かれた市議会全員協議会での西岡市長の答弁は、聞く側にそのことを強く印象付けた。
西岡市長は昨年12月の市長選で配布したチラシで、老朽化した福祉会館の建替えにあたっては、福祉会館と図書館本館、市役所庁舎を合築させた複合施設にする案(ケース1)を示し、イラストまで付けて蛇の目跡地に建設すると「公約」した。チラシではこの他にも、「蛇の目跡地は売却か交換、本町暫定庁舎と隣接地に新庁舎」(ケース2)、「JR高架下と蛇の目跡地に建設」(ケース3)の考えも記しているが、「ケース2」と「ケース3」は市役所庁舎を建てる場合の方策であり、福祉会館の建替えとは直接的には関係がない。そのことから福祉会館の建替えにおいては、「ケース1」があてはまることになる。
では、いつになったら「ケース1」が実現するのか。西岡市長は「私の掲げた政策が実現可能なのかどうかを、部局に検証してもらっている」と述べ、企画財政部長は「今後のスケジュール、財源は現時点、示せるところではない」と述べた。つまり、いまは何も示せないというのである。ところが西岡市長は何ら根拠も示さずに、「ケース1は実現できる方策だと思っている」と言い切る。
次々に質問の手が挙がり、多岐にわたる質問が市長に浴びせられた。質問を予定している議員は他にも何人もいると思われる。しかし、この日の全員協議会は午前中のみという約束。そのため先を見越した篠原議長は、質疑途中で次回の全員協議会の日程を提示。2月8日(月)の午後1時から4時までの3時間があてられることとなった。
私は西岡市長に、どうしても問いただしておきたいことがある。市長は、自身の政策が実現可能なのかどうかを検証すると言うが、「検証」に要する期間をどれくらいと考えているのであろうか。また「検証」の結果、実現可能となったら、その後の市民を交えた検討委員会をどれくらいの期間、開催すると考えているのであろうか。図書館本館や市役所庁舎も合築するというのであれば、福祉会館のみの検討では済まなくなり、相当な時間を要すると考えるのは素人でもわかることである。となると、新福祉会館のお目見えは、相当先になると思うのである。
もう一つ問いただしておきたいのは、「検証」の結果、「実現不可能」となった場合はどうするのであろうか。西岡市長の政策には、福祉会館の「単独建替え」は登場してこない。「ケース1」のみ、福祉会館が登場するのである。もしかしたら「単独建替え」も胸中にはあるのかもしれないが、ではその場合、どこに建てる考えなのであろうか。いずれにしろ「検証」の結果、「実現不可能」となった場合は、「検証」に要した期間そのものが「空白期間」となり、福祉会館建替えの検討は練り直しとなる。
西岡市長の方針でいくならば、最低限、福祉会館の代替施設は必要である。この先、いつになったら新福祉会館がお目見えするのか、わからないからである。なお、西岡市長は「ケース1の計画以外にも、行政内部で検討してもらっている」と述べているので、もしかしたら同時変更で、別の方策がすすめられていくのかもしれない。いずれにせよ、困るのは市民である。そのことを忘れずに、西岡市長には市政運営にあたってもらいたい。
(2016年1月28日付)
午前様の臨時議会
西岡新市長が、市長就任後初となる市議会を招集した。議案は補正予算である。この補正予算の審議の他に、昨年12月の市議補選で当選した議員の議会役職等を確定するための議決および、市議会側が市長に求めていた、西岡新市長の頭の中にある福祉会館の建替え方針を説明してもらうための市議会全員協議会もあわせて予定され、1月22日(金)に招集された臨時議会が一定の時間を要することは、誰もが想定をしていたところである。しかし、まさかこんな時間にまで及ぶとは・・・。
補正予算の概要は、昨年4月から民間委託となった「さわらび学童保育所」の委託先を今年4月から変更し、現在受託している事業者に対して、今年4月から新たに受託する事業者に、今年3月のひと月の期間で業務の引継ぎを行なわせるというものである。
当初小金井市は、現在受託している事業者にまるまる5年間、事業を任せるつもりであった。しかし事業者側にさまざまな問題点が発生し、学童保育所の保護者や児童との間に冷たい風が吹き込むほどの隔たりが生じたことから、事業者側が自らの判断で、今年3月末で撤退することとなった。
そこで問われるのは、なぜこのような事態になってしまったのか。二度とこのような事態をつくりださないために、この間の検証と総括が欠かせないということである。しかし、検証や総括が行なわれた形跡は市側にはどうも見受けられないのである。
ならば、議会側が検証・総括を果たさなければならない。委託するにあたっての委託仕様書は問題がないのか、仕様書どおりに事業は行なわれてきたのか、単年度で撤退という事態を招くに至った経緯はどうだったのか、委託費は適切だったのか、委託費の大部分は人件費となるが、雇用労働者に適切な給料が支払われる仕組みになっていたのか、市側は事業者にどこまで指導を行ない、その指導が適切なものとなっていたのか、そもそも委託することが適切だったのか―――などなど。
22日(金)の午前中は、議会役職等を確定するための人事案件が滞りなくこなされていったが、午後に入ると動きがとたんに鈍くなった。理由はただ一つである。新年度から新たな事業者に委託をするということに対して、保護者側の理解を得ていないということと、保護者側には1月27日(水)に説明するという、後追いになっているということである。これでは、1月22日の臨時議会で補正予算が承認された場合、「議会議決」を前面に押し立て、保護者の意見を押し切ることにもなりかねない。こんなことは到底、認められないということである。行政側と議会側および議会の会派間で、今後のすすめ方の調整が断続的にすすめられていった。その結果、補正予算の上程・説明は午後6時15分からとなった。
議会側が検証・総括を行なうためには、それにかかわる資料が不可欠となる。当然に議会側からは資料要求がなされた。しかし、すぐに出せるものもあれば、時間を要するものもある。必要な資料が提出されないもとでは、議会質疑には入れない。そのため、資料提出の調整が部局側と資料要求側との間で継続的に行なわれていった。気がつけば時計の針は日付をまたごうとしている。議長職権で本会議が再開され、会期延長1日が議決された。
23日(土)の午前0時5分開会が言われていたが、本会議はいっこうに開かれず、時間だけが刻々と過ぎていく。これからどのようなすすめ方をするか―――正副議長を中心に部局側や資料要求側との調整が続く。会派控室では椅子に座りながら船を漕ぐ人々・・・眠い。午前3時15分、本会議開会のコール。「本臨時会は2月2日まで10日間延長し、次回は2月2日の午前9時からとする」。時計の針はまもなく午前3時30分になろうとしている。眠気がいっきに押し寄せてきた。
日本共産党市議団は、委託化に反対である。第一の理由は、委託化の最大の理由が「人件費削減」にあるからである。今日、働く人の4割、若者の半数が非正規雇用におかれ、これまで正規職員でになわれてきた業務が年収200万円前後の人々に置き換えられる事態が次々にすすめられてきている。「働く貧困層」が大きな社会問題となっているにもかかわらず、そのお先棒を自治体がになうようなことは到底、認められないのである。しかも、事業を受託した事業者が限られた委託費のなかで利益をあげるには、委託費の大部分を占める人件費をさらに切り縮める以外になく、最低賃金すれすれの給料しかもらえない事態がつくりだされることになるのである。こんなことはぜったいに容認できない。
反対する第二の理由は、低い人件費で働かされることから職員が長続きせず、1年の間に職員が何人も入れ代わる事態が起きるということ。学童保育所や保育園は子どもの成長を育む職場なのに、その職場で職員が安定的に働けずに職員が次々に入れ代われば子どもの心は不安定となり、同時に、職場運営にも支障をきたすことになるのである。5年間の委託を予定していた「さわらび学童保育所」の受託事業者が1年間で受託を終える事態となったことは、日本共産党市議団がかねてから指摘してきた懸念・問題点が、事実をもって証明されたといえるのではないだろうか。原因の検証・総括がなされないままに、新年度から別の事業者に委託を行なうということは、同じ過ちが繰り返されるのではないかとの疑念を抱かずにはいられないのである。保護者の不安は当然であろう。拙速なやり方は改めるべきである。
市報「こがねい」に西岡市長の就任挨拶が掲載されている。そこには「これまでの間、私は地域を歩き、多くの市民の声を聞いてきました。その声は、市民の力、地域の力をもっと市政に活かしてほしい、市民の声をしっかり聞いてほしいということでした。この声を市政に反映させることが私の使命であり、そのためには、行政の意識改革が必要です」と記され、「西岡市政の基本は対話、市民との対話、議会との対話を大切にすること」「職員は積極的に地域に出て、市民の声に耳を傾け、その声を市政に反映できるよう努力すること」と明記。そのうえで「市民一人一人が大切にされ、真の幸せを実感できるまちづくりを実現」と結んでいる。西岡市長に言いたい。本当にそう思っているのであれば、保護者の理解を得ていない補正予算はただちに撤回せよ、と。
長年、議員をつとめている私などは、このような時間帯になることは珍しくもないが、初めて議場の椅子に座った新人議員2人は、どのように思ったであろうか。大変なところに来てしまったと思っても後の祭りである。今後も同様な状態が続くであろうと想像するのは、私だけではないだろう。
※臨時議会で承認された議会人事一覧のまとめをPDFファイルで掲載します。
(2016年1月25日付)
三多摩で一番高い国保税
小金井市は国民健康保険財政が厳しいとの理由から、昨年度と今年度の2年連続で国保税の引上げを行なった。2012年度も昨年度同様に大幅引上げを行なっており、この4年間では実に3回、2年前(2013年度)の最高限度額の引上げを含めると毎年度、改定している。その結果、小金井市の国保加入者の一人あたりの負担額は、三多摩でもっとも高い金額になってしまっている。
国保税の税額は、国保加入者が医療機関にかかった際に、小金井市の国保財政で負担する保険給付費の大小で決まる。保険給付費が多ければ国保税の引上げにつながり、保険給付費が少なければ、国保税の引き下げが可能となる。
昨年度(2014年度)、小金井市の国保加入者一人あたりの保険給付費は三多摩26市のなかで21番目に少なかった。しかし、国保税は何故か三多摩で一番高くなっている。国保の加入者が小金井市と同程度の国分寺市は、一人あたりの保険給付費が小金井市よりも4千4百円も多いのに、国保税額は小金井市よりも1万2千円低くなっている。なぜ、小金井市の国保税は高いのであろうか。
9月の決算委員会でその点をただすと、担当課長は「国分寺市は、前期高齢者交付金や都費補助金が小金井市よりも多いから」と述べ、補助金や交付金が小金井市よりも多いために、小金井市よりも低い国保税額で対応できると言う。しかし、国分寺市以外の他の自治体の数字でみると、説明がつかなくなる。
三鷹市と比較すると、小金井市と三鷹市は一人あたりの保険給付費がほぼ同額。しかし、一人あたりの前期高齢者交付金は三鷹市の方が6千円少なく、一人あたりの都費補助金は6百円ほど多い程度。しかし三鷹市の一人あたりの国保税額は1万4千円も小金井市より低くなっている。
小平市と比べてみても、市の説明ではおかしくなる。小平市の一人あたりの保険給付費は小金井市よりも千3百円ほど多く、一人あたりの都費補助金はほぼ同額であっても、一人あたりの前期高齢者交付金は千円少なくなっている。しかし国保税額は小金井市より2万円も低い。11月議会の一般質問でこの点をただすと、担当課長は「小金井市は国の調整交付金も少ない」と、9月の決算委員会では一言も触れなかった「国の調整交付金」を持ち出してきた。
その一方で「小金井市は国保加入者が減っていることから、国保税収入が予定額に達していない」「国保加入者は全体では減っているが、国保加入の前期高齢者(65歳〜74歳)数が増加していることから、保険給付費は増加している」と、国保税の増税を正当化。しかし、国保加入者の減少や前期高齢者数の増は、小金井市にかぎらず他の自治体も同様であり、市の説明は「説明」にはならない。国保税が三多摩最高の額になる理由としては不十分である。
私は「小金井市の国保税額が高いのは、国保会計の不足分を補てんするための一般会計からの繰入額(その他一般会計繰入金)が抑えられているため」と述べ、「三鷹市は小金井市よりも一人あたりの繰入額(その他一般会計繰入金)が6千円多く、小平市は小金井市よりも2千円多い」ことを示すと、担当部長は「無尽蔵に増額できるということにはならない」と、私の指摘を否定しなかった。
国民健康保険は法律で「社会保障」と明記されている。社会保障でありながら、高すぎる国保税を納めきれずに滞納せざるをえない状況は異常としか言いようがない。市民の暮らしを守るためにも一般会計からの繰入金を増やして、国保税の引き下げを行なうべきである。
※PDF「多摩26市における国保税等の被保険者一人あたり額(年額)の状況」参照
(2015年12月26日付)
審議会等の公募委員選考基準
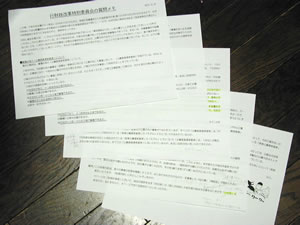 |
行財政改革調査特別委員会での質問原稿 |
小金井市には現在、数多くの審議会、協議会、委員会と称される附属機関が設置され、これら附属機関の大半に「市民参加条例」にもとづく「公募市民」枠が設けられ、委員の3割余を占めるようになっている。
附属機関には「公募市民」の他に、「学識経験者」や「団体推薦」の委員も存在する。「団体推薦」とは、小金井市に関わる商工関係や労働関係、東京都の関係部署、福祉や教育にかかわる団体等の代表であり、「学識経験者」は、市内の大学の教授が委員として加わることが多い。「団体推薦」の場合は、当該団体から人選されて委員に就任し、「学識経験者」は、「つきあいのある大学教授にお願いしている」というのがこの間の市の説明である。
附属機関は市長からの諮問に応じて、あるいは担当部局からの要請にもとづいて、市の施策への意見や見解を示し、具体的な提案を行なうことを任務としており、附属機関から発せられた内容をもとに小金井市は市政運営をすすめるとしている。よって、付属機関からどのような内容が発せられるのかは、行政運営の行方をはかるうえで大きな比重を占めるものとなる。
「行財政改革市民会議」という市長の諮問機関がある。「学識経験者」は2人、「団体推薦」は5人、「公募市民」は3人となっている。この行革市民会議はこの間、市長からの諮問に応じて行財政改革のさまざまな提言・進言を行ない、なぜか市民への負担増や有料化、サービス見直し、民間委託化を矢継ぎ早に打ち出し、今年3月の「答申」では施設の統廃合まで求めるようになっている。一方で、「市財政は危機的状況」と言いながら、莫大な財源を必要とする大型開発は不問にする状況である。
同じことは「長期計画審議会」にも言える。小金井市長期計画審議会は今年3月、市長からの諮問に応じて第4次基本構想・後期基本計画の策定作業をすすめ、10月に後期基本計画(案)を答申した。この内容も、「市財政が厳しい」としながらも莫大な財源を必要とする大型開発は既定事実として扱い、財源確保を最優先に計画を組んでいる。こちらも委員16人中、公募市民が5人存在する。
私は常々、なぜ市財政に大きな影響をおよぼす駅前の大型開発や都市計画道路建設は不問にし、なぜ市民に負担を求める「受益者負担の適正化」や民間委託化を次々と求めてくるのかと、疑問をもってきた。市民に意見を聞けば、「これ以上の生活に対する負担はやめてほしい」「駅前開発よりも、いまは暮らしにお金を使ってほしい」の声がいたるところから寄せられており、そうであるならば、行革市民会議であっても長期計画審議会であっても、あるいは各種附属機関においても、いまの小金井市の市政運営とは異なる意見を持つ市民が公募市民のなかに入っていてもおかしくない、違う意見を持つ人がいてもおかしくないと思うのである。しかし、そのような場面はなかなか見られない、なぜであろうか。そこで考えるのが、「公募市民」はどのように選ばれるのかということである。
小金井市は、市民参加型の各種附属機関における「公募市民」の募集において、「公募委員選考基準」を設けている。それによると、応募者にはテーマ指定の小論文や作文の提出を求め、小論文や作文を審査して評価することをうたっている。小論文や作文をどのように審査し評価しているかといえば、たとえば「子ども・子育て会議委員」の場合は、(1)現状や課題を的確にとらえているか。(2)先見性があり、かつ現実的な主張であるか。(3)審議に必要な知識があるか。(4)社会的に公平・中立な立場で審議できるか。(5)審議をまとめる協調性があるか。(6)誤字・脱字はないか―――の6項目となっている。この6項目にもとづいて、市長・副市長・教育長・所管の部長・所管の課長が選考委員となって選考するとしている。
私は、6項目のなかで「先見性があり、かつ現実的な主張であるか」「社会的に公平・中立な立場で審議できるか」「審議をまとめる協調性があるか」に対しては、選考委員の考え方によっては見解が分かれる、あるいは受け止め方いかんによっては、政治的な判断が入り込む余地があると考えている。はたして、このような基準で、幅広い市民の意見を集約する附属機関になるのかとの疑問を持つのである。
今年6月に募集が行なわれた「社会教育委員」の場合は、(1)現状や課題を的確にとらえているか。(2)先見性があり、かつ現実的な主張であるか 。(3)審議に必要な知識があるか。(4)社会的に公正・中立な立場で審議できるか。(5)具体的な問題解決の視点が示されているか。(6)整然とした論理展開がなされているか―――となっている。「具体的な問題解決の視点が示されているか」についても、選考委員の考え方によっては見解が分かれる、あるいは政治的な判断が入り込む余地があると考えるものである。
しかも「社会教育委員」の場合は、面接による二次選考まで行なわれ、「審議をまとめる協調性があるか」という、「子ども・子育て会議委員」の小論文における審査・評価基準が持ち込まれるとともに、面接においても小論文の審査基準と同様な「社会的に公平・中立な立場で審議できるか」の項目が持ち込まれている。
同じく今年6月に募集が行なわれた「公民館運営審議会委員」の場合の小論文の審査では、(1)現状や課題を的確にとらえているか。(2)先見性があり、かつ現実的な主張であるか 。(3)審議に必要な知識があるか。(4)社会的に公正・中立な立場で審議できるか。(5)具体的な問題解決の視点が示されているか。(6)整然とした論理展開がなされているか―――となっており、こちらも面接による二次選考が行なわれ、「社会教育委員」と同様に、「審議をまとめる協調性があるか」という、「子ども・子育て会議委員」の小論文における審査・評価基準が持ち込まれるとともに、面接においてでさえも小論文の審査基準と同様に、「社会的に公平・中立な立場で審議できるか」の項目が持ち込まれている。これらの見解が分かれるもの、あるいは政治的な判断が入り込む余地がある審査・評価基準にもとづいて、公募委員は選考されていくのである。
この選考基準はいつから導入されたのであろうか。企画財政部に問い合わせたところ、11年8カ月前の2004年3月に策定された「市民参加条例の手引」に「委員公募選考基準」の「モデル」が示されており、「基準モデル」の「論文審査」に、これまでに紹介した項目が列挙されている。
では「基準モデル」の大本となる「市民参加条例」はどのようになっているだろうか。第10条「公募委員の選任等」では、「市は、公正な方法によって公募委員の選任等を行わなければならない」「市は、公募委員を選考する場合は、あらかじめ選考基準を公表しなければならない」と述べるのみである。条例では「公正」という文言が登場するが、選考の手法を「公正な方法」で行なうことをうたったものであり、社会的な立場や審議のあり方に対して「公正・中立」をうたっているわけではない。
しかも、附属機関を設置する理由を、「市民参加条例の手引」の「説明」では「附属機関等を設置することによって、市民の意見をいかし、市長の政策決定に実質的な影響を与える役割を期待しているものです」としている。つまり、市民の多様な意見・考えを反映させるというのが、附属機関等の設置の目的となっているのである。
ではなぜ、「市民参加条例の手引」に明記されている「委員公募選考基準」の「基準モデル」は、このような形になったのであろうか。11月16日の行財政改革調査特別委員会で質問したが、担当課長は「11年も前のことなので、詳細はわからない」と述べるのみ。企画財政部長は「次回までの宿題とさせていただきたい」と答弁した。
現在用いられている「委員公募選考基準」は、「附属機関等を設置することによって、市民の意見をいかし、市長の政策決定に実質的な影響を与える役割を期待している」と明示する「市民参加条例の手引」から逸脱していると私は思う。市民の多様な意見が反映される「選考基準」に改めるべきであろう。
また、今年3月に策定した「長期総合計画策定方針」では「市民参画」をうたい、「後期基本計画の策定に当たっては、広範な市民等の意見を反映させるため」に、長期計画審議会の設置と市民意向調査の実施を行なうとしている。しかし、長期計画審議会の公募市民5人も、「市民参加条例の手引」に記載されている「委員公募選考基準」の「基準モデル」にもとづいて選考されており、みずから「広範な市民等の意見を反映させる」とうたいながらそのような選考基準とはなっていないことには大きな問題がある。しかし担当課長は「問題はない」との答弁に終始するのみであった。
これでは、行革市民会議を筆頭に、稲葉市長になりかわって小金井市の行政全体にハッパをかけさせ、思うようにすすまない市民負担増や有料化、サービス見直し、民間委託化を促進させる役割を附属機関に担わさせる。そのために、この「基準モデル」がつくられていると思われてもしかたないところである。
なお、市民参加条例の第10条では次のような条文がある。「選考結果をその理由とともに遅滞なく公表しなければならない」。「市民参加条例の手引」の「説明」では、「選考結果をその理由とともに速やかに広報紙等で明らかにすることも、公募委員選考の公正さを示すことになります」と記している。この原稿を書きながらこの間の「市報」を繰っているが、「公募委員選考基準等により、次の方々を委員に選任しました」としか記されてはいない。「公募委員選考基準等により」の説明が選考結果の「理由」に果たしてなりうるのであろうか。すくなくとも“これこれこういう理由で、この方たちに決まりました”というのが、「理由」だと私は思うのだが。
企画財政部長は宿題を持ち帰っている。「審議会等の公募委員選考基準」は引き続き、議論していく課題である。
(2015年11月17日付)
雨水浸透事業と特別会計
小金井市の雨水浸透桝設置率は今年3月末で59.9%に達し、設置率では世界一とも言われている。家屋の雨樋から流れ落ちる雨水を地中に埋め込んだ桝で受け止め、桝に開けられた穴から徐々に地中へとしみこませるというもので、雨水の河川への流出抑制、地下水の涵養等の自然環境の保全・回復を目的に、下水道工事指定店の協力のもと、事業をすすめている。
昨年度、小金井市は市内南部の市道に、150個の雨水浸透桝を設置した。3つの区域に分けて実施したもので、市道沿いの下水道管に雨水が流れ込むのを少しでも減らそうとの考えから行なわれたものである。その決算額が下水道事業特別会計に記されている。合計で5千万4千円となっている。その金額が記されている決算書のところで、私の手が立ち止まった。金額が“おかしい”とかではない。「なぜ、ここのページに、この記載があるのか?」との疑問が私の手を止まらせたのである。
下水道事業特別会計は、公共下水道に関する事業、事務等の経費で構成される。だから下水道管の設置や維持管理はこの特別会計の最たるものとなる。しかし、雨水浸透桝は異なる。なぜなら、雨水浸透桝は下水道に流れようとする雨水を下水道管流入口の手前でくい止め、桝の中へと誘い込み、地中へと浸透させるのが役割だからである。公共下水道を使用させないのであれば、下水道事業特別会計で扱うのは筋違いだと私は思うのである。
そのことを問われた下水道課は「雨水浸透桝は道路上に設置する。そこからオーバーフローした分は下水道へ流れる」と述べ、オーバーフロー分は下水道へ流れるから、下水道事業特別会計で扱うのは問題がないという見解を示した。だが、それは問題のすり替えである。雨水浸透桝からのオーバーフローはあくまでも結果にすぎない。雨水浸透桝を設置する目的は、雨水を下水道管に流れさせないためであり、公共下水道の使用を防ぐために設置したのであれば、公共下水道の使用に沿って設けられている下水道事業特別会計での扱いは、前提そのものがなくなるのである。
小金井市は、市民が自宅に雨水浸透桝や雨水浸透管を設置する場合、一定の要件に合致すれば助成金を支給する制度を設けている。昨年度は、助成件数が1件、浸透桝を5個設置したということで、15万円の助成を行なっている。ところが、この助成金15万円も、下水道事業特別会計で組んでいる。この場合は、オーバーフローによる下水道への流入は到底、考えられない。なのに特別会計で扱っているのである。下水道課の説明は、説得力を持たないでいる。
下水道事業特別会計は、歳出の額をもとに歳入が組まれていく。下水道使用料(下水道料金)や国・東京都からの補助金ですべてが賄えない場合には、一般会計からの繰入れで対応せざるをえなくなる。小金井市でも昨年度、4億500万円余が一般会計から繰り入れられている。
では、下水道事業特別会計で扱うには筋違いのものが数多く歳出のなかに組み入れられるようになったらどうなるか。一般会計からの繰入額の増加、あげくのはてには、下水道料金の引上げへとつながっていくことになるのではないか―――――。目に止まった雨水浸透桝設置事業を通して、いろんな方向に考えは移りめぐっていくのである。
(2015年10月6日付)
区画整理事業と特別会計
小金井市は現在、JR中央線「東小金井駅」北口で区画整理事業を行なっている。10.8ヘクタールにもおよぶ広大な区域で、減歩緩和のための土地取得から数えると、すでに20年の歳月を要している。現在は、仮換地が順次すすめられ、進捗率は今年3月末で61.17%となっている。
総事業費は、減歩緩和・減価補償のための土地取得費を除いた本体だけでも93億1,718万円(借金の利子含まず)。このうち小金井市が負担するのは45億4,566万円(48.79%・借金の利子含まず)とされている。今年度も一般会計で12億3,309万円を予算化し、市の負担は3億4,579万円を予定している。小金井市は現在、「危機的財政状況」だと市民にアピールしているが、東小金井駅北口区画整理事業の市負担額が「危機的財政状況」の大きな要因となっていることは、疑いのないところである。この市負担額をいかに圧縮するか―――――このことは、市民生活にできるだけ多くの財源を充てたいと願う者ならば、誰もが思うことである。
私はこれまで、その年度その年度の区画整理事業の事業費を一般会計から眺めてきた。しかし、特別会計にも区画整理事業の経費は組まれており、単年度の区画整理事業の事業費を見る場合には、特別会計で組まれている分も含めて見ていくことが必要となる。ということぐらいは、わかっているつもりであったが、先日終了した9月定例議会の決算委員会で、あらためてそのことを再認識する事態に立ち至った。
小金井市は、東小金井駅北口土地区画整理事業を東京都都市づくり公社に事業委託している。昨年度の決算数値を見ると、一般会計での委託料が8億5,768万7,073円、下水道事業特別会計では「下水道整備等委託料」の名で2,579万4,707円となっている。決算書の2つの会計に分けられた区画整理事業委託料の金額を前にして、私はふと立ち止まった。「なぜ下水道事業特別会計に区画整理事業の経費が登場するのか?」。みなさんはおそらく「下水道整備なのだから、下水道事業特別会計で対応するのはあたりまえ」と思うかもしれない。しかし、私はここで立ち止まってしまった。なぜなら、下水道事業特別会計の歳入部分を見ると、国や東京都からの補助金がわずかしか計上されていないという事実に直面したからである。
下水道整備事業を一般会計で対応し、一般会計で区画整理事業のすべてを完結する形式にしたらどうなるだろうか。もしかしたら、下水道整備事業も国や東京都からの補助金の対象事業のなかに組み入れられるのではないか―――――これが私の観点である。
いや、もしかしたら駅前の大型開発事業における下水道整備事業は、下水道事業特別会計で取り扱うという国からの指導があるのかもしれない。そこでまず、すでに事業が終了している武蔵小金井駅南口第一地区の再開発事業における下水道整備事業を、どの会計で対応したのかを質問した。答弁は「都市再生機構への負担金で対応している」であった。「負担金で対応」とは一般会計で対応しているということであり、南口第一地区再開発事業は一般会計ですべて対応しているということになる。ということは、下水道整備事業の部分も、国や東京都の補助金の対象事業に参入されているということになる。では、東小金井駅北口土地区画整理事業の下水道整備事業を下水道事業特別会計で対応した場合、補助金は入ってくるのか。答弁は「入っていない」であった。
なぜ下水道事業特別会計で対応したのか。答弁は「700mm以上の下水道管部分は、特別会計に移すことにした。理由は、区画整理事業区域外の下水も集めることになるから」。しかし前述のように、区域外の下水をも集める南口第一地区再開発事業では、そのような扱いはしていない。到底、説明にはなっていないと思うのである。では、一般会計で対応した場合、補助金はどれくらい入ってくるのだろうか。答弁できる担当者が議会に詰めていなかったことから、その点は明らかにされなかった。
一般会計で対応した場合、どれくらいの補助金が入ってくるであろうか。後日、資料を繰ってみた。2007年度の予算でみると、武蔵小金井駅南口第一地区再開発事業に「再開発事業公共施設整備負担金」というものがあり、この年度の負担金予算額は1億4,603円である。そのうち補助金は1,550万円となっており、思ったより少なめではあったが、それでも1,550万円の補助金を得られれば、その分、市民生活に財源を回すことができるわけである。もしかしたら、再開発事業と区画整理事業は補助割合が異なるかもしれない。あるいは、市施行の区画整理事業においては、一般会計で対応しても補助金は出ないのかもしれない。しかし、肝心のその部分も含めて、答弁はいっさいなされなかった。
区画整理事業の担当部署は、最初に事業計画をたてる際に、どちらの会計に下水道整備事業を組み入れたら補助金を得られるか、ということを考えたのだろうか。そんなことは考えずに、「下水道事業」という視点のみで特別会計扱いという判断に立ってしまったのだろうか。はたまた、なぜ「700mm以上の下水道管」という区分けをしたのであろうか。「700mm未満」の下水道管整備事業は一般会計扱いとなるのだから。
私は自身にも反省している。これまでの予算書・決算書においても、下水道事業特別会計で下水道整備等事業委託料が組まれていた。しかし、いままでこんな疑問を持ったことは一度もなかった。恥ずかしい限りである。いま、この文書を書き上げてはいるが、議会で答弁に至っていない部分を知れば、もしかしたら、疑問は解消されるのかも知れない。
決算委員会は生煮えの状態で終了してしまった。よって、来年3月定例会の予算委員会もしくは11月に開催される行財政改革調査特別委員会、あるいは建設環境委員会で再度、この点を深く掘り下げたいと思う。その後に、詳細な続編を記したいと思う。
(2015年10月5日付)
都市計画道路3・4・8号線
都市計画道路というものがある。自動車交通が容易にはかどるように、道路予定区域を自治体作成の地図上に書き入れたもので、おおかたは50年以上も前に計画されたもの。当時は田畑や山林区域が中心で、計画を作成する際にはそれほど問題視されてはいなかったが、その後の都市化のなかで住宅が建ち並び、計画どおりに道路建設をすすめようとすれば、多くの住民に立ち退きが求められ、土地の買収や建物の移転保障などに莫大な費用を要する事態となる。加えて、環境破壊への危惧もとりざたされ、都市計画道路建設をめぐる住民と自治体間での争いに発展するケースが続出している。だから、計画があるからといって、「ああそうですか」となるものではなく、事業をすすめるにあたっては、様々な角度での考慮が必要となる。
6月定例市議会のなかで小金井市から、都市計画道路建設の「事業延伸」と受け取れる発言がとびだした。小金井市の都市計画道路3・4・8号線の事業化が計画どおりに行かなくなっているというのである。
都市計画道路3・4・8号線は、小金井市東部の中央線高架下を南北に走る、長さ380m余の道路建設計画。幅6〜7m程度の道路を16mにまで拡幅し、自動車の往来を容易にするというものである。この計画に小金井市は14億円の財源を投入しようとしている。
計画が表面化したのは2011年3月。小金井市の第4次基本構想・前期基本計画の「中期財政計画」(計画期間は2011年度〜2015年度)に「2013年度から事務手続きに関する予算を計上」が明記されたのである。そのことから小金井市は、小金井市が100%出資する小金井市土地開発公社で用地の先行買収を行なうことを決め、先行買収を行なった翌年度から、小金井市がその用地を土地開発公社から買い取る方針を固めたのである。
6月定例市議会に入ってまもなく、党市議団のもとに情報が舞い込んだ。「市役所の職員が3・4・8号線の住民宅を訪れ、事業を先送りすると言っている」。そのことから私は、6月15日の市議会建設環境委員会でことの真意を確かめた。答弁は次の通りである。
「土地開発公社が地権者と交渉している。市の財政が厳しい中で公社が取得した場合、翌年に市が土地を買い戻せない場合は利子の補給が必要になるが、利子の補給も土地が大きくなると金額も大きくなるので、3〜4年、大きなところについては見送るということに・・・」と都市計画課長が核心部分にさしかかったところで市長が課長答弁を抑え、代わりに答弁に立った。市長は「『延伸』とか『中止』とかではない。この事業の実施時期をいつやるのか、買収の時期はいつなのかということで、一部の人には、このへんで買収させていただきたいというお願いをしている」。そのうえで市長は述べる。「財政状況等をみながら、事業をすすめていくことになる。事業延伸もありうることになる。今回は延伸を示したのではなく、事業の実施時期がこのへんになるということを地権者に説明したもの」。
都市計画道路3・4・8号線は当初計画より1年遅れでスタート。当初計画では2013年度に土地開発公社が用地の先行買収を行ない、翌2014年度に小金井市が土地開発公社から土地を買い戻すとされていた。しかし地元地権者の合意を得ることができずに1年経過し、昨年8月末にようやく1件分の土地を土地開発公社が先行買収。それも、土地開発公社評議員会が用地先行買収「不承認」を下したにもかかわらず、評議員会の意思を無視しての強行であった。
市長は「『延伸』とか『中止』とかではない」と述べつつも、「財政状況等をみながら」「事業延伸もありうる」と述べた。都市計画課長は「市の財政が厳しい中で」と述べており、3・4・8号線は実質的な「事業延伸」と見るべきであろう。それを証明するように、7月2日の土地開発公社評議員会では以下のやり取りがあった。今年度の小金井市土地開発公社の予算には、3・4・8号線の事業用地の先行取得経費が入っている。「この部分の予算変更が出てくるのではないか」と私がただしたところ、都市計画課長は6月15日の建設環境委員会での答弁を繰り返しつつも、「今後、事業計画の見直しもありうる」と答弁した。
この文章を書くにあたり、手元にはこの間の共産党市議団の予算組み替え案や「しんぶん小金井」のバックナンバー、この間の私の市政報告資料を置いている。これらを見ながら考えるのは、小金井市は3・4・8号線の事業計画見直しをすでに始めているのではないかという点である。先述したように、昨年8月末、小金井市は用地1件を先行買収した。本来であれば、今年度の小金井市の予算で土地開発公社から買い戻すはずである。しかし今年度の小金井市の予算には「事業予定地管理に伴う整備工事 270万円」が組まれているにすぎない。つまり、市財政の面から買い戻すことを断念しているのである。評議員会の「不承認」を蹴ってまで強行買収した用地面積は「94.70平方メートル」である。そう大きくはない。我が家の敷地面積と同程度である。それでも今年度の小金井市の予算には買い戻しの費用は組まれていない。「3〜4年、大きなところについては見送る」と都市計画課長は説明するが、「94.70平方メートル」の土地であっても買い戻しを断念するということは、大部分が「大きなところ」に該当することになる。実質的な事業延伸であり、武蔵小金井駅南口第二地区の事業化を迎え、毎年、市財政負担が発生する現状においては、3・4・8号線は「凍結」状態に入ったと見るべきであろう。
しかし口が避けても「凍結」とは言えない。なぜなら、国に事業化を求め、それが認められ、毎年、国と東京都から補助金がくるようになった段階において「凍結」ともなれば、小金井市の信用問題に発展するからである。だから「事業延伸」と述べるのが、せきのやまなのである。
ところで巷の話では、この3・4・8号線の事業計画は、庁内合意のもとにスタートしたものではないという。財政部門のあずかり知らないところで官報に掲載されていたという。あくまでも巷の話なので、真偽は不明である。しかし、今回の「3〜4年、大きなところについては見送る」は、第4次基本構想・前期基本計画の「中期財政計画」に入れたこと自体がどうだったのかを問うものとなっている。
(2015年7月20日付)
行革市民会議の実態
「小金井市行財政改革市民会議」という組織がある。市長の諮問機関ではあるが、その内実は、稲葉市長みずからが事業縮小や廃止などを打ち出しにくい部門に対して、諮問機関からの「答申」「建議」という形で意見を出させ、小金井市に「行革」を実行させる役割を負わせている。事実、この組織が「答申」「建議」などで打ち出した「行革」の内容は、その後、内部の異論を排して実行に移されたり、「行革」推進派議員の「答申」「建議」の履行を迫る質問によって、拍車がかけられる事態となっている。
「小金井市行財政改革市民会議」は「第三者からの意見」という装いをつくろってはいるが、実態はとても「第三者」とは呼べない代物である。
この組織は現在10人で構成されている。学識経験者が2人、市内の地域団体およびその他の団体の代表が5人、公募市民が3人である。この10人が任期を終了し、新たなメンバーの選考に入る準備を小金井市は行なっている。その中の「公募市民3人」の選考基準が示された。
ではどのような選考基準となっているであろうか。「選考方法」では次のように記されている。「指定テーマ『行財政改革について』に対する専用応募用紙による提出論文について審査し、選考します」と述べ、800字以内の小論文が必要となる。では、提出された小論文をどのように審査するのであろうか。「書類審査」では次のように記されている。「(1)現状や課題を的確にとらえているか。(2)先見性があり、かつ現実的な主張であるか。(3)審議に必要な知識があるか。(4)社会的に公平・中立な立場で審議できるか。(5)審議をまとめる協調性があるか。(6)誤字・脱字がなく、適切な文章表現であるか」。各項目10点ずつとして、各項目の得点集計によって評価するというのである。
「(1)現状や課題を的確にとらえているか」は何を意図しているのであろうか。この間の「小金井市行財政改革市民会議」は一貫して福祉部門の経費が増加していることを指摘し、その縮減の必要性を説いている。これを「現状や課題」として「的確にとらえているか」と言いたいのであろうか。「(2)先見性があり、かつ現実的な主張であるか」も眉唾物である。なにが「先見性」であり「現実的」なのかは、その人の立つ位置によって変わってくる。「(3)審議に必要な知識があるか」も大雑把な表現である。小金井市の市財政に対しての知識なのか、それともこの間の小金井市の「行革」の方向性に対する知識なのか、あるいは国の「骨太方針」の知識なのか、はたまた稲葉孝彦市長の考えている「行革」なのか。「(4)社会的に公平・中立な立場で審議できるか」も何を機軸にして「公平・中立」と見るかが不明である。「(5)審議をまとめる協調性があるか」にいたっては、この組織の幅の狭さを見事に表現している。「異論があっても、最後は自身の考えを脇におき、全体の考えに従え」と言っているに等しい。このような「書類審査」を、市長、副市長、教育長、企画財政部長、総務部長が選考委員となって、公募市民3人を決めるというのである。結局、市長の考え方に沿った人選にならざるをえないではないか。
では、それ以外の7人はどのように選出されるのであろうか。6月18日の市議会行財政改革調査特別委員会で担当課長は次のように述べた。学識経験者2人は「小金井市と付き合いのある大学教授にお願いしている」。市内の地域団体およびその他の団体の代表5人は「市で推薦している」。では、何人もの大学教授からどのような基準で2人を特定しているのか、地域団体等からはどのような基準で推薦しているのか。それに対する答弁は「総合的な判断にもとづく」。なんのことはない、稲葉市長の「行革」方針に沿った人物で「行財政改革市民会議」が埋まるように「総合的に判断」しているということではないか。これが「幅広い見地からの建議、助言を得るため」と銘打って設立される「小金井市行財政改革市民会議」の実態である。
この組織、けっして問題視しないのが「駅前大型開発」や「都市計画道路の整備・拡幅」である。一方で、市民の暮らしに欠かせないサービスや事業は「縮小」「廃止」を求め、市民負担増も平気で打ち出す。3月末に発表した「答申」は地域コミュニティづくりに不可欠な公民館や集会施設の統廃合まで明記するに至った。どこが市民の代表だと言うのであろうか。偏った人選のもとで発せられた「答申」「建議」に踊らされて、市議会で「行革」を推進せよと主張することほど、市民不在で愚かなことはないであろう。悲しいかな、担当部局は、偏った人選のもとで発せられた「答申」「建議」が錦の御旗となって、事業の縮小や削減に追い込まれていくのである。私は小金井市の職員に呼びかけたい。「それでいいのか。『おかしい』と声をあげるときではないのか」。
(2015年6月29日)
新福祉会館建設期間中の措置
小金井市は6月11日の市議会連合審査会に、耐震診断をふまえて「建替え」を選択した福祉会館の経過措置案を提出した。「経過措置案」とは、現在の福祉会館内にある各種施設・事業を、福祉会館の建替え中にどのようにするかというものである。事業を明確に「継続させる」としているものもあれば、「調整中」というものもあり、すべての事業が継続されるわけではないというのが実感である。
「調整中」とされているのは、小金井市が社会福祉協議会に事業を委託しているもの、もしくは福祉会館内で行政財産使用許可で実施している事業等とされており、法令上、事業の実施が義務化されていないものとなっている。社会福祉協議会も行政財産使用許可で事業を行なっている団体も、独自の建物や施設を持っているわけではないことから、他の建物・施設の斡旋が小金井市からされなければ、独自で民間マンション等の空き室を探し出すしか道はなく、場合によっては、福祉会館の建替え中は少なくない事業がストップする恐れが起きる。小金井市はそのことを否定できず、「どのような形で事業を継続していくかを協議していく」と答弁するのみであった。
一方、新たな福祉会館に移される事業はどうであろうか。私は「公民館本館」と「浴室」に対する考えを問いただした。小金井市が示している計画では、新たな福祉会館には「公民館本館」と「浴室」が入っていないからである。
小金井市は、市民を交えた建設検討委員会で、新たな福祉会館に入れるべき施設を検討するとしている。では、建設検討委員会でこの2施設を「入れるべき」となった場合、小金井市は応じるのだろうか。
昨年12月の厚生文教委員会で小金井市は、「公民館関係は建物の敷地規模の関係から入っていない」「浴室は一日の利用者が30人程度であり、費用対効果の関係から入れなかった」と述べている。この答弁がそのまま活きるのであれば、公民館本館はスペースがないことから「入りようがない」ということになる。では「浴室」はどうか。そこで目に止まるのが建設検討委員会の「所掌事務」にうたわれた「費用対効果に十分配慮」という文言である。「浴室」は「費用対効果の関係から入れなかった」との答弁からすれば、これも「入りようがない」のである。しかし、これから設置予定の建設検討委員会の協議に枠をはめるわけにはいかず、「入りません」とはさすがに答弁はできない。だから公民館長は「新福祉会館内には、まだ空きスペースがある」と苦し紛れの答弁をすることとなった。「浴室」についても地域福祉課長は「検討することになる」と述べざるをえないのである。
「入れるべき」と建設検討委員会が判断した場合、両課長はどうするのであろうか。もしかすると、「入れない」という方向に議論を誘導するのではないだろうか。私はそう思えてならない。
新福祉会館内に「公民館本館」が入らないことになったとしても、他の場所に公民館本館が移るということは十分にありうることである。公民館長は「公民館本館の在り方は、公民館運営審議会で諮って行くことになる」と述べている。その通りだと思う。しかし私は懸念する。今年3月に小金井市行財政改革市民会議が市長に提出した「答申書」で次のように記しているからである。「公民館本館は借地であり、新たに改築すべき特段の理由が見当たらないので、廃止とする。なお、利用者を他施設に誘導するきめ細かな対応が必要」。市長が行革市民会議の答申に従うとなれば、公民館本館は「廃止」されるのである。結局、公民館運営審議会で行革市民会議の答申内容が紹介され、「廃止」へと議論が導かれていくのではないだろうか。私にはそう思えてならない。
6月11日の連合審査会で質問には至らなかったが、社会福祉協議会への「指定管理委託」は、新たな福祉会館の建設中はどうなるのであろうか。おそらく様々な施設へ事業が分散されることから、指定管理委託ではなく、事業委託に切り換わるのではないかと思われる。同時に懸念されるのは、建設期間中、社会福祉協議会の収入が激減するのではないかということ。現在、手がけている事業に合わせて人員が配置されている。しかし建設中は事業が縮小される可能性が高い。人員削減・合理化でもしなければ、社会福祉協議会は採算が合わなくなるのではないだろうか。そのことを小金井市はどのように考えているのであろうか。
小金井市は当初、3年後に新たな福祉会館ができるとのスケジュールを示していたが、6月11日に示した案では、5年前後はかかるとの計画案に変更された。建設検討委員会で内容を協議するなどが入ったことによる。しかし、建設検討委員会で内容が決まったからといって、すぐに着工とはなりにくい。隣接する耐震不足の民間マンションがあるからである。
この民間マンション、大地震の際には福祉会館建設予定地側に崩れ落ちると主張する者がいるが、6月11日の連合審査会では注目する答弁があった。「隣接マンションについては耐震補強設計ができあがり、陳情にかかわる倒壊箇所に関する耐震補強は見られなかった」「陳情でいう崩壊図は『専門的シミュレーションが必要』と専門家は述べている」「東側に崩れるというのは、耐震診断や耐震設計からは見られない」「鉄筋コンクリートの建物としては、東側に崩れるというのは考えにくい」。これに対して、東側に崩れ落ちると主張する議員は、市の答弁を否定するモノを持ちえないことから、「100%、東側に崩れないと言い切れるのか」と言うのが精一杯であった。「100%」と言われれば、たとえ日本一の専門家であっても言い切れないのは百も承知であろうに。議会の質疑とはどうあるべきであろうか。私たちの側はそのことをよく考えるべきである。
(2015年6月15日付)
議会人事
小金井市議会をはじめ多くの地方議会では、任期4年の前半と後半とで、議会役職の見直しが行なわれる。任期2年を終えて3年目を迎えた小金井市議会では5月12日から14日までの3日間、協議が行なわれ、特別委員会以外の役職のすべてが内定。5月21日の臨時議会で確定された。
見直しにあたり私は、委員長職に就くことだけは避けたいと考えていた。前半の2年間、厚生文教委員長を務めたが、委員長として全体をいかにまとめながら混乱なくスムーズにすすめるかに神経が向かい、自身が議案の内容を深くつかみ取るという点で、十分さを欠いてしまったと感じるからである。だから、今回の見直しで委員長職につかずにすんだのはありがたいことであった。後半の2年間は、質問内容に神経を注ぎたいと思う。
私は建設環境委員に就任。駅前開発や都市計画道路問題、交通問題、環境問題など、幅広い分野で頑張ることができるとともに、都市計画審議会委員にも就くことになり、論戦力に磨きをかけたいと思うところである。
周囲の人からときどき聞かれるのは「東京都11市競輪事業組合ってなんですか」「6市競艇事業組合ってなんですか」――。「競輪」「競艇」と名が付くことから、なにやら怪しげな組織と見られているらしい。「11市競輪事業組合」とは、小金井市を含む三多摩11市が一部事務組合を設立し、府中市の京王閣で行なわれる競輪事業の一部を運営しているもので、「6市競艇事業組合」とは、小金井市を含む三多摩6市が一部事務組合を設立し、江戸川で行なわれる競艇事業の一部を運営しているものである。ひらたくいえば、公営ギャンブルである。私は今回、この2つの組合議会のメンバーに入ることになった。とはいえ私自身、今回で3回目。事業の概要も組合議会の状況も、少なからず理解はしていると自負している。
日本共産党市議団は、公営ギャンブル組合の議会役職を求めてはいなかった。他の一部組合議会の役職に付くことを切望していたのだが、他の会派の賛同を得られず、唯一役職に空席のあった公営ギャンブル組合議会に入らざるをえなくなったのである。この2つの組合議会、メンバーに入るのはどの自治体でも、当選回数の多い議員が付いている。それくらいどこの自治体でも高い位置に置いているのである。しかしその役職が一人分、なぜか空席があり、6期目の私が再登板することとなった。年3回程度の議会の他に視察もあり、けっこう大変なのである。しかしカミさんはなぜか私を白い目で睨んでいる。なにはともあれ、後半2年間、全力で頑張らなければと思う。
※PDFファイルで後半2年間の市議会人事一覧を掲載します(PDF48KB)
(2015年5月21日)
年間予算組替え案
 年間予算の組替え案を日本共産党市議団は毎年、3月定例市議会に提案している。組替えとは、税金の使い方を「このように改めてくださいな」というもので、予算修正のように「このように変えなさい!」という絶対的なものではない。だから、組替え案が可決されても市長はそれに従う義務を負わないし、組替え案全てを受け入れなければならないというものでもない。ただし、組替え案が可決されるということは、市長が提案している予算原案が否決される可能性が高いということになる。だから、組替え案が可決される可能性がある場合には、市長は組替え案に賛成しそうな議員や会派と交渉し、組替え案に明記されている何がしかの項目を取り入れることを約束する必要性に迫られる。そうすることによって、予算原案に賛成してもらうのである。だから、組替え案は修正案に匹敵する効力を持つのである。 年間予算の組替え案を日本共産党市議団は毎年、3月定例市議会に提案している。組替えとは、税金の使い方を「このように改めてくださいな」というもので、予算修正のように「このように変えなさい!」という絶対的なものではない。だから、組替え案が可決されても市長はそれに従う義務を負わないし、組替え案全てを受け入れなければならないというものでもない。ただし、組替え案が可決されるということは、市長が提案している予算原案が否決される可能性が高いということになる。だから、組替え案が可決される可能性がある場合には、市長は組替え案に賛成しそうな議員や会派と交渉し、組替え案に明記されている何がしかの項目を取り入れることを約束する必要性に迫られる。そうすることによって、予算原案に賛成してもらうのである。だから、組替え案は修正案に匹敵する効力を持つのである。
私はだいたい隔年ごとに、組替え案の作成を担当している。組替え案の作成には慣れているはずなのだが、いざつくる段階になるとあれこれ考えはじめ、寝床に入ってからも頭の中には数字や項目がぐるぐる回っている。出来上がったと思っても、見返してみるとおかしな箇所があったり、思い違いがあったりでなかなか完成しない。数字の帳尻が合わなかったり、字句が間違っていたりなどはしょっちゅうである。それでも議会事務局職員の力を借りてなんとか完成にこぎつけた暁には、やれやれと肩の荷を下ろす。しかし、それで安心できるわけではない。本会議での予算組替え提案の説明と質疑が待っているのである。質疑でしどろもどろにでもなれば、組替え案の内容への信頼は地に落ちることになる。だから、組替え項目の説得力と数字の根拠は確実におさえておくことが必要になる。
小金井市の共産党市議団は、予算案が手元に届いた段階で予算案の問題点を議論し、市議団に寄せられている市民要求や、それを反映させた予算要望書などを手元に引き寄せ、予算委員会で何を質問するかなどを協議する。予算委員会の初日が始まるあたりから組替え案の検討に入り、予算委員会の後半あたりになると組替え案の素案作成にとりかかる。素案から原案、そして完成にいたるまでに1週間から10日は要することになる。そのため作成を担当する者は、予算委員会では組替え案に関係する箇所の質疑をしっかりノートに書き込み、聞き漏らしたり、必要な数字が答弁で出て来ない場合には、担当部局から資料を取り寄せたり、必要な事項を聞きにいったりする。だから、他会派の人が質問している時も組替え案の項目にかかわる質疑であれば気は抜けず、断じて寝たりしてはいけないのである。
小金井市議団が作成した予算組替え案を見た他の自治体の同僚議員からは「え!?、こんなに詳しいモノをつくるのか?」と聞かれることがある。一般的に組替え案というものは、項目とそれを実施するのに必要なおおよその額を一覧表にして提出するのが通例のようだが、小金井市議会の場合は、予算修正案と同等の形式で作成するのが定番となっている。だから、組替え案も修正案も見た目は同じである。ただし、修正案の場合は一字一句、数字を含めて間違いは許されないし、辻褄が合わなくなれば、取り下げが迫られることになる。私は10年ほど前に予算修正案を作成したことがあるので、そのあたりの厳しさは身に沁みている。
予算修正にしろ予算組替えにしろ、その提案は、なぜ私たちが市長の提案する予算に賛成できないのかを、わかりやすく示すものとなる。同時に、政策・対案を具体的に示すものとなる。だから、賛成討論や反対討論を行なわなくても、それを見るだけで言いたいことがわかるというしろものである。今回は、日本共産党の他には生活者ネットも組替え案を提出した。市長提案の予算原案に反対したのは6会派。そのうち2会派が組替え案を提出したわけである。来年はさらに多くの会派が提出することを望みたい。
なお、日本共産党市議団が提出した組替え案と組替え項目をPDFファイルで掲載しますので、ご参照願います。
2015年度一般会計予算組替え動議、2015年度一般会計の予算組替え項目(PDF224KB)
(2015年3月30日)
貧困化
2月23日から小金井市議会の3月定例議会が始まった。市長の施政方針への質疑や一般質問が行なわれているが、「市財政の改善」「受益者負担の適正化」の名で、さらなる民間委託や有料化、負担増を求める議員が少なからずいる。でも、それが暮らしに何をもたらすかを、果たして考えているのか疑問である。
いま若者の6割は年収200万円前後で暮らしている。正規職の仕事に就くことができず、やむなく派遣や期間社員、パート・アルバイトで暮らしている。非正規雇用の大部分は社会保険に加入できず、国民年金も多い。負担割合の高い国民健康保険税を納め、月々1万5千円を超える年金を支払っている。なかには、払えずに、滞納せざるをえない若者も存在する。国保の場合には督促状や催告状が届き、最悪の場合には給料の差し押さえに発展する。年金が払えない場合には、老後を無年金で過ごすことになる。
民間委託の職場で働く人の少なくない人が、非正規に置かれている。正規職であっても年収はようやく250万円に届くかどうかである。アベノミクスがもてはやされているが、委託職場は自治体からの委託料が上がらないかぎり、賃上げはおろか定期昇給も期待できない。厚生年金であっても、年収が低ければ、老後にもらえる年金額は少ない。国民年金の場合には、最高でも月々6万5千円前後である。それも65歳からでないともらえないし、果たして65歳からもらえるのかどうかも怪しい。
高校や大学を卒業後、正規職に就けずに非正規職となった若者は悲惨である。年収200万円前後ということは、月々では16万円から17万円である。そこから税金が引かれるので、手取りはさらに少ない。アパートで一人で暮らしている場合には家賃も払うため、ようやく食べていけるかどうかの額しか残らない。
卒業後から低収入で暮らし、賃上げも定期昇給も望み薄。正規職の仕事を見つけようと思っても、探し歩くだけの時間もなければ正規職の仕事自体が少ない。そのまま歳を重ね、気がつけば年金をもらう歳に。しかし国民年金では家賃を払うと、手元にはいくばくかのお金すら残らない。だから、生活保護にすがるしかなくなる。
「民間委託」を主張する議員は、このことをどこまで認識しているのであろうか。若者が社会保険に入れない事態をつくるということは、生涯、貧困を背負い込む生活に追いやるということになるのである。そのうえ「受益者負担」を求めるというのであれば、低賃金で働き暮らす人々を、社会から除外するに等しいやり方である。
日本は貧しい国ではない。アメリカ、中国に次いで世界で3番目の経済大国である。なのに貧富の差は拡大している。豊かな者はますます富み、苦しい人はますます貧しきなかへと追いやられている。ここにメスを入れずして、どうして国や民が栄えるというのであろうか。議会の質疑を聞いていて、憤りをおぼえる。
市議会には「行財政改革調査特別委員会」というものがある。市民の暮らしや福祉を守りながら市民サービスの向上、市財政の改善をすすめるというのが、委員会設置の目的であるはず。ところが、大部分の議員は「有料化、負担増、委託化」の促進を市政に求めている。まるで、それ以外に市財政の改善はないかのように。このような委員会は即刻、廃止すべきであろう。
この3月で、この委員会は2年間の活動を終え、一定の報告をまとめあげる段階となった。日本共産党市議団が議会事務局に提出した「中間報告への意見・要望」を以下に掲載するので、ご一読いただければ幸いである。
(2015年3月4日)
行財政改革調査特別委員会の「中間報告」への意見・要望
「行財政改革調査特別委員会」設置の主目的は、市民の福祉・暮らしを守るために、現行の行財政運営を点検・検証し、市民の施策増進に向けた行財政の改革、新たな方策の追求にある。その点で、本委員会がその役割を果たしえているのかどうかが、今日問われている。
本委員会が市民の福祉・暮らしを守るために第一に行なわなければならないことは、市税の使われ方の点検である。小金井市は今日、「市財政が危機的状況」と述べ、市民から切実な要求・要望が寄せられても、「お金がない」を理由に応えようとはせず、逆に、市民に負担を求める有料化・負担増を次々に打ち出している。しかし、莫大な財源を必要とする大型開発は「聖域」扱いにしており、本委員会には大型開発の在り方を点検・検証することがなによりも求められている。
小金井市は2013年3月、「三菱UFJリサーチ&コンサルティング」に調査を委託した「行政診断報告書」を公表した。ところが、この報告書ではなぜか、市財政に一番影響を及ぼす大型開発事業や都市計画道路事業への言及が行なわれておらず、一方で、市民にさらなる負担を求める「受益者負担」は端々に登場する。なぜ、このような報告書になったのか。理由は、小金井市が委託業者に示した「委託仕様書」のなかで「提案する改善策の内容は、できるかぎり小金井市第4次基本構想及び小金井市第3次行財政改革大綱が示すまちづくりの実現を目指すものであること」としているからである。つまり、武蔵小金井駅南北の開発や東小金井駅北口区画整理事業、都市計画道路の建設計画を明記した「第4次基本構想」をふまえることを求め、そのうえで「受益者負担」「事業の委託化」を列挙した「第3次行財政改革大綱」に沿った報告書の作成を求めるというものになっている。このことは、「すべての事務事業の洗い出し」をいいながらも、基本構想や行革大綱に示した既定方針は「聖域」扱いするというものである。これでは、「危機的財政状況」と述べる要因の中から開発事業を覆い隠すということであり、これでどうして「危機的財政状況」を打開できるというのであろうか。市の姿勢そのものが問われるものである。
小金井市監査委員による2012年度小金井市歳入歳出決算に対する意見書は、この「行政診断報告書」の内容を前提に記され、小金井市行財政改革市民会議が2013年9月24日付で示した「緊急提言」も、小金井市の第4次基本構想や第3次行財政改革大綱を前提に、大型開発や都市計画道路建設などを「聖域」化し、市民負担増・事業の委託化を早急に求めるものとなっている。監査委員や行革市民会議がこのような意見書・提言を示すことになる背景には、小金井市自身に、大型開発や都市計画道路建設などを「聖域」化するという姿勢がある。ここにメスを入れてこそ、市民への負担増やサービス削減・切り捨てを行なうことなく、福祉・暮らしを守るための施策推進への取り組みに向かうものとなる。小金井市は、市政運営の在り方をただちに転換すべきであり、行財政改革調査特別委員会は、大型開発を聖域化する小金井市に対して、真正面から問題点を指摘し、是正を迫る取り組みを行なうことが求められる。
小金井市は、市財政が厳しくなっている要因として、「扶助費の増加」をことあるごとに述べている。たしかに格差拡大をすすめる国の政治によって、生活保護受給者が年々増加し、低所得者対策がいっそう求められる状況になっている。しかし「危機的財政状況」の原因は、駅前開発や都市計画道路の建設にこそある。なぜならば、扶助費などの福祉関係経費の増は、現下の社会経済状況によって徐々に現れてくるものであり、突如として登場するものではない。一方、駅前開発や都市計画道路の建設は、事業を始めた時点で億単位の財源を必要とし、起債をすれば、利子含めた借金返済が毎年、発生することになる。
小金井市は、市財政運営が2010年度からさらに厳しくなったと述べるが、その2010年度は、武蔵小金井駅南口再開発事業に4億円、東小金井駅北口区画整理事業に9億 3,600万円を使い、その財源確保のために4億 4,120万円の起債を行なっている。また、「財政的余裕がない」事態になっていると訴えた2011年度は、投資的経費が2010年度と比べて75.9%もの増となった。その最大の理由は、市民交流センター等の取得に42億円近くを投入したためである。この市民交流センターを取得するために小金井市は27億 9,120万円の起債を行ない、そのことから、2011年度の起債総額は近年になく膨れ上がっている。
小金井市は扶助費などの福祉関係経費の増を問題にしているが、多額の市税と基金を一気に使い、新たに多額の借金を背負う大型開発に対しては、なんら問題視していない。そのことが「危機的な財政状況」にならざるを得なくなった最大の要因である。ところが、1997年度からの「第1次行財政改革大綱」から今日の「第3次行財政改革大綱」に至るまで、いっさいこのことには触れず、「行革市民会議」も「監査委員」でさえも触れることなく、聖域化している。これでは「危機的財政状況」になるのは当然である。
小金井市や「行革市民会議」「監査委員」は扶助費などの福祉関係経費の増を問題にしているが、扶助費は市税だけで賄われているわけではない。よく引き合いに出される「生活保護費」は、小金井市の負担割合は4分の1、残りの4分の3は、国や東京都の支出金であり、扶助費全体でも小金井市の負担割合は3割前後にすぎない。
一方、いまなお続く東小金井駅北口区画整理事業は、小金井市の負担は市税と基金および起債を含めて48.8%にのぼり、借金の利子を含めると小金井市の負担は50%を超える事態となる。都市計画道路3・4・12号線においては、小金井市の負担割合が6割を超える状況となり、これから本格化しようとしている3・4・8号線においても、小金井市の負担割合は5割を超える。小金井市は、開発の場合には国や東京都から補助金が来ると述べるが、補助金・負担金・支出金などの交付金が来るのは開発や都市計画道路だけではなく、扶助費にもしっかりと来ている。しかも、補助金や負担金などの交付金の割合は、扶助費の方がはるかに高くなっているのである。この点をふまえない議論は、木を見て森を見ないものとなる。
「扶助費」は市民の暮らしを守るために不可欠の経費である。しかも、市民の願いとは裏腹に、今日の日本の社会経済状況は先行きが見えず、年収 200万円以下という働く貧困層、ワーキングプアと呼ばれる人々が年々増加し、生活保護を受けなければ生きていくことができない人たちも、増え続けている。これは、国民・市民の責任ではない。高齢化社会に対する対応は当然に考えなければならない課題ではあるが、それに必要な経費を予算化するのは、どの自治体でも同じであり、小金井市に限ったものではない。国・東京都・小金井市含めて対応していくべき課題である。そのことから「扶助費」に対しては、国や東京都の補助金・負担金・支出金が事業費の7割を占めるようになっているのであり、「扶助費」の増や福祉予算を問題視するのは不見識である。
ところが、第3次行財政改革大綱は「受益者負担」の名のもとに負担増を明記し、2015年度からは胃ガン検診・肺ガン検診の有料化、集会施設の有料化を予定し、国保税、介護保険料も引き上げられようとしている。一方で、武蔵小金井駅南口第2地区の再開発事業には2015年度だけでも1億円を越える補助金を投入しようとしており、お金の使い方が歪んでしまっている。まさに本末転倒の市政運営となっている。「事務事業の見直し」や「業務運営の簡素・効率化の推進」「財政健全化の諸方策」を言うならば、ここにこそメスを入れるべきである。
この2年間においてさえも、事業の委託化が次々とすすめられた。一昨年9月の小学校5校の給食調理業務の委託化を皮切りに、同年10月からの児童発達支援センター「きらり」の委託化でのスタート、昨年4月の北町地域センターの委託化スタート、そして2015年度の学童保育所4箇所の委託化、8月からの東センターの委託化計画である。予算書に記された委託料からは、そこで働く職員の人件費が低く抑えられる状況がみてとれる。現に、小金井市の小中学校の給食調理業務を受託している事業者の求人広告では、正規職員や契約社員でさえも年間で 200万円を若干上回る程度の給与となっており、夏冬の一時金を加えた場合でも 250万円前後と推測される状況である。求人公告の大部分はパート・アルバイトであり、記されている時給額は最低賃金をわずかに上回る程度となっている。委託化することによって、自治体自らが、ワーキングプア、働く貧困層をつくりだす事態となっている。
この事態を防ぐためには、賃金条項を明記した公契約条例の制定が求められるが、小金井市はいまだに具体化しようとはしていない。結局、委託化によって年収200万円から250万円程度の職員に置き換え、人件費を削減させるというものである。もちろん、委託化によって、市民サービスが拡充されるところは出てきている。そうでもしないと、委託化に対する利用者や市民の理解はえられないからである。しかし、そこには、自治体自らが働く人々の間に格差拡大をもたらしていることへの反省は、ひとかけらも見られない。これが「行財政改革」の名で平然と行なわれていることに、怒りをおぼえるものである。
職員の時間外勤務の増加が懸念されている。2014年度は、年間時間外総数が10万時間を切るようにとの号令のもとで、10万時間を切る可能性も生まれてはいる。しかし「地方分権の推進」「権限委譲」の名のもとに地方自治体に業務が次々に下ろされ、一方で職員数削減がすすめられているもとでは、果たして時間外が減るのかとの疑問はぬぐえない。業務量が増えているのに職員の時間外が減るということは、どこかにしわ寄せが行くということにならざるをえない。結局は、時間外が数字となって現れる一般職員の残業を減らし、その分、管理職者が休日出勤などをして補うということになる。このようなみせかけの時間外の削減ではなく、時間外や休日出勤をしなければならない職場の実態を直視し、業務量にふさわしい職員配置を行なうべきである。
2014年度も年度当初から、あるいは年度途中から「欠員」状況が起きる職場が生まれた。ところが小金井市は2012年4月採用者以降、名簿登載を行なわなくなり、年度途中で「欠員」状況になると、正規職員ではなく臨時・非常勤で対応せざるをえない現実が起きている。職場の業務を確実に遂行するとともに、そこで働く職員の健康保持をはかるためにも、名簿登載を行なわないために「欠員」となる状況は改めるべきである。
「行財政改革」の名で「有料化」「負担増」「委託化」「事業見直し」が行なわれている。しかしその内実は、大型開発を聖域化し、市民への負担増やサービス削減につながる施策の再編成に終始するものとなっている。小金井市は「行革」は「手段」といいつつも、実態は「目的化」している。行財政改革調査特別委員会が、その小金井市の市政運営を後押しすることがあってはならない。そのような行財政改革調査特別委員会であるならば、市民にとってはサービス削減、負担増ばかりが押し寄せ、百害あって一利なしとなる。
小金井市には厚生文教委員会、建設環境委員会、総務企画委員会という3つの常任委員会がある。行財政改革調査特別委員会で議論している事柄は、すべて常任委員会で議論しうるものである。日本共産党市議団は、行財政改革調査特別委員会を2014年度限りで閉じることを強く求めるものである。
以上。
PDFファイルを閲覧するためにはアドビ社製の「Adobe Acrobat Reader」が必要になります。
AdobeのWEBサイトよりダウンロードしてご使用になれます。

|