�w�O�J���̐����₤�Z�����[���Ĕی�
�@�n�������@��74���̋K��ɂ��ƂÂ��A�s�����L���҂�50���̂P�ȏ�̗L���������W�߂Ē�o�������Ă��A10��14����29���̂Q���ԁA�s�c��ŐR�c���ꂽ�B���Ă̖��̂́u������s�̕���������w�����Q�n��s�X�n�ĊJ�����ƂɌW��s�s�v��ċy�юs��̎x�o�ւ̎^�ۂ�₤�Z�����[���v�B������s�̎x�������n���҂��w�O�ĊJ�����Ƃ�i�߂悤�Ƃ���Ȃ��ŁA�v��ĂƐŋ��̓������u���v�Ƃ��邩�u�ہv�Ƃ��邩�̔��f���A������s���̓��[�Ō��߂Ă��炨���Ƃ������̂ł���B
�@������s�͍����A�u�s�̍����͊�@�I�v�ƃA�s�[�����A��N���獡�N�ɂ����č��ېł̑��ŁA���w�Z���H�����Ɩ��̈ϑ��������s�B���t�ɂ͏W��{�݂̗L�����A�݃K���E�x�K�����f�̗L�����A�w���ۈ珊�̖��Ԉϑ������v�悵�Ă���B�����ď�����s�́A�V�S�~�����{���݂�V���Ɍ��݁A������ق̌��đւ��Ȃǂ�����Ă���A�V���Ȏ��Ƃɍ����Ă�]�T�͂Ȃ��͂��ł���B�Ƃ��낪������s�́A���Ԃ��s�Ȃ��w�O�J����15���~�]�̕⏕�����x�o����Ƃ����̂ł���B���̂��Ƃ��玿�^�Q���ڂƂȂ���29���́A������s�̒������I�ȍ����v��̌����Ə�����s�����S����15���~�]�̕⏕���̍��������^���ꂽ�B
�@�܂��u�������I�ȍ����v��v�ł���B�s�����ɑ傫�ȉe�����y�ڂ����Ƃ��ڔ������̂Ȃ��A�V���ɉw�O�J���ɕ⏕�����o���Ƃ����̂ł���Ȃ�A����̎s�����̌��ʂ��A�e�N�x�̎����Ǝx�o�̐��v���������Ƃ��s���ƂȂ�B�����������������́u���N�H�ɂȂ�Ȃ��Ǝ����Ȃ��v�ƌ����B�u����ł͓���A�b�ɂȂ�Ȃ��ł͂Ȃ����v�Ƌl�ߊ��ƁA�u�w�O�J�������Ɖ������A���Ɣ��\�Z�v�サ�Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ�������Əq�ׂ�B�܂�“���₪�����ł��\�Z�v�シ�邵���Ȃ��B���ꂪ�S�������̖���”�Ƃ����킯�ł���B
�@���Ɂu15���~�]�̕⏕���̍����v�ł���B�u��@�I�����v�Ƃ������Ƃ́A�⏕���̑唼���؋��ɗ��邵���Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B�Ƃ��낪�A�N��(�؋�)�������F�߂Ă���邩�ǂ����͂킩��Ȃ��Ƃ����B����Ɏ��₳���ƁA�w�O�J���̕⏕�Ώێ��Ƃ̂����u�����v�v���v�Ɓu�y�n������v�́A�u�N������̂ł͂Ȃ����v�ƌ����B�Ƃ������Ƃ́A�u�N�s�v�̑��z�S��3,500���~�́A��ʍ����Řd��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ƃł���B�s�����炳��ɍ����A���Ԉϑ��E�T�[�r�X�팸�ŁA�S��3,500���~�̍������m�ۂ��悤�Ƃł������̂ł��낤���B���Ȃ݂ɁA���ق����̂́u�܂��Â���S�������v�B���X�s�����ɋc��̔��Α���������B���̐�ɂ͊����������������Ă����B
| �⏕�Ώێ��� |
���Ɣ�T�Z�z |
�s�⏕�z |
�N�� |
| �����v�v��� |
11��1,000���~ |
�P��8,500���~ |
�N�s�� |
| �y�n������ |
15���~ |
�Q��5,000���~ |
�N�s�� |
| �����{�ݐ����� |
63��9,000���~ |
10��6,500���~ |
�N�\ |
| ���v |
90���~ |
15���~ |
|
�@�ĊJ�����Ƃ̋�̉��Ɍ����āA������s�͌��݁A�n���n���҂Ƌ��c���s�Ȃ��Ă���Ƃ����B���̂Ȃ��ɂ͕⏕�����܂܂�Ă���Ƃ̂��ƁB�⏕�Ώێ��Ƃ̂Ȃ��ɋN�s�̂��̂��z�肳���Ȃ��A�⏕����S�z�A�o�����Ƃ��ł���̂��B�܂��Â���S�������͓��قł��̂悤�ɂ��q�ׂĂ���B�u�⏕���͕⏕�v�j�ɂ��ƂÂ��čs�Ȃ��邪�A�w�\�Z�͈͓̔��Łx�Ƃ��Ȃ��Ă���v�B���̂��Ƃ�“�⏕���͑S�z�o���Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�܂����”�Ƃ����悤�ɂ���������̂����E�E�E�E�B�����������Ƃ���A���Ⓦ���s�̕⏕�z�������邱�Ƃ��z�肳���B�Ȃ��Ȃ�A������s���\�Z�������⏕�z�ɉ����āA���Ɠ����s���⏕�z���������Ƃɕ⏕����t���邩��ł���B���ɏ�����s�����Ȃ߂̗\�Z�����v��ł��Ȃ������ꍇ�́A���Ȃ߂ɗ\�Z�����ꂽ�z�ɍ��킹�āA�⏕�z���������Ƃɍ��Ɠ����s�͕⏕����t����̂ł���B
| |
�⏕�z�̊��� |
| ������s |
�⏕�Ώێ��Ɣ�T�Z�z�̂U���̂P |
| �����s |
�⏕�Ώێ��Ɣ�T�Z�z�̂U���̂P |
| �� |
�⏕�Ώێ��Ɣ�T�Z�z�̂R���̂P |
�@������ɂ��Ă��A������s�̎s�����^�c�͌��ʂ��������Ȃ��A�ǎ��s�\�ȏ�ԂɊׂ낤�Ƃ��Ă���B���̑D�ɏ悹���Ă���11���l�]�̏�����s���قLj���Ȃ��̂͂Ȃ��ł��낤�B�Ȃ̂ɁA���̉w�O�ĊJ�����Ƃ��Z�����[�ʼnۂ������悤�Ƃ�������̏��ĂɎ����}�A�����}�A����}�A���v�A���������A�L�������� 5,454�M�̊肢�݂ɂ����Ă��܂����B����A��������̂ł͂Ȃ��B
�i2014�N11���R���t�j
�@���ȉ��A���Ăɑ�����{���Y�}�s�c�c�̎^�����_���f�ڂ��܂��B
�Z�����[���ւ̎^�����_
�@���{���Y�}�s�c�c���\���āA�Z�����[��ᐧ������߂�{�c�ĂɎ^���̓��_���s�Ȃ��܂��B
�@���߂ďq�ׂ�܂ł��Ȃ��A�s���̎�l���͎s���ł��B��l���ł���s�����A������s�̌����ł��镐��������w����̊X�݂̍�����A�s���̑��ӂŌ��߂Ă����A���̂��߂̎葱�������߂悤�Ƃ����͓̂��R�̂��Ƃł��B�V�����{����W�����{�܂ł̐^�Ă̐^�������ŁA�Z�����[���̐�������߂钼�ڐ��������^��������Ă���ꂽ�����̕��X�̂��w�͂ɁA�S����h�ӂ�\���܂��ƂƂ��ɁA���������ꂽ�� 5,800�l�A�L���������ł� 5,454�l�ƂȂ���X�̐����s���ɓ͂��邽�߂ɕ������ꂽ�݂Ȃ���̂��s�͂ɁA����������v���ł��B
�@����������w�����Q�n��s�X�n�ĊJ���v��́A�ȉ��̗��R�����肪����܂��B
�@���ɁA�s��𓊓�����Ƃ������ł��B������s�́u�s�̍����͊�@�I�v�Əq�ׁA���N�x���獑�ېł̑啝���グ���s�Ȃ��A���N�x�ɂ͎s���W��{�݂̗L�����A�݃K���E�x�K�����f�̗L������\��B�E���l������팸���邽�߂ɍ�N�X�����珬�w�Z�T�Z�̋��H�����Ɩ��̈ϑ������s�Ȃ��A���N�S������͊w���ۈ珊�S�ӏ��̈ϑ�����\�肵�Ă��܂��B�u��@�I�����v���q�ׂ鏬����s���A�w�O�J���Ȃ�ΐŋ��𓊓�����Ƃ��������͓���A�s���̗���������̂ł͂���܂���B
�@�����āA������s�͍����A�傫�ȍ�����K�v�Ƃ���l�X�Ȏ��Ƃ�����Ă��܂��B�����̎��Ƃ��s�������ɉe��������ڂ����ƂȂ��i�߂Ă������Ƃ��ł���̂��A�����̎s�������̂��Ƃɕs���ƌ��O������Ă��܂��B�Ƃ��낪�A���̂��Ƃɉ����邽�߂ɋ��߂��Ă��钆�����I�ȍ����v��́A���܂��Ɏ�����Ă͂��炸�A�����I�Ȍ��ʂ����Ȃ��A�Ƃɂ���15���~�]�̎s��𓊓������Q�n��ĊJ���ɓ˂��i�����Ƃ����킯�ł��B
15���~�]�̎s����ɂ��Ă��A�N���s�\�z���ǂꂭ�炢�ɂȂ�̂��A���������N���s���F�߂���K���ɂ��Ăǂ��Ȃ̂��ɂ��Ă��A�m������͎̂����Ȃ��Ƃ����ł����B����ł́A���z�̈�ʍ������[�Ă邱�Ƃɂ��Ȃ肩�˂��A�s�������ɕK�v�ȍ�����D�����Ƃɂ��Ȃ肩�˂܂���B����Ȑ�s���̕s�����Ȗ��ӔC����܂�Ȃ��s���^�c�͒f���ĔF�߂邱�Ƃ͂ł��܂���B
�@�������A������s�͂U���c��̂Ȃ��Łu��Q�n��ĊJ���̍����͂ǂ�����̂��v�Ƃ̎���ɑ��āA�u�����m�ۂɌ����čs�������v�̓O�ꂵ�����g�݂ɖ��߂�v�Əq�ׂĂ���A�u�s�v�v�ɂ���ē���ꂽ�������w�O�J���ɏ[�ĂĂ����Ƃ����z���l������Ă��܂��B�u�s�v�v�́u�s���T�[�r�X�[���̂��߁v�Ƃ������������܂₩���ł��邱�Ƃ����炩�ƂȂ�܂����B
�@������s��15���~�����̍����Ƃ��Ă���u�s�s�ĊJ���@ 122���v�́u�⏕���邱�Ƃ��ł���v�Ƃ������̂ł���A�`���K���ł͂���܂���B�u�s�����͊�@�I�v�𗝗R�ɁA�s���T�[�r�X�팸�E���S���������̂Ȃ�A�`���K���ł͂Ȃ��⏕�������͂�߂�ׂ��ł��B�������A�k�Е������Ƃ�U�N��̓����I�����s�b�N���Ƃɂ�鎑�ލ����ɂ���āA�⏕�o������オ�邱�Ƃ͕K���ł��B
�@����̎��^�Ŗ��炩�ƂȂ������Ƃ́A��Q�n��ĊJ�����Ƃɑ��f�x���b�p�[���ւ���Ă���A���Ɣ��p�o�����Ă���Ƃ������Ƃł��B�⏕���𓊓����Ȃ��Ă��A���ꂽ���z�Ŏ��Ƃ��\���ɂ܂��Ȃ���Ƃ����P�[�X��������Ă���A�⏕�������̕K�v���͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�ŋ������������̂Ȃ�A�s���ň��̔F�ۈ牀�s����O�����ł��Œ�N���X�̕����E����\�Z�̊g�[�ւƏ[�Ă�ׂ��ł��B���ꂱ�����u�X�Ȃ銈�����v�̈�Ԃ̕���ł��B
�@������s�́u�ĊJ���ɂ���ĐŎ����ɂȂ�v�ƌ����܂����A��P�n��̍ĊJ���ɂ���ď��������̂́A�c��ގs�����̎؋��Ɓu��@�I�����v�̖��̂��ƂɎs���ɉ��������S���ł��B����̑�Q�n��ɂ����ẮA�ː� 680�˂̕����}���V�������\�肳��Ă���A�t�@�~���[���т�q��Đ���̓������\�肳��܂��B�����w�Z�֒ʂ��q�ǂ������������邱�Ƃɂ�鋳���s����A�ۈ�{�ݕs���Ȃǂ�����Ɍ��O����܂��B�����̎{�ݐ����ɂ������p��������s�́A�ǂ����Ă���̂ł��傤���B���ǁA����悹�͔[�Ŏ҂ł���s���ɂ��邱�ƂɂȂ�܂��B�s���ɕ��S�����������ۂ����Ƃɂ����Ȃ�Ȃ��ĊJ�����Ƃւ̐ŋ������́A�s�Ȃ��ׂ��ł͂���܂���B
�@���ɁA14���̖{��c�ł̐�����\�҂̔����ɂ�����܂����悤�ɁA���̏�����s���ɂ́u�s���Q���v�̎��_���������Ă��邱�Ƃł��B�s�������S�̂ɂ����Ă��A�s�����ɂ����Ă��傫�ȉe����^����X�Â���ł���ɂ�������炸�A�s��������͂������P��̂݁B������������ł͌v��ɔ��̐��⌜�O��\�����鐺���������A����Ȃ������J�Â����߂鐺�����o���Ă���ɂ�������炸�A�킸���P��̂݁E�Q���Ԃ���̐�����œs�s�v�挈��ւƃR�g���^�сA���Ɖ��ւƓ˂��i��ł��邱�Ƃ͏d��ł��B
�@������\�҂̈�l�́A�������q�ׂĂ��܂����B�u�R�����̏����g������̎��ӏZ���ւ̐����́A�ʂ肢����̂��́B�����Ă��A�܂���̉�����Ă��Ȃ��Ƃ̂��ƂŁA�����킩��Ȃ���ԁv�B���̂��Ƃ���A���ӏZ���ɑ��Ă������v��T�v�͏\���ɒm�炳��Ă��炸�A�������A�������P��̎s��������݂̂œ����Q�n��ĊJ���v��������߂Ă������Ǝ��̂����܁A����Ă��܂��B�ł�����u�s���S�̂̈ӌ����Ăق����B�s���̈ӎv��`����B��̎�i�ł���Z�����[�����{���Ăق����v�Ƃ̎咣�́A���R�̂��Ƃł��B
�@��O�ɁA�s�s�v��̓��e�ł��B�����̍����ɂ����āu�X�J�C���C���̌`���v�Ƃ������̂��ƂɁA95���܂ŔF�߂���̂ƂȂ��Ă��܂��B�n�P�̌i�ς����Ƃ����̂Ȃ�A���ӏZ���̓��ƌ���D����������^��������A�����w�r�����\�Ƃ���悤�Ȍv��͔F�߂��A�A���ʂ�쑤�̍��������ɉ������v��ɉ��߂�ׂ��ł��B
�@�u�h�Џ�̉ۑ���������Ĉ��S�E���S�Ȃ܂��v�������̂Ȃ�A�n��Z���̐����͂��ɂ����Ȃ�悤�Ȓ����w�r���ł͂Ȃ��A��w�̍ĊJ�����Ƃւƒn���n���҂��ׂ��ł��B��������Q�n��͋�����30�����������������Ă��炸�A�c���70���͋������H�⒓�ԏ�A�n�ƂȂ��Ă��܂��B�Z��W�n�Ƃ͓��ꂢ�����A���I�����𓊓�����K�v���Ȃǂ���܂���B
�@�Z�����[��ᐧ������߂钼�ڐ��������^���̒��Ŗ��炩�ƂȂ������Ƃ́A����̓����Q�n��ĊJ���v��̑��ݎ��̂��A�����̎s�����m��Ȃ��A�m�炳��Ă��Ȃ������Ƃ������Ƃł��B�Q���̒����w�r�����v�悳��A�s��܂߂�60���~���̐ŋ�����������悤�Ƃ��Ă��邱�ƁA�s��𓊓����邾���̌��������Ȃ����ƂȂǂł��B���ӏZ��������ł͏����g������́u��̉�����Ă��Ȃ��A�킩��Ȃ��v�ƌ����A�s��������͂킸���P��̂݁B����Œ����w�r�������āA�i�ςˁA���ӏZ���̐������ւ̉e�������肾���w�O�ɂ��Ă����̂��A��炵����ςȂƂ��Ɏs�łĂĂ����̂��ȂǁA�����̈ӌ���s���A�^�₪�o�����͓̂��R�ł��B���̂��Ƃ��s���́A�ǂ��l���Ă���̂ł��傤���B�s���̐��Ɏ����X����ׂ��ł��B
�@������s�͒��N�ɂ킽���ăS�~�����{�ݖ�������A�X�����s�c��ł͓˔@�A�s�����u���[�X���ɔ����v�������o���ȂǁA���̊Ԃ̎s�������ψ���̋c�_�������A������ʂĂ����ԂƂȂ��Ă��܂��B�Ȃ̂ɁA�w�O�J���́u��@�I�����v�ł����Ă��ːi����Ƃ����̂́A���܂�ɂ��s���s�݁E���ӔC�Ȏs���^�c�ł��B���̂悤�ȏ�����s���̂Ȃ��ɂ����āA����̓����Q�n��ĊJ�����Ƃ̓s�s�v��݂̍���A�s�����̎x�o�݂̍����������s���̏Z�����[�Ŏ^�ۂ�₢�A���f�����߂Ă������Ƃ����{�c�Ă̓��e�́A�Z������l�������������n�������@�̐��_������A������s�s���Q�����̊�{���O���炢���Ă����R�̎p�ł���A�s���̒��ڐ����^����҂܂ł��Ȃ��A������s�݂����炪���f���ďZ�����[���s�Ȃ��ׂ����̂ł��B
�@�s������юs�c��́A�L�������� 5,454�l�̖��ӂɏ]���A�Z�����[�����{���ׂ��ł��B����āA�Z�����[���{�����߂�{�c�ĂɑS�ʓI�Ɏ^�����邱�Ƃ�\�����A�^�����_�Ƃ�����̂ł��B
���w�Z���H�����Ɩ��̈ϑ���
�@������s�͍�N�X������A�s�����w�Z�X�Z�̂����T�Z�̋��H�����Ɩ��̈ϑ��������s�����B�ϑ����͐V�N�x�ɓ����ĐE���c�̂ƍ��ӂ������Ƃ��A�}�����̉����ꂽ���́B���̂��߁A�Q�w������̈ϑ����Ɍ����A���������ȃX�P�W���[�����g�܂ꂽ�B
�@�E���c�̂Ƃ̍��ӂ́A�S��15���t�̐E���c�̃j���[�X�u���͂悤�v�œˑR�A�\�����ꂽ�B
�@�u12����A�c�̌����s�Ȃ��A���w�Z�T�Z�̋��H�����̖��Ԉϑ����ō��ӁB���N�X������ϑ����v�Ƃ������̂ł���B���ꂩ��̏�����s�́A�X������̈ϑ����Ɍ����Ĉ꒼���ɋ삯�������B�ȉ��ɂ��̌o�߂��L���B
���T���P���t�u�s��v�ɕی�Ґ�����������f��
���T��14���̎s�������c(�s���̈ӎv����@��)�ňϑ������ŏI�m�F(����)
���T��13���`20������тU���T��(��)�Ōv10��̕ی�Ґ�����
���T��31���ɋƎґI��̂��߂̃v���|�[�U�����{�̋N�ď���o
���U���P���t�u�s��v����тU��10���t�u�z�[���y�[�W�v�ňϑ��Ǝ҂̌���\
���U���R������̂U���c��Ɉϑ��\�Z(�T�Z×�V�J������ �v7,795���Q��~)���o
���U��10���`21���A�Ǝ҂̐\���ݎ�t�E���{�v�̓��̔z�t�A�Q���ӎv�m�F
���U��24���`28���A�Ǝ҂̎����t
���U��26���̍ŏI�{��c�Ŏ^�������ňϑ��\�Z����
���V���P���A�Ǝ҂ւ̎���ɑ����
���V��12���܂ŁA�Ǝ҂̎Q�����i�m�F���ށE��ď����̒�o
���V��19���A��ꎟ�R��(���ސR��)
���V��26���A��R��(���ނ���уq�A�����O�ɂ�鑍���R��)
���W���Q���A�R�����ʂ̌��\
���W���T���A�ϑ��Ǝ҂Ɛ��ӌ_�����
���W��23���A���ӌ_��m��
���W��24���`31���A�s�������ƈϑ��Ǝ҂Ƃ̊Ԃł̈��p��
���W�����{�A�w�Z�E�o�s�`�E�W�҂̎��H��
���X������ϑ� |
�@�u�����Ƀ����ȃX�P�W���[���ňϑ����ւƂ����̂ł͂Ȃ����v��10���R���̌��Z���ʈψ���Ŗ₤�ƁA�w���ے��⍲�́u�����g�A�^�C�g�ȃX�P�W���[�����ȂƎv���Ȃ���i�߂Ă����B�ϑ����Ǝ҂ɂ����f�������Ă��܂����v�Əq�ׂ��B�Ȃ��A���̂悤�ȁu�^�C�g�ȃX�P�W���[���v�ƂȂ����̂��B����́A�����Ȃ�ł��ϑ����𐄂��i�߂�Ƃ�����t�s���̕��j�����邩��ł���B
�@�v���|�[�U���ŋƎ҂�I�肷��ɂ�����A������s�͈ϑ�����z�������Ă���B���Ԃ�2013�N�X������2014�N�R���܂ł̂V�J���Ԃł���B�ł͎��ۂ̌��Z�z�͂ǂ��������̂��B�ȉ������̊z�ł���B
| |
�ϑ�����z |
�ϑ����Z�z |
�� |
�ϑ��Ǝ� |
| ��w�Z |
1,536���T��~ |
1,469��2,650�~ |
95.6�� |
�O���[���n�E�X |
| ��l���w�Z |
1,535���W��~ |
1,458��9,750�~ |
95.0�� |
���m�H�i |
| �O�����w�Z |
1,533���Q��~ |
1,501��6,050�~ |
97.9�� |
��y�m�t�[�h�T�[�r�X |
| �@���w�Z |
1,656���R��~ |
1,572��9,000�~ |
95.0�� |
���m�H�i |
| ��@���w�Z |
1,533���S��~ |
1,467��7,950�~ |
95.7�� |
�O���[���n�E�X |
| ���v |
7,795���Q��~ |
7,470��5,400�~ |
95.8�� |
|
�@�ł́A���̈ϑ����z�ŁA���Ǝ҂͒����Ɩ����s�Ȃ��E���ɂǂꂭ�炢�̒������x�����Ă����̂ł��낤���B��������肷��O��Ɉϑ����Ǝ҂��o�������l�L���ł́A�ȉ��̂悤�ɂȂ��Ă���B�u�����⏕�̃p�[�g�E�A���o�C�g ����900�~�A�L���i��1,000�~�v�u�_��Ј�(�����X�^�b�t) ����17���~�ȏ�v�u���K������ ����15���T��~�`26���~�v�B���Ɂu����17���~�v(�_��Ј�)�̏ꍇ�A�N���Ŋ��Z����Ƃ�����ɂȂ�ł��낤���B�u204���~�v�ł���B
�@�_��Ј��E���K�������̏ꍇ�́u�ܗ^����v�ƂȂ��Ă���B���ɁA�N�ԂłS�J���́u�ܗ^�v���������Ƃ��Ă��u272���~�v�ł���B�������A����Ȃɏܗ^���x�������̂��B�������ٗp���N�x�Ŏx�������̂��낤���B
�@���H�����̈ϑ�����ł́A�������⒲���⏕���̊�Ԃꂪ�Ђ�ς�ɓ������B�Ȃ��Ȃ�A���^�Ȃǂ̑ҋ��E�J���������悭�Ȃ�����ł���B���̂��Ƃɑ��錩�����������ƁA�w���ے��⍲�͎��̂悤�ɓ��ق����B�u�������̓�����肪���������Ƃ͏��m���Ă���A�ϑ���ɐ�߂�l������̔c���ɂ��ẮA����̌����ۑ�Ƃ������v�B
�@���͎v���B���������A�ϑ����邱�Ǝ��̂��u�l����팸���ʁv��_�������̂ł���A������Ǝ҂ɂƂ��Ă��A���肫��̐l������m�ۂł��Ȃ��d�g�݂ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ��� �B�u�l����팸�ł����v�Ɗ�Ԑl�X�́A���̂��Ƃ��ǂ̂悤�Ɍ��Ă���̂ł��낤���B�ϑ�����Ŋ������炵�ē����l�X���v���ƁA���͓���A��ׂȂ��̂ł���B
�i2014�N10��28���t�j
�݂���E�x���f�̗L����
�@������s���A���f�̗L�����ɓ��ݏo�����B10��16���ɊJ���ꂽ�s�����N�Â���R�c��Ɂu�݂��f�v�u�x���f�v�ւ̎��ȕ��S�����Ă����₵���̂ł���B���f�̗L�����ɂ��ẮA�s���̍l�����ɗ��l�X�ō\�������u�s�������v�s����c�v�����N�Q��13���ɔ��\�����u���ԓ��\�v�ňȉ��̂悤�ɋL���A������s�̐K���������Ă���B
�@�u�Ǝ����f��e���f�͂��̂قڑS�Ă������ōs���Ă���A�ꕔ�̎�f�҂̂��߂ɁA���Ⓦ���s�̕��S������Ƃ͂����A��f���Ȃ��s���̕��S�ɗ���\���ƂȂ��Ă���v�u�e��(��)�f�ɂ��ẮA�s���Ԃ̕��S�̌������̊m�ۂ�A�����̈�Ô�̑����ւ̑Ή��A�s���̈�Ô�ւ̊S�����߂邽�߂ɂ��A�ꕔ���ȕ��S�������邱�Ƃ͗����������₷���ƍl�����A�����ɓ�����}��ׂ��ł���v�B
�@�K���������ꂽ������s�́A16���̎s�����N�Â���R�c��Ɂu�݂��f 1,000�~�v�u�x���f�̋��������g�Q�� 500�~�A�\ႌ��� 500�~�v�̎��ȕ��S�����Ă��āB�����āu�݂��f�v�Łu�v���������v�ƂȂ����ꍇ�̎�f�E�����̎��ȕ��S�z�������x��p�~���A�݂��f�̐��������ł����S�����߂�Ƃ��Ă���B������s�͗��N�x����L�������s���Ƃ����̂ł���B
�@�������������Ɂu�L�����v�����ł͎s���̗������Ȃ��ƍl�����̂ł��낤�B����̗L�����œ����������g���Č��f�Ԃ̊��p���Ԃ��������A��f��������̂Ԃ₷�ƂƂ��ɁA�݂��f�Ɣx���f���Ɏ��{���邱�Ƃɂ��A��f�����ɒ[�ɒႢ�x���f�̎�f�������}�肽���Ƃ��Ă���B���̂��Ƃ��珬����s�́A����̗L�����ɂ����221���~�̍Γ����m�ۂ��锽�ʁA���f�Ԃ̊��p���ԉ������f�ґ��ɂ����225���P��~�̎x�o����\��B���������S���P��~�̎����o���ɂȂ�Ƃ��Ă���B
�@�L�����́A���łɎ��ȕ��S����������Ă���u�����f�v(2,000�~)�ƍ���́u�݂��f�v�u�x���f�v�ɂƂǂ܂�̂��낤���B�s�����������j�ł́A�u����A���s�̓����y�їL�����̓����ɂ��e�������l�����A���f�Ԃɂ�邪�f����i�K�I�ɗL���������{����v�Ƃ��Ă���B�܂�u�咰���f�v�u�q�{���f�v���u�i�K�I�ɗL���������{����v�̂ł���B�����珬����s�́A�s�����N�Â���R�c��ɎO����26�s�̗L�����̎������o�B�u�T���f�S�ėL�� 11�s�v�u�����f�̂ݗL�� ������s�܂�10�s�v���Əq�ׂĂ���B
�@�L�����́u�a�C�̑��������E�������Áv�ɋt�s����B�������i�C����ɎЉ�ی����̃A�b�v�A�����̌����A�S������̏���ő��łɂ���āA���������͊m���ɒቺ���Ă���B����Ȏ��ɗL�������s�Ȃ��A��f���̒ቺ�������̂͋^���̂Ȃ��Ƃ���B���͌��f��f���ڕW��50���ɒ�߁A������s���u���N���i�v��v��2016�N�x�̖ڕW��ݒ�B�u10�N�ԂŁA���S����20��������v�Ƃ��Ă���B�Ȃ̂Ɂu�L�����v�ł͖ڕW�B���ǂ��납�A���������̌�ނ������N������������Ȃ��B
�@����ɏ�����s�́A�Ǝ����N�f������茒�f�A�������҈�Ì��f�̗L����������ɓ���Ă���B�u�s�������v�s����c�v�́u���ԓ��\�v�Łu�������{�v��˂������A��R���s�������v��j�ł݂�����u��v�ҕ��S���̒����v�L���Ă��邩��ł���B�u���ȕ��S�Ȃ��ő��������E�������Âɓ����v���ƂƁu�s���Ԃ̕s���������Ȃ����v��V���ɂ����A“���S�����o���Ȃ��҂͌�(��)�f�͎����Ȃ��B���ꂪ�����Ȃ�����”�Ƃ����p���͍s���̂Ȃ��ׂ��݂���ł͂Ȃ��B�������ėe�F�ł�����̂ł͂Ȃ��B
�@�u�s�������v�s����c�v�́A������Ɂu�������ׂ����Ɓv�Ɓu�p�����ׂ����Ɓv�ɐU�蕪���Ă���̂ł��낤���B�u���ԓ��\�v�̈�A�̋L�q����́A�u�s�����̊�@�I�v�𗝗R��“�������炨������������”�Ƃ��������ӎv������������B�悤����ɁA�s���Ɋ�@�ӎ���������A�Ƃ�₷���Ƃ��납��Ƃ��Ă�낤�Ƃ��������ł���B�������A��t�s�����i�߂������Ă����^�J�����Ƃ�s�s�v�擹�H���ݎ��Ƃ́A���Ƃ��s�����ɔ���Ȏx�o�ƒ����I�ȕ�����������̂ł������Ƃ��Ă��A�u�������ׂ����Ɓv�ɂ͊܂߂Ȃ��̂ł���B
�@�ǂ�ȂɗL�Ӌ`�ő�Ȏ��Ƃł����Ă��A�s���̍l���ɂ����킸�A�s���̈ӂ����u�s�������v�s����c�v�Ɂu�s�v�v�u�������v���ɂ܂ꂽ��]�킴������Ȃ��\�\�\���̂悤�Ȏs���^�c�ł����̂��낤���B���āu���Ǝd�����v�ŕK�v�Ȏ��Ƃł����Ă���̂ĂĂ���������}�����́A�Z���Ԃɍ����̎x���������]�����Ă������B��t�s���̗��������������͂Ȃ��ł��낤�B
������s�́w���f�x�̐����iPDF578KB�j
�i2014�N10��25���t�j
���t����W��{�݂S�ӏ���L����
�@������s�́A��R���s�������v��j�Łu�L�����v�������o���Ă���s���S�ӏ��̏W��{�݂��A���N�S�����痘�p�����̒������{�ɓ��ݏo�����Ƃ��Ă���B�V��11������W��13���܂ł̂ЂƂ��̊ԁA������s�͗L�����Ɍ��������n�Â�����s�Ȃ����߂ɁA�L�����Ώۂ̏�V����فA���V���فA�㐅��فA�w�l��ق̂S�ӏ��Ɂu���p�҃A���P�[�g�v��u���A�L�����ɑ���ӌ��c�������{�B�X������̑������ψ���ɏW�v���ʂ����ꂽ�B
�@�u���p�҃A���P�[�g�v�ł͗L�������s�Ȃ����R�Ƃ��āA�u�W��{�݂𗘗p������Ƃ��Ȃ����Ƃ̌������̊ϓ_����v�Ɛ����B���̂����ŁA�u�L���ƂȂ����ꍇ�ɗ��p���邩�ǂ����v�Ɩ₢�����A�u�L���Ȃ痘�p���Ȃ��v�u���p�������z�Ȃ痘�p�������v�u�L���ƂȂ��Ă����p�������v�̂Ȃ�����I������悤�ɋ��߂Ă���B
�@�������s�̏W��{�݂́A����̒c�̂�l�łȂ���Η��p�ł��Ȃ��Ƃ������̂ł͂Ȃ��A�s���ł���ΒN���������u�ĂȂ����p�ł�����̂ł���A���܂͗��p���Ă��Ȃ��Ă��A�₪�Ă͗��p���鑤�ɂȂ肤����̂ł���B������������s�́u���U�w�K�v���d�v�����Ă���A�����ق�}���قƓ��l�ɁA�W��{�݂��s�����ǂ��M�d�ȏ�ƂȂ��Ă���B
�@�u�L���ƂȂ����ꍇ�ɗ��p���邩�ǂ����v�Ƃ����ݖ�قNj����Ȃ��̂͂Ȃ��B�W��{�݂��L�������ꂽ�Ƃ��Ă����ɂǂ��ꏊ���Ȃ�������𗘗p����ق��ɓ��͂Ȃ��A�u��ނȂ����p����������Ȃ��v�Ƃ����̂�����ł���B
�@�W��{�݂̗L�����ɑ��ẮA�s���̍l�����ɗ��l�X�ō\�������u�s�������v�s����c�v�����N�Q��13���A�u���ԓ��\�v�\���A�L�������i�����߂�ȉ��̕�����˂������B�u�{�ݔ����ɂ��ƏW��{�ݑS�̂ł͎x�o�ɑ�������̊����͖�W���i���x���z��8,915���~�j�����A���̗��p�p�x������ƁA���P��ȏ㗘�p���郊�s�[�^�[�����p�ґS�̖̂�80���A�X�ɂ��̒��ŏT�P��ȏ㗘�p���郊�s�[�^�[����30�����ƂȂ��Ă���A���s�[�^�[�̗��p���啔�����߂�����@�����B����͏W��{�݂̉^�c�o��̑啔�����A���p���Ă��Ȃ��s���̐ŕ��S�Řd���Ă��邱�Ǝ����Ă���A���}�ɗ��p�ҕ��S�����ׂ��ł���B�܂����K�͂̏W��{�݂ɂ��ẮA����ւ̏��n�┄�p�Ȃǂ̉\��������ɓ���A�{�݂̓��p�����l���Ă����K�v������v�B������s�́A���́u���ԓ��\�v�ɒǂ����Ă���悤�ɁA�L�����ւƓ����������̂ł���B
�@������s�͏W��{�݂̗L�����ŁA�N�� 689���~�̍����m�ۂ�\��B���̈���ŁA�n�傪�s�Ȃ��J���ɂ�������炸�A����������w����̐V���ȊJ���ɂ�15���~�]���^����Ƃ����B�������u�s�������v�s����c�v�́A�w�O�J���ւ̔���Ȑŋ������ɑ��Ă͈ꌾ����낤�Ƃ͂��Ă��Ȃ��B
�@�]�ɂ��y���ގs���̎���I�����ɖ����̏W��{�݂��[�Ă��邱�Ƃ́u���v�Ƃ��Ȃ���A�n��̗��v�m�ۂ̂��߂̉w�O�J���́u�s��v�ɂ���\�\�\�u�s�������v�s����c�v�̒ꂪ�m�ꂽ�Ƃ������̂ł���B
�L�����ΏۏW��{�݂̔N�ԗ��p�����iPDF463KB�j
�i2014�N10��23���t�j
�w���[�X���ɔ��������x�̓^���Ɖۑ�
�@������s��1994�N�P������W�K���Ă̖��ԃr������A�S�ق��u�s������Q���Ɂv�Ƃ��ė��p���Ă���B���ݎŎx�����Ă������z�͍��N�X�����܂ł�20�N�X�J���ŁA������50��7,666���~�A�אڂ̒��ԏ�ɂR��2,605���~�A���v��i�ێ��Ǘ����j��18��2,984���~�ƂȂ��Ă���A���z�ł�72��3,255���~�ɂ̂ڂ��Ă���B�ʏ́u���[�X���Ɂv�ƌĂ�邱�̌����Ɠy�n�i���ԏ�܂ށj���A��t�F�F�s���͂X��12���̉�h��\�҉�c�œ˔@�u�����v�Əq�ׁA�u���̂��߂̕�\�Z���o����̂ŁA�X��24���̖{��c�ŋc�����Ăق����v�Əq�ׂ��B
�@�c���“�Q���ɐ�”�ł���B�����Ȃ��Ƃ���X�A��}���̋c���ɂƂ��ẮE�E�E�E�B�u�����Ȃ��Ƃ��v�Ƃ����Č����̂́A�����}������}�Ȃǂ̗^�}�̋c���ɂ́A���łɑ��k���s���Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv����t�V�����邩��ł���B�Ȃ��Ȃ�A�X���S���̎s�c��{��c�̈�ʎ��⏉���ɁA�����}�̋{���c�����u�s�����{���ɂ̑ϐk�f�f�𑁋}�ɍs�Ȃ��v�Ǝ咣���Ă��邩��ł���B����ɑ���s���̓��ق͂Ȃ��������A���́A�{���c���̎���ʍ������������ɁA�u�S�N��ɂ͎s�������ݗ\��n�ɐV���ɂ����݂���v�Ƃ̕��j������Ȃ��ŁA“�Ȃ��A���̂悤�Ȏ�����s�Ȃ��̂��낤���H”�ƕs�v�c�Ȏv���ɂƂ���Ă����̂ł���B���܂���v���A�u���[�X���ɔ����v�Ɍ���������̎��₾�����̂ł͂Ȃ����B�����v���̂����R�ł��낤�B
�@�s�����u���[�X���ɔ����v�̗��R�ɂ����Ă���̂́A�u���[�X���ɂ������ق����A�ƒ���������������N�ԂP���~�]�̍������ʂ�����A�s�������ݗ\��n�ɐV���ɂ����Ă邽�߂̍����m�ۂɂȂ�v�u�\�肵�Ă����w2018�N�S���ɐV���Ɋ����x�͍����s���̂��߂ɓ���̂ŁA�������ʕ��̔N�ԂP���~�]�N����ɐςݗ��āA15�N��ɂ͐V���ɂ����Ă�v�Ƃ������̂ł���B�Ȃ�قǁA���̐����͂킩��₷���B�����A�������A��Ԃ̂͒N���E�E�E�E�H�B
�@�u���[�X���ɔ����v���j��m���������̎s���͓{�����B20�N�ȏ�ɂ킽���Ė��ԃr�����葱���������ɁA���x�́A�y�n�t���Ƃ͂����V�����������̃r�����Ƃ͂ǂ��������Ƃ��I�ƁB��t�s�����c��ɒ�o���������̂��߂̕�\�Z�ł́A�������U��2,023���S��~�A�y�n��12��4,571���~�Ŕ����Ƃ����B���z�ł�18��6,594���S��~�B�s���Y�Ӓ���s�Ȃ��������ł̋��z���Ƃ����B�������s���͌����B�u���ł���̂͌����Ɠy�n�����L���Ă���l�v�B�Ȃ��Ȃ�u�s�i�C�Ȑ��̒��B�s�������P�ނ�����A�W�K���Ă̒��Ãr���ɓ����Ă���e�i���g�Ȃǂ��Ȃ��v����ł���B�����āA���đւ��悤�ɂ��A���̏ꏊ�́u�Z���}���V�����͌��Ă��Ȃ��ꏊ�v�ƂȂ��Ă���̂ł���B�n�傳��ɂ��Ă݂�A�u�����v�́A���肪�����b�ł���B
�@�˔@�~���ėN�����u�����v���j�B�������u��\�Z�𑁋}�ɋc������v�ƌ����B�Ƃ�ł��Ȃ��b�ł���B��X��}���͉����B�_��̓I�́u���N�P���~�]�̍������ʁv���ʂ����Ė{���Ȃ̂��H�Ƃ����_�B�����I�Ȏ��^�͂X��19���i���j�E22���i���j�E25���i�j�E26���i���j�̂S���Ԃł������B���̌��ʁA���炩�ƂȂ����̂́A�u���N�P���~�]�̍������ʁv�͍���̘O�t���Ƃ������ƁB
�@���R�́A�i2�j��Q���ɂ̌����i���u���[�X���Ɂv�j���g��������Ƃ������Ƃ́A�z49�N�̎s�����{���ɂ��g��������Ƃ������ƁB�������A�{���ɂ̑ϐk�⋭�H�����K�͉��C�̌o��v�Z�ɓ����Ă��炸�A���[�X���ɂ̏��L�҂��疈�N�����Ă���Œ莑�Y�łȂǂ�����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��v�Z�Ɋ܂܂�Ă��Ȃ����ƁB���̂��Ƃ���A�������v�Z�Ɋ܂߂�Ɓu�N�P���~�]�̍������ʁv���قƂ�NJ��҂ł��Ȃ����ƁB�i2�j�������ʂ����҂ł��Ȃ����Ƃ���A�u15�N��ɐV���Ɍ��݁v�������ł��邱�ƁB�i3�j�{���ɂ��g��������Ƃ������Ƃ͕��U���ɂ����������łȂ��A�ϐk�⋭�H�������s�Ȃ������10���N��ɂ͖{���ɂ̌��đւ��ɔ����A�{���ɂ̌��đւ����I��������A���x�͑�Q���ɂ̌��đւ��������}����Ƃ����ӂ��ɁA���z�Ɋׂ邱�ƁB����ł́A15�N��݂̂Ȃ炸�A�V���Ɍ��݂͉ʂĂ��Ȃ����Ȃ��̕����ɒǂ�����Ă��܂����Ɓ\�\�\�ł���B
�@���^�̂Ȃ��ł́A�s���̓ƒf��s�����炩�ƂȂ����B����̃��[�X���ɔ����Ɍ����������́A�s���Ǝs���̈ӂ������������̂Q�l�Ŕ閧���ɂ����߂�ꂽ�B�����������w�����镛�s�����A���������S������������������A���̓�����m�炳��Ă͂��Ȃ������B�s�����̎��g�݂��߂��K������A�傫���͂��ꂽ�����ł���B
�@13�N�O�A���͒��Õ����̉䂪�Ƃ��w�������B���̍ہA�w���\��̒��Õ����̓o�L������O�ɑ��葤���猩���Ă��炢�A���葤�Ɗm�F��Ƃ��s�Ȃ����B�Ȃ́A�}�C�z�[�����w������ۂ̒��ӎ������L�������Ђ����O�ɓǂ݂�����A���S�̑̐��Ŕ����_��ɗՂB�Ƃ��낪������s�A�u���[�X���Ɂv�̌����Ɠy�n�Ɂu������v���t���Ă��邱�Ƃ��A�X��17���ɓo�L������ď��߂Ēm�����Ƃ����̂ł���B���z�́u�X��3,000���~�v�B18��6,600���~�Ŕ������A���̔��z��������̖����ɏ[�Ă��Ă����Ƃ������ƂɂȂ�B����ł́A���L�҂̎؋��ԍς̂��߂ɁA�s���̐ŋ����g����Ƃ������ƂɂȂ�ł͂Ȃ����B
�@��f����}���B�ǂ��l�߂����t�s���B�X��29���i���j�ߑO11��25���A���c�����^�I���������O�ɓ������ꂽ�B�u�s���ɑ��āA�\�Z�̎�艺����i������v�B��30���i�j�ߑO11��40���A�s���������B�u�c���̐i�����d���~�߁A���߂ē��e������K�v�����邽�߁A�P��v�B�s���͎��[�����Ȃ��ꂽ�B
�@�u���[�X���ɔ����v�̐^���͂킩��Ȃ��B�{���ɐV���Ɍ��݂́u�����m�ہv�̂��߂������̂��B�͂��܂��u���L�ҋ~�ύ�v�������̂��B�^�̗��R�͈ł̒��ł���B�s���͒f�O�����킯�ł͂Ȃ��B�u���߂ē��e������K�v�����邽�߁v�Ƃ����q�ׂĂ͂��Ȃ��B
�@����Łu�ꌏ�����v�ł͂Ȃ��B�ۑ�͎c���Ă���B�s���́u���Ă邽�߂̍������Ȃ��v�𗝗R�ɁA�s�������ݗ\��n�ł̐V���Ɍ��݂�扄�����悤�Ƃ��Ă���B���̂܂܂ł̓��[�X���ɂ͂���ɑ������ƂɂȂ�B����āA���Ă�������m�ۂ��Ȃ���A�����ɂ��Ďs�������ݗ\��n�ɐV���ɂ����Ă邩�\�\�\���̂��Ƃ�����Ă���B���{���Y�}�s�c�c�́A�V���ȉw�O�J����s�s�v�擹�H���݂ɍ������[�Ă�̂ł͂Ȃ��A�s�����������Ȃ�������ςݗ��āA�y�ʓS���^�ōŒ���K�v�ȋK�͂̒��Ɂi��9,000�������[�g���j�����Ă�ׂ��Ǝ咣���Ă���B
�i2014�N10��11���t�j
�w���z���^�x���t�o�C�N
 �@������s�̌��Z�ψ���́A�܂��I����Ă��Ȃ��B������s�̈�t�s�����X�����{�ɓ˔@�A�u���[�X���Ɂv�ƌĂ����ݎ̎s���Ƀr�����u�����v���Ƃ�\�����A�X�����{�Ɏ擾�\�Z�̋c�����s�Ȃ��悤�Ɏs�c��ɋ��߂Ă�������ł���B���̂��ߋc��͋�]�B�\�肵�Ă������Z�ψ���̎��^�������ŏI�ՂɃY�����݁A�c�������^���ڂ͕�̌��Z�ψ���ň����悤�ɂȂ�������ł���B���̂��Ƃ���A�Œ�ł��S���ԊJ����錈�Z�ψ���͂R���Ԃ̎��^���I�����i�K�ŃX�g�b�v�B�����́A11�����{�ɗ\�肷�錈�Z�ψ���摗��ƂȂ��Ă���B �@������s�̌��Z�ψ���́A�܂��I����Ă��Ȃ��B������s�̈�t�s�����X�����{�ɓ˔@�A�u���[�X���Ɂv�ƌĂ����ݎ̎s���Ƀr�����u�����v���Ƃ�\�����A�X�����{�Ɏ擾�\�Z�̋c�����s�Ȃ��悤�Ɏs�c��ɋ��߂Ă�������ł���B���̂��ߋc��͋�]�B�\�肵�Ă������Z�ψ���̎��^�������ŏI�ՂɃY�����݁A�c�������^���ڂ͕�̌��Z�ψ���ň����悤�ɂȂ�������ł���B���̂��Ƃ���A�Œ�ł��S���ԊJ����錈�Z�ψ���͂R���Ԃ̎��^���I�����i�K�ŃX�g�b�v�B�����́A11�����{�ɗ\�肷�錈�Z�ψ���摗��ƂȂ��Ă���B
�@�X������̂P���ڂ̌��Z�ψ���͍ŏ��ɁA��ʉ�v�́u�Γ��v�̎��^����s�Ȃ�ꂽ�B�u�Γ��v�̕����Ŏ��́u���i���������v�́u�����@�t���]�Ԕ��������E�R��4,650�~�v�ɒ��ځB���z�͂����������̂ł͂Ȃ����A�u�R��4,650�~�v���ǂ̂悤�ȗ�����o�āA���̋��z�ɂȂ����̂���m�肽���Ǝv�����̂ł���B�u���������v�Ƃ������ƂȂ̂ŁA��ʓI�ɂ́u�����v���s�Ȃ��Ă���̂��낤�Ƃ͎v���̂����B
�@�c��ɓ���̎�������o���ꂽ�B����ɂ��Ɓu�����@�t���]�Ԕ��������E�R��4,650 �~�v�̓o�C�N�Q��̍��v���z�Ƃ̂��ƁB�Q��Ƃ��A�s�������o�C�N���w�������̂́u����17�N�U���P���v�A���p�����̂́u����26�N�R��20���v�ƂȂ��Ă���B�w�����Ă���킸���X�N���炸�ŁA�P�䂠����P��7,325�~�Ŕ��p���Ă���̂ł���B
�@�ł́A�ǂ̂悤�ȗ���Ŕ��p�����̂��B�u�R�҂ɂ��w���������D�v�ƂȂ��Ă���B�H�����D�Ɠ��l�Ȃ����ŏ�����s�ƌ��т��̂��鎖�Ǝ҂R�Ђ��w�����A���D���i�̈�ԍ����������Ǝ҂ɔ��蕥�����Ƃ������Ƃł���B���z���Q��Ƃ����z�Ȃ��Ƃ���A�Q��Ƃ��������Ǝ҂����D�����Ǝv����B
�@�Ȃ��u�����v�ɂ����Ȃ��̂��B�S���ۂ́u�Ɩ��̔ɎG���ɉ����āA�I�[�N�V�����̃m�E�n�E���Ȃ��B�V�X�e���I�ɂ��Ή��ł��Ȃ��v���炾�ƌ����B�ł͂Ȃ��A�킸���X�N���炸�Ŕ��p���邱�ƂɂȂ����̂��B�u�g�p�p�x���Ⴍ�A�قƂ�ǎg���Ă��Ȃ��v�ƒS���ۂ̐����B�u�����肪�����邤���ɔ��肽���v�Ƃ������ƂŁA�������D�ɂ������Ƃ����̂ł���B�قƂ�ǎg���Ă��Ȃ����R�ɂ��Ắu�w�����b�g�����Ԃ�Ȃǂ̎�Ԃ��h�����ꂽ�Ǝv���v�ƒS���ہB�u�o�C�N�ɑウ�āA�d���t���]�Ԃ��w�������v�Ƃ����B
�@���p���ꂽ�o�C�N�����Ă��Ȃ��̂őz���ł������m�͌����Ȃ����A�w�����Ă���X�N���炸�A�������قƂ�ǎg���Ă��Ȃ��ƂȂ�A�u�P��E�P��7,325�~�v�͂��Ȃ肨�g�N�B���D�������Ǝ҂́A�������������C���ŊX���𑖂����Ă��邱�Ƃł��낤�B
�@���āA�䂪���ԁB���N��21�N�ځB��N�G���W���������I�[�o�[�z�[�����A����ł���Ƃ�������Ȃ�����ꂽ�B���̍��́A���ɂ����Ԃ�D�����B�M���҂��̂��߂ɉ��f�����O�Œ�Ԃ���ƁA�A�C�h�����O�X�g�b�v�����Ă����B��Ԉʒu������̓r�����Ƃ�����ƍ���B�u���[�L�܂Ȃ��ƁA�⓹�����藎���悤�Ƃ��邩��ł���B���s�����͂V���L�����[�g�������Ƃ���B�u�J�u�͏��Ɏg���A10���L�����炢�͍s���܂���v�ƏC�������Ă��ꂽ�o�C�N���̂�������B�P���v�Z�ł����A���ƂX�N�߂����Ȃ��ƁA�ڕW��10���L�����[�g���ɂ͓��B���Ȃ����ƂɂȂ�B����܂łɃo�C�N�̎ԑ̂͂��̂��H�A���̑̂͂��̂��H�B�u�P��E�P��7,325�~�v�̎��������Ȃ���A���ߑ������B
�i2014�N10���W���t�j
�p�����ʌ��_����
�@2010�N�T���ɔ��\����������s�u��R���s�������v��j�v�ł́A�u2012�N�x������_��������{����v�Ɩ��L���Ă���B�������A���܂��ɉe���`���������A���낤���ĉ����Y�����炢�ł���B�u���������ǂ��Ȃ��Ă���̂��H�v�ƂT��15���̍s�������v�������ʈψ���Ŗ₤�ƁA�u�����������߂����̂łȂ��ƌ��_����Ƃ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ̎Љ������A�܂�����������܂��Ă͂��Ȃ��v�Ƃ̓����B�悤����ɁA�u������������ꂽ���Ȃ��v�Ƃ����̂��{�S�̂悤�ł���B�Ȃ����ꂽ���Ȃ��̂��H�B����́A�Ɩ��ϑ�������H���̔������z�������グ�邱�ƂɂȂ邩��ł���B
�@�u���[�L���O�v�A�i�����n���w�j�v�Ƃ����̂������Ƃ����邾�낤���B�ꐶ���������Ă���̂ɁA�N����200���~�O��ɂ����Ȃ�Ȃ��l�X�̂��Ƃł���B�����A��҂̔����A�����l�̂S�����K�ٗp�ɒǂ�����A�u���[�L���O�v�A�v�̏�Ԃɒu����Ă���B����ȎЉ�𑱂��Ă������҂̖��������{�Љ���_���ɂȂ��Ă��܂��B���߂Č����J���ɂ�����镔��ɂ����Ă̓��[�L���O�v�A���Ȃ����Ă������|�|�ƁA�K���Ȓ����E�P���A�܂Ƃ��ȘJ�������E�J�����𐧓x��������g�݂��N����A�������ቻ�������̂��u���_����v�ƌĂ�Ă���̂ł���B�Ȃ̂ɁA���[�L���O�v�A���Ȃ������߂̕K�{�v���ł���u���������v����ꂽ���Ȃ��Ƃ́A�Ȃ�Ƃ������肳�܂ł��낤���B
�@������s�͒��w�Z���H�����̖��Ԉϑ����ɂÂ��āA��N�X������͏��w�Z���H�����̖��Ԉϑ����ɓ��ݐ����B���N�S������͊w���ۈ珊�̈ϑ�����\�肵�A����A�����ۈ牀�̈ϑ������s�Ȃ����Ƃ��Ă���B“�@�߂ɍ��v����Ζ��Ȃ�”�Ə�����s�͌������낤�B�������A������s�̏��w�Z���H�����Ɩ���������Ă��鎖�Ǝ҂̋��l�L��������ƁA�Œ�������������x�̒��������݂̂ŁA�����ۈ牀�̈ϑ���̎M�ƂȂ�\���̂��銔����Ђ̕ۈ珊�ɂ����Ă��A���l�̏ł���B����ł́A�Љ���ƂȂ��Ă���u���[�L���O�v�A�v�͑����邱�Ƃ͂����Ă��A���邱�Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B
�@�V������ł́A�ۈ�m�̂Q�����d�������߂����ƍl���Ă��邱�Ƃ����Ă����B���������A�����ԘJ���A�ȘJ�����Ȃǂ���ł���B������s�͌��_����𐧒肷��ړI�Ƃ��āu�����J����A�j�������Q��A�������̎Љ�I���l�̎����̐��i�̂��߁v�Ɩ��L���Ă���B���[�L���O�v�A���Ȃ������߂́u���������v����ꂸ���āA�Ȃɂ䂦�Ɂu�����J����v�u�������̎Љ�I���l�̎����v���͂����悤���B
�@�u���������v�̕����ɂ�����鏬����s�́A���ǂ̂Ƃ���A�o��ߌ������ᒆ�ɂ͂Ȃ��̂ł���B���ł́u�s�v�̓T�[�r�X����E�g��̂��߁v�ƌ������A���Ԉϑ������ꂽ�{�݂œ����l�X�́A���܂܂ňȏ�ɃT�[�r�X����E�g�傪���߂��A�Ȃ̂ɋ����͒Ⴍ�A�����ԘJ���ɒu����Ă���B������s��“�������̊֒m����Ƃ���ł͂Ȃ�”�Əq�ׂ�ł��낤�B������E�����ԘJ���ł����Ă��A�T�[�r�X����E�g�傪�͂����A�u�s�v�v�̖ړI�͉ʂ��������ƂɂȂ�Ƃ����l���ł���B
�@����ł͉��\���Ƃ����P�ʂ̊J�����Ƃ������߁A��������ł́A�o��ߌ����ő�̖ړI�Ƃ������Ԉϑ�����i�߂鏬����s�̂��Ƃł́A�u���_����v���`�ƂȂ��Č������͂��Ȃ��ł��낤�B�u���[�L���O�v�A�i�����n���w�j�v������̂��̍��ŁA��҂⓭���l�X�͖����̊�]����邱�Ƃ��ł���̂ł��낤���B
�i2014�N�T��17���t�j
�s�����������Ȃ���V���Ɍ��݂͉\��
�@������s�͐V�N�x�\�Z�Ɂu�V���Ɍ��݊�{�v�ϑ���(3,295���P��~)�v���v�サ���B1994�N�P�����瑱�����ݒ���(���u��Q���Ɂv)���������邽�߂ɁA2018�N�U������V���ɂŋƖ����ꕔ�J�n�A2018�N�X���ɂ͑S�ʈڍs�E���ݒ��ɂ��I���ł���悤�ɂ��邽�߂̂��́B���̂��߂ɁA�V���ɂ́u��{�v���j�̍���v�u��{�v�}���̍쐬�v�u�T�Z�H����̌����v����Ǝ҂ɍs�Ȃ��Ă��炤�Ƃ���Ă���B
�@����́u�V���Ɍ��݊�{�v�ϑ����v�\�Z�́A������s����N�R���ɍ��肵���A�s�������݂Ɍ������u�V���Ɍ��݊�{�v��v�Ŗ��L�������݂܂ł̃X�P�W���[���ɉ������̂ł���A���̂��Ǝ��̂́A���̊Ԃ̒��ڐ����^���Ȃǂ��������Ȃ��ł͗����ł���Ƃ���ł���B�������A�O�r�ɂ͂Q�̖ʂŖ��_������Ă���B�P�́A�v��ǂ���ɃR�g���^�Ԃ̂��Ƃ������ƁB
�@�V���Ɍ��ݗ\��n�ɂ͌��݁A���T�C�N����Ə��⎑���������{�݂�����A������ʂ̏ꏊ�Ɉړ]�����Ȃ���ςȂ�Ȃ��B�u�V���Ɍ��݊�{�v��v�ɂ��ƁA�ړ]�́A��̍H���܂߂�2015�N�x�ƂȂ��Ă���B���ƂP�N��ɂ́A���̎������}���邱�ƂɂȂ�B�ł́A�ǂ��ֈړ]������̂��B�u����v�Ƃ����̂��R��13���̗\�Z�ψ���ł̓��قł���B���̂����ŁA���T�C�N����Ə��⎑���������{�݂̓P���E�ڐ݂̉ۂ̔��f�́u����26�N�x���v�A�܂�A���N�R�����܂łɍs�Ȃ��Əq�ׂĂ���B
�@�����Ŏ��́g�͂ĂȁH�h�Ǝv���B�\�Z�v�コ�ꂽ�u�V���Ɍ��݊�{�v�ϑ����v�ɂ��ƂÂ��ϑ��Ǝ҂̑I�l�͂T���I�Ղ���X�^�[�g���A�V�����{�ɂ͑I�肳�ꂽ�ϑ��Ǝ҂Ɋ�{�v�̋Ɩ������邱�ƂɂȂ邪�A�V�����{�ȍ~�A���X�ƋƖ��𐋍s���A���N�R�����ɂ́u��{�v���j�v�u��{�v�}���v�u�T�Z�H����v�����ʕi�Ƃ��Ĉϑ��Ǝ҂�����ꂽ���_�ŁA���T�C�N����Ə��⎑���������{�݂��u�����_�ňړ]��͖���v�ƂȂ�����A���ꂽ���ʕi�͂ǂ��Ȃ�̂��낤���B�ꍇ�ɂ���Ă͒��ꂽ���ʕi���A���̂܂܂ł͐�������Ȃ����Ƃɂ��Ȃ肩�˂Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�����玄�͎v���B��{�v�Ɩ�������O�ɁA�܂�́A�ϑ��Ǝ҂��W����O�̎��_�A�悤����ɍ��N�̂T�����{�܂łɁA���T�C�N����Ə��⎑���������{�݂̈ړ]����m�ۂ��Ă����K�v������̂ł͂Ȃ����낤���A�ƁB�s�͌����ł��낤�B�g���ꂽ���ʕi�́A�V���ɂ̌��ݎ������Y�����Ƃ��Ă����p�ł���h�ƁB�������ɁA�u�V���Ɍ��݊�{�v��v�̃X�P�W���[���ǂ���ɍs���Ȃ��Ȃ��Ă��A���肵�Ă��������{�v�}�������ƂɐV���ɂ����ĂĂ����Ƃ����̂ł���A�u�T�Z�H����v�̌��������x�ł��ނ̂�������Ȃ��B���������̎��_�Ŗ��ƂȂ�̂��A2018�N�W�����܂łɒ��ݒ��ɂ���������Ƃ����s���ւ̖ł���B�u�����_�ňړ]��͖���v�ƂȂ����Ƃ���ɁA���ݒ��ɂ̂���Ȃ鉄�����҂��邱�ƂɂȂ�B
�@���Ɂu2018�N�W�����܂łɒ��ݒ��ɂ���������v�Ƃ̖����Ƃ����̂ł���A���T�C�N����Ə��⎑���������{�݂��c�����܂܂ŁA�]���Ă���~�n�����ɁA���ݒ��ɂɎ��e����Ă��镔���݂̂����Ă�Ƃ���������Ƃ炴��Ȃ��Ȃ�B�����Ȃ�ƁA���N�R�����ɒ��ꂽ���ʕi���A������g����������܂ŕۊǂ��Ă����̂��A���邢�͐V���Ɍ��݂���̉����ꂽ���ɂ��蒼���̂��A�͂��܂����ݒ��ɕ���V���Ɍ��ݗ\��n�Ɍ��Ă邽�߂̐v�}����V���ɍ��̂��A�̑I�������߂��邱�ƂɂȂ�B���̋��ꂪ����Ȃ��ŏ�����s�́A�u�V���Ɍ��݊�{�v�ϑ���(3,295���P��~)�v���v�サ���̂ł���B
�@�S�������͂��̎w�E�ɑ��āu�w�E����錜�O�͂��邪�A�����_�ł́A��{�v��ɉ����Ă����߂Ă����Ƃ������Ƃł���Ă���v�Əq�ׂ��B
�@�����P�̖��_�́A������̉ۑ�ł���B������s�͍���A�����̍�����K�v�Ƃ��鎖�Ƃ�����Ă���B��̓I�ɂ́A�i�P�j����s�ƍ������s�Ə�����s�̋����̉R�S�~�����{���݁A�i�Q�j���܂Ȃ�������������w�k���y�n��搮�����ƂƗp�n�擾�A�i�R�j����������w�����Q�n��ĊJ�����ƁA�i�S�j�s�s�v�擹�H�R�E�S�E�W�����g�����ƁA�i�T�j���ċp��Ւn�̕{���s���̎擾�����������̂T�̎��Ƃ����ł�������s��150���~�O��̍�����K�v��
���Ă���B����ɉ����Ă̐V���Ɍ��݂ł���B
�@��N�R���Ɏ����ꂽ�V���Ɍ��݂̍����v��ɂ��ƁA�����Ɣ��54��9,800���~�ŁA��������͒n����(�؋�)��33��9,400���~�A����J�������S���~�A��Q���ɕۏ؋��Ԋҋ����V���~�A��ʍ�����10��400���~�ƂȂ��Ă���B�������s�Ŏ������L�єY�݁A������s�̍�������݂Ă��A�u��ʍ���10��400���~�v�͎��Ɍ������B�v��ł́A2015�N�x�ɂP��5,270���~�A2016�N�x��9,400���~�A2017�N�x�ɂR��5,900���~�A2018�N�x�ɂ͂R��4,900���~��p���Ă���ƂȂ��Ă���B�܂�A���̔N�x�ɓ���ꂽ�Ŏ����炻�̊z��V���Ɍ��݂ɏ[�Ă�Ƃ������̂ł���B����ɐ���̂T�̎��Ƃ��d�Ȃ��Ă���킯�ł���B����Ŏs���̕�炵�ɂ���������Ă����̂��낤���H�B���݂��邽�߂̍����͊m�ۂł���̂��낤���H�B���ʂɍl���邾���ł�����������邱�ƂɂȂ�B
�@�v��ǂ���ɍs���Ȃ��Ȃ鋰��́A�V���Ɍ��ݗ\��n�̓s���ƍ����̓s���̑o���Ō����邱�Ƃł���B��������{���Y�}�s�c�c�͒�Ă���B�s�������������ݒ��ɂ𑁊��ɉ������邽�߂ɁA�V���Ɍ��݃X�P�W���[���̊��Ԃ����L���A�V���Ɍ��ݗ\��n�Ƀ��[�X�Ōy�ʓS���̎b�蒡�ɂ����݂��邱�ƁB�V���Ɍ��ݔ�p�ɏ[�Ă��ʍ������ɗ͗}��������x�Ɋ����ςݗ��āA�s������V���ɂ����݂ł���قǂ̗̑͂ɉ����邱�ƁB���̊ԂɁA���T�C�N����Ə��⎑���������{�݂̈ړ]��̌���S�苭�������߂邱�ƁA���B
�@
�������A�s���M�]���Ă���u����26�N�x���v�Ƀ��T�C�N����Ə��⎑���������{�݂̈ړ]��̃��h�����̂ł���A����ɂ��������Ƃ͂Ȃ��B���[�X�ɂ��y�ʓS���̎b�蒡�ɂ́A���ݒ���(��Q����)�Ɏ��e����Ă���Ɩ����ɉ����āA�{���ɂ̋Ɩ������܂߂��S�̓I�Ȃ��̂ɂȂ�ł��낤�B�����Ȃ�Ȃ��ꍇ�ɂ́A�b�蒡�ɂ̊��Ԓ��͖{���ɂƂ̉����ŕs�ւ����������ƂɂȂ邪�A��ςȐ������������Ă���s���̕�炵�ɍ������[�ĂĂ������߂ɂ́A�s�ւ�ɂ��܂Ȃ��p�������߂���B���R�ɁA�s�v�E�s�}�̑�^�J����s�s�v�擹�H���݂͒��~���ׂ��ł���B
�i2014�N�R��31���t�j
����ő��ŕ��̎g�r
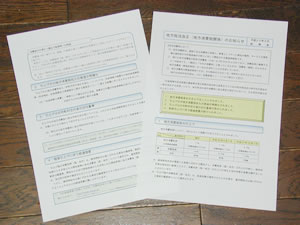 |
�����Ȃ̎w������ |
�@�S���������ł��W���ɑ��ł����B�u�������ݎ��v�v�Ə̂����ꎞ�I�Ȍi��������������ŁA�S������̋}���Ȏ��v�̗������݂ɕs��������l�X�������B�䂪�Ƃł��g����ł̏オ��O�ɔ����Ă����ׂ����̂́H�h�ƁA���͂����n���B�J�~����͎��X�Ɂu���]�Ԃ�������v�̐����B�q�ǂ������܂��O���炠�����䂪���ԁB���{���Ȃ̂ł���͂������肵�Ă�����̂́A�x�A�����O�t�߂��K�тĂ���A���s���͎��ɓ��₩�B�ԗւ��x����ׂ��t���[�����R�{�قǏ����Ă���B�����������������Ƃ���A�䂪�t�g�R���͕n�R�ɂȂ�̂ł���B�u�������ݎ��v�v�́A�삯���߂邾���̃t�g�R��������l�Ɍ����邱�ƂB
�@����ł��T������W���ɏオ��ƁA�n�������̂ɂ́u�n������Ō�t���v�Ƃ���������̂��������z�����B���s�͏���ł̂P���������Ă��邪�A�V�N�x����͂P.�V���ɑ�������z����t�����B�������A��Ƃ̌��Z�������قȂ邽�߂ɁA�V�N�x�̎��ۂ̌�t�z�͏���ŗ��̂P.�Q�����x�ɂƂǂ܂�ƌ����Ă���B
�@������s�ł��u�n������Ō�t���v�̑��z�����V�N�x�ɗ\�肳��Ă���B�R��2,200���~�̑��z���Ƃ����B�������A������s�̎s�����ɂ����Ă͏���ł̑��ŕ����Ώo�ŕK�v�ɂȂ邽�߁A�V�N�x�͍�������520���~�قǂ̐Ԏ��ɂȂ�Ƃ����B
�@�����Ȃ͍�N�S���A�n������Ō�t���̑��z���́u�Љ�ۏ�v�ɏ[�Ă�ׂ��Ǝw�����Ă���B�u�n���Ŗ@�����i�n������ŊW�j�̂��m�点�v�Ƃ��������ŁA�u���グ���̒n������Ŏ����i�s������t�������܂ށj�ɂ��ẮA�Љ�ۏ�S�o����x�Ƃ��Ċm�����ꂽ�N���A��Â���щ��̎Љ�ۏዋ�t�Ȃ�тɏ��q���ɑΏ����邽�߂̎{��ɗv����o��A���̑��Љ�ۏᐧ�x�i�Љ���A�Љ�ی�����ѕی��q���Ɋւ���{��������j�ɗv����o��ɏ[�Ă���̂Ƃ���v�Ƃ������́B�ł́A������s�͑����Ȃ̎w���ɑ��āA�ǂ̂悤�ȑΉ����Ƃ��Ă��邾�낤���B
�@������s���c��Ɏ����������ɂ��ƁA�n������Ō�t���̈��グ���R��2,200���~���Љ�ۏ�W�o��ɏ[�ĂĂ͂�����̂́A����ŁA��ʍ���������Ă��邱�Ƃ��킩��B�c��Ɏ����ꂽ�����͂Q��ށB��́A�V�N�x�́u�n������Ō�t���i���グ���j�̎Љ�ۏ����������v�B������́A�O�N�x(2013�N�x)�́u�Љ�ۏ�W�o���������v�B�Q�̎���������ׂ�Ɨǂ�������B
�@�V�N�x�̎Љ�ۏ�W�o��͑��z�Łu78��4,666���~�v�B����A�O�N�x(2013�N�x)�́u76��3,147���R��~�v�ƂȂ��Ă���B�����Ȃ̎w�������ɏ]���A�V�N�x�̎Љ�ۏ�W�o��́A�O�N�x�́u76��3,147���R��~�v�ɒn������Ō�t���̑��z���u�R��2,200���~�v���������z�A�܂�́u79��5,347���R��~�v�ɂȂ�Ȃ�������Ȃ��B���������ۂɂ́u78��4,666���~�v�ɂƂǂ܂��Ă���A���������P��681���R��~�̈�ʍ��������̕���ɉ�Ă��邱�ƂɂȂ�B���̖������w�E���ꂽ���ǂ́u�������Ȃ���A�s���������藧���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��v�Ɛ����B
�@�u�Љ�ۏ�̏[���̂��߂ɏ���ł������グ��v�́A���{������ɏq�ׂĂ������t�B���������ǂ́A����������s�ɂ����Ă��Љ�ۏ�Ɉ��z���[�Ă邾���ł���������A���̕���̍����Ɏg���Ă���̂ł���B
�@�ł́A�Љ�ۏ�ɏ[�Ă�ꂸ�Ɍ��z���ꂽ��ʍ����͂ǂ��ɍs���̂��B������s�͐V�N�x���A�s�s�v�擹�H���݂�w�O�J�����Ƃɑ��z�̍������[�ĂĂ���B���ǂ́A������ɐU�蕪������̂ł���B
�@�Q��28���A�F�ۈ牀�ɓ���Ȃ������̕ی��60�l���A������s�Ɂu�ًc�\�����āv���s�Ȃ����B������s�ł́A�F�ۈ牀�ւ̓����\���݂��s�Ȃ��Ă��u�s���F�v�ƂȂ銄�����s�����[�X�g�P�ł���B�F�ؕۈ珊��ۈ玺�A�ƒ땟�����i�ۈ�}�}�j�̎����g�����肳��A�S������q�ǂ���a����ꏊ���Ȃ��ی�҂́A�d�������߂���Ȃ��l���o�Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B�u�Љ�ۏ�̏[���v�̂��߂ɑ��ł��s�Ȃ��ƌ����Ȃ���A���ۂ͑��̕���ɂ������g���Ă��܂��Ă���B
�@���āA�䂪�ƁB����ł����ł���Ă������͑����Ȃ��B�u�������ݎ��v�v���������Ă��t�g�R�����������B�䂪���Ԃ͐V�N�x���A���₩�ȉ��𗧂ĂĊX�Ȃ����삯��邱�ƂɂȂ肻���B�������A������w���w�B�ƌv�͒�₦�̋G�߂ɓ���B�^�N�A���ƃ��U�V�Ɣ[���Ɩ��X�`�̐H��̂Ȃ�����A���ӁA�����䂭���̂��o�Ă������B�܂��܂��g�ׂ͍��Ȃ�ɂ���B
�i2014�N�R��27���t�j
�����E�����E���傪���ېŒl�グ���F
�@������s�c��͂R������ŏI���̂R��24��(��)�A��t�s�����c��ɒ�o���Ă����������N�ی��ł̑啝�l�グ�Ă��A�����E�����E����Ȃǂ̎^�������ʼn����܂����B����ɂ��A�s���̂S���̂P�A���тł͂R���̂P���������Ă��鍑�ېł��A�S������N�z�ň�l���ςP���~�A���ł���邱�ƂƂȂ�܂����B
�@�l�グ�ĂɎ^�������̂�13�l�������}�A�����}�A����}�A���v�A���A��������������낭�����B�������̂�10�l�����Y�}�A�݂�Ȃ̓}�A�����҃l�b�g�A�s�������A�s����c�B
���́A�s�������o���ꂽ�u���ېł̑��ł��������A���S���Ĉ�Âɂ������悤�ɂ��邱�Ƃ����߂��v(������1,219�M)�ւ̎^�����_���s�Ȃ��܂����B�ȉ��A���_���e���Љ�܂��B���킹�āA�l�グ�̊T�v���o�c�e�t�@�C���Ōf�ڂ��܂��̂ŁA���Q�Ƃ��������B
�@���{���Y�}������s�c�c���\���āA�{��ւ̎^�����_���s�Ȃ��܂��B
�@�������i�C����̂Ȃ��A�s���̕�炵�͔N�X�A�������𑝂��Ă��܂��B���{�́u�A�x�m�~�N�X�v���ʂ��`���܂����A�X�Ȃ��ŏo��N�����u�������̂Ƃ���ɂ́A�܂����������Ȃ��v�u���Ƃ����̘b�v�Ƃ����������Ԃ��Ă��܂��B�S���������ł̑��ł��\�肳��A�N���x���z������ɂP�����z����悤�Ƃ��Ă��܂��B�ꕔ�̑��Ƃł͒��グ�������Ă��܂����A���̋��z������ł̑��łɂ͒ǂ������A�����命���̐l�X�́A���グ�ǂ��납�������������������A�{�[�i�X�̌��z�����������Ă��܂��B
�@����Ȏ��ɍ������N�ی��ł̒l�グ���s�Ȃ���A�₦�������ƌv�����A�s���̕�炵���ǂ��ւƓ˂����Ƃ����̂ƂȂ�܂��B���{���Y�}�́A���ېł̈��グ�ɒf�Ŕ�������̂ł��B
�@�������N�ی��́A�K�ٗp�J���ҁA���c�ƎҁA�ސE�ҁA�N�������҂Ȃǂ��������Ă���A�Ꮚ���҂��������߂Ă��܂��B���т̏����K�w�Ō���ƁA�N�ԏ����� 200���~������70���]����߁A150���~�����ɂ����Ă�62���߂����߂Ă��܂�(2012�N�x���ە�)�B ���݂̐ŗ��ɂ����Ăł������A�����̂P���߂������ېł̎x�����ɏ����Ă���A�Ꮚ���Ғ��S�ɍ��ېł̑ؔ[���т����܂�Ă��܂��B����ȏ�̕��S���́A�����������������������̂ƂȂ�܂��B
�@�Ƃ��낪�A����̒l�グ�́A�����ґS���ɕ��ۂ����u�ϓ����z�v���u��Õ��v�ŔN��4,000�~�A�u�������Ҏx�������v��N��1,000�~�����グ�A�S�l�Ƒ��S�������ۂɉ������Ă���ꍇ�A�u�ϓ����z�v�����ŔN�ԂQ���~���̑��łƂȂ�܂��B�����āA�v�w��40����64�܂łł���A����Ɂu��앪�v�́u�ϓ����z�v�� 5,700�~�A�b�v���v�w�Ƃ��ɕ������Ԃ���A�S�l�Ƒ��̏ꍇ�A�N�ԂłR��1,400�~���̕��S������C�ɉƌv���P���܂��B�Ꮚ���҂̑������������Ă��鍑�ۂɂ����āA����A��������̂ł͂���܂���B����ȑ��ł��ǂ����ĔF�߂邱�Ƃ��ł���ł��傤���B
�@�������s�c��ɂ́A�s���̕�炵����邽�߂̖������ʂ������Ƃ����߂��Ă��܂��B������s���s���ɂ���Ȃ镉�S�킹�悤�Ƃ��Ă����ꍇ�ɁA���̖��_���������ƂƂ��ɁA�s���̕��S��a�炰��A�s���ւ̕��S���������Ȃ����߂̕�����������Ƃ����߂��܂��B
�@���{���Y�}�s�c�c�́A���ɁA�@���Ŗ��L���Ă���u�Љ�ۏ�v�Ƃ��Ă̍������N�ی����x���邽�߂ɁA��ʉ�v����̌J��o���z��2012�N�x���Z�Ȃ݂Ɉ����グ�邱�ƁB���ɁA���茒�f�⌒�f���Ƃ̏[�����s�Ȃ��A���������E�������Â��{�����Ƃɂ���ĕa�C�̏d�lj���h���A��Ë@�փw�̎s���S���̑�����}���Ă������ƁB��O�ɁA�����N�X�팸���Ă��鍑�ɕ⏕�z�����̐ӔC�ň����グ�����A�u����T���v�ɂӂ��킵�����x�ɉ��߂����邱�ƁB��l�ɁA�����U�ւ�R���r�j�ł̔[�t�̂o�q���s�Ȃ��A�[�t�̂��Y��ɂ��ؔ[��h�����g�݂�ϋɓI�ɂ����߂邱�ƁB�����̎��g�݂������߂邱�Ƃɂ���āA���ېł̑��ł��X�g�b�v���邱�Ƃ��Ăт����Ă��܂��B
�@���{���Y�}�s�c�c����Ă������������߁A�i�C����Ə���ő��ŁA�N���x���z�̍팸�ŋꂵ�ގs���̕�炵�Ɖc�Ƃ���蔲�����Ƃ́A�N�����肤���R�̓��ł��B���̂��߂ɂ��A�F�l�����{��Ɏ^������邱�Ƃ��������߂���̂ł��B
�S�����獑�����N�ی��ŁA�������҈�Õی��������ł��iPDF62KB�j
�s��������{�z�[���ƔF�ۈ牀�̑��݂�
�@���݊J��̂R�����s�c��Łu���{�z�[���̑��݁v�Ɓu�F�ۈ牀�̑��݁v�����߂��ʎ�����s�Ȃ��܂����B�ǂ���������̕��X��������҂��Ă���A������s���̋i�ق̉ۑ�ƂȂ��Ă��܂��B
�@������s�ł͍�N�S���P�����_�ŁA���ʗ{��V�l�z�[���ւ̓�����҂��Ă���l��400�l�ȏ�ƂȂ��Ă��܂��B�Ƃ��낪������s�́A�݂�����f�����u2013�N�x��100�l���̓��{�z�[����ݒu����v���߂̋�̍���Ƃ炸�A���N�x�ȍ~�ɐ摗�肵�Ă��܂��B
��ʎ���Ŏ��́u���{�z�[����ݒu���邽�߂̓y�n�𓌋��s�Ɏ擾���Ă��炢�A������s���N���œ����s�ɕԍς��Ă����B���邢�́A������s�⎖�Ǝ҂������s�����������A�����s�Ƌ��c���Ȃ��猟�����ׂ��v�Ǝ咣�B�u2015�N�x����̉��ی����ƌv��ɋ�̓I�ȕ���L���ׂ��v�Ɨv�����܂����B����ɑ��ĕ����ی������́u���x����̓������d�����Ȃ���A�K�ɔ��f���Ă��������v�Əq�ׂ܂����B
�@����A���{���v�悵�Ă���T�[�r�X��̂Ẳ��ی����x�����ɑ��Ắu�p���I�ȃT�[�r�X������悤�Ȏ��Ƃ̎��{�A���p�҂̕��S���Ȃ�ׂ�������Ȃ��悤�ȉ��\�h�̎��g�݂ɂ��Č����������v�Ɠ��ق��܂����B
�@���ی����x�́A���������\�Z�팸��_���Ȃ��ŁA�������S����C�ɉ����鋰�ꂪ�łĂ��܂��B�����������Ȃ������������߂Ȃ���A�����̂ɑ��ẮA���x�̈ێ��E�g�[�A���p�ҕ��S���ɂȂ�Ȃ����g�݂𔗂��Ă������Ƃ��d�v�ł��B
�@�s������F�ۈ牀�̖����[���ł��B�Q��28���A�S������̔F�ۈ牀�������s�����ƂȂ���60�l�̕ی�҂��A������s�ɑ��Ĉًc�\�����Ă��s�Ȃ��܂����B�������s�́A�u������s�̕ۈ�s�����s�\�����Ƃ������Ƃ��w�i�ɂ��邩��ł͂Ȃ����v�Ǝw�E�������Ƃɑ��āA�u�ڕW�ɉ����Ĉ��̎��v�ʂ��m�ۂ��Ă��邪�A�ۈ�ɑ�����v�ʂ��A���������������v�Əq�ׁA����̕s�\������F�߂悤�Ƃ͂��܂���ł����B
�@���́u�F�ۈ牀�̐V�݁E���݂Ɍ������v��Ă��A�V�N�x�ɐݒu�����w�q�ǂ��E�q��ĉ�c�x�Ɏ��₷�ׂ��v�Ǝ咣���A���ƌ������Z���s�c�Z��~�n���̋X�y�[�X�������s�Ȃ��A���Ⓦ���s�ɔF�ۈ牀�ݒu�̂��߂̗p�n�����߂Ă����ׂ��Ɨv�����܂����B
�@�q�ǂ��ƒ땔���́u�F�ۈ牀������Ȃ��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�q�ǂ��E�q��ĉ�c�ňӌ������������Ă����v�Ɠ��فB�X�y�[�X�ɂ��Ắu�c���ł��Ă��Ȃ��v�Əq�ׁA�������炵�Ă��Ȃ����Ƃ����炩�ƂȂ�܂����B
�@�F�ؕۈ珊�Ȃǂɕۈ�s�����ς˂铮��������܂����A�F�ؕۈ珊�͕ۈ痿�������A�F���ɂ���ׂĊ���ɘa����Ă��邽�߂ɁA�^�c���Ǝ҂̕��j�ɂ���ẮA�ۈ�̎��͉_�D�̍��ƂȂ��Ă��܂��܂��B�F�ۈ牀���݂̐������߂Ă������Ƃ����߂��܂��B
�@������s�c��ł͖{��c�A�ψ���A�S�����c��̖͗l���A�C���^�[�l�b�g�́u���[�X�g���[���v�ŕ��f���Ă��܂��B�C���^�[�l�b�g�Łu������s�����v���u�s�c��v���u������s�c��[�X�g���[���z�M�v�ŒH�蒅�����Ƃ��ł��܂��B����̎��̈�ʎ���̖͗l�́A�R���R���̖{��c�A�ߌ�P�����猩�邱�Ƃ��ł��܂��B�ŏ��Ɂu���{�z�[���v�A30����Ɂu�F�ۈ牀�v�����₵�Ă��܂��B���⌴�e���o�c�e�t�@�C���Ōf�ڂ��܂��̂ŁA�Q�l�܂łɂ������������B
���{�z�[�����݂Ɖ��ی������Ăւ̑Ή����₤�iPDF183KB�j
�F�ۈ牀���݂Ɍ��������j��₤�iPDF215KB�j
�ш�k���n��Z���^�[�x���\�Z
�@�S���J�ݗ\��̊ш�k���n��Z���^�[���A�ۂ��Ƃm�o�n(��c���g�D)�Ɉϑ����悤�Ƃ��Ă��鏬����s�́A���N10������12�����܂ł̎x���\�Z107���R��~�� �����āA�P������R�����܂ł̂R�J���ԁA�m�o�n���Վ��E��10�l���ٗp����o��Ȃ�335���S��~���A12���s�c��̕�\�Z�Ɍv�サ�܂����B
�@10�l�̗Վ��E���́A�}���ق��W�l�A�����ق͂Q�l��\��B�P�����{�ɐE����W���s�Ȃ��A�S���̊J�݂ɊԂɍ��킹�邽�߂ɁA�Q������R���܂ł̂Q�J���ԁA�s�̌����فA�}���قɌ��C�h�������āA�Ɩ����e���n�m������Ƃ������̂ł��B
�@�������}���ق̗Վ��E���W�l�͂��������11������14���̋Ζ��Ƃ���A�}���قŌ��C�����Ƃ��Ă��A�{�i�I�Ȑ}���ًƖ��ɂǂ��܂őΉ��ł���̂��͋^��ł��B
�@���{���Y�}�s�c�c�́A�u���U�w�K�{�݂Ƃ��Ă̋Ɩ����\���ɔ������邽�߂ɂ��A�m�o�n�ϑ��ł͂Ȃ��A�����فE�}���ق̉^�c�ɏn�m����s�̐E���őΉ����ׂ��v�Ǝ咣���A�\�Z�ɔ����܂����B�ȉ��A����12��18���̖{��c�ōs�Ȃ����A��\�Z�ւ̔��Γ��_���f�ڂ��܂��B
��ʉ�v��\�Z(��T��)�ւ̔��Γ��_
�@���{���Y�}������s�c�c���\���āA��ʉ�v��\�Z(��T��)�ւ̔��Γ��_���s�Ȃ��܂��B
�@����̕�\�Z�̓����́A�O�N�x�ɍ��Ⓦ���s���炫�Ă����⏕���E���S���̂P�� 2,400���~�]��̕Ԋ҂ƌ��M����� 6,150���~�̑��z����сA�ی��E��������̗��p�ґ��Ȃǂɑ�����̂ƂȂ��Ă���A���̍����[�u�Ƃ��āA���������������R���~���J����A�\������ 6,770���~�A�[��������̂ƂȂ��Ă��܂��B
�@���̂Ȃ��ɂ����ẮA������s�̎Y�ƐU����ړI�ɒ������̍��ˉ��ɐݒu�����u�x���`���[�E�r�n�g�n�������v�֘A�o���Q�ً̋}�ٗp�n�o���Ƃ���сA�e�����̂ő��݂��s�Ȃ��Ă���F�ۈ珊�A�F�ؕۈ珊���̕ۈ�m�m�ۍ�Ƃ��āA�����s���s�Ȃ��ۈ�m�̐l��������グ�̂��߂̏������P���Ɣ�⏕�����v�コ���ȂǁA�]���ł���_������܂����A�ȉ��̓_�Ŗ�肪���邱�Ƃ��甽������̂ł��B
�@������ő�̗��R�́A���N�S���ɊJ�ݗ\���(����)�ш�k���n��Z���^�[�̈ϑ��\���Ƃ����m�o�n�ɑ���⏕���̗\�Z���ɖ�肪����ƍl���邩��ł��B������s�́A( ����)�ш�k���n��Z���^�[�̊J�݂ɂ������āA�o���}���邱�Ƃ�ړI�Ɂu�s�������v �u�����A�g�v�̖��̂��ƂɁA�m�o�n�ɂ��^�c�ϑ���ł��o���A���N�W���ɏ�����s�̑S�ʎx���̂��Ƃŋ}����m�o�n��ݗ��B�X���̕�\�Z�ł͂��̔C�Ӓc�̂ւ̕⏕�����v�サ�A�{���A�m�o�n���炪�s�Ȃ��ׂ��Ɩ����Љ�����c����̎x���g�D�Ɋە����ōs�Ȃ킹�郌�[���܂ŕ~���āA�m�o�n�x���������߂Ă��܂����B
�@���̂X����\�Z�̍ۂɋc��ɒ�o���ꂽ�X�P�W���[���\�ł́A���N12���Ɂu�m�o�n�@�l�ݗ��F�E�ݗ��o�L�v�Ƃ���A�@�l�o�L���ꂽ�m�o�n�ɑ��āu�Վ��E���v�̌ٗp�o����܂ޕ�\�Z��12���c��Ɍv�シ��Ƃ������̂ł����B
�@�������A10�����̒i�K�ɂȂ��Ăm�o�n�F�ɑ��ĕs�s���ȓ_�����炩�ƂȂ�A�u�m�o�n�@�l�ݗ��F�E�ݗ��o�L�v�͑����Ă��Q�����A�x����R����{�ɂȂ鎖�ԂƂȂ�܂����B�܂�A������s�����玦�������A�X�P�W���[���ɍ���Ȃ��Ȃ����ɂ��ւ�炸�A�]������̕��j�ɉ������\�Z������A��Ă��Ă������̂ł��B�������A���̂m�o�n�ɑ��Ă͕⏕���x�o������Ă��Ȃ��ɂ�������炸�A���̒c�̂ɑ��Ă͐ݗ��i�K����x�o����Ƃ����ٗ�̈����ɂȂ��Ă��܂��B
�@������s�́A�C�Ӓc�̂ł���F�ؑO�̂m�o�n���ٗp����Վ��E�����A������s�̌����قƐ}���قɌ��C�h���Ƃ������ڂŎ����Ƃ̂��Ƃł����A������s�̂ǂ̋K��ɂ��ƂÂ��Ď����̂��Ƃ̎���ɑ��ẮA�u���݁A���蒆�v�Ƃ������̂ŁA�Ȃɂ��Ȃ�ł��m�o�n�Ƃ����A�u�m�o�n��ɂ��肫�v�̎p�����@���Ɏ����ꂽ���̂ƂȂ��Ă��܂��B
�@�����فE�}���ق�z�u�����ш�k���n��Z���^�[�́A�n��Z���̒��N�̔ߊ�ł���A�҂��ɑ҂����Җ]�̎{�݂ł��B���ꂾ���ɁA�Љ��{�݂Ƃ��Ă̑��݈Ӌ`�Ɩ������\���ɔ������A�n��Z���ɂƂǂ܂�ʑ����̕��X�̐��U�w�K�̏�Ƃ��Ă̋@�\���ʂ������Ƃ����߂��܂��B���̂��߂ɂ́A�����فA�}���ق̉^�c�ɏn�m���A�����ي����s�ψ��̕��X�Ƃ��\���Ȉӎv�a�ʂ��͂����o���L���ȐE���̔z�u���������܂���B�������A�̐S�̐E���͊J�݂̂R�J���O�ɍ̗p��W���s�Ȃ��A�Q�������肩��s�̌����فA�}���قɔh�����ĕ����Ă��炤�Ƃ����ł��B����ł́A�t���Ă��n�I�Ȃ��̏ꂵ�̂��̂��̂ƂȂ�A���N�҂����ꂽ�Љ��{�݂̊J�݁E�^�c�ɐӔC�����̂Ƃ͂Ȃ�܂���B�S���J�݂ɂ�������ƐӔC���ʂ����Ƃ����Ȃ�A�s�̐E���ɂ�钼�c�ł̉^�c�ɉ��߂�ׂ��ł��B�������s�̓��ق́A�����܂ł��u�m�o�n��ɂ��肫�v�ɌŎ����Ă���A����A�����ł�����̂ł͂���܂���B����āA���̗\�Z�v��ɂ͎^���ł��܂���B
�@����̕�\�Z�ł́A�����ی�̑��ɔ����\�Z���v�コ��܂����B�Ƃ��낪���̍����ɁA������s�̈�ʍ�������x�o���Ă�����z���܂ޕُ��������̂܂[�Ă��Ă��邱�Ƃ��A���^�̂Ȃ��Ŗ��炩�ƂȂ�܂����B�ُ����̓���́A������̕��S�����S���̂R�A������s�̕��S�����S���̂P�ł��B���̋K�肩�炢���A������s�̕��S���ł��� 488���~�������������z���A�����ی��̕���ɏ[�Ă���ُ����ƂȂ�ׂ��ł��B�������A�����玦���ꂽ�ُ����̐��x�����̂悤�ɂȂ��Ă���Ƃ̂��ƂŁA���܂�ɂ��������Ȃ��Ƃł��B���ɑ��āA���x�̌����������߂�ׂ��ł��B
�@�܂��A����̕�\�Z�ł� 6,150���~���̌��M����̑��z���g�܂�܂����B�u2011�N�x���Z�z��10�����v�œ����\�Z��g�݁A�\�Z�s�������������Ƃ���ł��B�������A2011�N�x�͂��̔N�̂R���ɓ����{��k�Ђ��N���A�N�Ԓʂ��Č����{�݂̐ߓd���������ꂽ�N�ł���A���̎���10�����ō��N�x�̓����\�Z��g�ނ��Ǝ��́A�N���݂Ă������Șb�ł��B
�@������s�́u��@�I�����v���A�s�[�����A�s���{�݂�s�����Ɩ����s�Ȃ��{�݂��܂߂āA���M�������Օi��A�R����A�d�b���Ȃǂ́u���N�x�A10���팸�v��ł��o���A�ی�҂̗��������Ȃ��Ȃ��ŁA����ɂނɊw���ۈ珊��ۈ牀�̖��Ԉϑ�����i�߂悤�Ƃ��Ă��܂��B����ŁA�s���̂��炵�Ɋւ��\�Z�̍팸�ɂȂ����^�J����s�s�v�擹�H���݂ɑ��Ă͐��i��\�����Ă��܂��B����ł́A������u��@�I�����v���A�s�[�����Ă������͂Ɍ�������肩�A����Ȃ���������ɓ˂��i�ނ����ł��B12���̗\�Z�ψ���̒i�K�ɂ����Ă��A���N�x�\�Z�v���z�Ɨ\�肷��\�Z���z�Ƃ̊Ԃɂ́A���܂���26���~���̘���������Ƃ̂��Ƃł��B�Ȃ�Ȃ�����̂��ƁA����ȍ������₵�A���z�̎؋���w�������ƂƂȂ��^�J����s�s�v�擹�H���݂͌������A�J���D��̎s���^�c�����߂�ׂ��ł��B���̂��Ƃ��������w�E���A����̕�\�Z�ւ̔��Γ��_�Ƃ��܂��B
�݂��ً�s�͏��ᔽ
�@������s�̎w����Z�@�ւł���u�݂��ً�s�v���A��g����M�̉�Ёu�I���G���g�R�[�|���[�V����(�I���R)�v��ʂ��āA�\�͒c���֖� 230���E�Q���~�ȏ���̗Z�����s�Ȃ��Ă������́A���Z�����Q�x�̍s���������s�Ȃ��A�Ɩ����P���߂��o���܂łɂȂ��Ă���B���́u�݂��ً�s�v��������s�̎w����Z�@�ւɂ��Ă����Ă����̂��A���̂��Ƃ����ܖ���Ă���B
�@������s�ɂ́u�\�͒c�r�����v������A���̑�R���ł́u��{���O�v���������A�u�\�͒c�ƌ��ۂ��Ȃ����ƁA�\�͒c������Ȃ����ƁA�\�͒c�Ɏ�������Ȃ����ƁA�y�і\�͒c�𗘗p���Ȃ����Ɓv�Əq�ׂĂ���B���̋K��́A�s���ł��鏬����s�A�s���A���Ǝ҂ɋ��߂Ă�����̂ł���A���Ǝ҂ł���u�݂��ً�s�v���u�\�͒c�Ɏ�������Ȃ����Ɓv�Ƃ����������܂߂ĊY�����邱�ƂɂȂ�B
�@�܂��u������s�_��ɂ�����\�͒c���r���[�u�v�j�v�ł́u���ӌ_��̔r���v�Ƃ����K�肪����A���̋K��ɊY������u�ʕ\�v�ł́u���D�Q�����i�Җ��͂��̖��������A�����Ȃ閼�`�������Ă��邩���킸�\�͒c�����ɑ��āA���K�A���i���̑��̍��Y��̗��v��s���ɗ^�����ƔF�߂���Ƃ��v�́u���D�Q�����O�̑[�u�v�ɊY������Ƃ��Ă���B
�@�u�݂��ً�s�v�́A�R�N�O�ɗZ����̒������s�Ȃ������_�Ŗ\�͒c���ւ̗Z����c�����Ă���B�Ƃ��낪�A���̌���Q�N�ȏ�A���Ȃǂ̎葱�����Ƃ炸�ɕ��u���Ă����B����͒N�����Ă��A�\�͒c���ɗ��v��s���ɗ^����g�D����݂̍s�ׂł���B
�@���̂悤�ɁA�\�͒c���ɗZ�����s�Ȃ��Ă����u�݂��ً�s�v�́A������s�̏��Ɉᔽ���A������s�̓��D���珜�O�����c�̂ł���B���R�ɁA�w����Z�@�ւ̌_��������ƂȂ�B�u���v�u�v�j�v��҂܂ł��Ȃ��A�����̎��Ԃ́A�u�݂��ً�s�v�������c�̂̎w����Z�@�ւɂӂ��킵���Ȃ��Ƃ����̂́A�_��҂܂ł��Ȃ��Ƃ���ł���B
�@�u���E�v�j�Ɉᔽ���Ă���w�݂��ً�s�x�Ƃ̎w����Z�@�ւ̌����������߂���v�ƁA����10��15���̎s�c��Z���ʈψ���̍ŏI���Ɏs�̌��������������B���ق��������������́A�O�����n��ł͏�����s�܂ނV�s���u�݂��ً�s�v���w����Z�@�ւɂ��Ă���Əq�ׁA���̂����Łu���E�v�j�ɂǂ̂悤�ɊY�����邩�ڍׂɕ��͂��Ă��Ȃ��̂ŁA10��28���̋��Z���̋Ɩ����P���߂̓��e�����Ă��������v�Əq�ׂ��B
�@���̓��ق���͏��Ȃ��Ƃ��R�̓_�������Ă���B�P�́A������肵���肵�����E�v�j�ɉ����ă`�F�b�N���Ă����Ƃ����p�����������Ă��邱�ƁB�Q�ڂ́A���Z���Ƃ�����O�҂̔��f�Ɉς˂�Ƃ����T�ώғI�Ȏp���B�R�ڂ́A���E�v�j�Ɉᔽ���Ă���Ƃ������̎w�E��ے�ł��Ȃ��������� �ł���B10��28���̋��Z���̋Ɩ����P���߂��ǂ̂悤�Ȃ��̂ɂȂ邩�͕s�������A���̂܂܉������Ȃ��������̂悤�ɁA���N�x�ȍ~���u�݂��ً�s�v���w����Z�@�ւ̍��ɂ���ƂȂ�A������s�͎���̏��E�v�j�ɔw�����������ƂɂȂ�B
���w�����\�Z�̊g�[��
�@�u���w�����v�Ƃ������x������B�o�ϓI�ȗ��R�ŏC�w������Ȑl�ɑ��āA�C�w��K�v�Ȋw���������Ƃ������́B������s�͂��̏��w�������A�����w�Z�A��w�A�������w�Z�ɍ݊w���A�u���їD�G�v�u�S�g���S�v�u�o�ϓI���R�ɂ��C�w����v�̎O���������˔������l�ɑ��āA���z���x���i���t�j���Ă���B
�@�ߓ��̎s�c��Z�ψ���ł̓��قɂ��ƁA�u��w���y�э������w�Z��(��S�w�N�E��T�w�N)�v�ւ̋��t���x�́A�O�����n��ł͏�����s�̂݁B�u���Z���y�э������w�Z��(��P�w�N�����R�w�N)�v�ւ̋��t���x�́A�O�����n��ł͏�����s�܂߂�11�s����Ƃ����B������s�̏��w���͖��N�x�́u�\�Z�͈͓̔��v�Ŏx���l���E�z�����܂邪�A���\�̂悤�Ɏx���l���͖��N�ς�炸�A�z��2011�N�x����u���Z���y�э������w�Z��(��P�w�N�����R�w�N)�v���������ꂽ�B
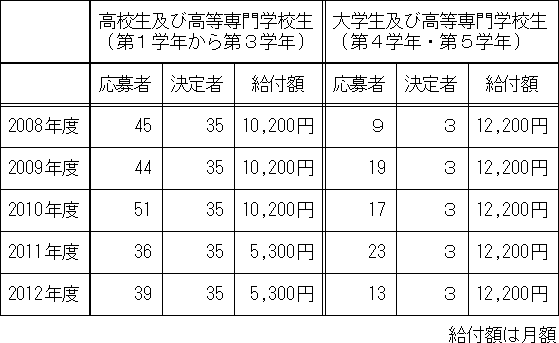
�@2011�N�x����u���Z���y�э������w�Z��(��P�w�N�����R�w�N)�v�������ƂȂ������R�́u���Z�̎��Ɨ��������v�ł���B�����������A���{�����ɂ����āu���Ɨ��������̌������v�������A���������̓������`���z�����Ă���B���̂��Ƃ���S���ۂ́u����ɂ��ẮA���w�����^�c�ψ���Ɏ����Ă��������v�Ƌc��œ��ق��Ă���B
�@���͏�L�̎������c��ɒ�o���ꂽ�����A�u���Z���y�э������w�Z��(��P�w�N�����R�w�N)�v���u��w���y�э������w�Z��(��S�w�N�E��T�w�N)�v���A���N�A�u35�l�v�u�R�l�v�Ƃ����l���ŐV�K�ɋ��t���肳��Ă�����̂Ɣ��f�����B�Ƃ��낪�A�ʂ̋c��z�z�����ł́A�u�V�K�v�Ɓu�p���v�����킹���l���ł��邱�Ƃ��L����Ă���A��̎��������ł͌�����F���Ɏ���Ƃ������Ƃ�����������B�c�����̎��₪�A���̂��Ƃ�F��������ł̎��₾�������ǂ����͕s���ł���B�ȉ��́u��v�Ȏ{��̐��ʂɊւ���������v�ɋL�ڂ���Ă��鐔���ł���B
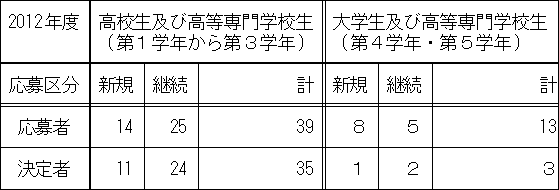
�@�������i�C����ɂ���āA�����̕�炵�͂܂��܂��������Ȃ��Ă���B���{����}���鏊�������̓��E�O�ɂ�����炸�A�ƌv�ɐ�߂鋳���͍����Ȃ����ł���B�䂪�Ƃɂ����Ă��A��w�Q�N�̑��q�̊w����w�����ɕt�������o��ƌv��h���Ԃ�A�v�w�Œ��N�����Ēz���グ�Ă����������A���낵���قǂɉ������Ă��Ă���B���������q�̉��ɂ͍��Z�R�N�̖�������B������w���߂����Ă��邱�Ƃ���A���q�Ɩ��̑�w�������d�Ȃ闈�N�x����̂Q�N�Ԃ́A�n���̓��X�ł���B�䂪�Ƃ̏ꍇ�͎�̒���������A�u���w�����v�ɂ�����܂łɂ͂�����Ȃ����A�q���������̉ƒ�ŁA�䂪�ƂƓ����ߖ��オ���Ă��邱�Ƃɋ^���Ƃ���͂Ȃ����낤�B���w�����\�Z�̊g�[����킸�ɂ͂����Ȃ��B
�܂₩���́w�s���f�f�����x
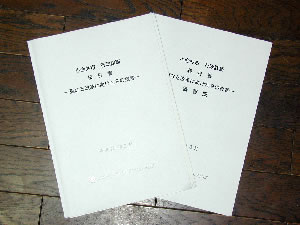 �@������s�͍����̎s�������u��@�I�v�Əq�ׂĂ���B�������ɁA�����̎s�����́u��@�I�v�ƌ����ɂӂ��킵�����ԂƂȂ��Ă���B������s�̍����s����₤���߂ɐςݗ��ĂĂ���u������������v�́A�����_��11���V�疜�~�ɂ������A���N�x�̗\�Z��g���_�ŁA�]�͂��Ȃ����ԂɊׂ�\���������B���̏��Ȃ�Ƃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl����̂́A���ꂵ�������ł���B �@������s�͍����̎s�������u��@�I�v�Əq�ׂĂ���B�������ɁA�����̎s�����́u��@�I�v�ƌ����ɂӂ��킵�����ԂƂȂ��Ă���B������s�̍����s����₤���߂ɐςݗ��ĂĂ���u������������v�́A�����_��11���V�疜�~�ɂ������A���N�x�̗\�Z��g���_�ŁA�]�͂��Ȃ����ԂɊׂ�\���������B���̏��Ȃ�Ƃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl����̂́A���ꂵ�������ł���B
�@������s�͂��̂��߂ɍ�N�x�A�u�s���f�f�����ϑ����v��\�Z�������B18�N�Ԃ�Ɏ��{���ꂽ�s���f�f�́A�������i�C����ɂ���čΓ��̍����ł���s�Ŏ������L�єY�݁A�Љ�ۏ�֘A�o��̑啝�ȑ����Ȃǎs�������ɒ�����������m�ۂ��������Ȃ�A���̈���ō�����������̌͊����ڑO�ɔ���ȂǁA�}���ȍ������̕ω��ɒ��ʂ��鎖�ԂƂȂ���������s�̎s�����^�c���A�s���ȊO�̑�O�҂̋q�ϓI����Őf�f���A��̓I�ȉ��P��̒�Ă����Ă��炤���������Ƃ����̂��ړI�ł���B
�@���N�R���A�u�X�Ȃ���v�Ɍ������X�̒v�Ƒ肵���u�s���f�f���v���A�������ϑ����ꂽ�u�O�H�t�e�i���T�[�`���R���T���e�B���O�v�����o���ꂽ�B�u���v�ŏq�ׂ�u�X�̒v�͈ȉ��̓��e����Ȃ��Ă���B�P��v���Ƃ̍����v��ɂ��Ǘ��A�Q�l������v�̍X�Ȃ鐄�i�A�R�s���]���̍č\�z�A�S��v�ҕ��S�̓K�����A�T����������Ɍ��������g�݂̐��i�A�U�s�L���Y�̗L�����p�̐��i�A�V�s�������v�ɂ��l�I�����̑n�o�A�W�l�I�����̍œK�z�����ɂ��g�D�̍č\�z�A�X�E���̈ӎ����v�Ɛl�ވ琬�ɂ��E���͂Ƒg�D�͂̌���B�����āA���̑S�̂𗬂���́A����R���s�������v��j�Ɍf�������g�݂̐��i�A���O���ϑ����ɂ���đΉ��\�ȋƖ��̖��m���A�������̎�v�ҕ��S�̒���I�����������[�����E�V�X�e�������鄟�������ł���B
�@���͂��̕������āA����������Ă��܂����B����́A�����̍����𓊓������z�̋N���s��K�v�Ƃ���A�s�����Ɉ�ԉe����^�����^�J�����Ƃ�s�s�v�擹�H���Ƃւ̌��y������Ă��Ȃ����Ƃł���B����ŁA�s���ɂ���Ȃ镉�S�����߂�u��v�ҕ��S�v�͒[�X�ɓo�ꂵ�Ă���B�������A���͎v���B�s�����^�c���`�F�b�N���邽�߂ɂ́A�s�����ɑ傫���e��������ڂ����Ƃ����ׂĐo���A��������ǂ̂悤�ɑΏ����A�}�����ׂ����̂͗}�����ׂ��Ƃ�������Ō�������̂��u�s���f�f�����v�̊�{�ł͂Ȃ����낤���B
�@�Ƃ��낪���ł́A��^�J�����Ƃ�s�s�v�擹�H���Ƃɑ��Ă͈�A�}����������A�t�Ɂu����������A�������䗼�w���Ӑ���(����)���A���z�̍�����K�v�Ƃ���d�v�ۑ肪�R�ς��v�Əq�ׁA�u�w���Ӑ������̓s�s�v�掖�Ƃ��͂��߂Ƃ���s���s���̌�N�x���S�������鎖�Ƃ́A�P�N�x�y�ь�N�x�̕��S�������v��Ɉʒu�Â��A�v��I�Ȏ��s�����߂���v�Ɨe�F���Ă���B�Ȃ����̂悤�ȕ��ɂȂ����̂���������������ɂ��Ĉȍ~�A���̂��Ƃ��^��Ƃ��Ă��т���Ă����B
�@�s���f�f�����̈ϑ����Ǝ҂̑I�o�́A�u�w���^�v���|�[�U���v�ɂ��ƂÂ��A�����̂̌v������o�c�f�f���̎�����т�����A������s�ɓo�^�̂���Ǝ҂̒�����V�Ђ�I��B���ސR���y�уv���[���e�[�V�����R���̑����]���_�̍ł��������Ǝ҂��ŗD�G��Ď��Ǝ҂Ƃ��đI�肵�Ă���B�R����́u������s�̍s���f�f�����̈ʒu�Â��𗝉����A��O�ҕ]���Ƃ��Ă̋q�ϐ����m�ۂ����悤��Ă���Ă��邩�B���Ă���Ɩ����e��I�m�ɂƂ炦�āA�K�Ȓ�Ă��Ȃ���Ă��邩�v�Ƃ���A�f�f��A���ɍl�����邱�ƂƂ��āu�����E���͂̍ۂɂ́A������s�̓��F�ł���}���Ɉ��������������N�������g�D�̐��A�X�ɂ͏�����s����芪���Љ�o�Ϗ���l�����邱�Ɓv�Ƃ��Ă���B���̊���̂́A�����Ăǂ��̂����̂Ƃ������̂ł��Ȃ��B�����A�u������s�̍s���f�f�����̈ʒu�Â��𗝉����v�Ƃ��������Ɓu���Ă���Ɩ����e��I�m�ɂƂ炦�āv�Ƃ����Ƃ��낪�Ђ�������B�����ŕ��ǂɁu�ϑ��d�l���v���o���Ă�������B
�@�u�ϑ��d�l���v������ƁA�u���P��̑O������v�Ƃ������̂��������B�ǂ̂悤�ɋL����Ă��邩���������B�u��Ă�����P��̓��e�́A�ł�����菬����s��S����{�\�z�y�я�����s��R���s�������v��j�������܂��Â���i�s���Q���E�s�������E�����A�g�j�̎�����ڎw�����̂ł��邱�Ɓv�B���������܂�A����������w��k�̊J���Ⓦ������w�k����搮�����ƁA�s�s�v�擹�H�̌��v��L�����u��S����{�\�z�v���ӂ܂��邱�Ƃ����߁A���̂����Łu��v�ҕ��S�v�u���Ƃ̈ϑ����v������u��R���s�������v��j�v�ɉ��������̍쐬�����߂�Ƃ������̂ł���B�v����ɁA�u���ׂĂ̎������Ƃ̐o���v�������Ȃ���A��{�\�z��s�������v��j�Ɏ���������̕��j�́u����v���������鄟�������Ƃ����킯�ł���B
�@���̂悤�ȍs���f�f�����͑S���Ӗ����Ȃ��Ȃ����肩�A�Ӑ}�I�ȁu�O������v�ɂ���āA�܂₩���́u���v���쐬����A���̕��̓��e�������ɂ��q�ϐ������邩�̂悤�Ɉ����邱�Ƃɂ���āA�s���Ɂu��@�I�����v�̐^�̌�����`���Ȃ�����Ƃ������Ԃ����肾�����ƂƂȂ�B���߂������Ƃ̂ł��Ȃ��A�s�̎p���ł���B
�@����10���R���̌��Z���ʈψ���ł��̓_���w�E���A�u���̍s���f�f���͔j�����邩�A�������͈�̑O�������t�����ɁA�s���f�f����蒼���ׂ��v�Ǝ咣�����B��������t�s���́A�u��S����{�\�z�͎��̑I������ł���A���Y�}�Ƃ͈ӌ����قȂ�v�Əq�ׁA��^�J����s�s�v�擹�H���݂��u���扻�v����u�s���f�f�v���A����������l�����������B����łǂ����āA��@�I������ŊJ�ł���Ƃ����̂ł��낤���B��t�s���ł́A������s�̊�@�I�������������邱�Ƃ͕s�\�ł���B
�@������s�č��ψ��ɂ��2012�N�x������s�Γ��Ώo���Z�ɑ���ӌ����i�č��ӌ����j�ł́A�����̎s�����ɑ��āu�����̍d���������O�����v�Əq�ׁA�u�����ɂ킽���Ď����\�����������s������Ղ̊m����}���Ă������߂ɂ́A��R���s�������v��j�����͂ɐi�߂Ă����ƂƂ��ɑ�O�҂ɂ��s���f�f���ʂ�^���Ɏ~�߁A�����K�����ɂ߂邱�ƂȂ��A��@�ӎ��������Ă��̓�ǂ�ŊJ���邱�Ƃ��������߂�v�Əq�ׂĂ���B�܂��A�s�v�𐄐i���邽�߂ɂ���ꂽ�u������s�s�������v�s����c�v�͂X��24���t�Łu�ً}�v����t�s���ɒ�o�B���N�x�̗\�Z�Ґ��Ɍ����āu��v�ҕ��S�̓K�����Ɍ��������g�݂̋����v�u�e���Ƃ̖��c���Ɍ��������g�݂̐��i�v�u�������S���v��̍���v�����߂Ă���B
�@��������A��^�J����s�s�v�擹�H���݂Ȃǂ��u���扻�v���A�s�����S���A���Ƃ̖��Ԉϑ������������u��R���s�������v��j�v�������߂邱�Ƃł́A��t�s���Ɠ�������ł���B������s�č��ψ����s�������v�s����c���A�̐S�Ȃ��̂����悤�Ƃ͂��Ȃ��A���邢�́u���扻�v����_�ŁA�{���̔C�����ʂ����鑶�݂Ƃ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B����A��t�s���Ƌ����������Ƃ邱�Ƃ��A���̗��g�D�̖����ɂȂ��Ă���̂�������Ȃ��B������ɂ��Ă��A�s���̖ڐ��Ƃ������ꂽ���g�D�̎��_�ł���B
�i���́j�ш�k���n��Z���^�[
�@�n��Z���^�[�Ƃ��Ă͂S�ٖڂƂȂ�u(����)�ш�k���n��Z���^�[�v�����N�S���ɊJ�ق�\�肵�Ă���B�n��Z���ɂƂ��Ă͒��N�҂���т��A�Җ]�̎{�݂ł���B���̊ԁA�s�̌v��Ɋ��x���o�ꂵ�A�����Ɍ������\�Z���v�コ��Ă͂������A�u������v�𗝗R�Ɂu���f�E�摗��v�̘A���ł������B�������A���ɒ��H�̉^�тƂȂ�A�����̎p�������悤�ɂȂ����B
�@���̊ш�k���n��Z���^�[�ɂ́A�����قƐ}���ق����݂����B���̎{�ݑS�̂�������s�͈ϑ�����Ƃ����B�ϑ��ƂȂ�ƁA�Љ��{�݂Ƃ��ẮA������s�ł͏��߂Ă̂��ƂƂȂ�B�������A�ϑ���́u�m�o�n�@�l�v���Ƃ����B
�@�����قƐ}���ق����݂����{�݂ł��邱�Ƃ���A������s�͂��̎{�݂̉^�c�`�Ԃ̂�����ɂ��āA�����ى^�c�R�c��Ɛ}���ً��c��Ɂu���l�����������������v�Ƃ̎�����s�Ȃ����B
�@�����ى^�c�R�c��ɑ��Ă͍�N�X��21���Ɂu�P�w�s�������x�w�����A�g�x�ɂ��V���Ȍ����ى^�c�ɂ��āB�Q��҃R�[�i�[�݂̍���ɂ��Ą��������̂Q�_�ɂ��āA�ǂ̂悤�ɂ���s�Ȃ���̂��A�܂��A�ǂ̂悤�ȉۑ肪����A���̉����̂��߂ɂ͂ǂ̂悤�Ȕz���A���ӎ������K�v���v�Ƃ����ۑ��N�ł���B
�@����A�}���ً��c��ɑ��Ă͍��N�̂R��28���Ɏ�����s�Ȃ��Ă��邪�A���̎�����e�َ͈��ł���B�u�}���ى^�c��ړI�Ƃ����m�o�n�@�l�ݗ����x�����āA���}���ٕ����^�c�Ɩ����ϑ����A�s���Ƃ̘A�g��}��Ȃ���J�ٓ��E���Ԃ̊g��ȂǁA�s���j�[�Y�ɉ������}���ٕ����̉^�c��}�邱�Ƃ��l���Ă��܂��B���̂��Ƃɂ��āA�ǂ̂悤�Ȕz���A���ӎ������K�v�Ȃ̂��A���ӌ��A���������������������������v�B���łɁu�m�o�n�@�l�ϑ��v���O��ƂȂ��Ă���̂ł���B
�@�����ى^�c�R�c��͍��N�̂V��26���ɓ��\���s�Ȃ����B���₪�u�w�s�������x�w�����A�g�x�ɂ��V���Ȍ����ى^�c�v�𒌌��Ă��Ă��邱�Ƃ���A�u�c�^�̉^�c�`�Ԃ��̗p����ꍇ�ɂ́v�Ƃ̑O�u�������������ŁA�u���Ƃ��āA�\���ȉ^�c�\�͂�����������c�̂��A�n��ɂ����Ē����I�Ɋm�ۂ��邽�߂ɂ́A�s���Ǝs�����A�g���Ăm�o�n�@�l���琬����Ȃǂ̕�����l������Ƃ���ł���v�ƁA�s���ۑ��N�����u�z���A���ӎ����v�ւ̉������Ă���B
�@����̐}���ً��c��B���\�͂V��19���ɍs�Ȃ�ꂽ���A���̓��e�͎���i�K�Ō����̕��������������Ă��邱�Ƃ���A���̂悤�Ȍ��t�Ŏn�܂��Ă���B�u���╶��ǂ�ł݂܂��ƁA�ш�k���n��Z���^�[���ɊJ�݂���V�����}���ق̉^�c���m�o�n�@�l�Ɉϑ�����Ƃ����}���ق̍l���������łɎ�����Ă��܂��B���c��Ƃ��ẮA�s�����V�����}���قɊ��҂��邱�Ƃ�c�����A�s���̋��߂�}���كT�[�r�X�Ƃ͉����𖾂炩�ɂ��A�}���ى^�c�̊�{����������ŁA�m�o�n�@�l�ֈϑ�����ꍇ�̏��ۑ�ɂ��Č�������Ƃ��������ŋc�_��i�߂��Ă܂����v�B
�@���̂����Ő}���ً��c��́u�m�o�n�@�l�ֈϑ�����ꍇ�̏��ۑ�v�L���A�����ē��\���ł́u�}���ى^�c�̊�{�v�Ƃ̒����Ă��s�Ȃ��A�����Ȋw�Ȃ́u�}���ق̉^�c�y�щ^�c��̖]�܂�����v(2012�N12��19���E����)�Ɠ��{�}���ً��2010�N�X���ɔ��\�����u�}���َ��Ƃ̌��_���ɂ��āv���Љ�Ă���B�܂��u�m�o�n�@�l�ւ̈ϑ��ɂ�����z�����ׂ������Ɋւ��Č��O�����ӌ�������܂����v�Əq�ׁA�u�s�̖ڎw���w�s�������x�����A�}���ق̊J�ٓ��E�J�َ��Ԃ̊g��A���c�����̌o���̌p���A�E���̐�含�y�ьo��팸�Ɋւ��ẮA�\���Ɍ���������ŐV�����}���ق̉^�c��}���邱�Ƃ�]�݂܂��v�ƋL���Ă���B�����ɂ́u�m�o�n�@�l�ϑ��v��}���ً��c��̋c�_�����Ŏ����Ă����s�ɑ���A�}���ً��c��̍��f�Ԃ�A�{���ǂݎ�邱�Ƃ��ł��鄟�������ƁA���͎v���̂ł���B
�@������s�́A�}���ً��c���̓��\�ƌ����ى^�c�R�c���̓��\���āA�����ى^�c�R�c��瓚�\�������ꂽ�V��26���ɋ���ψ�����J�ÁB����ψ���́u�m�o�n�@�l�ϑ��v�𗹏������B
�@�������A�O�q�̂悤�Ɍ����ى^�c�R�c����}���ً��c����u�m�o�n�@�l�ϑ��v���u���v�Əq�ׂĂ���킯�ł͂Ȃ��B�}���ً��c��ɂ������ẮA����i�K�Łu�m�o�n�@�l�ϑ��v���O��Ƃ���Ă��܂��Ă���̂ł���B�Ƃ��낪������s�́A�u���̓��\�d���āA���\�ɋL�ڂ̂��鏔�������N���A�[���A�m�o�n�@�l�Ɉϑ�����v�Ƃ̔��f���������Ƃ����̂ł���B�u�m�o�n�@�l�ϑ��A�����ɂ��肫�v�ƌ��킴������Ȃ�����悤�ł���B
�@�}���ً��c��Ɏ��₷��i�K�ŁA���łɁu�m�o�n�@�l�ϑ��v�̕��j��������Ă���B�u�N�����߂��̂��B����̗���𖾂炩�ɂ���v���������W���P���̌��������ψ���œ��{���Y�}�̐���m�u�c�����₢���������B���U�w�K�����́u���N�P��30���̗����ҋ��c�ŁA�m�o�n�@�l�ϑ��̕��������o���ꂽ�v�Ɠ��فB�����ى^�c�R�c��͋c�_���A�}���ً��c��͎��₷��A����Ă��Ȃ��B����@�֖����́A���܂�ɂ�����Ȃ����ł���B
�@�Ȃ��u�m�o�n�ϑ��v�Ȃ̂��B�s�́u�s�������v�u�����A�g�v�Əq�ׂ邪�A���ǂ̂Ƃ���́u�o��팸�v�u�l����팸�v�̈�_�ł���B�u�m�o�n�v�͖��ԉ�ЂƈقȂ�A���v��Nj�����c�̂ł͂Ȃ��B�u������v�̂Ƃ���V���Ȏ{�݂�������B�Ȃ�u�s�������v�u�����A�g�v���s�̕��j�ƂȂ��Ă���̂�����A�u�m�o�n�v�ł���Ă݂悤�����������ꂪ�z���l�ł��낤�B
�@�������A�}���قƌ����ق����݂���{�݂��܂邲�ƈϑ����邽�߂́u�m�o�n�@�l�v�́A������s�ɂ͑��݂��Ă��Ȃ��B�������J�ق͗��N�S���ł���B������s�͋}�s�b�`�Łu�m�o�n�@�l�v�����グ�ւƑ������B�����ق̗��p�c�̂ցA�̂��Ȃ݈ē���𑗕t���A�V��30���Ɂu���p�ҍ��k��v���J�ÁB�W���R���Ɂu�m�o�n�@�l�ݗ����N�l��v���J���A�W��10���Ɂu�ݗ�����v�J�ÁB�N���ɂm�o�n�̖@�l�����s�Ȃ��A���N�S���ɂ͈ϑ��Ƃ����A�����ʂ�̋삯���X�P�W���[���ł���B�W�҂���́u���܂�ɂ��ّ��v�Ƃ̈ӌ����o����Ă���B�����ى^�c�R�c����}���ً��c����A���̂悤�Ȃ�������ԁA�뜜���Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�}���ً��c��Ɛ}���ِE���͍��N�T��17���ɁA�m�o�n�@�l�ʼn^�c���s�Ȃ��Ă��铡��s�̒ғ��s���}���ق����@�����Ƃ����B������s�c��̌��������ψ���́A������s�ŏ��߂ĂƂȂ�m�o�n�@�l�ϑ��̎��ۂ��w�Ԃ��߂ɁA����s�ւ̎��@��Őf�����B�������A����s����́u�������˂�v�Ƃ̕Ԏ����͂��A���@�͎������Ȃ��Ȃ����B�c�O�ł���B
�@�Љ��{�݂��܂邲�ƈϑ��A�������m�o�n�@�l�ւ̈ϑ��ł���B�T�d�ɂ��T�d���d�˂邱�Ƃ����߂���B�u�ّ��v�Ƃ̈ӌ����o����錻��A������s�͕��j���čl���ׂ��ł��낤�B
�s�����S�����s���ɐ錾
�@�u����25�N�x���ɁA����26�N�x�̍��ېł̌���������������������Ȃ��v�u����26�N�x�̓����\�Z��g�i�K�ŁA������������͒��˂��v����������t�s���̂��̔����́A�u����A�s���̕��S�͑����Ă������ƂɂȂ�v�Ƃ������Ƃ��A�s���݂����炪�s���ɐ錾������̂ƂȂ����B
�@�T��21��(��)�A������s�c��́A�������N�ی���v�̕�\�Z��R�c����Վ��c����J�Â����B2012�N�x�̍��ۉ�v�̎��x���s�����邽�߂ɁA�T�����̏o�[���܂ł̊��Ԃ�2013�N�x�̍��ۉ�v����s���z���J������(�J��グ�[�p)�Ƃ������̂ŁA���ۉ�v���N�����Ă��邱�Ƃ��������̂ł���B���̐R�c�̉ߒ��ŁA�`���̔�������яo�����B
�@���͂Q�̓_�Ŏs���̌��������������B�P�ڂ́A����ȏ�̎s�����S���́A�����Ă͂Ȃ�Ȃ����ƁB���N�S���������ł̑��ł������A���N10������͔N���x���z�̍팸���n�܂�B����Ȏ��ɂ���Ȃ�s�����S���́A�s��������j��ȊO�̂Ȃɂ��̂ł��Ȃ��B���ł͂�߂�ׂ��ł���A�ƁB�Q�ڂ́A�u����������������˂��v�Ƃ������A�Ȃ�A�����Ȃ�Ȃ��悤�ɁA�s�����ɑ傫�ȕ��S������ڂ���������w�k����搮�����Ƃ═��������w�����Q�n��̍ĊJ���v��A�k���̊J���v����������ׂ��ł���A�ƁB�������s���́u�����\�ȍ����^�c�̂��߂ɂ����߂Ă����v�Əq�ׁA�s���̂������ύX����l���͂Ȃ����Ƃ��������B
�@���̂��Ƃ͉����Ӗ����邩�B�s���������悤�ɁA���N�x�̓����\�Z��g�ޒi�K�ō���������������˂����Ƃ́A�قږڂɌ����Ă���B�������s���́A��^�J����s�s�v�擹�H���݂戵���ɂ��āA�����ɂ����߂Ă����ƌ����B�Ƃ������Ƃ́A���̕��A���炩�̕��@�ō������m�ۂ��邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�Ƃ������ƂɂȂ�B�܂�́A��R���s�������v��j�Ŗ������Ă���u�s�����S���v�u�L�����v�u���Ԉϑ����v������ɂނɓ˂��i�߂�Ƃ������ƂɂȂ�B�u���Ԉϑ����v�ł͂��łɏ��w�Z���H�����̖��Ԉϑ����̃X�P�W���[����������A�E���c�̂ɂ́A�ۈ牀�A�����فA�w���ۈ�̈ϑ������c�̑��k���������܂�Ă���B�����āA���ېł̑��ŕ\���ł���B
�@��N�́A���ېŁA���ی����A�������҈�Õی����������ݒl�グ����A�s���̔ߖ��s�����ɉ������N�ł������B�Ȃ̂ɁA��^�J���������߂����ł���Ȃ�s�����S���E�L���������������̂悤�Ȏs���^�c���s�����]��ł���Ƃł������̂ł��낤���B�����ɕ��S�������t���鐭���͌Í������A���������������͂Ȃ��B��t�s�����������������E�����E����̊e�c���ɂ��A���̎s���^�c�̂������������Ă��炢�������̂ł���B
�O���̋c���E�m��
�@18��(��)�̎s�c��Վ��c��ŁA�S�N�Ԃ̂����̑O���Q�N�Ԃ̋c���E�l�����m�肵�܂����B���{���Y�}�s�c�c�͖�E�l�������߂�ɂ������āA�i�P�j�s���ɂ킩��₷�����@�Ȃ�тɗ\�肳��Ă�������Ō��肷��悤�w�͂��邱�ƁA�i�Q�j�l���̂Ƃ������O���[�v��g�ށu�l����h�v�u�l���O���[�v�v�͔F�߂Ȃ����ƁA�i�R�j������h�̌������\���ɕۏႷ�邱�ƁA�i�S�j�c���A���c���ɂ��Ắu�����̏퓹�v���Q�l�ɂ��A�ő��h����c���A���ɑ�����h���畛�c���A�R�Ԗڂɑ�����h����č��ψ���I�o���邱�ƁB�b�������Ō��_���o�Ȃ��ꍇ�A�I���őI�o����Ƃ��������ɗ����Ԃ邱�Ƃ����蓾�邱�Ƅ��������̂S�_�̐\������
��S�Ă̋c���ɍs�Ȃ��܂����B
�@��E�l�������߂邽�߂̘b�������́A�����̓����ǂ���11���E12���E15���̂R���ԂŏI���B���ׂĂ̖�E�l�����b�������Ŋm�肵�܂����B�����\��̓����Ō��܂����̂́A����20�N�Ԃ̋c�������̂Ȃ��ł��A���Ȃ蒿�������Ƃ��Ǝv���܂��B
�@�ő�̏œ_�ł������u�c���v�E�ɂ́A�Q�l��h�̉��v�A���̎��Ђ낵�����A�C���܂����B�{���ł���ő��h�̎����}���A�C���ׂ��ł����A�����}�����̎��ɑ��������}���u�͕s���v�𗝗R�ɌŎ��B�u���Y�}�ɋc�����v�Ƃ����b�����`�����Ă��܂����B���̂��߁A�b�������̏�����11���͈�،��܂炸�ɏI���B�Q���ڂ�12���ɂȂ��āA�c���E�o���҂ŋc�������ł��������Ђ낵���̖��O�������}��������炳��A����B���c���E�����X���Ԃ�������܂������A�����}�̘I���N�����ɓ��肵�܂����B�����āA�R���ڂ�15���ɂȂ�Ɛl���|�X�g�̌��߂Ă������o�ŁA�X���[�Y�ɐi�s�B�ߑO���ɂ��ׂĂ̖�E�l�������肵�܂����B
�@���͂Ђ��т��Ɍ��������ψ���S���ցB���Y�}���玄�Ɛ���m�u�������������ψ���S���ƂȂ�A���Y�}����ψ����E���o�����Ƃ����܂�܂����B�ǂ��炪�ψ����E�ɏA���������Y�}�c���c�Ō����������ʁA�O���܂ł̌��������ψ���̎��^���e���n�m���Ă��鐅��m�u�������^�Ŋ撣��K�v������Ƃ̌��_�ɒB���A���܂�n�m���Ă��Ȃ������ψ����E�ɏA�����ƂɂȂ�܂����B
�@18���̗Վ��c��Ŗ�E�l�����m�肵�A�������������ψ����Ɍ��܂����r�[�A�����Ɋւ��e���ʂ���̉�c�A����̈ē��E���m�点�������Ă��܂����B���������ψ����͋c��̊O�ł̂��d�����������������̂ł��B���������ψ����E�ɏA�C�����̂͂Q�x�ځB�O���10�N�O��2003�N�T���ł����B
���u�c��E�ψ���Ȃǂ̐l���ꗗ�v���o�c�e�Ōf�ځiPDF56KB�j
�����\�Z�̑g�ւ���
 �@���{���Y�}�s�c�c�͖��N�A������s�̔N�ԗ\�Z(�����\�Z)�ɑ��āA�\�Z�̑g�ւ��Ă��Ă��Ă��܂��B�Ȃ��A�s������o�����\�Z�Ɏ^���ł��Ȃ��̂��A�ǂ̂悤�ȗ\�Z�ł���ׂ��Ȃ̂��𖾂炩�ɂ��邽�߂ɁA���{���Y�}�s�c�c�̍l�����������̂ƂȂ��Ă��܂��B �@���{���Y�}�s�c�c�͖��N�A������s�̔N�ԗ\�Z(�����\�Z)�ɑ��āA�\�Z�̑g�ւ��Ă��Ă��Ă��܂��B�Ȃ��A�s������o�����\�Z�Ɏ^���ł��Ȃ��̂��A�ǂ̂悤�ȗ\�Z�ł���ׂ��Ȃ̂��𖾂炩�ɂ��邽�߂ɁA���{���Y�}�s�c�c�̍l�����������̂ƂȂ��Ă��܂��B
�@�g�ւ��Ă̎��́A(�P)�s�������������𑝂��Ă�����Ƃł́A����Ȃ��^�J����V���ȓ��H���݂͍s�Ȃ��ׂ��ł͂Ȃ����ƁB(�Q)���H�g���v���s�s�v�擹�H�̌��݂ɂ����āA�y�n�̋������p�͍s�Ȃ��ׂ��ł͂Ȃ����ƁB(�R)���(���[�X����)�̒��ݎ،_������N12�����ŏI�������邱�Ɓ\�\�\�����ƂɁA�����Ő��܂ꂽ�������A(�P)���Ԃ��ݗ�����F�ۈ牀�A���ʗ{��V�l�z�[���֕⏕���s�Ȃ��B(�Q)���ېł���l�N�z�T��~�A�l��������B(�R)�����x���@�ڍs�Ő����鎙�����B�x���Z���^�[�ƕ���������Ə��̗��p�ҕ��S����S�z��������B(�S)�s�����K�͓X�܌��菤�i���̃v���~�A�����̕⏕���s�Ȃ��B(�T)�ϐk�f�f����������ёϐk���C�������̃A�b�v�ƏZ��t�H�[���������x�̑n�݁B(�U)�ЊQ��W��̑��z�B(�V)�A�w�����W�̊g�[�\�\�\�Ȃǂ��s�Ȃ��Ƃ������̂ŁA�Ώo�\�Z�̂킸��0.73����g�ݑւ��邾���Ŏ����\�Ƃ������̂ł��B�R���U���̖{��c�ł́A�g�ݑւ��Ă������E�쐬���������A���{���Y�}�s�c�c���\���Ē�Đ������s�Ȃ��܂����B
�@�g�ݑւ��Ă��Ă����̂́A���{���Y�}�s�c�c�����ł����B�����}�A�����}�A����}�A�Ж��}�͎s����Ă̓����\�Z�Ɏ^�����邱�Ƃ���g�ݑւ��Ă�C���Ă��o���Ȃ��̂͗����ł��܂����A�s����Ă̓����\�Z�ɔ�����u�݂ǂ�s���l�b�g�v�͑ΈĂ��������A���{���Y�}�s�c�c��o�̑g�ݑւ��Ăɂ������Ă��܂��܂����B
�@�ӔC���c�����h�ł���Ȃ�A���߂ĔN�ԗ\�Z(�����\�Z)�ɑ��Ă͑ΈĂ������āA����̍l����咣�𖾂炩�ɂ��ׂ��ƍl���܂��B�N�ԗ\�Z(�����\�Z)�ɑ��đg�ݑւ��Ă��������쐬����̂́A�����ւ�ȘJ�͂�K�v�Ƃ��܂����A���̘J�͂�ɂ��܂����킷�邱�Ƃ��A���߂���p�����Ǝv���܂��B���̓w�͂��ʂ����Ȃ������u�݂ǂ�s���l�b�g�v�̔����̋c���́A����̎s�c�I�ŗ��I���Ă��܂��܂����B
�@���{���Y�}�s�c�c��o�́u2013�N�x��ʉ�v�\�Z�g�ւ����c�v�u2013�N�x��ʉ�v�̗\�Z�g�ݑւ����ځv���o�c�e�t�@�C���Ōf�ڂ��܂����A�c��W�҂Ȃ���킩�肢�������܂��悤�ɁA������s�c��̏ꍇ�́A���Ƃ��g�ݑւ��Ăł����Ă��A�\�Z�C���ĂƓ��l�̌`�����Ƃ��Ă��܂��B�܂�A���ł��\�Z�C���Ă���o�ł���悤�ɂƁA�c����ǂ̉������w���̂��ƁA�������͌P���������Ă���Ƃ����킯�ł��B
�E2013�N�x��ʉ�v�\�Z�g�ւ����c�iPDF88KB�j
�E2013�N�x��ʉ�v�̗\�Z�g�ݑւ������iPDF153KB�j
�F�ۈ牀�̕ۈ痿������������
�@���Ɉ�t�s�����ϔO�����B��N�t������{���Y�}�s�c�c�����ߑ����Ă����u�F�ۈ牀�̕ۈ痿�̈��������v�����N�S��������{���邱�Ƃɓ��ݐ����̂ł���B
�@���Ƃ̋N����͔N���}�{�T���̏k���E�p�~�ł���B����}��������ɁA�q�ǂ��蓖�̍�����Ƃ��ĔN���}�{�T���̏k���E�p�~�����s����A���̂��Ƃɂ���āA�F�ۈ牀�̕ۈ痿�̌v�Z��b�z���ς��A��N�S������ۈ痿���啝�ɃA�b�v�����̂ł���B�u�����͑����Ȃ��̂ɉ��̏オ��̂��v�u����ł͕�炵�����藧���Ȃ��Ȃ�v�Ɣߖ̐����������A�T����������{���Y�}�s�c�c�̂��Ƃɋ~���̎�����߂鐺�����͂��߂��B
�@�N���}�{�T���̏k���E�p�~�ɂ���ĕۈ痿���ւ̉e���������邱�Ƃ́A���������킩���Ă������Ƃł���B���������ۂɕی�҂̕��X�̘b�����������ƁA�ۈ痿�A�b�v�̕��͑�ςȂ��̂ł������B18�Έȉ��̎q�ǂ�����������ƒ�قǁA�A�b�v�̕��͑傫���Ȃ�̂ł���B���{���Y�}�s�c�c�͒������J�n�����B���̌��ʁA�����J���Ȃ��e�����̂ɒʒm���o���Ă������Ƃ��킩�����B
�@�ۈ痿���ւ̉e�������O���������J���Ȃ�2011�N�V���A�N���}�{�T���̏k���E�p�~�ɂ���ĉe���������Ȃ��悤�ɑ���Ƃ邱�Ƃ��e�����̂ɒʒm�B�Ƃ��낪������s�͂��̒ʒm�����A����Ƃ邱�Ƃ����Ȃ������̂ł���B
�@2012�N�T���̎s�c����������ψ���œ��{���Y�}�̐���Ђ낵�c���́A������s�c��ōŏ��ɂ��̖������グ�A���J�Ȓʒm�ɏ]���悤�v���B�����łU���s�c��ł͎�����ʎ���Ŏ��グ�A������s�̍s���葱����̖��_��Njy�B�U�����{�ɂ́A������s�c�c�ɑ��k����ꂽ�ی�҂��s�c��ɒ���o���A�X���s�c��̖`���Ŏ^�������ō̑��B�������X���s�c��̈�ʎ���ŐX�˂悤�q�c�����A��̑����ĕۈ痿�����Ƃɖ߂��ׂ��Ɨv���B12���s�c��ɂ͕ۈ�W�̒c�̂�������o����A���N�Q���c��̖`���Ŏ^�������ō̑����ꂽ�B��������t�s���͋c��ӎv�ɏ]��Ȃ��ԓx�ɏI�n���A�ی�҂̔ߖɎ��������Ȃ����Ԃł������B�Ȃ�Ƃ����Ȃ���E�E�E�B���Ƃ͕ۈ痿�������������c����Ăōs�Ȃ������Ȃ��B
�@���́A���{���Y�}�s�c�c�͍�N�X���i�K�ŁA�ۈ痿���������̏��Ă��������Ă����B����o���邩�̍����������v����Ă����̂ł���B����Q����̑����ꂽ�ɂ�������炸�s���͉����悤�Ƃ͂��Ȃ��B�Ȃ̂ɖڂ̑O�ɂ͐V�N�x�������Ă���E�E�E�B
�@�Q���s�c��̖`���A���{���Y�}�s�c�c�͋c��^�c�ψ���̐ȏ�ŁA����Ă�\���B���s���āA���Ăւ̎^���҂�����g�݂������߁A���ɋc����h���m�ۂ��邱�Ƃɐ����B����ɍQ�Ă��̂��s���ł������B�u���̂܂܂ł͋c����Ă̈���������Ⴊ�c���ʂ��Ă��܂��E�E�E�v�B
�@�^�}��h������{���Y�}�s�c�c�ɑ��k����ꂽ�B�u�c�Ă���艺���Ăق����B���̂����s����Ăň������������o������v�B���s��������A����𗠕t����b���͂��A���{���Y�}�s�c�c�͏��Ă���艺���邱�Ƃɂ����B�Ȃ��A�O�̂��߂ɗ\�Z�ψ���̏�Ŏs���̌��������߁A��t�s������́u�c��̈ӎv�ɏ]���v�u�V�N�x����Ή�����v�̔���������A�����Ɏ�艺�����s�Ȃ����B
�@�R���S���̎s�c��{��c�ɏ�����s������ۈ痿�̈���������Ⴊ��Ă���A�S���v�ʼn��E�����B���ɂS������l�グ�O�̕ۈ痿�ɖ߂����Ƃ��\�ƂȂ����B���̎d���A���{���Y�}�s�c�c�����Ȃ������炯�����āA�Ȃ����Ȃ��������̂ł���B
�w�w�O��ɏW���x�p�r�n��ݒ���j
�@����܂œs���{���Ɍ��茠���������y�n���p�̕��j��p�r�n�擙�̐ݒ���j���A���N�x�����s�����Ɍ����Ϗ�����邱�ƂɂȂ�܂����B���̂��Ƃ��珬����s�͍�N11���P���̓s�s�v��R�c��Ɏs�̕��j�Ă�����B�P��23���̓s�s�v��R�c��ł͓��\�Ă�������܂����B
�@�s�̕��j�́A��N�R���ɍ��肳�ꂽ�u������s�s�s�v��}�X�^�[�v�����v�܂������̂Ƃ���A����������w���ӂ���ѓ�������w���ӂ�s�s�����̋��_�Ƃ��A�������H�����ɓs�s�@�\�̏W�ς��͂��邽�߂̗U�����݂��邱�Ƃ��������Ă��܂��B�����āA���̎����̂��߂ɁA���w���z�����\�ƂȂ�悤�ȓs�s�v�挈����s�Ȃ��A400���ȏ�̗e�ϗ����w�肳�ꂽ���ɂ��ẮA�אڂ���Z���ւ̓��ƌ��m�ۓ���ړI�Ƃ��������̖k���ΐ����������߂Ȃ����ƂL�B�X���݂���ւ̔z����ړI�ɁA���̕~�n�ʐψȉ��̌����͔F�߂Ȃ��[�u���Ƃ邱�ƂȂǂ����L���Ă��܂��B
�@�����ꂽ���j�Ắu�����ڏ��v�Ƃ͂������̂́A��ɏW���E�ߖ����𑣐i���铌���s�̕��j���������o����̂ł͂Ȃ��A�u���v�Ɓu�݂ǂ�v�������I�ȏ�����s�̊X���݂Ƃ́A�������ꂽ���̂ɂȂ��Ă��܂��B
�@���̓��\�Ăɑ��ĂP��23���̓s�s�v��R�c��ł͓��{���Y�}�݂̂������A�u�݂ǂ�v��u���v�̑�����q�ׂĂ���u�݂ǂ�s���l�b�g�v�܂߂āA�^�������ň�t�s���ɓ��\���邱�Ƃ����肳��܂����B
�@�����{���Y�}�s�c�c�͓��\�ɂ������āA�ȉ��̈ӌ����q�ׂ܂����B���Q�Ƃ���������K���ł��B�i2013�N�P��30���t�j
[���{���Y�}�s�c�c�̓s�s�v��R�c��ł̈ӌ��\��]
�@�u�p�r�n�擙�Ɋւ���w����j�ɂ��āv�ɑ��āA�ӌ����q�ׂ����Ă��������܂��B����̈Č��́A�p�r�n��̌��肨��ѕύX�̌������A��N�S�������s�����Ɍ����ڏ����ꂽ���Ƃ��āA�s�s�v��R�c��ɕt�c���ꂽ���̂ł��B���̈Ӗ��ł́A��s�����Ǝ��ɁA���̎����̂�u�܂��v�ɍ������p�r�n������肷�邱�Ƃ��ł���Ƃ������̂ł���A����܂ł̓s���{���Ɉς˂��Ă����A��s�����̂܂��Â���Ɋւ���y�n���p�̕��j��p�r�n�擙�̐ݒ���j���A�n�������ɂӂ��킵���A�{���̂�����ɂȂ������̂Ƃ����܂��B
�@�Ƃ��낪�A�t�c���ꂽ�Č������܂��ƁA�����s�������߂悤�Ƃ��Ă���A�s�X�n�̍ĕ҂�i�߂Ȃ���̓y�n���p�̋K���E�U�����������A�����̂̐����ړI�ɍ��v����J���v��ɂ��Ă͋K����e�͉�������e�����L����Ă��܂��B�܂�A�����s�������߂Ă���u�����̓s�s�Đ��v�̖��ɂ���ɏW���E�ߖ������i�̕��j�Ɍĉ����āA�����U���^�̂܂��Â���������߂悤�Ƃ������̂ƂȂ��Ă��܂��B
�@�������̂悤�ɁA������s�͓s�������Ɉ͂܂�A�k�ɋʐ�㐅�A��ɂ͖�삪����A�n�P�ƌĂ��i�u�������ɑ���A�n�������L�x�ɗN���o��A�u���v�Ɓu�݂ǂ�v����F�Ƃ����u�܂��v������������ɂ��Ă��܂��B���̏�����s�ɂ����āA�����s�̕��j�ƕς��Ȃ��A�w�O�ɍ��w���z����z�u���A�������H�����ɓs�s�@�\�̏W�ς��͂��邽�߂̗U�����݂���Ƃ����y�n���p�̕��j��A����ɉ������p�r�n��̐ݒ���j�́A�u���v�Ɓu�݂ǂ�v������������ɂ���������s�ɂ́A�ӂ��킵�����̂ł͂���܂���B
�@�����ڏ��ɂ���āA�p�r�n��̌��肨��ѕύX�͏�����s���g�Ō��߂邱�Ƃ��\�ł��B���̂��Ƃ́A��N11���P���̓s�s�v��R�c��ɂ����āA�����ƂȂ�@�����u�s�s�v��@��19���R���v�́u���c�v�Ƃ��������ɂ��邱�Ƃ������ǂ��玦����A�u�����s�Ƌ��c���Ȃ���A�s�Ǝ��̕��j�͉\�v�Ƃ̐���������Ă��邱�Ƃ�������Ăł��B
�@�ł���ɂ�������炸�A�u���v�Ɓu�݂ǂ�v����F�Ƃ����u�܂��Â���v���炩�����ꂽ�A�����s�̈�ɏW���E�ߖ������i�̕��j�Ɍĉ���������̓��e�́A������s�̓��F���Ȃ�������ɂ�����̂ł���A�F�߂�킯�ɂ͂����܂���B����āA�{�t�c�Č��Ɂu���v��\��������̂ł��B
�I�O��Ȕ��e���فw�{���s�����w���������x
�@���̎���ɑ��āA���̂��̂悤�ȓ��ق��o�Ă���̂��H���������ߓ��̎s�c��ł̎��̎���ɑ���s���̓��قɁA���܂Ȃ������������������Ȃ��B
�@����́A�P��24��(��)�̏�����s�c��ݏ����{���ݓ��������ʈψ���̍Ō�̎��^�ł̂��ƁB���N�x���Łu���ċp��Ւn�v�̍X�n�����������A���͂������P.�T���̋��Ԃň͂����ƂɂȂ��Ă��邱�Ƃɑ��āA�����u������s�̎����� 3,700�������[�g���̎g�����̌����X�P�W���[���͍l���Ă��Ȃ��̂��H�v�Ǝ��₵�����Ƃւ̎s���̓��قł���B
�@���̎���͎��ɒP���ł���B�s���ɂ̓O���E���h�����Ȃ��A�싅��T�b�J�[�Ȃǂ��s�Ȃ��O���[�v�́A���K�ꏊ�T���Ɏl�ꔪ�ꂵ�Ă���B�����ɏo�������̂��A���ċp��Ւn�B������s�A���z�s�A�{���s�����ꂼ�� 3,700�������[�g�������L����`�ԂƂȂ��Ă���B���̏�����s�̏��L�����ǂ̂悤�Ɋ��p����v��Ȃ̂��B���p���邽�߂̌����X�P�W���[���͍l���Ă���̂��B�����A���ꂾ���̎���ł���B�Ƃ��낪�Ԃ��Ă������ق͈ӕ\��˂��A�����̓��e�ł������B
�@��t�s���ƎO�ؕ��s������������킹�A�Ȃɂ��R�\�R�\�B�����ĎO�ؕ��s���������オ��A���̂悤�ɏq�ׂ��B�u�{���s��(3,700�������[�g��)�̍w���ɂ��āA���A�������Ă��������v�B
�@�G�b!?�B�܂������\�����ʁA�v�������ʓ��قł������B�Ⴆ�Ă����A�o�b�^�[�{�b�N�X�ɗ����Ă��鎞�ɁA�}�E���h�̓��肩��{�[�����������܂�Ă���Ǝv���Ă�����A��ێ肩��{�[�������ł������������ɓ��������̂ł������B������A���̓��قɑ��ĕԂ����t���o�ė����A���̂܂���͏I���Ă��܂����B�u�Ȃ�̂��߂ɍw������̂��v�u�ړI�͂Ȃɂ��v�ƁA�{���Ȃ�Ď���ɂȂ�ׂ��Ƃ���ł���̂ɁB
�@�O�ؕ��s���̓��قɂ͒N���������͂��ł���B�ψ����̓n�ӑ�O�������Ɠ��l�Ɂu!?�v�Ƃ����\��������Ă����B�Ƃ��낪�A���ċp��Ւn�ɋ߂��������������_�ɂ���c�����܂߂āA�^�}�n�̋c���͂���قǂł��Ȃ��l�q�ł������B���̂悤�ȓ��ق��o�Ă���A�u�w������ړI�͂Ȃɂ��v�Ə��Ȃ��Ƃ����₷��̂��ʏ�ł���B�������A����n�ӑ�O���̂悤�Ȋ���ł͂Ȃ������B����������ƁA�^�}�T�C�h�ɂ͎��O�ɘb���������̂�������Ȃ��B�����Ƃ����v���Ȃ��悤�ȕ\��ł������B
�@�u�{���s���̍w���ɂ��āA���A�������Ă��������v�́A�����Z���ɂƂ��Ă��{���s�ɂƂ��Ă��A�����Ē��z�s�ɂƂ��Ă������ׂ����قł���B�Ȃ�̂��߂ɍw������Ƃ����̂��H�B����̓��e�Ɗ��ݍ���Ȃ��g���e���فh�͍���A�ǂ̂悤�ȃn���[�V������ł����ł��낤���B
�A�w�����̎x����ڂ̊g���
�@�ǂ̎����̂ɂ��A���������w�Z�ɒʂ������E���k�ɑ���u�A�w�����v���x������܂��B�u�o�ϓI�ȗ��R�ŏA�w������Ȏ����A���k�̕ی�҂ɑ��Ċw�Z����ɕK�v�Ȕ�p���x�����A�����A���k�����S�ɋ`��������邱�Ƃ��ł���悤�ɉ�������v�i������s�A�w������x���v�j�̑�P���j�Ƃ����̂��A�ړI�ł��B���̐��x�́u�����ی���Ă���Ƃ��Ȃ��Ƃɂ�����炸�A�ی��K�v�Ƃ����Ԃɂ��鐢�т̎����E���k�v(�v�ی�)����сu����ɏ�������x�ɍ������Ă��鐢�т̎����E���k�v(���v�ی�)�ɑ��čs�Ȃ����̂ŁA������s���܂ޑ����̎����̂ŁA�x���Ώۂ��u�v�ی�v�Ɓu���v�ی�v�Ƃɕ����ĉ������Ă��܂��B
�@���̏A�w�������x�ɑ��ĕ����Ȋw�Ȃ�2010�N�x����A�u�N���u������v�u���k���v�u�o�s�`���v���������ڂɒlj����A�u�v�ی�v�̎����E���k�ɑ��Ă͍�����̕⏕�����x�o����Ă��܂��B����āA������s�ł����̂R�̔�ڂ��u�v�ی�ҁv�Ɏx������Ă��܂��B����A�u���v�ی�ҁv�ɑ��Ă͒n����t�łɂ��̕�����悹����Ƃ������ƂŁA�g���������肳��Ȃ���ʍ����ł̈����Ƃ���Ă��܂��B��ʍ����ł̈����Ƃ͂����Ă��A�u���v�ی�ҁv�ւ̂R�̔�ڂ̎x���g�傪�O��Ƃ���Ă��܂��̂ŁA�R�̔�ڂ��u���v�ی�ҁv�ɓK�p����͓̂��R�̂��Ƃł��B
�@������s�͌��݁A�n����t�ł̌�t�c�̂ƂȂ��Ă���A�R�̔�ڂ��u���v�ی�ҁv�֓K�p�����邽�߂̊z����t�ł̒��ɑg�ݍ��܂�A�����炨�������Ă��܂��B�Ƃ��낪������s�́A�u���v�ی�ҁv�̏A�w�����̂Ȃ��Ɂu�N���u������v�u���k���v�u�o�s�`���v��K�p�����Ă��͂��܂���B
�@�ł́A������s�ɂ����āu���v�ی�ҁv�Ɂu�N���u������v�u���k���v�u�o�s�`���v��K�p�������ꍇ�A�ǂꂭ�炢�̗\�Z�[�u���K�v�ƂȂ�ł��傤���B����ψ���w���ۂ���o���������ɂ��ƁA�u���k���v�͏����w�Z�Ƃ��Ɏ��ȕ��S������܂���̂Łu�[���v�B�u�o�s�`���v�͏����w�Z�̍��v�� 154��845�~�A�u�N���u������v�͏��w�Z�́u�[���v�A���w�Z�͍��v�� 75��6,112�~�B�܂�A�S�������킹��Ɓu229��6,957�~�v�Ƃ������ƂŁA230���~����u���v�ی�ҁv�ւ̓K�p�͉\�Ƃ������ƂɂȂ�܂�(�\�Q��)�B�O�q�����悤�ɁA���̂����̈��z���n����t�łɏ�悹����č����炨�������Ă��܂��̂ŁA������s�̏����ȕ��S�z�́A230���~�������Ȃ��Ȃ�܂��B
[������s�ɂ�����u���v�ی�v�����E���k�ւ̓K�p���Z 2013�N�x������]
|
���v�ی�
|
���k���
|
�o�s�`���
|
�N���u������
|
�� �v
|
|
���w�Z
|
515�l
|
�O�~
|
938,845�~
|
�O�~
|
938,845�~
|
|
���w�Z
|
301�l
|
�O�~
|
602,000�~
|
756,112�~
|
1,358,112�~
|
|
���v
|
816�l
|
�O�~
|
1,540,845�~
|
756,112�~
|
2,296,957�~
|
�@����2012�N12�����s�c��̓��j�c��̈�ʎ���ŁA�u�����Ȋw�Ȃ̒ʒm�ɂ��ƂÂ��A�A�w�����̏��v�ی�҂ɑ��Ă��A�w���k���x�Ɓw�o�s�`���x�A�w�N���u������x���A�w�����̎x����ڂƂ��ēK�p������ׂ��v�Ɨv�����܂����B�������A�w�Z���畔���́u�A�w�����͎s�撬���̎��Ƃł���A�x����E�x���葱�͎s�撬������߂���́B�O����26�s�̂Ȃ��ł���ڂ�lj�����Ƃ���͂Ȃ��̂ŁA����ł��������������������v�Ƃ������̂ł����B
�@���͂��̂悤�ȓ��قɂ́A����A�[���ł��܂���B������̒n����t�ł̊z�̂Ȃ��ɏ��v�ی�҂ɑ���R�̔�ڕ����܂܂�Ă���킯�ł�����A���v�ی�҂̏A�w�����ɂR�̔�ڂ�lj�����͓̂��R�̂��Ƃł��B���������邽�߂ɍ���Ƃ��v�����Â��܂��B
�@�Ƃ���ŁA�����}�▯��}�A���{�ېV�̉�Ȃǂ́A�����ی�������т̑������āA�����ی��̈��������Ȃǂ̌�������\�����͂��߂Ă��܂��B�������A�����ی���������������A�A�w�����𗘗p���Ă��鎙���E���k�̂Ȃ��ɂ́A�ΏۊO�ƂȂ�q�ǂ����o�Ă��Ă��܂����ƂɂȂ�A�o�ϓI�ȗ��R�ŋ`��������邱�ƂɎx�Ⴊ�o�Ă��邱�Ƃɂ��Ȃ肩�˂܂���B
�@�����ی�̑����́A�����̑��ɖ�肪����킯�ł͂���܂���B�A�����J�E�����Ɏ����Ő��E�R�ʂ̌o�ϑ卑�ł���Ȃ���A���̌o�ϗ͂��������ɊҌ������邱�Ƃ��ł��Ȃ������̑��ɐӔC������܂��B�����ی��̈��������͒f�Ŕ��ł��B
���v�ی�҂̏A�w������ڂ̊g���
�@�o�ϓI�ɍ���ȉƒ�ɕ�炷���w�Z�A���w�Z�̎����E���k�ɑ��āA����ɌW���p����������A�w�������x������B�����ی���т܂��͐����ی��K�v�Ƃ���鐢�т̎����E���k�i�u�v�ی�ҁv�j�ƁA�����ی���тɏ�������x�Ɍo�ϓI�ɍ������Ă��鐢�т̎����E���k�i�u���v�ی�ҁv�j��ΏۂɎ��{����Ă�����̂ŁA������s�̏ꍇ�A���v�ی�҂́A�����}���ɂ����āA�����ی��z�̂P.�W�{�܂ł�ΏۂƂ��Ă���B
�@�����Ȋw�Ȃ�2010�N�x����A���̏A�w�����̑Ώ۔�ڂɁu�N���u������v�u���k���v�u�o�s�`���v��lj����A�v�ی�҂Ɏx�������z�̂Q���̂P��⏕���Ƃ��Ēn�������̂Ɍ�t���邱�ƂƂȂ����B���̂��Ƃ���A�ǂ̎����̂ł��A2010�N�x����v�ی�҂̏A�w������ڂɂ��̂R���ڂ�����邱�ƂƂȂ������A�����ی���т̎����E���k�ɂ����ẮA�����ی�̋���}����̒��ɂR���ڂɗv����o��x������Ă��邱�Ƃ���A�A�w�����Ƃ����`�ł̎x�������ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B�u������A������s�̏A�w�����̗v�ی�҂̎x����ڂɂ́A���̂R�������Ă��Ȃ���ł��v�ƁA�S���ے��͎��ɐ���������B
�@�����������́g�����A�����Ȃ̂��h�Ǝv�����̂����A��A�^�₪���܂ꂽ�B�S���ے��́A���ȏȂ��쐬�����u�v�ی쎙�����k������⏕����t�v�j�v�́u�ʋL�P�v�Ƃ������������Ƃɏq�ׂ��̂����A�ł͂Ȃ��A�u�N���u������v�u���k���v�u�o�s�`���v�Ɠ���������}���Ŏx������Ă���Ǝv����u�Z�O������v���A������s�̏A�w�����̗v�ی�҂̎x����ڂɓo�ꂷ��̂��낤�� �B�킩���B
�@���āA�{��͂��ꂩ��ł���B�A�w�����́A�u�`������͖����v�Ƃ������@��26���Ȃǂ̊W�@�ɂ��ƂÂ����{����Ă���B������A�v�ی�҂����łȂ��A���v�ی�҂��������x�������ׂ����̂ł���B�������A���ȏȂ��lj������R�̍��ڂ͗v�ی�҂����Ɏx������i���ۂɂ͐����ی�̋���}����Ŏx���j�A���v�ی�҂͑ΏۊO�ƂȂ��Ă���B
�@�X���c��̌��Z���ʈψ���Ŏ��́A�u�N���u������v�u���k���v�u�o�s�`���v�̎��ȕ��S�z�͂����炩�H�Ǝ��₵���B�Ƃ��낪�S���ے��́u�c�����Ă��Ȃ��v�Ƃ����̂ł���B���Ɏ��́u���v�ی�҂ɂ��K�p�������ꍇ�́A���z�łǂꂭ�炢�K�v�ɂȂ�̂��v�Ƃ̎�����l���Ă����̂����A�u�c�����Ă��Ȃ��v�ƂȂ������߁A�u�����I�v�ƂȂ����B�u���ȏȂ̂Q�N�O�̕����͒m���Ă����v�ƒS���ے��͏q�ׂA�u�����I�Ɍ������A��ڂ𑝂₷�͓̂���v�Ɣ��f���āA�����ĂR���ڂ̎��ȕ��S�z��c�����邱�Ƃ����Ȃ������Ƃ����̂ł���B
�@�����c���������݂��B�u����Ƃ����̂́A�N�����f�����̂��v�B�S���ے��́u���̔��f�Łw�����Ή����ł��Ȃ��x�ƍl���A�����ɂ��`���Ă��Ȃ��v�Ɠ��فB�ے��̑O�Ŏ��^���Ă����S�������͊��Ԃ�߁A���f�����l�q�ł������B�S�������́u���N�x�Ɍ����āA�������݂Ȃ��画�f���Ă��������v�Ɠ��فB���璷���u����A�������Ă��������v�Əq�ׂ��B
�@���Ȃ݂ɁA���ȏȂ��������R���ڂ̍���̎x�����z�́A�u�N���u������v�����w�Z 2,630�~�A���w�Z 28,780�~�A�u���k���v�����w�Z 4,440�~�A���w�Z 5,300�~�A�u�o�s�`���v�����w�Z 3,290�~�A���w�Z 4,070�~�ƂȂ��Ă���B������s��2011�N�x�̏��v�ی�҂́A���w���� 569�l�A���w���� 286�l�ł��邱�Ƃ���A����̎x�����z�ɂ��ƂÂ����z�� 1,680��5,740�~�ƂȂ�B
�@���̕������L���p�\�R���̂������ɂ́A���ȏȂ̒S���ǒ����e�s���{������ψ���璷���ɏo�����u�v�ی쎙�����k������⏕���y�ѓ��ʎx������A�w�����⏕����t�v�j�̈ꕔ�����ɂ��āi�ʒm�j�v����ѕ⏕����t�v�j�̐V���Ώƕ\�A2010�N�S���P���t�ňꕔ�������ꂽ�⏕����t�v�j�A����Ɋւ��鎑���u�ʋL�P�v�u�ʋL�Q�v�A������s�́u�A�w������x���v�j�v���Ƃ��닷���ƒu����Ă���B�����ߒ��߂��Ȃ��當�����������߂Ă����̂ł��邪�A�����܂ł̕����Ɏ���܂łɑ����ɉE���������Ă����B����͂Ȃ����B���̒��ɁA����₱���Ƌ^�₪������ł��邩��ł���B
�@���ȏȂ́A�v�ی쎙�����k�̏A�w������ɂQ���̂P�̕⏕�����o���Ƃ����B�������A�u�w�p�i��v�u�ʊw�p�i��v�u�Z�O������v�u�ʊw��v�u�̈���Z�p���v�u�N���u������v�u���k���v�u�o�s�`���v�ɂ��ẮA�����ی�̋���}�����s�Ȃ��Ă���҂������Ƃ����A�������R�Łu�V���w�������k�w�p�i��v�������}�����s�Ȃ��Ă���҂������Ƃ����B�悤����ɁA�����ی�ł��̔�ڂ��x���ΏۂƂȂ��Ă���l�ɑ��Ă͏A�w�����Ƃ����`�ł̎x���Ƃ͂Ȃ�Ȃ��̂ŁA�Q���̂P�̕⏕�ΏۂƂ͂Ȃ�܂����Ƃ������Ƃł���B����́A�����ł���B���������������̂́A���ȏȂ��Q���̂P�⏕�̑ΏۂƂ��Ă���u�v�ی쎙�����k�v�Ƃ����̂́A�u�����ی���т̎������k�v�Ȃ̂ł́H�Ƃ������ƁB�����珬����s�̒S���ے��́u������s�̏A�w�����̗v�ی�҂̎x����ڂɂ́A���̂R�������Ă��Ȃ���ł��v�Ǝ��ɐ��������̂ł͂Ȃ��̂��B�����͂��ł���B
�@�l�����邱�Ƃ́A�����ی��̐��������Ă��Ȃ��琶���ی�����ɂ��鐢�т����݂��A���̎����E���k���A�w�����́u�v�ی�ҁv�ɂȂ��Ă��� �Ƃ������ƂȂ̂ł͂Ȃ����B������A���ȏȂ́u�v�ی쎙�����k�̏A�w������ɂQ���̂P�̕⏕�����o���v�Ƃ����K�肪����̂ł͂Ȃ����B�����A���̍l���������Ă���̂ł���A������s�̏A�w�����́u�v�ی�ҁv�̎x����ڂɂ��u�N���u������v�u���k���v�u�o�s�`���v���������Ă����K�v������̂ł͂Ȃ��� �B����Ȃ��Ƃ��l���Ȃ��玞�v������ƁA�钆�̂P��������Ă����B�Q��I�B
2011�N�x��ʉ�v���Z���^�������ŔF��
�@������s�c��́A�X�����s�c��(��R�����)�̉�����Ɍ��Z���ʈψ�����J���A�O�N�x�̈�ʉ�v�Ɠ��ʉ�v�̌��Z�R�����s�Ȃ��Ă���B���N�̌��Z���ʈψ���͂S���ԍs�Ȃ��A10���T���̍ŏI�{��c�ŁA�^�������ŔF�肳�ꂽ�B
�@���{���Y�}�s�c�c�́A�����̎g��������������炸�̑�^�J���D��ł���A����ŁA�s���T�[�r�X�k�����s�Ȃ��Ă��邱�Ƃ���A�F��ɔ������B�F��ɔ������̂́A���{���Y�}�Ɓu�݂ǂ�E�s���l�b�g�v�̂X���B�^���͎����}�A�����}�A����}�A���v�A���̌v13���B�^�����_�͌����}�̋{�����c���Ǝ����}�̉����S���q�c���A���Γ��_�́u�݂ǂ�E�s���l�b�g�v�̐Ђ���c���Ɠ��{���Y�}�̎��E�q�^��ł������B
�@�^�����_�A���Γ��_�Ƃ��ɁA���ꂼ��̍l�����ɂ��ƂÂ��čs�Ȃ���͓̂��R�ł��邪�A�����ɍ���Ȃ����_���e�̓`�g����B�Ƃ����̂��A���Γ��_���s�Ȃ����u�݂ǂ�E�s���l�b�g�v�̐Ђ���c���̓��e�ɐ��������Ȃ�����ł���B
�@�؋c���́u�݂ǂ�E�s���l�b�g�v���\���Ĕ��Γ��_���s�Ȃ����B�؋c���͔��Γ��_���A�s���𗬃Z���^�[���w���������Ƃ����Ƃ�����_�ɍi���ďq�ׂ��B����͂���ō\��Ȃ����Ƃ����A�ł́u�݂ǂ�E�s���l�b�g�v�̂��������̋c���́A�u�s���𗬃Z���^�[�w���ɔ��v�ň�ѐ��������Ă����̂��낤���B
�@��N�S�����̎s���I���ō����a�Y�s�����a�������B���̍����s���̂��ƂŁA�u�s���𗬃Z���^�[�̕��ѐݔ��E���i�ނ̉��i�����s�Ȃ����߂ɕK�v�v�Ƃ̗��R�ŁA��N�X���c��ɁA�s���𗬃Z���^�[���ɔ�������Ă��镍�ѐݔ��E���i�ނ̍w���\�Z�R��3,656���~���c��ɒ�o�B10���I�Ղɂ́A�s���𗬃Z���^�[���u�P�M�R���v�ŕs���Y�o�L�����邽�߂̏����ƂȂ�A������s�̌��������m�肳���邽�߂̗\�Z340���~���}�����o���A������������E�����E����ƂƂ��ɍ����s�������������c���̎^�������ʼn��������B����ɂ��s���Y�o�L�͉\�ƂȂ�A���Ƃ͍Ō�̒i�K�́A�s���𗬃Z���^�[���w�����邽�߂̋c�Ă��c��ɒ�o���邾���Ƃ������ԂƂȂ����B����A�����a�Y�s���̂��ƂŁA�s���𗬃Z���^�[���w�����邽�߂̏����������s�Ȃ��A���̗\�Z�Ɂu�݂ǂ�E�s���l�b�g�v�̂��������̋c�����^�����Ă������Ƃ������ƂɂȂ�B
�@�����a�Y�s�������������c�������������a�Y�s���ɑ��āA�u�s���𗬃Z���^�[���w�����邽�߂̏��������͍s�Ȃ��ȁv�Ɣ���A�\�Z��Ă������Ă��Ȃ���A�؋c�����q�ׂ�u�s���𗬃Z���^�[���w���������Ƃ͖��v�Ƃ������Ԃ��}�����ɍς̂ł���B�ɂ�������炷�\�Z�͒�Ă���A����������Ɏ^������Ƃ��������ׂ��Ή����u�݂ǂ�E�s���l�b�g�v�̂��������̋c���͍s�Ȃ����̂ł���B�Ȃ̂Ɂu�s���𗬃Z���^�[���w���������Ƃ͖��v�Əq�ׂ�̂�����A�����������������Ȃ��̂ł���B
�@�w���̂��߂̏����������s�Ȃ��A�R�����Ŋ��������Љ�{����������t���̐\�����Ԃɍ����`�ŁA�Q���Ɏs���𗬃Z���^�[�̍w���c�Ă���Ă���A�^�������ʼn�����Ă������B�w���̂��߂ɏ�����s��27��9,120���~�̎؋����s�Ȃ��A���ꂩ��̎s�����ɏd���̂������邱�ƂƂȂ����̂ł���B
�@�ȉ��ɓ��{���Y�}�s�c�c���\���āA���E�q�^�炪�s�Ȃ������Γ��_���f�ڂ��܂��B����ǂ���������K���ł��B���Ȃ݂ɁA���{���Y�}�s�c�c�́A�S���҂��쐬�������_���e�̈Ă��S�l�S���œ��c��������������Ƃ����Ή����Ƃ��Ă��܂��B����āA���_���e�͂܂������u���{���Y�}�s�c�c���\�v���Ă���̂ł��B�Ȃ��A��ʉ�v���Z�̔F��ɑ��锽�Γ��_�̌��e�Ă͎��E�q�^�炪�쐬���A���e�Ă��S�l�ŏW�c���c���Ă܂Ƃ߂����܂����B
2011�N�x��ʉ�v���Z�̔F��ւ̔��Γ��_
�@���{���Y�}������s�c�c���\���āA2011�N�x��ʉ�v���Z�̔F��ɑ��锽�Γ��_���s�Ȃ��܂��B
�@�������i�C����̂��ƁA�s���̕�炵�͂��������������ɒu����Ă��܂��B���̂��Ƃ́A�s�ł̍����𐬂��l�s���ł��N�X�������A�ېŕW���z��200���~�ȉ��̐l�X���� �����Ă��邱�Ƃ���������邱�Ƃł��B���X�g���E�������ɂ���������������s���A�N���҂̔N���z�������I�ɒቺ�A�q��Đ������O�ł͂Ȃ��A�ۈ痿��[�߂���Ȃ����������Z�N�x��336���ƁA�O�N�x���56���������A�w���ۈ痿���O�N�x������447���̖��[���N���Ă��܂��B���т�33�����������鍑�����N�ی���28���̐��т��ی��ł�ؔ[���A�����ی���т� 2010�N�x��1,000���т�˔j�A�Ȃ��ł���Ґ���ő������Ă���̂������ł��B���̂悤�ɁA�������������������Ă���s���̕�炵�������ɉ������Ă����̂��A���̂��Ƃ��s���^�c�ɂ͋��߂��Ă��܂��B
�@���̓_�ɂ��Č��Z�N�x�́A��K�͉������w���ۈ珊�̂Q�{�݂����邽�߂̌��ւ��H�����s�Ȃ��A�ш��Z���^�[�ɃG���x�[�^�[��ݒu�A�S�Ă̏����w�Z�̕��ʋ����ɃG�A�R����ݒu�������Ƃ́A�s���v�]�ɑ���ϋɓI�Ȏ��g�݂Ƃ��ĕ]���ł�����̂ł��B���킹�āA�ۈ玺���̕ی�ҏ����������z 9,000�~�ɑ��z���A���ʎx���w���̎x������z�u���A���ʎx���w���̐V�ݓ��ɍ��킹�ēo���Z���̃X�N�[���o�X�ԁA�q�{��K���\�h���N�`���ڎ�ɑ��鏕���𒆊w�Z�P�N���`���Z�P�N�����q��ΏۂɎ��{�������ƂȂǁA�]���ł��镔�������Ȃ��炸����ƍl������̂ł��B
�@�������A�ȉ��̓_�Ŏs���^�c�ɑ��Ă̍��{�I�Ȗ�肪����ƍl������̂ł��B
�@��P�́A�s�����Ȃɂ������߂Ă���A��炵�̕��S���y�����A�s���T�[�r�X���[�����邽�߂̎{�s�\���Ȃ��Ƃł��B���ʗ{��V�l�z�[���̑ҋ@�҂�400�l���A������ ���Ȃ���ΐH�ׂĂ����Ȃ�����ɂ�������炸�A�ۈ牀�̑ҋ@����100�l���Ă��܂� �B���ېł���ی����̕��S�ɔY�ސ��т͑����A�s���ł̑ؔ[���т����Ȃ��炸���݂��܂��B���{�z�[����F�ۈ牀�̑��݂ȂǕK�v�Ȏ{�ݐ����������߂�ƂƂ��ɁA���S�y���̐V���Ȏ{���߂��܂��B�������A�ۈ玺���̕ی�ҏ������̑��z�͂��ꂽ���̂́A���S�y���̎��g�݂͓���A�s���̊肢�ɉ��������̂Ƃ͂Ȃ��Ă��܂���B
�@�������A�����J���Ȃ���͑Ή������߂�ʒm�����Ă����ɂ�������炸�A�N���}�{�T���̏k���ɂƂ��Ȃ��F�ۈ牀�̕ۈ痿�̉e������̑[�u���Ƃ�ꂸ�A�����Ȋw�Ȃ���͏A�w�����̏��v�ی�҂ւ́u�N���u������v�u���k���v�u�o�s�`���v�̎x�����s�Ȃ��w�j�������ꂽ�ɂ�������炸�A���܂��ɑ[�u����Ă��Ȃ����ƂȂǁA�s�Ȃ��ׂ����Ƃ���s�Ȃ�Ȃ��s���^�c�͔F�߂��܂���B�s�v�s�}�̓s�s�v�擹�H���^�J���ɂ��S�O�Ȃ����t���A�s���̕�炵����������{��͍�����̒ʒm�����Ă��s�Ȃ�Ȃ��B����Ȏs���^�c�͒f���ċ�������̂ł͂���܂���B���}�ɑΉ����邱�Ƃ��������߂���̂ł��B
�@��Q�́A�s�������E���A�P�N�̊ԂɎs���I�����Q�x���s�Ȃ��鎖�Ԃ������N�������u���ݏ������v�̑ŊJ�A�ˑR�Ƃ��Ďs���̑O�ɖ��炩�ɂ���Ă��Ȃ����Ƃł��B���s�̗�����n��Z���̗����������Ȃ��u���Ւn�v�ɂ����݂��A�������鎖�Ԃ����肾�������Ȃ͈�Ȃ��A�s���̕s���ɉ����邽�߂̑ŊJ��ɂ��ẮA���܂��Ɂu�ł�����̂͂Ȃ��v�ƌJ��Ԃ�����Ȃ��s���^�c�݂̍���́A�s���̗���������̂ł͂���܂���B���Ȃ��Ƃ��A���ݏ����̌���Ǝs�̍l���Ă�����������s���ɐ������ׂ��ł��B�Ƃ��낪���̂�����O�̗v���ɑ��āA�O�ؕ��s���́u�c���̑�����������v�Ƌ؈Ⴂ�̓��ق�����܂����B�s���ɑ���s���̐����ӔC��������A�s����\�̋c��Ɏs���ւ̐��������߂�Ƃ��������ׂ������ł���A�f���ĔF�߂�����̂ł͂���܂���B�s�����ӔC�������Ďs���Ɍ���ƕ�������m�点��ƂƂ��ɁA���}�Ɏ����\�ȕ�����������Ƃ����߂���̂ł��B
�@��R�́A�s�����ɑ傫�ȉe�����y�ڂ��A�����W�����G�ŁA���܂��ɊǗ��K������Ԃ��Ƃ̂ł��Ȃ��s���𗬃Z���^�[���擾�������Ƃł��B�s���𗬃Z���^�[�͍�N�U������s�s�Đ��@�\�̊Ǘ��̂��ƂŎs���̗��p�ɕt����A��z�[�������z�[������c���Ȃǂ��A���p�������Η��p�ł���悤�ɂȂ��Ă��܂����B�Ƃ��낪���N�Q���̗Վ��c��Ō����{�̂��w�����邽�߂̗\�Z��������A����ɂ��V���Ȏ؋���27��9,120���~�����邱�ƂƂȂ�A�w��Ǘ��ϑ����Ǝ؋��̕ԍςɁA2031�N�x�܂Ŗ��N�S���~�O����g�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�܂����B�Ŏ����L�єY�ނȂ��ł̖��N�S���~���̋`���I�o��̊m�ۂ́A�s���{��̗\�Z�팸�ɂȂ����Ă������̂Ɗ뜜������̂ł��B���ɁA���Z�N�x�̓r������A���ۊm�F�̂��߂́u�ЂƐ��K�⎖�Ɓv��u���ƂԂ����e����t���Ɓv���k������܂����B
�@�������A�s�s�v�擹�H�R�E�S�E12�����̐����̂��߂ɁA������s�̎��ƂƂ��Ă͏��߂ĂƂȂ�y�n���p�̎葱�����Ƃ��A�������������Ƃ����A���Z�N�x�͗p�n�擾��ɂQ��752��2,617�~���[�Ă��܂����B�����āA�}���K�v�Ȃǂ܂������Ȃ��A�n���҂̗����������Ă��Ȃ��s�s�v�擹�H�R�E�S�E�W�����̎��ƔF��O��Ƃ����d�������a�\���v�ϑ������g�܂�A2014�N�x����̈�ʉ�v�ł̎��Ɣ�v��̓��������Ă��܂��B
�@��������w�k���y�n��搮�����Ƃ͍����A�s�����ɑ傫�ȕ��S��^���Ă��܂��B���Z�N�x�ɂ����Ă��ϑ����Ɨp�n�擾���12���W�疜�~���v�サ�Ă���A���̂����s�̕��S�z�͂V���~�ɂ̂ڂ�܂��B��搮�����Ƃɗv�����N�̏��҂����N�P���T�疜�~�ɂȂ邱�Ƃ��z�肳��A����������w����̍ĊJ�����Ƃ�s���𗬃Z���^�[���݂ɑ��z�̐ŋ��𓊓����A���Ɛ��i�̂��߂ɔ��s�����s�̏��҂Ɏs���̐ŋ����[�Ă��Ă������Ƃ���A�s���F�߂�u��@�I�����v�ɂȂ��Ă���킯�ł��B���̂܂܋�搮�����Ƃ������߂邱�Ƃ́A�s�����ɂ����Ċ댯�Ȏ��ԂƂ��킴��܂���B�\�Ȃ�Ύ��Ƃ̌��������A�����łȂ��Ă����Ƃ̂���Ȃ鉄�L���s�Ȃ��A���N�̕��S�z�̌y�����s�Ȃ��ׂ��ƍl���܂��B�����ɁA�s�v�s�}�̓s�s�v�擹�H�͎�𒅂���ׂ��ł͂���܂���B�����̎g������芷����ׂ��ł��B
�@����A���^�̒��ł��č��ӌ����ɂ����Ă��A�Љ�����c��ւ̎s�̕⏕���A�ϑ���̂����������܂����B�s�̕⏕���x���̋K��ɔ����邠����𑁊��ɉ��߂邱�ƁA�Љ�����c��̍�����v�̎d�g�݂Ə�����s�̕⏕���E�ϑ���̎x���̎d�g�݂���������悤�ɉ��߂邱�ƁA�����āA�s���ɖ��m�ɐ������s�Ȃ�����e�ɂ��Ă������Ƃ��������߂���̂ł��B
�@2012�N�x�̍��N�x����́A���ېŁE���ی����E�������҈�Õی������l�グ����A�N���}�{�T���̏k���ɂ���āA�q��Đ���͏����ŁE�Z���ł��A�b�v���Ă��܂��B�����ĂQ�N�ォ��͏���ł̑��ł��\�肳��A�s���̕�炵�͂��������ǂ����܂�Ă������Ƃ����炩�ł��B�����炱���A��^�J���D��̎s���^�c�����߁A�s���̕�炵����������s���ɐ芷���Ă������Ƃ��K�v�ł��B�������A���ԈˑR�̂����̎g�����ɌŎ����A����Ȃ�s�s�v�擹�H�̌��݂��ł��o����A���w�Z���H������}���ّ����Ɩ��̖��Ԉϑ����A�s�m�L�I�c�����̖��Ԉϑ�������Ă����s���^�c�ł́A�s���̊肢�ɉ���������̂ł͂���܂���B����ē��{���Y�}�s�c�c�́A���Z�̔F��ɔ�������̂ł��B
�������璼���ɓP�ދ��߂�ӌ�������
�@������s�c��͂X��26���̖{��c�ŁA���{���Y�}�s�c�c�����c�����u�������璼���ɓP�ނ��A���q�͋K���ψ���l����P�邱�Ƃ����߂�ӌ����v���^�������ʼn��B�c�����Ő��{�ɑ��t����葱���ɓ���܂����B
�@�ӌ����Ɏ^�������̂́A��ĉ�h�̓��{���Y�}�S�l�Ɓu�݂ǂ�s���l�b�g�v�̂T�l�ɉ����āA�Ж��}�ɐЂ�u�����䐳���c���A�����}�̘I���N���c���̌v11�l�B�������̂́A�����}�̂S�l�Ǝ��Ђ낵�c���A�����Ė���}�̂R�l�̌v�W�l�ł��B�I���c�������������}�̂R�l�͑ސȂ��܂����B�����ꂽ�ӌ������ȉ��Ɍf�ڂ��A�����āA���̎^�����_���f�ڂ��܂��B
[�������璼���ɓP�ނ��A���q�͋K���ψ���l����P�邱�Ƃ����߂�ӌ���]
�@���{�́u�����錾�v�ɂ�������炸�A�d�厖�̂��N���������������͈ˑR�Ƃ��ĕ��ː��ʂ������A���܂Ȃ�16���l�]��̐l�X��������]�V�Ȃ�����Ă���B
�@�����������A���{���G�l���M�[�������̂��߂Ɏ��{�����ӌ�����(�p�u���b�N�R���� �g)�ł́A87���������[�������߂�ӌ����q�ׂĂ���B���̂��Ƃ͕����������̂̐[���� ���������d���~�߂Ă��邱�Ƃ������Ă���A���{�͂��̐��_��^���Ɏ~�߂邱�Ƃ����߂���B
�@�Ƃ��낪�A����}�̃G�l���M�[�E��������X���U���Ɏ��܂Ƃ߂��V���ȃG�l���M�[����Ɋւ���ł́A�u�����[���v�ɂ��āA�u�ғ����Ă��錴�����[���ɂ���v�ƈӖ��t���A�u��������̓P�ށv�m�ɂ͂��Ă��Ȃ��B�����ɂ��Ă��u2030�N��Ɍ����ғ��[�����\�Ƃ���悤�A�����鐭���𓊓�����v�Ƃ��Ă���A���m�Ȋ����Ƃ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B
�@���̏�ŁA�u���q�͋K���ψ���̈��S�m�F�����̂̂݁A�ĉғ��Ƃ���v�ƁA�ĉғ��e�F�̗���m�ɂ��Ă���B����ł͑��������[�������߂鈳�|�I�����̐��_�ɉ�������̂ł͂Ȃ��A����F�߂�����̂ł͂Ȃ��B
�@�܂����A���N�̖ҏ��ɕC�G���鍡�āA���䌧�E��ь����̍ĉғ������s�������d�͂ɂ��d�͎����̌��ʂ��ɂ����āA�����ĉғ��Ȃ��ł��d�͕s���͋N����Ȃ����Ƃ��A���d�͎��g�����\���������Ŗ��炩�ƂȂ����B�������A���d�͂̑�ь����ȊO�͌������P����������Ă͂��炸�A�d�͎��v�̃s�[�N���ł������A�����Ȃ��őS���I�ɓd�͂͑���Ă��邱�Ƃ��ؖ�������̂ƂȂ����B���̂��Ƃ́A�����ɗ���Ȃ��Ƃ��A�d�͎��v�͘d����Ƃ������Ƃł���B
�@�����������A���{�́A�X��19���Ɍ��q�͍s���̈��S�K����S�����q�͋K���ψ���̐l�����A�ψ���ݒu�@�Ɋ�Â���O�K���K�p���Ď����ŔC�������B�������A���q�͋K���ψ���̐l�������ƒf�ŔC�����邱�Ƃ́A�����ĉғ����肫�ŁA���_���������������\���ł���B
�@�������A���q�͋K���ψ���̊�Ԃ�́u���q�͎��Ǝғ��v��C�����Ȃ��Ƃ������ۏ��́u���i�v���v�ɊY������^���̂�����̂ł���A����ł͂܂Ƃ��ȋK���@�ւƂ͐��蓾���A�l�����̂��̂�����F�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@����āA������s�c��́A���{�ɑ��A�ȉ��̓_�����߂���̂ł���B
- ���{�����{���������I�����̌��ʂɏ]���A���䌧�E��ь������~���A�������璼���ɓP�ނ��邱�ƁB
- �����ŔC���������q�͋K���ψ���l����P�邱�ƁB
�@�ȏ�A�n�������@��99���̋K��ɂ��ӌ������o����B
�@���{���Y�}������s�c�c���\���āA�{�ӌ����ւ̎^�����_���s�Ȃ��܂��B
�@��N�R��11���̑�k�Ђɂ�镟�������̏d�厖�̂́A���{�́u�����錾�v�ɂ�������炸�A�����ɂ����Ă����˔\����˔\��тт���p����r�o���Â��A���܂Ȃ�16���l�]�̔����҂ݏo���Ă��܂��B��Ôg�ɂ��d���r���Ƃ������Ƃ��O�X����w�E����Ă����ɂ�������炸�A�u�z��O�v�Ō������̂��ЂÂ����悤�Ƃ��Ă��鍡���A���������{�����݂̂Ȃ炸�A�S���E�̐l�X���A����̏d�厖�̂���Ȃɂ��w�Ԃ̂��A�G�l���M�[����͂ǂ�����ׂ��Ȃ̂���^���ɍl���Ă������Ƃ����߂��܂��B
�@�Ƃ��낪���{�͕��䌧�E��ь����̍ĉғ������s���܂����B���R�́A�ď�̓d�͋������s�����邩��Ƃ̂��Ƃł��B�Ƃ��낪�A���d�͂�����z�[���y�[�W��Ō��\�����d�͎����ł́A���N�̖ҏ��ɕC�G���鍡�Ăł����Ă��A���d�͊Ǔ��̓d�͋����͓d�͎��v���\���ɏ���A��ь������ғ������Ƃ��A�Ȃ����ʂ�80��KW�̗]�T�����������Ƃ����炩�ƂȂ�܂����B���̂��Ƃ́A����܂ł̊��d�͂̐��������{�̐������A�����ɔ�������̂ł������Ƃ������Ƃł���A��ь����͂������ɉғ��𒆎~���ׂ��ł��B
�@�����̑命���́u�����[���v���������߂Ă��܂��B���{���G�l���M�[�������̂��߂Ɏ��{�����p�u���b�N�R�����g�ł�87���������[�������߂�ӌ����q�ׁA�S��11���ł̍������璼�ژb���ӌ������ł�68�����u�[���v�ƉA���_�^���_�����ł́A���_���̒����Łu�[���v��46.7���ƂȂ�܂����B�܂��A���T���j���̖�A���@�O�ł͐����l�K�͂̍R�c�s�����������Ă���A�}�X�R�~�����̖͗l�����������Ȃ��܂łɁA�����̑傫�Ȑ��_�ɔ��W���Ă��܂��B���{�͂��̐���^���Ɏ~�߂�ׂ��ł��B
�@�Ƃ��낪���{�́u�G�l���M�[�E����c�v���X��14���Ɍ��肵���u�v�V�I�G�l���M�[�E���헪�v�ł́A�u�����[���v�̊����ɂ��āu2030�N��Ɍ����ғ��[�����\�Ƃ���悤�A�����鐭���𓊓�����v�Ƃ���݂̂ŁA�u�����[���v�̊����Ƃ��Ă͂��܂�ɂ��x�����̂ƂȂ��Ă��܂��B�������A�����J�ɑ��āA����͂����܂ł��u�w�͖ڕW�v�Ɛ��������Ƃ̂��Ƃł��B�����ĂX��19���ɂ́A���̒x������u2030�N��Ɍ����[���v�荞�u�G�l���M�[�E���헪�v�ł���A�o�ϊE�ƃA�����J�̈��͂ɋ����Ċt�c�����������܂����B�����̌����[�����肤�������_�ɔw�����̂ƌ��킴������܂���B
�@�܂��A�X��14���Ɍ��肵���u�v�V�I�G�l���M�[�E���헪�v�ł́A�j�R���T�C�N������ɂ��āA�u���������]���̕��j�ɏ]���ď������ƂɎ��g�ށv�Ƃ��Ă���A�V���Ȋj�R�������肾�����ƂL���Ă��܂��B���̂��Ƃ́A����Łu�����[���v�����ɂ��Ȃ��炻�̎�����摗�肵�A�������������ɌŎ����闧����������̂ł���A�f���ċ�������̂ł͂���܂���B
�@���{�͂X��19���ɁA���q�͍s���̈��S�K����S�����q�͋K���ψ���̐l�����A�ψ���ݒu�@�Ɋ�Â���O�K���K�p���Ď����ŔC�����܂����B�����Ƃ͂����A�l���͏O�Q���@�̓��ӂ��Ȃ�����C���ł��Ȃ����̂ł���A��O�K����g�����ƂłȂ�������ɂ��邱�Ƃ͔F�߂�����̂ł���܂���B
�@���������̊�Ԃ���݂�ƁA���{���q�͌����J���@�\���������Ȃǂ��C�����l�����ψ����ɐ�����ȂǁA���������̂̒����ɑ�����l�����ψ�����ψ��ɂ��Ă���A�������i�@�ւ���Ɨ��������q�͈��S�K���s�����s�Ȃ��Ƃ�����|���`�[����������̂ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A�u���q�͎��Ǝғ��v��C�����Ȃ��Ƃ������ۏ��́u���i�v���v�ɂ��Y������^����������̂ł��B
�@���q�͋K���ψ���͔�������19���ɏ�����J���܂����B�L�҉�����ψ����́A���ݒ��̌����Ɋւ��āA�V�������S���K��������܂Ō��݂𒆒f���ׂ����ǂ���������ƁA�u�҂��҂��Ȃ����͓d�͉�Ђ̔��f�B�҂��Ȃ����Ƃ�������͂Ȃ��v�Əq�ׁA�͂₭���������i�̑��ɐg��u���Ă����l���Ƃ��Ă̕З��̂������Ă��܂��B���̂悤�Ȍ��q�͋K���ψ���l���͂������ɓP�ׂ��ł��B
�@���{���Y�}�́A���q�͔��d�Ɉˑ�����G�l���M�[��������߁A���z�����d�╗�́E���͔��d�ȂǁA���R�Đ��G�l���M�[����{�̃G�l���M�[����̊�{�ɒu�����Ƃ����߂�ƂƂ��ɁA�P���{�����ׂĂ̌������炽�����ɓP�ނ��鐭�����f���s�Ȃ��A�u���������[���v�̎������͂��邱�ƁB�Q�����ĉғ����j��P�A��ь������~�����A���ׂĂ̌������~�������܂܂ŁA�p�F�̃v���Z�X�ɓ��邱�ƁB�R�X���Z�������́u�ď����{�݁v������A�v���g�j�E���z�������瑦���P�ނ��邱�ƁB�S�����̗A�o����𒆎~���A�A�o���֎~���邱�Ƅ����������������߂���̂ł��B�ȏ�̂��Ƃ���A�{�ӌ����Ɏ^�����܂��B
�ʂ̍������z�H��
�@������s�c��̂��ݏ����{���ݓ��������ʈψ���͂V���S��(��)�A��ʌ��̊��ɂ���u�ʂ̍������z�H��v�̎��@�ɏo�����܂����B���̏ꏊ�ɂ͊�ƂW�Ђ����ꂼ��̎{�݂��\���A���̂����̂Q�̎{�݂����@���܂����B�ȉ��́A�����s�c��ɒ�o�������@���z���ł��B
�ʂ̍������z�H��̍s�����@���z��
 |
|
�I���b�N�X�����z��
|
�@��ʌ����A1989�N(�������N)�����ʌ��̍ŏI������Ƃ��āA�R��Ԃ�A��100ha�������甃���グ���Ƃ����ꏊ�Ɂu�ʂ̍��������H��v����ƂW�Ђɂ���Đݗ�����Ă���B����̍s�����@�́A���̂����́u�I���b�N�X�����z������Ёv�ɂ��u�T�[�}�����T�C�N���v�Ƃ����{�݂ƁA�u������ЃG�R�v��v�́u�������T�C�N���v�{�݂����w���邱�ƂɂȂ����B�u�I���b�N�X�v�̎{�݂ł́A������s���̎��Ǝ҂̎������݃S�~�������A�u�G�R�v��v�ł͍�N�܂ŁA������s�ʼn�����ꂽ�z�c���������܂�Ă����Ƃ����B
�@���҂́A�u���T�C�N���v�Ƃ����Ŕ��f�����A�u���T�C�N���v�̕����͑ǂ����ł���B�u�I���b�N�X�v�̎{�݂́A50�p�ȉ��̔p�����ł���Ȃ�ł������A2,000�x�̍����ň�u�ɂ��ėn�����A���ݎ���(�X���O)���������(���^��)�ȂǂɕԊ҂��čė��p���A���������K�X�͔��d�ɗ��p����Ƃ������́B����́u�G�R�v��v�́A�������܂ꂽ�p������O��I�ɕ��ʂ��čė��p�̓����ɏ悹��Ƃ������̂ŁA�ė��p�s�̂��̂́A�u�I���b�N�X�v�̂悤�Ɂu�T�[�}�����T�C�N���v(�ċp)�ŏ�������Ƃ����B���Ȃ�ɗv��ƁA�u�I���b�N�X�v�́A�R�₵�����ʁA�����������̂��ė��p����A�u�G�R�v��v�́A�ł��邾���g������͎̂g���Ă����Ƃ������́B�O�҂́A����23������B��҂́A�O���������Ƃ����Ƃ��납�B
 |
|
�G�R�v��
|
�@���������{�I�ɈقȂ邱�Ƃ���A�{�݂̊T�v�����R�ɈقȂ�B�u�I���b�N�X�v�́A�d�����ɕ����A�u�G�R�v��v�́A���i���Ƃ����X�^�C���B�d�����̕��́A���������ɑΉ��ł��錘�S�Ȑݔ���z�u���A���i���̕��́A�w�����b�g������Ȃ��قǂ̊T�v�B�������A���ꂼ��Ɂu���T�C�N���v�ɂ͂��邳���炵���A�����������o���̃p���t���b�g�ɂ́A�g�������������l�ҁh�Ƌ���ł���悤�B
�@�A��̃o�X�̂Ȃ��ł́A�ǂ���̃X�^�C�������������_����ꂽ�B�u�I���b�N�X�v�𐄂��O���[�v�́A�S�~�r�o���̎�ԃq�}�̖ʂ���ʂł̕]�������A�u�G�R�v��v�𐄂��O���[�v�́A���m��厖�ɂ���Ƃ����ϓ_�Ɩ{���́u���T�C�N���v�Ƃ����_�Ō��ꂽ�B���́A�{���I�Ɍ�҂ɑ����邪�A���ꂩ��̎Љ�́A�����炭�͑O�҂ɐi�ނ̂ł͂Ȃ����Ǝv����B
�@��ʌ��̕��j�͂ǂ��Ȃ̂��|�|�|�A���̂��Ƃ��A�A��̃o�X�̒��ł͋c�_�ɂȂ����B��ʌ��́A�X�^�C���̈قȂ��Ƃ�ׂ荇�킹�ɔz�u���A���ꂼ�ꂪ�u�䂱�������T�C�N���v�Ɩ��ł��Ă���B�����A��ʌ��́u�I���b�N�X�v�X�^�C�������C���ɂ��Ă���悤�Ɋ�����B�Ȃ��Ȃ�A���̂V��Ƃ́A���ł��P�ނł���u�ϑ��v�����ŗU�v����Ă��邪�A�u�I���b�N�X�v�̂݁A�o�e�h������20�N�Ԃ̎��Ƃ��`���Â����Ă��邩��ł���B
�@�قȂ�����́u���T�C�N���v�B�����ɂ́A�֗����Ƃ͉����A���T�C�N���Ƃ͉����A�u�n���ɂ₳�����v�Ƃ͉����w���Č����̂��A���̂��Ƃ����k���ꂽ�`�ŁA�������ɖ₢�����Ă���悤�Ɏv����B�����́A����B����Ȃ��Ƃ��l���邤���ɁA�o�X�͏�����s�̊X���ւƓ����čs�����B
�����ق̐ݔ��E���i���̏[����
�@������s���u���U�w�K����̎{�݁v�Ɉʒu�Â��Ă�������فB�������A�{�݂�ݔ��E���i�̘V�������ڗ����A�Ⴊ���҂����p���₷���悤�ɂ���o���A�t���[�̑Ή����s�\���ȏ�Ԃł��B
 |
|
�{���{���̃J�}�h
|
�@���͂U���c��̈�ʎ���ŁA���đւ��v�悪������Ă�������ٖ{�ق������A�n��̌����ق̌�����q�ׁA����������߂܂����B
�@�Z���^�[�ł́A�����ٌ����̈�p�ɂ���o�[�x�L���[�{�݂̃J�}�h���{���{���ɂȂ��Ă���A�ؐ��̒�����̍����͕����āA�O���O�����Ă��܂��B���|�q�͒ʏ�A�ϗp�N����10�N����20�N�̂Ƃ�����A���ł�21�N���o�߂��A���т��уg���u�����������Ă��܂��B
�@���Z���^�[�ł́A�u�G���x�[�^�[�̐ݒu���v�̐������Ă��܂��B����́A�K�i�̒[�����Ɍ�t���̏��~�@�����t�����Ă��܂����A�i���Ɏ��Ԃ������邽�߂ɁA�g�����肪�����Ƃ̐����������Ă��܂��B
�@�{�����قł́A�u�g�C���̏L�C�v�ւ̋������o����Ă��܂��B�{�����ق͍�N�x�A�ϐk�⋭�H�������{����܂������A�g�C���̉��C�H���͍s�Ȃ��܂���ł����B
�@�ш��Z���^�[�́A�쑤�ɖ��ԏZ��אڂ��Ă��邽�߁A�Q�K�̓쑤���̖h�����߂��Ă��܂��B�܂��A�����o���̃G�A�R���͒��q�������A�����������K�v�ƌ����Ă��܂��B
 |
|
�Ԉ������ꂽ�u����
|
�@�����ق͔��i���̗\�Z���N�X�팸����A����֎q�̕s��A�u�ߓd�v�������Ƃ����u������Ɩ����̊Ԉ����A�g�C���b�g�y�[�p�[���M���M�������p�ӂł��Ȃ��Ƃ������Ԃł��B
�@���ق������U�w�K�����́u�\�Z�v�������Ă��A�������������Ȃ��ł́A�v���������̂��S�ė\�Z���������̂ł͂Ȃ��v�ƒ��ߊ�B������S�����镔���́u����ꂽ�����͌��ʓI�A�����I�Ȕz���ɓw�߂Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Əq�ׂ�݂̂ł��B
�@���̏�����s�B���H�g�����i�̗\�Z��g�݁A��������w�k���̋�搮�����Ƃɂ́A���N�x�����ł�13��7,300���~��\�Z�����Ă��܂��B
�@����A�����ّS�̂̍��N�x�̏C�U��E���i��E���Օi��̗\�Z���v�z�́A668���T��~�ɉ߂��܂���B�����̎g�������A���������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�s�����Q�̐H�i�̕��˔\�������������
�@������s�ł́A�s�������ׂĂق����Ǝ������H�i�̕��ː��ʂׂĂ���鐧�x��20�N�]�ɂ킽���đ����Ă���B�H�i���̃Z�V�E��134����уZ�V�E��137�̔Z�x�𑪂�Ƃ������̂ŁA�`�F���m�u�C���������̌�Ɏs���̉^����1990�N�X�����琧�x�����ꂽ���́B�����Ƃ́A������s����ϑ����ꂽ�u������s���˔\�����^�c�A�����c��v���s�Ȃ��Ă���B
�@���莖�Ƃ����߂Ă���22�N�B���̊ԁA���˔\�����͂����̈�x���V�����ꂸ�A�N�ɂR�`�S����x�̃����e�i���X�ł��̂��ł����B�������A��N�R���̑�k�Ђɂ�镟�������̕��˔\�����Ȍ�A�s������̐H�i�̔Z�x����˗����}�����A���܂ł͑��肵�Ă��炦��܂łɂP�J���҂��Ȃ��ƂȂ�Ȃ��قǂɍ��ݍ����Ă���B�������A�����͘V�����̈�r�����ǂ��Ă���B
�@��k�Јȍ~�A�c��ł͑����̐V�������߂�ӌ����A�䂪�}�܂߂ďo����Ă���B������������s�́u�������������v�𗝗R�ɗ\�Z�������Ԃ�A�����ɂ������Ă����ڂ���I�ڂ̃��h�͂����Ă��Ȃ��B
�@����Ȑ܁A����Ғ����珬����s�Ɂu���˔\�����̑ݗ^����v�̒ʒm���͂����B��N12��26���t�ŏ�����s�����o�ωۂ��A�V�����������˔\�����̂��Ƃ��܂Ƃ��āA�ݗ^�肢��\�����Ă������Ƃ��F�߂�ꂽ�̂ł���B
�@�Ƃ��낪�A�����ɂ��āA�o�ωۂ̈Ӑ}�Ƃ͕ʂ̕����Ɏ��Ԃ͗��ꂽ�B�ݗ^����鑪����V�������������̂��Ƃ��܂Ƃ��āA�ϑ���̏�����s���˔\�����^�c�A�����c��ɓn�����̂ł͂Ȃ��A�s�̒n����S�ۂ��Ǘ����A�ً}�ٗp�n�o���Ƃō̗p�������Ώ����E���ɁA�����Ƃ��ς˂�Ƃ����̂ł���B�悤����ɁA�ϑ���Ŏg�p����̂ł͂Ȃ��A�s�����ځA�g�p����Ƃ����̂ł���B
�@���ꂾ���Ȃ�A�ϑ��悾�낤���A�s�����ڍs�Ȃ������A���͂Ȃ��悤�Ɏv���B�Ƃ��낪�A������s�̎茳�ɓ͂�������Ғ�����̑����ł́A�����w�Z�ƕۈ牀�̋��H�H�ޓ��͑��肷����̂́A�s�����������H�i�͑��肵�Ȃ��Ƃ����B�s���͈��������A�ϑ���̏�����s���˔\�����^�c�A�����c��ő��肵�Ă��炦�Ƃ����̂ł���B�������A���̑����͘V�������A�c���͐V�������߂�ӌ������Ă���B
�@�u��ꂽ��ǂ�����̂��v�Ƃ̂U���c��ł̎���ɑ��āA������s�́u���̎��ɍl�������v�Ƃ����n���B�����Č�����̂́A����킪��ꂽ�i�K�Łu�ϑ������v�Ƃ����}���B���̎��_�ŁA���N�A������s���S���Ɍւ��Ă����u�s�������Q����H�i�̕��ː��ʂ̑�����s�Ȃ��v�Ƃ������Ƃ͖������낷���ƂɂȂ�B
�@�ϑ��ł���s���c�ł���A�s���̕s���ɉ����鐧�x�͌������ׂ��ł���B���́A���̂��Ƃ������咣����B
�N���}�{�T���p�~�ŕۈ痿���啝�A�b�v
�@�u�N���}�{�T���v�Ƃ����̂����������낤���B���c�Ǝ҂��X�s�c��c���Ȃǂ����N�R���̊m��\���̍ۂɋL������m��\�����ɂ́u�}�{�T���v�ƋL����A�T�����[�}���̔N�������p���ɂ��A���̕������L����Ă���B
�@�u�N���}�{�T���v���ו�������ƁA�O����15�܂ł��u��ʕ}�{�T���v�A16����18�܂ł��u����}�{�T���v�ƌĂсA�����ŁA�Z���ł��ꂼ��ɁA�Ŋz�T���̖������ʂ����Ă���B
�@���́u��ʕ}�{�T���v����N���珊���łŁi���c�Ǝ҂Ȃǂ̏ꍇ�͍��N�R���̊m��\����ɔ[�߂鏊���ł���j�p�~����A�u����}�{�T���̉��Z�z�v�������ɔp�~���ꂽ�B�܂��A���N�U������͏Z���ł́u��ʕ}�{�T���v�Ɓu����}�{�T���̉��Z�z�v���p�~����A�����ł͍�N����i���c�Ǝ҂Ȃǂ͍��N�R���̊m��\����ɔ[�߂鏊���ł���j�A�Z���ł͍��N�U������A�Ŋz���A�b�v�����B
�@���̂��Ƃ��ؖ�����悤�ɁA���̏����ł̊m��\����������ƁA2010�N���ł͖��̈�ʕ}�{�T����38���~�A���q�̓���}�{�T����63���~(���Z�z�܂�)�ƂȂ��Ă����̂��A2011�N���ł́A���q�̓���}�{�T���݂̂̋L�ڂƂȂ��Ă���B�������A���Z�z25���~���p�~���ꂽ���߁A�T���z��38���~�ł���B
�ł́A�N���}�{�T���̔p�~�ɂ���āA�N�Ԃ̐Ŋz�͂ǂꂭ�炢�A�b�v�����̂����������B�����ł́u��ʕ}�{�T���v�̔p�~��38���~�A�u����}�{�T���̉��Z�z�v�̔p�~��25���~���u�}�{�T���v����r������A���ɏ����ł�10���ł������ꍇ�́A�u��ʕ}�{�T���v�̔p�~�łR���W��~�A�u����}�{�T���̉��Z�z�v�̔p�~�łQ���T��~������(�N�z)�ƂȂ�B����A�Z���łł́u��ʕ}�{�T���v�̔p�~��33���~�A�u����}�{�T���̉��Z�z�v�̔p�~��12���~���u�}�{�T���v����r������A�Z���Ŋz�͈ꗥ10���Ȃ̂ŁA�u��ʕ}�{�T���v�̔p�~�łR���R��~�A�u����}�{�T���̉��Z�z�v�̔p�~�łP���Q��~�̑���(�N�z)�ƂȂ�B
�@�N�z�ł��ꂭ�炢�Ȃ�����������Ƃ͂Ȃ��ƁA�v����������Ȃ��B�������A�N���}�{�T���̔p�~�ɂ���āA�F�ۈ牀�̕ۈ痿�Ə�����s���̊w���ۈ痿�ɉe����������̂ł���B
�@�܂��A�ۈ痿���猩�Ă݂悤�B�啔���̐��т̕ۈ痿�̌v�Z�����́u�O�N���̏����ʼnېŐ��т̏����Ŋz(�N�z)�v�ƂȂ��Ă���B������s�̏ꍇ�A���̕������u�c�v�K�w�ƌĂсA�����Ŋz�̒Ⴂ������u�c�P�v�u�c�Q�v�u�c�R�v�Ƃ�����ɁA�����Ŋz�̍������ւƊK�w���㏸���Ă����B���́u�c�v�K�w�̊e�敪�́A�����Ŋz(�N�z)�������悻�R���~�̕��ł������Ă���A�Ⴆ�A�K�w�敪�u�c�U�v�̏ꍇ�́u�X���~�ȏ�A12���~�����v�A�u�c11�v�̏ꍇ�́u24���~�ȏ�A27���~�����v�Ƃ�����ɂł���B�Ƃ��낪�A�u�R���~���̏����Ŋz�ŊK�w�敪���݂����Ă���v�Ƃ������Ƃ��A�ȉ��̂悤�Ȏ��Ԃ����炽�����ƂɂȂ����B
��q�����悤�ɁA�N���}�{�T���̔p�~�ɂ���āA��ʕ}�{�T����38���~�Ɠ���}�{�T���̉��Z�z25���~�������ł̕}�{�T������r������A���ɏ����ł�10���̏ꍇ�ɂ́A��ʕ}�{�T��(38���~)�̔p�~�ň�l������R���W��~�A����}�{�T���̉��Z�z(25���~)�̔p�~�ň�l������Q���T��~�������Ŋz�̃A�b�v�ƂȂ��Ă����B��ʕ}�{�T���ɊY�����Ă����q�ǂ����P�l�����ł��A�����Ŋz���R���W��~�A�b�v�ƂȂ�A���ꂾ���ŕۈ痿�̊K�w�敪�͂P�敪�㏸����B����ɓ���}�{�T���̊Y���҂��P�l�����A���Z�z�p�~�ɂ���ĂQ���T��~�̏����Ŋz�A�b�v�ƂȂ邽�߁A��C�ɂQ�敪�㏸�ƂȂ�B�敪���㏸����ƁA�ۈ痿�͒��ˏオ��̂ł���B
�@�ۈ痿�̒��ˏオ��́A�F�ۈ牀�ɒʂ��Ă��鉀�����ꂼ��ɂ������Ă���B�Ⴆ�A�Q�l�̉������ʂ��Ă���A���q�����q���ۈ痿�͒��ˏオ��̂ł���B�܂������A�_�u���p���`�ł���B����āA�����Ŋz�ŕۈ痿���v�Z�����u�c�v�K�w�́A�قƂ�ǂ̐��т��Œ�ł��P�����N�A�ň��̏ꍇ�ɂ͂Q�`�S�����N�A�K�w�敪���㏸�������̂ƍl������B
�@���ۂɁA�ǂꂭ�炢�e���z�������������낤���B���{���Y�}�s�c�c�̋c���̂��ƂɊ�ꂽ���[�����Љ�悤�B�u�䂪�Ƃɂ́A�q�ǂ����S�l���܂��B��ԏオ���w�P�N���̒����B�������w�Q�N���̒��j�B�����Ďs���ۈ牀�ɒʂ��Q�̑o�q�̎��j�A�O�j�ł��B���j�̕ۈ痿�ł����A�c�U�i�K���獡�N�x�͂c13�i�K�ւƌ��z24,500�~�オ��A�O�j�̕������킹��ƁA���z26,350�~����62,900�~�֑��B��N�Ɣ�ׂĖ���36,550�~�̕��S���ƂȂ�܂����B��N�ł�43��8,600�~�ɂ��Ȃ�܂��v�B���ɁA�[���ł���B
�@�w���ۈ痿�͗��N�x����e������������B�u�O�N�x�̎s�������ł̉ېŕW���z�v�Ō��܂邩��ł���B�O�q�̂悤�ɁA�s�������ł̃A�b�v�͍��N�x����ł���B����āA�w���ۈ痿�ւ́A���N�x����ƂȂ�B�������A������s�̊w���ۈ痿�́u�ېŕW���z�v�K�w�敪�̋��z���͍L�����߁A�u�e�����鐢�т́A���������͂Ȃ��v�Ǝs�̒S�������͏q�ׂĂ���B
�@�啝���S���ƂȂ�ۈ痿�B����ł͐��������藧���Ȃ��Ȃ�A�ۈ痿��ؔ[���鐢�т��}�����邱�Ƃ��\�������B���̂��Ƃ�J���������J���Ȃ͍�N�V���A�s���{���m����ߎw��s�s�s�����ĂɁA�ʒm�����������B�����J���Ȃ̌ٗp�ϓ��E�����ƒ�ǒ����ɂ��u�T���p�~�̉e�������p�������x���ɌW��戵���ɂ��āv�Ƃ������̂ŁA�e�����̂ɂ������āu�}�{�T���������O�̋��Ŋz���v�Z���铙�ɂ��A�}�{�T���̌������ɂ��e�����\�Ȍ��萶�������Ȃ��悤�Ή������肢����v�Əq�ׂĂ���B�����Ēʒm�����ł́A���̎w���́A���{�Ő�������́u�T���p�~�̉e���ɌW��v���W�F�N�g�`�[���v�̕��j�ɂ��ƂÂ����̂Ƃ���Ă���B
�@�ł́A�Ȃ�������s�ł͕ۈ痿�����N�x����啝�A�b�v�ƂȂ����̂��B�����ɂ́A��t�F�F�s���́A�ۈ痿��������_��������݂������Ă����B
�@�T��21���̎s�c����������ψ���œ��{���Y�}�̐���Ђ낵�c�����A�����J���Ȃ̒ʒm�ɂȂ��]��Ȃ������̂��Ɩ₢���������Ƃ���A��t�F�F�s���́u(12�N�O��)�ۈ痿��l�グ�������ɔN���}�{�T������������A�ۈ痿���z�������Ȃ������B���̂��ߍ���A�ʒm�ɂ��ƂÂ����[�u�͂Ƃ�Ȃ������v�Ɠ��فB12�N�O�̕ۈ痿����œ���͂����������������m�ۂ��邽�߂ɁA�����J���Ȃ̒ʒm�ɏ]��Ȃ������Ƃ����̂ł���B
�@�U�����s�c��̎��̈�ʎ���i�U���V���j�ł́A������s�̗��s�s�ȑΉ��̂���������炩�ƂȂ����B�V�����{�̌����J���Ȃ���́u�e������v�̒ʒm������c������������s�́A�ۈ�ۓ����őΉ������c�B��t�F�F�s���ȂǗ����҂̈ӌ����������Ȃ�����A�e�����[�u���Ƃ�Ȃ����Ƃ��u�ۈ�ۓ����Ŕ��f�����v�Ƃ����̂ł���B���قł́u�e�s�̏����Ȃ���Ή������v�Ƃ������A�e�����[�u���Ƃ�Ȃ������̂́A�O�����ł͏�����s�ƎO��s�A�s�s���ł͏a�J��̌v�R�����݂̂̂ł���B
�@��q�����悤�ɁA�ۈ痿�K�w�敪����C�ɂc�U�i�K����c13�i�K�ւƒ��ˏオ�������т��o�Ă���B�u�K�w�敪���㏸���邱�Ƃ͏��m���Ă����v�ƒS�������͏q�ׂ����A�ł͂Ȃ��A����قǂ܂łɑ傫�ȉe������������̂�ۈ�ۓ����Ŕ��f���ĉ��[�u���Ƃ�Ȃ����Ƃɂ����̂��B�������A�ӔC�̏��݂m�ɂ����u�N�ď��v�Ƃ����`���Ƃ炸�A�s�����ق��u���Ă͂��Ȃ��v�Ƃ����̂ł���B
�s���E���s���E���璷�E�e�����ō\�������u���c�v�ɂ͎������̂��H���������B���ق́u�R�����s�c��̌��������ψ���ɕ���O�́A�Q��28���̒��c�Ɏ������v�Ƃ̂��ƁB����́A�u���������ψ���ł́A���̂悤�ɕ��܂���v�Ƃ������̂ł���A�u�e������̑[�u���Ƃ邩�ǂ����v�̋c�_���s�Ȃ����߂̂��̂ł͂Ȃ��B
�@����̕ۈ�ۂ̑Ή��̂��������сA�ӌ���ۈ�ۂ��狁�߂�ꂽ�s���̑Ή��̂�������A������s�́u�������ًK���v�ɂ��u���c�Ɋւ���K���v�ɂ����m�ɔ�������̂ƌ��킴��Ȃ��B
�@������A�Ή��̎d���Ƃ��Ė�肪����̂́A������s�̎��������R�c��Ɏ����Ă��Ȃ����Ƃł���B���������R�c��́A���������@��56���R���̋K��ɉ����āA�ۈ痿�ɂ��������ɑ��Ĉӌ����������@�ւɈʒu�t�����Ă���B���̂��Ƃ��ؖ�����悤�ɁA������s�̎��������R�c��K���ł��u�s���̎���ɌW��ۈ�y�ъw���ۈ瓙�Ɋւ��鎖���ɂ��Ē����R�c����v�Ɩ��L����Ă���B�����J���Ȃ̒ʒm�ɉ���Ȃ��Ή����Ƃ�Ƃ����ꍇ�ɂ����Ă͕ۈ痿�ւ̉e���������邱�Ƃ���A���������R�c��Ɉӌ����������͓̂��R�̂��Ƃł���B���̓_�ł��A�S���ۂ���юs���̑Ή��͒f�߂����ׂ����̂ł���B
�@�s���́u���s�̐��x�ł������Ă��������v�Əq�ׁA�ۈ痿�̑啝�A�b�v�ɋꂵ�ގs���̐��ɂ��A�e����������߂������J���Ȃ̊肢�ɂ��w��������ԓx���������B�u�e������v���s�Ȃ�Ȃ��������Ƃ���A������s�̕ۈ痿�����z�͑O�N�x��Ŗ�3,400���~(�N��)�̑����ɂȂ�Ƃ����B����A�Q���Ɏ擾�������s���𗬃Z���^�[�̍��N�x�̎w��Ǘ��ϑ����͂Q��3,100���~�ł���B�����̎g�������W�߂������A���̐������l�ɘc��ł���B
�@�@���U���V������ʎ���Ŏg�p�������e���o�c�e�t�@�C���Ōf�ڂ��܂��B
���݊��ψ���@�A���{�s�E�ѓc�s
 �@�T��16��(��)�E17��(��)�̂Q���ԁA������s�c��݊��ψ���͐M�B�̏��{�s�Ɣѓc�s�֍s�����@�ɏo�����܂����B���{�s�͏��{�鉺�́u�܂��Ȃ݊��������Ɓv�A�ѓc�s�́u���z�����d���Ɓv�ł��B���@�̊T�v�E���z�́A�ʋL�����Q�Ƃ��������B �@�T��16��(��)�E17��(��)�̂Q���ԁA������s�c��݊��ψ���͐M�B�̏��{�s�Ɣѓc�s�֍s�����@�ɏo�����܂����B���{�s�͏��{�鉺�́u�܂��Ȃ݊��������Ɓv�A�ѓc�s�́u���z�����d���Ɓv�ł��B���@�̊T�v�E���z�́A�ʋL�����Q�Ƃ��������B
�@���{�s�͌��킸�ƒm�ꂽ���쌧�B������s����������ꍇ�͈�ʓI�ɁA�����{���u���������v�𗘗p���܂��B�Ƃ��낪��X�ɂ��Ă���ꂽ�̂́u�}�C�N���o�X�v�B������s���珼�{�s�܂Łu�o�X�ōs���I�v�Ƃ����̂��A�s�c����ǂ���������ʎ�i�ł����B
�@�u����Ⴀ�A���邼�E�E�E�v�ƁA�������ĎႭ���Ȃ���s�͑O�r���Ă��Ȃ���o�X�ɏ�ԁB�{�����璆�������ԓ��ɓ����āA��H�A�M�B�ցB�K���ɁA���̏ꍇ�͓����̍s�Ȃ����ǂ��������炩�A�V�C�͉����B�������Q����l�����Ȃ��قǂɁA�o�X�̎ԑ����猩������͂̌i�F�ɂ��������E�b�g���Ƃ�������B�G�߂͐V�B�������R���ɓ���ƃA���v�X�̎R�X����������ƌ����A�����x��b���x�����������}���Ă���܂����B�u�o�X���Ȃ��Ȃ������킢�v�ƁA�������育���x�B�r���A�k����Ɛz�K�̃T�[�r�X�G���A�ɗ������A�R�[�q�[�Ȃǂ����ɉ^�тȂ���A�܂䂢�i�F�Ɍ�����܂����B
 �@���{�s�͎��ɂƂ��ẮA�����炭20���N�Ԃ�B�c���ɂȂ��Ă���͏��߂Ă̂��Ƃ��Ǝv���܂��B���̂��߁A�v���`���Ă������o�Ƃ͈قȂ��Ă��܂����B�g�X���͈ӊO�ƁA������܂�Ƃ��Ă���ȁh�g���{����āA����Ȃɏ��������������H�h�ƁB�܂��A���J�q�w�Z�����{�邩��߂����Ƃ��A�C���[�W�Ƃ͈قȂ��Ă��܂����B�鉺���ɍ��킹���u�܂��Â���v���i�s���̏��{�s�́A�Ԃ��ƕ����Ă݂����Ȃ�A����邽�����܂��������Ă��܂����B �@���{�s�͎��ɂƂ��ẮA�����炭20���N�Ԃ�B�c���ɂȂ��Ă���͏��߂Ă̂��Ƃ��Ǝv���܂��B���̂��߁A�v���`���Ă������o�Ƃ͈قȂ��Ă��܂����B�g�X���͈ӊO�ƁA������܂�Ƃ��Ă���ȁh�g���{����āA����Ȃɏ��������������H�h�ƁB�܂��A���J�q�w�Z�����{�邩��߂����Ƃ��A�C���[�W�Ƃ͈قȂ��Ă��܂����B�鉺���ɍ��킹���u�܂��Â���v���i�s���̏��{�s�́A�Ԃ��ƕ����Ă݂����Ȃ�A����邽�����܂��������Ă��܂����B
 �@�h���n�́A�o�X�ňɓߒJ��쉺������̔ѓc�s�B�u�J�v�ƌĂԂɑ��������o���̎R���ڋ߂����ꏊ������A���͂��L���ꏊ������A�ɓߒn���͓Ɠ��̕��͋C���������o���Ă��܂����B�r���A��x�T�[�r�X�G���A�ɂċx�e�B����������x��T�����A�ǂꂾ���킩�炸�B�r���c���́u�ē��Ŕ��������ǁA��������͌����Ȃ��炵�����v�ƌ����܂��B�Ȃ�A�Ȃ�Łu��x�T�[�r�X�G���A�v���Č������������H�B���X�Ŕ������݂��ق���Ȃ���A����Ђ˂�n���ł����B �@�h���n�́A�o�X�ňɓߒJ��쉺������̔ѓc�s�B�u�J�v�ƌĂԂɑ��������o���̎R���ڋ߂����ꏊ������A���͂��L���ꏊ������A�ɓߒn���͓Ɠ��̕��͋C���������o���Ă��܂����B�r���A��x�T�[�r�X�G���A�ɂċx�e�B����������x��T�����A�ǂꂾ���킩�炸�B�r���c���́u�ē��Ŕ��������ǁA��������͌����Ȃ��炵�����v�ƌ����܂��B�Ȃ�A�Ȃ�Łu��x�T�[�r�X�G���A�v���Č������������H�B���X�Ŕ������݂��ق���Ȃ���A����Ђ˂�n���ł����B
�@�h�́A���فB���O�ɃC���^�[�l�b�g�ł��̗��قׂ��Ƃ����O�q�̂r���c���́A�u������10���~�������v�ƌ����܂��B�u���فv�u10���~���v�Ƃ������Ƃ���N�����l�����̂́A�u����͒N�ƈꏏ�̕����ɂȂ�̂��낤���E�E�E�H�v�B���̔]���ɂ͉��l���̋c���̊炪�����сA�C�r�L���������l�Ȃ�ǂ��̂����ƁA�o�X�̒��ň�l��l��i��߂��鎖�ԂɁB�����炭�A���̋c�������l�Ȃ��Ƃ��l���Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�Ƃ��낪�c����ǐE���̂s�����́u��l�ꕔ���ł��v�ƌ����B�ցH�A10��Ɉ�l�H�B����Ȃ̏��߂Ă��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��e�l���v���Ȃ��痷�قɓ����B�Ƃ��낪���ق̒��ԏ�ɂ͑�^�ό��o�X���S�����܂��Ă��܂����B����A���ق͂���Ȃɑ傫���͂���܂���B�g����Ⴀ�A�\����Ȃ����Ƃ������B��X��10���l���ŁA���̒c�̂����10��ɂ����l�ߏ�Ԃł͂Ȃ����h�B�Ƃ��낪�A�c�̂���͂����ɂ͔��܂��Ă��Ȃ��Ƃ����܂��B�u���k�����͔_�Ƃ̑̌��w�K�̂��߁A�����Ƀo�X���߂āA�_�Ƃɖ��h���Ă��܂��v�B���ق̐l�͂��������āA��������l��l�ɕ����̃J�M��n���܂����B
 �@���͓͂c��ڂƔ��A�����ĎR�B���n������A�X�͂���܂���B�O�Ɉ��݂ɍs�����ɂ��A�ړI�n�͌����܂���B��A���͈͂Èłɂǂ��Ղ�Ƃ���A�z�c�ɓ��������������P�����̂́A�C�r�L�ł͂Ȃ��J�G���̑升���ł����B �@���͓͂c��ڂƔ��A�����ĎR�B���n������A�X�͂���܂���B�O�Ɉ��݂ɍs�����ɂ��A�ړI�n�͌����܂���B��A���͈͂Èłɂǂ��Ղ�Ƃ���A�z�c�ɓ��������������P�����̂́A�C�r�L�ł͂Ȃ��J�G���̑升���ł����B
�@�o�����ꏊ���Ȃ��A�\�����ʏn�����ʂ������������͗���(17��)�A�}�C�N���o�X��20���]�̔ѓc�s�����֏o�����܂����B���̔ѓc�s�A���ɕs�v�c�Ȓn�`�����Ă��܂��B�����Ɛ����Ƃɋu��u���A���̊Ԃɂ͒J��݂����ɐ삪�����B���������̐�̗����ɂ��A�u�̏�ɂ��X���`������A�u����Ȃ��炩�ɌX���̂ڂ��Ă����ƎR�ɂ��ǂ蒅���Ƃ�������悤�B�u�͊ݒi�u�v�Ƃ������t���A�ѓc�s�̐E�������ɂ��܂����B���w�⍂�Z�̒n���̎��ԂɎ��ɂ����P�ꂪ�A���\�N�Ԃ肩�Ɏ��ɔ�э���ł����̂ł��B
 �@�E���������ɂ́A�ѓc�s�����͕W��550���[�g���̋u�̏�Ɉʒu���A�J��̂悤�ȉ����ɗ�����͕W��300���[�g���̓V����B�Ƃ������Ƃ́A�ѓc�s�����̂���u�ƓV����Ƃ̕W������250���[�g���Ƃ������ƁB����Ȃɂ��邩���ȁA�Ɣ��M���^�ł͂�����̂́A��͂������ɂ͂邩�����𗬂�Ă��܂��B�ѓc�s����������V������͂���Ŕ��Α��̋u������ƁA�����瑤�Ɠ������炢�̋u�̍����ƂȂ��Ă��܂��B���Â̐̂́A�����̋u�͂Ȃ����Ă����̂��낤�ȂƁA�n�`�̂������낳�ɋ����͐s���܂���B �@�E���������ɂ́A�ѓc�s�����͕W��550���[�g���̋u�̏�Ɉʒu���A�J��̂悤�ȉ����ɗ�����͕W��300���[�g���̓V����B�Ƃ������Ƃ́A�ѓc�s�����̂���u�ƓV����Ƃ̕W������250���[�g���Ƃ������ƁB����Ȃɂ��邩���ȁA�Ɣ��M���^�ł͂�����̂́A��͂������ɂ͂邩�����𗬂�Ă��܂��B�ѓc�s����������V������͂���Ŕ��Α��̋u������ƁA�����瑤�Ɠ������炢�̋u�̍����ƂȂ��Ă��܂��B���Â̐̂́A�����̋u�͂Ȃ����Ă����̂��낤�ȂƁA�n�`�̂������낳�ɋ����͐s���܂���B
�@�ѓc�s�����̂�����͂��̐́A�ѓc��̏鉺���Ƃ��ĉh�����ꏊ�B�Ƃ������Ƃ́A�隬������͂��ł��B���@���I�����A���H��̃}�C�N���o�X��Ԃ܂Ŏ��Ԃ����邱�Ƃ���A���H���I�������͏隬������ׂ��u�܂��Ȃ��T���v�����s�B�ό�����ŋ����Ă�������隬�܂ł̂��₩�ȍ�������Ă����܂����B
 �@�隬�Ƃ͂������̂́A�Ƃ��ɍH�v���ꂽ�ē���z�u���Ă���킯�ł��Ȃ��A���̂����肪�隬�ł���A�Ƃ������x�ł��B�O�q�����悤�ɁA���̂�����͋u�̏�B�������ѓc��́A�V����̓���ɓ˂��o�������̂悤�ȋu�̐�[�����Ɍ��Ă��Ă������߁A�隬�̒��S�Ɍ������ĉ����Ă������Ƃ́A�u�̍��E�̕�������ɋ��܂��Ă����Ƃ�����B�悤����ɁA�E���݂Ă������݂Ă��A����200���[�g���]�̒f�R��ǂ��҂��\���Ă���Ƃ������Ƃł��B�����̓r���ɂ͐}���ق���j�I�������Ƃł����������Ȍ����̏��w�Z�A�����߂��炵�����p�قȂǂ�����A�����ɂ��̂͏�̕~�n���������Ǝv���邽�����܂��ł��B�u�̐�[�ɂ͐_�Ђ�����A��������͎O���ʂɌ��n����A���Ȃ��̌i�F������܂����B �@�隬�Ƃ͂������̂́A�Ƃ��ɍH�v���ꂽ�ē���z�u���Ă���킯�ł��Ȃ��A���̂����肪�隬�ł���A�Ƃ������x�ł��B�O�q�����悤�ɁA���̂�����͋u�̏�B�������ѓc��́A�V����̓���ɓ˂��o�������̂悤�ȋu�̐�[�����Ɍ��Ă��Ă������߁A�隬�̒��S�Ɍ������ĉ����Ă������Ƃ́A�u�̍��E�̕�������ɋ��܂��Ă����Ƃ�����B�悤����ɁA�E���݂Ă������݂Ă��A����200���[�g���]�̒f�R��ǂ��҂��\���Ă���Ƃ������Ƃł��B�����̓r���ɂ͐}���ق���j�I�������Ƃł����������Ȍ����̏��w�Z�A�����߂��炵�����p�قȂǂ�����A�����ɂ��̂͏�̕~�n���������Ǝv���邽�����܂��ł��B�u�̐�[�ɂ͐_�Ђ�����A��������͎O���ʂɌ��n����A���Ȃ��̌i�F������܂����B
�@�ēx�A���{�s��ѓc�s�ɗ���Ƃ�����ǂ��炪�����H�ƕ����ꂽ��A�����Ɩ������Ƃł��傤�B�n�`�̂������낳��Â��Ȃ������܂��Ȃ�A�ѓc�s���B��Ə鉺���̕���𖡂키�Ȃ�A���{�s�����������B�}�C�N���o�X�͐���n�����T���̈ɓߒJ���A�������Ə�����s�ւƑ���͂��߂܂����B
�@�ȉ��ɁA�s�c��ɒ�o�������@���z�����f�ڂ��܂��B����ǂ���������A�K���ł��B
���݊��ψ���s�����@���z��
[���{�s�E�܂��Ȃ݊���������]
 �@�u���{�s�v�ƌ����Α��A�u���{��v�Ǝ��͓�����B�ʖ��u�G(���炷)��v�Ƃ��Ă�A���{�ŌÂ��ւ鍕�F�̍���d�V��́A���{�s��K���l�Ȃ炾������ڂɂ�����j�I�������ł���B���킹�āA���{�s�ɂ́u���J�q�w�Z�v������B1876�N����1964�N�܂ŏ��w�Z�Ƃ��Ďg���Ă����[�m�����z���ŁA���̏d�v�������Ɏw��B���{�邩��͓k���V�����x�̂Ƃ���ɂ���B�����x�̎҂ɂ��A���ꂭ�炢�̒m����A�����ނقǂɏ��{�s�͗L���ł���B���̏��{�s���n�揤�Ɛ��ނ̊�@���}���A�u�܂��Ȃ݊��������Ɓv�Ɏ��g�Ƃ����̂�����A���X�����Ă���B �@�u���{�s�v�ƌ����Α��A�u���{��v�Ǝ��͓�����B�ʖ��u�G(���炷)��v�Ƃ��Ă�A���{�ŌÂ��ւ鍕�F�̍���d�V��́A���{�s��K���l�Ȃ炾������ڂɂ�����j�I�������ł���B���킹�āA���{�s�ɂ́u���J�q�w�Z�v������B1876�N����1964�N�܂ŏ��w�Z�Ƃ��Ďg���Ă����[�m�����z���ŁA���̏d�v�������Ɏw��B���{�邩��͓k���V�����x�̂Ƃ���ɂ���B�����x�̎҂ɂ��A���ꂭ�炢�̒m����A�����ނقǂɏ��{�s�͗L���ł���B���̏��{�s���n�揤�Ɛ��ނ̊�@���}���A�u�܂��Ȃ݊��������Ɓv�Ɏ��g�Ƃ����̂�����A���X�����Ă���B
�@���Ƃ̔��[�́A���{�w���ӂ̋�搮�����Ƃ��s�Ȃ������ʁA���n��̏��X�X�����т�Ă��܂��A���т�Ă��܂������X�X�́u�܂��Â���v���s�Ȃ����Ƃɂ���āA�W�q�͂����߂悤�Ƃ������́B�u�܂��Â���v�ł͒n��̐��i���c��𗧂��グ�A���̒n��̑S���тɉ���ɂȂ��Ă��炤�B���̂Ȃ��̎�����⏤�H��̖��������c��̖����ɏA���Ƃ����B
�@���́A�u�n����̉�V���̌����}��v���ƁB���{�w���~�藧�������X���A���{��⋌�J�q�w�Z�Ȃǂ̖ړI�n�Ɍ������r���ŁA�X���݂��y���݂Ȃ��甃���������Ă��炤�A���邢�́A�ړI�n�ɍs�������łɎ��ӂ��y����ł��炤�����������̂��Ƃɂ���Ƃ����B
�@������A�܂��Â���̑��̂́u�����Ă݂����鉺���������Ɓv�ƂȂ��Ă���B
�@�Ώۋ��̐������Ƃ𒅎肷�邽�߂ɂ́A�l���S���o�Ă���B���g�̌������鉺���ɍ����������ɐV�z�E���z����ꍇ�ɂ́A��������(���H�ɖʂ�������)�̉��C���ɂ�����o��̂R���̂Q������(���300���~)����B450���~�ȏ�̍H���ł���A300���~��⏕���邱�ƂɂȂ�B���̂悤�ɂ��Č`����Ă��Ă���̂��A�����̏��{����ӂ́u�܂��Ȃ݁v�ł���B
 �@�ǂ̂悤�ȃX�^�C���̊X���݂ɂ��Ă������͋�悲�Ƃɒn��̐��i���c��������A�s�̒S���E�����R�[�f�B�l�[�^�[�ƂȂ�A���X�͑�w�����̃A�h�o�C�X���āA���߂��Ă����B�u���s����̘A���v�Ƃ̂��ƁB�������A�u�܂��Ȃ݂������Ō������Ȃ��̂́w�d���̒n�����x�v�ƁA�������ꂽ�S���҂͏q�ׂ�B�u����ɂ���ĕ��s�҂��������A�X�܂��Ȃ��Ȃ����v�Ƌ��������B�S���e�n�Œn��̂܂��������̂��߂̎��Ƃ��W�J����Ă��邪�A����u���{��v�����A���Ղ������������鏼�{�s�̎��g�݂́A���ɂ��Ȃ������̂ł���Ɗ�����B���́u�܂��Ȃ݊��������Ɓv�ɂ���Đ��܂�ς�����u�������̉�فv�́A����ɂ��ł́A���̃K�C�h�u�b�N�ɂ��o�ꂷ��قǂɗL���ƂȂ��Ă���B �@�ǂ̂悤�ȃX�^�C���̊X���݂ɂ��Ă������͋�悲�Ƃɒn��̐��i���c��������A�s�̒S���E�����R�[�f�B�l�[�^�[�ƂȂ�A���X�͑�w�����̃A�h�o�C�X���āA���߂��Ă����B�u���s����̘A���v�Ƃ̂��ƁB�������A�u�܂��Ȃ݂������Ō������Ȃ��̂́w�d���̒n�����x�v�ƁA�������ꂽ�S���҂͏q�ׂ�B�u����ɂ���ĕ��s�҂��������A�X�܂��Ȃ��Ȃ����v�Ƌ��������B�S���e�n�Œn��̂܂��������̂��߂̎��Ƃ��W�J����Ă��邪�A����u���{��v�����A���Ղ������������鏼�{�s�̎��g�݂́A���ɂ��Ȃ������̂ł���Ɗ�����B���́u�܂��Ȃ݊��������Ɓv�ɂ���Đ��܂�ς�����u�������̉�فv�́A����ɂ��ł́A���̃K�C�h�u�b�N�ɂ��o�ꂷ��قǂɗL���ƂȂ��Ă���B
�@�Ђ邪�����ĉ䂪������s�B�u���{��v��u���J�q�w�Z�v�Ƃ܂ł͂����Ȃ��܂ł��A�̐�L�d�ɕ`���ꂽ�ʐ�㐅�̍�����]�˓�����������u�������������k���Ɏ����A�쑤�ɂ͍��̖����u���v��Q�̓s������������Ă���B���̎��R�E�������������u�܂��Â���v�ɗ͂����Ă����A�n��̂܂��������ƂȂ�A�n�揤�X�X�̊������ɂȂ����Ă����Ǝv���B
�@�w���~�肽��A�ǂ̉w�O�Ƃ������悤�Ȍ��i�̂܂��Â���ł́A�l�͖��͂������Ȃ��B������s�ɂ͏�����s�ɍ������܂��Â�����s�Ȃ��Ă����u�K�ꂽ���Ȃ�܂��v�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B���R�E�������������܂��Â���ք����������{�s�̎��Ƃ�q�����āA�܂��܂����̂��ƂɊm�M���������B
[�ѓc�s�E���z�����d����]
 �@�ѓc�s�̑��z�����d���Ƃ͑����̃}�X�R�~�łƂ�グ���A�����]���Ă���B���Ə����Ɍb�܂ꂽ���̒n�ŁA���z���p�l���u���Ђ��ܔ��d���v���s���o���ŕ��y������g�݂ł���B�}�X�R�~�ɂ��ƁA�u���z���p�l���͓����A�ѓc�s��ߗׂ̕ۈ牀�Ȃnj����{��162�ӏ��Ő�s�I�ɕ��y���i�v�Ƃ���A�u���܂ł͈�ʉƒ�ɂ��Ώۂ��L���Ă���v�Ƃ���Ă���B�悤����ɁA�����͎s�P�ƂŌ����{�݂Ȃǂɑ��z���p�l���̐ݒu�������߂Ă����A���Ɉ�ʉƒ�ւ̕��y�Ɏ��g��ł���Ƃ������́B�����{�ݓ��ւ̂���Ȃ镁�y�ƈ�ʉƒ�ւ̕��y�ɍۂ��āA�s���o���ɂ�鑾�z���p�l�����y�Ƃ����`�Ԃ��̗p����Ă������炵���B �@�ѓc�s�̑��z�����d���Ƃ͑����̃}�X�R�~�łƂ�グ���A�����]���Ă���B���Ə����Ɍb�܂ꂽ���̒n�ŁA���z���p�l���u���Ђ��ܔ��d���v���s���o���ŕ��y������g�݂ł���B�}�X�R�~�ɂ��ƁA�u���z���p�l���͓����A�ѓc�s��ߗׂ̕ۈ牀�Ȃnj����{��162�ӏ��Ő�s�I�ɕ��y���i�v�Ƃ���A�u���܂ł͈�ʉƒ�ɂ��Ώۂ��L���Ă���v�Ƃ���Ă���B�悤����ɁA�����͎s�P�ƂŌ����{�݂Ȃǂɑ��z���p�l���̐ݒu�������߂Ă����A���Ɉ�ʉƒ�ւ̕��y�Ɏ��g��ł���Ƃ������́B�����{�ݓ��ւ̂���Ȃ镁�y�ƈ�ʉƒ�ւ̕��y�ɍۂ��āA�s���o���ɂ�鑾�z���p�l�����y�Ƃ����`�Ԃ��̗p����Ă������炵���B
�@�ł͂Ȃ����z�����d���Ƃɒ��肵���̂��B�S���҂̐����₢�������������ɂ��ƁA������140���ԁ`200���ԂƂ����L�x�ȓ��Ǝ��Ԃɒ��ڂ����ѓc�s���A�V���Ȋ����ƓW�J��ړI�Ɋ��Ȃɕ⏕��(�܂ق�Ί��ƌo�σ��f������)��\���B�⏕���Ƃ��̑�����A�ǂ̂悤�Ȏ��Ƃ�W�J���Ă������̎��s���������ߒ��̂Ȃ��ŁA�m�o�n�@�l�u��M�B���Ђ��ܐi���v�������A���̖@�l���̂Ƃ����Ёu���Ђ��ܐi���G�l���M�[(��)�v�𗧂��グ�āA��q�̑��z���p�l���u���Ђ��ܔ��d���v���s���o���ŕ��y������g�݂ւƐi�W���Ă������l�q�B
 �@���Ƃ̌����͎s������̏o���B�u��450���̑S���̎s�������Q���~�̏o�����A38 �̑��z�����d���ƏȃG�l���M�[���Ƃ�W�J�v�Ǝ����ɋL����Ă���B���̌��������ƂɁA�ѓc�s���̌ˌ��ďZ��̉����ɑ��z���p�l�����u�[���v�~�Őݒu�B����ɁA���X19,800�~�̗��p�������X�N�ԁA�u���Ђ��ܐi���G�l���M�[(��)�v�Ɏx�����Ă��炤�Ƃ��Ă���B����ɂ���āA�p�l���ݒu��p200���~���y�C�ł���Ƃ����B�u19,800�~�v�͒����d�͂̓d�C�����Ɣ�r����ƌ��X�T�`�U��~�̊����ƂȂ邪�A�ߓd�ɓw�߂�Γw�߂�قǁA�����d�͂ւ̔��d������������(���X���ςS��~���x)�Ƃ������̂ŁA���S���͂����傫�Ȃ��̂Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B�������A�p�l���ݒu10�N�ڂɂ͗��p����(19,800�~)�̎x�������Ȃ��Ȃ邽�߁A�t�ɁA���d�ł̎�������������B����A�o���҂ɑ��ẮA���d���v�̈ꕔ�����z���Ƃ��Ē���I�Ɏx������Ƃ������́B �@���Ƃ̌����͎s������̏o���B�u��450���̑S���̎s�������Q���~�̏o�����A38 �̑��z�����d���ƏȃG�l���M�[���Ƃ�W�J�v�Ǝ����ɋL����Ă���B���̌��������ƂɁA�ѓc�s���̌ˌ��ďZ��̉����ɑ��z���p�l�����u�[���v�~�Őݒu�B����ɁA���X19,800�~�̗��p�������X�N�ԁA�u���Ђ��ܐi���G�l���M�[(��)�v�Ɏx�����Ă��炤�Ƃ��Ă���B����ɂ���āA�p�l���ݒu��p200���~���y�C�ł���Ƃ����B�u19,800�~�v�͒����d�͂̓d�C�����Ɣ�r����ƌ��X�T�`�U��~�̊����ƂȂ邪�A�ߓd�ɓw�߂�Γw�߂�قǁA�����d�͂ւ̔��d������������(���X���ςS��~���x)�Ƃ������̂ŁA���S���͂����傫�Ȃ��̂Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B�������A�p�l���ݒu10�N�ڂɂ͗��p����(19,800�~)�̎x�������Ȃ��Ȃ邽�߁A�t�ɁA���d�ł̎�������������B����A�o���҂ɑ��ẮA���d���v�̈ꕔ�����z���Ƃ��Ē���I�Ɏx������Ƃ������́B
�@�u���Ђ��ܐi���G�l���M�[(��)�v����鑾�z���p�l���ݒu���ƈȊO�ɂ��A�ѓc�s�ɂ́A���15���~�̐ݒu�⏕���x������A�����ѓc�s�ł́u���������Ői�߂鑾�z�����d�v�Ɩ��ł��Ă���B�Ȃ��A���z���p�l���ݒu�͒n���Ǝ҂ɗD�攭���B�n���Ǝ҂̎d���m�ۂɂȂ����Ă���B
�@�����܂Ő������Ă��ˑR�Ƃ��āA�u�Ȃ��A���z�����d�Ɍ��������̂��v�u�s���͑f���Ɏ��ꂽ�̂��v�̋^�₪�c��B�S���E���̐����ɂ��ƁA�u���̒n��͔_�ƒ��S�̉ƒ낪�����A���̕ω��͎s�������ɑ傫�ȉe�����y�ڂ��B������A���ɂ͕q���ɔ�������B�܂��A�ѓc�s�͔_�����͂����Ă������Ƃ���A���z�M������̕��y����30���ɒB���Ă���B������V���Ȋ����ƂƂ����ۂɁA���z���p�l���͈�a���Ȃ��������ꂽ�v�B���Ə����Ɍb�܂�Ă��邱�Ƃ��瑾�z�M������̕��y�������݁A���̂��Ƃ��瑾�z�����d�ɂ��J�x���Ȃ��A�����Ċ��ɕq���Ȕ_�ƒ��S�̂܂��������B�����ɁA�S���I�ɂ��ˏo������g�݂ƂȂ����w�i���B��Ă���B�������A�s�����̊��́E�K���͂��D��Ă��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B
�@�������A�s���o���ɂ�鎖�ƂƂ́A���X�Ƃ܂ǂ��B���Ƃ����܂������Ȃ���Ώo���҂ւ̕��z���ł��Ȃ��Ȃ�A�傫�Ȗ��ɔ��W����B����ԈႦ�A���ă}�X�R�~����킵���u����t�@���h�v�̂悤�ȃP�[�X�ɂ��Ȃ肩�˂Ȃ��B���̎��Ƃ������̂��ꏏ�ɂȂ��Đ��i����Ƃ����̂�����A��قǎ��M���������̂��A�͂��܂��A�[���l���Ă͂��Ȃ������̂��E�E�E�B
 �@���������̑�ЊQ���@�ɁA���R�G�l���M�[�ɑ傫�ȊS���W�܂��Ă���B���Ǝ��Ԃ��N��1,900���Ԉȏ�̓��{�́A�S���ǂ��ł����z�����d�ɓK���Ă���Ƃ����B�܂��͌����{�݂���A�����ă}���V�����Ȃǂ̏W���Z��A��ʉƒ�ցB���˔\�����̐S�z�̂Ȃ����R�G�l���M�[�ւ̓]�������A�q�ǂ��⑷�ցA���̒n������n���Ă�����X��l�̐Ӗ��ƂȂ�B������s�ɂ́u�Z��p�V�G�l���M�[�@�퓙���y���i�⏕�v���x�����邪�A�s���C���̎��g�݂ł́A�q�ǂ������ɖ��邢������ۏႷ����̂Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B��i�����̂̎��g�݂ɑ傢�Ɋw�сA������s�Ǝ��̎{�W�J�ł���Ǝv���B �@���������̑�ЊQ���@�ɁA���R�G�l���M�[�ɑ傫�ȊS���W�܂��Ă���B���Ǝ��Ԃ��N��1,900���Ԉȏ�̓��{�́A�S���ǂ��ł����z�����d�ɓK���Ă���Ƃ����B�܂��͌����{�݂���A�����ă}���V�����Ȃǂ̏W���Z��A��ʉƒ�ցB���˔\�����̐S�z�̂Ȃ����R�G�l���M�[�ւ̓]�������A�q�ǂ��⑷�ցA���̒n������n���Ă�����X��l�̐Ӗ��ƂȂ�B������s�ɂ́u�Z��p�V�G�l���M�[�@�퓙���y���i�⏕�v���x�����邪�A�s���C���̎��g�݂ł́A�q�ǂ������ɖ��邢������ۏႷ����̂Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B��i�����̂̎��g�݂ɑ傢�Ɋw�сA������s�Ǝ��̎{�W�J�ł���Ǝv���B
�@�ѓc�s�́A���z�����d�̑��ɂ��A�؎��o�C�I�}�X���p�̕��y�ɗ͂����A�����͔��d�̌����ɂ��Ƃ肩�����Ă���B�߂����͎Y�ƊE�Ƃ̘A�g���܂߂��u�����f���s�s�v�ł���B���̐�A�ѓc�s����͖ڂ������Ȃ��B
��ԕ��ː��ʂ̑���p�x������
�@������s�́A�F�ۈ牀�⎄���c�t���A�����w�Z�Ŏ��{���Ă����ԕ��ː��ʂ̑���p�x�����N�S�����猩�������Ƃ��A�S��15���t�u�s��v�ŕ\�����܂����B�������A���ꂪ�s���̗�������̂��A���ɂ͋^��ł��B
�@���N�R���܂ŏ�����s�́A�ۈ牀��c�t���A�����w�Z�ŁA��C���̕��ː���(��ԕ��ː���)�̑�������Q��A�Q�T�Ԃ����̃y�[�X�Ŏ��{���Ă��܂����B������S������́A�R�J���ɂP��̃y�[�X�ɉ��߂Ă��܂��B���߂����R���u�s��v�ł́A�u�X�J���ԑ��肵�Ă������ʂ��A���l�ɑ傫�ȕϓ����Ȃ����Ƃ���v�Ɛ����B�������A���������S���@�̎g�p�ς݊j�R���v�[���̖��c�Ȏp�������Ȃ��ŁA�u���l�ɑ傫�ȕϓ����Ȃ��v����Ƃ����đ���p�x���ɂ߂邱�Ƃ��Ó��Ȃ̂ł��傤���B���K�͂̒n�k���N�����ꍇ�ɂ́A�g�p�ς݊j�R���v�[���ɂ��e�����N���Ȃ��Ƃ�������܂��A�V���ȍЊQ�����O����܂��B�s�̒S�������́u�]���̑���ӏ����R�J���ɂP��̊����ɕύX���邩���ɁA�����Ȃǂւ�����ꏊ���L���Ă��������v�Əq�ׁA���������߂Ă��܂����A�s�����o�Ƃ͂�������Ă���Ɗ����܂��B
�@������s�ɂ͌��݁A��ԕ��ː��ʂ𑪒肷��@�킪�R�䂠��܂��B�P��͎s���w�������|�P�b�g�T�C�Y�̂��́A���Ƃ̂Q��͓����s����ݗ^���ꂽ���̂P��i�|�P�b�g�T�C�Y�j�ƕ{���ی�������肽���̂P��i��^�̖{�i�I�Ȃ��́j�B�s���ɑ݂��o���Ă���@��́A�s���w�������|�P�b�g�T�C�Y�̂��̂ł��B�ۈ牀��c�t���A�����w�Z�łR���܂ő��肵�Ă����@��́A�����s����ݗ^���ꂽ�|�P�b�g�T�C�Y�̂��̂��g�p���Ă���A�S������R�J���ɂP��̊����ő��肵�Ă���@��́A�{���ی��������Ă����{�i�I�Ȃ��̂ł��B
�@�O�q�����悤�ɁA������s�͎s���Ƀ|�P�b�g�T�C�Y�̑���@���݂��o���Ă��܂��B�������A�݂��o���j���͌��j��������j���܂łŁA�y�j�E���j�E�j���݂͑��o���Ă��܂���B�s������͓y�j�E���j�E�j�������p�������Ƃ̗v�]�����Ă��܂����A�u�݂��o���̑̐����Ƃ�Ȃ��v�𗝗R�ɁA�������Ă��܂���B
�@�Ƃ��낪�A���ׂ̍������s�ł́A�y�j�E���j�E�x���ł��s���ɑ݂��o�����s�Ȃ��Ă��܂��B�������s�c��ɒ�o���ꂽ�����ɂ��ƁA�u�����̊Ǘ�����ё݂��o���́A�������v��ۂ��s�Ȃ��B�������A�x�����݂̑��o���ɂ��ẮA�����������ۂ̋��͂���̂Ƃ���v�B������s�ӂ��Ɍ���������A�u�����̊Ǘ�����ё݂��o���́A����������ۂ��s�Ȃ��B�������A�x�����݂̑��o���ɂ��ẮA�������Ǎ��ۂ̋��͂���̂Ƃ���v�ƂȂ�܂��B
�@��̓I�ɂǂ̂悤�ɍs�Ȃ��Ă���̂��B�������s�̑����ۂɂ����������Ƃ���A�u�����ۂ̓����̐E���̂��ƂɁA���v��ۂɎ��O�ɋx�����̗��p��\������ł���s���̃��X�g���͂����A�����̐E�����\������ł���s���ɑ݂��o���B����āA�����̐E�������ː����l�̎�����L���Ă���킯�ł͂Ȃ��v�B
�@������s�̑������Ǎ��ۂ̎{�݊Ǘ��W�̐E���ɁA�������s�̑����ۂ̓����E���Ɠ��l�Ȃ������s�Ȃ��Ă��炦��A������s�ł��x�����Ɏs���ւ̑����݂��o�����s�Ȃ����Ƃ͉\�Ȃ̂ł͂Ȃ������������B���̂��Ƃ��A�T��22���̌��݊��ψ���ŋ��߂��Ƃ���A������ے��́u�����������v�Əq�ׂ܂����B�ǂ����Ƃ́A���A���s�Ɉڂ��Ă������������Ǝv���̂ł��B
�V���ȍ~�A���ł̍r�g��
�@�R���s�c��Ŏ^�������ŋ��s���ꂽ���ېłƉ��ی����̒l�グ�A����ѓ����s�������҈�ÍL��A���c��ʼn����ꂽ�������҈�Õی����̒l�グ�́A��������ۂɐg�ɍ~�肩�����Ă���̂��낤���B��������S������̒l�グ�ł͂��邪�A�R���c��ŋc������Ă����ɔ�ی��҂̕ی����Z��ɊԂɍ����Ƃ͎v���Ȃ��B
�@�����ŁA�s�����̒S�������ɖ₢���킹���Ƃ���A�ʎ��o�c�e�t�@�C���̉��B�[�t���ƌ����������͂V������A�N���V�����͉��ی����łW������A���ېłƌ������҈�Õی�����10������Ƃ������Ƃł���B��������A�N�x�̂P�N�ԕ��̒l�グ�z��U�蕪���ĕ��ۂ��邽�߁A���Ŋ��͂����������܂�Ǝv����B�s�����̒S�������́A�V��������̂��X���X�Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B
�@���{�̐��x�����ɂ���āA�N���}�{�T���̔p�~�A����}�{�T���̉��Z�̔p�~�������邽�߂ɁA�q��Đ������C�ɕ��S������Ă���B����ɉ����ď���ł̑��ł����s����邱�Ƃɂł��Ȃ�A�i�C�̓h����ɂ܂ŗ��Ƃ���邱�Ƃ͋^���̂Ȃ��Ƃ���B�ŋ���[�߂�̗͂��Ȃ��Ȃ�A�Ŏ����ǂ��납�A�Ŏ����ɂȂ�͕̂K��ł���B���܂����A�����̏W�ߕ��Ǝg������ς���A�傫�Ȃ��˂��z���グ�鎞�ł���B
�@�@���o�c�e�t�@�C���Łu���ېŁE���ی����E�������҈�Õی����̑��ł̉e�������v���f��
2012�N�R���s�c�� �Z���[�E�ؖ������̌�t�萔���l�グ
�@�R�����s�c��Ɉ�t�F�F�s���́A�s���������Ŕ��s���Ă���Z���[��s�ŏؖ����A��ӓo�^�ؖ����Ȃǂ̌�t�萔���������グ�����o���s�Ȃ��A���{���Y�}�ȊO�̎^�������Ő����B���N�S�����痿���l�グ�����{����Ă���B
�@�萔���̒l�グ���s�Ȃ����R��������s�́A�i�P�j��R���s�������v��j�ŗ������������������A�i�Q�j2010�N�x���Z�̊č��ӌ����Ō��������w�E����Ă��邽�߁A�Ɛ����B�������Ɋč��ӌ����ł́u�ؖ������̌�t�萔���v�ɂ��ċL���Ă���B�������A�č��ӌ������q�ׂĂ���̂́u�X���ɂ��ؖ������̌�t�萔���v�ɂ��Ăł���A�������đ�����t�̂��Ƃł͂Ȃ��B
�@�ł́A2010�N�x���Z�̊č��ӌ����͂ǂ̂悤�ɋL���Ă��邩�B�ȉ��A���̑S�����Љ��B�u�s�ł́A�Z���[���ӓo�^�ؖ��̂ق��A�e��ؖ����ނ̑唼��200�~�̎萔���ɂČ�t���Ă���B���̎萔���́A�s���������ł̌�t�A�Z��J�[�h�ɂ��R���r�j��t�A����ɂ͗X���ɂ���t�ł����Ă��A�ꗥ�ƂȂ��Ă���B�X���ɂ���t�͊J���┭���Ȃǂ̎��(�l����)�������邽�߁A����26�s�ł͔����߂��̎s���萔���������ݒ肵�Ă���ɂ���B���������āA�X���ɂ���t�葱���ɂ��ẮA��ƗʂɌ��������萔���Ƃ��邱�Ƃ��������ꂽ���v�B
�@��t�F�F�s���́A�X���ɂ��ؖ����̌�t�萔�����č��ӌ����ɏ]���āA�]���̑�����t�z�̂Q�{�ɐݒ肷��ƂƂ��ɁA�����ł̌�t�萔�����P.�T�{�Ɉ����グ���B����A�Z��J�[�h�ɂ��R���r�j�ł̌�t�萔���́A�]���̑�����t�z�Ɠ��z�ɂƂǂ߂��B�݂悤�ɂ���ẮA���y���͂��ǂ�Ȃ��Z����{�J�[�h�̕��y�𑣐i���邽�߂ɁA�u�Z��J�[�h�ɂ��R���r�j��t�̕��������ł���v�ƌ����������̂��Ƃ��ł���B
�@������̗��R�Ƃ���Ă���u��R���s�������v��j�ł������Ă���v�ł��邪�A�u�萔���̌������v�̍��ڂ݂͂�����Ȃ��B�����Č����u�e��g�p�������݂̍���̌������v�Ƃ������ڂł��邪�A�Ȃɂ����������Ƃ����A�u�e��g�p�����ɂ��āA��v�ҕ��S�̌����Ɋ�Â��A����I�����s�Ȃ����߂̕������������v�Ƃ������̂ł���A�u����I�����s�Ȃ����߂̕���̌����v�������ł͌f�����Ă���̂ł���B
�@�s���l�グ�̗��R�Ƃ��Ă���Q�����ɂ��ẮA����������������Ȃ����̂Ƃ��킴������Ȃ��B������s�͂��̒l�グ�ɂ���āA�N�Ԃ�1,622���~�̑�����������ł���B
�@���{���Y�}�s�c�c�́A���ېł���ی����̒l�グ�A�N���}�{�T���̔p�~�ȂǂŎs�����S����C�ɉ����Ă���Ȃ��ł̍���̒l�グ�͓���e�F�ł��Ȃ��Ƃ��āA���Ăɔ������B
�@���o�c�e�t�@�C���Łu������s�̏Z���[�E�ؖ������̌�t�萔���l�グ�ꗗ�v���f��
2012�N�R���s�c�� ������������s�̍ЊQ���\�Z
�@�����{��k�Ќ�̖{�i�\�Z�ƂȂ���������s��2012�N�x�\�Z�́A2011�N�x���l�ɁA�ЊQ����˔\�����ւ̑������߂��܂��B
�@�Ƃ��낪2012�N�x�\�Z�́u�ЊQ����v�́A�O�N�x63.2������4,244��6,000�~�A�ЊQ����܂߂��k�Њ֘A�{���S�̂ł��O�N�N�x��66.2������5,767��4,000�~���x�ł�������܂���B
�@�܂��A�y�듙�Ɋ܂܂����ː������̑���E���͌o����A2011�N�x��405��4,000�~�̗\�Z���g�܂ꂽ�ɂ�������炸�A2012�N�x�͗\�Z���g�܂�Ă��܂���B����ł͎s���̕�炵�͎��܂���B
�@���{���Y�}�s�c�c�́A�\�Z�ψ���Ŏs�̎p�����������ƂƂ��ɁA���Ȃ��Ƃ��ЊQ���p�̔��~�i�E���Օi�̗\�Z�z���A�s���̕s���ɉ�����ׂ��Ǝ咣���܂����B
�@���o�c�e�t�@�C���Łu2011�N�x��2012�N�x�̏�����s�̐k�Њ֘A�{��Ɨ\�Z�v�ꗗ���f�ڂ��܂��B
�{�����j���^
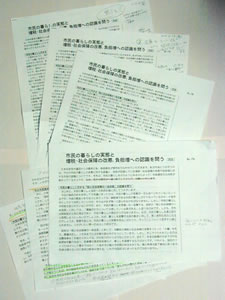 |
|
�����d�˂鎿�⌴�e
|
�@�Q��20�����珬����s�̂R�����s�c��X�^�[�g���A�Q��26���̓��j���ɂ́u���j�c��v���J����܂����B����̓��j�c��ł́A��N12���̎s���I���ŕԂ�炢����t�F�F�s���̎{�����j�ɑ���e��h���Ƃ̎��^���s�Ȃ��A���{���Y�}�͂S�l�S��������ɗ����A�ŏ��Ɏ������₵�܂����B
�@���{���Y�}�s�c�c�́A�{�����j�̎��^�ɂ������Ď��⌴�e�����ꂼ�ꂪ�������A�s�c�c�̉�c�łR��ɂ킽���ē��e�������B����܂��Ď���ɗՂ݂܂����B�ȉ��́A������e�Ǝs���̎�ȓ��قł��B�ڍׂȂ����́A������s�c��̃��[�X�g���[�����p�i�C���^�[�l�b�g���p�j���������������B
�s���̕�炵�̎��Ԃ�
���ŁE�Љ�ۏ�̉����A���S���ւ̔F����₤
�@�����s���ɂ��������̂́A�����̎s���̕�炵�̎��Ԃɑ���F���ƁA���{���v�悵�Ă��鑝�ŁE�Љ�ۏ�̉����╉�S���ɑ���s���̔F���ɂ��Ăł��B����́A�s���̕�炵���ǂ̂悤�ɂ݂邩�ɂ���āA�s���^�c�̕��������ς���Ă��邩��ł��B
�s���̕�炵�ɑ���u�łƎЉ�ۏ�̈�̉��v�v�̔F����₤
�@�͂��߂ɁA�s���̕�炵�ƍ����ւ̕��S�v��ɑ��Ă��������܂��B����̎{�����j��q�����ĕs�v�c�Ɏv�����̂́A�s���̕�炵�̎��Ԃ��ꌾ���q�ׂ��Ă��Ȃ��Ƃ����_�ł��B�s���̑ǎ����s�Ȃ��ɂ������ẮA�[�Ŏ҂ł���s���̕�炵���ǂ��Ȃ��Ă���̂��A������s�Ƃ��Ăǂ��Ή����Ă����̂��A���̓_���܂����Ɍ���Ȃ���Ȃ�܂���B�������A�s���̕�炵�����̂�����Ă��Ȃ��̂ł��B�܂��A�s���̕�炵���ԈႢ�Ȃ���������A���{�́u�łƎЉ�ۏ�̈�̉��v�v�ɑ��ẮA�u�c�_�̍s���ɂ��Ē������Ă����K�v������v�Əq�ׂ�݂̂ł��B�������A����͍����ʂ��猩�����_�ł���A�s���̕�炵�̎��_����ł͂���܂���B�Ȃ��A�s���̕�炵��^���ʂ��璼�����悤�Ƃ��Ȃ��̂ł��傤���B�Ȃ��A��炵�����鍑�̓����ɑ��āA��O�ғI�Ȍ����ɂȂ�̂ł��傤���B��t�s���ɂ́A�s���̕�炵�̎��Ԃ����Ȃ����肩�A����Ă������Ƃ����N�w���犴�����܂���B���������������̓_�͂��̕����ł��B
�@���{�́u�łƎЉ�ۏ�̈�̉��v�v�Ə̂��āA����ł̑��łƎЉ�ۏ�̉��������������u��j�v�����A�t�c���肵�A�R�����܂łɂ͖@�Ă̒�o���s�Ȃ��Ƃ��Ă��܂��B�������A�����ł������Ă���̂́A����ŗ����Q�N��̂S���ɂW���A2015�N10�������10���Ɉ����グ�A�����āA�N���x���z�̈���������x���J�n�N��̐摗��A��Ô�̊��ҕ��S���ȂǁA��炵��j����̂���ł��B����ǂ��A�����̃t�g�R���͂������ĖL���ł͂Ȃ��A������s�̌l�s���ł̏��݂Ă��A�l�����͒ቺ�X���ɂ���܂��B�����͑����Ȃ��̂ɕ��S�͌����ݑ�����A����ł͍����͂��܂������̂ł͂���܂���B
�@��������܂ł��Ȃ��A�s���̕�炵�͐[���ł��B���{���Y�}�s�c�c�̂��Ƃɂ��A�������̐������k�����܂����A�Ȃ��ł������̂��A�����ی������Ȃ��ɂ��炳��Ă���Ƃ������Ԃł��B���k�ɗ���ꂽ������́A�����N���Ɣh���J���̎����Őe�q�Q�l�ŕ�炵�Ă���Ƃ����̂ł����A�A�p�[�g�̉ƒ��ƌ�������������A�قƂ�ǎ茳�ɂ͎c��Ȃ��Ƃ������̂ł����B�ʂ̕��́A�������Ȃ��ĕa�@�ɒʂ��Ȃ����߂ɁA���ސg�̂��Ђ��Â�悤�ɁA�������̂��Ƃɑ��k�ɗ����܂����B�������ꂵ���A�ƒ���ŃC�U�R�U���N����A���w���̎q�ǂ�������̂ɗ�������������Ȃ��Ƃ����P�[�X������܂����B���̂悤�ɁA�s���̕�炵�́A���ʂ̐��������Ă��Ă���炵�Ă����Ȃ��Ȃ�A�d�����Ȃ�������A�Ƒ��̂Ȃ��ŕa�C�ɂȂ�l���o���肷�邾���ŁA�����܂������͐��藧���Ȃ��Ȃ�킯�ł��B���̎s���̕�炵�������ɉ������Ă����̂��A���̂��Ƃ��s���ɖ���Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�{�����j�Ŏs���́A���{�́u�łƎЉ�ۏ�̈�̉��v�v�ɑ��ẮA�u����������m�ۂ��悤�Ƃ������́v�Ƃ̌���������Ă��܂��B���̌������^��ł��B�ʂ����āu��������̊m�ہv�ɂȂ�ł��傤���B
�@����ł́u�R���v�œ�������A1997�N�̋��{���t�̂��Ƃł̐ŗ��T���ւ̈����グ�ƈ�Ô�̒l�グ�ȂǂŁA�X���~�̕��S�����s�Ȃ��܂����B�������A���̂��Ƃɂ���ĉ̓r��ɂ������i�C�͂ǂ��ɗ������݁A���̌��ʁA�����j�]�����������Ђǂ��Ȃ�܂����B
�@����͂ǂ��ł��傤���B����ł̐ŗ�10���ւ̈����グ��13���~���̑呝�łɂȂ�̂ɂ��킦�āA�N���̍팸��x�����ɂ��N���E��ÂȂǂ̕ی����l�グ�����킹��ƁA�N��20���~���̕��S���ɂȂ�܂��B�������n���Ɗi�����L����A�n��o�ς��[���ȂȂ��ł̑呝�łƂȂ�܂��B����ŗ��T���ւ̃A�b�v�̎��ȏ�ɁA�����̕�炵�ɂ͂���m��Ȃ��Ō���^���A���{�o�ς��ǂ��ɓ˂����Ƃ��A�����n���������j�]�����������Ђǂ����邱�Ƃ͖��炩�ł��B�u��������v�ǂ��납�A�����j�]�����������[���ɂ��A�s���̕�炵���h����Ɋׂ����̂ł�������܂���B
�@���{�́u�����\�ȎЉ�ۏᐧ�x�ɂ��邽�߁v�Ɛ������Ă��܂����A����ł̑��łƂƂ��ɁA�̐S�̎Љ�ۏᐧ�x�����������̂ł��B�u�����v�ł͂Ȃ��u��̂āv�ł��B
�@�s���ɂ��������܂��B���{���Y�}�́A�����̎s���̕�炵�́A��s���������Ȃ��s���̂Ȃ��ɒu����A����������A���S�����̂Ȃ��łƂĂ������ɂ�Ƃ�ȂǂȂ��ƍl���܂��B�s���́A�s���̕�炵�̌�����ǂ̂悤�Ɍ��Ă���ł��傤���B�܂��A��炵���A���ƒn���̍������j�]�ɓ�������ł̑��ł͓���A���������̂ł͂���܂���B����ł̑��łɃL�b�p���Ɣ����A���{�ɑ��ł̓P������߂�ׂ��ƍl���܂����A�������ł��傤���B
| �@�s���@ |
�u���݂̎Љ�ۏ��̑������݂����ɁA���������S���Đ������V��𑗂�Ƃ������ƂɂȂ�ƁA����łɗ��炴��Ȃ����낤�Ǝv���B����ł̈����グ�ɑ��ẮA��ނȂ��Ɣ��f����v |
�s�̎s�����S���v��́A��炵���������j�]����
�@���ɁA������s�̕��S���̌v��ɂ��Ăł��B������s�����̊ԁA���{���Ă���s���A���P�[�g��v�]�ł́A�u�����̏[���v�����߂鐺�����|�I�ɑ����Ȃ��Ă��܂��B���ꂾ���A��炵���������Ȃ��Ă��邩��ł��B�������A�s������ԋ��߂Ă��镟���̏[���ɑ��āA�{�����j�ł́u�N�����Z�݊��ꂽ�n��ŕ�炵�������邱�Ƃ��d�v�ł���ƍl���Ă���܂��v�Əq�ׂ邾���ŁA��̓I�ȃ��m�͎�����Ă��܂���B�������A������s���ł�����҂̌ǓƎ����������ł���Ƃ����̂ɁA����҂̌���苍���ɏ������������A�Ώێ҂��s���Ŕ�ېł݂̂Ɍ��肵�Ă��܂��܂����B�ǂ��Ɏ{�����j�ŏq�ׂĂ���u�N�����Z�݊��ꂽ�n��ŕ�炵�������邱�Ƃ��d�v�v�Ƃ������_������Ƃ����̂ł��傤���B�����Ă��邱�ƂƁA���ۂɍs�Ȃ��Ă��邱�ƂƂ͂܂���������Ă��܂��B
�@���������ɑ�ςȕ��S�������t���悤�Ƃ��Ă���ɂ�������炸�A��t�s���͍����s�c��ɁA���ېł���l���ρA�N�z�P���T��~�̒l�グ�A���ی����̊�z��N�z�łP���S,400�~�̒l�グ��ł��o���A�������҈�Õی����ɂ��Ă���l���ρA�N�z 8,765�~�̒l�グ��������Ă��܂��B�܂��ɁA�����j��̃I���p���[�h�ł��B���ېł̒l�グ�̗��R���u�~���ȍ����^�c���m�ۂ��邽�߁v(��ė��R)�Əq�ׂĂ��܂����A������������ǂ��납�����Ă���Ȃ��ł̒l�グ�E���ł́A�s���̕�炵��j����̂ł�������܂���B�������l�グ�̒��S�́A���т̂Ȃ��ō��ۉ����҂������قǕ��S�������ށu�ϓ����v�̑啝�����グ�ƂȂ��Ă���A�����҂��R�l����A���ꂾ���ł������ɂR���~���̒l�グ�ƂȂ�܂��B�܂��ɁA�����̒Ⴂ�l�قǕ��S���d���Ȃ�ň��̑��łł��B�܂��A���ی����͖{�l��ېłł����Ă����т̂Ȃ��Ɏs���ʼnېŎ҂�����ΔN�ԂP�� 4,400�~���̒l�グ�ɂȂ�Ƃ������̂ł���A�������҈�Õی����̒l�グ�������A�ƌv�ւ̕��S�͂͂��肵��Ȃ����̂ƂȂ�܂��B����A�F�߂�����̂ł͂���܂���B
�@�s���ɂ��������܂��B���̂悤�ȑ��ł��s�Ȃ��A�s���̕�炵�͗��������Ȃ��Ȃ�A�Љ�ی�����ŋ���[�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�Ǝv���܂����A�s���͂ǂ̂悤�ɂ��l���ł��傤���B�܂��A�[�߂���Ȃ��l�������Ă���A�s�̍������̂��̂��s���l�܂��Ă���ƍl���܂����A�������ł��傤���B����ɁA�s���ɕ��S�����߂�s���𑱂��Ă����A�{�����j�ŏq�ׂĂ���u�N�����Z�݊��ꂽ�n��ŕ�炵��������v���Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�܂����A�s���͂ǂ̂悤�ɂ��l���ł��傤���B
| �@�s���@ |
�u�����\�Ȑ��x�Ƃ��ĉ^�c���Ă������߂ɂ́A���S�\�͂ɉ����ĕ��S���Ă��������Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�Ǝv���Ă���v�u���ېʼn���ɂ��Ŏ����������邱�Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��ƍl���Ă���v |
�@���ېł������グ��Ε����Ȃ��Ȃ�l���o�Ă��āA���z�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����Ȃ�Ƒ��̎s�ł��[�߂���Ȃ��Ȃ�A�s��������ςɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�s���@�u�����������Ƃ����肤�邩�Ǝv���v
�s���̕�炵�����̂��s���̑��̖���
�@���{���Y�}�s�c�c�͂P�N�O�ɁA�s���A���P�[�g��S�˔z�z�ōs�Ȃ��܂����B�����Ă������������� 387�l�ł��B�u���炵�v�ɂ��Ă̐ݖ�ł́A�u�ꂵ���Ȃ����v��59���Ń_���g�c�ł���A���̗��R�́u��Ô�̎x�o���v�u�Љ�ی����̕��S���v�u�N���̖ڌ���v�u���^�̌����v���������߂Ă��܂��B������������炩�Ȃ悤�ɁA�ƂĂ�����ȏ�̕��S�����߂���ł͂���܂���B
�@��N�A������s�ł͂Q�x�̎s���I�����s�Ȃ��܂������A�����ł̌��ʂ��猩���Ă���̂́A�������i�C����╉�S���̂Ȃ��ŁA��炵���Ȃ�Ƃ����Ăق����A����������Ăق����Ƃ����s���̐؎��Ȋ肢���Q�����Ă���Ƃ������Ƃł��B
�@�s���ɂ��������܂��B���ېł���ی����̒l�グ�ȂǁA�s���ւ���ȏ�̕��S�����߂邠����͒��~���A��^�J�����Ƃ�s�s�v�擹�H���Ƃ̌��������s�Ȃ��A�s���ɕ��S�����߂�s������A��炵�����s���Ɏs���^�c��]�����ׂ��ƍl���܂����A�������ł��傤���B�ȏ�A�����Ȃ����ق����肢���܂��B
| �@�s���@ |
�u�s�����������͉̂�X�̑傫�ȉۑ�B�������A�����Ɍ����Ă̂������Ƃ����X�������Ă����Ƃ����̂��A�傫�ȉۑ�B���������Ēʂ�Ƃ����킯�ɂ������Ȃ��B�S�̂����Ȃ���\�Z�[�u�����Ă��������Ǝv���Ă��邵�A�s���ɕ��S�����Ă��������Ƃ���͂��肢���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl���Ă���v |
���ېł̑��ł�}���邽�߂̈�l
�@������s�̈�t�F�F�s�����R�����s�c��ɒ�o�����������N�ی���(���ې�)��20.37�����̑啝�l�グ�́A�c��̗^�}�c��������X�萺���オ��قǂɁA��ςȑ㕨�ł���B�Ƃɂ����l�グ�̒��g���q��ł͂Ȃ��B�u�ϓ����v�Ƃ����A���ۉ����҈�l��l�Ɉꗥ�ɉېł���z���A�N�z�u7,000�~�v����u17,000�~�v�Ɉꋓ�ɂP���~�������グ���邩��ł���B���ꂪ�ǂ�Ȃɑ�ςȂ��̂��B�Ⴆ�Έ�Ƃɍ��ۉ����҂��R�l����A�ꋓ�ɔN�ԂR���~���̕��S�������邱�ƂɂȂ�B������s�ł̔[�t���ɂ��[�t(���ʒ���)�́A�N�W��ɕ����čs�Ȃ��Ă��邩��A�P����̍��ېŊz���S��~�߂��������邱�ƂɂȂ�B�ƂĂ��Ή����������̂ł͂Ȃ��B
�@�����ɒl�グ��}���邩�B���ꂪ�s����\�ł���c��ɂ͖���Ă���B���{���Y�}�s�c�c�́A�������̕�����Ă��Ă���B�i�P�j�ی����t��̎Z��̂�������A�K�Ȃ��̂ɂȂ��Ă��邩�ǂ����Ƃ����_�B���Ԃ������߂ɎZ�肳��Ă���A�ی���������̎����o���������邽�߁A�ی��ł̏グ�������̕��A������B�ی����t��̎Z�藦�����������Ƃ�����ɓ����ׂ��ł���B�i�Q�j�u��Õ��v�݂̂̈����グ�őΉ����Ă��邱�Ƃ��K�Ȃ̂��B����̒l�グ�́u��Õ��v�݂̂̉���őΉ����Ă��邪�A�u��앪�v�u�������Ҏx�����v�ɂ͐U�蕪���Ȃ��Ă悢�̂��B�u��Õ��v�ɂ��ׂĂ̕��S�����߂Ă��邱�Ƃ���A�Ԃ�V��q�ǂ��ɂ��ېł����u�ϓ����v�̕��S���[���ɂȂ�̂ł���B�i�R�j���x�z��@����x�z�܂ň����グ�Ă͂ǂ����B�u��Õ��v�u��앪�v�u�������Ҏx�����v��@����x�z�܂ň����グ���ꍇ�A1,400���~�̑����ɂȂ�Ƃ����B���z�����҂ɂ͕��S��S���Ă��炤�Ƃ������Ƃ��K�v�ł���B�i�S�j��l������̈�ʉ�v�J�������A�O�������ϊz�܂ň����グ��ׂ��B������s�̖@��J������������l������̈�ʉ�v����̌J���z�́A�O����26�s���A21�ԖڂƂ����Ⴓ�ł���B������s��2011�N�x�̈�ʉ�v�ŏI��ŁA�S���R�疜�~��������������ɐςނƂ����B�\���ɎO�������ς܂ŌJ������z�͂���̂ł���B
�@�����������́A�S���R�疜�~��������������ɐςޗ��R���u�����\�ȍ����^�c�ɂ��邽�߁v���Ƃ����B�������A���ېł������オ���Ĕ[�߂���Ȃ��Ȃ�A�s�������̂��̂���@�Ɋׂ�B�u�����\�v�ǂ��납�A�u�j�]�v�̓��ł���B
�@���{���Y�}�s�c�c�́A���̊p�x����A���ېł̒l�グ�}���Ɍ����đS�͂Ŋ撣�錈�ӂł���B
�s�����ɑ傫�ȕ��S�w�s���𗬃Z���^�[�x
�@������s�c��͂Q���X��(��)��A�s�s�Đ��@�\(�t�q)���ێ��Ǘ����s�Ȃ��Ă���u�s���𗬃Z���^�[�v�̍w���c�Ă��^�������ʼn����A�R���P�����珬����s�̏��L���ɂ��邱�Ƃ����߂܂����B�������A�������i�C����Ɠ����{��k�ЂŐŎ����������A����Ő����ی�╟���ɂ������o����������Ȃ��Ȃ��ł̃n�R���̍w���́A������s�̍����^�c�ɑ傫�ȏd�ׂɂȂ��Ă����܂��B�������̂��ĊJ�����Ƃł����Ă��邽�߂ɁA�~�n��������s�P�Ƃ̏��L�Ƃ͂Ȃ��Ă��炸�A�~�n�̗��p���߂����ẮA���܂��܂ȉۑ������鎖�ԂƂȂ�܂����B�ƂĂ�������Ŋ�ׂ�ł͂���܂���B������s�͎s�c��c�Ă����������̎�����A���ꂩ��K�����ɗ��������킴��Ȃ��Ȃ�܂����B
�@�ȉ��A�����u�s���𗬃Z���^�[�v�w���c�Ăɔ����闝�R���L���܂��B
[�q�^��͈ȉ��̗��R�ŁA�s���𗬃Z���^�[�̍w���ɔ����܂�]
�@���́A�V�����Ŏ��ꂽ������ɑ���A�s�����ǂ���z�[���͕K�v���ƍl������̂ł��B����ŁA�s�����ɗ]�T���Ȃ��Ȃ��ɂ����ẮA����̌��đւ��͒n���̍����w�O�ł͂Ȃ��A������~�n�ł̌��đւ����s�Ȃ��ׂ��ƈ�т��ċ��߂Ă��܂����B�������A������s�͔���ȍ�����K�v�Ƃ���w�O�ĊJ���ɏ��o���A�ĊJ�������ł̃z�[���m�ۂɌŎ��������܂����B���̌��ʁA���Ԓn���Ҋ܂ޑ��̒n���҂ƕ~�n�����L����u�P�M�����v�ł̃z�[���m�ۂƂ������ԂƂȂ�A�����̉ۑ�������{�݂ɂȂ��Ă��܂��܂����B
 �@�������̋c�Ăɔ�������̗��R�́A�s�c��̂��ׂẲ�h�����߂Ă����A�Ǘ��K�����ł����Ԃł̎擾�c�ĂƂ͂Ȃ��Ă��Ȃ����Ƃł��B�s���𗬃Z���^�[���܂ނP�|III�X��́A���̒n���҂Ƃ̌����W����������敪���L�����̕~�n�`�ԂƂȂ��Ă��邽�߁A�~�n�̊Ǘ��E���p���@����茈�߂邱�Ƃ����߂��܂��B�������A�擾�c�Ă���o����Ă���ɂ�������炸�A�����ł���܂łɎ����Ă��܂���B��t�s���́u�z�[���擾�ƊǗ��K��̓Z�b�g�ł͂Ȃ��v�Əq�ׂ܂����A���Ԓn���҂̌������������e���A�ٔ����N����Ȃ��ł����߂��Ă����ĊJ�����ƂƂ����o�܂���݂āA���[�������܂��Ă��Ȃ��Ȃ��ł̊Ǘ��E�^�c���ʂ����ăX���[�Y�ɍs����̂��A�N�������O����͓̂��R�ł��B�z�[���擾�c�Ē�o�̍ۂɂ͒����ł����Ԃł̊Ǘ��K����������Ƃ��K�v�Ƃ����̂́A�s�����̊Ǘ��E�҂������l���ł��B����͎s�c��ɒ�o���ꂽ�u���c�L�^�v�ł̊Ǘ��E�҂̔������e�ŏؖ�����Ă��܂��B �@�������̋c�Ăɔ�������̗��R�́A�s�c��̂��ׂẲ�h�����߂Ă����A�Ǘ��K�����ł����Ԃł̎擾�c�ĂƂ͂Ȃ��Ă��Ȃ����Ƃł��B�s���𗬃Z���^�[���܂ނP�|III�X��́A���̒n���҂Ƃ̌����W����������敪���L�����̕~�n�`�ԂƂȂ��Ă��邽�߁A�~�n�̊Ǘ��E���p���@����茈�߂邱�Ƃ����߂��܂��B�������A�擾�c�Ă���o����Ă���ɂ�������炸�A�����ł���܂łɎ����Ă��܂���B��t�s���́u�z�[���擾�ƊǗ��K��̓Z�b�g�ł͂Ȃ��v�Əq�ׂ܂����A���Ԓn���҂̌������������e���A�ٔ����N����Ȃ��ł����߂��Ă����ĊJ�����ƂƂ����o�܂���݂āA���[�������܂��Ă��Ȃ��Ȃ��ł̊Ǘ��E�^�c���ʂ����ăX���[�Y�ɍs����̂��A�N�������O����͓̂��R�ł��B�z�[���擾�c�Ē�o�̍ۂɂ͒����ł����Ԃł̊Ǘ��K����������Ƃ��K�v�Ƃ����̂́A�s�����̊Ǘ��E�҂������l���ł��B����͎s�c��ɒ�o���ꂽ�u���c�L�^�v�ł̊Ǘ��E�҂̔������e�ŏؖ�����Ă��܂��B
�@�Ǘ��K�������̂Ȃ��ŁA�����Ƀ��[�����m�����Ă����̂��B����̗Վ��c��ŏ�����s�́A�敪���L�@�▯�@�őΉ�����Əq�ׂ܂������A������̏��݂Ă��A���������L���Ă���҂͋��L�������g�p�ł���Ƃ����̂���O��ł���A�����҂̗��p��ۏႷ��͓̂��R�ƂȂ�܂��B����ɁA��肪����Ǝv����s�ׂ������҂̂Ȃ��ł������ꍇ�ɂ��A����ւ̑Ή��́u���̋敪���L�ґS���̓��Ӂv���邢�́u�W��ł̉ߔ������c�v�ƂȂ��Ă���A�敪���L�@�őΉ�����ɂ͌��E������܂��B���̂��߁A������s�́A�敪���L�@�ł̓J�o�[�ł��Ȃ��������u�Ǘ��K��v�Ń��[�������悤�ƍl���Ă����킯�ł��B
�@�Ƃ��낪�A������s���s���𗬃Z���^�[�擾�̑�O��Ƃ��Ă����u�J���ԏ�v�̐�p�g�p�����m�ۂł����A�P�|III�X����̃t�F�X�e�B�o���R�[�g���u�n���҂̍��Ӂv���Ȃ���Η��p�ł����A�E�b�h�f�b�L��O�\�����܂߂���̓I���p��������A�ł��Ȃ��Ȃ��ł̎s���𗬃Z���^�[�̎擾�Ƃ������ԂɂȂ��Ă��܂��B���̂悤�Ȏ��ԂɂȂ����ő�̐ӔC�́A���̒n���҂Ƃ̋��L�~�n�ƂȂ�ĊJ����@�ł̃z�[�����ݕ��j��F�߂�������s�ɂ���܂��B
�@�ĊJ�����{�s�����s�s�Đ��@�\�ɑ��ẮA�J���ԏ�̐�p�g�p���̊m�ہA�E�b�h�f�b�L�܂߂��t�F�X�e�B�o���R�[�g�̈�̓I���p���ۏ�ł���ȂǁA������s���s���ɐ����̂��ӔC����Ǘ��K��𑁋}�ɂƂ�܂Ƃ߂�悤�������߂�ƂƂ��ɁA�����Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃł����A�Ǘ��K��������Ȃ��Ȃ��ł̓P�ނƂ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��悤�A������s�́A�s�s�Đ��@�\�Ƃ̊Ԃŋ��菑�������킷�悤�A���߂���̂ł��B
�@��������̗��R�́A�敪���L�Ƃ����`�Ԃ̂Ȃ��ł́A������s�̍s�����Y�ł�����~�n�𗘗p���Ă̎��v���Ƃ��s���ȊO���s�Ȃ����Ƃւ̐���������Ă��Ȃ����Ƃł��B���̂��Ƃ́u���c�v�̂Ȃ��ł��A�s���ɑ��Ăǂ̂悤�ɐ����ӔC���ʂ��������A�ۑ�Ƃ��Ďc���ꂽ�܂܂ł��B�Վ��c��ł̒S���ے����u�T�d�Ȍ�����v����v�Ƃ̓��قŏI����Ă��܂��B����������Ă��Ȃ��Ȃ��ł̌��蔭�Ԃ͖��ł��B
�@�������O�̗��R�́A�s���𗬃Z���^�[���擾���邱�Ƃɂ��A�s�����ւ̉e���ł��B�s���𗬃Z���^�[�͂��łɁA�s�s�Đ��@�\�̊Ǘ��ʼn^�c����A�s����������s�����p�ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B�����̉^�c�`�Ԃɂ����Ă��x��Ȃ����p�ł��Ă��邱�Ƃ́A��t�s�����g���P��31���t�u�s���V��v����Łu�~���ȉ^�c���s�Ȃ��Ă���A��莋�͂��Ă��Ȃ��v�Ɩ��m�ɏq�ׂĂ��邱�Ƃ�����ؖ�����Ă��܂��B�����ď�����s�������̍����𓊓����Ă܂ŁA���݂ł��~���ȉ^�c���s�Ȃ��Ă���s���𗬃Z���^�[���擾����K�v�͂���܂���B
�@������s�́A���̌����E�~�n���擾���邽�߂ɁA�n�����֏�A�t�ѐݔ��E���i�܂߂āA�N��(�؋�)��28���~�߂������s���A������R���S�疜�~�A���N�x�̈�ʍ������P���T�疜�~�߂��[�Ă�Ƃ��Ă��܂��B�ʂ����āA������s�̍����̍�������A���̂悤�ȍ����������s�Ȃ�����ł��傤���B�P��17���́u���c�L�^�v�ł́A�V�N�x�̗\�Z�Ґ��ɂ����č�����������𑊓��ɏ[�Ă�K�v�������������Ƃ���A������������̎c�����Q���R�疜�~�ɂȂ��Ă��܂������ƁA��ʉ�v��2013�N�x(����25�N�x)��10���~���x�A�J��z���Ȃ���A2013�N�x�̗\�Z�Ґ����ł��Ȃ����Ƃ��q�ׂ��Ă��܂��B�����_�ł��A���̂悤�Ȑ[���Ȏ��Ԃ��}���Ă���Ƃ����̂ɁA�s���𗬃Z���^�[���擾���邱�Ƃɂ���ċN��(�؋�)�̌�N�x���S���������A�����āA�w��Ǘ��ϑ��������N�Q���R�疜�~�A�K�v�ƂȂ�܂��B���̂��Ƃ���A�V�N�x����͂Q���V�疜�~�]�A�N�̌������҂��}����2015�N�x(����27�N�x)����͖��N�S���Q�疜�~�]�̎x�o���`��������A�s�����Ɍv��m��Ȃ��e�����y�ڂ����ƂƂȂ�܂��B�P��17���́u���c�L�^�v�ɂ́A���̂��߂Ɂu���s�ł́A�⏕���̈ꗥ�J�b�g�̑�p�f�������Ă���Ƃ��������v�ƋL����Ă���A�s�������ɕK�v�Ȍo�����肱�ނ��Ƃ��z�肳���L�q�ƂȂ��Ă��܂��B���̂��Ƃ�Վ��c��Ŏw�E����ƁA�����������́u�s���𗬃Z���^�[�擾�ƁA��O���s�v��j�͓���ɋc�_�ł��Ȃ��v�Əq�ׂ܂����B�s�����ɐӔC�������̓��قƂ͓���A��������̂ł͂���܂���B���̓��ق́u�s���𗬃Z���^�[�ɂ͔���ȍ����𓊓����A�s���T�[�r�X�팸�E�s�����S���͓Ǝ��ɂ����߂�v�Ƃ����錾�ł���A�s���������ԋ߂Ɍ������Ă��鎄�ɂ͓���A�F�߂�����̂ł͂���܂���B
�@������s�́A���N�x���Ŋ������}���鋌�܂��Â����t���̖�10���~�����p����Ƃ����v������A�Ǘ��K�������ł��Ȃɂ��Ȃ�ł��s���𗬃Z���^�[���擾����Ƃ��������ɂȂ��Ă��܂��B�������A��t���̊������ԋ߂ɔ��鎖�ԂƂȂ������������̋N����́A�s�s�Đ��@�\�̕s��ۂ�����N11�����̎擾���������ƂȂ������Ƃ���ł��B�������A������Ă���Ǘ��K��Ă͏�����s�������ł�����̂ł͂���܂���B�����̎��Ԃ����肾�����s�s�Đ��@�\�ɂ����ӔC���ʂ������A�s�����炪�u�~���ȉ^�c���s�Ȃ��Ă���v�ƔF�߂�A�s�s�Đ��@�\�ł̊Ǘ��E�^�c���s�Ȃ킹��ׂ��ł��B
PDF�t�@�C�����{�����邽�߂ɂ̓A�h�r�А��́uAdobe Acrobat Reader�v���K�v�ɂȂ�܂��B
Adobe��WEB�T�C�g���_�E�����[�h���Ă��g�p�ɂȂ�܂��B

|
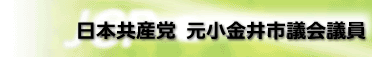

 �@������s�̌��Z�ψ���́A�܂��I����Ă��Ȃ��B������s�̈�t�s�����X�����{�ɓ˔@�A�u���[�X���Ɂv�ƌĂ����ݎ̎s���Ƀr�����u�����v���Ƃ�\�����A�X�����{�Ɏ擾�\�Z�̋c�����s�Ȃ��悤�Ɏs�c��ɋ��߂Ă�������ł���B���̂��ߋc��͋�]�B�\�肵�Ă������Z�ψ���̎��^�������ŏI�ՂɃY�����݁A�c�������^���ڂ͕�̌��Z�ψ���ň����悤�ɂȂ�������ł���B���̂��Ƃ���A�Œ�ł��S���ԊJ����錈�Z�ψ���͂R���Ԃ̎��^���I�����i�K�ŃX�g�b�v�B�����́A11�����{�ɗ\�肷�錈�Z�ψ���摗��ƂȂ��Ă���B
�@������s�̌��Z�ψ���́A�܂��I����Ă��Ȃ��B������s�̈�t�s�����X�����{�ɓ˔@�A�u���[�X���Ɂv�ƌĂ����ݎ̎s���Ƀr�����u�����v���Ƃ�\�����A�X�����{�Ɏ擾�\�Z�̋c�����s�Ȃ��悤�Ɏs�c��ɋ��߂Ă�������ł���B���̂��ߋc��͋�]�B�\�肵�Ă������Z�ψ���̎��^�������ŏI�ՂɃY�����݁A�c�������^���ڂ͕�̌��Z�ψ���ň����悤�ɂȂ�������ł���B���̂��Ƃ���A�Œ�ł��S���ԊJ����錈�Z�ψ���͂R���Ԃ̎��^���I�����i�K�ŃX�g�b�v�B�����́A11�����{�ɗ\�肷�錈�Z�ψ���摗��ƂȂ��Ă���B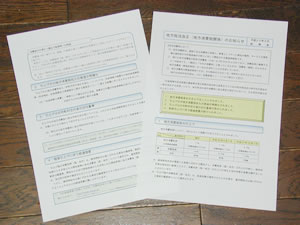
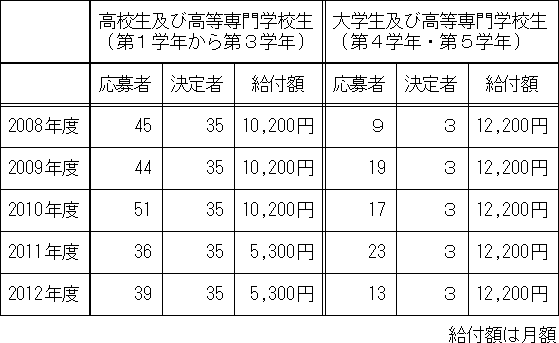
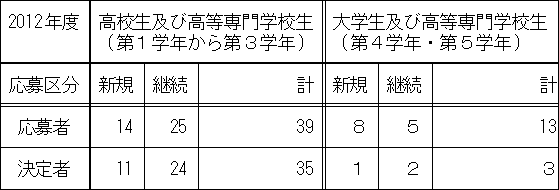
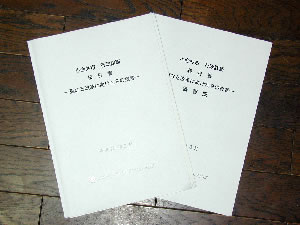 �@������s�͍����̎s�������u��@�I�v�Əq�ׂĂ���B�������ɁA�����̎s�����́u��@�I�v�ƌ����ɂӂ��킵�����ԂƂȂ��Ă���B������s�̍����s����₤���߂ɐςݗ��ĂĂ���u������������v�́A�����_��11���V�疜�~�ɂ������A���N�x�̗\�Z��g���_�ŁA�]�͂��Ȃ����ԂɊׂ�\���������B���̏��Ȃ�Ƃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl����̂́A���ꂵ�������ł���B
�@������s�͍����̎s�������u��@�I�v�Əq�ׂĂ���B�������ɁA�����̎s�����́u��@�I�v�ƌ����ɂӂ��킵�����ԂƂȂ��Ă���B������s�̍����s����₤���߂ɐςݗ��ĂĂ���u������������v�́A�����_��11���V�疜�~�ɂ������A���N�x�̗\�Z��g���_�ŁA�]�͂��Ȃ����ԂɊׂ�\���������B���̏��Ȃ�Ƃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl����̂́A���ꂵ�������ł���B �@���{���Y�}�s�c�c�͖��N�A������s�̔N�ԗ\�Z(�����\�Z)�ɑ��āA�\�Z�̑g�ւ��Ă��Ă��Ă��܂��B�Ȃ��A�s������o�����\�Z�Ɏ^���ł��Ȃ��̂��A�ǂ̂悤�ȗ\�Z�ł���ׂ��Ȃ̂��𖾂炩�ɂ��邽�߂ɁA���{���Y�}�s�c�c�̍l�����������̂ƂȂ��Ă��܂��B
�@���{���Y�}�s�c�c�͖��N�A������s�̔N�ԗ\�Z(�����\�Z)�ɑ��āA�\�Z�̑g�ւ��Ă��Ă��Ă��܂��B�Ȃ��A�s������o�����\�Z�Ɏ^���ł��Ȃ��̂��A�ǂ̂悤�ȗ\�Z�ł���ׂ��Ȃ̂��𖾂炩�ɂ��邽�߂ɁA���{���Y�}�s�c�c�̍l�����������̂ƂȂ��Ă��܂��B



 �@�T��16��(��)�E17��(��)�̂Q���ԁA������s�c��݊��ψ���͐M�B�̏��{�s�Ɣѓc�s�֍s�����@�ɏo�����܂����B���{�s�͏��{�鉺�́u�܂��Ȃ݊��������Ɓv�A�ѓc�s�́u���z�����d���Ɓv�ł��B���@�̊T�v�E���z�́A�ʋL�����Q�Ƃ��������B
�@�T��16��(��)�E17��(��)�̂Q���ԁA������s�c��݊��ψ���͐M�B�̏��{�s�Ɣѓc�s�֍s�����@�ɏo�����܂����B���{�s�͏��{�鉺�́u�܂��Ȃ݊��������Ɓv�A�ѓc�s�́u���z�����d���Ɓv�ł��B���@�̊T�v�E���z�́A�ʋL�����Q�Ƃ��������B �@���{�s�͎��ɂƂ��ẮA�����炭20���N�Ԃ�B�c���ɂȂ��Ă���͏��߂Ă̂��Ƃ��Ǝv���܂��B���̂��߁A�v���`���Ă������o�Ƃ͈قȂ��Ă��܂����B�g�X���͈ӊO�ƁA������܂�Ƃ��Ă���ȁh�g���{����āA����Ȃɏ��������������H�h�ƁB�܂��A���J�q�w�Z�����{�邩��߂����Ƃ��A�C���[�W�Ƃ͈قȂ��Ă��܂����B�鉺���ɍ��킹���u�܂��Â���v���i�s���̏��{�s�́A�Ԃ��ƕ����Ă݂����Ȃ�A����邽�����܂��������Ă��܂����B
�@���{�s�͎��ɂƂ��ẮA�����炭20���N�Ԃ�B�c���ɂȂ��Ă���͏��߂Ă̂��Ƃ��Ǝv���܂��B���̂��߁A�v���`���Ă������o�Ƃ͈قȂ��Ă��܂����B�g�X���͈ӊO�ƁA������܂�Ƃ��Ă���ȁh�g���{����āA����Ȃɏ��������������H�h�ƁB�܂��A���J�q�w�Z�����{�邩��߂����Ƃ��A�C���[�W�Ƃ͈قȂ��Ă��܂����B�鉺���ɍ��킹���u�܂��Â���v���i�s���̏��{�s�́A�Ԃ��ƕ����Ă݂����Ȃ�A����邽�����܂��������Ă��܂����B �@�h���n�́A�o�X�ňɓߒJ��쉺������̔ѓc�s�B�u�J�v�ƌĂԂɑ��������o���̎R���ڋ߂����ꏊ������A���͂��L���ꏊ������A�ɓߒn���͓Ɠ��̕��͋C���������o���Ă��܂����B�r���A��x�T�[�r�X�G���A�ɂċx�e�B����������x��T�����A�ǂꂾ���킩�炸�B�r���c���́u�ē��Ŕ��������ǁA��������͌����Ȃ��炵�����v�ƌ����܂��B�Ȃ�A�Ȃ�Łu��x�T�[�r�X�G���A�v���Č������������H�B���X�Ŕ������݂��ق���Ȃ���A����Ђ˂�n���ł����B
�@�h���n�́A�o�X�ňɓߒJ��쉺������̔ѓc�s�B�u�J�v�ƌĂԂɑ��������o���̎R���ڋ߂����ꏊ������A���͂��L���ꏊ������A�ɓߒn���͓Ɠ��̕��͋C���������o���Ă��܂����B�r���A��x�T�[�r�X�G���A�ɂċx�e�B����������x��T�����A�ǂꂾ���킩�炸�B�r���c���́u�ē��Ŕ��������ǁA��������͌����Ȃ��炵�����v�ƌ����܂��B�Ȃ�A�Ȃ�Łu��x�T�[�r�X�G���A�v���Č������������H�B���X�Ŕ������݂��ق���Ȃ���A����Ђ˂�n���ł����B �@���͓͂c��ڂƔ��A�����ĎR�B���n������A�X�͂���܂���B�O�Ɉ��݂ɍs�����ɂ��A�ړI�n�͌����܂���B��A���͈͂Èłɂǂ��Ղ�Ƃ���A�z�c�ɓ��������������P�����̂́A�C�r�L�ł͂Ȃ��J�G���̑升���ł����B
�@���͓͂c��ڂƔ��A�����ĎR�B���n������A�X�͂���܂���B�O�Ɉ��݂ɍs�����ɂ��A�ړI�n�͌����܂���B��A���͈͂Èłɂǂ��Ղ�Ƃ���A�z�c�ɓ��������������P�����̂́A�C�r�L�ł͂Ȃ��J�G���̑升���ł����B �@�E���������ɂ́A�ѓc�s�����͕W��550���[�g���̋u�̏�Ɉʒu���A�J��̂悤�ȉ����ɗ�����͕W��300���[�g���̓V����B�Ƃ������Ƃ́A�ѓc�s�����̂���u�ƓV����Ƃ̕W������250���[�g���Ƃ������ƁB����Ȃɂ��邩���ȁA�Ɣ��M���^�ł͂�����̂́A��͂������ɂ͂邩�����𗬂�Ă��܂��B�ѓc�s����������V������͂���Ŕ��Α��̋u������ƁA�����瑤�Ɠ������炢�̋u�̍����ƂȂ��Ă��܂��B���Â̐̂́A�����̋u�͂Ȃ����Ă����̂��낤�ȂƁA�n�`�̂������낳�ɋ����͐s���܂���B
�@�E���������ɂ́A�ѓc�s�����͕W��550���[�g���̋u�̏�Ɉʒu���A�J��̂悤�ȉ����ɗ�����͕W��300���[�g���̓V����B�Ƃ������Ƃ́A�ѓc�s�����̂���u�ƓV����Ƃ̕W������250���[�g���Ƃ������ƁB����Ȃɂ��邩���ȁA�Ɣ��M���^�ł͂�����̂́A��͂������ɂ͂邩�����𗬂�Ă��܂��B�ѓc�s����������V������͂���Ŕ��Α��̋u������ƁA�����瑤�Ɠ������炢�̋u�̍����ƂȂ��Ă��܂��B���Â̐̂́A�����̋u�͂Ȃ����Ă����̂��낤�ȂƁA�n�`�̂������낳�ɋ����͐s���܂���B �@�隬�Ƃ͂������̂́A�Ƃ��ɍH�v���ꂽ�ē���z�u���Ă���킯�ł��Ȃ��A���̂����肪�隬�ł���A�Ƃ������x�ł��B�O�q�����悤�ɁA���̂�����͋u�̏�B�������ѓc��́A�V����̓���ɓ˂��o�������̂悤�ȋu�̐�[�����Ɍ��Ă��Ă������߁A�隬�̒��S�Ɍ������ĉ����Ă������Ƃ́A�u�̍��E�̕�������ɋ��܂��Ă����Ƃ�����B�悤����ɁA�E���݂Ă������݂Ă��A����200���[�g���]�̒f�R��ǂ��҂��\���Ă���Ƃ������Ƃł��B�����̓r���ɂ͐}���ق���j�I�������Ƃł����������Ȍ����̏��w�Z�A�����߂��炵�����p�قȂǂ�����A�����ɂ��̂͏�̕~�n���������Ǝv���邽�����܂��ł��B�u�̐�[�ɂ͐_�Ђ�����A��������͎O���ʂɌ��n����A���Ȃ��̌i�F������܂����B
�@�隬�Ƃ͂������̂́A�Ƃ��ɍH�v���ꂽ�ē���z�u���Ă���킯�ł��Ȃ��A���̂����肪�隬�ł���A�Ƃ������x�ł��B�O�q�����悤�ɁA���̂�����͋u�̏�B�������ѓc��́A�V����̓���ɓ˂��o�������̂悤�ȋu�̐�[�����Ɍ��Ă��Ă������߁A�隬�̒��S�Ɍ������ĉ����Ă������Ƃ́A�u�̍��E�̕�������ɋ��܂��Ă����Ƃ�����B�悤����ɁA�E���݂Ă������݂Ă��A����200���[�g���]�̒f�R��ǂ��҂��\���Ă���Ƃ������Ƃł��B�����̓r���ɂ͐}���ق���j�I�������Ƃł����������Ȍ����̏��w�Z�A�����߂��炵�����p�قȂǂ�����A�����ɂ��̂͏�̕~�n���������Ǝv���邽�����܂��ł��B�u�̐�[�ɂ͐_�Ђ�����A��������͎O���ʂɌ��n����A���Ȃ��̌i�F������܂����B �@�u���{�s�v�ƌ����Α��A�u���{��v�Ǝ��͓�����B�ʖ��u�G(���炷)��v�Ƃ��Ă�A���{�ŌÂ��ւ鍕�F�̍���d�V��́A���{�s��K���l�Ȃ炾������ڂɂ�����j�I�������ł���B���킹�āA���{�s�ɂ́u���J�q�w�Z�v������B1876�N����1964�N�܂ŏ��w�Z�Ƃ��Ďg���Ă����[�m�����z���ŁA���̏d�v�������Ɏw��B���{�邩��͓k���V�����x�̂Ƃ���ɂ���B�����x�̎҂ɂ��A���ꂭ�炢�̒m����A�����ނقǂɏ��{�s�͗L���ł���B���̏��{�s���n�揤�Ɛ��ނ̊�@���}���A�u�܂��Ȃ݊��������Ɓv�Ɏ��g�Ƃ����̂�����A���X�����Ă���B
�@�u���{�s�v�ƌ����Α��A�u���{��v�Ǝ��͓�����B�ʖ��u�G(���炷)��v�Ƃ��Ă�A���{�ŌÂ��ւ鍕�F�̍���d�V��́A���{�s��K���l�Ȃ炾������ڂɂ�����j�I�������ł���B���킹�āA���{�s�ɂ́u���J�q�w�Z�v������B1876�N����1964�N�܂ŏ��w�Z�Ƃ��Ďg���Ă����[�m�����z���ŁA���̏d�v�������Ɏw��B���{�邩��͓k���V�����x�̂Ƃ���ɂ���B�����x�̎҂ɂ��A���ꂭ�炢�̒m����A�����ނقǂɏ��{�s�͗L���ł���B���̏��{�s���n�揤�Ɛ��ނ̊�@���}���A�u�܂��Ȃ݊��������Ɓv�Ɏ��g�Ƃ����̂�����A���X�����Ă���B �@�ǂ̂悤�ȃX�^�C���̊X���݂ɂ��Ă������͋�悲�Ƃɒn��̐��i���c��������A�s�̒S���E�����R�[�f�B�l�[�^�[�ƂȂ�A���X�͑�w�����̃A�h�o�C�X���āA���߂��Ă����B�u���s����̘A���v�Ƃ̂��ƁB�������A�u�܂��Ȃ݂������Ō������Ȃ��̂́w�d���̒n�����x�v�ƁA�������ꂽ�S���҂͏q�ׂ�B�u����ɂ���ĕ��s�҂��������A�X�܂��Ȃ��Ȃ����v�Ƌ��������B�S���e�n�Œn��̂܂��������̂��߂̎��Ƃ��W�J����Ă��邪�A����u���{��v�����A���Ղ������������鏼�{�s�̎��g�݂́A���ɂ��Ȃ������̂ł���Ɗ�����B���́u�܂��Ȃ݊��������Ɓv�ɂ���Đ��܂�ς�����u�������̉�فv�́A����ɂ��ł́A���̃K�C�h�u�b�N�ɂ��o�ꂷ��قǂɗL���ƂȂ��Ă���B
�@�ǂ̂悤�ȃX�^�C���̊X���݂ɂ��Ă������͋�悲�Ƃɒn��̐��i���c��������A�s�̒S���E�����R�[�f�B�l�[�^�[�ƂȂ�A���X�͑�w�����̃A�h�o�C�X���āA���߂��Ă����B�u���s����̘A���v�Ƃ̂��ƁB�������A�u�܂��Ȃ݂������Ō������Ȃ��̂́w�d���̒n�����x�v�ƁA�������ꂽ�S���҂͏q�ׂ�B�u����ɂ���ĕ��s�҂��������A�X�܂��Ȃ��Ȃ����v�Ƌ��������B�S���e�n�Œn��̂܂��������̂��߂̎��Ƃ��W�J����Ă��邪�A����u���{��v�����A���Ղ������������鏼�{�s�̎��g�݂́A���ɂ��Ȃ������̂ł���Ɗ�����B���́u�܂��Ȃ݊��������Ɓv�ɂ���Đ��܂�ς�����u�������̉�فv�́A����ɂ��ł́A���̃K�C�h�u�b�N�ɂ��o�ꂷ��قǂɗL���ƂȂ��Ă���B �@�ѓc�s�̑��z�����d���Ƃ͑����̃}�X�R�~�łƂ�グ���A�����]���Ă���B���Ə����Ɍb�܂ꂽ���̒n�ŁA���z���p�l���u���Ђ��ܔ��d���v���s���o���ŕ��y������g�݂ł���B�}�X�R�~�ɂ��ƁA�u���z���p�l���͓����A�ѓc�s��ߗׂ̕ۈ牀�Ȃnj����{��162�ӏ��Ő�s�I�ɕ��y���i�v�Ƃ���A�u���܂ł͈�ʉƒ�ɂ��Ώۂ��L���Ă���v�Ƃ���Ă���B�悤����ɁA�����͎s�P�ƂŌ����{�݂Ȃǂɑ��z���p�l���̐ݒu�������߂Ă����A���Ɉ�ʉƒ�ւ̕��y�Ɏ��g��ł���Ƃ������́B�����{�ݓ��ւ̂���Ȃ镁�y�ƈ�ʉƒ�ւ̕��y�ɍۂ��āA�s���o���ɂ�鑾�z���p�l�����y�Ƃ����`�Ԃ��̗p����Ă������炵���B
�@�ѓc�s�̑��z�����d���Ƃ͑����̃}�X�R�~�łƂ�グ���A�����]���Ă���B���Ə����Ɍb�܂ꂽ���̒n�ŁA���z���p�l���u���Ђ��ܔ��d���v���s���o���ŕ��y������g�݂ł���B�}�X�R�~�ɂ��ƁA�u���z���p�l���͓����A�ѓc�s��ߗׂ̕ۈ牀�Ȃnj����{��162�ӏ��Ő�s�I�ɕ��y���i�v�Ƃ���A�u���܂ł͈�ʉƒ�ɂ��Ώۂ��L���Ă���v�Ƃ���Ă���B�悤����ɁA�����͎s�P�ƂŌ����{�݂Ȃǂɑ��z���p�l���̐ݒu�������߂Ă����A���Ɉ�ʉƒ�ւ̕��y�Ɏ��g��ł���Ƃ������́B�����{�ݓ��ւ̂���Ȃ镁�y�ƈ�ʉƒ�ւ̕��y�ɍۂ��āA�s���o���ɂ�鑾�z���p�l�����y�Ƃ����`�Ԃ��̗p����Ă������炵���B �@���Ƃ̌����͎s������̏o���B�u��450���̑S���̎s�������Q���~�̏o�����A38 �̑��z�����d���ƏȃG�l���M�[���Ƃ�W�J�v�Ǝ����ɋL����Ă���B���̌��������ƂɁA�ѓc�s���̌ˌ��ďZ��̉����ɑ��z���p�l�����u�[���v�~�Őݒu�B����ɁA���X19,800�~�̗��p�������X�N�ԁA�u���Ђ��ܐi���G�l���M�[(��)�v�Ɏx�����Ă��炤�Ƃ��Ă���B����ɂ���āA�p�l���ݒu��p200���~���y�C�ł���Ƃ����B�u19,800�~�v�͒����d�͂̓d�C�����Ɣ�r����ƌ��X�T�`�U��~�̊����ƂȂ邪�A�ߓd�ɓw�߂�Γw�߂�قǁA�����d�͂ւ̔��d������������(���X���ςS��~���x)�Ƃ������̂ŁA���S���͂����傫�Ȃ��̂Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B�������A�p�l���ݒu10�N�ڂɂ͗��p����(19,800�~)�̎x�������Ȃ��Ȃ邽�߁A�t�ɁA���d�ł̎�������������B����A�o���҂ɑ��ẮA���d���v�̈ꕔ�����z���Ƃ��Ē���I�Ɏx������Ƃ������́B
�@���Ƃ̌����͎s������̏o���B�u��450���̑S���̎s�������Q���~�̏o�����A38 �̑��z�����d���ƏȃG�l���M�[���Ƃ�W�J�v�Ǝ����ɋL����Ă���B���̌��������ƂɁA�ѓc�s���̌ˌ��ďZ��̉����ɑ��z���p�l�����u�[���v�~�Őݒu�B����ɁA���X19,800�~�̗��p�������X�N�ԁA�u���Ђ��ܐi���G�l���M�[(��)�v�Ɏx�����Ă��炤�Ƃ��Ă���B����ɂ���āA�p�l���ݒu��p200���~���y�C�ł���Ƃ����B�u19,800�~�v�͒����d�͂̓d�C�����Ɣ�r����ƌ��X�T�`�U��~�̊����ƂȂ邪�A�ߓd�ɓw�߂�Γw�߂�قǁA�����d�͂ւ̔��d������������(���X���ςS��~���x)�Ƃ������̂ŁA���S���͂����傫�Ȃ��̂Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B�������A�p�l���ݒu10�N�ڂɂ͗��p����(19,800�~)�̎x�������Ȃ��Ȃ邽�߁A�t�ɁA���d�ł̎�������������B����A�o���҂ɑ��ẮA���d���v�̈ꕔ�����z���Ƃ��Ē���I�Ɏx������Ƃ������́B �@���������̑�ЊQ���@�ɁA���R�G�l���M�[�ɑ傫�ȊS���W�܂��Ă���B���Ǝ��Ԃ��N��1,900���Ԉȏ�̓��{�́A�S���ǂ��ł����z�����d�ɓK���Ă���Ƃ����B�܂��͌����{�݂���A�����ă}���V�����Ȃǂ̏W���Z��A��ʉƒ�ցB���˔\�����̐S�z�̂Ȃ����R�G�l���M�[�ւ̓]�������A�q�ǂ��⑷�ցA���̒n������n���Ă�����X��l�̐Ӗ��ƂȂ�B������s�ɂ́u�Z��p�V�G�l���M�[�@�퓙���y���i�⏕�v���x�����邪�A�s���C���̎��g�݂ł́A�q�ǂ������ɖ��邢������ۏႷ����̂Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B��i�����̂̎��g�݂ɑ傢�Ɋw�сA������s�Ǝ��̎{�W�J�ł���Ǝv���B
�@���������̑�ЊQ���@�ɁA���R�G�l���M�[�ɑ傫�ȊS���W�܂��Ă���B���Ǝ��Ԃ��N��1,900���Ԉȏ�̓��{�́A�S���ǂ��ł����z�����d�ɓK���Ă���Ƃ����B�܂��͌����{�݂���A�����ă}���V�����Ȃǂ̏W���Z��A��ʉƒ�ցB���˔\�����̐S�z�̂Ȃ����R�G�l���M�[�ւ̓]�������A�q�ǂ��⑷�ցA���̒n������n���Ă�����X��l�̐Ӗ��ƂȂ�B������s�ɂ́u�Z��p�V�G�l���M�[�@�퓙���y���i�⏕�v���x�����邪�A�s���C���̎��g�݂ł́A�q�ǂ������ɖ��邢������ۏႷ����̂Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B��i�����̂̎��g�݂ɑ傢�Ɋw�сA������s�Ǝ��̎{�W�J�ł���Ǝv���B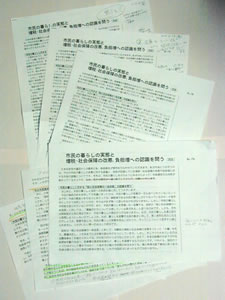
 �@�������̋c�Ăɔ�������̗��R�́A�s�c��̂��ׂẲ�h�����߂Ă����A�Ǘ��K�����ł����Ԃł̎擾�c�ĂƂ͂Ȃ��Ă��Ȃ����Ƃł��B�s���𗬃Z���^�[���܂ނP�|III�X��́A���̒n���҂Ƃ̌����W����������敪���L�����̕~�n�`�ԂƂȂ��Ă��邽�߁A�~�n�̊Ǘ��E���p���@����茈�߂邱�Ƃ����߂��܂��B�������A�擾�c�Ă���o����Ă���ɂ�������炸�A�����ł���܂łɎ����Ă��܂���B��t�s���́u�z�[���擾�ƊǗ��K��̓Z�b�g�ł͂Ȃ��v�Əq�ׂ܂����A���Ԓn���҂̌������������e���A�ٔ����N����Ȃ��ł����߂��Ă����ĊJ�����ƂƂ����o�܂���݂āA���[�������܂��Ă��Ȃ��Ȃ��ł̊Ǘ��E�^�c���ʂ����ăX���[�Y�ɍs����̂��A�N�������O����͓̂��R�ł��B�z�[���擾�c�Ē�o�̍ۂɂ͒����ł����Ԃł̊Ǘ��K����������Ƃ��K�v�Ƃ����̂́A�s�����̊Ǘ��E�҂������l���ł��B����͎s�c��ɒ�o���ꂽ�u���c�L�^�v�ł̊Ǘ��E�҂̔������e�ŏؖ�����Ă��܂��B
�@�������̋c�Ăɔ�������̗��R�́A�s�c��̂��ׂẲ�h�����߂Ă����A�Ǘ��K�����ł����Ԃł̎擾�c�ĂƂ͂Ȃ��Ă��Ȃ����Ƃł��B�s���𗬃Z���^�[���܂ނP�|III�X��́A���̒n���҂Ƃ̌����W����������敪���L�����̕~�n�`�ԂƂȂ��Ă��邽�߁A�~�n�̊Ǘ��E���p���@����茈�߂邱�Ƃ����߂��܂��B�������A�擾�c�Ă���o����Ă���ɂ�������炸�A�����ł���܂łɎ����Ă��܂���B��t�s���́u�z�[���擾�ƊǗ��K��̓Z�b�g�ł͂Ȃ��v�Əq�ׂ܂����A���Ԓn���҂̌������������e���A�ٔ����N����Ȃ��ł����߂��Ă����ĊJ�����ƂƂ����o�܂���݂āA���[�������܂��Ă��Ȃ��Ȃ��ł̊Ǘ��E�^�c���ʂ����ăX���[�Y�ɍs����̂��A�N�������O����͓̂��R�ł��B�z�[���擾�c�Ē�o�̍ۂɂ͒����ł����Ԃł̊Ǘ��K����������Ƃ��K�v�Ƃ����̂́A�s�����̊Ǘ��E�҂������l���ł��B����͎s�c��ɒ�o���ꂽ�u���c�L�^�v�ł̊Ǘ��E�҂̔������e�ŏؖ�����Ă��܂��B