�c��ƑI���̂͂��܂�
�@12��14�����[�̏O�@�I���́A�����}�Ɛ^��������Ό��ł�����{���Y�}���c�Ȃ�傫���L�����ʂƂȂ����B������s�������[�����[���J�[���鑍���̈�قœ��{���Y�}�̊J�[����l�߂Ă������̂��Ƃɂ́A�䂪�}�̋c�Ȋl�����g�у��[���ɂЂ�ς�ɔ�э���ł���B��������Ȃ���A���͋v�X�̋������o�����B
�@�J�[�͂܂��A���I���悩�炷���߂�ꂽ�B�䂪�}�́u�䂤�����v�[�́A�����}�▯��}�̕[�Ƃ͔�ׂ�قǂɂ��Ȃ�Ȃ����A����ł��A���̉��ł���܂łɌ������Ƃ��Ȃ������͂��������Ă����B���I���搧�ɂȂ��Ă���A������s�ł͏��߂Ă̂W��[����������̂ł���B
�@�ł́A���}�����������[�͂ǂ��ł��낤���B���I����͌��҂��R���Ȃ̂ŁA�u�䂤�����v�����̕[���邱�Ƃ͏\���ɂ��肤�邱�Ƃł���B���������[�͈Ⴄ�B���}��10���o�Ă���̂ł���B���R�ɕ[��������A�u�䂤�����v�قǂɂ͂����Ȃ��ł��낤�A�Ǝ��͎v�����B
�@���[�̊J�[��Ƃ������ނȂ��ŁA���}���Ƃɕ[�𑩂˂���̏�ł́A�u�����}�v�Ɓu����}�v���������������J��L����B�O�i�́u�y�������v�Ɓu�����l�v�̑��������邪���Ƃ��ł���B�������A���̖T��Łu���{���Y�}�v���K���Ɍ������Â��A�u�ېV�̓}�v�����Ԃɉ���鐨���������Ă����B����A�u�����}�v�͌����Ƃ�A�u������̓}�v��u�Ж��}�v�͂͂邩���Ȃ��ł������ł���B�u�����̓}�v�͂ǂ�����������N�������悤�ł���B
�@�J�[���I����Ă݂�ƁA�u�����}�v��u����}�v�ɂ͈�n�g����n�g�������ꂽ���A�u���{���Y�}�v�͓��X�̂R�ʁB�[�����u�䂤�����v��100�[�]�����Ă����B�匒���ł���B���{���Y�}�͉��I�O�̂W�c�Ȃ���A�\�Z��Ȃ��@�Ă��O�@�ŒP�ƂŒ�o�ł���21�c�ȂւƑ���i�B�䂪�}�̂�����l�̊J�[����l�ƌł���������킵���B
�@�O�@�I����12���Q������X�^�[�g�������A���̂S���O��11��28�����珬����s�̒��s�c��X�^�[�g�B�����ʂ�A�c��ƑI���̓̑��܂ƂȂ����B���̗����ɂ͂��܂�Ȃ��ŁA����11��29��(�y)�̌ߌ�A�s������J�ÁB�I�����ԋ߂ɍT���������ɂ�������炸�A�吨�̐l�ɂ����ł����������B�o�c�e�œ����z�t�����Q�̃��W�������f�ڂ��܂��̂ŁA�����Ԃ̂�����͂���ǂ��������B
�u���[�X���ɔ����v�����̓^���Ɖۑ�iPDF267KB�j
���N�x�u�L�����E�ϑ����v�I���p���[�h�iPDF235KB�j
�i2014�N12��19���t�j
�W��{�ݗL�����̐�����
�@���N�S������W��{�݂S�ӏ��̗L�������v�悵�Ă��鏬����s�́A10��28������e�{�݂ŗ��p�Ґ�������X�^�[�g�B����10��30��(��)�ߌ�V������̑O�������V���ق̐�����Ɋ���o�����B�Q���҂͎��܂߂�18�l�A�s���͕����A�ے��A�W���ȂǂS�l�ł���B
�@�`���A�s������A�L���������̍l�����Ɏ��������R�Ɨ��p�����̗\��z����ы��z�̍������b���ꂽ�B����ɑ��ďo�Ȏ҂���́A�s���q�ׂ�u��v�ҕ��S�v�̍l������u�{�݂��g���l�Ǝg��Ȃ��l�ƂŌ������Ɍ����v�Ƃ̐����Ɉ٘_���o����A������s�̂����̎g�����ւ̋^�₪�q�ׂ�ꂽ�B�܂��u�L���ƂȂ�A��̉��������グ�邩���p�����炳�Ȃ��ƂȂ�Ȃ��v�Ƃ̈ӌ����o����A�W��{�ݗ��p�c�̂̑唼���߂�s���T�[�N���̉^�c�ɉe�����N���邱�Ƃւ̌��O�������ꂽ�B����A�L�������j���x������ӌ����o����A�u���V���ق͓����s����s�����Y�̎g�p���Ė����Ŏs����Ă���A���p��������邱�ƂɂȂ�ƁA�s�����Y�����g�p�̋��v���ɔ�����̂ł͂Ȃ����v�Ƃ̐��I�Ȉӌ����q�ׂ�l�������B
�@������͎��^�������W�X�ƍs�Ȃ��B�Q���҂̑唼��“�L�����ɂȂ����ꍇ�A�����̒c�̂͌��ɂǂꂭ�炢�̕��S�ɂȂ�̂��낤��”�Ƃ̃C���[�W���v���߂��炵�Ă���l�q�ł������B�����ɂ́u�L�����͍��邯��ǁA�L���ƂȂ����ꍇ�ɂ́A�ǂꂭ�炢�������K�v�ɂȂ�̂��낤���v�Ƃ̔��R�Ƃ����v���ŎQ�����Ă���Ƃ����ӂ��ł���B
�@���̂��Ƃ́A������s���V��11������W��13���܂Ŏ��{�������p�҃A���P�[�g�̌��ʂɂ�����Ă���B�u�����ŗǂ��v(66.8��)�u�ł���Ζ����̕����ǂ��v(25.3��)��92.1�����߁A�u�L���ł��ǂ�(�L���ł���ނ����Ȃ�)�v(5.3��)�u�L���ł���ׂ��v(0.8��)�̂U.1���Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ������������Ă��Ȃ���A�L�������ꍇ�̗��p�ӌ��ɂ��Ắu�L���Ȃ痘�p���Ȃ��v��28.2���ɑ��āA�u���z�Ȃ痘�p�������v(54.1��)�u�L���ł����p�������v(9.5��)�����킹��63.6���ƂȂ��Ă��邱�Ƃƕ�������B�悤����ɁA�{�ݐ������Ȃ����Ƃ���A���Ƃ��L���ɂȂ����Ƃ��Ă��A�������p���Ă��邻�̎{�݂��g�킴������Ȃ��Ƃ������Ƃł���B����āA�A���P�[�g���ʂ◘�p�Ґ�����̌��ʂ��u�L������F�߂��v�Ƃ����ӂ��ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B
�@�Ƃ���ŏ�����s�́A����̗��p�Ґ�����ŗ��p�҂��牽�����Ǝv�����̂ł��낤���B���p�Ґ�������ē�����u�s��v10��15���t�ł́A���̂悤�ɋL���Ă���B�u�s�ł́A��R���s�������v��j�Ɋ�Â��A�w�l��فA��V����فA�O�������V���ق���э����㐅��ق̗L�����ɂ��Č������Ă����Ƃ���ł����A�s�Ƃ��Ĉ��̍l�����܂Ƃ܂������Ƃ���A�e�ٗ��p�҂�ΏۂɁA��������J�Â��܂��v�B�܂��A������ɔz�t���ꂽ�����ł́u�L�����ɂ��Č������Ă����Ƃ���ł����A���̕���������܂���邱�Ƃ���A���O�ɗ��p�҂̕��X�ɂ������̏�A���ӌ����f�����߁A��������J�Â����Ă��������܂����v�Əq�ׂĂ���B�܂�u�L�����ɑ�����̍l���A���������܂Ƃ܂��Ă����̂ŁA�ӌ����������������v�Ƃ������Ƃł���B�ł́A�ӌ������������Ăǂ�����̂��B
�@�L�������O��ƂȂ��Ă���B���������N�S�����炾�Ƃ����B���̂����ňӌ������������Ƃ������Ƃ́A������Łu�L�����͔��v���������߂��Ƃ��Ă��A�ӂɉ���Ƃ������Ƃł͂Ȃ����B���邢�́A���p�����z��\��z���������Ă����܂�Ȃ��A���邢�͗��p�����̌��Ɣ͈͂◘�p���Ԙg�ɂ��āA�����̗]�n������Ƃ������ƂȂ̂��낤���B
�@���̂��Ƃ́A�V�����{����W�����{�ɂ����čs�Ȃ�ꂽ���p�҃A���P�[�g�ł�������B�A���P�[�g�ł́u�����ŗǂ��v�u�ł���Ζ����̕����ǂ��v��92.1�����߂Ă����ɂ�������炸�A������s�͗L�����Ɍ����Ă̋�̉��������߂Ă����̂ł���B
�@���p�҃A���P�[�g�̌��ʂ́A������s�Ƃ��Ă͂��Ȃ炸�������҂������̂Ƃ͂Ȃ�Ȃ������Ƃ�����B���̂��ߗ��p�Ґ�����ł́A���p�҃A���P�[�g���ʂ���������������o����Ȃ������̂ł���B���ǂ̂Ƃ���A���p�҃A���P�[�g�����p�Ґ�������A�`�����̂��̂ɂ����Ȃ��̂ł���B�u��ɗL�������肫�v���A������s�̊�{�p���ƂȂ��Ă���B�Ȃ��A������s�����p�Ґ�����Ŏ������L�����T�v(�\��)�͈ȉ��̂Ƃ���ł���B
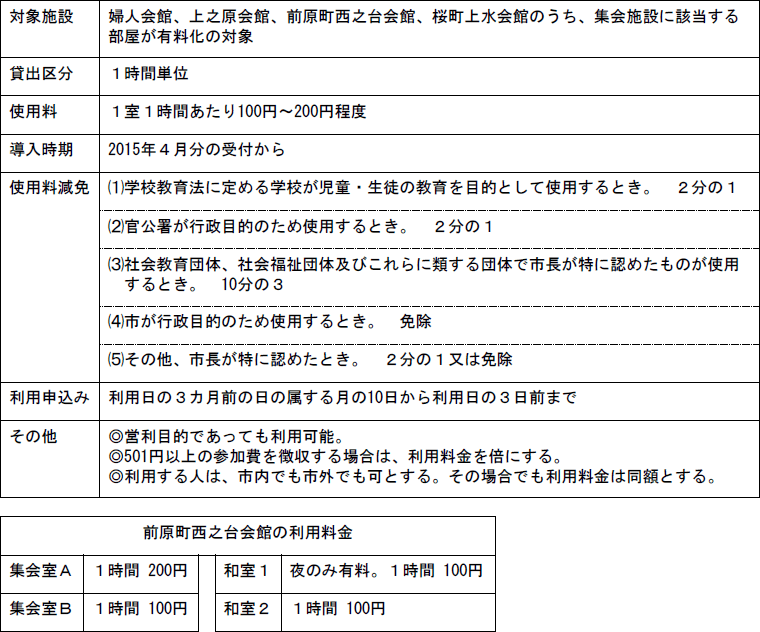
�i2014�N11���R���t�j
���ڐ���
 �@�n�������@��74���́u���̐���܂��͉��p�v�ʒn�������c�̂̒��ɑ��Đ������邱�Ƃ��ł���ƋK�肵�Ă���B���͈̏�ʓI�ɂ́u���ڐ����v�ƌĂ�Ă���A������s�ł͂��̋K������p���āA�V��18������W��17���܂ł̂P�J���ԁA���ڐ��������^�����W�J����Ă���B �@�n�������@��74���́u���̐���܂��͉��p�v�ʒn�������c�̂̒��ɑ��Đ������邱�Ƃ��ł���ƋK�肵�Ă���B���͈̏�ʓI�ɂ́u���ڐ����v�ƌĂ�Ă���A������s�ł͂��̋K������p���āA�V��18������W��17���܂ł̂P�J���ԁA���ڐ��������^�����W�J����Ă���B
�@���ڐ����ŋ��߂Ă���̂́A������s���A���Ԃ��s�Ȃ�����������w�����Q�n��ĊJ�����Ƃɐŋ��𓊓����悤�Ƃ��Ă��邱�ƁA����сA������s�����̍ĊJ���ɂ����ėp�r�n���e�ϗ��E���������ɘa���A�����w�r���Q�������Ă���v��ɂȂ��Ă��邱�Ƃɑ��āA������s���̗L���҂̓��[�ɂ���Ă��̍ĊJ�����Ƃ��s�Ȃ������~���邩�����߂����Ăق����A���̂��Ƃ������������𐧒肵�Ăق����Ƃ������́B������s�̌����ł���w�O�̂܂��݂̍���͎s�������߂�ׂ��Ƃ����A���ɓ�����O�̎��g�݂ł���B
�@�����^���̈���ł��鎄���A���������̂V��18������ɃX�[�p�[��w���Ńn���h�}�C�N������A�����̌Ăт������s�Ȃ��Ă��邪�A���g�̐��N�������L�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������ɂ�������炸�A�Ⴂ�����܂߂āA�����̕��X�������ɉ����Ă���Ă���B
�@���̏����^���͖@���ɂ��ƂÂ��čs�Ȃ��Ă��邱�Ƃ���A�n�������@��74���̂S�ł́A���̉^����ۏႷ�邽�߂̋K�肪�������Ă���B��̓I�ɂ́A�u�������Җ��͏����^���҂ɑ��A�\�s�Ⴕ���͈З͂������A���͂�������ǂ킩�����Ƃ��v�u��ʎႵ���͏W��̕ւ�W���A���͉�����W�Q���A���̑��U�v���p���s���̕��@�������ď����̎��R��W�Q�����Ƃ��v�u�������ҎႵ���͏����^���Җ��͂��̊W�̂���Ў��A�w�Z�A��ЁA�g���A�s�������ɑ���p���A����A���A���̑�����̗��Q�W�𗘗p���ď������Җ��͏����^���҂��Д������Ƃ��v�́A�S�N�ȉ��̒����Ⴕ���͋�������100���~�ȉ��̔����B�u���̐���Ⴕ���͉��p�̐����҂̏������U�����Ⴕ���͂��̐��������Җ��͏����낻�̑��̏��̐���Ⴕ���͉��p�̐����ɕK�v�ȊW���ނ�}���A�ʉ�Ⴕ���͒D�悵���ҁv�́A�R�N�ȉ��̒����Ⴕ���͋�������50���~�ȉ��̔����A�Ƃ������̂ł���B
�@�����^�����i�W���A�s���̂Ȃ��ɍĊJ�����Ƃ̖��_���Z������Ȃ��ŁA���̏����^����������悭�v���Ă��Ȃ��ꕔ�̊Ԃ���A�u������s�͂����͏o���Ȃ��v�Ƃ��u���̏����^���̓f�^�������v�ȂǂƈӐ}�I�ɗ��z���铮�����o�Ă���B���ꂾ���A�ނ�͏ł�͂��߂Ă���Ƃ������Ƃł��낤�B
�@�v���Ԃ��Ă������������̂́A�U�N�O�̏H�A����������w����̍ĊJ���r�����Ɏs�������ɂ�����v�悪��̉����������Ƃ��ɒ��ڐ����^�����N���A���̉^���ɓG���������}�̌��E�c���̂����Q�l�����N�R���̎s�c�I�ŗ��I�����Ƃ��������ł���B�s���̈ӎv�ɔ����鐨�͂́A�s�����猵�����R������Ƃ������Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B
�@�~�J���J���A�ҏ��̓��X���}�����B�u�q����͐g�̂��ׂ�����A�����ɂ͋����ł���H�v�ƌ����l������B����������͎��Ԃ����܂�ɂ��m��Ȃ��߂��錩���ł���B������т�̂ł���B���ւ̏�ɃX������u�������Ƃ��A�ď�̍אg�̐g�͔̂���Ԃ�悤�Ɋ�����т�B���V���Ńn���h�}�C�N���I�������́A������т��g�̂��Ԃ点�邽�߂ɁA������J�~������ɂ܂�Ȃ���A�̏o�郂�m����C�Ɉ��݊����B
�@�Ȃ��A�V��19���̎s����Ŕz�z�������W�������o�c�e�t�@�C���Ōf�ڂ��܂��̂ŁA���Q�Ƃ���������K���ł��B
�����҂̗��v�̂��߂̓����Q�n��ĊJ���iPDF716KB�j
�i2014�N�V��30���t�j
�X�����킷����������w�����Q�n��ĊJ��
�@���Z�𑲋Ƃ����̂�37�N�O�̂R���W���B���ꂩ��15����̂R��23���ɁA�E�������킩��Ȃ������ɒP�g�㋞�B�㋞�������̓��ɏ�����s�ɐg��u���A�ȗ��A�����܂ŏ�����s�ɏZ�ݑ����Ă���B
�@�ŏ��ɏZ�̂͊��쒬�S���ځB��Ђɍs�����߂ɗ��p���铌������w�̏��z�[���͍��˂ł͂Ȃ��A�Ȃ̂Ƀz�[������x�m�R�����邱�Ƃ��ł����B���ɐg��u�����͓̂����S���ځB���̎��ɂ͕x�m�R�̌���������Ɍ������������сA�z�[������͕x�m�R��q�ނ��Ƃ͂ł��Ȃ��Ȃ��Ă����B
�@����������w�𗘗p����悤�ɂȂ����̂́A�s�c��c���ɂȂ锼�N�O�́A�ш�쒬�S���ڂɈڂ�Z��1992�N10������ł���B���̍��̕���������w�͍��Ƃ͔�ׂ悤���Ȃ��قǂɌÂт��ؑ��̉w�ɂł��������A�߂���ǂ��ƂȂ����D�̔O�ɂЂ��邱�̍��ł���B
�@�X���ς��䂭�̂́A�Ȃ��s�v�c�ł͂Ȃ��B�l�����āA�����Ő�������l������A�_�n��n�����̂��̂Ɏp��ς��A�����������A�w�ɂ�����ς����A���H�����ˉ����Ă����͓̂����ł���B�������A�w�O�J���͂����P���ł͂Ȃ��B���Ƃɍ���̍ĊJ�����Ƃ́A�X�Â���Ƃ��Ăَ͈��ł���A�X�݂̍�����̂��̂��������̂ƂȂ�B
�@�S��26���ɊJ�������̎s����ł́A�u�w�O������Ȃӂ��ɂ���Ă��܂��͍̂���v�u������s�ɂ͂���ȊX�Â���͎�����Ȃ��v�u�Ȃ�Ƃ��~�߂Ăق����v�̐������o�����B�w�O�����킢������̂ɂȂ邱�Ƃɂ́A������٘_�͂Ȃ��B�������A�����w�r��������ɂQ�������A�w�O���������키�悤�ȊX�݂̍���ɂ͖�肪����ƁA�Q���҂͌������낦�Č����B
�@�ĊJ�������̌����҂�60�l�ł���B����60�l�̂��߂ɕ⏕����60���~���[�Ă��A�����������w�r�����������ԁ|�|�B���݂̍����s�v�c�Ɋ����Ȃ���t�s���́A�s�����o�ƍ��{����Y���Ă���ƌ��킴��Ȃ��B�݂Ȃ���͂������v�����낤���B
�@�s����ł́A������s������������������w�����Q�n��ĊJ�����Ƃ̊T�v���܂Ƃ߂����W������z�z�B�o�c�e�t�@�C���Ōf�ڂ���̂ŁA���Ђ����������������B�Ȃ��A���W�����R���ڂ́u������s�͂������傫�Ȏ��Ƃ�����Ă���v�̕\���́u�V�S�~�����{����(�R�s����)�v�́u28��4,330���~�v�́A��N11��28���t�̐V���Ɍf�ڂ��ꂽ���l�ł���B
�X�����킷����������w�����Q�n��ĊJ���iPDF941KB�j
�i2014�N�T���Q���t�j
�S�g�Ⴊ����(��)�̉��l�h�����Ƃ��k��
�@������s�͍��N�x����A�ݑ�̐S�g�Ⴊ����(��)�ւ̉��l�h�����Ƃ��A����ɏk�����悤�Ƃ��Ă���B���R��h�����Ă������̂��A���Q��Ɍ��炷�Ƃ������̂ŁA�P����̗��p���Ԃ͂W���ԂƂȂ��Ă���B���̎��Ƃ́A�Ƒ��̓˔��I�ȕa�C��}�p���ŁA�ꎞ�I�ɉ���K�v�Ƃ���S�g�Ⴊ���҂⎙���̂���ƒ�ɉ��l��h������Ƃ������́B2012�N�x��22��6,100�~�̗\�Z���[�ĂĂ���B
�@�s�̐����́A���Ƃ���������s�������́u�s���]���v�ɂ����āA�u���Ək���ƂȂ������Ƃ���v�Ƃ������́B�ł́A���̎��Ƃɑ��āA�ǂ̂悤�ȕ]�������ꂽ�̂ł��낤���B
�@�u�������ƕ]���V�[�g�v�ł́A�ȉ��̋L�ڂ��o�ꂷ��B�u���݂܂łɎ��{���@�̌����������s�Ȃ��Ă��Ȃ��v���R�ɂ��āA�u�{���Ƃ͎����x���@���{�s�����O���瑱���Ă���A�����쓙���[�����Ă������݂̕����ɂ͍���Ȃ����Ƃ��Ɗ�����B�������A���N���p��]�҂�����Ō��������s���ƁA���l�̓o�^�Ґ��y�сA�h�������̌����������܂�A�s���̕s���v�ɂȂ�ƍl�����邽�ߌ�����ێ������v�B�u���_�v�ɂ��ẮA�u�����s���ݏZ�̖��ԓĎu��(��ɉ��l�h����]�҂̋ߗׂ�F�l)�����l�Ƃ��ēo�^���A���̉��h����p������ŕ��S������{���@�ɖ�肪����B�\�����R������ѓ��������Ɋm�F�ł��Ȃ��Ȃ��A�w���p�[���i�������Ă��Ȃ��҂��g���(��)�̉����s�����Ƃ͊�Ԃ܂��v�B����āu�\�����R�m�ɂ��邽�߂ɐ\�����R�m�F������l�̎��ѕ��̒�o�����߂�悤�ɂ���B�܂��A�w���p�[���i��L���Ȃ��҂������s���댯���ɂ��ẮA���̂��N����Ȃ�������������Ă����B����ɔ����A���X�ɗv�j�̐������s���Ă��������B�v�ƌ���ł���B���́u�]���V�[�g�v�����ƂɁA�����ł��̎��Ƃ��ǂ����Ă������̌������s�Ȃ��A�u�����ʂ́w�v���P�x�v�u�\�Z�́w�k���x�v�ƂȂ�A���N�x����h���̏k���Ƃ��ꂽ�킯�ł���B
�@�������A���ƒS���ۂ̎��������x���ۂ͂��̎��Ƃɑ��āu���l�h���̐\�������͑����X���ɂ���A�ݑ�̏�Q��(��)�̕����̌���̂��߁A�K�v�Ȏ��Ƃł���v�Ɓu��P���]���v�ŏq�ׂĂ���A�u�k���v�̔��f�͎��Ƃ̕K�v�����炢���Ă���肪����ƌ��킴��Ȃ��B���_�Ƃ����u�\�����R�������Ɋm�F�ł��Ȃ��v�ɑ��ẮA�u�\�����R�m�F������l�̎��ѕ��̒�o�����߂�v���ƁA�u�w���p�[���i�̂Ȃ��҂���Q��(��)�̉����s�����Ɓv�ɂ��ẮA�u���l�̌��C�u���v�Ȃǂ��s�Ȃ��ׂ��ł͂Ȃ����낤���B���̂��Ƃ������s�Ȃ킸�Ɂu�k���v�́A�ّ��ł���B
�@��N�S������A����܂ł́u�����x���@�v���u�����x���@�v�ɕύX�ƂȂ����B�u�]���V�[�g�v�ł́u�����쓙���[�����Ă������݂̕����ɂ͍���Ȃ����Ƃ��Ɗ�����v�Əq�ׂĂ��邪�A����͎��ԂƂ͂�����Ȃ��L�q�ł���B�Ⴊ���ҁE�����́A�u��Q�x���敪�v�ɂ��ƂÂ��Ďx���T�[�r�X�̗ʂ����܂�B������ɁA����́u���l�h�����Ɓv�́u�Ƒ��̓˔��I�ȕa�C��}�p���ŁA�ꎞ�I�ɉ���K�v�Ƃ���v�ꍇ�Ɋ��p���鐧�x�ł���A�x���T�[�r�X�ʂ����߂��Ă���i��������Ă���j�u�����x���@�v�ł͑Ώ��ł��Ȃ��P�[�X���܂��Ȃ��Ă���̂ł���B������A�S���ۂł��鎩�������x���ۂ��u���l�h���̐\�������͑����X���ɂ���A�ݑ�̏�Q��(��)�̕����̌���̂��߁A�K�v�Ȏ��Ƃł���v(��P���]���j�Əq�ׂĂ���̂ł���B
�@�����������̎��ƁA����Ȃɑ傫�ȍ�����K�v�Ƃ�����̂ł͂Ȃ��B�`���q�ׂĂ���悤�ɁA2012�N�x���Z�ł́u22��6,100�~�v�ł���B�������A���̂����̔����͍��ɕ⏕������t����Ă���A�s�̕��S�͔��z�ɂ����Ȃ��B�u�ݑ�̏�Q��(��)�̕����̌���̂��߁A�K�v�Ȏ��Ɓv�ƔF�����Ă���Ȃ�A�u�s���]���v�̘�ɂ̂��āu���������c�v�̑Ώۂɂ��邱�Ǝ��ԁA���������Ǝv���B
�@����̌������͂R��14���t�ŊW����s���ɑ��t����Ă���B�R��14���Ƃ����A�s�c��\�Z�ψ���̐^���Œ��B�������A�������R�c���Ă��邿�傤�ǂ��̓��ł���B���������x���ے��╟���ی������́A��A���̂��Ƃ����Ȃ������B
�@����̌������̌���m�点�Ă��ꂽ�l�͏q�ׂ�B�u���s�̋�����T�[�r�X�ł́A�ً}�ɉ�삪�K�v�ƂȂ�ꍇ�ɑΉ��ł��Ȃ��B���Ɏg����T�[�r�X���Ȃ��Ȃ��ŁA���̎��Ƃ����邱�Ƃŋ~���Ă���ƒ�������B�K�v���͑����Ă���A�k�����邱�Ƃ͖��B��y���ꂽ��Q�Ҍ������̐��_�ɂ������Ă���v�B�s�͍��N�x����̏k���ɂ������āA�W�҂ւ̎��O�����������A���蕶���𑗕t����݂̂ł������B
| �ߋ��T�N�Ԃ̎��Ǝ��� |
| �N�x |
�h������ |
�N�ԋ��z |
�h���� |
���l�ӗ���z |
| 2008�N�x |
58�� |
17��5,450�~ |
���T�� |
3,025�~�^�� |
| 2009�N�x |
68�� |
20��5,700�~ |
���T�� |
3,025�~�^�� |
| 2010�N�x |
96�� |
29�� 400�~ |
���T�� |
3,025�~�^�� |
| 2011�N�x |
124�� |
37��5,100�~ |
���T�� |
3,025�~�^�� |
| 2012�N�x |
113�� |
22��6,100�~ |
���R�� |
2,000�~�^�� |
| 2014�N�R�����_�ŁA���p���т�53���сA���l�o�^��41�l |
�i2014�N�S���R���t�j
�s�E���c�̂��w���ۈ珊�ϑ��ō���
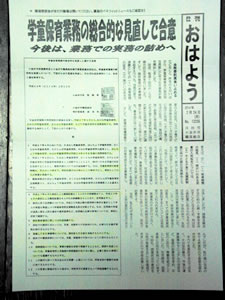 �@������s�̐E���c�́u�����J������s�E���g���v�͂Q��20���A�w���ۈ珊�̈ϑ��𗈔N�S��������{���邱�Ƃ�F�߁A������s�Ƃ̊ԂŁu�o���v�ɒ������Ƃ��A�Q��24���t�̐E���c�̋@�֎��u���͂悤�v�Ɍf�ڂ���܂����B�u�o���v�̑S���͈ȉ��̒ʂ�ł��B �@������s�̐E���c�́u�����J������s�E���g���v�͂Q��20���A�w���ۈ珊�̈ϑ��𗈔N�S��������{���邱�Ƃ�F�߁A������s�Ƃ̊ԂŁu�o���v�ɒ������Ƃ��A�Q��24���t�̐E���c�̋@�֎��u���͂悤�v�Ɍf�ڂ���܂����B�u�o���v�̑S���͈ȉ��̒ʂ�ł��B
�w���ۈ�Ɩ��̑����I�Ȍ������Ɋւ���o��
�@�w���ۈ�Ɩ��̖��Ԉϑ��̎��{�����ӂ��A����27�N�S������A�����ˊw���ۈ珊�A�����ъw���ۈ珊�A�܂��͂�w���ۈ珊�A�݂ǂ�w���ۈ珊�Ԉϑ�����B���Ԉϑ���������Ƃ��āA���L�̂Ƃ��荇�ӂ���B
�P�D����27�N�S���ɂ����ẮA���܂ނ��w���ۈ珊�A�ق傤�w���ۈ珊�A������Ȃ݊w���ۈ珊�A�����Ƃ�ڊw���ۈ珊�A�݂Ȃ݊w���ۈ珊�͒��c�Ƃ��A�ق傤�w���ۈ珊�A�݂Ȃ݊w���ۈ珊�͕���29�N�S����ړr�ɖ��Ԉϑ�����B
�Q�D����27�N�S������A���܂ނ��w���ۈ珊�A������Ȃ݊w���ۈ珊�A�����Ƃ�ڊw���ۈ珊�Ɋw���ۈ�w�������P�l���z���邱�Ƃɂ��A�Ⴊ���̂��鎙���̑Ή����[�����邱�ƂƂ��A�Ɩ����e�ɂ��Ă͕ʓr���c����B�Ȃ��A�w���ۈ珊�̕ۈ玞�Ԃ́A������19���܂ŁA�w�Z�x�Ɠ��͂W������19���܂łƂ��A�����Ƃ��āA�Ђ�Ύ��Ƃ����{����B
�R�D�E���̐��́A���܂ނ��w���ۈ珊�A������Ȃ݊w���ۈ珊�A�����Ƃ�ڊw���ۈ珊�͐��K�E���R�l�A�ق傤�w���ۈ珊�A�݂Ȃ݊w���ۈ珊�͐��K�E���Q�l����{�Ƃ���B
�S�D����27�N�S���̈ϑ��ɂ��E���z�u��13�l�̂��ߍ팸���͂V�l�A����29�N�S���̈ϑ��ɂ��E���z�u�͂X�l�̂��ߍ팸���͂S�l�ƂȂ�A�C�p�����s�Ȃ��B
�T�D�ϑ��ɔ����C�p���ɂ��ẮA����22�N�x�ȍ~�̗̍p���̏�������{�Ƃ��Ė{�l�̊�]�����d���w���ۈ珊���K�E���S����ΏۂƂ���B�Ȃ��A�C�p���̊�]���߈��l��������ꍇ�̑I�l��ȂǁA�C�p���ɕK�v�Ȏ����ɂ��ẮA���O�ɘJ�g�Ŋm�F����B
�U�D�ϑ��ƎґI��Ɋւ��Ă͕ʓr���c����B
�V�D�ϑ��ł̊J���ɓ������ẮA�����A�ی�҂̕s�������̂��߁A�K�v�Ȉ��p�����Ԃ�݂�����̂Ƃ���B
�W�D���{���Ă������Ɠ��ɂ��ẮA�ϑ���������������{������̂Ƃ���B
�X�D�ϑ��ł̐E���̐��ɂ��ẮA�����A�ی�҂̕s���̂Ȃ��悤�ɓw�߂���̂Ƃ���B
10�D���Ԉϑ��ɂ��ẮA���Ƃ̌���J�g�Ŏ��{����ƂƂ��ɁA�Ɩ��̌������ɂ��ẮA�w���ۈ珊�Ǝ����ق̕��ݎ{�݂݂̍���Ɋւ��A�K�v�ƔF�߂鎖���ɂ��Ă����c������̂Ƃ���B
11�D���̈ڍs�ɔ����Đ��ݏo���ꂽ�����E�l���ɂ��ẮA�s���S�̂̋Ɩ��̏[���ɏ[�Ă���̂Ƃ���B
12�D���̊o���ɋ^�`���������ꍇ�́A�J�g�o�������ӂ������ĕʓr���c������̂Ƃ���B
�@���̍��ӂɂ��āA���{���Y�}������s�c�c�͗e�F�ł�����̂ł͂���܂���B�Ȃɂ����A�ی�҂̗����Ă��Ȃ����ƁB�ϑ��{�݂̑����ŁA�����E���̐l����Ⴍ�A�K�ٗp�ȂǕs����Ȑg���ɒu����Ă��邱�Ƃ���A�E���̓�����肪�Ђ�ς�ɋN���邱�Ƃ���ł��B
�@�w���ۈ珊�̈ϑ������ł́A�R���R��(��)�̖{��c��ʎ���ŁA���{���Y�}�̊֍��D�i�c�����s�̑Ή����������ƂƂ��ɁA�R���V��(��)�̌��������ψ���ł��_�킪�W�J����邱�ƂɂȂ�܂��B
���ېň��N�ɑ����啝�l�グ
�@������s�́A���N�x(2014�N�x)����̍������N�ی��ł��ی��҈�l������N�z9,530�~�A�l�グ���悤�Ƃ��Ă���B�Q�����{����n�܂�R�����s�c��ɒl�グ�Ă��Ă�������B���ېł̑啝�l�グ�͈��N(2012�N�x)�ɍs�Ȃ�ꂽ����ŁA�S�����狭�s��������ł̑��ł�70����74�܂ł̈�Ô�S���������A�ƌv�ɑ�Ō��ƂȂ�͕̂K�R�ł���B
�@����̒l�グ�\��Ắw��Õ��x�ɂ����ẮA�u�������z�v���O.�R���A�b�v�A�u�ϓ����z�v���N��4,000�~�A�b�v�A�u���Y���z�v�͂V.�T���̈��������ƂȂ�B�w�������Ҏx�������x�ɂ����ẮA�u�������z�v���O.29���A�b�v�A�u�ϓ����z�v���N��1,000�~�A�b�v�ƂȂ�A�w��앪�x�ł́A�u�������z�v���O.�W���A�b�v�A�u�ϓ����z�v���N��5,700�~�A�b�v�Ƃ������̂ł��邪�A�ł͍���̍��ېł̒l�グ�́A�䂪�Ƃł͂ǂꂭ�炢�̕��S���ɂȂ�̂ł��낤���B
�@�䂪�Ƃ͎��Ǝq�ǂ��Q�l�����ۂɉ������Ă���̂ŁA��ی��҂͂R�l�ƂȂ�B�R�l�S���Ɋւ���Ă���̂́w��Õ��x�́u�ϓ����z�v��l������N��4,000�~�̃A�b�v�Ɓw�������Ҏx�������x�́u�ϓ����z�v��l������N��1,000�~�̃A�b�v�ł���B����Ɂw��앪�x�́u�ϓ����z�v�N��5,700�~�A�b�v�����ɂ������Ă���̂ŁA�e��́u�ϓ����z�v�A�b�v�����ł݂Ă��A�N�ԂłQ��700�~�̑��łƂȂ�B�y�n�E�����̌Œ莑�Y�ɂ�����w��Õ��x�́u���Y���z�v�������������Ă��A�w�������Ҏx�������x�́u�������z�v�Ɓw��앪�x�́u�������z�v���A�b�v����邱�Ƃɂ���đ��E�����̂ŁA�N�ԂłQ���~�O��̑��łɂȂ邱�Ƃ͋^���̂Ȃ��Ƃ���B�����͑������A���S���肪������̂�����A�ƂĂ����܂������̂ł͂Ȃ��B
�@�茳�ɁA�䂪�Ƃ�17�N�Ԃɂ킽�鍑�ېł̔[�t�L�^������B16�N�O��1997�N�x�͑O�N�x�ɖ������܂�Ă��邱�Ƃ���A���łɍ����Ɠ�����ی��҂͂R�l�ł���B�݂�Έ�ڗđR�����A���ېł��啝�l�グ���ꂽ2000�N�x��2004�N�x�A2006�N�x�A2012�N�x�ɐŊz�����ˏオ���Ă���B�N�W��ɕ����Ĕ[�߂�[�t�z���A����������P����̔[�t�z�͓��R�̂悤�ɒ��ˏオ���Ă���B�Ȃ��ł�2012�N�x����̒l�グ�́A�O�N�x�Ɣ�ׂĂP����̔[�t�z���P���~�������Ă���A�ƌv�̔ߖ����̐��������ł��킩��Ƃ���ł���B
�q�^��Ƃ̍��ېŊz�̐���
|
�N�x
|
�N�Ŋz
|
�P����̔[�t�z
|
| 2013�N�x |
55��6,800�~
|
�U��9,600�~
|
| 2012�N�x |
55�� 400�~
|
�U��8,800�~
|
| 2011�N�x |
47��3,100�~
|
�T��9,100�~
|
| 2010�N�x |
46��1,500�~
|
�T��7,700�~
|
| 2009�N�x |
46��9,100�~
|
�T��8,000�~
|
| 2008�N�x |
46��4,200�~
|
�T��7,000�~
|
| 2007�N�x |
49�� 100�~
|
�U��1,000�~
|
| 2006�N�x |
49��2,600�~
|
�U��1,000�~
|
| 2005�N�x |
46��6,500�~
|
�T��8,000�~
|
| 2004�N�x |
44�� 500�~
|
�T��5,000�~
|
| 2003�N�x |
42��7,600�~
|
�T��3,000�~
|
| 2002�N�x |
41�� 400�~
|
�T��1,000�~
|
| 2001�N�x |
40��3,600�~
|
�T���~
|
| 2000�N�x |
39��3,500�~
|
�S��9,000�~
|
| 1999�N�x |
33��1,000�~
|
�S��1,000�~
|
| 1998�N�x |
33��4,600�~
|
�S��1,000�~
|
| 1997�N�x |
35��1,200�~
|
�S��3,000�~
|
�@���ېł͑O�N�̏������m�肵���Ƃ���ŔN�Ŋz�����܂�B�܂�A�O�N�̏����z�ɉ����Ė{�N�x�̍��ېŊz�����܂�Ƃ������ƂɂȂ�B����2005�N�x��2006�N�x�̂Q�N�ԁA���c���E�ɏA���A���c���E�蓖���o�Ă������Ƃ�A���̑��̔N�x�ɂ����Ă��ꕔ�����g�����C�ψ���̈ψ����E�ɏA���Ă����肵���̂ŁA�N��49���~�Ƃ����s�c��c����V�z�ȊO�̏������A���܂��܂Ȍ`�ŔN�Ŋz�ɔ��f����Ă���B���̂��߁A�N�x�ɂ���āA�O�N�x�������ېŊz��������P�[�X���łĂ���B�������A������ɂ��Ă����ېł͍����B������s�̐E����ސE�����m�l�����݂��݂Əq�ׁA�Q���Ă����B
�@��N12��22���ɍs�Ȃ����s����ł��A���ېł��l�グ����邱�Ƃւ̔ߖ��オ�����B�o�Ȏ҂̔����߂������ۂɉ������Ă���ʁX������ł���B��ʉ�v����̍����[�u�𑝂₵�A�l�グ��}���邱�Ƃ��Ȃ�Ƃ��Ă����߂���B�ȉ��A�s������ɔz�z�����������o�c�e�t�@�C���Ōf�ڂ��܂��̂ŁA���Q�Ƃ��������B
�w��@�I�����x�̉A�ŐV���ȊJ����
�@��N�t������A������s�́u��@�I�����v�𐺂����ɋ��т͂��߁A�s�Ɩ��̖��Ԉϑ�����s�����S�����������u��R���s�������v��j�v������ɂނɂ����߂Ă��Ă���B���̈���ŁA�w�O�J����s�s�v�擹�H���݂͐��扻���A�u��@�I�����v�Ɏ������̂́A�s���̕�炵�╟���Ɋւ��u�}����̑��v���ƌ������B
�@���̂��܂�ɂ����s�s�Ȏs���^�c�����߂����Ȃ�������A��������ő��ł⍂��҈�Ô�S���Ȃǂ��p�����ɑł��o���Ȃ��ŁA�s���̂��炵�͂܂��܂��[���Ȏ��Ԃւƒǂ����܂�Ă��܂����ƂƂȂ�B
�@12���s�c��̈�ʎ���A�\�Z�ψ���A�s�������v�������ʈψ���Ŏ��́A�ȏ�̓_��O���ɂ����āA������s�����扻���Ă���w�O�J����s�s�v�擹�H���݂������Ɏs�������u��@�I�����v�Ɋׂ点�Ă��邩���A���Ȃ�̕��͂ɂ��ƂÂ��Ď����W�J�����B
�@12��22���̌ߌ�A12���s�c���̎s������J�Â������́A12���c��̎���̍ۂɍ쐬�������e�⊈�p�����������܂Ƃ߂āA�ЂƂƂ���̃��W������p�ӂ����B�����������A���X�}�j�A�b�N�Ȗʂ͂��邪�A���݂̎��̓��B�_���܂Ƃ߂��������̂Ƃ��āA�����Ȃ�ɕ]���ł�����̂Ɗ����Ă���B
�@�ȉ��A�s����̂��߂ɗp�ӂ������W�������o�c�e�t�@�C���Ōf�ڂ��܂��B���ЁA�������������B
���w�������z�\
�@�o�ϓI�ȗ��R�ŏC�w������Ȑl�ɑ��āA�C�w��K�v�Ȋw���������u���w�����v�Ƃ������x������B������s�́u���t�^�v���̗p���A�s���̎���@�ւł���u���w�����^�c�ψ���v�����x�݂̍�����c�_���Ă���B
�@10��21��(��)�[���A������s�̏��w�����^�c�ψ�����N�x�Q��ڂ̉���J�����B���̉�ł́A���N�x�̏��w�����̉^�c�ƂƂ��ɁA���N�x�̉^�c�݂̍���ɂ��ċc�_���s�Ȃ�ꂽ�B���́A�ߓ��̎s�c��Z�ψ���ł́u���Z���Ɨ��������̓����v�ɑ��镔�ǂ̓��فA�u����ɂ��ẮA���w�����^�c�ψ���Ɏ����Ă��������v���A�ǂ̂悤�Ȍ`�Ŏ������̂��A���̂��Ƃ��C�ɂȂ�A�ψ���̖T���ɂ��������B
�@���w�����^�c�ψ���̃����o�[�͂W�l�ł���B�s����ψ����Q�l�A�s���w�Z�̋��E�����Q�l�A������L����҂P�l�A�����Č���s�����R�l�ł���B�ψ����͎s����ψ���ψ����A�C���Ă���B
�@�܂��A���N�x�̏��w�����̉^�c�́A���L�̒ʂ�ƂȂ��Ă���B
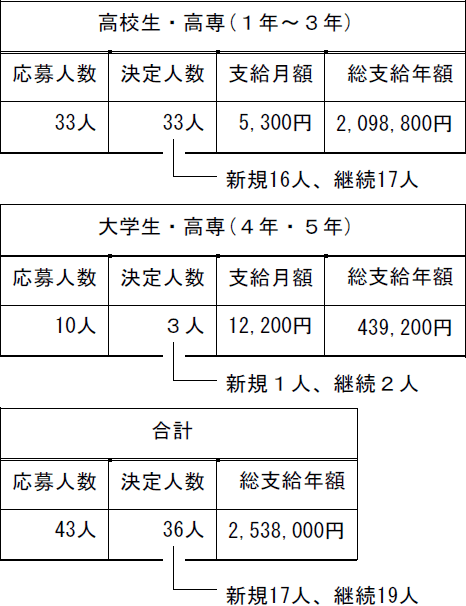
�@����A���N�x�̉^�c���e�ɂ��ĒS�����ǂ��^�c�ψ���Ɏ���������ẮA�ȉ��̒ʂ�ƂȂ��Ă���B
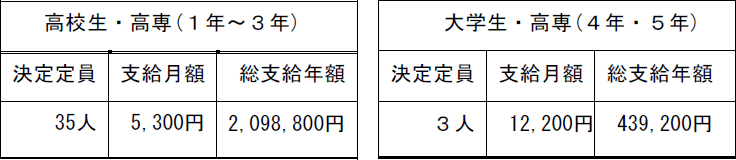
�@�܂��A���N�x�̉^�c�ɂ��āB�u���Z���E����(�P�N�`�R�N)�v�́u����l���v�u����l���v���A�Ƃ��Ɂu33�l�v�ƂȂ��Ă��邪�A��W�l���́u35�l�v�ōs�Ȃ��Ă���B�Ƃ��낪�u33�l�v�������傪�Ȃ��������߂ɁA����ґS��������ƂȂ������̂ł���B����ɑ��Ắu���z5,300�~�Ƃ�����z�ɂȂ��Ă��邩��ł͂Ȃ��̂��B�o�ϓI�ɂ͌�������Ԃ������Ă���B���z5,300�~�̂��߂ɁA�����ĔώG�ȏ��ނ�p�ӂ���Ƃ����ӂ��ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ȃ��Ă���̂ł͂Ȃ����v�Ƃ̈ӌ����ψ��̒�����o����Ă���B����A�u��w���E����(�S�N�E�T�N)�v�ɑ��ẮA�u�z��萔�����₵�Ă����ׂ��v�u���їD�G�Ȑ��k�����l�����Ȃ���A�R�l�ɍi��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�萔�𑝂₹��Ǝv���v�̈ӌ����ψ��̒�����o����Ă���B
�@���ɁA���N�x�̉^�c���e�ɂ��āB���Z�ψ���ł́u����ɂ��ẮA���w�����^�c�ψ���Ɏ����Ă��������v�Ƃ̓��قł��������A��o���ꂽ����Ă͏]���Ɠ����ł���B����ɑ��āu���Z���E����(�P�N�`�R�N)��50�l���x�A��w���E����(�S�N�E�T�N)�͂T�l���x�ɒ���𑝂₷�ׂ��B������s�̋��t���x�͋����Ĉێ����Ă����ׂ��v�u�w���Z���E����(�P�N�`�R�N)�̋��z�̈��グ���K�v�B��w���E����(�S�N�E�T�N)�̒���𑝂₷�ׂ��x�Ƃ̈ӌ��\���Ă��悢�̂ł́v�̈ӌ����o����A�u��w���E����(�S�N�E�T�N)�̒���𑝂₷�Ƃ����̂͐����͂�����B���Z���E����(�P�N�`�R�N)�̋��z�������グ��Ƃ����l���͗����ł���v�ƌĉ�����ӌ����o���ꂽ�B����A�u���s�̂܂܂ŁA���������l�q�����Ă͂ǂ����B�s�̋��t���x�͈ێ����A�������Ȃ��悤�ɂ��Ă������Ƃ��厖�v�Ƃ̈ӌ����o���ꂽ�B
�@���̂悤�Ȃ���肪��莞�ԁA�J��L�����A�ŏI�Ղňψ�������u���_���o���悤�Ɂv�Ƃ̈ӌ����o����A�ȉ��̓��e�œ��\���邱�Ƃ��S����v�Ŋm�F���ꂽ�B
| ���\���e |
�i�P�j���Z���E����(�P�N�`�R�N)�̎x�����z�u5,300�~�v���u7,000�~�v�ɃA�b�v�B
�i�Q�j��w���E����(�S�N�E�T�N)�̌������u�R�l�v���u�T�l�v�ɑ����B
�i�R�j����Ɍ����������v�z��\�Z�����邱�ƁB |
�@�Ȃ��A�u7,000�~�v�̎Z�o�����́A�u�����ی��z�v�́u���ƕ}���v�́u��{�z(�w�p�i��A�ʊw�p�i��v�́u5,300�~�v�ƁA�������u���ƕ}���v�́u�w���(�w����A���k���v�́u1,700�~�ȓ��v�����v�����z�ƂȂ��Ă���B
�@���́A��l��l�̔������Ȃ���A�ǂ̂悤�Ȍ��_�ɗ��������Ă����̂��C�𝆂�ł����B�����Ɋe�ψ����A����o��̉ƌv�ɂ�����o�ϓI���S���ϐS�z����Ă��邱�ƂɁA�e�ψ��̏��w�����^�c�ψ��Ƃ��Ă̌ւ�ƗǐS������v���������B������A���ǂ������炭�͑z�肵�Ă��Ȃ������ł��낤���\���e�Ɍ��܂����Ƃ��A���͐S�̒��Ŕ���𑗂��Ă����B
�@���́A���̓��\������t�s�����A�͂����ē��\���e�ǂ���ɗ\�Z�v�サ�A�������Ă��c��ɒ�o���邩�ǂ����ł���B���邢�́A���Z���E����(�P�N�`�R�N)�̎x�����z���u7,000�~�v�ɃA�b�v�����Ƃ��Ă��A������(35�l)�����炷�\��������Ƃ������Ƃł���B�s�����ǂ̂悤�ȕ��j�ŗ��N�x�A�Ղނ̂��B���̓����́A���N�̂Q�����{����n�܂���s�c��ł͂����肷��B
�@����̏��w�����^�c�ψ���ŁA����ψ����q�ׂ����t���ƂĂ���ۓI�ł������B�u�����������グ�����߂铚�\�������Ȃ�������A���̂��Ƃ͐i�܂Ȃ��v�B�B��̖T���҂ł��������݂̂����̌��t��Ƃ��߂��A�[�����ꂽ�S�ŋA�r�ɂ����B
������s������Q����(���[�X����)
�@������s�ɂ͒��ݒ��ɂ�����B�����E��敔���s�����A�c��W���������A�s�������Ɋւ�邷�ׂĂ̕��������߂��W�K���Ă̌����ŁA�s������́u���[�X���Ɂv�ƌĂ�Ă��鏬����s������Q���ɂ̂��Ƃł���B
�@���U���ɂ��������悤�ƁA�����s���������Ă邽�߂̓y�n���w�����Ă����Ȃ���A�u�s���������Ă邨�����Ȃ��v�𗝗R�ɁA1994�N�P�����疯�ԃr�����ۂ��Ǝ��u���[�X���Ɂv�����s�B���N12�����Ŋ�20�N�ƂȂ�B
�@�N�Ԃ̒��ݗ��͂Q��2,686���~�A�אڂ��钓�ԏ���N��1,487���~�Ŏ�Ă���A�����̈ێ��Ǘ���7,475���~���܂߂�ƁA�N�ԂłR��1,648���~���̋��z�����[�X���ɂɎg���Ă��邱�ƂɂȂ�(2013�N�x�\�Z)�B���̌�������20�N�ԁA�葱���Ă���Ƃ������Ƃ́A70���~�O��̍�������₳�ꂽ���ƂɂȂ�B
�@2008�N�̏H�A�u���[�X���ɂ͈����������������v�Ǝs���̓{��̉^�����N���A��t�s���͍��N�R���A�悤�₭�����s�������݃X�P�W���[���v��\�B����ɂ��ƁA�����s�����̌��݂�2016�N�̉č�����J�n���A2018�N�S���Ɋ����B���N�U�����瑍���s�����ŋƖ����J�n���A���N�W�����Ń��[�X���ɂ��I���Ƃ������́B�������A�v��ǂ���ɃR�g���^�Ԃ̂��A�^�Ԃ��߂̎肾�Ă�{���ɂƂ�̂��A�s���̊Ԃɂ͋^���悷�鐺���������B
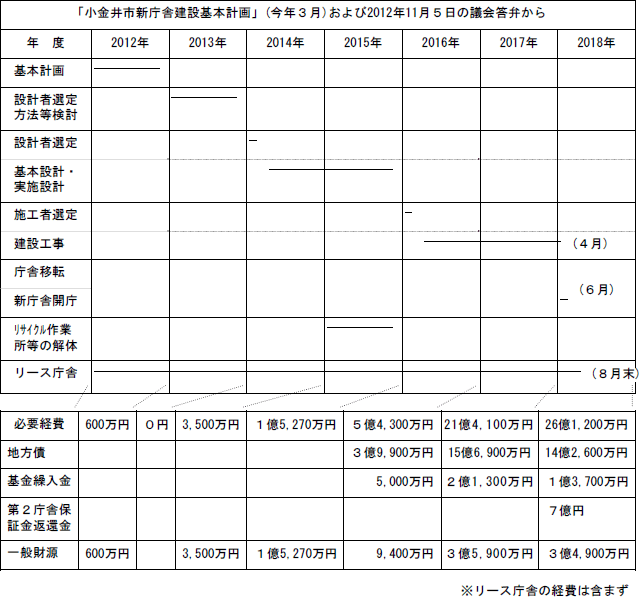
�@�ő�̉ۑ�́u�����v�ł���B�v��ǂ���ɂ����߂邽�߂ɂ́A�\�Z�[�u���K�v�ƂȂ�B�Ȃ��ł����z�́u��ʍ����v���[�Ă�u2015�N�x�v�u2017�N�x�v�u2018�N�x�v�ɁA�v��ǂ���ɗ\�Z���g�߂�̂��H���������N�����l����_�ł���B
�@�X���c��Ŏ��́A���N�x(2014�N�x)�Ɂu��{�v�E���{�v�̗\�Z���v�シ��̂��v�Ǝ��₵���B���z��3,500���~�ł���B���������ق́u�\�Z�Ґ��ߒ��ɂ����đ����I�Ȓ����A���f�������Ă��������v�Ƃ������́B3,500���~�̗\�Z�[�u�ł��炱�̂悤�Ȃ��Ƃł́A���P�ʂ̈�ʍ�����K�v�Ƃ���N�x�́A�{���ɗ\�Z�[�u���ł���̂��������������l����͎̂������ł͂Ȃ��ł��낤�B
�@�����āA�����s���������Ă�ꏊ�ɂ́u���T�C�N����Ə��v���u����Ă���B���̎{�݂̉�́E�P���A�ړ]���K�v�ƂȂ邪�A�ړ]��͖���ł���B���̓_�ɂ��Ď��₷��ƁA�u�V���Ɍ��݂̃X�P�W���[���A��{�v�悪����̂ŁA���̌v��ɉ����Ă����߂���悤�w�͂��Ă��������v�ɂƂǂ܂��Ă���B�ړ]�����邽�߂ɂ́A�ړ]��̒n��Z���̔[���ƍ��ӂ��K�v�ƂȂ�B�ړ]��̌��n����܂��������サ�Ă��Ȃ�����ŁA�͂����āu2015�N�x�Ɏ{�݉�́v�ɂȂ����Ă����̂��A���̓_�ł��^��ł���B���̂��߁A�s���̊Ԃ���́u2018�N�W�����Ń��[�X���ɏI���v�́u�G�ɕ`�����݁v�Ƃ̔�]���������B
�@���[�X���ɂ͍��N12�����Ŋ�20�N�ƂȂ�B�s�̌v��ł͂���ɂS�N�W�J���A��邱�ƂɂȂ邪�A�S�N�W�J���ł͏I��炸�A���ǂT�N�ԁA�葱���A���̌���葱���邱�ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ������������B�����Ȃ�A�s���̓{��͒��_�ɒB����ł��낤�B
�݂��ً�s�̖\�͒c�Z�����
�@�݂��ً�s����g����M�̉�Ёu�I���G���g�R�[�|���[�V�����i�I���R�j�v��ʂ��āA�\�͒c���֖�230���E��Q���~���̗Z�����s�Ȃ��Ă������Ƃ����炩�ƂȂ�A2010�N�V�����_�ŁA�݂��ً�s�̓�����A���̗Z����c�����Ă������Ƃ��A�݂��ً�s���̋L�҉�Ŗ���݂ɏo���B
�@�u�\�͒c�v�͂��̖��̂Ƃ���A�\�͂��`�������Ȃ���A���邢�͒��ږ\�͂��ӂ邢�Ȃ���l�X�Ɋ�Q��������\�͏W�c�ł���A�u���Љ�I�W�c�v�Ƃ��Ēf�߂���Ȃ���Ȃ�Ȃ��㕨�ł���B�Љ�S�̂���A�݂��ً�s���ӔC������͓̂��R�̂��Ƃł���B
�@���́u�݂��ً�s�v�́A�O�g�̕x�m��s�����1973�N�W���P���ȍ~�A�����܂ŏ�����s�̎w����Z�@�ւƂȂ��Ă���A������s������Q����(���[�X����)�̂P�K�̉E���ɑ�����u���A�������N�ی��ł�s�ŁA���ی����A�ۈ痿�A�w���ۈ�琬���A�������҈�Õی����Ȃǂ̑����[�t�Ή����s�Ȃ��Ă���B���́u�݂��ً�s�v�A�S�N�O�̐����ɂ��ƁA������s�̌����̎戵����������33.9���ƂȂ��Ă���A���Z�@�ւ̂Ȃ��ł͍ł������䗦���߂Ă���B����A������s�̃��C���o���N�Ƃł������ׂ����݂ł���B�������u���C���o���N�v�Ƃ��Ă̖������A�݂��ً�s���ʂ����Ă������ǂ����͋^��ł��邪�B
�@����̎����������āA���͎v���B�ʂ����Ă��̂܂܁A�݂��ً�s��������s�̎w����Z�@�ւɈʒu�t���Ă����Ă����̂��A�ƁB�݂��كt�B�i���V�����O���[�v�́u��ƍs���K�́v�ł́A�u�s���Љ�̒�������S�ɋ��Ђ�^���锽�Љ�I���͂Ƃ́A�f�łƂ��đΌ����܂��v�ƋL����Ă���Ƃ����B���������ۂɍs�Ȃ��Ă������Ƃ́A�u�f�łƂ��đΌ��v�ǂ��납�A�u�Z�����s�Ȃ��ď����Ă����v�̂����Ԃł������B���̂悤�ȋ�s��������s�̎w����Z�@�ւɈʒu�t���Ă����Ă����̂��B
�@�S�N�O��12�����s�c��ŁA���䐳���c��(����)���u�w����Z�@�ւ̌������v���N���Ă���B���̎��̊����������̓��ق́u�ʋ�̓I�Ŗ��m�Ȏw����Z�@�ւ̌�������͓��ɒ�߂Ă��Ȃ��v�Əq�ׁA���̌��ʁA�����܂ŏ�����s�̎w����Z�@�ւ̒n�ʂ��߂�ƂȂ��Ă���B
�@�������A���̎��̓��قł킩�������Ƃ́A�i�P�j���N�S���P�����痂�N�̂R��31���܂ł̂P�N�Ԃ̌_����ԂƂȂ��Ă���A������p���X�V���Ă���A�i�Q�j�_����ԏI���S�J���O�܂łɌ_����I��������|�̈ӎv�\�������Ȃ��Ƃ��́A���̌_����X�V�������̂Ƃ݂Ȃ��Ƃ̋K�肪�u������s�̌����̎��[�y�юx�����Ɋւ��鎖�����Ɋւ���_�v��15���ɖ��L����Ă���A�i�R�j�u�S�J���O�v�Ƃ͖��N12�����܂ń��������Ƃ������Ƃł���B
�@��t�s���́u���������Ō��܂肾�Ƃ����b�ɂ͂Ȃ�낤�Ǝv���܂��v�Əq�ׁA�u�݂��ً�s�v�ȊO�̑I�����ꍇ�ɂ���Ă͂��肤��Ƃ̍l���������A�����������́u���s�̌�������ɂ��Ă������̏�A�܂��A������҂̂��ӌ����l���̏�A������������邱�Ƃ��\���ǂ����ɂ��Ă��܂߂܂��āA����̌����ۑ�Ƃ����Ă������������v�ƒ��߂������Ă���B
�@���̎��̊����������͍����A���s���ƂȂ��āA������s���̑ǎ�����t�s���ƂƂ��ɒS���Ă���B���䐳���c���̎��₩���S�N�B�㌴�G�����s���ǂ́A�u�����ۑ�v�̌������ʂ͂����ɁB�u�܂��������v�ł͍ς܂���Ȃ����Ԃ��A�݂��ً�s���߂����Ă͋N���Ă��܂����B
�s�c�I��A���Ԉϑ����֓˂��i�ވ�t�s��
�@�R���̎s�c�I��A�����E�����E����Ɏx����ꂽ��t�F�F�s���́A�R�N�O�̂T���ɍ��肵���u��R���s�������v��j�v��i�߂邽�߂ɁA�������ɑ���o���܂����B�܂��͏��w�Z���H�����Ɩ��̈ϑ����B�S���ɐE���c�̂ƈϑ����ō��ӂ���₢�Ȃ�A�T���ɂ͕ی�Ґ�������s�Ȃ��A�U���c��Ɉϑ��\�Z���āB�W����{�ɂ͈ϑ��Ǝ҂����肵�A�X������ϑ��J�n�Ƃ�����ۂ̂悢����悤�ł��B
�@�����č��x�́A�ۈ牀�Ɗw���ۈ珊�̈ϑ����B����́A�E���c�̂Ƌ��c�������߂Ă���i�K�ł����A��t�s���͏��w�Z���H�����Ɠ����悤�ɁA�E�������u�M�u�A�b�v�v����̂����������ƒ��߂Ă���ł��B�c�O�Ȃ���A���܂̐E���c�̂����Ă���ƁA���ӁA�ϑ����ō��ӂ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����ƁA���O����܂��B
�@�V��27���̎��̎s����ł́A���̈ϑ�������̃e�[�}�Ƃ��ĕB21���ɎQ�@�I���I���A24��������R�c�R�c�ƍ��͂��߂����W�����́A�C�����a�S�T�C�Y�łU�y�[�W�ɂ��Ȃ�܂����B�����A�z�z�������W�����u�s�c�I��A���Ԉϑ����֓˂��i�ވ�t�s���v���o�c�e�t�@�C���Ōf�ڂ��܂��B���ЁA�������������B
���w�Z���H�̖��Ԉϑ���
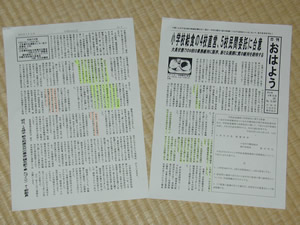 |
|
�u�ϑ������Ӂv���u���͂悤�v
|
�@�S��15���t�̎����J������s�E���g���j���[�X�u���͂悤�v�́A������s�Ǝs�E���g����12��(��)��A�c�̌����s�Ȃ��A���w�Z�T�Z�̋��H�����̖��Ԉϑ����ō��ӂ����ƕ܂����B�ϑ����͍��N�X����\��B����A�ϑ����Ɍ��������������ƌv��쐬�������߂��Ă������ƂɂȂ�܂��B
�@������s�͉w�O��^�J���������߂����A�R�N�O�̂T���ɔ��\�����u��R���s�������v��j�v�Łu���w�Z���H�Ɩ��̌������v�L�B���w�Z�X�Z���A�R�`�S�Z�̋��H�����Ɩ��Ԉϑ���������j�����������A���H�����E�����ސE��a�C�ɂȂ��Ă����K�E�����̗p�����ɁA�g�����s����Ȕ��E�Վ��E���őΉ����Ă��܂����B���̂��ߋ��H�������ꂪ���肹���A�ϑ��������܂�������Ȃ����Ԃɒǂ����܂�Ă����܂����B����A�S�Ă̏��w�Z�Ő�����s�Ȃ��A�T��21��(��)�J�×\��̗Վ��c��Ɉϑ��\�Z����Ă���錩���݂ł��B
�@���w�Z�T�Z�̋��H�����Ɩ��̖��Ԉϑ����œ�����u�������ʁv�́u5,300���~�v(��N�R���̗\�Z�ψ����)�B���w�Z�X�Z�̂����̂ǂ̊w�Z���H�Ԉϑ������邩�́A���炩�ɂ���Ă��܂���B
�@���{���Y�}�s�c�c�͂��̊ԁA�H���A�����M�[�Ή��⏬����s�̋��H�̋Z�p�E�`���̌p���̖ʂ���A���w�Z���H�����Ɩ��ƈϑ������ꂽ���w�Z���H�����Ɩ��̑o���̌����s�Ȃ����Ƃ�v���B�ϑ�����ɂ��肫�̎p�������߂�悤�咣����ƂƂ��ɁA���Ԉϑ�����Ă��钆�w�Z���H�������ꂪ�u�[�������v��Ԃɂ���̂ł͂Ȃ����ƁA�^��𓊂������Ă��܂���(��N�R���̎��̈�ʎ���)�B�T��21���ɗ\�肳��Ă���Վ��c��̈ϑ��\�Z�R�c�ł́A���̖ʂ���̎��^�������Ă͒ʂ�܂���B
�@�Ƃ���ŁA�S��12��(��)��ɒc�̌����s�Ȃ��邱�Ƃ́A�u���͂悤�v�Ɉ�A�\��������܂���ł����B������肩12��(��)�̒��x�݂Ɏs�E���g���������ɑ����^�сA���̏�ɂ������s���̕��Ɂu�{����A�c�̌�������炵���ł��ˁv�Ɛ���������ƁA�u�悭�������ł��ˁv�Ƃ̓������Ԃ��Ă���n���ł����B
�@12��(��)�̖�A���w�Z���H�����̖��Ԉϑ������Œc�̌����s�Ȃ���Ƃ������́A�����������炳��܂����B���̏�Ȃ�������A15���̒��Ɂu���͂悤�v������܂ŁA�܂������m��Ȃ��������ƂɂȂ�܂��B�u���Ԉϑ����v�͎s�E���̘J�������ɂ�����邾���łȂ��A�����Ƃ��̕ی�҂ɒ��ډe��������ł��B�����E��œ����Ƃ������Ƃ͂ǂ��������ƂȂ̂��A�����őg�D����Ă���E���c�̂ɉʂ��������͉̂����A���̂��Ƃ��s�E���c�̂͂悭�l���Ă������������Ǝv���Ƃ���ł��B
�S�~�������̌���Ɖۑ�
�@���N12���̎s���I���ŕԂ�炢����t�F�F�s��������A�S�~�������ł́u����24�N�x���܂łɎ����\�ȕ���������v�܂ŁA�P���]�Ɋ������������B��N11�����ɓ���s�̔n��s�����A����s�̂Ȃ��ɍ������s�Ə�����s�Ɠ���s�̋����̃S�~�����{�݂����Ă�l���ł��邱�Ƃ�\�����A����̐V���ł́A�R���P���ɁA�V�����{�݂̌��݂Ɍ������v�揑�ƂR�s�������������o�����A���Ȃɒ�o����^�тł��邱�Ƃ����炩�ƂȂ����B�������A����s�̒n���Z���̍��ӂĂ���킯�ł͂Ȃ��A�O�r�͌��������̂��\�z�����B
�@����s�̏ɂ��ẮA������s���̂������ŕ��G�Ȏv�����������Ă���B���O�̃S�~�����{�݂������Ȃ������ɁA�{�݂����Ă�p�n���������Ă��Ȃ��Ȃ��ŁA���s�̏����{�݂Ɉˋ�����������Ȃ��Ƃ����\����Ȃ��ƁA������s���̂ǂ����Ɏ{�݂����Ă邽�߂̓K�n�͂Ȃ����A���Ւn�͂Ȃ�Ƃ��Ȃ�Ȃ����A�Ƃ̎v���ɂ�����ȂǁA�s���ɂ��������A�����ɂ������Ȃ��Ƃ������o�ł���B������A���Ȃǂ��n�������ƁA�u�S�~�����Ȃ�Ƃ����Ă��������v�Ƃ̐����K���������Ă���B�������A�����g�����G�Ȏv���ō����̎��Ԃ��}���Ă���̂ł���B
�@�Q��16��(�y)�̖�A�n��̏����̏W�܂�ɏ�����A�S�~���̘b�����Ăق����Ɨ��܂ꂽ�B�������A�����g�����G�Ȏv���������A��������ΑŊJ�ł���Ƃ̕�����������Ȃ��Ȃ��ł́̕A�����炭�W�܂������X���������肢���Ȃ������̂ł͂Ȃ����낤���B�c�O�Ȃ���A�s���ɃS�~�����{�݂̓K�n���Ȃ��Ȃ��ł́A�����g�A����s�̍���������ȊO�ɂ͂Ȃ��Ȃ��Ă���B
���Q��16���̏W�܂�ɔz�������W�������o�c�e�t�@�C���Ōf�ڂ��܂�
�S�����畉�S���A����Ŏs���𗬃Z���^�[�w��
�@�R�����s�c��R��24�������ɏI�����A���Â��Ԃ��Ȃ�31���ɂ͎s������}���܂����B���̎s����ł́A�S�����牟���鍑�ېł���ی����̒l�グ�ƁA���̈���Ŕ���ȍ����𓊓�����s���𗬃Z���^�[�̍w�����s�Ȃ�ꂽ���ƁA��t�s�����Ŏ����Ă������ł̃S�~�����{���ݕ��j���j�]�������ƂȂǂ��A���W���ɉ����ĕ��܂����B
�@���Ԃ�45���ԁB���̌�̎��^��90���]�ɂ��y�т܂����B����͑���ɂ킽��܂������A������������̎s���̂�����ɓ{����q�ׂ���̂���B�Q���҂̑����͔N�z�҂��������Ƃ�����A�V��̕s�������A���܂̎s���ł͕s���ɉ������Ȃ����Ƃ�N�����q�ׂĂ��܂����B
�@���N�R���͎s�c��c���I�����s�Ȃ��܂��B���̎s����ς��Ȃ���ƁA���ӂ����������ł߂���̂ƂȂ�܂����B
���s����ɔz�z�������W�������o�c�e�t�@�C���Ōf�ڂ��܂��B
������s���̍s���l�܂�ŊJ�̕���
�@11��12���t�ō����a�Y�s�������E���A�s���̂����ς�̊S���́A12��18�����[�ōs�Ȃ���s���I���ɒN������₷��̂��Ƃ������ƁB�����_�ɂ����Ă͂Q�l�̖��O���������Ă��邪�A�u�S�~���ʼn��������������Ȃ��������s������ł͂˂��v�Ƃ��A�u�����玩���ȏo�g������Ƃ����Ă��A�悻�҂ł͂˂��v�Ȃǂ̐����J�ł͉Q�����Ă���B�������A�u���Y�}�͂ǂ������ł����H�v�̐����������A���}�Ɏ��������������Ƃ����߂��Ă���B
�@������ɂ��Ă��A�s�����̍ŏd�v�ۑ�Ɂu�S�~���v�����邱�Ƃ͂��Ȃ߂��A���x�̎s���I���ł́A�s���l�܂����S�~�����ǂ̂悤�ɑŊJ���Ă����̂����A���_�̒��S�ɂȂ��Ă����B�����ɁA���̎s���I���́A����S�N�Ԃ̏�����s�̎s���^�c��C����l����I�Ԃ��̂ł�����A�S�~���ƂƂ��ɁA�s���̕�炵�̖��A���̂��߂̂����̎g�����̖�肪�傫������Ă����B��������ł̑��ŕ��j��ł��o���Ă�����ƂŁA��^�������Ɛ��i�̎s���^�c����A��炵�����̎s���^�c�ɐ芷���Ă������Ƃ��������K�v�ƂȂ��Ă���B
�@����Ȃ��Ƃ�O���ɒu���Ȃ���A�ߓ���20��(��)�ߌ�A���̎s������J�Â����B�����͑O���̂ǂ���Ԃ�Ƃ͈قȂ�A������J���b�Ɛ��ꂽ�g�����z�C�B���ł������g�t�����߂Ă��ł����������Ȃ�悤�Ȑ�D�̍s�y���a�ƂȂ�A�Q���l���͌��ɏo���Ă͂����Ȃ��قǂł������B
�@�������g�p�������W�������o�c�e�t�@�C���Ōf�ڂ��܂��̂ŁA��������������K���ł��B
�����a�Y�s���i��h�̘_�_�Ɩ��_
�@������s�̍����a�Y�s�������E��\���������Ƃɑ��āA�����a�Y�s����i�삷��l�X����A���܂��܂Ȕ��M������Ă���B���̑����͎�����F�╨���̔c���ɐ��m���������Ă�����̂ł���A�Ȃ��ɂ͍����a�Y�s�����������������ٌ삷�邽�߂ɁA�b�����̕����Ɍ��т��悤�Ƃ��郂�m������B
�@�����g�ɂ��A���̉w���ňӌ����q�ׂĂ����l�A�d�b�ŃN���[�����q�ׂ�l�Ȃǂ�����A�����a�Y�s���������������̐S��𗝉��ł��Ȃ��킯�ł͂Ȃ����A�Ӑ}�I�ɘb�����肠���悤�Ƃ��铮����������B����āA�����g�Ɋ�ꂽ�����a�Y�s����ٌ삵�悤�Ƃ��鑤�́u�������v�������ŏЉ�A���Ȃ�̌������q�ׂ邱�ƂƂ���B
�����a�Y�s���i��h�̘_�_�Ɩ��_
�u�w20���~�̃��_�g���x�͈�t�s���ɑ���ᔻ�B�L��x����ɑ�����̂ł͂Ȃ��v�ɂ��āB
�I������̋L�ڂ́u��t�s���̃��_�g�� ���ݏ��� �S�N�Ԃ�20���~�v�ƂȂ��Ă���B�m���ɁA��t�s���ɑ���u���_�g���v�Ƃ���Ă���B�������A���́u���_�g���v�̑Ώە��́u�S�N�Ԃ�20���~�v��₵�Ă���u������s�����r�o����R�₷�S�~�̏�����(�ϑ���܂�)�v�ł���A���������ď����������Ă���̂́A�n��Z����c���������Ď���Ă���x����ł���B
�u���_�v�Ƃ͂ǂ������Ӗ����B��g�̍��ꎫ�T�ɂ��Ɓu���ɗ����Ȃ����ƁB���ʁE���p���Ȃ����Ɓv�ł���B�u���ɗ����Ȃ����Ɓv���x����͐��������Ă����Ƃ������Ƃł���B����ł́A�x����͎��g�̏Z����c��ɐ��������Ȃ��B�u���ɂ����Ȃ��v���Ƃ������Ă������ƂɂȂ邩��ł���B
�������A���̎x���͏�����s�̕����炨�肢���Ă�����̂ł���B�����s����i�삷��l�X�́A�u���ɗ����Ȃ��S�~�����̎x���́A���肢����K�v�͂Ȃ������v�Ƃł������̂ł��낤���B���ċp�ꂪ�I��������ƂŁA�N��13,500�g�����̔R�₷�S�~���A���̂S�N�ԁA�ǂ��������悤�ƍl���Ă����̂ł��낤���B�u��ċp�E�R�~���e(�g�c�l)�V�X�e���v�ƌ����Ă��A�ƒ�S�~�̐��S�~��S�ʁA�u��ċp�E�S�~���e�v�őΉ��ł��Ă��鎩���̂͂Ȃ��B�ċp�����͌���ł͔����Ēʂ�Ȃ��̂ł���B������c��͂��̊ԁA�L��x�����_�����Ƃ͒N��l�Ƃ��āA�����Ă͂��Ȃ������̂ł���B
�u���_�g���v����ɑ��ẮA�����s�������������T�l�̋c�����u���l�сv��\�����Ă���B10���U���̎s�c��{��c�Ŋ��l���q�c�����T�l���\���āu������F�ł���A�Ԉ�����咣���A����܂ŏ�����s�̉R�S�~�������Ă��������Ă��������̂Ȃǂ̊W�҂݂̂Ȃ��܂ɂ��s���Ȏv����^���A����̃S�~�����̍L��x���ɑ�ϐ[���ȉe����^���Ă���v�u�I������Łw�������܂��x�Ɩ��O���o�����ӔC�͏d���A�w20���~�̃��_�g���x�Ƃ����咣��F�߂Ă��܂������Ƃɂ��Đ^���ɔ��Ȃ��Ă��܂��v�Əq�ׂĂ���B
�u���_�g���v�ƌ�����A�x���悪�{��͓̂��R�ł���A���f���ɔF�߂邱�Ƃ������^���ȑΉ��ł���B����āA�u���_�g���v�́u�L��x����ɑ�����̂ł͂Ȃ��v�Ƃ����̂́A�T�l�́u���l�сv�ɔ�������肩�A���܂�ɂ����ӔC�Ȍ������ł���B
�u�c��͎s���ɑ��āw�Ӎ߁E�P��x�����߂邾���łȂ��A�ꏏ�ɂȂ��Ďx����ɂ��l�тƎx���v���ɍs���ׂ��������v�ɂ��āB
�s������A���̂悤�ȗv��������A���R�Ɍ����ɒl������̂ł������낤�B�������A�s�������������T�l�̋c�����u�������͗^�}�ł͂Ȃ��v�Ɛ錾����Ȃ��ł́A�ƂĂ��u�s���ƈꏏ�ɂȂ��āv�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B�܂��́u���_�g���v���s���ƈꏏ�ɂȂ��Đ�`�����s���̉����c�����u�s���ƈꏏ�ɂȂ��āv���l�эs�r�ɂ����ׂ��ł������B�u�c��͂Ȃɂ�����Ă���v�̌������́A�s���ƈꏏ�ɂȂ��āu���_�g���v���`�����T�l�̋c���Ƒ��̋c�����ꏏ�����ɂ��錩���ł���A�T�l�̋c����ƍ߂�����̂ƂȂ�B����A�e�F�ł��Ȃ��B
�u�����s���͎��E�𔗂�ꂽ�B��������Y�}���e�F�����v�ɂ��āB
�����s���́u�ӔC����邱�ƂőŊJ��}�肽���v�Ǝ����̈ӎv�Ŏ��E��I�������B�u���E�𔗂�ꂽ�v�Ƃ����̂́A11���P���t�u�����v�́u������s���Ɏ��C�_�@�����q�s���������v���w���Ă̂��Ƃ��ƍl�����邪�A���̋L���Ŗ��炩�Ȃ悤�ɁA�����s���������q�s���ɃA�h�o�C�X�����炢�ɍs���A�����Łu����̊o�����������Łi���ݏ����ϑ������ӎ����̂Ɂj���肢���邱�Ƃ��A���̎��Ԃ���������B��̓����v�Ƃ̌����������ꂽ�Ƃ������́B�u�A�h�o�C�X�v�����̂ł���A�u���E�𔗂�ꂽ�v�Ƃ����̂Ƃ͈قȂ�B�u���E�𔗂�ꂽ�v�Ƃ��������́A�����q�s���ɑ��Ď���ł���ƂƂ��ɁA�����s���̖��_�̂��߂ɂ����߂������Ƃ͂ł��Ȃ��B
���{���Y�}�s�c�c�͍����s���ɑ��āu�R�S�~���W�Ə������X�g�b�v�����Ȃ����߁A�s�����ӔC�������Ă����������Ƃ邱�Ɓv(10��18���̐\����)�ȂǁA�R�S�~�����ɐӔC�������đΉ����邱�Ƃ��������߂Ă����B���{���Y�}�s�c�c�͎s���Ɂu���E�v�����߂Ă͂��Ȃ��������肩�A�S�~�������X�g�b�v�����Ȃ����߂ɁA�����s�A���s�A�{���s�A���]�s�̋��Y�}�s�c�c�ƍ��k���A�x���v�����s�Ȃ��Ă����B�������A�����s���������s���ʂāA�u���E�v�Ŏ��ԑŊJ��}�肽���Ɣ��f�������Ƃ���A��X�͂�������ꂽ�̂ł���B
�g11�����{�ɃS�~���W���X�g�b�v�h������Ȃ��ŁA�u���E�v�̑I���̑��Ɂu�ŊJ��v������Ƃ����̂ł���A�����s������������Ă�����X�́A�s���ɐi�����ׂ��ł������낤�B����Ȃ��ɋc���ᔻ���Ă��A�����͂͂Ȃ��B�����s����i�삷�鑤�̌��������Ă���Ɓu�S�~���W���X�g�b�v���Ă��\��Ȃ��v�ƍl���Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ����^�������Ȃ�B���������ł���Ȃ�A�s�������ւ̖��ӔC�������������Ă���B�����̐����Ɍ������Ȃ��S�~�����͒f���ăX�g�b�v�����Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�������s���̎��E�\���ɂ���đŊJ�̂���������
�@�Ƃ���ŁA�}�X�R�~�ɂ��ƁA�����s���̎��E�\���Ƃ��l�сE�x���v���ɂ���āA�������Ȃȑԓx���Ƃ��Ă��������̂̒����A����ɑO�����Ȕ����������Ă��Ă���B���̂��Ƃ́A�����s���́u�ӔC����邱�ƂőŊJ��}�肽���v���A���̖ڂ����邱�ƂɂȂ�B�����s���́u���f�v��]���������Ǝv���B
�@����̎��Ԃ́A�S�~�𑼎s�ɂ��肢����Ƃ������Ƃ̏d�݂��s���S�̂ɒm�炵�߂邱�ƂƂȂ����B�s���̖���ŏ��������s�ւ̃S�~�����ł͂����Ă��A�������āu���_�g���v�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B���O�̏�����������Ȃ�������́A���s�ɂ��肢������Ȃ��̂ł���B
�@�S�~���ɑ��邱�̊Ԃ̎s����ᔻ����̂ł���A�u���_�g���v�Ƃ����\���ł͂Ȃ��A�u����ɂ���āA�S�~�����ɑ����̔�p��������悤�ɂȂ����v�Ƃ����悤�ɁA���m�ɕ\�����ׂ��ł���B�u���_�g���v�̕\���͒Z�����t�ł��邱�Ƃ���A�l�X�̔]���ɃX�b�Ɠ��荞�ނ��̂ł͂��邪�A���m���������邽�߂ɁA�x����ɂ��A�~�肩���錾�t�ƂȂ�̂ł���B���̂��߂ɁA�����a�Y�s���̏I���Ɍ��т����ƂƂȂ����B
�������a�Y�s���͈�t�O�s���Ƃǂ����قȂ�̂��H
�@�����a�Y�s����i�삷��l�X�́A�����E�����̎s���Ɍ�߂肳����킯�ɂ͂����Ȃ��Ƃ̎v������A�i�삷�����������B�������A�����s���ƈ�t�s���ŁA�ǂ����ǂ��Ⴄ�Ƃ����̂��낤���B
�@�����s���́A�A�C���X�Ɍ}�����U���c��ŁA�u�S�~�����v�͈�t�s���̘H���������p���ƕ\�����A10���I�Ղ̋c��ł́A�u�s���𗬃Z���^�[�v���u�����v�Ƃ�������𖾂炩�ɂ����B�u�s�������ɖ��v�ł́A���łɈ�t�s���I�ՂɃW���m���Ւn�ł̌��݂ւƕ��j�]��������A���Ƃ́A���̎��������ꂽ�ɂ����Ȃ��B�������A�s���𗬃Z���^�[���ƂȂ�A���Ɍ��݂̍������낤���Ȃ�B�s���T�[�r�X�̖��Ԉϑ��A���S���E�L�����A�w�O�J����O��Ƃ�����t�s������́u��S����{�\�z�v���u���̐�����ꗂ͂Ȃ��v�ƌ�������ɂ������ẮA�Ȃ�̂��߂Ɏs���ɂȂ����̂��ƁA�₢�����Ȃ�B����ł́A��t�s���Ƃ̈Ⴂ�������o���͓̂���B�������A�����s���ɂȂ��Ă��炱�̊ԁA�s���͍������Ă���̂ł���B
��12��18�����[�Ŏs���I��
�@�s�����E�ɂ���āA�s���I����12��18�����[�ōs�Ȃ���B���{���Y�}�͑����̕��X�Ƌ����ŁA�s���̕�炵����Ɍ��߂邱�Ƃ̂ł������i���������ƍl���Ă���B���I���邱�Ƃ��ł���A���{���Y�}�̂S�l�̎s�c�c�͓��R�Ɏs���̗^�}�ƂȂ�B�ӔC�������Ďs�����������A�x���Ă����B�����a�Y�s���̏ꍇ�́A���������T�l�̋c�����u�^�}�ł͂Ȃ��v�Ɛ錾�������߂ɁA�s���͑��k���鑊�肪�Ȃ��A�Ǘ����Ă��܂����B�������A���{���Y�}�͂���Ȗ��ӔC�ȑΉ��͂Ƃ�Ȃ��B�ӔC�������āA�s�����x���Ă����B
�V�����珬����s�����˔\������J�n
�@������s�́A�����������̂̕��˔\�s���ɉ����邽�߂ɁA�V�����珬���w�Z�̋��H�H�ނ̕��˔\������J�n�B�s�������w�Z(14�Z)�A�F�ۈ牀(13��)�A�����c�t��(�U��)�A�s������(�S����)�̕~�n�̑�����n�߂܂����B
�@���H�H�ނ́A�`�F���m�u�C���������̂��@��21�N�O�ɍw�������������g���čs�Ȃ��A�Z��≀��Ȃǂ̕~�n�́A�����s����ݗ^���ꂽ�ȈՌ^�������g���Ă��܂��B�܂��A�s������̗v�]�ɉ����āA�w�Z�v�[���Ɗw�Z�̓y�������B��������A���̂Ȃ����l���ʂƂȂ��Ă��܂��B
�@�����A������s�͕��˔\����ɑ��ď��ɓI�ł����B�������A���{���Y�}�s�c�c���s��128�����œƎ��ɑ��肵�����Ƃ��傫�Ȕ������ĂсA�s�c��Ɏs�����瑪����{�����߂�����o�����Ȃ��ŁA�s�̏d�����������Ƃ��ł��܂����B
�@���˔\���͒Z���ԂŏI�����̂ł͂���܂���B�p���I�ȑ�����s�ɍs�Ȃ킹�邱�Ƃ���ł��B
�����s���a���Ŏs���̕�炵�͗ǂ��Ȃ�̂�
�@�J�炵���J���~�����Ƃ̋L�����c��Ȃ��܂܂ɁA��������Ɣ~�J�������Ă��܂��܂����B�~�J�����ƂȂ����X��(�y)�ߌ�A���̎s������s�Ȃ��A�ҏ��ɂ�������炸�A���V����13�l�����Ă��������܂����B
�@�Q���҂̊S���́A�����������̂ł̏�����s���̕��ː��ʏƁA����A�����e�[�}�Ɍf�����A�V�s���̎s���^�c�ɂ��āB�V�s���̎s���^�c�ł́A�S�~���Ǝs���𗬃Z���^�[����ђ��Ɍ��ݖ��Ɏ��₪�W�����܂����B
�@�������A�����z�z�������W�������o�c�e�t�@�C���Ōf�ڂ��܂��̂ŁA���Q�Ƃ��������B
�s���𗬃Z���^�[�̂Ăƍ���
 �@�s�s�Đ��@�\(�t�q)���u���ʁA�b��Ǘ��v���s�Ȃ����ƂɂȂ����u������s���𗬃Z���^�[�v�B�Ȃ��A����Ȏ��ԂɂȂ����̂��B�ʂ����āu���ʁv�ōςނ̂��B�S���ȍ~�A���̃z�[���͂ǂ�����̂��B������s���w������K�v������̂��B�ȂǂȂǁA�u�s���𗬃Z���^�[�v���߂����ẮA�l�X�Ȉӌ�����ь����Ă��܂��B �@�s�s�Đ��@�\(�t�q)���u���ʁA�b��Ǘ��v���s�Ȃ����ƂɂȂ����u������s���𗬃Z���^�[�v�B�Ȃ��A����Ȏ��ԂɂȂ����̂��B�ʂ����āu���ʁv�ōςނ̂��B�S���ȍ~�A���̃z�[���͂ǂ�����̂��B������s���w������K�v������̂��B�ȂǂȂǁA�u�s���𗬃Z���^�[�v���߂����ẮA�l�X�Ȉӌ�����ь����Ă��܂��B
�@���̊Ԃ̌o�߂ƌ��݂̏A�ǂ�����ׂ��Ȃ̂��ȂǁA���̓��̐��������˂āA�u�s���𗬃Z���^�[���v���e�[�}�Ƃ����s������P��22��(�y)�ߌ�A22�l�̎Q���̂��Ƃōs�Ȃ��܂����B
�@�e�[�}�͂�����A�u����������w�����ʍL��Ɖw�Ɂv�B�ĊJ�����Ƃ̈�ōs�Ȃ��Ă�������ʍL��̐����ƁA���ˉ����Ƃōs�Ȃ��Ă���w�ɂ̐����A�����č��ˉ����p�ȂǁA�ĊJ�����Ƃւ̎^�ۂ⍂�ˉ����Ƃւ̌����͗l�X���낤�Ƃ��A���ɓ����Ă��鎖���ɑ��Ă̎s���̊S�͓��R�ɂ���܂��B���̓��e�ƍ���̗\��𒆐S�ɐ������s�Ȃ��܂����B
�@���^�ł́A�S�~����t�ɍs�Ȃ���s���I�̌��Ґl�I�Ȃǂɂ�����сA����������Ȏs����ƂȂ�܂����B
�@�z�z�������W�����͂Q�_�B�P�_�́u�s���𗬃Z���^�[�̂Ăƍ���v�B���̊ԁA���z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă������e�𒆐S�ɂ܂Ƃ߂��������̂ŁA�a�S�łU�y�[�W�ɂ���Ԃ��̂ł��B�����P�_�͂a�S�łP�y�[�W�́u����������w�����ʍL��Ɖw�ɂ̐����v�B�o�c�e�t�@�C���Ōf�ڂ��܂��̂ŁA���Q�Ƃ��������B
����ȁw�s���𗬃Z���^�[�x�ł����̂��H
 �@������s�̈�t�s���́A���݊J����Ă���X�����s�c��ɁA�u�s���𗬃Z���^�[�v�̎擾�c�Ă��o���܂����B�ĊJ�������ɓs�s�Đ��@�\(�t�q)�Ɉ˗����Č��ĂĂ���������̂ł��B���������̌����́A���z�[���͍��Ȑ����ő��150�ȕ��A��z�[����578�Ȃ����Ȃ��A���N������s���J�Â��Ă��鐬�l�����h�V����A���w�Z�⒆�w�Z�̘A�����y��Ȃǂ��A�ꓯ�ɏW�܂��čs�Ȃ����Ƃ��ł��Ȃ������㕨�ł��B�������A�w�O�̂����Ƃ��n���̍����ꏊ�Ɍ��Ă��Ă��邽�߁A�����ɂ�������炸�A�s�s�Đ��@�\����擾���鉿�i�ׂ͂�ڂ��ɍ����B���������ƕۗ����������킹��63��4,000���~�]�B�n�����֏�╍�ѐݔ��A���̑��������̍��N�x�ɕK�v�Ȍo���������ƁA����70��3,400���~�߂��ɂȂ�Ƃ������̂ł��B �@������s�̈�t�s���́A���݊J����Ă���X�����s�c��ɁA�u�s���𗬃Z���^�[�v�̎擾�c�Ă��o���܂����B�ĊJ�������ɓs�s�Đ��@�\(�t�q)�Ɉ˗����Č��ĂĂ���������̂ł��B���������̌����́A���z�[���͍��Ȑ����ő��150�ȕ��A��z�[����578�Ȃ����Ȃ��A���N������s���J�Â��Ă��鐬�l�����h�V����A���w�Z�⒆�w�Z�̘A�����y��Ȃǂ��A�ꓯ�ɏW�܂��čs�Ȃ����Ƃ��ł��Ȃ������㕨�ł��B�������A�w�O�̂����Ƃ��n���̍����ꏊ�Ɍ��Ă��Ă��邽�߁A�����ɂ�������炸�A�s�s�Đ��@�\����擾���鉿�i�ׂ͂�ڂ��ɍ����B���������ƕۗ����������킹��63��4,000���~�]�B�n�����֏�╍�ѐݔ��A���̑��������̍��N�x�ɕK�v�Ȍo���������ƁA����70��3,400���~�߂��ɂȂ�Ƃ������̂ł��B
�@�����āA���́u�s���𗬃Z���^�[�v�͑��̌����Ɓu�P�M�P���v�̈����Ƃ���Ă���A���������̈ꕔ�⌚���O���̒ʘH��������ѕǖʂȂǂɁA���̌����҂Ƃ̋��p�������������A���݂��܂��B���̂��߁A���̋��p�����������ҊԂŋ��c���āA�x��Ȃ��g����悤�ɂ��邽�߂́u�Ǘ��K��(�����ҊԂ̋��菑)�v��������邱�Ƃ��K�v�ł��B�������A�����̎擾�c�Ă��o���������ɂ����Ă��A�Ǘ��K��͒�������Ă͂��܂���B
�����̎s���́A���Ȑ�888�Ȃ̌�����ĊJ���ɂ���Ď��ꂽ���Ƃ���A����ɑ���{�݂Ƃ��Ắu�s���𗬃Z���^�[�v�Ɋ��҂��Ă��܂��B�����āu���̎{�݂Ōh�V���l�����悤�₭�ł���悤�ɂȂ�v�ƁA���̓���҂���тĂ��邱�Ƃ������ł��B�������A���̌����ł͈ꓯ�ɉ�邱�Ƃ͕s�\�ł��B�������A�Ǘ��K�������Ă��炸�A������s���\�肵�Ă��闈�N�S������̃I�[�v�����\�Ȃ̂��ǂ����A�^�₪�o����鎖�ԂƂȂ��Ă��܂��B
�@���������A2003�N12���ɏ�����s���s�s�Đ��@�\�ƌ��u�o���v�ł́A�s�c��s���𗬃Z���^�[�p�̌����̎擾�c�Ă���������ɁA�s�s�Đ��@�\�������̌��ݒ��H�ɓ��邱�Ƃ����L����Ă��܂����B�������A�s�s�Đ��@�\�͂��́u�o���v�����āA���ݒ��H�����s�B������s�����̍s�ׂ�e�F���A�ꏏ�ɂȂ��āu�o���v���z�S�ɂ��Ă��܂��܂����B�u�o���v�ǂ���Ɍ����̎擾�c�Ă��H�����H�O�Ɏs�c��Ɏ����Ă���A�s�c��́A�\�肳��錚�����ǂ̂悤�Ȍ`�ԂɂȂ�̂��A�����ҊԂ̒����ɂ͂ǂ�Ȃ��̂��K�v�ƂȂ�̂��A�h�V���l���͍s�Ȃ���̂��ȂǁA�v��}�ʂ����Ȃ���A���O�Ƀ`�F�b�N���邱�Ƃ��\�ƂȂ�܂��B���̍ۂɁA�u���̌����ł͎s���v�]�ɉ������Ȃ��B���܂��܂ȃn�[�h�����҂��\���邱�ƂɂȂ�v�Ƃ������Ƃ��킩��A�s���̌v��Ɏ^���̋c�����A�ĊJ�����ƂɈ٘_��������c�����A�����̌`�Ԃ̉��P�⌠���ҊԂ̃g���u���������Ȃ��悤�Ȏd�g�݂��A���̎��_�ŋ��߂邱�Ƃ��ł���킯�ł��B���̋@���D�����A��t�s���Ɠs�s�Đ��@�\�̐ӔC�͏d��ƌ��킴��܂���B
�@���{���Y�}�s�c�c�́A�X���S��(�y)�ߌ�A�s���𗬃Z���^�[�̉ۑ����_�ɂ��āA�s���ƍ��k�������J�Â��܂����B���k��ɂ�40���O��̐l���Q�����A���X�ɁA��t�s���̎s���^�c��ᔻ�B�u�ǂ̂悤�ɂ���A�s���𗬃Z���^�[��Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ��ł���̂��v�Ȃǂ̈ӌ�����ь����܂����B�@
�@�@�����k��Ŕz�z�������W�������o�c�e�t�@�C���Ōf�ڂ��܂��B���ЁA�������������B
�w�O��^�J���E���ɖ��Ɓw��R���s�v��j�i�f�āj�x
�@�R���U���̓y�j���̌ߌ�A�S�J���Ԃ�Ɏs������J���܂����B���J���p�����Ă���ɂ�������炸�A���ɂ͏�A�g�܂߂�20�����������A����ɔz�z���ꂽ���W������M�S�ɒ��߂Ȃ���A���̃c�^�Ȃ������Ɏ����X���Ă���܂����B
�@����̕�̃��C���́A���݊J����Ă���R�����s�c��Ɏs�������Ă���Ă���V�N�x�\�Z�̊T�v�ƁA�V�N�x����U�N�Ԃ̌v��Ŏ�����Ă���u��R���s�������v��j(�f��)�v�̊T�v�����B�����āA�s���̕��X�������Ƃ��S�̍����A�V�N�x����̃S�~���ɂ��Ăł��B
�@�P���Ԃ̐����̌�ɁA���^�̎��Ԃ��݂����܂����B�����ł́A����������w����ĊJ�����Ƃ̊T�v��S�~���̍s���A�Ȃ��S�~�����{�݂̌��ݏꏊ���m�肵�Ȃ��̂��ȂǁA���݂̎s���̒��S�ۑ�Ɏ��₪�W���B�����ɁA�w���ۈ�A�}���فA���w�Z���H�����̈ϑ����A������s���ɖ{���n��u���u�ӂ邳�ƃL�����o���v�̎��Ȕj�Y���ȂǁA���L�����₪�W�J����܂����B���͎茳�̎������Ђ�����Ԃ��Ȃ���A�l�ꔪ��̐����B���x�̂��ƂȂ���A���g�̕��s���ɋC���d���Ȃ邠�肳�܂ł����B�����z�z�������W�����E�������o�c�e�t�@�C���Ōf�ڂ��܂��̂ŁA���Q�Ƃ��������B
�ĊJ�����ƃS�~���Ŏs������J��
�@11���P���̓��j���̌ߌ�A�X�����s�c����I���Ă̎s�����15�l�̎Q���̂��ƊJ���܂����B����A�^����ꂽ�e�[�}�́u����������w����ĊJ�����Ɩ��v�Ɓu�S�~�����{���ݖ��v�B��������A�����̏�����s�̑傫�ȉۑ�ƂȂ��Ă�����̂ł��B
�@����������w����ĊJ�����Ƃ́A���E�I�ȕs���Ŏs�Ŏ�������������ł���ɂ�������炸�A��t�s��������ɂނɂ����߂Ă�����̂ŁA���łɁu��P�n��v(�R.�Sha)�͏�����s���擾�\��́u�s���𗬃Z���^�[�v�ȊO�͌����������B���݁A�s���𗬃Z���^�[�Ɖw�O�L��̐������s�Ȃ��Ă��܂��B��t�s���́u��P�n��v��������ɂ́A���̓쑤�́u��Q�n��v(�P.�Xha)�̍ĊJ�����_���Ă���A�������m�[��˂������A�����E�����̊J���D�搭�����Ђ�����������Ƃ��Ă��܂��B
�@�S�~�����{���ݖ��ł́A������s�����݂�ڎw���Ă���u���p�n�v���ߗ����̗̂������Ȃ��Ȃ��ŁA���܂����A���j�]�������߂��Ă��܂��B�W���T���̎s�c����ʈψ���ł͎s�����������Ă����Ж��}�̃x�e�����c������u12���c��^�C�����~�b�g�v�Ɠ˂������A���悢�拇�n�ɗ�������鎖�ԂƂȂ��Ă��܂��B�Ж��}�̋c���́u���s�̊����̏ċp�{�݉^�c�c�̂ւ̒��ԓ��������ɓ����ׂ��v�Əq�ׂĂ���A12���c��͑傫�ȎR����}���邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�s����ł͏�L�Q�̃e�[�}�ɂ��ƂÂ������W������z�z���܂����B�o�c�e�t�@�C���Ōf�ڂ��܂��̂ŁA���Q�Ƃ��������B
�s�c�I��A�ŏ��̎s����
 �@�s�c��c���I����̍ŏ��̒��s�c��U���ɍs�Ȃ��A�U��28���ɂ́A�U���c��̓�����s����o�c�Ă̓��e�Ȃǂ��Љ���s�����20�l�̏o�Ȃ̂��ƁA�s�Ȃ��܂����B���̍ۂɔz�z�������W�������o�c�e�t�@�C���Ōf�ڂ��܂��̂ŁA���Q�Ƃ��������B �@�s�c��c���I����̍ŏ��̒��s�c��U���ɍs�Ȃ��A�U��28���ɂ́A�U���c��̓�����s����o�c�Ă̓��e�Ȃǂ��Љ���s�����20�l�̏o�Ȃ̂��ƁA�s�Ȃ��܂����B���̍ۂɔz�z�������W�������o�c�e�t�@�C���Ōf�ڂ��܂��̂ŁA���Q�Ƃ��������B
�s�c�I��A�ŏ��̒��s�c����I���āi291KB�j
�s�c�I���T���Ă̎s����
 �@�R��22�������E29�����[�ŏ�����s�c��c���I�����s�Ȃ��܂��B16�N�O��34�œ��I���Ĉȍ~�A�c���̎d����n��̎d���ɑ�����A�C�������̂Q����50�B�S�N���ƂɎʐ^���B��̂ŁA�S�N�̊ԂɊ�̃V���┒���������Ă������Ƃ��ۉ��Ȃ��ɂ킩��܂��B�����S�g�̎ʐ^���B���Ă����Ȃ�A���̏o��܂ł�������Ɣ����������Ƃł��傤�B �@�R��22�������E29�����[�ŏ�����s�c��c���I�����s�Ȃ��܂��B16�N�O��34�œ��I���Ĉȍ~�A�c���̎d����n��̎d���ɑ�����A�C�������̂Q����50�B�S�N���ƂɎʐ^���B��̂ŁA�S�N�̊ԂɊ�̃V���┒���������Ă������Ƃ��ۉ��Ȃ��ɂ킩��܂��B�����S�g�̎ʐ^���B���Ă����Ȃ�A���̏o��܂ł�������Ɣ����������Ƃł��傤�B
�@16�N�O�́A�䂪�ƂɎq�ǂ��͂��܂���ł����B�S�N��ɂ͂Q�l�̓��c��������A���̂S�N��ɂ͏�̎q�͏��w�Z�P�N���B�����āA���̂S�N��̑O��́A�T�N���ƂR�N���ɂȂ��Ă��܂����B����͒��w�R�N���ƂP�N���B�q�ǂ����ǂ�Ȏ����������Ƃ������ƂŁA���̍��̂��Ƃ��v���o���Ƃ����ł��B
�@�s�c�I��O�ɂ��āA�P��31��(�y)�ƂQ��11��(��)�̗����A���̎s������J���܂����B�������20�l�O��ɂ����ł��������A�����̎s���̏d�v���ƂȂ��Ă���u�w�O�s�������v����v�u�S�~�����{���ݏꏊ���v�𒆐S�ɕ��܂����B�u�w�O�s�������v����v�ł́A�P�����{�Ɏs�������ݏꏊ���s���ɖ₤�u�Z�����[���(��)�v��R�c�����Վ��s�c��̌��ʂ𒆐S�ɐ������A�u�S�~�����{���ݏꏊ���v�ł͓��ċp��p�n���Ȃ�����Ȃ̂�����j�I�o�߂�n���I�Ȗ����܂߂Đ������܂����B�܂��A�Q��11���̕�ł́A��J�������n�܂����\�Z�c��̓��e�����܂����B
�@���ɖ����S�~�����A�s���̔M�����_�ƂȂ��Ă��܂��B�����\��̊e�w�c��������̖��ł̃`���V���`�������ɓW�J����A�s���̂Ȃ��ł̊S���������ɍ����Ȃ��Ă��Ă��܂��B�Z�����Ȃ��Ŏs����ɂ����ł������������X����́u�Ȃ�Ƃ��Ă��q����I�����Ȃ��Ắv�̐��ɉ����邽�߂ɁA�c��ł��n�抈���ł��A�����Č��҂Ƃ��Ă��A�S�͂Ŋ撣��Ȃ���Ɖ��߂Č��ӂ���v���ł����B�Ȃ��A�s����p�ɍ쐬���������R�_���o�c�e�t�@�C���Ōf�ڂ��܂��̂ŁA�������������B
�Q�O�O�X�N�x�N�ԗ\�Z�Ɍ��鏬����s���i�T�v�j�i299KB�j
�[���������u���ł̃S�~�����{���݁v���j�i303KB�j
�s���̍����������u�Z�����[��ᐧ��^���v�i823KB�j
��t�s���́w�w�O���Ɂx�v�����߂����悤
�@������s�͗��N�x�ɂ��A����������w�����Q�n��̍ĊJ�����Ƃ̓s�s�v�挈����s�Ȃ����Ƃ��Ă��܂��B���łɒn���n���҂̉�̐ȏ�ɂ́A�ĊJ�����Ƃ̌v��}�ʈĂ�������A�s���̒m��Ȃ������ɒ��X�ƌv�悪�����߂��悤�Ƃ��Ă��܂��B
�@���݂����߂��Ă����P�n��̍ĊJ�����Ƃł�����������s�͔���ȍ����𓊓����悤�Ƃ��Ă���̂ɁA����ɑ�Q�n��̍ĊJ���ɂ܂Œ��肷��悤�ɂł��Ȃ�A������u�s�������v�v���s�Ȃ����Ƃ���ŁA�����I�ɍs���l�܂邱�Ƃ͖ڂɌ����Ă��܂��B
�@������������s�́A��Q�n��̍ĊJ�������Ɏs���������݂��悤�Ƃ��Ă��܂��B�s���������Ă邽�߂ɗ��q�܂߂�119���~�ōw�������W���m���~�V���H��Ւn�������Ă��Ȃ���A�킴�킴�n���̍����w�O�Ɏs���������ĂāA�W���m���Ւn��43���~�Ŕ��肳���Ă��܂��Ƃ����̂ł��B�W���m���Ւn�����S�����x�ɋ����Ȃ����w�O�̓y�n���m�ۂ��邽�߂ɁB
�@������s�ɂ́u���[�X�i�؉Ɓj���Ɂv�Ƃ������̂�����܂��B�W���m���Ւn�ւ̎s�������ݎ������s�����Ă��邽�߁A���������܂�܂Ŗ��ԃr�����s�����Ƃ��Ď��Ƃ������̂ŁA���N��15�N�ڂɂȂ�܂��B�Ƃ��낪������s�͂W�N�O�Ɂu�w�O�J�����ւ̎s�������݁v���j��ł��o�������߁A���������܂邩���܂�Ȃ����Ƃ��������ł͂Ȃ��A�w�O�ĊJ�����Ƃ������ނ��ǂ����ŁA�s�������݂̃��h�����܂�Ƃ��������ɕύX����Ă��܂��܂����B���̂��Ƃ���A���100���~�߂���₷�u���[�X���Ɂv�́A������ʂĂ��Ȃ��������ԂɂȂ�܂����B
���̈���ŁA�u�������������v�u�s�������v�͓����v�Ə̂��āA�s���T�[�r�X�̍팸�E�p�~�A�s�����S���A���Ԉϑ��������s����A�s���̐؎��ȗv�������͌�ɂ���Ă��܂��B�u�w�O���Ɂv���j������������A�u���[�X���Ɂv�͑����A�s���̐؎��Ȋ肢�͎�������܂���B���܂����A�w�O���Ɍv�����߂����邽�߂ɗ����オ�邱�Ƃ��K�v�ł��B
�@�J���~��W��24��(��)�̌ߌ�A�n��̎s���W��{�݂Ŏ��̎s����J����܂����B�s�������Əċp�ꌚ�ݖ�����A20�l�̎Q���҂���l�X�Ȏ����ӌ����o����܂����B���t�͂T���ڂ��߂���������s�c��c���I���ł��B���炵����鏬����s�ցA�S�͂Ŋ撣��Ȃ���Ȃ�܂���B�Ȃ��A�����̃��W�����Q��ނ��o�c�e�t�@�C���Ōf�ڂ��܂��̂ŁA���Q�Ƃ��������B
��t�s���́u�w�O���Ɂv�v�����߂����悤PDF�i475KB�j
�ċp����n�u���p�n�v�ł͍s���l�܂�PDF�i186KB�j
�������҈�Ð��x��S�~���Ŏ��⑱�o
 �@���c��I��邲�ƂɊJ�Â��Ă���s������A�S��27��(��)�ߌ�A25�l�̎Q���҂̂��ƂŊJ���܂����B����̃e�[�}�́u�������҈�Ð��x�v�Ɓu���Ɍ��ݖ��v�B�������A����ȊO�̎����ł��A���₪����Γ����܂����B �@���c��I��邲�ƂɊJ�Â��Ă���s������A�S��27��(��)�ߌ�A25�l�̎Q���҂̂��ƂŊJ���܂����B����̃e�[�}�́u�������҈�Ð��x�v�Ɓu���Ɍ��ݖ��v�B�������A����ȊO�̎����ł��A���₪����Γ����܂����B
�@�S������X�^�[�g�����u�������҈�Ð��x�v�͓{��������A���g�̌o����{��������ɏЉ��l�A�u������s�̈�t��͂ǂ����Ă���v�ƁA��t��̑Ή��ɋ^���悷��l�A�u���̐��x�Ƀ����b�g�͂���̂��H�v�ƁA�����}�E�����}�ɓ{����Ԃ���l�ȂǂȂǁB�m��Βm��قǃq�h�C���x�ɁA�Ō�͓{��̑升���ƂȂ�܂����B
�@���Ɍ��ݖ��ł́A�M�d�Ȑŋ����ĊJ�����Ƃɂ����݁A�ĊJ�����Ƃ𐬗������邽�߂ɊJ�����ɒ��ɂ�g�ݍ���ł��邱�ƂɁA�����̐��B�������A�ĊJ�����ɒ��ɂ��ł���܂Ń��[�X(�؉�)���ɂ��p������邱�Ƃɑ��ẮA�u�Ȃɂ�����Ă���I�v�Ɠ{��S���B�u�ǂ�������s����ς��邱�Ƃ��ł���̂��H�v�ƁA���₳��鎖�ԂƂȂ�܂����B
�@��炵����ςȂ̂ɑ�^�J���ɐŋ��������̂悤�ɒ������܂�A���ł͈�Ð��x�̉����A�������N���A�K�\�����̎b��ŗ������ȂǁA�����̕�炵�������̂��Ńq�h�C�������J��L�����Ă��܂��B�u������ς���v�����������̂��Ƃ������قǁA���R�̂��ƂƂ��Č���Ă��鎞�͂���܂���B���U���I���ŁA���ӂ����������f����鐭���ɂ��邱�Ƃ���ł��B����̎s����ł͂Q��ނ̃��W������p�ӂ��܂����B�o�c�e�t�@�C���Ōf�ڂ��܂����̂ŁA�������������B
����́g���Ύ̂ĎR�h�u�������҈�Ð��x�vPDF�i246KB�j
�s��Ȗ��ʌ����u�ĊJ�����ւ̒��Ɍ��݁vPDF�i317KB�j
�������҈�Ð��x��S�~���Ŏ��⑱�o
�@�Q��17��(��)�̌ߌ�A�s�����n��̏W��{�݂ŊJ���܂����B�p�ӂ������W�����́A�S�~�������ƌ������҈�Ö��B�n�܂鍠�ɂ͗p�ӂ������W����������Ȃ��Ȃ�قǂ̎Q����(30�l�])���}���A���W���������炦�Ȃ��l�܂łłĂ��Ă��܂��܂����B�����ߕ��́A���̂ق�����P���ԁA�������A���Ƃ͎���ɉ�����`���B�\�z�͂��Ă��܂������A����ɂ킽���Ă̎��₪�J��o����A���̏�ł͑����ł��Ȃ����̂�����܂����B
�@�S�~���ł́u���S�~�����炷���߂ɂ͂ǂ̂悤�Ȃ������悢�̂��v��u�ǂ̂悤�ȃS�~��������������̂��v�Ƃ��������₪�o�����ƂƂ��ɁA�Q���Ҏ��g�̐��S�~���ʂɌ��������g�݂̌o��������܂����B����A�������҈�Ö��ł͐��x�ւ̓{�肪���X�ɔ�яo���A���{���ł��o�����o�ߑ[�u�̂��e�����ɁA����Ȃ�{�肪����܂����B�܂��A���茒�f�ɂ��T�N�Ԃ�10���́u���^�{���b�N�E�V���h���[���v�����炷���g�݂ɑ��ẮA�������̂悤�Ɍ�������t���傢�Ȃ����U���܂������A�P�Ȃ�W���[�N�Ƃ������Ȃ��̂��|���Ƃ���ł��B���̃W���[�N�Ƃ̈́��������B
�@�u����A�w��ׂ��x�Ƃ����R�c�m���ē̉f����ς��̂ł����A���̎���́A�����ɑ���l�����E�N�w�̈Ⴂ���w���x��������Ă��܂����B�ł�����̓��茒�f�́A�̏d�������Ƃ��������Łw���x�����ɂ��ꂩ�˂܂���B�Ȃ��Ȃ�A�w���^�{�x���T�N�Ԃ�10�����炳�Ȃ�������A���̎����̂̓y�i���e�B���ۂ����A�L��A���ւ̋��o���𑽂��x����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ邩��B����ȃq�h�C���x���A�w���^�{�x���炯�̍���c�������߂Ă��܂����̂ł��B���ꂩ��́A���̎��͂��L�����Ă��邾���Ŗ�莋����鎞�オ����Ă����ł��v�B
�@�u���^�{�v�łЂƂ�����b���炫�A�w�O�ĊJ�����Ƃ�w�Z���H�����Ɩ��̖��Ԉϑ����A�n�����g���ւ̑�ȂǁA�b��͌��s���܂���B�\�肵�Ă������Ԃ͂����Ƃ����Ԃɉ߂��A�u�܂��A���̂悤�Șb�����Ă��������l�v�Ƃ̂��肪�������t�����������Ȃ���A�s������I�����܂����B�����A�z�z�������W�������o�c�e�t�@�C���Ōf�ڂ��܂����̂ŁA�������������B
�S�~�����{�݂̌��ݏꏊ�I��͂ǂ�����ׂ���PDF�i1766KB�j
�������҈�Ð��x�ƌ��f���x�̕ύXPDF�i806KB�j
�������҈�Ð��x�Ɏ��⑱�o
�@10��27��(�y)�ߑO�A���̎s������T�J���Ԃ�ɊJ���܂����B�䕗���ڋ߂��A�����ɂ��̉J���~��Ȃ��ł̎��g�݂ƂȂ�܂������A18�l���Q�����Ă���܂����B
�@����̃e�[�}�́u����������w����ĊJ�����Ƃƒ��Ɍ��ݖ��v�Ɓu��Ð��x����ƌ������҈�Ð��x�v�̂Q�{�B�u����������w����ĊJ�����Ƃƒ��Ɍ��ݖ��v�ł́A��N����n�܂����w�O�J���̌���Ɩ��_�ɂ��āA����ђ��Ɍ��ݗ\��n���w�����Ă����Ȃ���؉ƃr���Ŏs�������^�c���A�������ɂ͍ĊJ�����Ƃ𐬗������邽�߂ɉw�O�ɒ��ɂ����Ă�v��܂őł��o���Ă��邱�ƁB�������s�����Ƃ��Ď�Ă���r�����w������Ƃ����b�܂Ŕ�яo�����Ԃ���Ă��܂��B����A�u��Ð��x����ƌ������҈�Ð��x�v�ł́A���N�S������X�^�[�g����75�Έȏ�҂ɑ����Ð��x�̊T�v�ƁA���茒�N�f�����Ƃ��Љ�B�Q�������l�̑������u�����̉䂪�g�v�ł��邽�߁A��Ð��x���̌������҈�ÂɎ��₪�W�����܂����B
�@�������҈�Ð��x�́A�}�X�R�~���ŕ��Ă��邱�Ƃ�����A���̌��t�͂��������̐l���m���Ă���悤�ł������A���̒��g�ƂȂ�ƁA���܂�m���Ă��Ȃ��̂������̂悤�ł��B�������W���������Ƃɂ��̊T�v���������ƁA�u�N���͑������˂Ƃ������Ƃł����H�v�Ƃ��A�u�܂�ŔN���͎ז��҈����ł��ˁv�Ȃǂ̐�����ь����ƂƂ��ɁA����ɕی������S�������邱�Ƃɑ���{�肪�����o���܂����B�܂��A���{���u�����v�����ɂ������Ă��邱�Ƃ���A�������҈�Ð��x���̂��u�����v���ꂽ�Ɗ��Ⴂ���Ă���l������A���N�S������̍��������܂��猩�ĂƂꂻ���ȏł��B
�@���͍���̎s����ɂQ��ނ̃��W�����ƂQ�̎�����p�ӂ��܂����B�o�c�e�t�@�C���Ōf�ڂ��܂��̂ŁA�Q�l�܂łɂ�������������K���ł��B
������s�̓��茒�N�f���̎��{�v��T�v�@PDF(124KB)
����������w������n��ĊJ���̌��z�H���X�P�W���[���@PDF(101KB)
��Ð��x����ƌ������҈�Ð��x�@PDF(208KB)
����������w����ĊJ�����Ƃƒ��Ɍ��ݖ��@PDF(320KB)
������s�̊w���ۈ珊
�@���̂S���A������s�̊w���ۈ珊�ɓ�������������666�l�ƂȂ�܂����B������s�ɂ͎s�����w�Z���ƂɊw���ۈ珊���ݒu����A���w�Z�P�N������R�N���܂ŁA��Q���͂S�N���܂ł�����ΏۂƂ��Ă��܂��B
�@������s�̊w���ۈ珊��1964�N12���A�Љ�����c��ւ̈ϑ����ƂƂ��Ďs���ɂQ�ӏ��i�����w�Z�Ƒ�O���w�Z�j�J�݂��ꂽ�̂��X�^�[�g�B1971�N�Ɋv�V�s�����a�������̂��@�Ɋw���ۈ玖�Ƃ̒��c���Ɛ��K�E�������s�Ȃ��܂����B������1979�N�ɕێ�s���ɂȂ�A�u�s�v�v�̖��̂��Ƃɐ��K�E���팸�̍U�����s�Ȃ��A�����������̑����ɑ��Ă͐��K�E���ł͂Ȃ��Վ��E���őΉ����鎖�ԂƂȂ�܂����B�܂��A1984�N�V������w���ۈ�̗L�������X�^�[�g�B���z�X��~����{�ɁA�Z���ł̉ېŊz�ɍ��킹�āu�[���v�u�R��~�v�u�T��~�v�u�V��~�v�̕��S�����������܂����i���̋��z�͍����ɂ����Ă������j�B
�@1990�N�S���A�����������͂��ɂT�S�l��˔j���܂����B���̔N�x����e�w���ۈ珊�̓���������u60�l�v�ɉ��߂��A���̂��Ƃɂ���ĂX�w���{�݂̍��v������u540�l�v�ɂ͎���Ȃ��������̂́A�u���܂ނ��v�u�����ˁv��60�l�����������������邱�ƂɂȂ�܂����i�u���܂ނ��v66�l�A�u�����ˁv72�l�j�B�e�w���ۈ珊�̒�����u60�l�v�ɂ����̂́A�O�N12������Łu�S�w���ۈ珊�̒����60�l�Ƃ�����C���āv���c����ĂŒ�o����A�S����v�ʼn����ꂽ���Ƃɂ����̂ł��B�������A���̎��̏��C���ĉ��ɍۂ��ĕt�ь��c���s�Ȃ��܂����B���e�́u�i�P�j�E�����ɂ����Ă͑��̕����Ƃ̋ύt��}�邤���ŁA���݂̐��K�E�������ɂ������邱�ƁB�Ȃ��A�K�v�ȐE�����s������ꍇ�ɂ́A���Ώ������ɂđΉ����邱�ƁB�i�Q�j����Q����10�������i�s�����K�v�ƔF�߂��Ƃ��́A�e�w���ۈ珊�̊����̂����ނ�10���͈͓̔��Ŋ������ē�����F�߂邱�Ƃ��ł���j��K�p���A�Ȃ������L�{�K�͂ł͑Ή��ł��Ȃ��w���ۈ珊�ɂ��ẮA���w�Z��̊w�Z���������g�p���đΉ����邱�ƁB�i�R�j�ȏ�Q�_���^�c���{�̐�Ώ����Ƃ��邱�Ɓv�Ƃ������̂ł��B���̕t�ь��c�����������������A���K�E������{�݂̐V�z�E�����z�����߂�v���ɑ��āA������s�͂��̌��c���|�ɋ��ۂ������Ă��܂��B
�@1990�N�S���ɂT�S�l��˔j���������������́A���N�S���ɂ͂�������T�S�l������A�ȍ~�A1998�N�x�܂łT�S�l����̏�Ԃ𑱂��Ă��܂����B������1999�N�S���ɍēx�T�S�l��˔j���������������́A2001�N�S���ɂ͍��v������u540�l�v����582�l�ɁA��N�S���ɂ͂��ɂU�S�l���鎖�Ԃɔ��W���܂����B�����āA���N�S���̓����������͂���܂łōō���666�l�B�X�w���ۈ珊�̂����̂V�w���ۈ珊�Łu10�������v��66�l���͂邩�ɏ��鎙�����������܂łɂȂ�܂����B
�@�e�w���ۈ珊�ɂ͎q�ǂ��������߂����u�琬���v������܂��B�e�w���ۈ珊�̈琬���̖ʐς�����������Ŋ����Ă݂�ƁA�u�����ˁi�P�j�v�Ɓu�ق傤�v��������l������Q�u���m�ہB����ȊO�̎{�݂͂Q�u�����̋����ʐς����m�ۂł��Ȃ��v�Z�ɂȂ�܂��B���́u�Q�u�v�͕ۈ玺�i�F�O�ۈ牀�j�̉�����l������̊�ʐρB�u������l������A�����ނ˂Q�u�ȏ�v���ۈ玺�̐ݒu��ƂȂ��Ă��܂��B���̊����m�ۂł��Ȃ������琬���ŁA�����ƈقȂ茳�C�����ς��삯��鎙�����������߂��Ă���̂ł��B
�@�t�ь��c���ǂ��̂����̂Ƃ����Ă���ԂɁA�����E���������̈����ɂ���ď����i�����L����A�������ƒ�̑����ɂƂ��Ȃ��w���ۈ珊�ɓ�������]���鎙�����������Ă��܂��B�w�O�J���ɓ�����������̈ꕔ���[�Ă邾���ł��A�{�݂̑����z�͏\���ɉ\�ł��B�����̎g�����������ł�����Ă��܂��B
�ߋ��R�N�Ԃ̊e�w���ۈ珊�����������̐��ځ@PDF(105KB)
��t�s���̂W�N�Ԃ�2007�N�x�\�Z�̓���
 �@�S��15�������E22�����[�ŁA������s���I�����s�Ȃ��܂��B�����E�����̎x�����A�W�N�O����s���ɏA�C���Ă����t�s���́A�u�������S���v�Ə̂��Ďs���ɗL�����E���S���킹�A�s���{������X�ɏk���E�p�~���Ă��܂����B���̈���A�o�u������Ɠ������o�ʼnw�O�̑�^�J���𐄐i�B2007�N�x�\�Z�ł́A�w�O��^�J���ɂW��1,300���~��\�Z�����Ă��܂��B �@�S��15�������E22�����[�ŁA������s���I�����s�Ȃ��܂��B�����E�����̎x�����A�W�N�O����s���ɏA�C���Ă����t�s���́A�u�������S���v�Ə̂��Ďs���ɗL�����E���S���킹�A�s���{������X�ɏk���E�p�~���Ă��܂����B���̈���A�o�u������Ɠ������o�ʼnw�O�̑�^�J���𐄐i�B2007�N�x�\�Z�ł́A�w�O��^�J���ɂW��1,300���~��\�Z�����Ă��܂��B
�@��t�s�������̂W�N�ԂŎs���ɕ��S�킹�A�s���{����k���E�p�~���ē������z�̍��v��12��8,575���X��~�B������̂Ȃ��ɂ́u���H��p���v�u���O�L�������萔���v�̂悤�ɁA�傫�ȗ��v���グ�Ă����Ƃɕ��S�����߂���̂�����A���ׂĂ���肾�Ƃ͂����܂��A���|�I�����͏����̃t�g�R�����炨����D�������̂ƂȂ��Ă��܂��B
�@���̂������A�w�O��^�J���ɂ����ނ��߂̊��(�ϗ���)�z�̑����������ɂȂ��Ă��܂��B�J�����Ƃɂ́A������������A�s�s�ĊJ����������A�����Z���^�[���݊�����[�Ă��Ă���A�����̃t�g�R������D��������z�ɕC�G����12��5,212���R��~���A���̂W�N�ԂŐςݗ��Ă��Ă��܂��B
�@�s���́u�s���ɕ��S�����Ă��������������A�V�K���Ƃɏ[�ĂĂ���v�Ɣ��_���Ă��܂����A�����̃t�g�R������D�������12��8,575���X��~�̒��ɂ́A�w�Z���H�����Ɩ��Ȃǂ̖��Ԉϑ��ŕ������o��͌v�コ��Ă��܂���B���ǂ́A���Ԉϑ��ɂ���ĕ������o���V�K���ƂȂǂɉA�{��̏k���E�p�~��L�����E���S���œ��������́A��^�J���̂��߂̊���ɐςݗ��Ă��Ă���\�}�ƂȂ�܂��B���ɏ�����s�́A�u�w�Z���H�����Ɩ��̖��Ԉϑ����ŕ����������́A����s���̊g�[�ɏ[�ĂĂ����v�Ɛ������Ă��܂��B
�@�R���R��(�y)�ߌ�A�s���I�����߂����Ċ������J��L���Ă���u�s���Q���̎s���������v�́A�s�����w�K��̑�R�e���J�ÁB�s�������𒆐S�ɍs�Ȃ�ꂽ����́A�����u��t�s���̂W�N�Ԃ�2007�N�x�\�Z�̓����v���20���ԁA�������܂����B���̍ۂɗp�ӂ������W�����Ǝ������o�c�e�t�@�C���Ōf�ڂ��܂��̂ŁA���ЁA���Q�Ƃ��������B
�u��t�s���̂W�N�Ԃ�2007�N�x�\�Z�̓����v���W�����@PDF(106KB)
�u��t�s���̂W�N�Ԃ�2007�N�x�\�Z�̓����v�����@PDF(239KB)
��t�s���̂����ł͏ċp����͑卬����
 �@�Q��12��(��)�ߌ�A���̎s�����n��̏W��{�݂ŊJ���܂����B���V�Ɍb�܂�A�N�������o�������������悤�ȗz�C�ł������A26�l���Q�����܂����B �@�Q��12��(��)�ߌ�A���̎s�����n��̏W��{�݂ŊJ���܂����B���V�Ɍb�܂�A�N�������o�������������悤�ȗz�C�ł������A26�l���Q�����܂����B
�@����̓��e�́A������s�̐V�����ċp�{���ݖ��B������s���������s�Ƌ����ŁA10�N���2017�N�S������ғ������悤�Ƃ��Ă���V�ċp�{�݂Ɍ����āA�ǂ̂悤�ȃv���Z�X��ł����ׂ��Ȃ̂����A���Ȃ�ɍl�������̂���܂����B
�@������s�̔R�₷�S�~���ċp���Ă�����ċp�ꂪ�V�����̂��߁A���N�R�����ʼn^�]���I�����܂��B���̏ċp���1958�N�S���ғ��Ƃ����܂�����A����49�N�Ԃ��^�]���Ă������ƂɂȂ�A�����̂̏ċp��Ƃ��Ắu�����ŌÁv�ł͂Ȃ����ƌ����Ă��܂��B������s�́A�^�]���I��������ċp��ɑ����āA���̂S������͍������s�̏ċp��ŏ�����s�̃S�~���ċp���Ă��炢�܂��B�������A�������s�̏ċp��ł͂R���̂P�̗ʂ����Ή��ł��Ȃ��̂ŁA�c��R���̂Q�͎O�����n��̑��̏ċp��Ɉ˗������܂��B�����������_�A������s�̔R�₷�S�~��S�ʁA�����ł��郁�h�͗����Ă��܂���B
�@������s�́A�V�ċp�{�݂��������s�Ƌ����ŏ�����s���Ɍ��Ă�v��������Ă��܂��B2017�N�S������̐V�ċp�{�݉ғ��܂ł̊Ԃ́A�������s�ȂǑ��̏ċp��ɏċp�˗������܂����A�����ɁA�V�ċp�{�݂����݂��邽�߂̎��g�݂��K�v�ɂȂ�܂��B������s�͂P��11���A�������s�ɑ��āA�V�ċp�{�����n�ĂƂ��ĂQ�ӏ�����܂����B�������A���ꂼ��̒n��Z���͎��O�̐�������Ȃ��������Ƃ�����A�{��Ɣ��������߂Ă��܂��B���̂܂܂ł́A10�N��̐V�ċp�{�݉ғ��͊��S�Ɂu�ԐM���v�ƂȂ��Ă��܂��܂��B�ǂ���������̂��A���̂��̂悤�Ȏ��ԂɂȂ����̂��A�����_�A�������ɂȂ��Ă���̂�����������̎s����́A�����܂ł̌o�܂��܂Ƃ߂����A��t�s���������ɏċp�{�ݖ����y�����Ă������A��@�������ɏZ�������ɂȂ��Ă����������S�̕�ƂȂ�܂����B
�@�Q���҂���́A���X�Ɏ��₪��яo���܂����B�u�������s�̏ċp��łR���̂P�����R�₹�Ȃ��Ƃ����̂́A�n��Z���̔������邩��Ȃ̂��v�u�W���m���Ւn�́A����������w����ĊJ�����̎s�������ݗ\��n�Ɠ����������邽�߂̃^�l�n�ɂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ����v�u�w�|��w�̃O�����h��ʐM�����������~�n�́A���n�Ƃ��ă_���Ȃ̂��v�u������n�͌��n�Ƃ��ă_���Ȃ̂��v�ȂǁB�܂��A�ċp���肾���łȂ��A�w�Z���H�����Ɩ��̖��Ԉϑ�����w�Z���H��̑ؔ[���Ȃǂ����₪�o����܂����B
�@����̎s�����ʂ��Ċ��������Ƃ́A�ċp���肪������s���̊Ԃł����ɊS�������Ȃ��Ă��邩�Ƃ������Ƃł����B�V���ŕ��A�e���r�ǂ���ނɂ���Ȃ��ŁA�܂��܂����̖��͎s����̑傫�ȏœ_�ɂȂ��Ă����܂��B���{���Y�}�s�c�c�́A�ċp�{�݂͕K�v���Ǝv���Ă��܂��B�����炱���A�ǂ̂悤�ɐV�ċp�{���݂Ɍ����Ă�����ł����ׂ��Ȃ̂����A�q�b���o�������Ȃ���c�_���������Ă��܂��B����̎s����Ŏ��������������W�������o�c�e�t�@�C���Ōf�ڂ��܂��̂ŁA���ЁA�������������B
�u��t�s���̂����ł͏ċp����͑卬���ɁvPDF(456KB)
�S�~��������ŁE���S���ɓ{�莟�X
�@�X���s�c��̕����˂��s�����10��22��(��)�ߌ�A�s�Ȃ��܂����B��ꂪ�����������Ƃ�����܂����A�Ȃ�ׂ��֎q���قƂ�ǖ��܂�قǂ̎Q���҂ŁA�p�ӂ��������͂قƂ�ǖ����Ȃ�܂����B
�@����̃e�[�}�́u�ǂ��Ȃ�H ������s���̔R�₷�S�~�v�u���ŁE���S�����y�����邽�߂̐��x���p�@�v�u����������w����ĊJ�����Ƃ̍����v�̂R�_�B�O�҂Q�_�͊e�Q���̃��W������p�ӂ��A�u�ĊJ�����Ɓv�́A�X���ɑS�˔z�z�����s�c�c���s�̑唻�`���V�����p���܂����B
�@���W�����E�`���V�������Ă̐������P���ԍs�Ȃ�����̎��^�ł́A�e�[�}���ꂼ��Ɏ��₪��ь����A���ŁE���S�����ł͍��N�x�A����O���t�̕��S���Ŏs�Ŏ������T���U�疜�]�̑����ɂȂ�ɂ�������炸�A���łŋꂵ��ł��鏎���̂��߂̕����T�[�r�X���팸���悤�Ƃ��Ă��邱�Ƃɓ{�肪���o�B����ŁA����ȍ�����K�v�Ƃ�������^�ĊJ�����Ƃ�����ɂނɂ����߂悤�Ƃ��Ă��邱�ƂɁA�ŋ��̎g�����͂���ŗǂ��̂��Ƃ̐���������܂����B
�@�����ɁA�����̐����ɒ��ɉe������R�₷�S�~�̗��N�S���ȍ~�̏����̃��h�������Ă��Ȃ����Ƃɑ��ẮA�Ȃ������ɂȂ��čQ�Ă邱�ƂɂȂ����̂�?�A�����s�̐ӔC�͂ǂ��Ȃ̂�?�A10�N�ォ��ċp����V�{�݂̌��ݏꏊ�͂ǂ��ɂ���̂�? �ȂǁA�����̏�����s�̃S�~�s���̕s�\�������w�E���锭���⎿�₪��p�����ɏo����܂����B
�@�܂��A���ŁE���S�����ł́A���N�x���藦���ł̔p�~��A�����ł���Z���łւ̃t���b�g��(�Ō��ڏ�)���s�Ȃ��邱�Ƃւ̌��O���o����A�R���̊m��\�����ނ�����ȑO�ɁA�ŋ��T���̎d�g�݂���@���w�ԉ��݂���ׂ��Ƃ̈ӌ����o����܂����B
�@���߂āA�ŋ��̎d�g�݂��s����ň����܂������A�����g�A�s���ŁA���₳��Ă��\���ɐ����ł��Ȃ��_������������܂����B���܂��܂Ȏ�����ӌ��ɉ�������悤�A����ɕ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ɗ���������ꂽ�s����ł����B�Ȃ��A����p�ӂ����Q�̃��W�������o�c�e�t�@�C���Ōf�ڂ��܂����̂ŁA�������������B
�u�ǂ��Ȃ�H�@������s���̔R�₷�S�~�vPDF(232KB)
�u���ŁE���S�����y�����邽�߂̐��x���p�@�vPDF(221KB)
�J���D��s���ł��Ȃ��̕�炵�͎��܂����H
 �@�R���c��́A�����̂̔N�ԗ\�Z��R�c����A�N�Ԃōł��d�v�ȋc��ł��B���́A�R���c��(�Q��28���`�R��28��)���n�܂钼�O�̂Q��26��(��)�ƁA�R���c��I����Ĉȍ~�̂S��23��(��)�Ɏs������J���A�Q��26����25�l���A�S��23���ɂ�22�l�ɎQ�����Ă��������܂����B �@�R���c��́A�����̂̔N�ԗ\�Z��R�c����A�N�Ԃōł��d�v�ȋc��ł��B���́A�R���c��(�Q��28���`�R��28��)���n�܂钼�O�̂Q��26��(��)�ƁA�R���c��I����Ĉȍ~�̂S��23��(��)�Ɏs������J���A�Q��26����25�l���A�S��23���ɂ�22�l�ɎQ�����Ă��������܂����B
�@���́A�s������}���邽�тɎ��������˂����W�������쐬���Ă��܂����A����́A�S��23���ɍs�Ȃ����s����ŎQ���҂ɔz�z�������W�������o�c�e�t�@�C���Ōf�ڂ������܂��B����A���Q�Ƃ��������B�Ȃ��A�E�̎ʐ^�͂Q��26���̎��̂��̂ł��B
�u�J���D��s���ł��Ȃ��̕�炵�͎��܂����H�vPDF(432KB)
���@�X���͐푈��h���ő�̗�
�@�����E�����͌��@�X���̂ɂ��邽�߂́u���@����v��_���Ă��܂��B���͒n��̋��Y�}�̐l�����ƂƂ��ɁA2005�N12�����疈�����A�n��̃X�[�p�[�O�Łu���@�X������낤�v�Ɛ�`�s���𑱂��Ă��܂��B�Ǝ��̃`���V�͂P���ɏo���オ��A�P���̐�`�s���Ŋ��p���܂����B���̌�A��C�����A�Q���̍s���ł͂o�c�e�t�@�C���Ōf�ڂ����`���V�i�a�S���\�j��z�z���A�u�Ԋ��v�������A���j�łɂ��܂荞�݂܂����B���ЁA���Q�Ƃ��������B
�u���@�X���͐푈��h���ő�̗́vPDF�i535KB�j
������t�̑呝�łŎs���̂��炵�͑��
�@�����E�����Ɏx����ꂽ������t�́A2005�N�x���珎�����ł�{�i���{�B2006�N�x�ɂ͒藦���ł̔����ȂǂŁA���������̑��ł��������悤�Ƃ��Ă��܂��B�呝�łŏ�����s���ɂ́A�ǂ̂悤�ȉe�����N����̂��B2005�N12���c��Ŏ����s�Ȃ�����ʎ�������ƂɁA���̉e�����܂Ƃ߂Ă݂܂����B�`���V�ɂ��Ĕz�z�������̂��o�c�e�t�@�C���Ōf�ڂ��܂��B
�u������t�̑呝�łŎs���̂��炵�͑�ρvPDF�i1402KB�j
�J���D��s���ł̓��[�X���ɂ͏I���Ȃ�
�@2005�N10��23���ɒn��ōs�Ȃ����A���̎s����W�������o�c�e�t�@�C���Ōf�ڂ��܂����B�������������B
�@�s����̓��e�́A10��18������21���܂ŊJ���ꂽ2004�N�x���Z�ψ���ɂ�����_�_�̂Ȃ�����A�i�P�j��t�s�������[�X�s����(�؉ƒ���)�����Ȃ��Ƃ��A���ƂW�N�Ԏ葱���邱�Ƃ�\���������Ƃƕ���������w����ĊJ�����ƂƂ̊֘A�ɂ��āB�i�Q�j���̈���ŁA�s���̂��炵�������ɑ�ςɂȂ��Ă��邩���������B���̓�_�𒆐S�Ɉ����Ă��܂��B
�@�Ȃ��A���W�����R���ڂ́u�q�^��̋c���v���A[�A�X�x�X�g��Q����s����������邽�߂̎{���]�́u�Q�̏��w�Z�v�̊w�Z���́A�u�Ώ��w�Z�v�Ɓu��w�Z�v�ł��B���̂Q�Z�͂W�����_�Ŕc���ł����Ƃ���ŁA���̌�u��O���w�Z�v�Ɓu�쒆�w�Z�v�ł��������Ă��܂��B�S�Z��������A���Ȏ����p�̃A���R�[�������v�t���̋��ԕ����Ɏg�p����Ă��܂����B�������A�S�Z�Ƃ����ۂɂ͎g���Ă��炸�A�I�̉��ɂ��܂��Ă����Ƃ̂��Ƃł��B
�@�s����ł͑����̈ӌ��⎿������A����(2005�N10�����_)�A����ɉ����邽�߂ɑ������Ă��܂��B
�u�J���D��s���ł̓��[�X���ɂ͏I���Ȃ��vPDF�i1657KB�j
������s�̎s�������w�Z�̑ϐk�f�f�E�ϐk�⋭�H���v��
�@������s��2005�N�x�ɑ�ꏬ�w�Z�A��w�Z�A�Ώ��w�Z�̑ϐk�⋭�H����\�肵�Ă��܂��B�܂��A�v��ɓ���Ă��Ȃ������s���ۈ牀�̑ϐk�f�f���X�^�[�g�����A2005�N�x�́u����̂ݕۈ牀�v�̑ϐk�f�f���s�Ȃ��܂��B�o�c�e�����́u����Ԃ���v��2005�N�T���P���t�Ɍf�ڂ������̂ł��B
�u������s�̎s�������w�Z�ϐk�f�f�E�ϐk�⋭�H���v��vPDF�i444KB�j
�������s���B���炵���������鐭�������߂��Ă���
�@�s�c�I�i�R��20�������E27�����[�j�O�ɊJ�����s����Ŕz�z�������W�������o�c�e�Ōf�ڂ��܂��B���{���Y�}�s�c�c������������w����ĊJ�����ƂɐT�d�ȑԓx�������Ă��闝�R���L���Ă��܂��B���Ђ������������B
�u����������w����ĊJ�����Ɓv�i1000KB�j
�L�����łȂ��A�S�~�̏o�����̎w���ɑS�͂�
�@������s�͍��N(2005�N)�̂W������A�ƒ납��o�����R�₷�S�~�ƔR�₳�Ȃ��S�~�̎��W�L�������X�^�[�g���܂��B���́A��N12���̎s�c��ŁA�ƒ�S�~���W�L�������ɔ����铢�_���s�Ȃ��A�����ɁA�s�����|�[�g�s���܂����B�o�c�e�Ōf�ڂ��܂��̂ŁA���Ђ������������B
�u05�N�W������ƒ�S�~���W���L���ɁvPDF�i555KB�j
�u�ƒ�S�~���W�L�������ւ̔��Γ��_�vPDF�i614KB�j
�N�ԗ\�Z�����Ɩ���}�s�c�̍��ېőؔ[�^�f���
�@2004�N�X���c��͂X���Q��(��)�ɊJ��A�����̊����ʂ�28��(��)�ɕ�܂����B������s�͔N�ԗ\�Z�����������ɂS������b��\�Z�������Ă��܂������A�X���c��ł悤�₭�N�ԗ\�Z�������B�U�J���̎b��\�Z�ɏI�~����ł��܂����B�܂��X���c��ł͖���}�s�c�̍��ېŒ����ؔ[�^�f��肪�w�E����A�c��́u���c�v�����B�����҂��^�����c��Ŗ��炩�ɂ��邱�Ƃ����߂܂����B
�@�Ȃ��A�䕗22������������10���X��(�y)�ߌ�A���̎s��������{�B�������Ŕz�z�����Q�̕����f�ڂ��܂��B
�u�N�ԗ\�Z�������A��^�J���\�Z�͓����vPDF�i633KB�j
�u�n�ӑ�O�s�c�i����j�ɍ��ېŒ����ؔ[�^�fPDF�v�i351KB�j
�Z�ݑ�����X������s���̂��Ƃ��l���Ă݂悤
�@����(2003�N�R��)�̎s�c����c��́A10�N�Ԃ̋c�������̂Ȃ��ł����M���ׂ��c������Ǝv���܂��B���ɁA���Y�}���܂ޖ�}�����ŔN�ԗ\�Z�̏C���Ă��o���A��������͉����������ƁB���ɁA�s�����\�Z�C�������ۂ��A�����o�����N�ԗ\�Z�𑒂�A�b��\�Z���o�������ƁB��O�ɁA�\�Z�C����j�~���邽�߂̗^�}���̌�������R���J��L����ꂽ���ƁB
�R��30��(��)�ߑO�A���͒n���Ŏs��������{�B���̍ۂɎg�p�������W�����u�Z�ݑ�����X������s���̂��Ƃ��l���Ă݂悤�v���f�ڂ��܂��B�S���o�c�e�t�@�C���ł������������܂��B
�u�Z�ݑ�����X������s���̂��Ƃ��l���Ă݂悤�v PDF�i368KB�j
�s�����S�ő�^�J���ɏ��o����t�s��
�@��t�s���́A�u��������ρv�Ƃ̗��R�ŁA��Q���s�v��j�\�B����ɂ��ƂÂ��u��Q���������S���v��v�ł́A�s�������E�T�[�r�X�Ɋւ�镔��̖��Ԉϑ���L�����A���������̒l�グ���ڔ������B�{���ɏ�����s�́u��������ρv�Ȃ̂ł��傤���B
�@����ŏ�����s�́A��^�J���ɓ˂��i�����Ƃ��Ă��܂��B�s�����S���E�T�[�r�X�ቺ�E�E���팸�ō������m�ۂ��悤�Ƃ��Ă��܂��B
�@���A�q�^�炪2002�N11���ɕ����u�s�����S�ő�^�J���ɏ��o����t�s���v�͂o�c�e�t�@�C���őS���������������܂��B
�u�s�����S�ő�^�J���ɏ��o����t�s���vPDF�i184KB�j
������s�̃S�~�s���̌���ƗL�����̓���
�@���߂���S�~�̌��ʁ|�|�R�E�s�R�S�~�̗L����(�L���ܐ��x)�����̎����̂ōL����n�߂Ă��܂��B�L�����ŃS�~���啝�����Ɛ�`����Ă��܂����E�E
�@��N�Q���T���ɏ�����s�����\�����u������s��Q���������S���v��v�ł́A���N10������u��ʉƒ낲�݂̗L�����v�L�B�u�Pkg������U�~�v���Q�l�ɁA�w��L���܂�����v��ƂȂ��Ă��܂��B�u���݂̌��ʉ�����}�邽�߁v���L�����̗��R(��Q���s�������v��j)�B�c��̒��ł��A�L�������咣����c�������݂��܂��B
�@�ʂ����āA�L�����ŃS�~�͌���̂ł��傤���H
�@���A�q�^�炪2002�N11���ɏo�����S�~��̕��͎��̂Ƃ���ł��B�S���o�c�e�t�@�C���Ōf�ڂ��Ă��܂��B
�u������s�̃S�~�s���̌���ƗL�����̓����vPDF�i260KB�j
�s���̐�Օۑ��̎��g�݂Ɍ�����
�|�푈����̐���ɓ`���A��x�Ƃ���܂����J��Ԃ��Ȃ����߂Ɂ|
�@�A�W�A�����m�푈���I�����57�N���o�߂��A�푈�̒��ڑ̌��҂����X�Ɏp�������Ȃ��A�،���ʂ��Đ푈�̔ߎS�����l�Ԑ����w�Ԃ��Ƃ�����Ȃ��Ă��Ă��܂��B�N�X��������̌��҂̐���ɑ����āA��㐢�オ���a�̑����`����w�͂����Ă������Ƃ����߂��Ă��܂��B
�@���̍ہA�푈�̐[�����Ղ��c����Ղ�╨���ł��邾������Ō��Ă��炢�A�،������ɂ����ʼn����������̂����A�㐢�ɓ`���Ă������Ƃ��������ɉۂ����Ă��܂��B
�@���A�q�^�炪2002�N11���ɔ��\�����u�s���̐�Օۑ��̎��g�݂Ɍ����āv�͂o�c�e�t�@�C���őS���f�ڂ��Ă��܂��B
�u�s���̐�Օۑ��̎��g�݂Ɍ����āvPDF�i408KB�j
PDF�t�@�C�����{�����邽�߂ɂ̓A�h�r�А��́uAdobe Acrobat Reader�v���K�v�ɂȂ�܂��B
Adobe��WEB�T�C�g���_�E�����[�h���Ă��g�p�ɂȂ�܂��B

|