|
12��
�@�u�N�̐��̉₩���������ĉ��N�ɂȂ낤���v�Ɩ{���ɋL���ĂU�N�B12�����}���Ă��X���͐Â܂�Ԃ�A�����Ɉ���������悤�Ɍi�C�͂��������₦���ށB
�@�T���^����Ɋ肢�����������߂Ă����䂪�Ƃ̎q�ǂ������́A�������e�ɗv�������o���悤�ɂȂ�A�ߔN�ɂ������ẮA���ꂷ�����������B
�@���S���̂Ȃ��Ńt�g�R�����C�ɂ���e�����āA�����S������̂��A�͂��܂��a�����Ƀh�J�[���Ƌ��߂Ă���̂��E�E�E�E�B12���͉����Ɨ��������Ȃ��B
�@���{�͏���ł��ė��N�̂S����������グ��Ƃ����B�u11���Ɂv�Ǝ咣���鐨�͂�����B�u��������ς�����v�u�����ɋ��������邩��v�ƌ������̂́A15�N�O�ɏ���ł��T���ɏオ��������A�����Â̕��S�͑����������B����A������N���͉��������B
�@�N���X�}�X��a�����Ɏq�ǂ������̖��ɉ����邽�߂ɂ��A�t�g�R����ɂ߂��鐭���̓S�������B�c��P�T�ԁA�͂̌���A�M����낤�B
�i�u����Ԃ���v2012�N12���X���t���j
�܂��͓s�m���I��
�@�m���̎d�������ŕ������s�m���I���́A�I���Ǘ��ψ�����Q�Ă������B���[���ƊJ�[���̊m�ہA�|�X�^�[�f���̐ݒu�ӏ��̊m�ہA�I���ɕK�v�ȗ\�Z�v��Ɛl�̎�z�Ȃǂł���B
�@�ǂ��ɂ��s�m���I�����}����̐��͂Ƃꂽ���̂́A���ɓ����悬��̂́u���I���͂��ɂȂ�̂��H�v�B�u�N�������X�ɑI���Ƃ��Ȃ�A�����܂߂Đ����ԏ�ł̎d���ɂȂ�v�ƒS���҂͏q�ׂ�B�R���Ɏs�c�I�A�Ăɂ͓s�c�I�E�Q�@�I�ւƑ������̂P�N�́A�u�ꐶ�Ɉ�x�A���邩�Ȃ����̎��ԁB�ʂ����Đg�̂����̂��H�v�ƕs����B
�@���Y�}�s�c�c���S�˔z�z�Ŏ��g�u���炵�̗v���A���P�[�g�v�̕ԐM��500�ʂɁB�u���炵���ꂵ���Ȃ����v�u�������������v�u�Љ�ی�����ŋ��̃A�b�v���Ȃ�Ƃ����āv�ȂǁA���������߂�肢���X�ƂÂ��Ă���B
�@�ꐶ�Ɉ�x���邩�Ȃ����̑�d���B�����������߂鍑���̓{�肪�A���̔w���������Ă���B�܂��͓s�m���I������B�@
�i�u����ӂ���v2012�N11��11���t����j
������
 �@�����w�̊ۃm���w�ɂ��A1914�N12���̊J�Ǝ��̎p�ɕ������ꂽ�B���̌����́A���S�������c����̍ĊJ���\�z�̂Ȃ��Ŏ��̊�@���}���邪�A�ۑ��^�������܂�Ȃ��ŁA�X�N�O�ɍ��̏d�v�������Ɏw��B����10������u�ԃ����K�w�Ɂv�Ƃ��Đl�X�̒��ڂ��W�߂Ă���B �@�����w�̊ۃm���w�ɂ��A1914�N12���̊J�Ǝ��̎p�ɕ������ꂽ�B���̌����́A���S�������c����̍ĊJ���\�z�̂Ȃ��Ŏ��̊�@���}���邪�A�ۑ��^�������܂�Ȃ��ŁA�X�N�O�ɍ��̏d�v�������Ɏw��B����10������u�ԃ����K�w�Ɂv�Ƃ��Đl�X�̒��ڂ��W�߂Ă���B
�@������s�ɂ������������݂���B�ʐ�㐅�⏬����T�N���Ȃǂ̍��w�肪�R�A�������ȂǓs�w�肪�Q�A�����Ďs�w�肪29�ł���B�@�������͑����āA�n��̗�����M�ӂɂ���Ďp����Ă���B�ۑ��E�p���̎��g�݂�����Ȃ���A���Ƃ����j�I�Ȍ������ł����Ă������Ă����B������A�������͂Ȃ�Ƃ��Ă���蔲���������̂ł���B
�@�����̎��Ƃ͂��āA�͘F���̂��鏬���Ȋ����������ł������B�]�ˎ���Ɍ��Ă�ꂽ���̌�����23�N�O�Ɏ��ꂽ���A�ɂ��ސ����������������B���X������Ƃ̖��́A�Âт������������B���������p�́A�ʐ^�̐��E�����ƂȂ����B
�i�u����Ԃ���v2012�N10��14���t����j
�u���`���A�ǂ����`!?�v
 �@��k�Ђ���P�N�����o�߂����B�e���r��V���ł́A��Вn�̕����⋳�P��A������͋N����ł��낤�V���ȑ�n�k���Ôg�ւ̔������Ăт����Ă���B �@��k�Ђ���P�N�����o�߂����B�e���r��V���ł́A��Вn�̕����⋳�P��A������͋N����ł��낤�V���ȑ�n�k���Ôg�ւ̔������Ăт����Ă���B
�@�������A������Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂́u�����v�B���S�ʂŖ������A���������˔\�������ƂȂ�댯�Ȃ��̂�������54���A���Ƃ����낤�ɐ��{�́A��ь������ĉғ��������B��������̂ł͂Ȃ��B
�@�{������߂āA�Ă̋A�Ȃ̐܁A��̈ē��ő�ь����ւƏo�������B���Ƃ���ԂłQ���Ԕ��A���l�s���ł͓y���~��ɂ����Ȃ�����H�蒅���ƁA�����~�n�����Ƀo���P�[�h�������A�x�������R�l�����A�u�_���v�ƍ��}�𑗂�B�������̂��q�ނ��Ƃ͂ł������܂��B
�@�Q���Ԕ��̍s�H���P�Ȃ�h���C�u�Ɖ�������s�́A�߂��̊C�ӂŐ��V�тɓ]���A���������锼�����ɂ݂Ȃ��狩�B�u���`���A�ǂ����`!?�v�B
�@��̎q�ǂ������́A�����������M���O�ɔ��ʂāA�A�H�̂Q���Ԕ����Ђ����疰�����B
�i�u����Ԃ���v2012�N�X��16���t����j
������
 |
| ���~�̕����w�O |
�@�����ɏo��35�N�]�B���~�̍��ɋA�Ȃ���ȊO�́A�����̒n�ނ��Ƃ͂Ȃ��B����Ȑ܁A�A�Ȃ�O�ɂ������̎茳�ɁA���w�Z����̓�����̈ē��͂����B���̊ԁA������̈ē�������x���������������Ƃ͂��������A10�N�]�O�Ɉɐ��u���ōs�Ȃ�ꂽ������ȍ~�A����o�������Ƃ͂Ȃ��B����������́A�A�Ȓ��ɋ����ŁA���������Ƃ���ԂłT�����x�̏��ŊJ�����B�u�o�ȁv���L�����āA�ԐM�n�K�L�𓊔������B
�@���w�Z����́A���܂�ǂ��v���o���Ȃ��B�����̓v�����X�S������B�W���C�A���g�n���A���g�j�I���Ȃǂ��u���E���ǂ���킵�A�R�u���c�C�X�g��l�̎��ł߁A�͂������߂Ȃǂ����w�Z�ł���͂��B���ׂ��䂪�̂ɑ����̋Z���|����ꂽ�̂��A�ē������ɂ����ۂɁA����̂��Ƃ��v���o���̂ł���B������A�Z���|�������c��������ɗ��邾�낤�ȁA�ȂǂƁA�����̈����ǂ�����l��l�A�v���o���Ă͋ᖡ����B
�@10�N�]�O�̈ɐ��u���ł̓�����́A�ɐ��_�{�ւ̖�������˂čs�Ȃ�ꂽ�B�������A���͈ɐ��u���̗��قɍ��������̂ŁA����ɂ͉�����Ă͂��Ȃ��B���̎����A���܂킵���v�����X���i���v���o���Ă͂������A�Z���|�������́A����Ȃ��Ƃ������������H�ȂǂƁA�ǂ��������B�Ȃ��₩�ɉ���ɓ˓����čs�����B���āA����͂ǂ����B
�@������ŁA�Ƃɂ����y���݂Ȃ̂́A���ꂼ�ꂪ�ǂ̂悤�ɕω������̂��A�Ƃ������ƁB�u�ω��v�Ƃ͂������A�̌^�ƕ��e�B�J�b�R�ǂ������A�C�c�́A�ǂ��ς�����̂��B����̂��̎q�́A���܂��f�G�Ȃ̂��B�����āA�̖̂ʉe�͂��܂�����̂��A�V���Ă͂��Ȃ����A�ȂǂȂǁB����A�s���Ȃ̂́A�����̒n�Œ�����炵�Ă��鎄���A�����̓������́A�ǂ��}����̂��낤���A�Ƃ������ƁB����Ȃ��Ƃ��l���Ȃ���A�W��15���̌ߌ�A������̉��u�����v�ɑ����^�B
�@���w�Z�̓������́A�Q�N���X���v��70���]�B�u���g�v�Ɓu���g�v�ɕ�����A�N���X�ւ��͂S�N���ɂȂ鎞�Ɉ�x�����s�Ȃ���̂݁B������A�����g�ɂȂ�Ȃ��������������A���O������v���o���Ȃ��ʁX������B������̉��ɂ́A���łɑ����̖ʁX���������Ă������A���̊�͒N�������H�A���O�������Ă���������v���o���Ȃ��E�E�E�E�Ƃ����̂��A�S���߂�����B����A���������ł��������āu���̐l�A����H�v�ƁA�ׂ̎҂ɕ����Ă����Ƃ����B������ɂ�35�����o�ȁB���̂���������10���ŁA�\�z�͂��Ă������A���̔N��ɂȂ�ƁA�����͂Ȃ��Ȃ��Q�����ɂ����̂悤�ł���B
�@�ߌ�P������n�܂���������i����j�́A�ߌ�T���߂��܂ő������B���ȏЉ��A�s�[���A�̂�J���I�P������킯�ł��Ȃ��A�r�[���̓������R�b�v�������Ȃ���e�[�u�����ړ����A�b�������l�ׂ̗ɍs���Ęb�����ނƂ�����B�P�P�Řb�������҂�����A���l���̃O���[�v�ɂȂ��Ęb�����ނƂ��������B�����A�����悤�Ƀe�[�u����ꏊ���ړ����Ȃ���P�P�ŁA���邢�̓O���[�v�̒��ɕ��������āA�ߋ�����荇�����B���������Ŏs�c��c�������Ă��邱�Ƃ́A���������̖ʁX���m���Ă����悤�ł���B
�@������̐ȏ�ɁA�������w�Z����ɍD�ӂ��Ă��������������B10�N�]�O�̈ɐ��u���ɂ͗��Ă��Ȃ������l�ł���B���w�Z����ׂ͍��������̎q���A���܂ł͏��X�A���ɍL�����������B���̏������ŏ��A�������āu���̐l�A����H�v�ƁA�߂��̐l�ɕ����Ă����Ƃ����B
�@�������{���Y�}�̎s�c��c��������Ƃ������Ƃł��낤���A���̂��Ƃɘb�����ɂ���ʁX�����l�������B���܂̐�����o�ς̂�����ɂ��āA���邢�͓��{�̏����ɂ��čl�����������������Ƃ����̂ł���B���猻��ɐg��u���Ă���ҁA�d���Œ����ɍs���Ă���ҁA���邢�͌����E��ē����Ă���҂ȂǂȂǁB���܂̐����ɕs��������Ȃ�����A���̉�����͂ǂ�����ׂ�����������������Ȃ��A��肫��Ȃ��S�̓������ɂԂ��邩�̂悤�ł������B�����ɂ́A���w�Z����̊��܂킵�����i�́A���͂⑶�݂��Ă͂��Ȃ������B
�@���āA�y���݂ɂ��Ă����u�̌^�E���e�v�ł��邪�A��������Ƒ̌^�����ɍL�����Ă����҂�A����������P���Ă����ҁA����������o���Ă���҂ȂǁA�ǂ��ɂł���������i���������B������C���ӂ��l������A���w�Z����͉��ɍL�����Ă����̂ɁA���܂ׂ͍��Ė��͓I�Ƃ��������������B
�@���̓��̖�A�z�O�s�X�̓����̉͌��ʼnԉΑ��Â����Ƃ����B�u��������ɍs�����B�������ň������v�ƁA�݂�ȂɗU��ꂽ���A�����̌ߌ�ɂ͓����ɋA��Ȃ���Ȃ�Ȃ��g�ł���A�N�V�����I�t�N���̂��Ƃ��l���āA���f��������B���Ƃ܂ł͕����Ă�20�����x�ŋA�邱�Ƃ��ł���̂����u�Ԃő����Ă����v�ƌ����A��q�́g���w�Z����͉��ɍL�����Ă����̂ɁA���܂ׂ͍��Ė��͓I�h�ȏ����ɎԂŎ��Ƌ߂��܂ő����Ă�������B
�@�������͌��X�Ɂu�q����ԁA�ς�����v�ƌ����B���Ƃɂ����́u�Z�M�́A���̓������Ɣ�ׂĎႭ�݂���v�ƌ����B�����̒n���������Ă���̂��A���邢�͎s�c��c���Ƃ����d�����A���������Ă���̂��E�E�E�E�B����̓�����́A�җ�̎��ɍs�Ȃ��Ƃ����B���̎����u��ԁA�ς�����v�u���̓������Ɣ�ׂĎႭ�݂���v�l�Ԃł��肽���B���̂��߂ɂ��A���N�R���̎s�c�I�ŏ������āA�Z�����Ȃ�����A��肪���̂��邱�̎d���𑱂�����悤�ɂ��Ȃ���Ǝv���B
��X�̃t�g�R���
�@�Q�N�R�J���Ԃ�̋A�Ȃ�O�ɁA��X�̃t�g�R�����s���ɂ�����o���������������B
�@�܂��͘V���������o�C�N�̏C���B�₪���鏬����ł́A�|���R�c�ł��������Ȃ���蕨�ƂȂ��Ă���B���ɍ��ېł̑��ŁB��P�������x�������V���I�ՁA���z�̂Ȃ�����P���~�D����Ԃ悤�ɏ������B�����ċA�Ȃ̂��߂̐ؕ��w���B���q�ƂQ�l�����̋A�Ȃł͂����Ă��A����܂ł̉^���͂������Ĉ����͂Ȃ��B
�@�����ď���ł̑��ŋ��s�B�Q�N��̂S������W���A�R�N���10���ɂ�10���ɂ���Ƃ����B
�@�����͂ǂ����B�݂Ȃ���̐ŋ����炢�������c����V�̎���z�������Ă���B�N���}�{�T�����̏k���ŁA�����ŁE�Z���ł��A�b�v��������ł���B
�@�A�Ȃ̗�Ԃ̒��A���q���ԓ��̔��̃W���[�X�Ɏ��L�����Ƃ���B������Ƒ҂āB��芷���w�̎����̔��@�Ŕ����Έ������I�B���������Ȃ���ʃr�[���𒍕����鎄�ɁA���q�̗₽����������B
�i�u����ӂ���v2012�N�W��19���t����j
���ېŃA�b�v
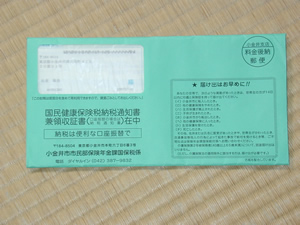 �@���N�x�̍������N�ی��ł̔[�Œʒm���������Ă����B���{���Y�}�̔������������Ēl�グ�����s����A���S���ɂȂ邱�Ƃ͂킩���Ă������A���̊z�ɂ͖ڂ����������B �@���N�x�̍������N�ی��ł̔[�Œʒm���������Ă����B���{���Y�}�̔������������Ēl�グ�����s����A���S���ɂȂ邱�Ƃ͂킩���Ă������A���̊z�ɂ͖ڂ����������B
�@�䂪�Ƃ̍������N�ی��̑Ώێ҂́A���܂߂ĂR�l�B�����畉�S�z���傫���B�O�N�x�Ɣ�r����ƁA���ɂV���V��~�̃A�b�v�B������Ƃ̔[�Ŋz���X��~�ȏ�̑��ł���B
�@�V���ɕ��S����������̂́A���ېł����ł͂Ȃ��B�[�Œʒm��������������Ƃ��̏ꍇ�́A���ی����A�������҈�Õی��������ƂȂ�B�W���ȍ~�́A�N���V�����҂ɂ���C�ɉ�����B
�@�l�グ�����s�����͎̂����E�����E����B���ł����A����ő��ł��s�Ȃ����Ƃ��鐨�͂ł���B��^���H��w�O�J���𐄐i����p���́A���ł�������s�ł������B���̃c�P�����S���ƂȂ��ĉ����Ă���B
�@���ꂽ�����𐁂�����悤�ɁA��W��̗����A�~�J���������B�����͂��ꂩ�炪�{�Ԃł���B
�i�u����Ԃ���v2012�N�V��22���t����j
�����ĉғ�
�@��ь����̍ĉғ������s����悤�Ƃ��Ă���B�u�ߓd�͌o�ϊ����ɉe����������v�ƌo�ϊE���猾��ꂽ����ł���B
�@���d�͂̔��\�ł��A�ҏ��̏ꍇ�̓d�͕s���́A�s�[�N���̌v71���Ԃɂ����Ȃ��B�Ȃ���ē��l�ɁA�ߓd�ŏ���ׂ��ł͂Ȃ����B�����Ɨ��v�Ƃ��Ă�҂�ɂ����邠����́A����A���������̂ł͂Ȃ��B
�@�����E�z�O�s�́u��������v�ዷ�p���甼�a30�L�������B���f�w���ЂƂ��і\���A��Q�̃t�N�V�}�ɂȂ鋰�ꂪ�\���ɂ��鏊�B�Ȃ̂ɐ��{�́A��ь����ɂÂ��āA���̌����̍ĉғ�������ɓ���Ă���B�R�N�O�̐������͈�́A�Ȃ����̂��B
��k�Ќ�A������K��Ă��Ȃ����͍��āA�A�Ȃ�\��B�ێ牤���ƑI���̂��тɕ��Ă������䌧�ł��A�ĉғ����̏W��J����A�����̓{��͉Q�����Ă���B��v�w�Ǝq�ǂ������A�����ĔN�V������e�����₩�ɕ�点�鋽���ɂƁA�����̒n�Łu�ĉғ����v�ɏ��a����B
�i�u����Ԃ���v2012�N�U��24���t����j
�����H
 �@�V�̃V���[�̒��A�䂪�Ƃ̘H�n�ł��ߏ��̐l�X����Ăɋ�����グ���B�P�l���������ώ@�p�O���X���W�܂����ʁX�����z�ɂ������A���R�̃J���N���ɂ�������̐��B�����ł�173�N�Ԃ肾�Ƃ����B �@�V�̃V���[�̒��A�䂪�Ƃ̘H�n�ł��ߏ��̐l�X����Ăɋ�����グ���B�P�l���������ώ@�p�O���X���W�܂����ʁX�����z�ɂ������A���R�̃J���N���ɂ�������̐��B�����ł�173�N�Ԃ肾�Ƃ����B
�@���{�̍L��ŋ����H������ꂽ�̂́A932�N�Ԃ肾�Ƃ������B�ώ@�p�O���X�̂Ȃ�����A�l�X�͂ǂ̂悤�ɂ��Ē��߂��̂��낤���B�������z�̒��S���ɉB��Ă���ƁA�m���Ă����̂��낤���B
�@���ɍL�͈͂ŋ����H���ϑ��ł���̂�300�N��B����ǂ����E�̃L�i�L�������Ă���ƁA���̎��ɐl�ނ͂��̒n����ɑ��݂������Ă���̂��낤���A�n���͕��˔\�ɉ�������Ă͂��Ȃ����낤���ƁA�s���ɂȂ�B
�@932�N�O�̐l�X�͉Ȋw�I�Ȓm�����Ȃ��������Ƃ���A�V��̌��i�ɋ��ꂨ�̂̂����B�������������͒m���������A�푈�⌴����Q��h���X�x��m���Ă���B
�@18�N��̖k�C���ł̋����H�́A�s���̂Ȃ��n���̂��ƂŌ}���������̂ł���B
�i�u����Ԃ���v2012�N�T��27���t����j
�ዷ�p
�@����̊C�ɒ����������l�A�w�ɂ͗ΑN�₩�ȎR�X�����сA�ĂƂ��Ȃ�Α����̊C�����q���K��邻�̒n�Ɉٗl�ȍ\�������o�������̂́A1970�N��ɓ����Ă���B���܂ł�11���̌������������ԁu��������v�ዷ�p�́A�䂪�����E���䌧�ɂ���B
�@���{�͉ď�̓d�͕s���𗝗R�ɑ�ь����̍ĉғ���_���Ă��邪�A���d�͂̎��Z�ł��A�ҏ��̏ꍇ�̃s�[�N���ɂ����Ăł��������v������������̂́A������13���ԁE�v71���Ԃɂ����Ȃ��Ƃ����B�Ȃ�Α�����p�҂ɁA���̎��ԑт̐ߓd��d�͗��p���������߂�悢�����ł���B�ĉғ����肫�̐��{�̎p���́A������������҂Ƃ��āA�f���ċ�������̂ł͂Ȃ��B
�@�ዷ�p�́u�C�̌�����ޗǁv�A��ь��������̏��l�s�́u�C�̏����s�v�ƌĂ��قǂɁA�����̌Õ��E���t������B�u�����v�Œ��ڂ��W�߂�̂ł͂Ȃ��A�u�C�̌�����ޗǁE���s�v�Œ��ڂ��W�߂鋽���ł����Ăق����B���Ȃ������ЁA�ዷ�̒n�ցB
�i�u����Ԃ���v2012�N�S��22���t����j
�w�v���d�x����P�N
�@�P�N�O�̍����́u�v���d�v�ɐU���Ă����B�����d�����g�у��W�I�����퐶���ɉ����A�v���d�ɍ��킹�ē��X�͓����Ă����B�s�c������l�ł���B�v���d�̍��Ԃ��ʂ��ċc��J����A�ْB�҂Ȑl���A���Ԃ̐���ɔ����Ă����B
�@�p�ɂɋN����]�k�ɋ����A�K�\�����X�^���h�͒��ւ̗�B�X�[�o�[����̓p�����A���g���g�H�i�������A�X�ܓ��͔��Â������B
�@���܂͂ǂ��ł��낤���B������O�̂悤�ɓd�C�����A�e���r���y���݁A�g�[�̃X�C�b�`������B����������������Ɠ����A�X�Ȃ��ɂ̓l�I�����Q�����Ă���B
�@�ł��Y��Ă͂Ȃ�܂��A�P�N�O�̂��̓��X���B���̂�厖�ɂ��邱�ƁA�u���������Ȃ��v�Ƃ����C�����������Ƃ��B
�@����Ȃ��Ƃ��v���o���Ȃ���A���̕��͂��L���������ł́A�e���r�������A�g�[������A���������������ƋP���Ă���B�p�\�R���̕��ʂ��̂������ގq�ǂ��́A���������̂悤�Ɏ��̊�������B
�i�u����Ԃ���v2012�N�R��25���t�j
�J��
 �@�u�J�v�Ƃ́A�u�f�Ƃ��ɂ��f����Ȃ��l�̊Ԃ̌��т��v�Ǝ����͂����B�R�E11�́u���̎��v����A�u�J�v�͓��{�����삯�߂���A���{���}�X�R�~���u�J�v�����ɂ���B �@�u�J�v�Ƃ́A�u�f�Ƃ��ɂ��f����Ȃ��l�̊Ԃ̌��т��v�Ǝ����͂����B�R�E11�́u���̎��v����A�u�J�v�͓��{�����삯�߂���A���{���}�X�R�~���u�J�v�����ɂ���B
�@�Ƃ��낪���{�́u�J�v������̂ł͂Ȃ��A�Y�^�Y�^�ɐ���Ƃ��Ă���B����ł̑��ł╉�S���ō����̗̑͂���߁A���э����Ă�����藣�����Ƃ����̂��B���{�Ɠ����y�U�ɗ��}�X�R�~���܂߂āA�u�J�v����鎑�i�͂Ȃ��B
�@����A��t�s���̎{�����j�ɂ́u�J�v�̕����͌������炸�B�����獑�ېł���ی����̒l�グ���A��������Ɠo�ꂷ��̂ł��낤�B
�@�u���̎��v����P�N�B���̍��̐����͋��ԈˑR�̂܂܂ł͂��邪�A�u�J�v����ɂ��������̑��͊m���ɕω����Ă���B�f�Ƃ��ɂ��f����Ȃ��u�J�v�����Đ�����ς��Ă����A�u���̎��v�ɖ��𗎂Ƃ����l�������S�������鎞���}����B
�@�R���͗������̎��B�Â��㒅��E���ŁA������O�֕��܂��悤�B
�i�u����Ԃ���v2012�N�Q��26���t����j
�V���s���a��
�@��N�S���I�Ղ����ȂƂȂ��Ă���������s�̕��s���E�ɁA�����������̏㌴�G�������A�C�����B�Q���P������2016�N�P�������܂ł̂S�N�Ԃ̔C���ł���B�㌴���̕��s���I�C�c�Ăɓ��{���Y�}�s�c�c�͑ސȂ������B�ێ�n�̎s���Ɠ�l�O�r�Ŏs���^�c�������߂��E�ł��邱�Ƃ���A����̐E��������Ȃ��Ŏ^�ۂ͔��f�����ׂ��ƍl�������߂ł���B���ɂƂ��ẮA���Ƃ��㌴�������߂Ȃ��l���ł���A���Ƌ⎕���s�J�b�ƌ��郆�j�[�N�Ȑl���ł����Ă��A�ł���B
�@���s����I�C�����P��31���̗Վ��s�c��́A���̑��ɂ��c�Ă�����Ă����B����������w����ĊJ�������ɓs�s�Đ��@�\(�t�q)�����Ă��u�s���𗬃Z���^�[�v���擾����c�ĂȂǁA�s���𗬃Z���^�[�ɂ������T�̈Č��ł���B���̓��͋c�Ă̐����Ǝ����v�����s�Ȃ�ꂽ�݂̂ł��邪�A�Վ��s�c��Q���ڂ̂Q���Q������͓O��I�Ȏ��^���J�n���ꂽ�B�Ƃ��Ƃ��āA������e�Ɏs������������Ȃ���ʂ�����A���x�ƂȂ����ْ�����x�e���J��L����ꂽ�B�V���s���ɂƂ��ẮA�Ƃ�o�ł���B
�@���s���E�ɏA�C�����㌴���́A��N11�����{����12�����{�܂ł�37���ԁA�s���E���㗝���Ƃ߂Ă����B�s�����C�Ŏs�����s�݂ƂȂ�A���s���E�������ł��������߁A�����������E�̏㌴�����s���E���㗝�ɏA������Ȃ���������ł���B�s���E���㗝�Ƃ��ď��߂Č}������N11��14���̖{��c�ŏ㌴���́A�E���㗝�̈ʒu�t�����s�c��ɐ��������B�g�E���㗝�͎s���̂悤�Ȍ����͎����Ȃ��B�������I���͈�ʐE�Ȃh�ƁA�c���⒡���E���ɃA�s�[�����邽�߂ł���B
�@�S�~�����̍s���l�܂�Ŏs�������C�������Ƃ����ɁA�����Ă��̐l�́u�s�������s�����s�݂ŁA�㌴����͑�ς��낤�ȁv�u��N�܂ł��Ƃ킸�����Ƃ����̂ɁA�㌴������C�̓łȂ��̂��v�Ǝv�����ɈႢ�Ȃ��B���������v�����B���������l�͂����ł͂Ȃ������B�E���㗝�ŏ��߂Č}�����{��c�ɏ㌴���͎U���p�ŗՂ݁A���������Ǝʐ^�܂ŋc����ǂɎB�点�Ă����̂ł���B
�@�Ƃ��낪�A���s���I�C�c�Ă��c��ɏ�����ꂽ�P��31���̎����A�{�i�I�Ȏ��^���X�^�[�g�����Q���Q�����A�㌴���͎U���p�ł͂Ȃ������B�����̏㌴����̂܂܂ł������B����Ă����̂́A�c��̍���ꏊ���炢�ł������B�s���E���㗝�̎��͎U���ɍs�����̂ɁA���s���E�ł͂ǂ����čs���Ȃ��̂ł��낤���B�Z�����ł́A�s���E���s���s�݂̎��́u�s���E���㗝�v�̎��̕����A�͂邩�ɖZ���������͂��ł���B�u������v�Ƃ݂�ꂽ�̂ł��낤���A�Q���Q������̎s�c��́A��̔@���i���n�߂��B
�@�㌴���̖{��c��̐Ȃ́A�s����������͕����Ȃ̒����ł������B��������������͎s���Ɠ����őO��̘L�����ȂɈڂ�A���s���ƂȂ������͎s���̗אȁB�ƂȂ�ƁA�c��Ȃ͂�����B������A�ׂ̐ȂɈڂ邱�Ƃł���B���̂Ƃ��ɂ́A�U���ǂ��납�A�����C���V�����ėՂނł��낤�B�������A�⎕�ł͂Ȃ������ł���B�҂�����������ł���B
�ς���䂭���S
 |
| 26�����́u���v |
�@������s�̍������N�ی��^�c���c��ɍ��ېł̒l�グ�Ă����₳�ꂽ23���̖邩�疢���ɂ����āA���̓~�͂��߂Ă̐ϐႪ�X���P�����B�H�ʓ����ɂ�鎖�̂��������A���s�҂̓]�|�p�����������Ɍ���ꂽ�B
�@��͂�����͏����A�X�͕��i�̐��������߂��B�������A�l�グ����鍑�ېł͂����͂Ȃ�Ȃ��B�Ⴊ�����ďt�ɂȂ�����A�������ɓ���ɍ~�肩����B
�@�~�肩����͍̂��ېł����ł͂Ȃ��B���ی����A�������҈�Õی��������ł̗����B������ǂ��납�A�~��ς������ł���B�����ɕ�点�Ƃ����̂ł��낤���B
�@���̏�����s�B31���ɗՎ��c������W���āA�s���𗬃Z���^�[�擾�̋c�Ă��������Ƃ����B�擾�ɗv����s���S�z�́A�ݔ���܂߂�32���X�疜�~�B���ېł̑��Ŋz�S���R�疜�~�̂V.65�{�ɂ��̂ڂ�B
�@�s���𗬃Z���^�[�͍����A���R�ɗ��p�ł���B�w�����Ȃ���Η��p�ł��Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B�c�����̎g�����́A�����s�݂̍����Ɠ����ł���B
�i�u����Ԃ���v2012�N�P��29���t����j
�����ۉ^�c���c����������u���ېł̒l�グ�ĊT�v�v���o�c�e�t�@�C���Ōf�ڂ��܂��B
�N���
�@�����̐����͕��͂�����̂́A����ȂɊ����͂Ȃ��A��Ɍb�܂ꂽ���₩�ȓ��X�ƂȂ����B���q����w���T���Ă��邽�߁A���Z�̂R�N�O�Ɠ��l�ɁA���Ƒ��q�݂̂������ɋ��c��B��A���̖钆�ɔN�z��������H�ׁA�����̒x�����H�͎G�ρB�݂����Ɏc���Ă��邽�ߒ��H�͂����č�邱�Ƃ��Ȃ��A�[�H�̓X�[�p�[�Ŕ��������ߗ����ōς܂���Ƃ������x�B���q�̎�O�A�e���r���T���A�����n�ǂł��Ȃ��V����G����ǂ݁A���R�ɑ|���������s�Ȃ��B�����ɂ����̂́u���v�́A�قƂ�Lj���ł��Ȃ��B���q���Q�l�����L���Ă���O�ŁA���ނ킯�ɂ͂����Ȃ��̂ł���B
�@�����ŋC�ɂȂ�̂́u�N���v�B����ׂ��l���痈�Ă��Ȃ��ꍇ�ɂ́A�u�����������̂��ȁv�u�Z�����āA�����̂��x���Ȃ����̂��ȁv�ȂǁA���ꂱ��v���߂��点��B����ȂȂ��A��������̎O�����ɂ����āA����ׂ��l����̔N��A���N�����Ȃ��͂����B�N�Ɉ�����̕ւ�́A���̐l�̋ߋ���m���ł̋M�d�ȍޗ��ƂȂ�B�Ƃ��낪�A�蔲���̉������Ȃ��炸������B�ʂ��Ղ̐V�N�̂������݂̂Ƃ����P�[�X�ł���B�����m�肽���̂́A���̐l�́u�ߋ��v�B���܂ǂ�Ȑ��������Ă���Ƃ��A�Ƒ����ǂ����Ă��邾�Ƃ��A�Ƃɂ����g�̉��̂��Ƃ�m�点�Ă��Ăق����̂ł���B
�@���̎��̎v���ɂ�������Ɖ����������A�Ȃ��ɂ͂���B���鏗���͂����J�ɁA���g�̎ʐ^�����Ƀv�����g�������Ă���B���̎ʐ^�������u�ԂɁu�����A���̐l��20�N�O�Ƒ̌^���قƂ�Ǖς���Ă��Ȃ��ȁv�ƈ�ڗđR�ƂȂ�̂ł���B���ɂ́A�u�̌^�͐̂ƕς�炸�E�E�E��������Ă�E�E�E�v�ƁA�N�����F�߂�R�����g���L����Ă����B
�@���Z�P�N���̖��́A���w����⍂�Z�̃N���X���C�g����̔N����X�Ɠ͂����B�ΏƓI�ɁA���Z�R�N���̑��q�̓`�����z�����B����������w�ɒǂ��Ă��邽�߁A�䂪���q���l�ɁA�N���ǂ���ł͂Ȃ������l�q�B��w�͍��Z�����A��ςȂ悤�ł���B
�@���̍��N�̔N���́A������ʓI�Ȃ��̂ɗ}�����B����A�J�~����u�]�v�Ȃ��Ƃ������Ȃ��Łv�Ƃ�����������������߂ł���B�ȉ��A���N�̔N�����Q�l�܂łɌf�ڂ���B
 ��10���W���`10���A��Вn�E�Ί��s�փ{�����e�B�A�ɁB�S��l�߂��]���҂��o�������̒n�́A�V�J�����o�����ł������Ղ͂�����Ƃ���ɁB�o�ϑ卑�ł���Ȃ���A�ǂ����[�_�[�Ɍb�܂�Ȃ������͕s�K�Ƃ��������悤���Ȃ��B���Ƃ�A�����J�ɕ����������Ƃ͕s�p���B ��10���W���`10���A��Вn�E�Ί��s�փ{�����e�B�A�ɁB�S��l�߂��]���҂��o�������̒n�́A�V�J�����o�����ł������Ղ͂�����Ƃ���ɁB�o�ϑ卑�ł���Ȃ���A�ǂ����[�_�[�Ɍb�܂�Ȃ������͕s�K�Ƃ��������悤���Ȃ��B���Ƃ�A�����J�ɕ����������Ƃ͕s�p���B
���u�R�E11�v�ȏ�ɗh�ꂽ������s�B�N�ɂQ��̎s���I�Łu������v�̖����S���ɁB�u�S�~���}�ւő����Ă�����v�̗F�l����̓d�b�ɁA���肪�������p�����������B������s�����[�_�[�ɂ͌b�܂�Ă͂��Ȃ��B
���䂪�Ƃ͍��t�A���q����w�B�����ԏ�ŏm�ʂ��B�ȂƖ����A�Ȃ����A�䂪�g�ɐ����E�|���E����̎O�d��B���q��O�Ƀe���r�����ꂸ�A�r�[���͗①�ɂɗ₦���܂܁B�����x�ꂽ�����d�グ�A�G�ς̍�����{�Ŋw�ԁB
�����Ԃ�����A�����̉����ɏo�����邱�̍��B�E���E�����E�{���E�E�E�A�]�˂̕�����c�����̒n�́A�S�̃I�A�V�X�B�����ɏZ���34�N�B�X���傫���l�ς�肵�Ă��A�l�Ɛl�Ƃ́u�J�v�͕s�ρB���N�����C�Ɋ撣��܂��B�@�@�@�@
����̖��x
�@������s�̍����a�Y�s�����u�S�~���v�̕s�K�Ȍ���Ŏ��E���A�S���̎s���I������W�J���ƌo���Ȃ������ɍēx�A�s���I�����s�Ȃ�ꂽ�B�����A�s�c����Łu�S�~���̔�펖�ԉ����v�̂P�_�ł̓�����i���̌����������߂�ꂽ�������Ɏ��炸�A�e�w�c�����҂�i�����I���̐��ɓ������̂�12���ɓ����Ă���ƂȂ����B
�@���݂�����i�����A��X���I���̐��ɓ������̂��A���̐w�c�Ƃقړ�������12���̖`���B11���ɂ͍������}���邽�߁A���Y�}�̂S�l�̎s�c��c���Ȃǂ𒆐S�ɗ����͏o�̂��߂̏�����x���g�D�����グ�Ȃǂ̑I���̐��Â��肪�}�s�b�`�ł����߂�ꂽ�B
�@�I���{�Ԃ�11���̍���������18�����[���܂ł̈�T�ԁB���̈�T�Ԃ����ɒ��������B���͉w���ł̐�`�s���̂��߂ɁA���V���O�ɂ͌��҃J�[���w�ɉ��t�����A��͑I�������̐����◂���ȍ~�̏����̂��߂�11���߂��܂őI���������Ɋʋl�B�������A���̎����͊����B���V������Q���Ԃ̉w����`�́A�Ƃ��Ɍ����������B�����Ⴍ�͂Ȃ��B50���߂������t���̈����g�̂́A�����ɑł��Ђ�����Ă����B���������Ɉ���̎������Ԃ͒����B�������d�������X�ɏP���Ă���B���̂��߁A������߂���̂��Ƃɂ����x���B�Ƃ������ƂŁA�I���{�Ԓ��̈�T�Ԃ͂ƂĂ��Ȃ�������T�ԂƂȂ����B
�@18���̓��[�����߂��A���ꂩ��̌����͎��ɑ��������B�V��ł����Ƃ��Q�Ă����Ƃ��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A���i�̐����ɖ߂��������ɂ����Ȃ����B
�@�C�����W���O���x���������ƌ����Ԃɉ�������A�ڂ̑O�ɂ͑�A��������B�u�N���𑁂����˂v�Ƃ��A�u���N���ɂ���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��d�����܂�����v�Ƃ��A�c��̓��ɂ����ɂ�݂Ȃ���ǂ�����X���}���Ă���B
�@�l���Ă݂�A���ꂩ��S�N���Ƃ�12���̎s���I��������Ă���B�S�N���50�Α�̌㔼�B���t���������ǂ��Ȃ�ۏ͂Ȃ��A�̗͍͂����͊m���Ɍ�������B�������A�I���Ƃ��Ȃ�A�����ő�����˂Ȃ�Ȃ��B�S�N��̎s���I���{�Ԃ́A����̖��x�����ȏ�ɔZ�������邱�ƂɂȂ�̂��낤���B����Ƃ��A����͓ˑR�̑I���ƂȂ������߂ɁA���x���Z�������邱�ƂɂȂ����̂��낤���B������ɂ��Ă��A12���Ƃ������������̑I���͂��肪�����͂Ȃ��B���I�������s���̈�t�F�F����r���Ŏ��E�ɒǂ����݁A�I��������ς�������Ƃ����ӋC���݂����߂���B�������A�Ă܂�������̑I�������肪�����͂Ȃ��B�t���H�����肪�����B�\�\�Ȃǂƍl���Ă���Ƃ��ɁA�u���A�Ƃ̑�|�����c���Ă���̃��I�v�ƁA�J�~������ł�߂����B����āA���N�̃z�[���y�[�W���M�͂��̒��x�ŁB�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�݂��̂��̖����|�\������ǂ�
 |
| �������������x�̉�́w���n�����~�x��x |
�@27���ɑ�ꏬ�w�Z�̈�قōÂ��ꂽ�u�����{��k�Е����x���v�́u�݂��̂��̖����|�\������ǂ��v�́A�����I�������B�s����ߌ��Ŋ������鈤�D��̗x��║�ɉ����āA��Вn�̋{�錧����͒����c�_�y�ۑ�����}������A�\���Ɋy���܂��Ă��ꂽ���炾�B
�@������肩�A�����c�_�y�ۑ���̂��Ȃꂽ���Ɗy��̉��F�A��������҂���́A�u�ǂ������������͐����Ă���v�Ƃ̋������b�Z�[�W�����ӂ�Ă���B�v�킸�����M���Ȃ����B
�@�k�Ђ̕����x���ɂ́A�l�X�ȉ�����������Ǝv���B��Вn�ւ̃{�����e�B�A�x��������A�����x�������ɉ�����Ƃ������@������B�������A����̎��g�݂ɂ͐���������B
�@��ꂢ���ς��̊ϋq�B���̑O�ŗx�蕑���l�X�B���߂Ă̏o��ɂ�������炸�A���鑤�������鑤���y�����Ȃ�A���C�����炦��B�������A��Вn�ւ̎x���ɂ��Ȃ��Ă����E�E�E�B�S���[������ĉƘH�ɂ����̂́A�������ł͂Ȃ��������낤�B
�i�u����Ԃ���v2011�N12���S���t����j
�C���r���ł̎s�����E
�@������s�ŔC���r���Ɏs�������E�����̂́A�����a�Y���łS�l�ځB
�@�ŏ������약�掁�B�����o����ւ̏������������ł���B���ɕۗ������玁�B�c����Ă̏����Ɉًc�������āA�c��ƑΗ��B����2004�N�U�����E�̈�t�F�F���B�b��\�Z�������Ȃ��ŁA�u����ĊJ���ւ̖��ӂ�₤�v�����R�B�S�l�ڂ��A����̌�����ŐE�������������a�Y���ł���B
�@�����a�Y�������̂R�l�ƈقȂ�̂́A�s���̖����̕�炵�ɉe��������ڂ������ł��邱�ƁB�u���_�g���v�ƌ�����A���ꑤ�́u����͂Ȃ���v�ƂȂ�A�u����Ȃ�A���������ŏ���������H�v�ƌ����āA�����s���͍s���l�܂��Ă��܂����B
�@�s���́A�\�Z���s��s�����s�Ȃǂ̌��\�����B�s�������ɏq�ׂ����̂́A�����̂��\����҂̔��M�ƂȂ�A�ΊO�I�ɂ��傫�ȏd�݂����B�c��ł͐������Ȃ��͂ł���B
�@���̂��Ƃ��킫�܂����s�����A�I��ōs���������̂ł���B
�i�u����Ԃ���v2011�N11���U���t�j
��Вn�̌���
 �@�ǂ��ɂł�����悤�ȍ`���B����������������ݓ����ƁA��ꂽ�p�����ڂɉf��A�Ɖ��̓y�䂾�����c����i�������B �@�ǂ��ɂł�����悤�ȍ`���B����������������ݓ����ƁA��ꂽ�p�����ڂɉf��A�Ɖ��̓y�䂾�����c����i�������B
�@���������͓���]���������A�C�ƎR�̊ԂɃq�^�C�قǂ̕��n��������x�B���낤���đ�Ôg���瓦�ꂽ�l�X�́A�������̉��ݏZ��ɐg���Ă���B��������v���H���痣�ꂽ���̒n�ɁA�x���̎肪���邱�Ƃ͏��Ȃ��B
�@���{���Y�}�̎x�������̑O�ɗ���Ȃ��l�X�́A�x���ɂ�������炸�N�z�҂������B�傫�Ȏ�܂�p�ӂ��A��������Ȃ��قǂɕ����������B�u���肪�Ƃ��������܂����v�B�����̐l�X���������ɓ���������B
�@���ꂩ��ӏH�A�����ē~���}����B���Q�����ѕz�͐��Ɍ��x������A��ނȂ����I�ƂȂ�B���������l�Ƃ͂��ꂽ�l�̕\��̍��ɁA�S���ɂށB�Ί��ł́A���Î��]�Ԃ̒��I�ɑ����̐l�����B���]�ԂȂ��ł͔����ɂ��s���Ȃ��Ƃ����B
�@�k�Ђ��炷�łɂV�J���B�����ւ̓{��͑�������ł���B
�i�u����Ԃ���v2011�N10��16���t����j
�w���悤�Ȃ猴���x���������W��
 �@�i�q��ʃ��J�w�������ƁA�w�O�ɂ͒c�̖��̃m�{�����������l��[�b�P���������l�A�v���J�[�h���������l�Ȃǂ��������ƏW�܂�A�����̈�ٕ��ʂɌ��������������̐l�ł������������Ă����B���̓�(19��)�͌ߌ�P��30������A���������Łu���悤�Ȃ猴���T���l�W��v���J�����̂ł���B�ߑO���A������̓��������̑��q�̍��Z�̕����Ղɍs���Ă������́A�i�q��ʃ��J�w�Ɍߌ�O��30���ɍ~�藧�����B�������A���łɂ��̗L��l�ł���B �@�i�q��ʃ��J�w�������ƁA�w�O�ɂ͒c�̖��̃m�{�����������l��[�b�P���������l�A�v���J�[�h���������l�Ȃǂ��������ƏW�܂�A�����̈�ٕ��ʂɌ��������������̐l�ł������������Ă����B���̓�(19��)�͌ߌ�P��30������A���������Łu���悤�Ȃ猴���T���l�W��v���J�����̂ł���B�ߑO���A������̓��������̑��q�̍��Z�̕����Ղɍs���Ă������́A�i�q��ʃ��J�w�Ɍߌ�O��30���ɍ~�藧�����B�������A���łɂ��̗L��l�ł���B
�@�u���悤�Ȃ猴���T���l�W��v�͍�Ƃ̑�]���O�Y����璘���X�����Ăт��������̂ŁA���{���Y�}�ɂ����͂̌Ăт��������ꂽ���̂ł���B�w���~�藧�������́A�����̈�ق̉���ʂ蔲���A�܂������ɉ��̖��������Ɍ��������B�߂Â��ɂ�A��`�J�[��n���h�}�C�N����̉�����������A���̕���ʼn̂��Ă���̂ł��낤���A���y���������Ă����B�������������ł͗l�X�Ȓc�̂��`���V��z��A�������Ăт����Ă����B�Ȃ��ɂ́A�\�͂Ő��E��ς��悤�ƍl���Ă���c�̂������A��Ⴂ�Ȓc�̂�������Ă���ȂƎv���قǁB�ߌ�O��45�����ɂ͉��̖����������ɓ������B�܂������͗]�T������B
�@�u���{���Y�}�v�̕�������������Ȃ��̂ŁA���Ă����b�ɂȂ��Ă����J���g���̊����߂����Ă����B�����������Ă��邤���ɉ����͍��G���͂��߁A���ɓ��肫��Ȃ��l������悤�ŁA���H�̕�����͎Q���҂�U������悤�ȃ}�C�N�����������Ă���B����ɂ̓w���R�v�^�[����ь����A�����͐l�ƃm�{�����Q�����B
�@�P��30������W��n�܂����B�䕗�̉e�����炩�A�K���ɉ��V���Ƃ͂Ȃ炸�A�_�̍��Ԃ��瑾�z�̌����������ނƂ������x�ƂȂ����B�R���N���[�g�̒n�ʂɍ��荞�Q���҂́A�}�C�N���痬���i���Ɂu�������v�u���̂Ƃ���v�Ȃǂ̊|�������A�^���Ɏ����X���Ă����B
�@�W��͂Q��30���ɏI������B�Ȃ����A���}�������͈�Ȃ������B���������̓��O�ɂ͏��Ȃ��Ƃ��R�̐��}���������A�����Ƌ��͓I�ȊW�ɂ���c�̂������ɂ͑����ɗ��Ă���Ǝv����B�J���g����s���c�̂ƂƂ��ɁA���}�����̏W��̐����ɗ͂���ꂽ���炱���A���ɓ��肫��Ȃ��吨�̎Q���҂��������̂��Ǝv���B�u�����̐��_�����߁A����������������Ȃ����Ă��������B���̕��@�͔�\�͂Łv�Ƃ����肢�����L����l�X���^����傫�����Ă������߂ɂ́A���̎�|�Ɏ^�����鐭�}�̖�����Ⴍ���邱�Ƃ������Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̐��}�̖�����傢�ɕ]�����A���̐��}�̂��������邱�ƂŁA���̐��}�̎x���҂⋦�͒c�̗̂͂�����Ɉ����o�����Ƃ��ł���̂ł���B�u���悤�Ȃ猴���T���l�W��v�́A���{���Y�}���傢�ɎQ�����Ăт�����Ȃ��ŁA�U���l�̎Q���҂Ő��������B
���Ղ�
 |
|
�ш�_�Ѝ�̎q�ǂ��_�`
|
�@�q�ǂ��̍��A���̏H�Ղ�͂ƂĂ��y���݂������B���̓��͖�ɐ_�Ђ̋����ʼnf���Â���A���̖ʁX����ɐH���Ȃ�����A�X�N���[���Ɍ������Ă����B�����ȑ��Ȃ̂ŁA��X�͏o�Ȃ��B�P��������̍Ղ�ł���B����ł��A���̓��͒�����A�C���������Ԃ��Ă����B
�@�ш�_�Ђ̍�́A��ו��ɂȂ�Ȃ��قǂɍ����ł���B�_�БO�ł͉��������N�A�����낢���A�q�ǂ��_�`�⑾�ہA�ш䚒�q�A�_�`���D��n����������B���K�����肵�߂Đ_�Ђɑ����Ă����q�ǂ������̎p�́A�c�����̎��������������Ƃ��Ă���B
�@�~�x�肪����A�炪�s�Ȃ��A�l�X�Ȏ��g�݂������߂��Ă���n��́A�q�ǂ����獂��҂܂ŁA���S���ĉ߂�����X���Ǝv���B
�@��k�Ђ��甼�N�]�B���܂��ɔ�Вn�͐����Č��̖ڏ����������A�Z���͗���Ȃ�ɂ���Ă���B��ƎQ���̕����v���������A�n��Z�������Y����x��������B�l���J����Ԃ̕�ł���B
�i�u����Ԃ���v2011�N�X��18���t����j
�����ʼn߂��������~
 |
|
���s�E�r�̘@�̉�
|
�@�C��35�x�A���������������B�u�����̉Ă͂��育�肾�v�ƌ������A35��ڂ̓����ł̉Ă��߂����Ă���B
�@��N�A�W���̂��~���߂Â��ƁA��Ƃŕ���̎��Ƃɏo�����Ă��邪�A���Z���̎q�ǂ��������Ċ��u�K���Ƃ��������Ƃ��ł��~���w�Z�ɏo�����A�J�~������d�����x�߂Ȃ��Ƃ������Ƃ���A����l�A�Ƃɒu������ɂ��ꂽ�B
�@�O�͖ҏ��B�������Ƃɂ��Ă��_���_�����邾���B�����ŕ��N���āA���V���̂Ȃ����Q���Ԃɕ����ēs���U��ɏo�������B�r��{�厛�A�����r�A�ő��㎛�A���s�E�r�A�����@�뉀�A�����V�_�E�E�E�E�B���N�A�����ŕ�炵�Ă͂�����̂́A�s�E�r�ȊO�͏��߂Ă̏ꏊ�ł���B
�@�܂������~�B�{�厛��㎛�ł͐����̂ɂ����ƂƂ��ɁA�njo�̐�������A����Q��̎p����������ꂽ�B�ҏ���Y��A�����Â��Ȏ��Ԃ��߂������B
�@���e���S���Ȃ�A���Ƃ͉��̂��B�W���͌̐l��E�Ԏ��Ԃł�����B
�i�u����Ԃ���v2011�N�W��21���t����j
��@
 �@�X���̔~�J�����ȍ~�A�ҏ��������������A�䕗�̉J���ŏ��X�߂�������X���}�����B����ǂ��ҏ��͂��ꂩ�炪�{�ԁB �@�X���̔~�J�����ȍ~�A�ҏ��������������A�䕗�̉J���ŏ��X�߂�������X���}�����B����ǂ��ҏ��͂��ꂩ�炪�{�ԁB
�@�����������̂Őߓd���Ăт������A�G�A�R�����T���Đ�@�𗘗p����ƒ낪�����Ă���B���̐�@���i���Ƃ��ŁA��N�ȏ�ɔM���ǂ̔�Q���S�z�����B
�@����A������s���͎q�ǂ������̋����ł̔M���ǔ�Q�Ɠd�͏���ʂ�V���ɂ����A�G�A�R���_���x�点���B�Ȃ̂ɁA�d�͂��ʂɎg�p����s���𗬃Z���^�[�́u�����Ă��ǂ��v�ƍl���A���X�Ə����ɓ����Ă���B�V���ɂ̂��郂�m������Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�̏Ⴕ���G�A�R���ɑ����āA�䂪�Ƃ̐Q���ł͐�@���劈��B�������A�Â��^�̂��߂ɉ������邳���B�����āA������v������҂ƁA���̂悤�ɔ����ł��Ƃ����҂Ƃ���̎��ɂȂ��ĐQ�Ă��邽�߁A���ʂƕ��������߂��鑈�����₦�Ȃ��B�Ă͂܂��P�J���ȏ�������B��@������O�ɖҏ��͏I����Ăق������̂��B
�i�u����Ԃ���v2011�N�V��24���t����j
��ɗ��҂̊�
�@��ɗ��҂͐l�̈ӌ��Ɏ����X���A���Ȃ��Ƃ������ɗ�������钆�g�ƍs���͂��K�v���Ǝv���B������ɁA���̍��̐����́A��ɗ��҂̊�ɋ^���������B������Ƃ����āA�������艺�낻���Ƃ���҂̂Ȃ��Ɋ킪����Ƃ��v���Ȃ��B
�@�����𑱂���̂́A������s���������B�u���_�g���v�ƑO�s����ᔻ�����I�����V�s���B�}�����c��`������u����v�̒�����P�N���A���g�ŏo������\�Z������������邱�Ƃ܂ōs�Ȃ����B���g�̌f����u������₷���s���v�Ƃ͂قlj��������ł���B
�@��ɗ��҂̊�ɂ́A�x���鑤�̐l�S����������x�ʂ����߂���B���̂��߂ɂ��A�x���鑤�Ƃ́u�Θb�v�͌������Ȃ��B
�@�V�s���̎{�����j�ł́A�u�E���́w���C�x�w�\�́x�������o�����Ɓv�u���̂��߂ɁA�E���Ƃ̑Θb���d�˂�v�Ƃ���B��������A�̍s���ɂ́A���g�̕��j�ɔ����镔����������B����Łu�s�������v�v���\�Ȃ̂��B�܂��͎��g�̉��v���K�v�ł���B
�i�u����Ԃ���v2011�N�U��26���t����j
�e���̖���
�@�e�����S���Ȃ��ĂR�N���o�����B�S���Ȃ����N�́A�����A�l�\����̖@�v�A���~�A�[���ƁA�ڂ܂��邵�����X�𑗂����B���N�͂P�����Ŗ����ɍ��킹�ċA���B��N�͂R����łT���̘A�x�ɋA�������B
�@�S���Ȃ��ĂR�N�B�@��������킯�ł͂Ȃ��A�������U���s�c��^�������B���t�����������ɕz�c�ɓ���A�ӂƋC�t���B�������A�����͐e���̖������B��������A�R�N�O�̂��ƁA�P�����̂��ƁA��N�̂��ƂȂǂ���݂�����B
�@�e�����S���Ȃ��Ă���A���Ƃւ̋A�Ȃ̎v�����キ�Ȃ����B��e�͎��Ƃɕ�炵�Ă͂��邪�A�����R�l�Ɉ͂܂�āA����Ȃ�ɏ[���������X�𑗂��Ă���B��v�w���A�Z�����Ȃ��ɂ���Ƃ̑单���Ƃ��đ�����A�U�l�̐��т������������Ă���B�g�����������Ƃ����b�����������A���������̗l�q�B������A�����̒n�ŁA���������̂��Ƃ݂̂��l���Ă���Ηǂ��̂ł���B
�@�e���̖������Ȃ��Ȃ����B�̐l�ɂ͐\����Ȃ����A�̐l��U��Ԃ邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��Ă����悤�Ɏv���B������A����Ȏ������߂悤�ƁA�����Ɩ����ɂ͖����ɗ����낤�Ǝv�������A��������������B�e���͐�ނ肪�D���Ȃ̂ŁA�����ɗ������A�����̎R���̌k�J�ɗ����Ă���̂��낤�B
�@�����̂U��22���́A������s�c��̋c��\�����B�c��̏o�Ԃ�҂��Ȃ���A�C�����Η[���T�����߂��A�o�Ԃ̎����͂܂������������B������s�c��͐V�s���̂��Ƃŗ^��}�̊_�����Ȃ��Ȃ�A�����Ȏ��^���A���A�W�J����Ă���B�ƂĂ��A��l�Â��Ɍ̐l���v����Ԃł͂Ȃ��Ȃ��Ă���B
��k�Ђ̏�����s�̏�
�@�����{��k�Ђ́A������s��Ők�x�T��̗h��������炵���B�s�������̈�ق̓V��ނ��������A���Ƃ̃u���b�N�����V�ӏ��|��A�������͂V���ŗ������A���w�Z��s�����{���ɂ̑��K���X�ɋT�������B
�@�m�l��e�ʓ��𗊂��đ����̕��X����Вn�𗣂�A13�����݂ŏ�����s�ɂ�76���сE144�l�̔��҂��m�F����Ă���B���������̔�Q���瓦��Ă����P�[�X�������Ƃ����B
�@���{�Ⓦ���d�͂́u�z��O�v�����ɂ��Ă����B���̍l���͏�����s�̒n��h�Ќv��ɂ��e�����A�n�k�ɂ�錴���̕��˔\��Q�͈ꌾ���L����Ă��Ȃ��B�u���Ⓦ���s�̌v������ƂɁA������s�̌v����쐬����邩��v�����̗��R�B
�@���C�n�k���N�����ꍇ�A�l�������̕��˔\��Q��z�N����͓̂��R�ł���B���{���ғ���~�����߂��̂́A���͂�u�z��O�v�Ƃ͌����Ȃ�����ł���B���̓��C�n�k�A������s��̗h��́u�k�x�T��v�Ƃ���Ă��邪�A������͑z����ł����Ăق����B
�i�u����Ԃ���v2011�N�T��29���t���j
�����킹�^�ׂ�悤��
�@�u�w�����킹�^�ׂ�悤�Ɂx�Ƃ����̂��݂Ȃ���A�������ł��傤���H�v�B�T��14��(�y)�̖�A�[�H������Ȃ��炩���Ă����m�g�j���W�I�́u�J�����v�Ƃ����ԑg�ŁA�j���A�i�E���T�[���X�s�[�J�[�̌����������王���҂ɖ₢�����Ă����B���߂ĕ����Ȗ��ł���B�j���A�i�E���T�[�͉̂̏Љ���s�Ȃ����B�u�̂̏Љ�J�[�h�ɂ��ƁA���̉̂��������̂́A�_�˂̏��w�Z���t�́w�������܂��Ɓx����Ƃ������ŁA������16�N�O�ɋN�����A��_��k�Ђ̂Q�T�Ԍ�ɔ���̐e�ʂ̂���ł���ꂽ�Ə�����Ă��܂��v�B�����Ēj���A�i�E���T�[�͌����B�u���̉̂͐_�˂ł́A�����炭�F����m���Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���v�B
�@�s�A�m�̑O�t�ɑ����āA�q�ǂ������̉̐������ꂾ�����B�u�n�k�ɂ������Ȃ������S�������ā@�S���Ȃ������X�̕����������ɐ����Ă䂱���@�������_�˂����̎p�ɖ߂����@�x�������S�Ɩ����ւ̊�]�����Ɂ@�Ђт��킽��ڂ������̉́@���܂�ς��_�˂̂܂��Ɂ@�͂������������̉́@�����킹�^�ׂ�悤�Ɂv�B
�@���̉̂��A���͑傫�Ȋ��������B����ȉ̂��������Ȃ�āI�B�������܃p�\�R���̃C���^�[�l�b�g�ŋȖ�����������ƁA��_��k�Ђ��N�����P��17���̐_�˂́u�ǂ��v�ŁA���̉̂��������Ă��邱�Ƃ��킩�����B�������A�b�c�ɂ��[�߂��Ă���B������x�A���������B�ł���b�c���茳�ɒu�������B����قǂ܂łɁA���͎̉̂��̐S��h���Ԃ����B
�@���Ă������Ă������Ȃ��v���ŁA�����A�������s�̂b�c������ɓd�b���āA�b�c�����邩�ǂ����������˂��B�u����܂���ˁB���ɂȂ�܂����A����ł������ł����H�v�B
�@�R����ɁA���̎茳�ɂb�c���͂���ꂽ�B������ɂ����b�c�́A�_�˂����_�Ɋ�������S�l�g�{�[�J���O���[�v�uvoice from KOBE�v�́uCooley High Harmony�v�Ƃ����A���o���ł���B�u�����킹�^�ׂ�悤�Ɂv�Ƃ����̂����߂ĂȂ�A�uvoice from KOBE�v�Ƃ����O���[�v�������߂Ăł���B
�@�R��11���̓����{��k�Ђł͂P���T��l���S���Ȃ�A���܂��ɂW��W�S�l�]���s���s���ƂȂ��Ă���B���s�̋߂��ɏZ�ޒm�l�́A�E��̍X�ߎ��ň�l�Œ��ւ��Ă���Œ��ɑ�k�Ђɑ��������B�u���b�J�[��������Ɨh��A�X�v�����N���[���쓮���Đ��Z���B���ʂ��Ǝv�����v�ƃ��[���Œm�点�Ă������A���̌�A���̒m�l�͓x�d�Ȃ�]�k�̂Ȃ��Ŗ���ʓ��X���}���A���炭���@���鎖�ԂƂȂ����B���̒m�l�ɂ��A�����Ė����ւ̊�]��͍����Ă����Вn�̕��X�ɂ����ЁA���̉̂��Ă��炢�����B�u�����킹�^�ׂ�悤�Ɂv�B
�I������
 �@�I���̎��ɗL���҂ɖ������̂��u�I������v�ƌ����B���́u�I������v�����āA���邢�͊X���ł̑i����x���҂���̌Ăт����ɂ���āA�L���҂͐�����[��N�ɓ����邩�f����B����̏�����s���I���ł́A�S���ڂ�ڎw�������E�̎s�����s�k���A�������V���L�҂�53�̐V�l���s���ɓ��I�����B �@�I���̎��ɗL���҂ɖ������̂��u�I������v�ƌ����B���́u�I������v�����āA���邢�͊X���ł̑i����x���҂���̌Ăт����ɂ���āA�L���҂͐�����[��N�ɓ����邩�f����B����̏�����s���I���ł́A�S���ڂ�ڎw�������E�̎s�����s�k���A�������V���L�҂�53�̐V�l���s���ɓ��I�����B
�@�I������̑�\�I�ȕ������u�I������v�ł���B���I�����������V���L�҂̑I������ɂ��������̌��f�����A���Ȃ��Ȃ��L���҂��A���̑I������𓊕[�̔��f��ɂ��Ă���ƍl������B������A���̑I������́A�I�����I���������Ƃ����Č�i�ɑނ��邱�Ƃ̂ł�����̂ł͂Ȃ����A���I�������҂̂��̂ł���Ȃ�����A���Ȃ��Ƃ�����S�N�Ԃ̑�ȁu����v�Ƃ��Ď茳�ɒu���Ă����ׂ��㕨�ł���B
�@���I�����V�s���̌��������ƁA�����������p�������̂�����ł���B���Ƃ��A���ݒ���(���[�X����)�̑���������s�����۔�̑啝�팸�A�����{��k�Ђ��Ă̂S�ً̋}�Ȃǂł���B�������A�����ł͂Ȃ����̂�����B�ꍇ�ɂ���Ă͂U���c��ŁA�V�s���̍l������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv�����̂�����B
�@�����Ȃ��Ƃ��Q�_�B���̂P�́u�s���𗬃Z���^�[�v�ɂ�����u���Ɍ��ׂ��������Ă��A�w���̐���͏Z�����[�Łv�Ƃ��������ł���B�u���ׁv�Ƃ́u�s���Y�o�L���ł��Ȃ��A�哹���y���������钓�ԏ�̎g�p���s����Ȃǁv(���w�c�̎��O�r��)�ł��邪�A���̌��ׂ��������Ă��u�����܂���v�Ƃ����Ȃ�A�����^���ł���B�������A�����ł͂Ȃ��A�u�w���̐���v���u�Z�����[�Łv���߂�Ƃ����̂́A����X����Ƃ���ł���B
�@�����_�ł̐��ڂ��猩��ƁA�s���𗬃Z���^�[���Ǘ����Ă���s�s�Đ��@�\(�t�q)�������́u���ׁv���ł��錩���݂͂Ȃ��B���ɓs�s�Đ��@�\(�t�q)���A���g���ڎw���Ă���u���N�X�����́w���ׁx�����v�𐬂��������Ƃ��Ă��A�w���̐����₤�Z�����[�́A����ȍ~�ɂȂ�B�Z�����[�ɂ�����ۂɂ́u�������S��g������̈����A�b�n�Q�̑�ʔr�o�Ȃǂ̖��_���s���ɖ��炩�Ɂv����(���O�r��)�Ƃ��Ă���A���̂��߂̎����������K�v�ɂȂ�B�Ȃ�₩��₵�Ă��邤���ɁA�Z�����[���{�͑����Ă�2011�N�x�I�ՁA���邢��2012�N�x�ɐH�����ނ��ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�Z�����[�̎������x���ƁA�V���Ȗ��_����������B�s���𗬃Z���^�[�̍w�������ɂ́A�s���̐ŋ�������؋��ɉ����āA������̌�t�����܂܂�Ă��邪�A����܂ł́u�܂��Â����t���v�����������A���̌�t����2010�N�x���ŏI���B���̂��ߍ��N�x�́u�Љ�{����������t���v���[�Ă邱�ƂɂȂ����B���������̌�t�������N�x���ŏI������Ƃ���Ă���B������̌�t�����[�Ă��Ȃ��Ȃ�ƁA�܂�܂�s�����S���邱�ƂɂȂ�B���N�x�A�s���𗬃Z���^�[�ւ́u�Љ�{����������t���v���X��9,870���~�\��B�������s���𗬃Z���^�[�̍w����2012�N�x�ɐH�����ނƁA�X��9,870���~�����̂܂s�̕��S�ƂȂ��Ă����̂ł���B
�@�ނ�̑I������⎖�O�r���ł́u�s���𗬃Z���^�[�擾���z75���~�v�́u���_�g���v�Əq�ׂĂ���B�u���_�g���v�ł���ƔF�߂Ă���̂ɁA�Ȃ��A�w���̐�����u�Z�����[�v�Ō��߂�Ƃ����̂��낤���B���������́u���_�g���v�̂Ȃ��ɁA�V���ɂX��9,870���~�̎s���S�������\���������̂ł���B�s���𗬃Z���^�[�́u���_�g���v�����ł͏I���Ȃ��B���O�r���ł́A�u�������S��g������̈����A�b�n�Q�̑�ʔr�o�v�ƁA���̖��_������Ɏw�E���Ă���B�Ȃ�A���_�Ƃ��Ắu�����܂���v�ƂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�����Ƃ́A�����̐M�O���m�łƂ��Ď��ׂ��ł���B�u���_�g���v�ł���̂Ȃ�A�u����Ȃ��v�ƂȂ�ׂ��ł���B�u�Z�����[�̎��{�v�͕������͂悢���A���ǁA�ŏI���f���s���ɈςˁA�u���_�g���ł����Ă��s�������߂��̂�����v�ƁA�s���ɐӔC��]�ł�����̂ƂȂ�B���̌��ʁA�s���������n�ɒǂ����ނ��ƂɂȂ�Ƃ��Ă��ł���B
�@����X������Ȃ������P�̓_�́A�u���ݏ����S�N�Ԃ�20���~�v���u���_�g���v�Ƃ����L�q�ł���B�u��t�s���̖��v��ȃS�~�����{��ɂ���āA�S�N�Ԃ�20���~���x�o������Ȃ��Ȃ����B����͋����Ȃ��v�Ƃ����L�q�Ȃ�Η����ł��邪�A�u20���~�����_�g���v�ƂȂ�ƁA������s���̉R�S�~������Ă��鑤�́A�u�Ȃ�A�������ނȁI�v�ƂȂ�ł��낤�B���̓_��������s�������o���̍ۂɋL�Ғc�ɖ��ꂽ�V�s���́A�u�o��ɂ��Ďs���ɒ��ӊ��N�����������v(�S��28���t�u�����v)�ƌ���Ă��邪�A����͖��ӔC�Ȍ������ł���B��q�����Ƃ���A�L���҂́u����v���d�����Ă���B�V�s���̑I������⎖�O�r���́A�u��t�s�����S�~������20���~�̃��_�g�������Ă���v�Ǝw�E���Ă���̂ł���A�u����ȃ��_�g�������Ă����t�s���ł悢�̂��H�v�Ƃ������Ƃ�L���҂ɖ₢�����Ă���̂ł���B�u���_�g���v�Ǝw�E���Ă����Ȃ���A�u���ӊ��N�̂��߁v�̈ꌾ�ŕЕt����̂́A������y�X�Ɉ������̂ł���B�Ȃ��A�t�����Ă������A�V�����������A�V�s���́u���_�g���v�̕\����P�Ă͂��Ȃ��B
�@�����܂ł��Ȃ��A�S�~�����͖����̎s�������ɒ�������B�I������ŐV�s�������f�������e�́A���Ȃ��Ƃ�����S�N�Ԃ̖��ł���B���e�ɂ���ẮA������s���݂̂Ȃ炸�A�������̂ɂ��g�y������̂ƂȂ�B�V�s���̂��ƂŁA�S�~��肪��t�O�s���ȏ�ɍ������鎖�ԂɊׂ�Ȃ���悢�̂����B
�@���āA�V�s���̗^�}�͂T�l�ł���B���̂��Ƃ͐V�s���̑I������́u�������܂��v�̗��ɁA�T�l�̎s�c��c���̖������邱�ƂŖ��m�ł���B���̂T�l�́u�݂ǂ�E�s���l�b�g�v�Ƃ�����h��g��ł���B���������̉�h�ɂ͂����P�l�A�c��������B���̐l���͎s���I���ł͕ʂ̌��҂𐄂����B���R�ɐV�����n�܂�c��ł́A�V�s���𐄂����T�l�Ƃ͕ʂ̉�h�ɑ����邱�ƂɂȂ�ł��낤���A�����Ȃ�Ȃ���A�s���ɂƂ��Ă��s�����Ȏ��ԂƂȂ�B
�@�T��17������A�V�s���̂��Ƃł̏�����s�c��̉�h�\���Ƌc���E�̋��c���n�܂�B�V�s���̗^�}�̂T�l�̒�����N���c���ɂȂ�̂��H�A�T�l�̂Ȃ��ɋc���E������l���͂���̂��H�A�c���E������邽�߂Ɂu�݂ǂ�E�s���l�b�g�v���C���C����������͂��Ȃ����낤���H�A�܂����T�l���ʁX�̉�h�ɕ����ꂽ��͂��Ȃ����낤�ȁH�ȂǁA�J�̊S���͂T��17���Ɍ������Ă���B
���~��炵
�@�䂪�Ƒ����A���̉ƂɈڂ�Z�̂�10�N�O�̂W���B���łɒz26�N���o�߂��A�����ڂ��������ăL���C�ł͂Ȃ����̉Ƃ��w�������ő�̗��R�́A�Z�����ς�炸�A����܂Œʂ�ɋߏ��Â���������������Ƃ�����_�ł������B�悤����ɁA���̉ƂƓ����H�n�̂Ȃ��ɂ���؉ƂɎ������͕�炵�Ă����̂ł���B
�@���̉Ƃ̑O�g�́u����v�B�P�K����q���A�Q�K���_������̏Z�܂��A���̏�ɉ���������������Ƃ��������ł���B����ł͏T�ɂP����x�A��q���s�Ȃ��A�N���X�}�X�Ƃ��Ȃ�ƁA����̊����ꏊ�ŁA�M�҂̕��X���^���̂��̂��Ă����B���̎��ɂ́A���َq�Ȃǂ��䂪�Ƃɂ��������킯���Ă���Ă����B���̋�������s���̍��Ɉړ]���邱�ƂɂȂ�A�ꎞ�A�؉ƂƂ��ė��p����A���̌�A����ɏo���ꂽ�̂ł���B
�@�w������ɂ������Ď��́A�P�K�����ƂQ�K�����̃��t�H�[�����s�Ȃ��A��q���͏Z���ɑ���ւ����B�������A��q���̒��ȂǁA�g���镔���͂��̂܂܊��p�����Ă�������B
�@���̉ƂɈڂ�Z��ł��炱�̊ԁA���X�A����������邱�Ƃ��N����B����́g���h�ł���B���͒��ԁA�Q�K�Ńp�\�R���̎d�����s�Ȃ����Ƃ�����B�����͎q�ǂ������͊w�Z�A�J�~����͐E��ɂ���̂Ŏ���l�̂͂��Ȃ̂����A���́g���h�͂����Ă��A�ߌ�̂܂������������ԑт���[���ɋN����B�h�A��߂鉹�ł���B�u�o�^���v�Ƃ����h�A��߂鉹�����āA�n�e�H�A�����q�ǂ��������A���ė����̂��낤���H�ƁA�P�K�ɉ���čs���Ă��N�����Ȃ��B�q�ǂ�����������čs���Ă��鎩�]�Ԃ��A����ɂ͂Ȃ��B���鎞�ɂ́A���ւ��J���߂��鉹������B�������A�N�����Ȃ��B�����悤�Ȃ��Ƃ��J�~����������B�u�P�K�ɂ��鎞�ɁA�Q�K�������������v�B
�@�����ȑO�ɏq�ׂ����t������B�u�������������ɂP�K�ŐQ�Ă�����A���̕����̃h�A�̌��Ԃ���A�������𒅂��I�J�b�p�̏����Ȏq���A�������Ă����B�|���Ȃ����̂ŁA�݂�Ȃ̂���Q�K�֏オ�����v�B���͌����u���̕����ɉ��������Ȃ��́H�v�B���̕����͂P�K�̉��B���̕����́A��q���̑啔���̑f�ނ����̂܂܊������Ă���ꏊ�ł���B
�@���~��炵�H�B����Ȏ����ŋ߁A�l����悤�ɂȂ����B������͗��_�A����M����҂ł͂Ȃ����A����ȃ��m��������������䂪�Ƃɂ���̂����m��Ȃ��ȁA�ƁA�D��S�����A�v�����������B����ȃ��m�����̉Ƃɂ���̂Ȃ�A�������낢����Ȃ����A�ƁB
�@�z30���N���o�����̉Ƃ́A���R�ɃK�^�����Ă���B������A�Ƃ������މ���ׂ̉Ƃ̉����A�Ƒ��ɍ��o���N�������Ă���̂��낤�ƁA���͗�ÂɎv���B�ł��A�悢�ł͂Ȃ����B�u���~��炵������Ƃ���v���Č�����Ƃ�����A�������낢�Ǝv���̂��B
�@�����A���~��炵�ƕt���������ƂɂȂ肻���B�J�l���Ȃ��̂ŁA�K�^�K�^�̂��̉Ƃ̌��ւ��͓����A���肦�Ȃ��̂�����B��H�A�܂��P�K�Łg���h�������B
�ߑR�Ƃ��Ȃ�
�@�n�k�̗h������O�ɒm�点��@�킪�A���т��ьx����B��k�Ђ��炷�łɂP�����]�A���܂��ɑ傫�ȗ]�k����Вn���P���B
�@�������̂̔����͊g�傳��A�댯�x�́u���x���V�v�̍ň��i�K�ɕύX���ꂽ�B�����������d�͂����{���u�`�F���m�u�C�����͕��˔\�̕��o���x�͒Ⴂ�v�Əq�ׁA���̔��������炢�����āu���v�v���J��Ԃ��B�z���g�ɑ��v�Ȃ̂��H�B
�@���Z�R�N���̑��q�����ȏ����L���Č����B�u�É��̕l�������͂����Ɗ�Ȃ��ꏊ�ɂ����v�B���ȏ�������ƁA�n�k�v���[�g�̌���镔���Ɉʒu���Ă��邱�Ƃ��킩��B�Ȃ�����ȏꏊ�Ɍ��Ă��H
�@�ߓd�ɗ͓_��u���A�u�v���d�v�͎��{���Ȃ��Ƃ����B���̂��Ǝ��̂͊��}�ł��邪�A�R���̊����Ȃ��Ōv���d�Ɍ�����ꂽ�҂Ƃ��ẮA�ߑR�Ƃ��Ȃ��B�Ȃ��ŏ����炻�����Ȃ������̂��H
�@�u�z��O�v���J��Ԃ������̓S�������B���܂��������̓]�����B
�i�u����Ԃ���v2011�N�S��17���t����j
���k�֓���k�Ёw�s�ӑł���d�x
�@�u��邼��邼�v�Ƃ�����14��(��)�A15��(��)�ƁA������s���ł́u�v���d�v���s�Ȃ��Ă��Ȃ����������d�͂́A�R���ڂ�16��(��)�ɂȂ��āA���Ɏ��{�����B������s�͑S�̂łT�O���[�v���邤���́u��Q�O���[�v�v�Ɓu��R�O���[�v�v�ɑ����Ă���B�������A�s���̂ǂ̋�悪������̃O���[�v�ɓ����Ă��邩�́A�悭�킩��Ȃ��B���������ƁA�����Z��ł���ш�쒬�͂P���ڂ���T���ڂ܂ł��邪�A�����d�͂̎����ł́A������̒��ڂ������̃O���[�v���Ɂu���v���t�����Ă���B�u���́A�ǂ��炩�̃O���[�v�ɑ����܂��v�Ƃ̐���������A���ڂ̂Ȃ��ł��u��Q�v�Ɓu��R�v�ɕ��G�ɕ�����Ă���Ƃ����̂ł���B
�@�ŏ��ɒ�d���}�����̂́u��Q�O���[�v�v�B�ߌ�R��20������̊J�n�ł���B��k�Ђɂ���Ē��f���Ă����s�c��̗\�Z�ψ���͖{���ĊJ����A������ςȂ���́u�v���d�v���{�ł��������A�s�c�����s�����{���ɂ́u��R�O���[�v�v���Ƃ����̂����O�ɓ����d�͂��玦����Ă����̂ŁA�Ƃ��ǂ�����Ă���]�k�ɗh���Ȃ�����A���キ���キ�ƐR�c�͑�����ꂽ�B
�@�ߌ�R��40�����ł��낤���B�ψ���R�c���̈ψ����Ȃׂ̗ɍ����Ă���s�c����ǒ��̂��ƂɎ����ǎ���������Ă��āA���ł��������B�����ǒ����u�����H�v�Ƃ�����������A�ψ����ɉ������������B���̌�Ɉψ������������ꌾ�ɁA�c����͋������B�u��Q���ɂ���d���܂����v�B
�@�u������Ƒ҂Ă�B��Q���ɂ͖{���ɂƓ����w��R�O���[�v�x����Ȃ������̂��H�v�E�E�E�E�B���̂Ƃ���B�����d�͂����O�Ɏ������敪���́A�u��Q���ɂƖ{���ɂ́w��R�O���[�v�x�v�ł���B�u��R�O���[�v�v�͖�̂U��20�������d�̗\��ƂȂ��Ă���B�������Q���ɂ͂���܂ł̊ԁA�Ɩ��͓I�ɑ����錈�ӂ��ł߂Ă����B�����ցA�ˑR�̒�d���P�����̂ł���B
�@�s���ہA�ۈ�ہA��앟���A��Q�����A�Ŗ��W�A�����A�����A�S�~�A���A�y�A�s�s�v��A����ȂǁA�s���Ώۂ̂�����@�\���W�������Q���ɂ̌����S���̏Ɩ��������A�p�\�R����ʂ��^���ÂɂȂ�A���̊O�̌i�F���������邭��������ƂȂ����B�����̃J�E���^�[�O�ł́A�s�E���Ǝs�����A�ˑR����Ă������Â��ɕ�R�Ƃ������B
�@�x�e���錾���ꂽ�c������ƂɁA�s�̊Ǘ��E�҂����킽��������Q���ɂɌ������B���l���̋c���������{�ʁH�ɁA���Ƃɑ����B�c���ꂽ�҂͎����ɖ߂�A�����d�͂��������O���[�v�����̎����ɍēx�A�ڂ�������B�e���r�ł́A��ɐk�����Вn���f���o���Ă���B
�@����̖�A�����̎O�����n��ł͔����q�s�Ɠ���s�Œ�d�����{���ꂽ�B�������A�\��O�̏ꏊ����d�����B��Q�҂͔����q�s�������ɂƓ���s�������ɂł���B��d���ł͂Ȃ��͂��Ȃ̂ɓˑR�A��d���P���A�����̎s�����Ɩ����X�g�b�v�����B����̏�����s�����l�ł���B������������s�̏ꍇ�ɂ́A�s�����s�����ɗ��Ă������ԑтł��������߂ɓˑR�̎��ԂɎs���͍������A�s�E���ɂ����Ă������ʂ��������B�S�̏������ł��Ă��Ȃ������s�E���͖h��ɒǂ�ꂽ�B
�@��A�\����25���x��ŁA�u��R�O���[�v�v�̒�d������Ă����B�\��ł͂U��20������ƂȂ��Ă������߁A�u���~�ɂȂ����̂��i�v�Ƃ̎v�������܂��Ă������ł̒�d�ł������B�������A�\�莞���̑O�ɉ����d���̓��d����_���Ă��������Ƃ���A�u���A�������i�v���x�ŁA��d�����}���邱�Ƃ��ł����B�������낢���̂ł���B�����u�Ă����Α��͓d�C���_���Ă���̂ɁA�����瑤�͏����Ă���Ƃ����ӏ��������炱����Ɍ�����B�����������������A�Â��ł���B�R���قnj����������V��ɂ���A�X�Ȃ����Ƃ炵�Ă���B�g���̖�������āA����Ȃɖ��邢�h�ƁA���炽�߂Ċ������B
�@�\����P����15���������A�ߌ�W��45���ɖ��邳�������߂����B�܂������ɒg�[���̃X�C�b�`�Ɏ肪�L�т��B
���k�֓���k�Ёw�v���d�x
�@�����̒�~�E�����ɂ���ēd�͋������鎖�ԂƂȂ������߂ɁA�����d�͂́u�v���d�v���X�^�[�g�������B������s�ł�14������̎��{�������d�͂���`�����Ă������A15�����_�ŁA���{����Ă͂��Ȃ��B
�@�u�v���d�v�����\���ꂽ13���̖�A�䂪�Ƃł������d���Ɠd�r�A�X�C�A�}�b�`���ƒ�����T���o���A�g����႟���Ă���ȁh�Ə���ɔ��f���Ă��������d�������ꂱ��f�@���Ďg����悤�ɂ��A�a�����P�[�L�ɕt���Ă��������ȘX�C���������߂āA���S�̑̐����Ƃ����B���܂̂Ƃ���o�Ԃ��Ȃ��̂́A���肪�������Ƃł���B
�@�������A�����A���f���Ă���B�����d�͂̕ɉ����āA������s�͑�������h�Зp�X�s�[�J�[�Ŏs���Ɂu�{���A�ߑO�U��40��������T�˂R���Ԓ��x�A�v���d�����{����܂��v�Əq�ׂ�����ɓ����d�͂��\���ύX���A������������s���u���~�v�̈ē���h�Зp�X�s�[�J�[�ōs�Ȃ킴������Ȃ��Ȃ��Ă���B���̂��т��ƂɎs���́A���ւ���o���葋���J���āA�X�s�[�J�[���痬��鐺�ɕ����������Ă�̂ł���B
�@�����d�͂́A�v���d���s�Ȃ����ǂ����́A�y�d��܂Ō��S���悤�Ƃ͂��Ȃ��B�ߑO�U��40������̌v���d�̏ꍇ�A����ȑO�ɃX�s�[�J�[����A�i�E���X���邱�ƂɂȂ�B15���̒��͌ߑO�U��20�����Ɂu���{����܂��v�̃A�i�E���X���X�s�[�J�[���甭����ꂽ�B�N�������̎��ԂɋN���Ă���킯�ł͂Ȃ��B���̃X�s�[�J�[�ł������N�������l������B�Ȃ̂ɑ����Ĕ�����ꂽ�X�s�[�J�[�́u���~�v�ł���B����႟�Ȃ����낤�B�䂪�Ƃ͂U��20���̃X�s�[�J�[�ł������N�����ꂽ�J�~���}���Ŏ����Ђ˂�A�����{�[�����ɒ��ߍ��B�f���ɔ����邽�߂ł���B���̐������܂��A�{�[���Ɠ�ɒ��ߍ��܂ꂽ�܂܁A�䏊�ɒu����Ă���B
�@�����d�͂́u�v���d�v���Ƌ�������B�������N���������A�u���v���d�v���ƁB�q�ǂ��̍��A�ߏ��̂��������͌����Ă����B�u�I�I�J�~��������A�I�I�J�~��������ƉR�����Ă������N���A�{���ɃI�I�J�~�������Ƃ��ɂ͒N�����M�p�����A���N�̓I�I�J�~�ɐH�ׂ��Ă��܂����v�ƁB�䂪�Ƃ̎q�ǂ������͍��܂ł͐ߓd�ɓw�߂Ă����B����������͕��i�̐����ɖ߂��Ă��܂��Ă���B������ɋْ����������Ă��܂����悤���B���͂̐l�����͌����A�u�I�I�J�~���d�v���ƁB
���k�֓���k�Ёw���̎��x
�@��t�F�F�s�����A���{���Y�}�̐X�˂悤�q�c���̎���ɓ��ق��Ă��鎞�������B�u�n�k���v�̐����c��ɋ����A���ق𒆒f�����s���������Ȃ���l�q�����������Ă���ƁA����ɗh������傫���Ȃ��Ă������B�u����̓��o�C���I�v�u�V��̌u�����̗����ɋC������I�v�u���̉��ɂ�����I�v�u�����̃h�A���J���Ă����I�v�u�ψ����A�x�e��錾����I�v�̋��ѐ����s�������B���̉��ɂ����낤�Ƃ���ҁA�V�����������Ȃ����R�Ƃ���ҁA���̊p�����݂Ȃ��琬��s���������ҁE�E�E�B�c�����s�����A�Ȃ����ׂ��Ȃ��A���������h�ꂪ���܂�̂�҂��������B
�@�h��͂Q�����炢�������낤���A����Ƃ��P�����x�������낤���B�h�ꂪ���܂�A�Ƃɂ����ψ�����o���B�u�傫�������ȃ@�v�u����Ȃ̏��߂Ă��v�u���Ɋ֓���k�Ђ������������Ǝv�����v�u�|�Ă��錚���������Ȃ��̂��v�u�]�k�����邩������Ȃ��]�v�ȂǂƁA�L���ŋc���A�����K���K�������ł���ƁA�������������ꂾ�����B�s���̐��ł���B�u�݂Ȃ���A�}���Ō���������Ă��������B�}���Ō���������Ă��������v�B�c�����E�����A�R�K�̈ψ���O����h���h���ƊK�i������A���ɑO�̒���ɏW�܂����B���͂�����ƁA���ł������̊O�ɐl�X����яo���Ă���B���ׂ�̏�������h���ł́A�E�������킽�������s�������Ă����B
�@�k���n�͋{�錧�����Ƃ����B�������k�x�V�B�u�����I��������Ȃ��́H�B���ꂶ��A�{�錧�͑S�ł���Ȃ��̂��H�v�B�N�����]����16�N�O�́u��_�W�H��k�Ёv���ׂĂ����B�O�͊������߁A�Ƃɂ��������ɖ߂낤�ƁA�����܂߉��l���̐l���������ɓ��ɓ������B�ƁA���̎��ɗ]�k������Ă����B�݂�ȋ}���Œ���ɋt�߂�B����������ƁA�K���X�˂��u�o�^�o�^�v�Ɖ��𗧂Ăėh��Ă���B����̑傫�Ȏ����h��Ă���B���̎��ɂȂ��Ă悤�₭�u�|���v�Ǝv���悤�ɂȂ����B���ɓ����ď㒅������Ă������̂����A�]�k���|���ĂȂ��Ȃ�����C�ɂȂ�Ȃ��̂ł���B
�@������s�����{���ɂ́A���܂���46�N�O��1965�N�Ɍ��Ă�ꂽ�B�q�b�\���ŁA�ϗp�N����50�N�B���ƂS�N�őϗp�N�����}����Ƃ����㕨�ł���B�������A���ϐk�\���ł��邽�߂ɁA�����̑ϐk������Ă��Ȃ��B�O�X����A�ϐk�f�f�̎��{�Ƒϐk�⋭�̕K�v��������Ă��������ł���B�h�ꂪ�P���Ă������ɁA�u���o�C�v�ƒN�����v�������Ƃł��낤�B���̓��̋c��͒��f�ƂȂ����B�s���E�������͂��ߎs�̐E���́A�s�������{�݂𒆐S�ɔ�Q�c���Ɍ�����������ł���B���A�c����ĊJ����C�ɂ��Ȃ�Ȃ������B
�@���̌�A���̓o�C�N�Ŋш�쒬��O�����𑖂����B�쒆�w�Z���k���搶�Ɉ�������ďW�c�ʼn��Z�B���w�Z�����͖h�Г��Ђ����Ԃ��āA�����ʼn��Z�B�S�z���ꂽ�|��Ɖ����Ȃ��A�܂��͈���S�ƂȂ����B�������A��ăe���r������ƁA�����ׂ����i����э���ł����B�N�����e���r�ɓB�t���ƂȂ��Ă������B
�@�n�k�̂��̎��A�J�~����͐E��̃r���̂W�K�Ō}�����B�u���ނ�H�킪�I�����яo���A�e���r���|��Ȃ��悤�ɉ������Ă����B�W�K�������̂ŁA���̂������h�ꂽ�v�B���w�R�N�̖��͒��w�Z�Ō}�����B�u�S�Z�W������̂ő̈�قɂ����B�̈�ق̓V�䂪���T���T��o���A�����Č������h��Ă����B�����̏Ɩ����傫���h��Ă����B�F�B�̂Ȃ��ɂ͋����Ă���q�������B���͗F�B�ƕ��������Ă����B�h�ꂪ���܂����̂ŋ����ɖ߂�����A�܂��h��Ă����B�搶���Z��ɋ}���ŏo��悤�ɂƂ������̂ŁA�݂�ȁA�Z��ɏo���v�B���Z�Q�N���̑��q�͉���ւ̏C�w���s���B�u���l�Ōg�ѓd�b�Ńj���[�X���݂Ă�����A�n�k�̂��Ƃ��o�Ă����B�Ôg������ƌ���ꂽ�̂ŁA���l�𗣂ꂽ�B�z�e���ł͂����ƁA�n�k�̖͗l�����Ă����v�B
�@���Y�}�̍T���ł́A�X�˂悤�q�c���̊��̏�̑啔���̏��ނ����ɗ����B�{�I�̏�ɒu���Ă����j���[�X�t�@�C�����������Ă����B����}�̕����ł́A�e���r���������đ�j�B�c���������ނ��U�������B����A�䂪�Ƃł́A��̏��ނ��{�I���痎���������x�ōςB
�@���̓��A�J�~����͋A���ƂȂ����B�����̖�A���ʂĂ��̌^�ŋA��B���q�����ꂩ�疳���A����B�J�~���A����R��12���́A�J�~����̒a�����ł������B�ꐶ�A�Y����Ȃ��a�����ƂȂ����B�@
�s�����Z����
�@�s�����Z�̓�����23���ɍs�Ȃ�ꂽ�B�i�C�����f���āA�O�N�ȏ�Ɏ����E���B�ƒ�̎���Ŏ����ɍs���Ȃ����k�́A�S�����i����킸�ɂ͂����Ȃ��B
�@�����c���ɂ��䂪�Ƃɂ��A���Z��������B�u�s���s�����Ă��B�b��������Ɓw�ق��Ăāx���āA���邳���v�Ɠ����c���B�䂪�ƂƓ������i�ł���B
�@�e���r�▟�������p���A���ȏ���Q�l��������p�ɕς�����͍̂����ɓ����Ă���B���܂�̐^�����ɁA�u���܂���Q�ĂĂ��E�E�E�E�v�Ƃ͂������Ɍ����Ȃ������B
�@�w�͂𑱂����҂݂̂����ւ̒i�K�ɂ�����̂́A�ǂ�Ȃ��Ƃł������B������s�̐V�N�x�\�Z�ɂ́A�V���ɂ̋@�\���ɂ��Ă̊�{�v������肷��u�s�������ψ���v�̗\�Z���v�コ�ꂽ�B�Q�N�S�J���O�̒��ڐ����^���́A���̒i�K�ւƎs�������Ă���B
�@���̕��݂�z���Ă����厲�̂P�l���A�s���]���ɒ��킷��B�����������悤�ɋl�߂Ă����������ɁA�傢�Ɏ^���������B�@
�i�u����Ԃ���v2011�N�Q��27���t����j
�s���̌�����ς����Z�����[��ᐧ��^��
�@�L���҂�11���A10,252�̏����́A�w�O���ɂ�_����t�s�������������A���ɂ̌��ݏꏊ����������s�������ψ�����������B����ł��s���́u�w�O���Ɂv��������邱�Ƃ����҂��Ă����Ǝv���B�������u�s���P���l�A���P�[�g�v�́u�ւ̖ڐՒn�v��62.6�����I���B�s���̎v�f�͂��낭�����ꋎ�����B
�@�Q�N�R�J���O�ɌJ��L����ꂽ�u�Z�����[��ᐧ��^���v�͍����A�s���̌�����傫���ς��悤�Ƃ��Ă���B�s���͓��\���o���ꂽ�ۂɁu���Ɍ��݊�����Q���T�疜�~�����Ȃ��v�Əq�ׁA���\�ɔw�������悤�Ƃ��Ă��邪�A�s���̔M�ӂ͏��Ɏp�����������ċ����Ȃ��ł��낤�B
�@��t�s��12�N�̊Ԃ����[�X���ɂ͌p������A�u�������������v�͂��Ȃ̂ɉw�O�J���͑��i���ꂽ�B���������������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�S���̎s���I���́u���Ɍ��݁v������邩�炾�B
�@���̖₢�ɐ^���ʂ��牞������̂́A�Q�N�R�J���O�ɉ^���̒��S��S�����҂����ł���B
�i�u����Ԃ���v2011�N�P��30���t����j
�s�������Ƃ̈ʒu
�@�i�C����̒������ŁA�s�������Ƃ̔N�Ԕ̔��z�́A1997�N����2007�N�܂ł�10�N�Ԃ�16������������ł���B�ǂ��ł���������悤�ɁA��N�R���ɂ͕���������w����ɑ�^���Ǝ{�݂��i�o�B������s�̒����ł��A���s�҂⎩�]�Ԃ̗��ꂪ����ĊJ�����ւƑ傫���ω��������Ƃ��L����Ă���B
�@���������x�́A�i�q�����������ˉ��̉w���߂ɁA���Ǝ{�݂�����Ƃ����B�������𗘗p�����l���A�w�\���Ŕ������ł���悤�ɂ���d�|���ł���B���̂悤�ȊX�Â�����A�B�X���X�ƌ��߂����ėǂ����̂��낤���B
�@�N�̐�����������A�N���X�}�X�\���O���X���𗬂��G�߂ɂȂ����B�������A�X�͂��������Ɋ��C�������Ȃ��B�Ζ��唄�o�����A�Ђ��������ڂɂ������Ă͂��Ȃ��B
�@���Ƃ̌��łƈ��������ɁA�������łւƓ����o���������t�B�n�揤�Ƃ����w�O�J����I��������t�s���B���N�͂ǂ�����I�T���o�ł���B
�i�u����Ԃ���v2010�N12��26���t����j
�����t
 �@�ҏ��Œɂ߂���ꂽ�X�̍g�t�͂ǂ�Ȃ��̂��ƋC�𝆂�ł������A�Ԃ≩�̐F�ʂ�����o�b�N�ɁA�X�S�̂������ȃf�b�T���Ɏd�グ�Ă���B���̍g�t���ӏH�ɓ���A��J���Ƃɗ����t�ƂȂ��ĐF�ʂ̏ꏊ��n�ʂւƈڂ��n�߂Ă���B �@�ҏ��Œɂ߂���ꂽ�X�̍g�t�͂ǂ�Ȃ��̂��ƋC�𝆂�ł������A�Ԃ≩�̐F�ʂ�����o�b�N�ɁA�X�S�̂������ȃf�b�T���Ɏd�グ�Ă���B���̍g�t���ӏH�ɓ���A��J���Ƃɗ����t�ƂȂ��ĐF�ʂ̏ꏊ��n�ʂւƈڂ��n�߂Ă���B
�@�����t�̋G�߂ɍ��킹��悤�ɁA�Ǔ��t�̎x�������}�����Ă���B�ٗp�₭�炵�ȂǍ����̊肢�ɑS���������A�����Ċt���̑������s��ہB�@���̎��ōςނ悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�����͎����}�ƕς��ʂ��܂̐����ɁA�m�[�������Ă���̂ł���B
�@�}����~�͌������Ƃ����B��w���̏A�E���藦�͂U����A���Z���͂S���O��B�Ȃ̂ɑ��Ƃ́A���X�g���E�������A���������߂ŁA200���~�ȏ���̂����ߍ���ł���B�t�𑁂��}���邽�߂ɂ��A���ߍ������������ɊҌ������鐭�����K�v���B
�@���N�����ƂЂƌ��B�ُ�C�ۂ��Â������������t�ƂƂ��ɃS�~���̒��ցB���ƂɃ��m�������鐭�������A���߂���B
�i�u����Ԃ���v2010�N11��28���t����j
�ӏH�E�E�E
�@�u�����������ފ݂܂Łv�ƋL���ĂP�J���B�C����10�x������A�܂�ŔӏH�̂悤�B�����߂����S��17���ɐႪ�~��A�V�����{����Q�J���]�͖҉Ă̗��B�u����₩�ȏH�v�����������ǂ������c��Ȃ��܂܂ɁA�k���ɐk������X���}�����B
�@�C��Ɠ������A�����̐��E�����芴�������Ȃ��B�����̊��҂��ēo�ꂵ������}�����́A�ٗp���������҈�Â���Ǝ҂⍑���̂��炵���A�܂�������������܂��B�O����������ނ��鎖�Ԃ���������B��Ƃ��猣�����A�A�����J�̊�F���茩�鐭���ł́A�����}����ƕς����̂ł͂Ȃ��B
�@���̂�����⍑���̕�炵�������ɗǂ����Ă����̂��A���̓�����N�������߂Ă���B
���}��������88�N�B�u���邱�ƂȂ���т��������f�������鐭�}�������A���̓������o����B�S�N�Ԃ�ɊJ�����u�Ԋ��܂�v�́A��D�̋@��ł���B
�i�u����Ԃ���v2010�N10��31���t���j
�O��̋�Y
 �@�u�O��v�B�o�q���[�t���b�g�ɂ́u��������180�q�B�n���̑�����S�g�Ŋ���������̃X�|�b�g�v�ƋL����Ă���B�����̒|�ŎV������q�D�łU����30���A�H�c��`����50�l����s�@��45���ŁA�ɓ������́u�����̃X�|�b�g�v�ɓ�������B �@�u�O��v�B�o�q���[�t���b�g�ɂ́u��������180�q�B�n���̑�����S�g�Ŋ���������̃X�|�b�g�v�ƋL����Ă���B�����̒|�ŎV������q�D�łU����30���A�H�c��`����50�l����s�@��45���ŁA�ɓ������́u�����̃X�|�b�g�v�ɓ�������B
�@�u�O��v�͓������ɓ������́u�哇�v�ƕ���ŁA�ΎR�̓��ł��̖���S���ɍ��������B���߂ł�10�N�O��2000�N�V���`�W���̗Y�R�R������̕��A���̑O��1983�N�̈��Òn��ł̕��A����21�N�O��1962�N�ɂ͒ؓc�n��ŕ����Ă���B�܂�A�����I�ɕ��������Ă���̂��u�O��v�ł���B
 �@10��20��(��)�̖�A������s�s�c��̑�\�V���Ƌc����ǐE���Q���̌v�X���́A�|�ŎV�����瓌�C�D�D�ɏ�D���ĎO��ɏo�������B������s�ƎO��͗F�D�����������Ă���A�s�c���̑�\�N�A�F�D�g�ߒc�Ƃ��đ����Ă���̂ł���B���{���Y�}�s�c�c����͎����Q�������B �@10��20��(��)�̖�A������s�s�c��̑�\�V���Ƌc����ǐE���Q���̌v�X���́A�|�ŎV�����瓌�C�D�D�ɏ�D���ĎO��ɏo�������B������s�ƎO��͗F�D�����������Ă���A�s�c���̑�\�N�A�F�D�g�ߒc�Ƃ��đ����Ă���̂ł���B���{���Y�}�s�c�c����͎����Q�������B
�@�O��̎����ɂ��ƁA������52�N�O��1958�N�����́A�l����7,121�l�������A���N�S���P�����_�ł�2,822�l�ɂ܂Ō����B���������ѐ���1958�N��1,775���тɑ��āA���N�S�����_�ł�1,716���тƁA�傫�ȕω��͌����Ȃ��B���̂��H�B���̂��Ƃ��O��c��̕��X�Ɏ��₵���Ƃ���A�ȉ��̓������Ԃ��Ă����B�u��҂͓��O�ɏo�čs���A�c���Ă��鑽���́A����҂����̐��сB���ѐ�������Ȃɕς��Ȃ��̂́A���O����P�g�œ]�����Ă���l�����邽�߁v�B2008�N�x�A�O��͏o����20�l�A���S��47�l�B���O����̓]����142�l�A�]�o��184�l�ƂȂ��Ă���B���̐��������邾���ł��A�N�X�A�l�����������Ă����͎̂�ɂƂ�悤�ɂ킩��B
 �@�Ƃ���Łu�]���v�Ƃ͂ǂ��������̂Ȃ̂��H�B����ɑ��Ă̓����́u������x�@�A���h���̐E���ȂǁA���O���畋�C���Ă���l���������S�B2000�N�̕��ΈȑO�͉Ƒ��A��ŕ��C���Ă������A���Ό�͒P�g���C���F�߂���悤�ɂȂ�A���ѐ��Ƃ��Ă̓J�E���g�ł��Ă��A�l���͒P�g�Ƃ������́v�B�Ȃ�قǁA���̐l���\��������ƁA�����̃s���~�b�h��70�Α�㔼�ɑ傫�ȎR������̂ɑ��āA�j���ł�50�Α�㔼�ɎR���}���Ă���B�����āA�j���̕�����������200�l�]�A�l���������Ȃ��Ă���B�܂�A�j���̒P�g���C�������Ƃ������Ƃł���B �@�Ƃ���Łu�]���v�Ƃ͂ǂ��������̂Ȃ̂��H�B����ɑ��Ă̓����́u������x�@�A���h���̐E���ȂǁA���O���畋�C���Ă���l���������S�B2000�N�̕��ΈȑO�͉Ƒ��A��ŕ��C���Ă������A���Ό�͒P�g���C���F�߂���悤�ɂȂ�A���ѐ��Ƃ��Ă̓J�E���g�ł��Ă��A�l���͒P�g�Ƃ������́v�B�Ȃ�قǁA���̐l���\��������ƁA�����̃s���~�b�h��70�Α�㔼�ɑ傫�ȎR������̂ɑ��āA�j���ł�50�Α�㔼�ɎR���}���Ă���B�����āA�j���̕�����������200�l�]�A�l���������Ȃ��Ă���B�܂�A�j���̒P�g���C�������Ƃ������Ƃł���B
�@�u�O��v�́A�u���ƂƔ_�Ƃ̓��v�Ƃ����C���[�W�������Ă����B���������ۂɂ́A��P���Y�Ƃ͂ق�̂킸���ŁA�����ƂȂǂ̑�Q���Y�Ƃ�20�����x�A���Ƃ̂V���]�͊ό��≵�E�����ƂȂǂ𒆐S�Ƃ�����R���Y�ƂŐ�߂��Ă���B�ό������C���ɓ��̌o�ς͐��藧���Ă���̂ł���B�������A�u���Ǝ҂̍���E��p�ҕs�����ɂƂ��Ȃ����h���̏h���{�݂̔����Ȃǂɂ�����̐��̖�肪����v�ƎO��̎����ł͏q�ׂ��A��x�Ɋό��q���吨�����Ă��A�Ή��ł���ɂ͂Ȃ����Ƃ��L����Ă���B
 �@�O��͌��݁A���̓������̒ؓc�n�悪���Z�x�ΎR�K�X�̂��߂ɗ����֎~���ƂȂ��Ă���B���C�D�D���牺�D����ۂɉ�X�̎茳�ɂ̓K�X�}�X�N���z��ꂽ�B���ɓ���ۂɂ́A�K�X�}�X�N�̌g�т��v�������̂ł���B���������ۂɂ́u���p���邱�ƂȂǂȂ��v�Ƃ����̂����̐l�X�̐����ł���B���̂Ȃ�u���Z�x�K�X������������A���̏ꏊ���炷���ɔ��邩��v�B�}�C�N���o�X�œ������ē����Ă������������A�o��l�����i����҂���j�͒N���A�K�X�}�X�N�炵�����̂������Ă͂��Ȃ������B���ӂ��邱�Ƃ͕K�v�ł͂��邪�A�u�K�X�}�X�N�̌g�сv�Ȃǂ��L�ꂽ�肷��̂́A�ό��Ő����Ă��铇�ɂ����ẮA�ǂ�Ȃ��̂��Ǝv���Ƃ���ł���B �@�O��͌��݁A���̓������̒ؓc�n�悪���Z�x�ΎR�K�X�̂��߂ɗ����֎~���ƂȂ��Ă���B���C�D�D���牺�D����ۂɉ�X�̎茳�ɂ̓K�X�}�X�N���z��ꂽ�B���ɓ���ۂɂ́A�K�X�}�X�N�̌g�т��v�������̂ł���B���������ۂɂ́u���p���邱�ƂȂǂȂ��v�Ƃ����̂����̐l�X�̐����ł���B���̂Ȃ�u���Z�x�K�X������������A���̏ꏊ���炷���ɔ��邩��v�B�}�C�N���o�X�œ������ē����Ă������������A�o��l�����i����҂���j�͒N���A�K�X�}�X�N�炵�����̂������Ă͂��Ȃ������B���ӂ��邱�Ƃ͕K�v�ł͂��邪�A�u�K�X�}�X�N�̌g�сv�Ȃǂ��L�ꂽ�肷��̂́A�ό��Ő����Ă��铇�ɂ����ẮA�ǂ�Ȃ��̂��Ǝv���Ƃ���ł���B
 �@�O��͍���łS��ڂ̖K��ɂȂ�B�O��͂S�N�O�B����Ɠ������s�c��̈���Ƃ��āA���Ό�̕����̗l�q�����ɗ��Ă���B���̑O�͕��ΑO�ŁA������s�c��̈���Ƃ��āA�O��̔_�ƍՂ̎��ɖK��B���̑O�̍ŏ��̎��́A���Ԃ����ƃv���C�x�[�g�ŗ��Ă���B����͏��J�܂���̎c�O�ȓV��ł��������A�ߋ��R��͓V��Ɍb�܂�A�O��̎��R�𑶕��ɖ��키���Ƃ��ł����B�������Ԃ����u�A�J�R�b�R�v���ώ@�ł���u�A�J�R�b�R�فv��O��ɌÂ�����Z��ł����l�X�̔��@����W�������u���y�����فv�ɓ���A�V�C���ǂ��Ƃ���1983�N�̕��ŏ��ł����u�V�Y�r�Ձv���ォ�璭�߁A���Ό��Ղ��r�Ɖ������u�A�J�R�b�R�فv�߂��́u��H�r�v�̐��ʋ߂��܂ōs���B�����͂��܂Ȃ��K�X�𐁂��グ��Y�R�̎R���ɎԂœ���A�n���K�X�Ō͂�͂Ă��R�����������Ɍ��Ȃ���A����̓W�]��܂ŎԂő���B�������A���Ό��ɂ͋߂Â��Ȃ����A�Y�R�͊댯���Ȃ̂ŁA��������̋����K�v�ɂȂ�B��������Ȃ�������A���̂Ƃ��͊C�ӂ̊�Ɉ͂܂ꂽ���R�̊C���v�[���ƂȂ��Ă���u�����Y�r�v�ɉ���Ă����A�j���ł��鋛�̊ώ@���s�Ȃ����B�[�������ގ��Ԃɍ��킹�Ĉ��Òn��̉���u�ӂ邳�Ƃ̓��v�ɓ���A�������ɒ��ޗ[�������\����E�E�E�B�h�̐H���͂������A�C�̍K�A�R�̍K�A�����āu�������t�̓V�Ղ�v�ł���B�O��̏Ē��ŐS���̂��ق����āA�Â��ȓ��̖��������䂭�܂Ŋy���ނׂ��B�������g�ѓd�b�̓I�t�ɂ���B�ꏊ�ɂ���Ắu���O�v�ɂ����Ȃ��Ă����B�d���̔���X�g���X�����₷�ɂ́A�����Ă����̏ꏊ�ł���B �@�O��͍���łS��ڂ̖K��ɂȂ�B�O��͂S�N�O�B����Ɠ������s�c��̈���Ƃ��āA���Ό�̕����̗l�q�����ɗ��Ă���B���̑O�͕��ΑO�ŁA������s�c��̈���Ƃ��āA�O��̔_�ƍՂ̎��ɖK��B���̑O�̍ŏ��̎��́A���Ԃ����ƃv���C�x�[�g�ŗ��Ă���B����͏��J�܂���̎c�O�ȓV��ł��������A�ߋ��R��͓V��Ɍb�܂�A�O��̎��R�𑶕��ɖ��키���Ƃ��ł����B�������Ԃ����u�A�J�R�b�R�v���ώ@�ł���u�A�J�R�b�R�فv��O��ɌÂ�����Z��ł����l�X�̔��@����W�������u���y�����فv�ɓ���A�V�C���ǂ��Ƃ���1983�N�̕��ŏ��ł����u�V�Y�r�Ձv���ォ�璭�߁A���Ό��Ղ��r�Ɖ������u�A�J�R�b�R�فv�߂��́u��H�r�v�̐��ʋ߂��܂ōs���B�����͂��܂Ȃ��K�X�𐁂��グ��Y�R�̎R���ɎԂœ���A�n���K�X�Ō͂�͂Ă��R�����������Ɍ��Ȃ���A����̓W�]��܂ŎԂő���B�������A���Ό��ɂ͋߂Â��Ȃ����A�Y�R�͊댯���Ȃ̂ŁA��������̋����K�v�ɂȂ�B��������Ȃ�������A���̂Ƃ��͊C�ӂ̊�Ɉ͂܂ꂽ���R�̊C���v�[���ƂȂ��Ă���u�����Y�r�v�ɉ���Ă����A�j���ł��鋛�̊ώ@���s�Ȃ����B�[�������ގ��Ԃɍ��킹�Ĉ��Òn��̉���u�ӂ邳�Ƃ̓��v�ɓ���A�������ɒ��ޗ[�������\����E�E�E�B�h�̐H���͂������A�C�̍K�A�R�̍K�A�����āu�������t�̓V�Ղ�v�ł���B�O��̏Ē��ŐS���̂��ق����āA�Â��ȓ��̖��������䂭�܂Ŋy���ނׂ��B�������g�ѓd�b�̓I�t�ɂ���B�ꏊ�ɂ���Ắu���O�v�ɂ����Ȃ��Ă����B�d���̔���X�g���X�����₷�ɂ́A�����Ă����̏ꏊ�ł���B
 �@���R�����ς��̎O��ł͂����Ă��A�ΎR�̔����E�S�����́A���̌�̓����ɏd���ׂ�w���킹�邱�ƂƂȂ����B����͑��ɁA���Ȃ������ΎR�K�X�ɂ��e���ł���B�ό��Ő����铇�ɂ����āA�ΎR�K�X�͊ό��œ��ɏo�����Ă݂悤�Ƃ����l�X�̑����~�߂�������ʂ����Ă��܂��Ă���B�O��ɂ͎O���`������B�H�c����S���P���P�����Ŕ���Ă���B�Ƃ��낪�ΎR�K�X�ɂ���āA�����Ό��q�ƂȂ�B���������u�H�c��`����̏o���̂��߁A�l�������烂�m���[���𗘗p���ĉH�c�܂ōs���B�Ƃ��낪�g���q�h�ƂȂ�����A�����܂ł̌�ʔ�܂�܂�Ӗ����Ȃ��Ȃ��Ȃ�B�Ƒ��ŗ��悤���̂Ȃ�A�Г������ł��Q�`�R��~�̏o��ƂȂ�B�Ȃ̂Ɂg���q�h�ł͘b�ɂȂ�Ȃ��B������ɔ�s�@���p����D���p�ւƈӎ��͕ς��B�������D�ł͗h����ɁA�V���ԋ߂����������Ă��܂��B������A�ό��q�͂Ȃ��Ȃ������Ȃ��v�Ƃ����̂ł���B����A�h�̑����A�u��s�@�ŗ��邨�q�v�̏ꍇ�́A�Ȃ��Β��߂�Ƃ����B��s�@�����q�ɂȂ�A���q�͗���Ȃ����炾�B��s�@�̔�ԗ��͂R�����Ƃ����B�僊�[�O�̏���G���Ȃ݂̊m���ł���B�O���`�́A���Z�x�̉ΎR�K�X����������ؓc�n��Ɉʒu����B�u���̊ό��̍ő�̏�Q�́A�ΎR�K�X�v�Ȃ̂ł���B �@���R�����ς��̎O��ł͂����Ă��A�ΎR�̔����E�S�����́A���̌�̓����ɏd���ׂ�w���킹�邱�ƂƂȂ����B����͑��ɁA���Ȃ������ΎR�K�X�ɂ��e���ł���B�ό��Ő����铇�ɂ����āA�ΎR�K�X�͊ό��œ��ɏo�����Ă݂悤�Ƃ����l�X�̑����~�߂�������ʂ����Ă��܂��Ă���B�O��ɂ͎O���`������B�H�c����S���P���P�����Ŕ���Ă���B�Ƃ��낪�ΎR�K�X�ɂ���āA�����Ό��q�ƂȂ�B���������u�H�c��`����̏o���̂��߁A�l�������烂�m���[���𗘗p���ĉH�c�܂ōs���B�Ƃ��낪�g���q�h�ƂȂ�����A�����܂ł̌�ʔ�܂�܂�Ӗ����Ȃ��Ȃ��Ȃ�B�Ƒ��ŗ��悤���̂Ȃ�A�Г������ł��Q�`�R��~�̏o��ƂȂ�B�Ȃ̂Ɂg���q�h�ł͘b�ɂȂ�Ȃ��B������ɔ�s�@���p����D���p�ւƈӎ��͕ς��B�������D�ł͗h����ɁA�V���ԋ߂����������Ă��܂��B������A�ό��q�͂Ȃ��Ȃ������Ȃ��v�Ƃ����̂ł���B����A�h�̑����A�u��s�@�ŗ��邨�q�v�̏ꍇ�́A�Ȃ��Β��߂�Ƃ����B��s�@�����q�ɂȂ�A���q�͗���Ȃ����炾�B��s�@�̔�ԗ��͂R�����Ƃ����B�僊�[�O�̏���G���Ȃ݂̊m���ł���B�O���`�́A���Z�x�̉ΎR�K�X����������ؓc�n��Ɉʒu����B�u���̊ό��̍ő�̏�Q�́A�ΎR�K�X�v�Ȃ̂ł���B
�@����������ȏ�ɐ[���Ȃ̂́A�����I�ɕ����J��Ԃ��O����̂��̂ł���B���̂��Ƃc��c���̕��X�͎��ɐX�Ƒi����B�u�Z���̑����͔��������A���������̐��������Ă���B�C�݂ɍs�������ނ��B��T�Ԃ̂����ɂقƂ�ǂ������g�����Ƃ��Ȃ��B������A�N�������ł��[���ɕ�点��B�������A20�N�����̕��ɔ����Ă̒��~��]�V�Ȃ������B������A���͂���ȂɎg���킯�ɂ͂����Ȃ��B��ςȂ͉̂Ƒ���������l�����B��������T�����[�}���ȊO�͎������s����Ȃ����߁A�Ƒ���{���Ȃ��B���̂��߁A���𗣂ꂴ��Ȃ��B����ɁA�K�X�̂��߁A�Ƃ��Ԃ������ɏ��ށB�K�\�����̓��b�^�[������200�~������v�u�����̈��萫���Ȃ��A����20�N�����ŋN����̂ŁA�Ƃ�ݔ��ւ̓������ł��Ȃ��B���̂��тɏZ���͗��o���Ă����v���������B���ɂ́A�ۈ牀�����E���w�Z���O��Z������B����ǂ���w��A�E�ƂȂ�Ɠ��O�֏o��ق��͂Ȃ��B������𗝗R�ɂ����Ƒ��ł̗�����A���O�ɏo�Ă���q�ǂ��������e���Ăъ�P�[�X�������A���̐l���͌����Ă�������ł���B�u���̓^�_�Ŏ����B�Ă���Ƃ͂�����ł�����B�������v�Ƒi����ނ�̊�ɂ́A��̌����Ȃ��ł肪�ɂ��ݏo�Ă���B11���U���E�V���ɂ͎O��Ńo�C�N���[�h���[�X���s�Ȃ���B�ό��q���ĂяW�߂�C�x���g��ے肷����̂ł͂Ȃ����A�x���̂���������{�I�Ɍ��߂Ȃ����K�v������̂ł͂Ȃ����낤���B�������A������Ƃ����Ď��ɗLjĂ�����킯�ł͂Ȃ��B���߂Ă��̎v���ŁA�O��̂o�q���s�Ȃ����炢�����Ȃ��̂ł���B�@���ʐ^�͍���B�e�������̂ƂS�N�O�̂��̂��g�p
�H���}����
�@�u�����������ފ݂܂Łv�Ƃ͂悭���������́B�u�����H�v�u�c���H�v�ƁA�X�����{�ł������C��ɂȂ�ƕ\������悢�̂������Ă������X������A�悤�₭�u�H�v�Ƌ^�����ƂȂ�������z�C�ƂȂ��Ă����B
�@�L�^�Â��߂̉Ẳe���Ŗ��ʕ��̉��i���͂˂�����A������ǂ��납������C���̎�����O�ɁA�l�D�����āA�L�т�����������Ђ����߂�p���A�����炱����Ō�����B�������̒ቺ�������邵�������A���̂P�l�ł���B
�@����}�̊ǎ́A���Ƃ̖@�l�ň��������̌����������߂Ă���B�����́H�̖₢�ɁA�u����ő��Łv���܂����땂��B�C��ɉe�������ʕ������A���x�͏���ő��łʼn��i���肠���鎞������Ă���̂��낤���B
�@�����̉Ă͋��������A��炵�����M�������͋���킯�ɂ����Ȃ��B�u�����⋋���\���Ɂv�̕ɗ�܂���A�A�̏o����̂��������ł������A�x���g���������߂āA�O�֑O�ւƓ��ݏo�����B
�i�u����Ԃ���v2010�N�X��26���t���j
�҉Ă̖h�ЌP��
 �@87�N�O�̂X���P���́u�_�ɕ����������������v�ƋL����Ă���B���N�̂X���P���́A�L�^�I�Ȗҏ��̘A���̂Ȃ��Ō}�����B �@87�N�O�̂X���P���́u�_�ɕ����������������v�ƋL����Ă���B���N�̂X���P���́A�L�^�I�Ȗҏ��̘A���̂Ȃ��Ō}�����B
�@���̖h�Ђ̓���O�ɏ�����s�́A�W��29���̌ߑO�A�����w�Z�Z��ő����h�ЌP�������{�B�u���������Ȃ��悤�Ɂv�̃A�i�E���X�̂Ȃ����A�����̎Q���҂�35�x�̉��V���Ŋ��𗬂����B
�@�P���ł́A����h�Бg�D����h�c����ĕ��������{�B�u�����ɕ�����������A����ɂ��ĉ�X�̕��ɕ������Ăق����v�̐���u�C�U�I�Ƃ������ɐ��͏o��̂��v�Ȃǂ̋^��������ꂽ�B
�@����Ƃł������ł��A���͌������Ȃ��B������������s���̏��ΐ��⋋���ǂ́A�k�x�T�ɑς�����̂݁B���ݐ����^�ԋ����Ԃ����L�͂P��B�̐S�̎搅�n�ł������A�s���ɂ͂P�J���������݂��Ȃ��B���z�ƌ����Ƃ̊Ԃɂ́A�܂��܂��傫�Ș���������B
�@�w�O�Ƀn�R���m������ȑO�ɁA���N���Ă����������Ȃ���n�k�ɔ������܂��Â��肱���A�܂����Ȃ��ł��낤�B
�i�u����Ԃ���v2010�N�X���T���t���j
������s�̐}����
�@�u���ł��A�ǂ��ł��A����ł��C�y�ɗ��p�ł���s���̏��ւł��葱����v���Ƃ��u�s���}���ق̊�{���j�v�Ɍf���钲�z�s�́A�{�قƕ��ق��킹��10�ق̐}���ق��^�c���Ă���B���K�E����60�l�A���Ώ����E�����܂߂��210�l�]�̐E����z�u���A�s���̂��� �̒n��̏�_�̊����������߂Ă���B
�@����A������s�͖{�قƕ��فE�}�������킹�ĂS�ق̂݁B�E���̐����A���K�E���Ɣ��Ώ����E�����킹�āA�킸����39�l�B�u�s���̏��ցv����́A�قlj����ƂȂ��Ă���B
�@������s�́A2014�N�S���J�ٗ\��ŁA�ш�k���n��Z���^�[�\�z�ɓ����Ă��邪�A�{�݂��܂邲�ƈϑ����A�}���ِE��������ɍ팸��������B�ϋɓI�Ȑ}���ي�����W�J���邽�߂Ɂu�s���c�v��I���������z�s�̎p���Ƃ́A�_�D�̍��ł���B
�@�ҏ��̉āB�}���قɑ����^�сA���y�̗��j�╶���ɐG��āA�g���S���[�������Ă��߂��������B�Ă͍����^������B
�i�u����Ԃ���v2010�N�W���P���t����j
�Q�c�@�I������
�@���̐��x�͌������������悢�Ǝv���B�Q�c�@�I������̓��[���@�̂��Ƃł���B�������̂Ƃ���A�Q�@����̓��I�҂́A���̐��}�ɓ��[���ꂽ�[�ƁA���̐��}�̔���o�ږ���ɋL�ڂ��ꂽ���҂ɓ��[���ꂽ�[�̍��v�Ől�������܂�B���������I���ʂ́A���̐��}�̔���o�ږ���̂Ȃ��̌��Җ��œ��[���ꂽ�[���������ƂȂ��Ă���B���̐��x�����邽�߂ɁA�J�[���ɏW�܂����J�[��ƈ��ƊJ�[����l�͔ߎS�Ȏ��Ԃ��߂������ƂƂȂ����B
�@�V��11��(��)���J�[�̎Q�@�I�̔���ɂ�12�̐��}�����҂�i�������B���Ȃ��Ă��T�l�A�������}�ł�45�l���̌��҂𖼕�ɓo�ڂ��Ă���A����̌��Җ��͑S����186�l�ɂ������ł���B�J�[��Ƃ�11��(��)�̌ߌ�X������n�܂����B������������s�̑I���Ǘ��ψ���͓����I����̊J�[��Ƃ�D�悵�Ă����߂����߁A�I����̊J�[�͕���Ă��A����͕���Ȃ����Ԃ��������B���̂��߁A�J�[����l�͊J�[�����������Ď��g�̐��}�̕[�̏o���ڂŊm���߂邵���Ȃ��ɒu���ꂽ�B
�@�����āA���}���̂ق��Ɍl���̕[������Ƃ�����ւ��J�[��ƈ����ꂵ�߂��B�O�q�����悤�ɑS����186�l������̖���ɓo�ڂ���Ă���B�[�̗p���ɋL�ڂ��ꂽ�������ǂ̐��}�ɑ����Ă���̂��A�͂��܂��A���̎����͖���ɓo�ڂ���Ă���̂��ȂǁA��ƈ���186�l�̎����������ꂽ�W�v���Ƃɂ�߂��������Ȃ���A�l���̕[���d�������A�������Ă����̂ł���B����͂܂�Ő_�o����Q�[����z�N��������̂ł������B
�@�����������Ă��������ɁA�����I����̊J�[���I�����A�J�[��ƈ�������̊J�[�ɕK�v�Ȑl�����c���āA�J�[������Ƃɂ���B�܂��A�����I����̊J�[����l���u�������ɂˁ`�v�Ƃ����Ȃ���A����̊J�[����l�̑A�]�̂܂Ȃ�����K�ڂɗ�������A�Â܂�Ԃ����J�[��ɂ͂������邵����C�����ꂽ�B
�@�����猩����O�̌i�F�ɔ��F���f���o����Ă���B�邪�����n�߂��悤���B�M���R�[�q�[�ł��������ƁA�����̔��@�̑O�ŏ��K��p�ӂ����B�������₽�����ݕ�����ŁA���������ݕ��͂��������Ȃ��B�ȑO�͗p�ӂ���Ă����J�[����l�p�̉������������A���x�̑I���Ǘ��ψ�����ǂ́u�o��ߌ��v�Ƃł��v���Ă���̂��A�p�ӂ���Ă��Ȃ��B�u�C�������Ȃ��I���Ǘ��ψ���v�ƃu�c�u�c�����Ȃ���A�V�[�V�[�������̃{�^�����������B
�@�u��ς����ꂳ�܂ł����v�Ƃ̑I���Ǘ��ψ����̒��߂̂������ŕ��ƂƂȂ����̂́A�ߑO�S��43���B�����т����Ȃ���ԂʼnƂɒ������̂͌ߑO�T���߂��B���Ԃ̌˂��J���Ƌ��������ƂɁA���q���e���r�����Ă����B���[���h�T�b�J�[���Ƃ����B�u�����͊w�Z����I�v�Ƃ����Ȃ玶��Ƃ�����A���錳�C���Ȃ��z�c�ɂ����肱�B�ׂł̓J�~����̃C�r�L���苿���B
�@������s�̊J�[�����͑��̎����̂Ɣ�ׂāA�����ɒx�����Ƃ��킩�����B���̗��R��I���Ǘ��ψ�����ǒ��́u�ǎ�@�̂P��ɁA�ǂݎ��X�s�[�h�̒��q���������̂����������ƁB�܂��A�ǎ�@�S��Ƃ��ɁA�[�v�Z�̃o�[�R�[�h�̓ǂݎ��ɕs�������A���̂��߁A�[�v�Z�����Ƃ��邱�ƂɂȂ������߁v�Əq�ׂĂ���i�V��16���̍s�������v�������ʈψ���ł̓��فj�B������s�́A����̊J�[�����́u�ߑO�Q���v��ڕW�ɂ��Ă����Ƃ����B������ɂ��Ă��A����Ɍl�����[�����A�l�������}�ɓ��[�����ƌ��Ȃ��A�������l���̑������ɓ��I���Ă����Ƃ������x�ɂ��Ă��邱�Ƃ��A�J�[��Ƃ�ώG�ɂ��Ă���̂ł���B���̐��x���������ꂽ���Ƃ���A�^�����g�𑽐��A���҂ɋN�p���鎖�ԂƂȂ��Ă��邱�Ƃ��A����܂��^��̂Ȃ��Ƃ���ł���B
�@�V��16���̈ψ���őI���Ǘ��ψ�����ǒ������ق����A�ߗ����̂̊J�[�m�莞�ԓ��͈ȉ��̂Ƃ���ł���B�Ȃ��A�o�c�e�t�@�C���Łu2010�N�Q�@�I���E����\�̓��[���ʁv���f�ڂ��܂��̂ŁA���Q�Ƃ��������B
|
�I���� |
���� |
�J�[��Ɛl�� |
�ǎ敪�ދ@ |
| ������s |
1�F50
|
4�F15
|
216�l
|
�S��
|
| ������s |
0�F30
|
2�F25
|
286�l
|
�U��
|
| �O��s |
0�F55
|
2�F20
|
267�l
|
�S��
|
| �������s |
0�F18
|
1�F05
|
237�l
|
�V��
|
| �����s |
0�F20
|
3�F25
|
126�l
|
�R��
|
| �������s |
1�F09
|
2�F45
|
317�l
|
�U��
|
�[���ł��Ȃ�
�@�[���ł��Ȃ��B�告�o�̓q�����ŁA�q����K�Ƃ̐e���Ƌ��������ɔ��W������ւ������܂��͉��ق���͓̂��R�B�������A�q���Ɋ֗^��������ȊO�̗͎m�͖��É��ꏊ�x��A�e���ƁA�����Ƃ̒�����̏��R�͋ސT�ŁA�u���É��ꏊ�͗\��ǂ���J�Áv�Ƃ����̂��D�ɗ����Ȃ��B
�@�����̐��E���[���ł��Ȃ��B�����Y����r��������u�����ƃJ�l�v�͂���ނ�ɂ���A���V�Ԋ�n�̌���ᔽ�����̂܂܁B�����ď���ő��łł́u�����̂��߁v�Ƃ����Ȃ���A�o�c�A�̗v���ɉ����āA���Ƃ̖@�l�Ō��ł̌����߂ɏ[�Ă�B
�@�告�o�́u���Z�v�B�����́u���̊�v�ł���B�����̋^��ɉ������ɂ��̏�����߂����A���������������ł́A�告�o�ɂ������ɂ��A�����͔w��������ł��낤�B
�@�������A����ő��łɂ͔w��������킯�ɂ͍s���Ȃ��B���N�x���ɖ@�Ă𐬗������A�Q�`�R�N��ɂ͐ŗ������グ���s�Ȃ��Ƃ����̂�����B
�i�u����Ԃ���v2010�N�V���S���t���j
����̕ČR��n
�@���{�ŗB��n��킪����������́A�����̂S�l�ɂP�l�����𗎂Ƃ��Ă���B1945�N�U�����A�퓬���悤�₭�I���B�R�⓴�A����߂��Ă����������ڂ̓�����ɂ����̂́A�_�n��S��Ԃň͂݁A��n���݂������߂�ĕ��̎p�ł������B
�@�Ȍ�65�N�B�U�ɂȂ鏗�̎q����������E���ꂽ�u�R���q������v(1955�N)�B���K����ɂ��鎩���̐��c�̗l�q�����ɍs�����������A��ɗ��Ă����ĕ��Ɂu�C�m�V�V�ƊԈႦ���v�Ǝ��ߋ����ŎˎE���ꂽ����(1959�N)�B�M���ʼn��f������n���Ă������w�����A�u���z�̌����܂Ԃ����ĐM���������Ȃ������v�Ƃ̗��R�Ńg���b�N�ɂЂ��������ꂽ�u����N�����v(1963�N)�F�F�B�ĕ��ɂ��ƍ߂����X�Ƒ����Ă���B
�@���̉���̕ČR��n���A����}�����̓^���C����Ƃ����B��n������钬�͂��Ɖ��\�N�A�ĕ��ƍ߂ɋꂵ�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��낤���B
�@�ʐς�20����ČR��n�ɒD��ꂽ����͍���23���A�{��̒��ŏI��L�O�����}����B
�i�u����Ԃ���v2010�N�U���U���t���j
�y�ւ̎v��
 �@���e�̎O����́A�V���f����S�[���f���E�B�[�N�̑O���ɍs�Ȃ�ꂽ�B���̎����ɋA�Ȃ���̂�15�N�Ԃ�B����ł͂��̎����ɓc�A�����s�Ȃ���B �@���e�̎O����́A�V���f����S�[���f���E�B�[�N�̑O���ɍs�Ȃ�ꂽ�B���̎����ɋA�Ȃ���̂�15�N�Ԃ�B����ł͂��̎����ɓc�A�����s�Ȃ���B
�@�@�v�̍��Ԃ��ʂ��āA���Ƃ̖ʁX�ƃc�c�W�����ɏo���������A���N�͓~�������������Ƃ���A�c�c�W�͂���ق�B����ǂ������Ȃ�̗z�C�ɗU��ꂽ�����̐l�X���A�����Ƀh�b�ƌJ��o���Ă����B
�@�c�A�����n�܂������c�̂������𑖂�ԓ��ł́A�䂪�Ƃ���삩�����Ђ������Ƃւ̂��Ƃ肪���킳��Ă����B�����s�Ȃ������R�������������オ�肾�Ƃ��A���c�̊Ǘ��͂Ȃ��Ȃ���ς��Ƃ��E�E�E�E�B��X�����Ă������e�̎������ɍs�Ȃ�Ȃ��Ȃ������Ƃւ́A������߂�����\����Ȃ����A������܂��ɂȂ��Č���Ă���B�ނ�̓y�ɑ���v�����A�_�Ԍ����C�������B
�@���{�̐H�Ǝ�������39���ɂ܂ŗ�������ł���B�y�ɂ܂݂�ĕ�炷�l�X���Ί�ŕ�点�鍑�Â����S���狁�ށB
�i2010�N�T���X���t�u����Ԃ���v���j
�����J�̓��w��
 |
|
�U���̑�l���w�Z���w��
|
�@�g���������芦��������Ƌɒ[�ȋC��̓������̂Ȃ��ŁA��N�Ȃ�R�����{�̑��Ǝ�������ɍ炫�n�߂�����A���N�͏o�@����������A�S���̓��w���O��ɂ��傤�ǖ��J���}���邱�ƂƂȂ����B
�@������s�ł����w�Z���U���ɁA���w�Z�ł͂V���ɓ��w�����s�Ȃ��A�����������ł̐��ꕑ��ƂȂ����B
�@�i�C����̂Ȃ��A���Z�Ɍ��炸�����w�Z�ɂ����Ă��A�����̊w�Z��I������ƒ낪�����Ă���Ƃ����B�s���쒆�w�Z�̓��w���ł́A150���̐V�P�N�����}�������A�ߔN�ł͍ō��̐l���ɁB�������u���̖��͂̂��܂��́v���Ɗw�Z���͂����̂����F�F�B
�@���T�ɎQ�āA�P�T�ԑO�܂ł͏��w�����������X�����V�P�N���߂Ȃ���A������s�̏A�w�������Ă��鐶�k�̊����u12���v���v�������ׂ��B
�@�q�ǂ������̖��▢�����A�o�ϓI�ȗ��R�ō��E����鐢�̒��ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�i�����L�������Љ�������Ă����������������߂��Ă���B
�i�u����Ԃ���v2010�N�S��11���t���j
�܂����킵
�@�w�O�̑�^�J�����A�u�܂��Â���v���Ǝs���͌����B��Ƃ�U�v����^�X�܂��\���āA�u�Ŏ��\����ς���v�Ƃ������B
�@�P�N�O�̂R���A����������w����ĊJ�����ɃC�g�[���[�J�h�[���I�[�v�������B�O�サ�āA�R�K�܂œX�ܓ�����ꂽ25�K���ăr�����������A�H�ɂ͌�ʍL��̓쑤�ɏ��ƃr�����I�[�v�������B
�@�R�̃r���̓X�ܓ��e������ƁA��������n�����X�X�Ƌ������邱�Ƃ��킩��B�����āA�r���ǂ��������q����荇���ɂȂ�A�P�N�̊ԂɃC�g�[���[�J�h�[�ł́A�����̃e�i���g������������B
�@�u�܂��Â���v�������Ȃ�A���N�A�n��̑䏊�Ƃ��Ċ撣���Ă����n�����X����āA���X�X�Ƌ������Ȃ����m���J�����ɒu���ׂ��ł���B�������s���̌�����́u�����w�́v�̌��t����������Ȃ��B
�@���X�����X�Ǝp�������A�w�O�ɂ����l�X���W�܂���i���ڑO�ɗ��Ă���B�u�܂����킵�v�́A�~�܂邱�Ƃ�m��Ȃ��B
�i�u����Ԃ���v2010�N�R��14���t���j
�A�C�h�����O�X�g�b�v
 �@�R���s���[�^�[�V�X�e�����̗p�����u�v���E�X�v�Ȃǂ̃u���[�L�s����w�E����A���R�[�����s�Ȃ���悤�ɂȂ����B�V�^�����Ԃ̈��S�����A��C�ɋ^����o�����ł���B �@�R���s���[�^�[�V�X�e�����̗p�����u�v���E�X�v�Ȃǂ̃u���[�L�s����w�E����A���R�[�����s�Ȃ���悤�ɂȂ����B�V�^�����Ԃ̈��S�����A��C�ɋ^����o�����ł���B
�@�R���s���[�^�[�͓��퐶���ɂ��[�����荞�݁A�R���s���[�^�[�Ȃ��ł͂��܂�l�����Ȃ��قǂɁB�䂪�Ƃɂ��p�\�R����e���r�A�G�A�R���ȂǁA���n���I���p���[�h��ԁB�ǂ��������ɍ쓮����Ȃ��Ă͍�����̂���B���ꂪ���S���̎����ԂƂ����ẮA�Ȃ�����̂��Ƃł��낤�B
�@�����g���^�ł��A�䂪���Ԃ̓R���s���[�^�[�Ƃ͂قlj����A10�N�ȏ���O�̋����B����́u�G�R�J�[�v�ȂǂƂ͔�r�ɂȂ�Ȃ��A���R�ɂ͗D�����Ȃ��㕨�ł���B����ł����S�Ɏ����^��ł����B
�@����A�䂪�o�C�N��17�N�ڂ̓����ҁB�u�܂��{�͑���܂���v�ƃo�C�N������B�u�G�R�J�[�v�ɕ������ɍŋ߂ł́A�M���҂����邽�тɁu�A�C�h�����O�X�g�b�v�v������ɍs�Ȃ��悤�ɂȂ����B
�i�u����Ԃ���v2010�N�Q��14���t����j
���l��
 �@��₦�̂��鐬�l�̓��̌ߑO�A������s�ł����l�����J���ꂽ�B������s�̐V���l��1,266�l�B�茳�̎����ɂ��ƁA�X�N�O��2001�N��1,576�l�Ȃ̂ŁA310�l�����Ȃ��B�S���I�ɂ͓��v���Ƃ�n�߂Ĉȗ��A�ł����Ȃ��l���ƂȂ�A40�N�O��1970�N�Ɣ�ׂ�Ɣ����Ɍ����Ă���Ƃ����B�����X���͂܂��܂����������B �@��₦�̂��鐬�l�̓��̌ߑO�A������s�ł����l�����J���ꂽ�B������s�̐V���l��1,266�l�B�茳�̎����ɂ��ƁA�X�N�O��2001�N��1,576�l�Ȃ̂ŁA310�l�����Ȃ��B�S���I�ɂ͓��v���Ƃ�n�߂Ĉȗ��A�ł����Ȃ��l���ƂȂ�A40�N�O��1970�N�Ɣ�ׂ�Ɣ����Ɍ����Ă���Ƃ����B�����X���͂܂��܂����������B
�@���l���Ŗڗ��̂́A�����w�̂��ł₩�ȐU�葳�p�B�H�D�т̒j���w�������Ă��Ă���B����ǁA������s�̐��l���Ɋ���������̂́A�V���l�̂U����B�Q���������Ă��Q���ł�����ɂȂ���҂�A�����邽�߂ɐE�����߂Ċ���̉����������Ă����҂������̂ł͂Ȃ����낤���B
�@31�N�O�A����������s��20���}�����B����ǂ��n���o�g�̎҂ɂƂ��āA����Ȃ��n�ł̐��l���͕~������������B���Ă��������Ȃ��A��l�����̒��Ńe���r�����Ă����L�����c��B���̂悤�Ȏ҂��C���˂Ȃ��Q���ł��鐬�l���ł����Ăق����B
�i�u����Ԃ���v2010�N�P��17���t���j
�������̍��ˉ�����
 |
|
����������w���
|
�@11�����{������A����������w����̗l�q���A�T�P�ʂŕω����Ă���B�w�O�L��̐����ɔ��Ԃ�������A����̏o�������ω����J��Ԃ��Ă��邩�炾�B������12���U���A�������̍��ˉ������������B���Z�ɒʂ����q�́u���z�[���ɍs���̂ɁA�֗��ɂȂ����B�w�ɓ���ƁA�Ȃ��s��I�ɂȂ�������������v�ƌ����B
�@���˂ɂ͂Ȃ������̂́A���ˉ��ɂ͈ˑR�Ƃ��Đ��H���~���ꂽ�܂܁B������X���̍��ˉ��Ŗ͗l���߂����Ă���ƁA�����Ԃ����H��O�Œ�~���A���E�߂ăo�c�������ɔ��i������i���������B�u�K���v�Ƃ́A���낵�����̂ł���B
�@�������������A���ˉ��̐��H��O�ŁA�����킸���E���m�F���Ă��܂����B���H������ƁA�d�Ԃ�����̂ł͂Ȃ����ƌ��Ă��܂��̂́A�Љ��̌����Ȑ��ʂł�����Ǝv���̂��B
�@����ɂ��Ă��A����L��͍L������B�ǂ����Ă���ȂɍL������K�v������̂��H�Ǝv���̂́A���������낤���B
�i�u����Ԃ���v2009�N12��13���t���j
�đ�s�̌���
 |
|
���ʐ^�͌ߌ�W���̕đ�s�̏��X�X
|
�@�R�`���đ�s�͐l���X���l�B�L���ȁu�đv�ƂƂ��ɁA���ݕ��f���̂m�g�j��̓h���}�u�V�n�l�v�̕���Ƃ��Ă��r���𗁂тĂ���B���̕đ�s��10�����A���a�a�@�g���c��̍s�����@�ŖK�ꂽ�B
�@�ߗ����̂������^�c���Ă��鑍���a�@�̎��g�݂��w�Ԃ��߂ɖK�ꂽ�đ�s�́A�u�V�n�l�v�̏㐙�i�������]�����ƂƂ��Ɋւ����̔s���A����ˎ�Ƃ��ĕ��C�����n�B�u�V�n�l�v���ʂ�����A��������₩�ȊX�ł��낤�ƁA�S�x�点�ĊX�ɍ~�藧�����B
�@�Ƃ��낪�A���X�X�͒��Ԃ��Ƃ����̂ɃV���b�^�[������A���������͂��������Łu���n�v�u�݂��Ɓv�̊Ŕ��������ԁB�v���ƌ����̋��ԂŁA���G�ȐS���Ɋׂ����B
�@�U��Ԃ��ď�����s�B�w�O����₩�ɂ���X�Â���ɂ͗]�O���Ȃ����A���X�X�Â���͓����ҔC���B���X�X�Ə�����̗E���R���n������ł����A�����̐l�ɗ��Ă��炦��Ƃ������́B�u���v�̊��͏�����s�ɂ����K�v��
�i�u����Ԃ���v2009�N11��15���t���j
���悢�擥�؏��ł�
 |
|
���ʐ^�͕���������w�쑤����
|
�@�u�J�����̓��ݐ�v�Ŗ���y�����i�q���������A12���U���̏����̍��ˉ��ŁA�����ԏ�ƂȂ�B�O�g�́u�b���S���v�J�݈ȗ��A120�N�B������s����Ă������H�ⓥ�����悢����ł���B
�@�����A���ł���������Ȃ��B�����Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ƃ́A���s���A���ň�U��~���Ă��������Ԃ��A���ꂩ��̓X�s�[�h���������܂܂̏�ԂŁA���ˉ���˂���Ƃ������ƁB
�@���O�����̂́A����������w�����̓��؎��ӂ̏�����X���B�M���@�̂Ȃ����H�������ɕ��s�҂����S�ɉ���̂��B���l�ɁA�w���̓o���Z���̓��؎��ӂ��댯�����w�E����Ă���B
�@�N��l�Ƃ��āA���ݐ�̂Ȃ�������s���o���������Ƃ͂Ȃ��B12���U���́A�v�������ʎ��Ԃ��҂�����ɂ��Ȃ肩�˂Ȃ��B
�@���炭�̊Ԃ́A���ˉ��̐��H�͓P�����ꂸ�Ɏc��B�d�Ԃ�����Ȃ��ɂ�������炸�A�����̂悤�ɒ�~���č��E�m�F���Ă��܂��o�C�N�̎����A�����炭�����邾�낤�B�@
�i�u����Ԃ���v2009�N10��18���t���j
������ʑϐk���v��
�@14�N�O�̍�_�W�H��k�Ђł͑����̌������|���B���̋��P�����ƂɁA1981�N�U���ȑO�Ɍ��Ă�ꂽ�����́A�ϐk�⋭�̑��i����������悤�ɂȂ����B
�@������s�͍��̎w�j�����ƂɁA�s���̌������z���▯�Ԍ����̑ϐk���C���j����N�R���ɍ���B2015�N�x�܂łɎs�������z���̑ϐk�⋭��100���s�Ȃ��Ɩ��L�����B�������A���܂��ɑϐk���Ɍ��������{�v��͎�����Ă��Ȃ��B
�@�Ȃ��A�����Ȃ��̂��H�B���̖₢�ɏ�����s�́u�ȂɂԂ�A�����̍�����K�v�Ƃ��邽�߁v�B���̈���œ���ĊJ���͒����ɂ����߂��A�w���ۈ珊�R�ӏ��̑ϗp�N���͉߂��Ă��܂����B
�@�s�����{���ɂɂ́A�s�̖h�Ћ��_���u����Ă���B�U�N��Ɍ����̑ϗp�N�����}����Ȃ��ŁA�h�Ћ��_�������ɒu���Ă悢���̂��H�B���̑f�p�Ȗ₢�ɂ�������s�́A�ς���ʕԓ����J��Ԃ��̂݁B���Ɠ������s���ł��u���������m�[�v��˂�����ׂ��B
�i�u����Ԃ���v2009�N�X��20���t���j
�����Đ^������
�@���X�Ɣ~�J�����錾����Ȃ���A�~�J���̂悤�ȓV���������ẮA�䕗�X���̒ʉ߂ƂƂ��ɁA�悤�₭�Ė{�ԂƂȂ����B��������͂��łɂW���㔼�B���Ԃ̃A�u���[�~��c�N�c�N�z�E�V�̍����Ɠ������ɁA�[������̓q�O���V���₵�����͂��߂�B
�@����A�����̐��E�ł́A�����Đ^������B�A�u���[�~��c�N�c�N�z�E�V�ɕ������ƔM�ق��J��L�����A���̐��ɉ�����悤�ɁA�����̊S������܂ňȏ�ɍ����B
�@���̂��Ƃɂ��A�u��Ô�������Ăق����v�u���{�z�[���ɓ��������Ăق����v�u�����ꏊ��T���Ăق����v�ȂǁA�؎��Ȋ肢������B���Ă̐�����ł́A�Ȃ�Ƃ��Ă����̊肢�ɉ������鐭���������Ă����Ȃ���Ǝv���B���̂��߂ɂ����ɂ߂��K�v�B���̐��}�����Ƃ�A�����J�ɓ��X�ƃ��m��������̂��ǂ����B
�@���܂��撣�莞�B�J�ł̓q�O���V�����Ă��A�����̐��E�ł͖����Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�i�u����Ԃ���v2009�N�W��23���t���j
�_��Ȃ����}���L�тĂ���
 �@���I�̓V�̃V���[���A������s�ł͌����_�ɕ����A�c�O�Ȍ��ʂɏI������B�����n���͑��z�̂S���̂R�܂ł������ɕ���ꂽ�Ƃ����̂����A���̊��ɂ͈Â��Ȃ����Ƃ������o���Ȃ��B���X�A���������������������ł���B �@���I�̓V�̃V���[���A������s�ł͌����_�ɕ����A�c�O�Ȍ��ʂɏI������B�����n���͑��z�̂S���̂R�܂ł������ɕ���ꂽ�Ƃ����̂����A���̊��ɂ͈Â��Ȃ����Ƃ������o���Ȃ��B���X�A���������������������ł���B
�@�}�X�R�~�e���͓V�̃V���[�Əd�ˍ��킹�āA���I���̍s����_���Ă���B46�N�O�̊F�����H�̔N�ɂ����U�E���I�����s�Ȃ�ꂽ���炾�B�u���������傩�v�Ƃ͂₵���Ă邪�A���Ƃ�A�����J�ɕt���]�����҂̂ǂ��炪�����ɂ����Ƃ��A�����̍���͕ς���Ă͂����Ȃ��B�����ł������́A�����������������ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B
�@��ƌ�����}�������Ƃ��������_�ɕ���ꂽ���}�ł͂Ȃ��A�u�Ԋ��v�w�Ǘ���l�����E�}��ȂǁA�ǂ����璭�߂Ă��_��Ȃ������������߂���{���Y�}���L�тĂ����A�������S���狁�߂鐭�����������Ƃ��ł���B�����G�߂ł͂��邪�A���I�̓V�̃V���[�ɂӂ��킵�����ʂ��o���Ă��������B
���ʐ^�́A����18��\����̏��݂���
�i�u����Ԃ���v2009�N�V��26���t���j
�s�E������250���Ԃ̎c��
�@��250���Ԃ̎c�ƂƂ́A�ǂ�Ȑ����ł��낤���B���W��30������[���T��15���܂ł��u�莞�v�̋Ζ��B���ꂩ�炳��ɂW���ԓ����A�d�����I����̂͗����̌ߑO�P���߂��B�������A���̓��̒��ɂ͍Ăюd�����X�^�[�g����B������P�J���܂�܂鑱����ƁA��250�� �Ԃ̎c�ƂƂȂ�B
�@���̋��C���݂��c�ƘJ�����A�s�c��c���I�����s�Ȃ�ꂽ���N�R���A������s�̑I���Ǘ��ψ�����ǂŋ�����ꂽ�B
�@���̎����̂ł́A�I���̂���N�͐E���̐�����������B������������s�́u�s�v�v�̊|�����̂��ƁA�s�c�I�A�O�@�I�̂��邱�̉Ă��A�]���̐E���̐��ŏ���Ƃ����̂��B
�@�u�E�����|���O�ɁA���炩�̑Ή����Ƃ�ׂ��v�Ƃ̗v���ɑ��ď�����s�́A�u���̕����ł����Ȃ��E���Ŋ撣���Ă���v�ƈ�R�B�E��������ɍ팸����v��܂ŗ����Ă���B
�@���[���Ȃ��Љ���A���[������Љ�ɁI�B���̉āA�M���������s�Ȃ��Ă��������͊J����B
�i�u����Ԃ���v2009�N�U��28���t���j
�e���̈����
�@�����͂U��22���ł���B���Ƃ̒킩��͓����A�u20���Ɉ�������s�Ȃ������v�Ƃ̘A�����������B������20���O��͂U���s�c��̍ŏI�Ղ��}���邽�߁A���̓s�������T�ԑ��߂�13��(�y)�Ɉ����������s�����ƂƂȂ����B
�@�u�U���Ɉ�����ɍs���Ă���v�ƉƑ��ɍ������Ƃ���A�u�����s�������v�u�I�����I�v�Ɨv�����˂������A���ǁA��Ƒ��o�ōs�����ƂɂȂ����B��킭�A�Q�����炢�͂������Ƃ��낾���A14���̓��j���ɑ��q�̃N���u���������邽�߁A13�����ɂ͏�����ɖ߂��ė��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��s��12��(��)�ߌ�U���̐V�����ɏ�Ԃ��A��11���O�ɕ���̎��Ƃɓ����B��13���̗[���U���O�̖k�����ɔ�я��A��11���ɏ�����ɖ߂�Ƃ����A���킽��������������}�����B
�@������Ƃ����Ă����i�A�\������̂ł͂Ȃ��B�Z�E�ɂ��Ă��炢���o�������Ă��炢�A����݂̗������Œ��H��H�ׂ�Ƃ������x�B�e���̌Z��Ƒ�������`���Ă����������ߏ��̕��X�A�e���̂ꂠ���ƂR�l�̎q�ǂ��A����т��̉Ƒ����o�Ȃ����B���ɂƂ��Ă͈�����ł��邪�A�q�ǂ������̖ڐ��ł́A�C�g�R���W�܂��Ĉ�ӁA�y����ł���Ƃ������o�B�Ă̒�A�ɂ��₩�Ȉ�����ł������B
�@������Ƃ��Ȃ�A�g���Ȃ��̒m��Ȃ����E�h�������B�u�t��܂ł͂������o�Ă������ǁA���܂͂����o�Ă����v��12���̖�A�Ƒ��c�R�̐ȏ�ł��ӂ��낪�������B�g�o�Ă���h�Ƃ́A�S���e��������Ƃ������ƁB�u�w����͂���������ŁA���Ƃ��̂ށx�ƃn�b�L���������B���N�R���̖������̂��ƁB�����Ėڂ��o�߂��v�Ƃ��ӂ���B���ӂ���͉��x�ƂȂ��e���̖�������Ƃ����B�����R�x�A�e�����o�ꂷ�閲�������B����ǂ��A��b�͂Ȃ��B���ɂ����t�������Ă��炢�������̂��Ǝv���B
�@�U�����{�͌u�������G�߁B12���̖�A�w�Ɍ}���ɂ�����ɁA�u�������ꏊ�֎Ԃʼn^��ł�������B�����q�ǂ����������͂����ƕ����Ă������낤�ɂƎv���B�������A�����炿�̉䂪�q�͋��에���B�Ȃ��Ȃ����̏�𗣂�悤�Ƃ͂��Ȃ������B�Ȃ�̉������Ȃ��A�Â܂�Ԃ����R�Ԃ̏W���̐쉈���ŁA�e�����u�ƂȂ��Ĕ��ł���̂��낤�B���N�͎O����B�₳�������͉߂��Ă����B
�w�Z�s���ƐV�^�C���t���G���U
�@�V�^�C���t���G���U�̊������L����Ȃ��A�s����ψ���͉��₩�ł͂Ȃ��B��₤�����w���ȂǁA�q�ǂ������ւ̊����h�~������߂A�s���ł̊������ɐ_�o���Ƃ��点�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�������A���s�E�ޗǂւ̏C�w���s���������ɍT���Ă����쒆�w�Z���A���{�������X�����߂ɉ����������ƂɂƂ��Ȃ��A�h��V�����̃L�����Z���葱���A�X���̏h�m�ۂȂǂ̑Ή��������A�U���ȍ~�ɂ͏����w�Z�̈ړ�������ъԊw�Z�̍s�����҂���B
�@�����n��⊴���҂�����ɍL����A�����̍s���͂ǂ��Ȃ�̂��A�y���݂ɂ��Ă���q�ǂ������̎v���͂ǂ��Ȃ�̂��B�V�^�C���t���G���U�͍s�����T����w�Z��q�ǂ������ɂƂ��āA�J�T�ȑ㕨�ł�����B
�@�C�w���s�̉����ɂ���āA�L�����Z���������������B�s����ψ���́u�ł���Ύs�̍����őΉ��������v�Əq�ׂ邪�A�m��ł͂Ȃ��B�ی�ҕ��S�͂����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�s�������ǂ̑Ή��ɒ������K�v���B
�i2009�N�T��31���t�u����Ԃ���v���j
�j�Ձw�]�ˏ�x
 �@�V��t��{�ۂȂǂ̌�a���c���Ă����Ȃ�A�s�S�̊X�Â���͈�������̂ɂȂ��Ă����ɂ������Ȃ��ƁA���Â��v���B�T���̘A�x�𗘗p���ĕ��䂩��㋞���Ă�����e��A��ĖK�ꂽ�]�ˏ�Ղ́A���Ɉ͂܂ꂽ�Ί_�̏�̍L��Ȍ����ł������B �@�V��t��{�ۂȂǂ̌�a���c���Ă����Ȃ�A�s�S�̊X�Â���͈�������̂ɂȂ��Ă����ɂ������Ȃ��ƁA���Â��v���B�T���̘A�x�𗘗p���ĕ��䂩��㋞���Ă�����e��A��ĖK�ꂽ�]�ˏ�Ղ́A���Ɉ͂܂ꂽ�Ί_�̏�̍L��Ȍ����ł������B
�@�����ɏZ���32�N�B���ł��s����Ǝv���Ȃ�����A�j�Ձu�]�ˏ�v�ɂ́A�Ȃ��Ȃ����������Ȃ����̂ł���B���̖̂{�ɂ��ƁA�]�ˏ��1457�N�ɐ퍑����̕����E���c���z�邵�A1590�N�ɓ��邵������ƍN�ɂ���č]�ˏ�̊g���H�����X�^�[�g�B�Ȍ�A���I�A�O�㏫�R�E�ƌ��܂ŏ鑢�肪�����߂��A�ߐ����ے�����S���ő�̌������ɂȂ����Ƃ����B�ܑw�̓V��t�͓�㏫�R�E�G���̂Ƃ��Ɋ����B������1657�N�P���̖���̑�i�u�U���Ύ��v�Ƃ������j�ɂ���āA�V��t�Ɩ{�ہA��̊ہA�O�̊ۂ��Ď��B�{�ۂȂǂ̌�a�͍Č����ꂽ���A�V��t�́u������v�𗝗R�ɍČ����ꂸ�A�ȗ��A�]�ˏ�͓V��t�̂Ȃ���Ƃ��č����ɂ������Ă���Ƃ����B
 �@�����V���Ђ̂���n���S�������u�|���w�v����]�ˏ�Ղ̑O�ʂɏo�Ă�����������s�́A���Ɋ|����ꂽ����傩����邵���B�������̂悤�ɁA�]�ˏ�Ղ͍����A�c���ƂȂ�A�A��ʐl�����邱�Ƃ��ł���̂́A�]�ˏ�̒��S���ł������{�ہE��̊ہE�O�̊ۂ���ѓV��t�Ղ̕����B1968�N�ɍc�����䉑�Ƃ��Ĉ�ʌ��J�����悤�ɂȂ�A�j�Փ����������j���Ƌ��j���̋x�����ȊO�͖����ŊJ������Ă���B������������ƁA�E�ɑ傫���Ȃ���⓹�ɂł����킵�A���Ȃ�ɂ����ނƎŐ��̐������������ɂ��ǂ蒅���B�K�ꂽ�T���S���͐��V�B�����̉Ƒ��A���A�x�b�N�����������U�����A�V��t�Ղɂ̂ڂ��āA���{�����ق̗ΐF�̉����߂���A���Ă͂R��l�̏������l�߂Ă����{�ہu�剜��a�v�̂������L��Ȍ����������낵���肵�Ă����B��e�́u�]�ˏ�Ձv�Ƃ������o�����A�u�c���v�Ƃ������o�̕��������炵���A�]�ˎ���Ɏv����y���鎄�̂������ŁA�e���r�ɉf���o����鐳���̈�ʎQ���]���ɕ����ׂĂ���l�q�B�e�q���ꂼ�ꂪ����Ȏv���������Ȃ�����傩��ޏ邵���B �@�����V���Ђ̂���n���S�������u�|���w�v����]�ˏ�Ղ̑O�ʂɏo�Ă�����������s�́A���Ɋ|����ꂽ����傩����邵���B�������̂悤�ɁA�]�ˏ�Ղ͍����A�c���ƂȂ�A�A��ʐl�����邱�Ƃ��ł���̂́A�]�ˏ�̒��S���ł������{�ہE��̊ہE�O�̊ۂ���ѓV��t�Ղ̕����B1968�N�ɍc�����䉑�Ƃ��Ĉ�ʌ��J�����悤�ɂȂ�A�j�Փ����������j���Ƌ��j���̋x�����ȊO�͖����ŊJ������Ă���B������������ƁA�E�ɑ傫���Ȃ���⓹�ɂł����킵�A���Ȃ�ɂ����ނƎŐ��̐������������ɂ��ǂ蒅���B�K�ꂽ�T���S���͐��V�B�����̉Ƒ��A���A�x�b�N�����������U�����A�V��t�Ղɂ̂ڂ��āA���{�����ق̗ΐF�̉����߂���A���Ă͂R��l�̏������l�߂Ă����{�ہu�剜��a�v�̂������L��Ȍ����������낵���肵�Ă����B��e�́u�]�ˏ�Ձv�Ƃ������o�����A�u�c���v�Ƃ������o�̕��������炵���A�]�ˎ���Ɏv����y���鎄�̂������ŁA�e���r�ɉf���o����鐳���̈�ʎQ���]���ɕ����ׂĂ���l�q�B�e�q���ꂼ�ꂪ����Ȏv���������Ȃ�����傩��ޏ邵���B
�@�]�ˏ�Ղ͓����w��������Ă�15���]�ŗ����B���邪������ł����Ɖ��Ȃ�����ǂ蒅���Ȃ��̂Ƃ͑�Ⴂ�ł���B�����͂������������n��58���[�g���ܑ̌w�̓V��t���������A�P�����̖{�ۂ̑��a�������̉��ʼn��サ�Ă��Ȃ���A�����̓����s�S�͑傫������Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B�]�ˏ�Ղ̌������I���A�A��Ă���茳�̏��Зނ������Ă݂�ƁA�����̍]�ˏ�́A���݂̍c�����j�ɂ��āA�鉺�̑喼�A���{���~���O�s�Ƃ���A�قڐ��c��S��ɂ킽�邱�Ƃ�����������B�����ɁA�J������Ă���c�����䉑�́A�V�c�̏Z�ސ���䉑�������������Ƃ��킩��B�]�ˏ�Ղ͍����E�s���̗��j�I�ȍ��Y�ł���B�S�̂���ʌ��J���ׂ��ł���B
�@�]�k�ł��邪�A�]�ˏ�Ղ̖k����p�ɂ͍��̖����E�k�̊ی���������B�]�ˎ���A��O���̓c���ƂƐ����Ƃ̉��~���������ꏊ�ŁA���݂́A�����I�����s�b�N�̏_�����ƂȂ������{�����فA�Ȋw�̎������y���߂�Ȋw�Z�p�قȂǂ�����A�V�c�����ׂ��߉q���̔������N�����u�|�������v(1878�N)�̋��߉q�t�c�i�ߕ��̒���(���u���������ߑ���p�ٍH�|�فv)����������B����19�̑��t�̋G�߂ɁA�����t�������Ă��������ƁA�k�̊ی����ł��т��уf�[�g�������B�����́A���̏ꏊ�����j�I�ɂǂ̂悤�ȏꏊ�Ȃ̂��͂܂������m�炸�A1878�N�ɐV���{�Ɉًc���ƂȂ��Ĕ������N�������߉q���m�����������Ւn�ŁA�y�������X�𑗂������̂ł���B���̖����ł͂��邪�A19�̎��̏t�͍����炭�O�ɂ�������ƎU��A�ȗ��A31�N�A���{�����قł̓}�̉�����ɑ����^�ԈȊO�́A�k�̊ی����ɂ���Ă��邱�Ƃ͂Ȃ��B���̍��̊Â��v���o���Ђ��B���ɂ��āA���x�A�Ƒ��ƈꏏ�ɁA�]�ˏ�Վ��ӂ̗��j�U��ɗ��Ă݂悤���ƁA���̖̂{������Ȃ���v�����̍��ł���B
�ً}�ٗp����
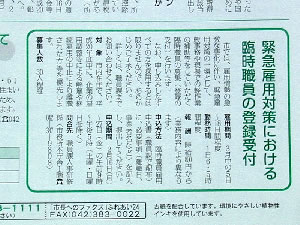 �@������s�͍��N�R���A���ق�ٗp�ł���ŐE���������l��ΏۂɁA�ً}�ٗp���Ƃ����{�����B�����{�݂̐��|�⎖���⏕�A���������Ɩ��ŁA������850�~����900�~�B�A�J���Ԃ͂T������18�����x�Ƃ������́B �@������s�͍��N�R���A���ق�ٗp�ł���ŐE���������l��ΏۂɁA�ً}�ٗp���Ƃ����{�����B�����{�݂̐��|�⎖���⏕�A���������Ɩ��ŁA������850�~����900�~�B�A�J���Ԃ͂T������18�����x�Ƃ������́B
�@�Ƃ��낪�A��W�l��30�l�ɑ��āA���ۂɌٗp���ꂽ�͎̂����⏕�̂S�l(�o�ωێY�ƐU���W�A�s���ʼnۏ��ŌW�A��ʑ�ی�ʑ�W�A�}���ٕ�d�W)�̂݁B�u�ً}�ٗp���Ƃ̒��g��m�肽���Ƃ����₢���킹�͂��������������A�T������18�����x�Ƃ������Ԃł��������߁A�������ꂽ�l�����������v�ƒS���ۂ͌����B�܂��A�A�J���Ԃ̒Z������Ɩ����e���i���A���̂��Ƃ��������������v���ƂȂ����̂ł͂Ȃ����Ɛ��������B
�@�R���Ɏs�c�I�����������Ƃ���A������s�̐V�N�x�\�Z�͗�N�����P�J�������c��ɒ�Ă��ꂽ�B���̂��߁A�V�N�x�ً̋}�ٗp���Ƃ͈���g�܂�Ă��Ȃ��B��\�Z����Ă����U���c��ł́A���ʂ���ٗp���Ƃݏo���A���҂ɉ�������s�����ɂ��邱�Ƃ��K�v���B
���ʐ^�́A�ً}�ٗp�̗Վ��E���o�^���ē�����u�s��v�Q��15���t
�i2009�N�T���R���t�u����Ԃ���v���j
���̖����@�ߏ��̖��
 �@�u���̖����v�Ƃ����A�s���ł͏�������璹�����A�n�c�����Ȃǂ��L�������A�O�����ł́u�s������������v���r���𗁂тĂ���B����������͏�����s�E�����s�E������s�E�������s�ɂ܂�����A�S���R��(��)�`�T��(��)�̂R���Ԃ́A������s�ό������Ấu���܂�v���J�Â��ꂽ�B���̂R���Ԃ͓V����悭�A���傤�ǖ��J�̎������}���A�T��(��)�ɂ͎s�c��c���I�����I�����e�w�c���A���ꂼ��̉����҂��]���A�l�o�ł���������������������ւƉԌ��ɌJ��o�����B �@�u���̖����v�Ƃ����A�s���ł͏�������璹�����A�n�c�����Ȃǂ��L�������A�O�����ł́u�s������������v���r���𗁂тĂ���B����������͏�����s�E�����s�E������s�E�������s�ɂ܂�����A�S���R��(��)�`�T��(��)�̂R���Ԃ́A������s�ό������Ấu���܂�v���J�Â��ꂽ�B���̂R���Ԃ͓V����悭�A���傤�ǖ��J�̎������}���A�T��(��)�ɂ͎s�c��c���I�����I�����e�w�c���A���ꂼ��̉����҂��]���A�l�o�ł���������������������ւƉԌ��ɌJ��o�����B
�@����������ɌJ��o���s���̑����́A�i�q����������k���n��ɏZ�ސl�̂悤�ł���B�쑤�n��ɂ͏���������Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ���������Ȃ����A����Ȃ�ɍ����y���ޏꏊ������A�L���ȂƂ���ł́u�s������������v�u�s���������v�A�����āu�s�������쉀�v������B�����쉀�͂��̖��̂Ƃ���u��n�v�ł��邪�A���̖����Ƃ��ċߍ݂ł͖����Ƃǂ납���Ă���B��������n�ł��邩��ɂ́A��⑲���k������A�����̓����������悤�B�������A�����̐l���Ԍ��ɌJ��o���Ă���A��⑲���k������̓����Ȃǂ͋C�ɂȂ炸�A���ł�����Ă���A�����̓������������Ɖ����B�������A��Ƃ��Ȃ�Ώ��Ȃ��炸�Ɠ��Ȃ����ނ����邪�A�u���Ȃ��̒m��Ȃ����E�v�𖡂���Ă݂�̂��I�c�Ȃ��̂ł���B����Ȏ��ԑтɂ��̏ꏊ�ɂ������Ƃ́A���͎v��Ȃ����B
 �@�䂪�Ƃ���50���قǗ��ꂽ�Ƃ���Ɂu���v������Ă���B�u�ꋉ�͐�v�ł͂��邪�A����20���قǂ����Ȃ��B�����s�͂��͔̉Ȃɍ��̖�A�����B���̂��ߐ쉈���̏Z������́u�ђ����Ƃ̒��ɓ����Ă���̂ō����Ă���v�Ƃ̋����Ă��邪�A�t�߂̐l�X�͂��̍��N�A�y���݂ɂ��Ă���B���傤�Ǎ������J���}�����S���U��(��)�͏��w�Z�ŁA�V��(��)�ɂ͒��w�Z�œ��w��������A�����Ƃ������A�������T�����{�̗z�C�ƂȂ������Ƃ���A�U����y���ސl��͐�~�ŕٓ����L���Ă��낮�Ƒ��ȂǁA������Ƃ����u�����v�ƂȂ��Ă���B�u�킴�킴����������═��������Ȃǂɍs���Ȃ��Ă��A���x����͂����ʼnԌ�����������Ȃ����H�v�ƗF�l�������قǂɁA��ƍ����X�e�L�ɒ��a���Ă���B�������A���̉͐�~�Ŏԍ��ɂȂ��Ď������킷�̂́A������ƒ�R������B�Ȃɂ��뗼���̒�̏����s�҂⎩�]�Ԃ��s�������A�W���W�������邱�ƂɂȂ�̂�����B������ɂ��Ă��A�������s�Ƃ̎s������������Ɏ����쉈���́A�k���⎩�]�Ԃō������Ȃ���U��ɂ́A�����Ă��́u�����v�Ƃ�����̂ł͂Ȃ����B���̃V�[�Y���͂��낻�떋�����낷���ƂɂȂ肻�������A�V�̎����ɂł����ЁA�U��������Ǝv���B �@�䂪�Ƃ���50���قǗ��ꂽ�Ƃ���Ɂu���v������Ă���B�u�ꋉ�͐�v�ł͂��邪�A����20���قǂ����Ȃ��B�����s�͂��͔̉Ȃɍ��̖�A�����B���̂��ߐ쉈���̏Z������́u�ђ����Ƃ̒��ɓ����Ă���̂ō����Ă���v�Ƃ̋����Ă��邪�A�t�߂̐l�X�͂��̍��N�A�y���݂ɂ��Ă���B���傤�Ǎ������J���}�����S���U��(��)�͏��w�Z�ŁA�V��(��)�ɂ͒��w�Z�œ��w��������A�����Ƃ������A�������T�����{�̗z�C�ƂȂ������Ƃ���A�U����y���ސl��͐�~�ŕٓ����L���Ă��낮�Ƒ��ȂǁA������Ƃ����u�����v�ƂȂ��Ă���B�u�킴�킴����������═��������Ȃǂɍs���Ȃ��Ă��A���x����͂����ʼnԌ�����������Ȃ����H�v�ƗF�l�������قǂɁA��ƍ����X�e�L�ɒ��a���Ă���B�������A���̉͐�~�Ŏԍ��ɂȂ��Ď������킷�̂́A������ƒ�R������B�Ȃɂ��뗼���̒�̏����s�҂⎩�]�Ԃ��s�������A�W���W�������邱�ƂɂȂ�̂�����B������ɂ��Ă��A�������s�Ƃ̎s������������Ɏ����쉈���́A�k���⎩�]�Ԃō������Ȃ���U��ɂ́A�����Ă��́u�����v�Ƃ�����̂ł͂Ȃ����B���̃V�[�Y���͂��낻�떋�����낷���ƂɂȂ肻�������A�V�̎����ɂł����ЁA�U��������Ǝv���B
���ʐ^�́A�䂪�Ƃ���50���̏��ɂ�����̖����u���v�B
�X�x���ǂߖ����̐킢
�@�R��29��(��)�ɓ��J�[���s�Ȃ�ꂽ������s�c��c���I���ŁA�����A�T�I���ʂ������Ƃ��ł����B�������Ă��������������̕��X�ɁA�S��������q�ׂ����Ă������������B
�@����̎s�c�I�́A�����}�����T��̑I���̂Ȃ��ł́A�����Ƃ��݂͂����l�������Ȃ��A���ׂĂ̌��҂��L�͌��Ɩڂ���A�N�������Ă����������Ȃ��ƌ�����قǂɁA�����ʂ�̏�������ł������B�T��ڂ̑I���Ƃ��Ȃ�ƁA�����ł�������x�͎��͂������A���̏���f�͂ł���悤�ɂȂ�B���̎��̖ڂ���݂��I����́A�u�s�C���v�̈��ɂ���B
�@�Ȃɂ��u�s�C���v���ƌ����A�L���҂̓������܂��������߂Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�������ٗp������������Ƃ������炱���A���_�́A�؎��ȁu���炵�E�����E�ٗp�v�Ȃǂ́u�v���v�ł���B����͂킩���Ă͂���̂����A����ŃC�R�[���A���Y�}�Ɏx�����W�܂�Ƃ������̂ł͂Ȃ��B�s�c�I�͒m�l�E���҂̂Ȃ��肪�傫�����E���A�����̓��������f�����B�����������Z�ފш�쒬����͒n��ɒm�l��Ȃ���𑽂�������}�̐V�l������₵�A���̊����n�Ղ̑O����������q��Đ���ɉe���͂��������V�l������₵�Ă���B�����ɂ��ď�������ł���B�u�q�^��ɂ͂S���E16�N�̎��т�����v�Ɛl�͌������A�u���сv��u����v�����ŗL���҂͔��f����̂��낤���B�P���ɂ͂����Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B�L���҂̑������߂�u���}�h�w�v�͂ǂ̂悤�Ȕ��f�������̂��낤�������������̂悤�Ȏv�����]�������܂Ƃ��A�s���ȂȂ��Ŏ��͑I�����Ԃ𑗂�A���[�����}���čs�����B
�@���ʂ���݂�A�s���^�}�̎����E�������[��傫����ނ����A�s���^�}�̌��E�R�l�����I�B���Y�}�͂S�l�S�������I���A�����g�͏��ʂ����O����͈���������̂́A�O����݂̕[���邱�Ƃ��ł����B���������Ӗ��ł́A�}�������Ă̑��͐�ŏ��������̂ɂ����킯�����A����̌��ʂ���͗l�X�Ȃ��̂������Ă���̂������ł���B
�@���ɂ�������̂́A�����̎����E�����ɑ���{�肪�s���ɂ����Ă��L���҂̈ӎ���傫�����E�������ƁB���́A�u92���~�̉w�O���Ɍ��݂̖��ʌ����v�ɑ���u�m�[�v�̎v�����A���[�s���Ɍ����ɂ����ꂽ���ƁB�ȏ�̓_�́A�����E�����̓��[�̑啝���Ő��������ł��낤�B��O�́A�����Y�E����}��\�̐������݂���̈�@�����^�f��肪����ɂ���A�ˑR�Ƃ��Ė���}�ɑ�����Ҋ������邱�ƁB����}�����[��傫���L�������Ƃ��A���̂��Ƃ��ؖ����Ă���B��l�́A������s�̃S�~��肪�����s�M�������A�c������V�������Ƃ̎v�������}�h�w�𒆐S�ɂ͂��炢�����ƁB�I���O����u�s�����������A���̊ԁA���̂��Ƃ������Ă����c��������v�Ƃ̈ӌ��������炱���炩�畷����Ă����B�V�l���S�������I�������Ƃ��A�[�I�ɗL���҂̈ӎ�������킵�Ă���B��܂ɂ́A�����}�ł�������}�ł���A���邢�͋��Y�}�▯��}�ł���A���}���F�̌�₪�S�����I�������Ƃ́A�L���҂����҂̐l�����ƂƂ��ɐ��}���ł���������Ɣ��f����Ƃ������R�̌����m�Ɏ����Ă���B���}�x���҂���݂�A�����炱�����̌��҂�ϋɓI�ɉ������郂�m�T�V�ɂȂ����Ƃ�����B���̂��Ƃ́A�����}�ɏ������Ȃ���u�������v�ŏo�n�������E�Q��₪�������ŗ��I�������ƂƂ̑Δ�Ŗ��Ăł���B��Z�ɁA�����͂����Ă��A�}���ł��o�����u����v�Ɣq�^��̂��̊Ԃ́u���сv�́A�L���҂����f���邤���ő傫�ȍޗ��ƂȂ����Ƃ������ƁB�䂪�}�͓��[�������[�����A�O���ŐL�����Ƃ��ł����B�������Ɏ��M�������ėǂ��Ǝv���B
�@�I�����Ԓ��ɍ��̉Ԃ��炫�n�߂��B���[��������ɂ͖��J�ɂȂ邩�Ǝv���Ă������A�ӊO�ɂ����Ƃ͂Ȃ炸�A���܁A���̌��e���L���Ă��鍠�ɂȂ��Ă悤�₭���J���}���Ă���B�u����̑I���͑O��Ɣ�ׂċC�����v�ƁA�O��̑I���i2005�N�R���j�ɑ����A�������Ă���Ă���N�z�̕��X���q�ׂ�B�������ȁH�B���͂���ȂɊ����Ƃ͎v��Ȃ������B�I�����Ԓ��A�����A�w���ɗ����A�ʋ����s���ɂ����A���s�Ȃ������A��܂������q�L�����p�����A�W�����o�[��R�[�g�ނ����p�������B�̂��悭�����A�O������͂邩�Ƀ��N�������B���͂����������̂����A�O��͑I�����Ԓ��ɍ����قږ��J�ɂȂ������ƂƔ�ׂ�A������ʂ�A����̕������������̂ł��낤���Ƃ��v���B������ɂ���A�̒������S��ԂŗՂ߂��͍̂K�^�ł������Ƃ�����B���Ȃ݂ɁA�J�~����́u����͂ƂĂ���ꂽ�v�ƒQ���A�g�t���A�J�c�L�����ڂ����h�ł͂Ȃ����A�I�����I������r�[�A�悭����B���̂����A�悭�H�ׂ�B�܂�Łg�V�����Ȕ���t�h�ł��邪�A�N����N���A�����悤�Ȃ��̂Ȃ̂ŁA���i�A��a���͂Ȃ��B
�@�u�T���ځv�B�����ł��M�����Ȃ����炢�B�O�C�҂̏����j�����U���Ŏs�c��E�ނ������Ƃ��݂�A���ƂP���őO�C�҂ƕ��Ԃ��ƂɂȂ�B�V�����s�c����݂�ƁA�V���ڂ��Q�l�A�U���ڂ��Q�l�A�T���ڂ��S�l�ł���A�T���ڈȏ�͍��v�łW�l�B24�l�̂����̂킸���O���̈�ɂ����Ȃ��B�S���ڂ̂Ƃ��́u�����ǂ���v�Ƃ����A�u���̌o�����Ƃ���v�ƌ����Ă������A�T���ڂƂ��Ȃ�ƁA�s���̖ڂ��s�����E���̖ڂ��قȂ��Ă���B�T���ڂɂӂ��킵�������ƍs���͂����߂���悤�ɂȂ�B�T���ڂɂӂ��킵���c���ɂȂ��̂��낤�������������̏d�݂Ƌ��߂����������������Ɗ������鍡�����̍��ł���B
�@�J�~����͕|�����݂ł���B�Q���̏��߁A�s�c�I���T�������ɑ��āA���|�̌��t�𗁂т��������B�u��n(���q)�ɂ́w�����x�Ƃ����X�x���ǂ߂����邯��ǁA���ɂ̓X�x���ǂ߂͂Ȃ�����ˁv�B�����������q�͂��̂Q���A�����A�s�����Z�����i�����B�����s�����Z�����s�����Ȃ�A�������Z�����邱�ƂɂȂ��Ă����̂ł���B�J�~����͂�������������ɂ��āA�g�ڂ�ڂ₵�Ă���Ɨ��I���邼�I�h�Ƃ̋����������Ă���̂ł���B�s�c��c���͂S�N���ƂɎ���������Ă���B�S�N�Ԃ̋Ɛт��s���ɔ��f���Ă��炤���߂̑I���Ƃ������̎������B���������̎����̓X�x���ǂ߂���Ȃ��B���I�����痂������́A�N�����������������Ȃ��̂ł���B�J�~����̋��|�̌��t��S�g�ɗ��тȂ���A�R��29���̓��[���܂Ŏ��͐S��A������v���Ŕn�Ԕn�̂悤�ɑ����Ă����B�C�����Ί�͓��ɏĂ��A�j�̓��͍킰�����A�o�������Ă����͂��̕��͏��X�ւ��݁A���ς��܂ł��Ă����B���̌��ʁA�����A�đI���ʂ������Ƃ��ł����B����A�J�~����́u��ꂽ�v�ƌ����Ȃ���A�悭����A�悭�H�ׁA�̏d�v�ɂ����邨������̂��悹�Ă���B���̂����e���r�̕ԑg�����ẮA�u�A�t�K�j�X�^����C���N�̎q�ǂ������́A�H�ׂ���̂��Ȃ��Ă��킢�����v�Ȃǂƌ����Ă̂���B�u���̋���ׂ����̂������Ă���̏d�v�̋C�����ɂ��Ȃ��Č���v�Ǝ��͐S�̒��ŋ��тȂ���A���̌��e���J�~����Ɍ����Ȃ��悤�ɂЂ�����Ə����̂ł���B���̒��̕|�����̂Ƃ��Ắu�n�k�E�J�~�i���E�Ǝ��E�J�~����v�Ƃ͂悭���������̂ł���B�E�E�E�E��������i�H�B
�T����
 �@�u���ɓ��ꂽ��B���߂ċ��Y�}�ɓ��[�����v�u������Ă����v�B���[���̗����A�w�O�őI�����ʂ��L�����j���[�X��z���Ă���ƁA����݂ƂȂ����l����������ق�����Ȃ��玟�X�ƕ��݊��A���̎���������肵�߂�B�v�킸�ړ����M���Ȃ����B �@�u���ɓ��ꂽ��B���߂ċ��Y�}�ɓ��[�����v�u������Ă����v�B���[���̗����A�w�O�őI�����ʂ��L�����j���[�X��z���Ă���ƁA����݂ƂȂ����l����������ق�����Ȃ��玟�X�ƕ��݊��A���̎���������肵�߂�B�v�킸�ړ����M���Ȃ����B
�@���ɂƂ��ĂT��ڂ̎s�c�I�́A�S�l�݂͂����̋ߔN�ɂȂ���������B�N�������Ă����������Ȃ��Ƃ���ꂽ�킢�́A�s���^�}�̌��E�R�l�����I���A�����A�������傫���[�����炵���悤�ɁA�����ւ̓{���傫�����f�������ʂƂȂ����B
�@����ŁA���[���͉ߔ����ɋy���A�O����݂ɂƂǂ܂����B�s�c�I���s���̋��ɓ͂�����Ȃ��́A�ˑR�Ƃ��đ傫�ȃe�[�}�ł���B
�@�W���ɂ͓��I�����c���̏��獇�킹���s�Ȃ��A�X������͋c��l�������߂Ă������߂̋c���A����J�n�����B�s�����߂����Ă̑傫�ȉۑ肪�������Ȃ��A�g���������߂āA����Ȃ钧��̓��������ł�������
�i�u����Ԃ���v2009�N�S���T���t���j
���ی���������������
�@�����N���͍ő�ł��A���z�U���T��~���x�����x������Ȃ��B75�Έȏ�͂�������A���ی����ƌ������҈�Õی������V��������A75�Ζ����̏ꍇ�́A���ی����ɉ����āA���ю傪���ۂɉ����������ґS����65�Έȏ�ł���A���ېł��V���������B
�@�����āA���N10������͏Z���ł��N������V���������B�O�q�̏ꍇ�A�N���x���z�̔�������ꍇ�͔[�t���ł̎x�����ɕύX����邪�A�Z���ł͂��܂킸�V��������Ă��܂��B�u�[�߂���z�ɕς��͂Ȃ��v�Ɛ�������邪�A������鑤�͂��܂������̂ł͂Ȃ��B
�@����ȂȂ��A������s�͍��N�S������A65�Έȏ�̂U���ɂ�����l�̉��ی������A�ő�Ō��z450�~�����������B���̊Ԃ̕��S�y�������߂�s���̉^����A07�N�X���̋��Y�} �s�c�c�̕ی����������������߂����Ă��A�����ł���������ł���B
�@���̋��Y�}�S�l�̋c�Ȃ����������s�c��ցB�R���͐�������̏����̌��ł���B
�i�u����Ԃ���v2009�N�R���P���t���j
�K��
�@�����Ƃœ����h���E�����J���҂̎��Ƃ����N�R�����܂ł�40���l�ɒB����Ƃ����B�m�l�̏��������̂P�l�B�u����A�p�[�g�S�����W�߂��A�R�����Ō_��ł���ƒʍ����ꂽ�v�B
�@���̊�Ƃ͋@�B���i�����������ǂ���B�S���̉c�Ə��ň�ĂɁA�p�[�g���_������Ƃ����B�����̂��߂Ƀp�[�g�����͌������Ȃ��B�������A�V���ȐE��͌����炸�B
�@���߂�������������Ƃ͐^����ɁA�h���E���ԍH�̎������s�B���_�̔ᔻ��O�ɁA���[�N�V�F�A�����O�Ə̂��āA�������������ƃZ�b�g�̎d���̕����������������͂��߂����A���ǂ͂��߂����ɂ͎��t�����A�ٗp����邽�߂̐g�K�́A���������o���Ȃ��Ƃ������́B
�@������s�͒x�܂��Ȃ���A�ٗp��̂��߂̗Վ��E���o���\�Z���B�������A10�������������ŗp�ς݂ł́A�ǂꂾ���̐l�����Ă���邾�낤���B��^�J�����������ɂ��������B�����̒��g��ς��Ă����A���炵�͎���B
�i�u����Ԃ���v2009�N�Q���P���t�j
���q�Ɖ߂���������
�@�u���ƂɋA�点�Ă��������܂��v�ƁA��A���ɍȂ͖���A��ďo�čs�����B�c���ꂽ���q�Ǝ��͋���ۂ̗①�ɂ�O�ɁA��A���̖邩�琳���O�����ɂ����Ă̐H�����B�ɑ���˂Ȃ�ʎ��Ԃ��}�����B
�@��N�A�����͉Ƒ��S�����Ȃ̎��ƂɏW�c�a�J����̂����A���N�̐����͂S�N���ƂɖK���s�c��c���I���̏����̂��߂Ɏ��͋��c��B���w�R�N���̑��q�����Z�ɐ�O���邽�߁A���������c��B�������āA���q�ƂQ�l�����̔N���E�N�n�ƂȂ����̂ł���B
�@���ɂ́A����̐������}����ɂ������Ă̍\�z���������B�m�g�j�́u�g���v���I������瑧�q�ƈꏏ�ɓs�S�ɂł����āA���w�Ȃǂɋ����邱�ƁB���X�g�����Ȃǂł����������̂�H�ׂāA���q�ɕ��Ȃǂ��Ă�邱�ƁA�ȂǂȂǁB
�@�Ƃ��낪�\�z�͖��c�ɕ��ꂽ�B�̐S�̑��q���{�C�ɂȂ��āA�����Ɍ����������炾�B�������A�e���r���ꏏ�Ɍ����B�����������N�z������G�ς��ꏏ�ɐH�ׂ��B�������A�O�ɂ͏o�悤�Ƃ��Ȃ��̂ł���B�������ɗU���Ă��A�u�~�������̂��Ă��v�ƌ����Ă��A�C��肵�Ȃ��Ԏ����Ԃ��Ă���̂݁B���ǁA���q���Ƃ̊O�ɏo���̂́A�߂��̐_�Ђɏ��w�ňꏏ�ɏo���������U�̌ߌ�̂P���Ԃ̂݁B�O�H�����܂ꂽ���߁A���̓J�~���߂��Ă���܂ł̊ԁA�O�x�O�x�̐H���Â���ɒǂ�ꂽ�B
�@�N����U���瑊�����œ͂����B��N�U���ɐe�����S���Ȃ�A�{���Ȃ�r���ł͂��邪�A�r���n�K�L���o���Ȃ������̂ŁA��N�ǂ���ɔN���ꂽ�B�N���͔N�Ɉ�x�A������̋ߋ���m���ł��y���݂Ȃ��́B�������N�̂����Ƀp�\�R�������B���A�N���Ȏʐ^��N���Ɉ�����đ����Ă�����̂�����B�Ƃ��낪�A���l�̎ʐ^�͍ڂ����ɁA�q�ǂ��̎ʐ^�݂̂��ڂ��Ă�����̂�����B����ɂ͂������肷��B���́A���̐l�̎q�ǂ��ɂ͈������S���Ȃ��̂ł���B�u�Ⴂ����Ƃ͗l�ς�肵���A���O����̐��c��̑̌^��N�G�̓�������`���������̂��v�ƌ��������B����ɍ������N��������B�N����̔N����킩��Ȃ����̂���N�A�����邱�Ƃł���B�N���ł��邽�߁A�X�ǂ̏�������Ă��炸�A�������ꂽ�n����킩��Ȃ��B���͂��������N�Ȃ̂��I�B
�@�N���z���������ɓ����āA�e���̎����ɊW�Ȃ��A�����m�l�ɔN�����o�����B�ȉ��́C���̕��ʂł���B�u���Z(��n)�͒��w�R�N�̎��B�w���]�͕�e���A���i�͕��e���x�Ǝ��͂͌����B��(�G)�͒��w�P�N�B�w���]�͕��e���A���i�͕�e���x�ƒN���������B�Q�w�����̒ʒm�\�́A�Z�͈�̐����݂̂�����Ȃ��B���̓o���G�e�B�ɕx�������삯�߂���B����������̒��w�����傫�������Ă���E�E�E�E�B���g�V�����Ȕ���H�h���߂��Ă��َq�܂Ɏ��L���Ȃ́A��l�A�䂪�Ƃ̃G���Q���W���������グ��B���̍��́A�̏d�v�ɏ��p���g���ƌ����B�����̏d�v�����킢�����ł͂��������E�E�E�E�B���N���X�}�X��A�˔@�����~�肽���C�́A���N�����̓�k���E����z�N������38�x���̔M�����ɂӂ�܂��A�g�̂̎��R��D�����B�g�i�J�C�͋��������A���ɂ͐ԕ@�̃g�i�J�C���f���o����Ă����B�����N�͎s�c�T���ڂւ̒���̎��B2009�N�͏����̔N�B�v
�@���̔N������ɂ����m�l����́u�v�����]���Ă����v�Ƃ̘A����A�u���ׂ͒������́H�v�Ƃ̂��S�z�̐��A�u����ȔN���������āA������͓{��Ȃ������H�v�̂��ӌ��܂ŁA�l�X�Ȕ�������B����������̂܂܂ɏ������̂����A���̎����A���̂����͂͏��̂ł���B
�����̔N
 �@2008�N�͍����̔N�������B�S���Ɍ������҈�Ð��x���X�^�[�g���A�{�肪�唚���B���{�͍Q�Ăāu������Áv�Ɍď̂�ύX�B���������g�́u�����v�Ƃ͖�����̎�҂����߁B10���ɂ́u�O������ҁv�̍��ېł̔N���V�������n�܂�A�������́u�R�N��̏���ł̑呝�Łv�B���̐ӔC�҂܂œ������n���B �@2008�N�͍����̔N�������B�S���Ɍ������҈�Ð��x���X�^�[�g���A�{�肪�唚���B���{�͍Q�Ăāu������Áv�Ɍď̂�ύX�B���������g�́u�����v�Ƃ͖�����̎�҂����߁B10���ɂ́u�O������ҁv�̍��ېł̔N���V�������n�܂�A�������́u�R�N��̏���ł̑呝�Łv�B���̐ӔC�҂܂œ������n���B
�@�̊�͕ς���Ă��A�����������g�͋��ԈˑR�ł���B�A�����J�Ɍ�����܂܂ɊC�����̃O�A���ړ]�ɋ��������o���A�h������ԍH���ʉ��ق�����E�ɂ͕�������킸�B���̂����A�C�O�q��Ђ̗��v�ɂ͐ŋ����|���Ȃ�������^���悤�Ƃ��Ă���B���ǁA���{���s�Ȃ���́A�A�����J����E�̖��d�Ȓ��g��ς����ɁA�����Ő��܂�鍑���Ƃ̖����ɍQ�ĂđΉ�����Ƃ��������̂��́B
�@�����w�I�H�D�x�̔��オ62���������B���[�������̐����ɑ��āA���ܑ����̍������{��������ɂ��Ă���B2009�N���ϊv�̔N�ɁB���悢�搳�O�ꂾ�B
�i�u����Ԃ���v2008�N12��28���t�j
�ЊQ���v�����
 �@��_�E�W�H��k�Ђł́A�Z���~�o�̍ő�̌��J�҂͒n��Z���ł������B���h����s���̎肪��炸�A�n��̐l�X���삯��������ł���B�������A����҂�Ⴊ���҂Ȃǂ̎�҂͍Ō�܂Ŏ��c����錋�ʂƂȂ����B���̐l�������g�߂ɏZ��ł��邱�Ƃ��m�炳��Ă��Ȃ��������߂ł���B �@��_�E�W�H��k�Ђł́A�Z���~�o�̍ő�̌��J�҂͒n��Z���ł������B���h����s���̎肪��炸�A�n��̐l�X���삯��������ł���B�������A����҂�Ⴊ���҂Ȃǂ̎�҂͍Ō�܂Ŏ��c����錋�ʂƂȂ����B���̐l�������g�߂ɏZ��ł��邱�Ƃ��m�炳��Ă��Ȃ��������߂ł���B
�@���̂��߁A��l�ł͔��ł��Ȃ����X��n��Z�����c�����Ă������Ƃ��d�v�ƂȂ��Ă���B�������A�l���ۗ̕L�҂͍s���B���̏����ǂ̂悤�ɂ��Ēn��Z���ɖ��炩�ɂ��Ă����̂��������A�傫�ȉۑ�ƂȂ��Ă���B
�@����A�c��@�ŖK�₵�����Ɍ��O�c�s�ł́A��ҏ���������ɓn���āA�C�U�I�Ƃ������ɂ͒n��Z��������������悤�ɂ�����g�݂������߂��Ă����B�x���������l���A�����̏������ɓn�����̂𗹉��̂����Ŏs�ɓo�^����Ƃ������@�ŁB��k�Ђ����P�Ɏn�܂������s����B������s�ł����݁A�������n�܂��Ă���B
�@�@�@�@�@���ʐ^�́A���Ɍ��O�c�s�́u�ЊQ���v����Ҏx�����x�v���Љ���p���t��
�i�u����Ԃ���v2008�N11���X���t���j
�e���̔[��
 �@�u�[���v���{�̈ē����X�����{�ɕ������B�ē�������܂ŁA�[���̂��Ƃ͑S���ᒆ�ɂ͂Ȃ������B�Ȃ������Ƃ������A�[�����̂��̂����邱�Ƃ����m��Ȃ������B�U��22���ɐe�����S���Ȃ�A�V��26���Ɂu�l�\����v�̖@�v���s�Ȃ��A�W���̏��~�ɗ��A������A����ň�i���Ǝv���Ă�����u�[���v�̒m�点�ł���B��ʂɏZ�ޒ킩��́u��������R�ɕ��������B��͎��Ƃ̂���A��͎��Ƌ߂��̂����A������͂����̖{�R�ւ̔[���Ɍ��܂��Ă���v�ƁA���̖��m�����������t���Ԃ��Ă����B�u�܂����䌧�֍s���̂��B���N�͖Z�����̂��v�Ǝv������A�u�{�R�v�͋��s�ɂ���Ƃ����B���s�ɗ����Ƃ����̂��B �@�u�[���v���{�̈ē����X�����{�ɕ������B�ē�������܂ŁA�[���̂��Ƃ͑S���ᒆ�ɂ͂Ȃ������B�Ȃ������Ƃ������A�[�����̂��̂����邱�Ƃ����m��Ȃ������B�U��22���ɐe�����S���Ȃ�A�V��26���Ɂu�l�\����v�̖@�v���s�Ȃ��A�W���̏��~�ɗ��A������A����ň�i���Ǝv���Ă�����u�[���v�̒m�点�ł���B��ʂɏZ�ޒ킩��́u��������R�ɕ��������B��͎��Ƃ̂���A��͎��Ƌ߂��̂����A������͂����̖{�R�ւ̔[���Ɍ��܂��Ă���v�ƁA���̖��m�����������t���Ԃ��Ă����B�u�܂����䌧�֍s���̂��B���N�͖Z�����̂��v�Ǝv������A�u�{�R�v�͋��s�ɂ���Ƃ����B���s�ɗ����Ƃ����̂��B
�@�u�[���v��10��12��(��)�B���́A���s�s���R��~�R���́u���{�莛�E��J�c�_�v�B��ʓI�ɂ́u����J�{�莛�v�ƌĂԂ炵���B����_�Ђ̋߂��A�~�R�����̓�ׂ�Ɉʒu����B���̏ꏊ�ɒ��X���ɏW������Ƃ����̂��r�傩��̎w�߂ł���B�u���X���v�Ƃ������Ƃ́A�����̒��A������s����n���d�Ԃɏ���Ă��Ԃɍ���Ȃ��B�Ƃ����킯�ŁA�O�����̋��s���肪�K�v�B�������A���̎����A���s�̏h���ȒP�Ɍ�������̂ł͂Ȃ��B�܂��Ă�11���͓y�j���A12���͓��j���A13���͑̈�̓��̎O�A�x�ł���B�h���m�ۂ��邱�Ƃ͎���̋Z���B�������Ƃ́A��ʂ̒�v�ȁA���Ƃ̑r��ꑰ�ɂ������邱�Ƃł������B�r��ꑰ�͓����A�����̑����ɎԂŕ���\�肾�������A�����̂S�l�ƍ�ʂ̕v�w���O���ɋ��s�ɏ�荞�ނ��Ƃ�m��A���ӂ���́u���s�������������v�̈ꌾ������łƂȂ��āA�r��ꑰ�V�l���O���̋��s��������ӂ����B
�@���s�ɏh���m�ۂł����̂́A�r��ꑰ�V�l�Ɖ�X�S�l�B�r��ꑰ�͋��s�k���̑哿���߂��̑f���܂�p�̋Ƃ��u�Ђ��Șb�Łv(�r��̌��t)�m�ہB��X�̓J�~���d���ŏh���������Ƃ̂���u���s���當���Z���^�[�v��}���邱�Ƃ��ł����B�u���s���當���Z���^�[�v�͍�����̋��s��w�a�@�߂��ɂ���A�n���S�E����d�ԁu�ۑ����v����k���T���A�s�o�X�◯���u�F��_�БO�v������k���T���̈ʒu�B����A��ʕv�w�͐V���w�O�̃z�e���h���ƂȂ����B������ɂ���A�[���O����11��(�y)�A�q��Ƃ͋��s���ӂɏW�����邱�ƂƂȂ����B
 �@��X�����s�ɑ��ݍ��̂́A11��(�y)�̌ߌ�S���O�B�܂��z�͏��ɂ���A�\���ɋ��s�s������邱�Ƃ��ł���B�P�g�Ȃ�Ζ������ՂɌ����������Ƃ��낾���A�J�~����̂����Ă̊肢�ŁA�J�~����̎d����̒m�荇���̍�i�W�Ɍ��������ƂƂȂ����B�ꏊ�͓����߂��̃M�������[�B��i�W�̈ē����͂��A���R�ɂ��A�X��������10��12���܂ł���i�W�̊��Ԃ��Ƃ����B �@��X�����s�ɑ��ݍ��̂́A11��(�y)�̌ߌ�S���O�B�܂��z�͏��ɂ���A�\���ɋ��s�s������邱�Ƃ��ł���B�P�g�Ȃ�Ζ������ՂɌ����������Ƃ��낾���A�J�~����̂����Ă̊肢�ŁA�J�~����̎d����̒m�荇���̍�i�W�Ɍ��������ƂƂȂ����B�ꏊ�͓����߂��̃M�������[�B��i�W�̈ē����͂��A���R�ɂ��A�X��������10��12���܂ł���i�W�̊��Ԃ��Ƃ����B
�@�u�Z�����l������A�{�l�͉��ɂ͗��ĂȂ���v�ƃJ�~����͌����A�M�������[�̓�����������B�r�[�ɁA�J�~����̊炪���邭�Ȃ����B�Z�����͂��̖{�l�������̂��B��i�W�̏o�W�҂͋��s�s�ݏZ�̖ؔʼn�ƁE�R�c���t����B�{�l�ɏo��܂Ŏ��́A�o�W�҂͏������Ǝv������ł����B�����āA�u���t�v���Ă����̂�����B�u�t�v�ƕt���Ώ�������l�E�E�E�E�B�W������Ă���ؔʼn�����n���ƁA�䂪�Ƃ̌��ւ̉��ʔ��̏�ɖ�����ɒu����Ă�����̂Ɠ������̂��A�K���X�ɂ͂߂��ď����Ă����B����������~�Ƃ����l�D���t�����āB���s����A�����J�~����́A�Q�Ăĉ��ʔ��̏ォ�狏�Ԃւƍ�i��u���ꏊ��ς����B�R�c���t����͑��ɂ����q������̂ɁA�������S�l�ɂ�������ő�������Ă��ꂽ�B���̓��̌ߌ�A��ʂ̒�v�w�͋��s�̑匴���U��B�r��ꑰ�͗��R�����ŃT���ƋY��Ă����B
 �@���āA�u���s���當���Z���^�[�v�B��ʂ̕ւ͐\�����Ȃ��B�h�����}�������҂ɂ��\�����Ȃ��B�f���܂�Ƃ͂����A��l3,500�~�ōςނ̂�����B�������A���C�͂R�l������Ƃ����ς��ɂȂ鋤�����C�ŁA�����͂U���̏������Ƃ����㕨�B����ł���X�Ɠ��l�̉Ƒ��A�ꂪ�h�����Ă���A�قږ��Ȃ������l�q�B��p��}�������l�ɂ͌���̏ꏊ�ł���B�`�F�b�N�C����A��X�͋��s�̔ɉ؊X�֗[�H�ɏo�����邱�ƂƂȂ����B�����ĂT���Łu�F��_�БO�v�o�X��B��������o�X��10�����炸�Łu�_���v�ɓ����B�l���������������l��ʂ������A�������X���u���X�K�v�B�R�N�O�̂X�����{�̉Ƒ����s�̍ۂɓ������X�ł���B�u�O�������ŐH�ׂ���v�ƃJ�~����Ǝq�ǂ��������猾���ċC�t���n���ł������B �@���āA�u���s���當���Z���^�[�v�B��ʂ̕ւ͐\�����Ȃ��B�h�����}�������҂ɂ��\�����Ȃ��B�f���܂�Ƃ͂����A��l3,500�~�ōςނ̂�����B�������A���C�͂R�l������Ƃ����ς��ɂȂ鋤�����C�ŁA�����͂U���̏������Ƃ����㕨�B����ł���X�Ɠ��l�̉Ƒ��A�ꂪ�h�����Ă���A�قږ��Ȃ������l�q�B��p��}�������l�ɂ͌���̏ꏊ�ł���B�`�F�b�N�C����A��X�͋��s�̔ɉ؊X�֗[�H�ɏo�����邱�ƂƂȂ����B�����ĂT���Łu�F��_�БO�v�o�X��B��������o�X��10�����炸�Łu�_���v�ɓ����B�l���������������l��ʂ������A�������X���u���X�K�v�B�R�N�O�̂X�����{�̉Ƒ����s�̍ۂɓ������X�ł���B�u�O�������ŐH�ׂ���v�ƃJ�~����Ǝq�ǂ��������猾���ċC�t���n���ł������B
 �@��12��(��)�͐��V�B�W���O�ɋ��當���Z���^�[���o�Ďs�o�X�ɏ�Ԃ��A���Ɠ����u�_���v�ʼn��ԁB�ڂ̑O�ɂ͔���_�Ђ��I�����W�F�ɋP���Ă���B����_�Ђ̉E�e�̍⓹���オ���Ă����ƁA�������~�R�����A�E���͑�J�c�_�ł���B�X���W���ł��邪�A��ʂ̒�v�w�������ԈႦ�A20���x���B���̂��߁A�r��ꑰ�͈�ԂŎ�t���ς܂��Ă������A�X��30������̔[���ƂȂ����B���������̔[����30���Ƃ����炸�A�ߑO10���ɂ͂������Ȃ��I���ƂȂ����B���Ƃ͎��R�̐g�B�߂��ɂ͐�����������B��J�c�_���琴�����ւƑ����Ώ�̓�����X��������Ȃ��U���Ă����B���R�̂��Ƃ��A�q���13�l�̐������Q�w�����s���ꂽ�B �@��12��(��)�͐��V�B�W���O�ɋ��當���Z���^�[���o�Ďs�o�X�ɏ�Ԃ��A���Ɠ����u�_���v�ʼn��ԁB�ڂ̑O�ɂ͔���_�Ђ��I�����W�F�ɋP���Ă���B����_�Ђ̉E�e�̍⓹���オ���Ă����ƁA�������~�R�����A�E���͑�J�c�_�ł���B�X���W���ł��邪�A��ʂ̒�v�w�������ԈႦ�A20���x���B���̂��߁A�r��ꑰ�͈�ԂŎ�t���ς܂��Ă������A�X��30������̔[���ƂȂ����B���������̔[����30���Ƃ����炸�A�ߑO10���ɂ͂������Ȃ��I���ƂȂ����B���Ƃ͎��R�̐g�B�߂��ɂ͐�����������B��J�c�_���琴�����ւƑ����Ώ�̓�����X��������Ȃ��U���Ă����B���R�̂��Ƃ��A�q���13�l�̐������Q�w�����s���ꂽ�B
�@���e�̔[���ŋ��s�ɏW���B���������Ԃ́A���ꂼ��̉Ƒ����H�̋��s���y���މƑ����s�Ɖ������B�u���N�Ɉ�x�̉Ƒ����s�v�Ǝ��Ƃ̒킩�烁�[�����͂������A�����܂������̎����ɋ��s�ɍs�����ƂɂȂ낤�Ƃ͎v���Ă����Ȃ������B�������[����ꂪ�������̋߂��ɂȂ낤�Ƃ́B12����̐V�����܂ł̊ԁA�킪�Ƒ��͔[���ɖ����肽���s���s��S�䂭�܂Ŋy���B
75�N�O
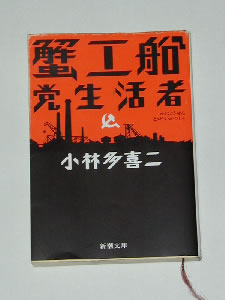 �@�u����v�������ꂽ����҂��A�����E����������ǂ��l�߂Ă���B�a����������̖����́u���x�̉��P�v�����������Ȃ��Ȃ�A�u�������҈�Ð��x�v�͔������N�ŁA�������j�]���}���悤�Ƃ��Ă���B �@�u����v�������ꂽ����҂��A�����E����������ǂ��l�߂Ă���B�a����������̖����́u���x�̉��P�v�����������Ȃ��Ȃ�A�u�������҈�Ð��x�v�͔������N�ŁA�������j�]���}���悤�Ƃ��Ă���B
�@10������́u�O���v�̐l�������A�����E����������ǂ��l�߂闧���҂ƂȂ�B���ю���܂ލ��ۉ����ґS����65����74�܂ł̐l�����́A���ېł��N������V��������邩�炾�B�����ė��N10������́A�Z���ł܂ł����N������V���������Ƃ����B
�@���N75���}���u����v�̃����o�[�ɂ��ꂽ���X�́A1933�N�ɐ��܂�Ă���B���̔N�́A���{���푈�ւƓ˂������ޕ����ꓹ�ƂȂ����u���ۘA���v����̒E�ނ̔N�ł���A�����N�̂Q��20���A���{���Y�}����ƁE���ё����́A�����x�@�̍���ɂ���ċs�E���ꂽ�B
�@��������������w�I�H�D�x�͍����A�����̎�҂Ɉ�����A�u����v�̐l�����ƂƂ��ɁA�����E����������ǂ��l�߂錴���͂ƂȂ��Ă���B
�i�u����Ԃ���v2008�N10���T���t���j
�_�Ƃ̌�p�ҕs��
 �@���N�̉ẮA��N�ȏ�ɏ������X�������Ă���B�����E����̉ẮA�C���̂��ɉ߂����₷�������Ǝv���Ă������A���N�̉Ă͈���Ă����B��͂�u�n�����g���v�̉e�����낤���B �@���N�̉ẮA��N�ȏ�ɏ������X�������Ă���B�����E����̉ẮA�C���̂��ɉ߂����₷�������Ǝv���Ă������A���N�̉Ă͈���Ă����B��͂�u�n�����g���v�̉e�����낤���B
�@�u���g���v�������Ȃ��A�_�n�E�Βn�̕ۑS�͍��ȏ�ɋ��߂���B�Ƃ��낪�_�Ƃ̌�p�ҕs���̂Ȃ��A������s�ł��_�n�����������Ȃ����Ԃ����܂�Ă���B�}���V�����⒓�ԏ�ɕς��A�����Ă̗v���ɂȂ��Ă���B
�@���e���S���Ȃ�A���Ƃł͗��N�̕ĂÂ���̐��c�_����Ă���B�c���ꂽ�Ƒ��ł͓���A�c��ڂɎ肪���Ȃ��Ƃ����̂����R�B��ԉɂ̂��ɓ����郂�m�����Ȃ��Ƃ����̂��w�i�ɂ���B�������A�����܂ʼn����t�����āB
�@�_�ƂŐH�ׂčs���鍑�Â��肪���߂���B���Ɛ��i�̗A�o���v�ƂЂ������ɓ��{�_�Ƃ��]���ɂ��鐭�{�̎p���ɁA���炽�߂ē{����o����B
�i�u����Ԃ���v2008�N�W��24���t���j
���ȏ��̑�
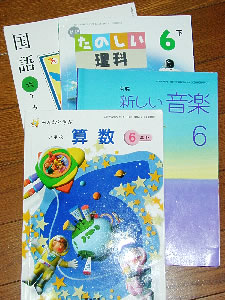 �@�V��29���ɊJ���ꂽ�s����ψ���ł́A���N�x����g�p����鏬�w�Z�Ə����w�Z���ʎx���w���̋��ȏ��̑����s�Ȃ�ꂽ�B �@�V��29���ɊJ���ꂽ�s����ψ���ł́A���N�x����g�p����鏬�w�Z�Ə����w�Z���ʎx���w���̋��ȏ��̑����s�Ȃ�ꂽ�B
�@���w�Z�Ŏg�p����鋳�ȏ���11�B�������ȂłX�ЁA���Ȃ����Ȃł͂Q�Ђ̋��ȏ��̒�����P�Ђ���I�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����ψ��T�l�̂����A���璷�ƈψ����������R�l�̈ӌ��ŕ��������܂��Ă����B
�@���E���ŕ������������A�q�ǂ������ɕ��a�̑�����`���Ă�������������ɂ͋��߂��Ă���B�Љ�Ȃ̋��ȏ��̑��ł́A���̊ϓ_����ψ��̈ӌ��Ɏ����X�����B�������A�u�킩��₷���v�u���₷���v�Ȃǂ̈ӌ��͔�ь������̂́A�ǂ��������_�ŋ����Ă������̘_�_�͕�����Ȃ������B
�@���N���W�����}�����B�U���ɂ͍L���ŁA�X���ɂ͒���ŕ��a�F�O���T���J�����B�����̋]���̂����ɁA�����̕��a�����邱�Ƃ�`���Ă������Ƃ́A��l�̎g���ł���B
�i�u����Ԃ���v2008�N�W���R���t���j
���e�̎�
 �@��ɂ�����ꂽ�����z���߂���ƁA���₩�Ȋ�Őe���͖����Ă����B�u���܋A�������v�Ɛ��������Ă��A���t�͂������ė��Ȃ��B�������ł͐e���̌Z�킽�����r����͂݁A���V�̎蔤�Ȃǂ����c���Ă���B �@��ɂ�����ꂽ�����z���߂���ƁA���₩�Ȋ�Őe���͖����Ă����B�u���܋A�������v�Ɛ��������Ă��A���t�͂������ė��Ȃ��B�������ł͐e���̌Z�킽�����r����͂݁A���V�̎蔤�Ȃǂ����c���Ă���B
�@�U��22��(��)�ߑO�O��10���A�Â܂�Ԃ����䂪�Ƃɓd�b���苿�����B�e���̊�Ă�m�点����Ƃ̉ł���(��̃J�~����)����̂��́B�u�����܂ł͎��Ǝv���v�Ɠd�b�̌��������̐��B�u��āv�ƌ����Ă��A���̎��ԑтł͂ǂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�d�Ԃ̓������܂ő҂����Ȃ��B�g����Ȃ���B�g�̂��x�߂Ȃ���E�E�E�E�h�B�����������킯���Ȃ��B�g���������Ȃ��E�E�E�E�h�ƕz�c�̂Ȃ��Ŏ��͂Ԃ₭�B����T�ԑO�A�x�b�h�ɐg�̂��N�����Ă���e���ɉ���Ă�������ł͂Ȃ����B
�@�Ƃɂ����A���ɂȂ�����o������p�ӂ����Ȃ���E�E�E�E�ƁA�g�̂��x�߂邱�Ƃ������l���A�z�c�̒��Ŏ��Ԃ��߂����B�ߑO�R��10���A�d�b���Ăі����B���킸�ƒm�ꂽ�u���v����������́B�قǂȂ��g�ѓd�b�ɁA��ʂɏZ�ޒ킩��̃��[�����͂����B�u���ɖڂɗ�������c�O�B���������āA��X�����������Ă��ꂽ�̂��������v���o�ɂȂ����v�B�S���߂��ɂ́A���Ƃ̒킩�烁�[�����͂��B�u���ɍۂ͋ꂵ����������Ȃ�������B�����r��r��ɂȂ�Ȃ���A���R�Ȋ����Ŏ~�܂�܂����B���������A�Ƃe����A��čs���܂��v�B
�@�\�����ʑ������̒m�点�ɁA�����}��������Ƃ����āA�����ɉƂ��яo���킯�ɂ͂����Ȃ������B�\�肵�Ă����d���̃L�����Z��������ԁA����ɂ��邱�Ƃւ̎蔤�B�Ȃɂ����U���c��^�������ł̑P���ɒǂ�ꂽ�B���̌��ʁA�ߑO�V��40���ɂ悤�₭������o�邱�ƂƂȂ����B�������P�g�ŁB�c���ꂽ�Ƒ��́A��23��(��)���ƂȂ����B
�@����������Ԓ��͈ȊO�Ɨ�Â������悤�Ɏv���B���e�̎��ł���Ȃ���A���e�Ƃ̎v���o�����ꂱ�ꏄ��킯�ł��Ȃ��A�߂��݂ɑł��Ђ������킯�ł��Ȃ��B���Ԃ�A���ӁA���e�����ʂ��Ƃ�\�����Ă�������ł��낤�B��T�ԑO�̕��䂩��̋A�r�̂ق����A�m���ɐh�������B�Ԓ��ł́A�i�n�ɑ��Y�́u�Ό��v�Ƃ���������ǂ݁A�ԑ��𗬂��i�F�߂Ă����B�ꐇ�����Ă��Ȃ��̂ɁA�������Q���x�������Ȃ������悤�Ɏv���B
�@�e����1931�N(���a�U�N)�T��12���A���䌧�r�c���ɂW�l�Z��̂T�ԖڂƂ��Đ��܂ꂽ�B�q�포�w�Z���ƌ�A���䌧���ŎR�d���ɏ]�����A���A�R�d�������߂čL�����ֈڂ�A��������������܂ōL���̎R���ŃL�R���̎d�������Ă����B�e�������O�A������Ƃ���ł́A�L���ɂ���Ƃ������a�@�i���F�L���ԏ\���E�����a�@�j�̓��O�g�������������Ƃ�����Ƃ̂��ƁB�\��̍����當�w�̐��E�ɐڋ߂��Ă����e���́A���l�E���O�g���������@��Ɍb�܂ꂽ�̂ł��낤�B�e���́A��ƁE����d���̐��E�œ��{���Y�}�ɓ��}�����B
�@����������(1957�N10���V��)���A�����ɋA���Ă����Ƃ���ցA���䌧�������̌��m��ʏ����Ƃ̌������������オ�����B���̏����́A�c���̍��ɕ�e������(���E)���A���e�͉Ƃ��o���܂ܓ����ŕ�炵�Ă���Ƃ����B�����ƈꏏ�ɕ�炵�Ă���̂́A�]���Z���c�ꂾ�Ƃ����B�o���A���ʎ��̌����������s�Ȃ��������ŁA1958�N�R��20���A������Ƃ����`�ŋ���(������̂��߁A�����u�����v����u�q�v�ɕς��)�B�V�Y26�A�V�w18�B���������͂��邩�̂悤�ɁA���N�T��10���A�����̑c�ꂪ�݃K���Ŏ����B���N��1959�N�Q��20���A��(�^��)���a�������B���N�A2008�N�͐e���Ƃ��ӂ���̋������ł���B
�@�u�[���v�Ƃ������̂�����B�ʖ���}���邻�̓��̌ߌ�A���V�������āA�l�Ɉ�̂�[�߂�Ƃ������̂ł���B���Ƃɋl�߂����Ă����e���̌Z��₱�̉Ƃ̏Z�l�A�q�ǂ�����������钆�A�e���͔������ɒ��ւ��ė������������āA�l�̒��ɓ����ꂽ�B�[���̍Œ��ɁA���������������̃J�~����Ɩ�(���w�P�N)�����������B���������q(���w�R�N)�͊��������̏����Əd�Ȃ������߁A���Z�̔N�Ƃ������Ƃ������āA��l�A�����Ɏc�����B�₪�Đe���́A�ߏ��̂���(��ю�)�ɉ^�ꂽ�B���̂����Œʖ�Ƒ��V���s�Ȃ��B
�@�ʖ�Ƒ��V�̎蔤�������߂Ȃ���A���̓��̒��́A��l�����Ɏc�������q���C�ɂȂ����B�Ȃɂ��돉�߂Ă̂��ƂȂ̂�����B�[�H�̂��Ƃ�A��l�Ŗ���}���邱�ƁA�����N����邩�ȂǁE�E�E�E�B�K���ɂ��āA�ߏ��ɐS���܂�l������A�����͗a���Ă��������ւ̃J�M�ʼnƂɓ���A���q���������N�����Ă����Ƃ����B���܂��ɁA���H�܂ŗp�ӂ��Ă����Ƃ����̂��B���̐l�̂������ŁA���q��23���`25���̎O���Ԃ̊����e�X�g���I���邱�Ƃ��ł����B
 �@23��(��)�̒ʖ�ɂ́A�吨�̑��l���Q���B��l�ɁA�e���������Ƃ������A���@���Ă������Ƃ���m��Ȃ������l�����������B�ʖ�Ƒ��V��n���̂����ōs�Ȃ����Ƃ́A���ӂ��낪���߂Ă����B�u���̑��ɖ��Ƃ��Ă���ė��āA���Y�}�Ƃ������Ƃł��ꂱ�ꌾ���A����ł����̈���Ƃ��Ċ撣���Ă����̂�����A���V�́A���l�������^�т₷���n���̎��ōs�Ȃ������v�B24��(��)�̌ߑO���̑��V���A�����̑��l������������B �@23��(��)�̒ʖ�ɂ́A�吨�̑��l���Q���B��l�ɁA�e���������Ƃ������A���@���Ă������Ƃ���m��Ȃ������l�����������B�ʖ�Ƒ��V��n���̂����ōs�Ȃ����Ƃ́A���ӂ��낪���߂Ă����B�u���̑��ɖ��Ƃ��Ă���ė��āA���Y�}�Ƃ������Ƃł��ꂱ�ꌾ���A����ł����̈���Ƃ��Ċ撣���Ă����̂�����A���V�́A���l�������^�т₷���n���̎��ōs�Ȃ������v�B24��(��)�̌ߑO���̑��V���A�����̑��l������������B
�@���V���I���A������Α���ւƈ�̂��ڂ����߂́u�o���v���}�����B�o���̍ۂɂ͈⑰�E�e�������S�ƂȂ��āA�l�̒��̈�̂̎���ɋe�Ȃǂ̉Ԃ������ʂ��}����B���ӂ�����v�w�A�e���̌Z��A�J�~����A�䂪���Ȃǂ����X�ɉԂ����Ă����B����ǂ��A���͞l�ɋ߂Â����Ƃ��ł��Ȃ������B�e���̊�����邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�����̈�ւ�����邱�ƂȂ��w�������āA�ړ����n���J�`�łʂ����̂�����Ƃ������B�Α���͎Ԃ�30���]�̂Ƃ���B�Α��ɕt�����O�̍Ŋ��̂��ʂ�̂Ƃ��ɂȂ��āA�悤�₭���͐e���̊�����邱�Ƃ��ł����B
�@���E���́A���ƍ�ʂɏZ�ޒ�v�w�A����Ɏ��Ƃ̒��w�Q�N�̏��̎q�Ɖ䂪��(���w�P�N)�̌v�T�l�B�e���̂��Ƃ�m���Ă���Α���̐l���Ă��c�������̐��������Ă��ꂽ�B���̎q�Q�l�͋����邱�Ƃ��Ȃ��A�������A��������ɓ���Ă����B�R�d�������Ă��������ɁA���͂�������Ǝc���Ă����B
�@�g�j�ǂ�������ԂɁh�Ƃ������ƂŁA�Z��R�l�ƒ�̃J�~��������āA�e���̈�i(���炭��)�����ɂƂ肩�������B�n�R���Ȑe���́A�̂Ă�悢���̂ł������㐶�厖�ɕۊǂ���N�Z������A�o���o���A�Љ�l�Ƃ��Ď��������ɏo�čs��30�N�]���O�Ɍ����o���̂���g���炭��"�����X�ƁB���܂��ɁA�Ԍɂ̋��ɂ͎g���Ȃ��Ȃ����Ζ��X�g�[�u���S�`�T���ς܂�Ă���B�R�̂悤�Ɂg���炭��"�͏o�Ă������̂́A�g����"�͉���Ȃ��A�u���Z����A�`���ɂȂɂ������ċA���ẮH�v�Ƃ��̉Ƃ̉ł���Ɍ���ꂽ���A�g���炭��"�ł͎����ċA��C�ɂ��Ȃ炸���܂��B�������A��ʂɏZ�ޒ�́A���̒�����`���ƂȂ�i��T�����āA�����猩��Ɓg���炭��"�ɂ����v���Ȃ����m���o�b�O�ɋl�߂Ă����B���̒��ɂ͐e���̎���̎Z�Ղ�����A����������čs���ꂽ���̉Ƃ̉ł́u���`���A���̎Z�Ղ͎q�ǂ������̂�������ɂȂ��Ă����̂ɁE�E�E�E�v�Ǝc�O�����Ă����B����A��ʂ̒�̃J�~����́A�g���炭��"�̒��ɁA�_���i�̍��Z����̊�ʐ^���\��ꂽ�w���蒠�����A�_���i�Ɍ�����Ȃ��悤�ɁA�w���蒠���������A�t�g�R���ɔE�����B�������āA���V���߂��ʂ��������i���������s����A��ʂ́g���炭��"�́A�z�O�s�̐��|�Z���^�[(�ꕔ�����g�����^�c)�ɐe�������p���Ă����g���b�N�łQ��ɕ����ĉ^�ꂽ�B�����萔����10�s��60�~�I�B�M�����ʈ����B���ɂP�g����������ł��A�U��~�ŕЂÂ��B���̐��Őe���́A�����߂ȉƑ���q�ǂ������ɑ��āA�܂��Ă���ł��낤�B
�@���ɂ͐S�c�肪��������B��́A���j�̎��ɐe���͌����c���������Ƃ��������̂ł͂Ȃ����B31�N�O�̂R�����A���Z�𑲋Ƃ������́u�T�N�ԁv�̖œ����֔�яo�����B���������A�����܂œ����ŕ�炵�����Ă���B���̊ԁA�������ʂ֔�яo���A���ǂ͎O�j�̖��킪�Ƃ��p�����ƂƂȂ����B�e���͎��������Ɏc�������Ƃɑ��āA�܂𗬂��Ĕ߂���ł����Ƃ����B�e����A���Ɍ����c���Ă����������Ƃ��������̂ł͂Ȃ��̂��H�B������́A�U�����{�ɕa�@�e�������������Ƃ��ɁA�e���Ɖ�b���ʂ����Ȃ��������ƁB�N�Ɉ�x�A�W���̖~�x�݂����̋A�Ȃ������̂ŁA�Ŋ��̉�b�͍�N�̂W���ƂȂ�B�b�������������B��b�������������B���̂��Ƃ��S�c��Ƃ��āA�U�����{�̋A�Ȉȍ~�A����܂�Ă����B�Ƃ��낪���V�̌�A���킩��ӊO�Ȃ��Ƃ����B�U��15��(��)�Ɏ����a�@�Ɍ��������ۂɁA�����e���ɑ��āu�ǂ�������H�v�Ɩ₤���Ƃ��ɐe���́u�K�^�K�^����v�Ɖ������Ƃ����B���ɂ͓��ꎕ���͂������e���̌��t�������ł��Ȃ������̂����E�E�E�E�B��b���ł��Ă����B�����������ɂ��Ă��邱�Ƃ𗝉��ł��Ă����B���ꂵ�������B�Ƃɂ����A���ꂵ�������B
�@�u���̂��т́E�E�E�E�v�ƁA���V���I����Ĕ����������ł��A�m�l���琺����������B�����������邽�тɁA�݂肵���̐e���̂��Ƃ��v���o�����B77�E����Ƃ��������ł͎Ⴂ���ނł��낤�B���@���ĂP�J���������Ȃ������ɂ��̐�����������e���ɑ��āu��������v�Ƃ������t�͓��R��������Ȃ��B����ǂ����͎����Ɍ����������Ă���B�u���ԂȂ̂�����v�ƁB�䂪�Ƒ��̂Ȃ��ō��Ƃ������ɓV�ɏ�����Ă����A�e���ɂ��̎��������Ƃ��������ɂ����Ȃ��̂��ƁB���������W��������B�~�ɗ��A�肵�Ă��e���͂������Ȃ��B
�]��
 �@���Ƃ͐X�є��̋ƁA�~�ɂȂ�Ǝ�Ŗ�R���삯������j���A���܁A�a���Őg�̂��x�߂Ă���B�w�Z�𑲋Ƃ��Ă���N�V���ĕa�C�ɂȂ�܂ŁA���̒j�͎R�ƂƂ��ɕ�炵�A�Ȃ��߂Ƃ�܂ł͍L���̒n�ŃL�R�����R�̐����𑗂��Ă����B26�̎��A���e�����ɁA�����ɕ����߂��Ă����܂Ɍ����������A�I�������̒n�ɂ������ƂƂȂ����B �@���Ƃ͐X�є��̋ƁA�~�ɂȂ�Ǝ�Ŗ�R���삯������j���A���܁A�a���Őg�̂��x�߂Ă���B�w�Z�𑲋Ƃ��Ă���N�V���ĕa�C�ɂȂ�܂ŁA���̒j�͎R�ƂƂ��ɕ�炵�A�Ȃ��߂Ƃ�܂ł͍L���̒n�ŃL�R�����R�̐����𑗂��Ă����B26�̎��A���e�����ɁA�����ɕ����߂��Ă����܂Ɍ����������A�I�������̒n�ɂ������ƂƂȂ����B
�@�U��15��(��)�[���A�a���̔����J����ƁA���̒j�̍Ȃ́u�Z�����̂ɉ������炫�Ă�����Ĉ����ˁv�ƁA�����}�����ꂽ�B���̒j�̓��N���C�j���O�x�b�h�ɉ������A�g�̂̂�����Ƃ���Ɍv���p�̊���t�����A�@�ɂ͎_�f�̊ǂ������A�h�{�܂ƃ����q�l�̓_�H���Ă����B
�@�j�̍Ȃ͎����������Ƃ������邽�߂ɁA�v�̐g�̂�h����A���肩��ڊo�߂����悤�Ƃ��Ă���B�u������B���R�ɋN����܂ő҂�v�Əq�ׁA���͂����߂�ꂽ�֎q�ɍ������B�a�l�͎v�����������C�����Ȃ̂ŁA����S�B�������A���̒j�́A��������40���قǂ̊Ԃ��قƂ�ǖ��̂Ȃ��ʼn߂����A�������邱�Ƃɂ͋C�t�������܂��B
�@����(16��)�̒��X���A���͍ēx�A�a����K�ꂽ�B�a�l�͑O���Ƃ͈قȂ�A�_�f�}�X�N�����Ă��Ă����B�u�ċz�̉����Ȃ��Ȃ��Ă���̂Łv�ƊŌ�m�̐����B����ǂ����l�͎_�f�}�X�N�����т��т͂����A�}�X�N���ז��҈����B�a�l�Ƃ͂����A��������������蓮�����߁A�z�c���͂ˏグ�A�g�̂ɕt����ꂽ������菜�����Ƃ���B���̓s�x�A�v��̌x��������A�Ō�m���a���ɓ����Ă���B
�@���O�A�a�l���ڊo�߂��B�a�l�̍Ȃ͎������邱�Ƃ�傫�Ȑ��Ŏ����œ`����B�������A���̖ڂ͂���ʕ����Ɍ������A�������Ȃ��B�u�����N�����킩�邩�H�v�ƕ����Ă��A���̔����������Ȃ��B���́u�s�c��c���E�q�^��v�̖��h�����o���A�j�̖ڂ̑O�Ɍf�����B�������A�j�͖��h�����[���ƌ��߂��܂܁A�g���났�����Ȃ��B�u�����q�l�̉e���Ō��o������A���������܁A�ǂ��ɂ���̂����킩��Ȃ��̂ł́v�ƍȂ��q�ׂ�B���̒j�͂Ƃ�����A������������ׂ�B���������ꎕ���͂�����Ă��邱�Ƃ������āA�Ȃ�̂��Ƃ��͂����ς�s���B�ȂɌ�����ꂽ���t�Ȃ̂��A����Ƃ����Ɍ�����ꂽ���t�Ȃ̂��A�͂��܂����o�̒��ł̂��ƂȂ̂��B�J������������ƁA�t�@�C���_�[����̂����j�̗e�p�͌��C���������ɖ߂��������B�������A�����͒�܂��Ă͂��Ȃ��B
�@�j�Ƃ̉�b���ʂ������A���ւ̊፷�����邱�Ƃ��Ȃ��A�ߌ�R�����}�����B������s�̂U���c��܂������Ȃ��A����ȏ�A���̒n�ɂƂǂ܂�킯�ɂ������Ȃ��B���͋A��|��j�̍Ȃɓ`�����B�u�����A��v�Ɨ����オ�������̔w�Ɍ��t���ƂԁB�s���Ǝ₵����������܂��ɂ������̌��t���A�d���̂�������B
�@�a���̌��������̓i�[�X�X�e�[�V�����ƂȂ��Ă���B�����ɂ��̒j�̎厡�オ�����B�a�l�́u���N�����ς������ǂ����v���A�R�����Ɏ����ꂽ�f�f���ł������B���͎厡��Ɍ����q�ׁA�u���N�����ς��ł����H�v�Ɩ₤���B�u�����E�E�E�E�v�u�H���H�v�u�E�E�E�E���������ς������ǂ����ł��v�u�U���ł����E�E�E�E�v�u(����)�v�B
�@�o�X�̎��Ԃ�����Ȃ����߂ɁA�a�@�̌��ւ���i�q����w�܂ŁA���͎���40���������n���ƂȂ����B��͉����B�~�J�̐���Ԃł���B����w�܂ł�40���A�����Ėk�����A�V�����ƁA�����Ɍ��������̔w���ɂ́A�d���\���˂��w���킳�ꂽ�B���̒j�̈�ԍŏ��̎q�ǂ��ɂȂ���49�N�B�����悤�ł�����A��������Ɖ߂����悤�ł�����B
�@��ň�_����̒j���A���������}�������N�A�l���ɖ������낻���Ƃ��Ă���B���Ɏ������̒n�ɗ���Ƃ��́A�r��������Ă���̂��낤���B
�N���V����
�@�u����҂����߂͂Ƃǂ܂�Ƃ����m��Ȃ��B�����łɉ����ĉ��ی������N������V��������A�S������͌������҈�Õی������V�����A10������͍��ېł��V��������A���N10���ɂ͏Z���ł܂ł����������B
�@���Ă͕����X���C�h���ŁA�����̏㏸�ɉ����ĔN���z�����������̂��A���܂ł͋t�Ɍ��葱�������B�{�l�̈ӌ������ɓV������������ɁA�{�肪�L����͓̂��R�̂��ƁB�u������������́A�V���������̂ł́v�Ƃ̐��܂ŁB
�@�U������A75�Έȏ�̉^�]�҂Ɂu���݂��}�[�N�v�\�����`�������ꂽ�B�ᔽ�̏ꍇ�A���_��_�Ɣ����������ۂ�����B�������҈�Õی����̒����őŌ�����A���x�̓}�[�N�̋`�����B�u�܂�Ŏז��҈������v�Ƃ͒m�l�̕فB
�@���ё����́u�I�H�D�v�̂悤�ɁA�����オ�邱�ƂŖ����͌�����B���܂����{����W�߂悤�B
�i�u����Ԃ���v2008�N�U���W���t����j
�b��
�@�ꎞ�I�Ȃ��̂��u�b��v�ƌĂԁB���́u�b��v���P�����畜�������B�O���܂ł̓��b�^�[������125�~�ŃK�\���������邱�Ƃ��ł������A��閾����ƃ��b�^�[160�~�B35�~���̒l�オ�肾�B
�@���肵���S�[���f���E�C�[�N���O�B�S���̍ŏI���ɉƑ�����́u�����̂����ɃK�\���������Ă�������v�ƃA�h�o�C�X�������A���ׂẴK�\�����X�^���h�����ւ̗�B�������A���߂��ɂ́u�����v�̊Ŕ��\�肾����Ă��܂����B
�@�u�b��v�͈ꎞ�I�Ȃ��̂������B�u�b��v����A�K�\�����������Ȃ����S���݂̂��A���ɂ́u�b��v�Ɏv���Ă��悤���Ȃ��B�u�K�\�����������܂܂��ƎԂ𗘗p����l��������v�ƕ��c�͏q�ׂ邪�A�ł͂Ȃ��A���H�����葱����̂��H�B�t�ɁA�Ԃ𗘗p�������Ȃ�ł͂Ȃ����B
�@�A�x���A�s�y�n�͎Ԃ̗������B�����₩�Ȗ��܂ŒD���u�b��v�����ŁA�����K�\�����ɔߖ������Ȃ���B���Ɖ��\�N�u�b��v�͑������B
�i�u����Ԃ���v2008�N�T��11���t���j
�V����
 �@���̉Ԃт炪�����Ȃ����A�q�ǂ��������ʊw�H����ށB���w�Z�̒ʊw�H�Ɉʒu����䂪�Ƃ���́A���F�������h�Z���ɉB���悤�ɁA���ǂ��Ȃ��̎c��V�P�N�����w�Z�ւƌ������p���ڂɉf��B �@���̉Ԃт炪�����Ȃ����A�q�ǂ��������ʊw�H����ށB���w�Z�̒ʊw�H�Ɉʒu����䂪�Ƃ���́A���F�������h�Z���ɉB���悤�ɁA���ǂ��Ȃ��̎c��V�P�N�����w�Z�ւƌ������p���ڂɉf��B
�@��l���w�Z�̐V������81�l�B���낤���ĂR�N���X�ɂȂ������A����80�l��������A40�l���̂Q�N���X�ɂȂ��Ă���A�搶���Q�Ă����Ƃ��낤�B����A�쒆�w�Z�̐V������126�l�B�P�N����R�N�܂łS�N���X���ƂȂ�A�₪�Ă���̈�Ղ́A�w�N�c�f�̂S�N���X�R�̔M�킪���҂����B
�@1980�N�ȗ��A�P�N���X�u40�l�v��������Ă���B�������A�����s�ȊO�̓��{���ł�2002�N�ȍ~�A�Ǝ��ɏ��l���w���ɓ��ݏo���A�䂫�Ƃǂ������Ƃ߂����ēw�͂��Ă���B�Ό��s�m���́A�q�ǂ������̋�����A��s�o�c�̂ق����厖�炵���B
�@�䂪��������A���w�̖�����������B�t�{�Ԃł���B�������A���ǂ��Ȃ��͂��܂��Ɏc��B
�i�u����Ԃ���v2008�N�S��13���t���j
�a�����v���[���g�Ɩ��̎v�f
 �@���͂�A���̍ɂȂ��āu���߂łƂ��v�ƌ����Ă��A�Ԃ����t�͉��������Ȃ��B40���߂��Ă���A�����̌o�̂��Ȃ�Ƒ������Ƃ��B�C�����A50�̎�O�B�u��������v�Ƌߏ��̎q�ǂ��������琺�������Ă��A���̈�a���������Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B�̂́u��������ł͂Ȃ��B���Z����ł���I�v�ƌ����Ԃ������̂����A�C�͂����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B �@���͂�A���̍ɂȂ��āu���߂łƂ��v�ƌ����Ă��A�Ԃ����t�͉��������Ȃ��B40���߂��Ă���A�����̌o�̂��Ȃ�Ƒ������Ƃ��B�C�����A50�̎�O�B�u��������v�Ƌߏ��̎q�ǂ��������琺�������Ă��A���̈�a���������Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B�̂́u��������ł͂Ȃ��B���Z����ł���I�v�ƌ����Ԃ������̂����A�C�͂����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B
�@�P��́A�q�ǂ���������̒a�����v���[���g����ꂽ�B�Ƃ����Ă��A���w�U�N���̖��݂̂ŁA���w�Q�N���̑��q�́A���e�̒a�����ȂNJᒆ�ɂȂ��B���w���̒j�̎q�ɂ́A���e�͂��邳�����݂ł����Ȃ��̂��B�v���[���g�����ꂽ�����A�͂����Ă��܂ŕ��e�̒a�������C�ɂ��Ă��Ă���邩�B�������A������Ƃ����āA�C�ɂ��Ă��Ă���Ȃ��ƍ���Ƃ������̂ł��Ȃ��̂����E�E�E�E�B�v���[���g���������ꂽ�ŁA���낢��l���߂��炵�Ă��܂��A����Ȃ���A�ׂɂ���ŔY�ނ킯�ł��Ȃ��B�悤����ɁA�����ǂ��ł��悢49�Ƃ����A���r���[�ȍȂ̂��B
�@�������ꂽ�v���[���g�́A��܂Ə�������ƃn���J�`�ƃJ�[�h�P�[�X�B���ɂ͈������A���܂�Ӗ������߂�ꂽ�Ƃ������̂ł͂Ȃ��l�q�B�킩��₷�������A����Ƃ葁���������i���Ƃ����Ƃ���B�N�Ɉ�x�̍s���̈�Ƃ��āA�w�O�̃f�p�[�g�ɍs���Ĕ�������ł����Ƃ������ł���B
�@�������A���̍s���̒ꗬ�ɂ́A�ڑO�ɔ���䂪�g�̒a�����ւ̊��҂���������Ă���B���e�Ƀv���[���g��n���Ă����A���g�̒a�����ɂ́A����ȏ�̃��m���Ԃ��Ă��邾�낤�Ƃ����A��̂��ꂽ���_���B����āA���e�̒a��������قǂȂ��}���鎩�g�̒a�������I�������閺�́A���g�̒a�����̃v���[���g���A�e�ɂ��邩����A���e�ւ̃v���[���g�w���Ƃ����g���������邱�ƂƂȂ�B���Ƃ����e���A���e���g�̒a�����̓����������v���Ă��Ȃ��Ƃ��B
�@����A���q�͍K�^�ł���B�a������N���Ɏ��ނ́A�N���X�}�X�v���[���g�����炢�A�a�����v���[���g�����炢�A�A�Ȑ�̕�e�̎��Ƃ̂����������A���������ɏj���Ă��炢�A�N��������Ƃ��N�ʂ����炤�B�܂������ނɂƂ��āA�N������N�����ɂ����Ă̓S�[���f���E�B�[�N�Ȃ̂ł���B�������~�x�݂̐^�������ł���B�Q�ΔN���̖��Ƃ́A�V�ƒn�قǂɌb�܂�Ă���̂ł���B
�@���ꂵ�����Ȃ�49�Ƃ����a�����v���[���g��������Ă��܂������́A�ڑO�ɍT�������̒a�����v���[���g���ǂ����邩�A�Y�ޓ��X�ɓ˓������B�u�s���̈�Ƃ��āA�w�O�̃f�p�[�g�Ŏ���Ƃ葁���v�Ƃ͂����Ȃ��̂�����B�c��̏����ƃv���[���g�̒��g�ŁA�Y�ނ��̍��ł���B
���H�������
�@�u���H��������v������̑傫�ȏœ_�ɂȂ��Ă���B���H�����̂��߂�10�N�Ԃ�59���~�m�ۂ��A�K�\�����ł̎b��ŗ��E���b�g��������25�~��10�N�ԉ������āA���H��������ɂ����ނƂ������́B�u���H�����v�Ƃ����Ȃ���A���y��ʏȐE���̖싅�O���[�u��싅���P�b�g�̍w����ɂ��[�Ă��A��������̕K�v�����^�⎋����Ă���B
�@���H��������́A�n�������̂̓��H�����ȊO�̎��Ƃɂ���t����Ă���B���̂����̈��2006�N�x����X�^�[�g�����u�܂��Â����t���v�B�w�O�J�����ƂȂǂ́u�s�s�Đ����Ɓv�ɏ[�Ă��A������s��2010�N�x�܂ł̂T�N�Ԃ�24���~��\��B���̂����̂S�����A���H����������Ƃ����B
�@�b��ŗ��ɂ���ă��b�g�� 150�~�̍����K�\�����킳��A����Ń[�l�R���̂��߂̑�^�������Ƃɍ������[�Ă���c�c�B�����̕�炵�������̂��Ŏg��������肷��A����ȗ₽�������͂܂��҂炾�B���܂����{����s���ɁB
�i�u����Ԃ���v2008�N�Q��17���t���j
���l��
 �@���l�̓���14���A������s�ł����l�����J���ꂽ�B������s�̐V���l��1,373�l(�j762�l�A��611�l)�A���̂���������685�l(�j364�l�A��321�l)�����̒�����w�������Z�u���ɏW�܂����B �@���l�̓���14���A������s�ł����l�����J���ꂽ�B������s�̐V���l��1,373�l(�j762�l�A��611�l)�A���̂���������685�l(�j364�l�A��321�l)�����̒�����w�������Z�u���ɏW�܂����B
�@�����A�r�ꂽ���l�����}�X�R�~���ɂ��킹�Ă��邪�A������s�̐��l���͐S�z���邱�Ƃ��Ȃ��A���A�ɗ������s���A�s�c��c���́u��l�Ƃ��Ă̐ӔC�����Ƃ��v�̌Ăт����ɂ����C�Ȕ������Ԃ�قǁB
�@����A�\�ɑ�l�ɂȂ����͂��̍���c���̂Ȃ��ŁA����̌����ɐӔC�������Ȃ��l���o�Ă���͎̂n���������B���{�̐V�e�����[�@�ɐ^���ʂ��甽���f���Ă����͂��̖���}�E����}��́A�@�Ă̍̌����ɍ���c���Ƃ��Ă̍ŏd�v�C��������B�}��݂�����}�̕��j�ɔ�����ԓx���Ƃ����B
�@�V���l������傫���c��܂��Ȃ���ӋC�g�X�ƕ���ł�����ɁA�܂����Ă��푈�̉e���܂Ƃ����ʂ悤�ɁA���{���Y�}�͕��a���@�����ʂ��Ӗ����ʂ���������B
�i�u����Ԃ���v2008�N�P��20���t����j
�N�̐�
 �ߏ��́u���v
�ߏ��́u���v
�@�N�̐����}���A�������~�������Ă����B���N�͂Ƃ��Ɍ��������B�������W�����W�����Əオ���Ă��邩�炾�B
�@�[���Ȃ̂́A�����ƃK�\�����B����18L��ʂ� 1,800�~�I�B�uL�S�~�v����ɓ˓������B��̑O�̃K�\�����̒l�i�ł���B���̃K�\�����B�o�C�N�ɖ��^���ɓ���Ă��炢�A�������ꂽ���z���Ď����^�����BL 154�~���Ƃ����B�o�C�N�ōs�����d�Ԃŏo�������ق��������̂ł͂Ȃ����ƁA�v���قǁB
�@���{�E�o�ϊE�́A����ő��ł̑升���B�����̂��߂Ɏg���Ƃ������A��������������グ�����̂��߂Ɏg���Ƃ����̂ł́A�o�ϊE�͕��͒ɂ܂Ȃ��B
�@�J�ł̓W���O���x�����苿���B�䂪�Ƃ̎q�ǂ��͐����ɊW�Ȃ��A�@�O�ȃv���[���g��v���B����ő��ł�����O�ɁA�䂪�Ƃ̉ƌv���X�������B�e�̕������A�v���[���g�����炢�������炢���B�T���^��A�������ɁB
�i�u����Ԃ���v2007�N12��16���t����j
�G�v��������
 �@�u�n�N�����v�����Ԃ��ɂ��킵�Ă���B����������A����̑ސE���̔������Ȃ̂��̂ɂȂ�Ƃ����@�����ł����Ƃ��ŁA���̒j���͐�X���X�ƂȂ��Ă���B�ƂƉ�Ђ̉��������̓����o�`�j���ɂƂ��āA�ȂɎO�s���i�݂�����͂�j��˂������ł�������A��������̐l���͐^���Âł���B�܂��A�q�ǂ������͍Ȃ̑��ɕt���B�q�ǂ������̗{�������X�A����˂Ȃ�Ȃ��B�������A�䏊�͂��ׂčȂɔC���Ă����̂ŁA���V�̍�����A�킩��Ȃ��B���Ɍ��ݏZ��ł���Ƃ����Ă����Ă��A�Ƃ̑|�������܂܂Ȃ�Ȃ����A���A�ǂ��ɂȂɂ����邩�����킩��Ȃ��B�Ƃ������ƂŁA���`�Ə̂���鎄�ł������A���Ă��Ȃ��悤�ɔ������ɏo�����A�䏊�ɂ����̂ł���B �@�u�n�N�����v�����Ԃ��ɂ��킵�Ă���B����������A����̑ސE���̔������Ȃ̂��̂ɂȂ�Ƃ����@�����ł����Ƃ��ŁA���̒j���͐�X���X�ƂȂ��Ă���B�ƂƉ�Ђ̉��������̓����o�`�j���ɂƂ��āA�ȂɎO�s���i�݂�����͂�j��˂������ł�������A��������̐l���͐^���Âł���B�܂��A�q�ǂ������͍Ȃ̑��ɕt���B�q�ǂ������̗{�������X�A����˂Ȃ�Ȃ��B�������A�䏊�͂��ׂčȂɔC���Ă����̂ŁA���V�̍�����A�킩��Ȃ��B���Ɍ��ݏZ��ł���Ƃ����Ă����Ă��A�Ƃ̑|�������܂܂Ȃ�Ȃ����A���A�ǂ��ɂȂɂ����邩�����킩��Ȃ��B�Ƃ������ƂŁA���`�Ə̂���鎄�ł������A���Ă��Ȃ��悤�ɔ������ɏo�����A�䏊�ɂ����̂ł���B
�@�䏊�ɗ��Ƃ��ɂ͕K���G�v�����𒅂���B���ݎg�p���Ă���G�v�����͓��ځB�{����47�̒a�����Ɏq�ǂ����������ꂽ�O��ڂ������̂����A�q�ǂ��������ƒ�Ȏ��ƂŎg�p����Ƃ��ŁA�w�Z�ɏo�������܂܂ł���B���̂��߁A���ڃG�v�����͌��v�����Ȃ��܂܂Ƀt����]�œ����A�����Ԃ�Ɖ���Ă��܂����B���v�����m�ۂ��A�Ђ����������b�ɂȂ��Ă��Ȃ�����@�ɓ���Ă����邱�Ƃ��K�v�ɂȂ��Ă���B
�@����ȂƂ��A������s�̐V���{�w�l�̉�̃o�U�[�Ō@��o�������������B��̓J�G���̃C���X�g���������ΐF�A������́u�ӂ邳�ƃL�����o���v�̏Љ���������F�B����킹��150�~�Ȃ̂ŁA�u�����������������l�v�ƌ����Ă��������炢�ł���B�V���{�w�l�̉�̂�����݂̖ʁX�́u�j�������v�̍l�������t���Ă���l���肾����A�����G�v�������Ă��A���Ԃ������Ɍ��邱�Ƃ͂Ȃ��B�u�����䏊�ɗ����Ȃ�����v�Ƃ����ڂŁA�������Ă���ɂ������Ȃ��B
�@�䏊�ɗ����Ă���Ƃ��ɁA���ւ̃s���|������Ƃ�������B���������ւɏo�čs���̂ŁA�G�v�����p�̂܂܂ł���B�������A���ւ̊O�ɂ���l�͐V���{�w�l�̉�̖ʁX�Ƃ͈���āA���̎p������Ȃ�g�M���b�I�h�Ƃ���l����B�u������ɓ�����ꂽ�̂ł����H�v�Ƃ͂������Ɍ��ɏo���Ă͌���Ȃ����A��z�̒j����@�����y�̕��X�̖ڂ́A�^���[�����Ɏ������߂�B�����玄�́u�����͎����������Ԃł��ăl�v�ƁA���A�E�\�������Ă��܂��B�u���Ă��Ȃ��悤�ɂ��Ă����ł��v�Ƃ͌����Ȃ��̂ł���B
�@�G�v�������o�U�[�Ŕ��������ł��A����Ȃɂ��ꂱ��v���߂��炳�Ȃ���Ȃ�Ȃ����{�̌���́A�܂��܂��j�������ɂ͂قlj����Ƃ������Ƃł͂Ȃ����낤���B�����ɁA���̈ӎ��̒��ɂ��A�j�����������t���Ă��Ȃ����Ƃ̏؍��ł����邩������Ȃ��B
�i�q�����Ήw�����̉���[�u
 �@�l�͍���̑Ή����u���@�K�I����[�u�v�ƌĂԁB�������A���p�ґ����猩��A���p�Җ{�ʂ̓��R�̑[�u�ƍl����ł��낤�B�i�q�����{�u�����Ήw�v�����̐E��������������̑[�u�́A�ǂ̂悤�ɔ��f����ɂ���A������s�c��j��ɂ����钿�����Ƃ��Č��p����Ă������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B �@�l�͍���̑Ή����u���@�K�I����[�u�v�ƌĂԁB�������A���p�ґ����猩��A���p�Җ{�ʂ̓��R�̑[�u�ƍl����ł��낤�B�i�q�����{�u�����Ήw�v�����̐E��������������̑[�u�́A�ǂ̂悤�ɔ��f����ɂ���A������s�c��j��ɂ����钿�����Ƃ��Č��p����Ă������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B
�@���̎�����11��13��(��)�B������s�c��̍s�������v�������ʈψ���V�������Ԍ�A�i�q�����Ήw�̐V�����o�����D��ʉ߂���Ƃ��ɋN�����B��Ԍ��ƍ��Ȏw�茔�A���}���̌v�R�����o�����D�@�B�ɓ��ꍞ���̂��ƁB�ƁA�����ŐV�����̍��Ȏw��ɏ�Ԃ��ꂽ���Ƃ̂���l�Ȃ�A�g������Ƒ҂Ă�h�ƂȂ�ł��낤�B�Ȃ������R��������̂��H�@�������������B���̎����́u�����R������v�Ƃ������Ƃ���N�����o�����ł������B
�@��X��s����ɂ����ؕ��́A�i�P�j�u����������|���R�v�̏�Ԍ��A�i�Q�j�u�����|���R�v�̐V�������}���A�i�R�j�u�����|�����v�̐V�������Ȏw�茔�A�̂R���B���̂R�����g���āA�����Ήw�Łu�r�����ԁv���悤�Ƃ����̂ł���B���R�ɁA�����Ήw�ʼn��Ԃ��邱�Ƃ͂ł���B�������A�V�����̏o�����D�@�B����Ăь���o���ؕ��́A�u����������|���R�v�̏�Ԍ��݂̂ł������B�܂�A�{���̍ŏI�ړI�n�A�u���R�w�v�܂ł̐V�������}���͉��D�@�B�Ɏ��e����Ă��܂����̂ł���B����ł́A���R�w�܂ŏ�Ԍ��݂̂ōs���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���s�̎s�c����ǐE���́u�����Ήw���牪�R�w�܂ł��ݗ����ōs���A�Q���Ԃ͂�����v�Ɛ����B�ꓯ�A���R�ƂȂ����B
�@���D������20�����ꂽ�w�\���ɁA�o�}���̖��Ύs�����E�����|�c���Ƒ҂����Ȃ���A�����Ήw�E���Ƃ̂��Ƃ肪�J�n���ꂽ�B��X�̎咣�͂�����u���R�w�܂ł̐V�������}����Ԃ��Ăق����v�B����A�w�E���́u�����Ήw�����Ԃ������Ƃɂ���āA���̎��_�ŁA���̐�i���R�w�j�܂ł̐V�������}���͖����ƂȂ�v�B��Ԍ��͓r�����Ԃł��L�������A���}���͖����ɂȂ�Ƃ����̂��B���x���̉����ⓚ���J��Ԃ��ꂽ�����`���������A���Ԃ��Ԉ�s�͖��Ύs�����E���̂��ƂɌ��������B
�@�ł����̂́A���s�̏�����s�c����ǐE���B�u�����Ήw���牪�R�w�܂ł��A�Q���Ԃ�������킯�ɂ͂����Ȃ��B���Ƃ��ƁA�����肮���ɂ���Ă��܂��v�B�w�E���Ɖ����ⓚ���J��Ԃ��������A������s�c����ǂɓd�b���w�������B�Ȃɂ���A��A�̐ؕ��͔ނ��w�������̂ł͂Ȃ��A���s�㗝�X����������́B�ނɂ���A�V�����̂ł���B��������̎��������߂Ȃ��܂܁A���Ύs���}���ق̎��@�Ɉڂ�B�ނ̓��ɂ́A�����Ήw���牪�R�w�܂ł̍s�H���ǂ����邩�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B���ǁA������s�c����ǂ����������@�́A�ēx�����A��ނȂ��ꍇ�͐����Ήw���牪�R�w�܂ł̐V�������}�����w�����邱�ƁB�����Ήw�E�����̌R��ɂ����邱�Ƃ��~�ނȂ��ƂȂ����B
�@���Ύs���}���ق̎��@���I���A�Ăѐ����Ήw�ցB�W�����Ԃ����߁A�c�����w�\���ɎU�����̂����͂����s�c����ǐE���ƁA���@�ɉ������������s�̐}���ْ��A��搭��ے��⍲�͉w�����ɂ����ނ��A���Ɉڂ����B�s�c����ǐE���̎�ɂ́A��s�̐����Ήw���牪�R�w�܂ł̐V�������Ȏw�茔�����肵�߂��Ă����B�悤����ɗ��s�㗝�X�́A�u�����|�����v�̐V�������Ȏw�茔�̑��ɁA�u�����|���R�v�̍��Ȏw�茔����z���A��Ԍ��Ɠ��}�������R�w�܂ł̒ʂ����ɂ��Ă����̂ł���B�������A�����Ŏv��ʂ��Ƃ��u�������B�u�����|���R�̍��Ȏw�茔�͖����ł��v�Ɖw���͎咣����̂ł���B�ޓ��������ɂ́u���Ȏw�茔�͓��}���������Ă������͂�����̂ł���A���̓��}���͐����Ήw�����Ԃ������Ƃŏ��ł��A���̎��_�ŁA���̐�̍��Ȏw�茠���͖����ƂȂ�v�B�w��Ȍ��ɖ��L���ꂽ�V�����͂܂��������Ă��Ȃ��̂ɁA�������Ƃ����̂ł���B�������A���̂��Ƃ��ʂɎ��͗�������Ă��Ȃ��B���̌�̂��܂��܂ȏ������ƂɋL���Ă���̂ŁA�����炩���ق����邩������Ȃ����A���̒��x�͋��e�͈͂Ǝv���Ă������������B�W�����Ԃ��߂Â��A�U���Ă����c�������D���O�ɏW�����Ă����B�������A�w�����ł͏�����s�̂R�l�̐E�����w�E���ƌ��𑱂��Ă���B�����֏W�������c����������藧������l�q�����ɍs���B�����̏��́A�l��{�D��S�����Ȏs�c��c�����ɒ���A���ꂽ�B
�@������s�E���R�l�̌��́A20���͑������ł��낤�B���̔M�ӂ�����ς������B�܂��A�u�����v�ƂȂ����͂��́u�����Ήw���牪�R�w�܂ł̓��}���v���������A�����āA�������u�����v�Ƃ��ꂽ�u�����Ήw���牪�R�w�܂ł̍��Ȏw�茔�v���L�������ƂȂ����B�������A�u�����w���牪�R�w�܂ł̐V�������}���v�����̂܂ܗL���Ƃ���킯�ɂ͂����Ȃ��̂Łi�Ȃɂ���A�r�����Ԃ����̂�����j�A�u�����|�����v�Ɓu�����|���R�v�Ƃœ��}�����čw�������Ƃ݂Ȃ��[�u���Ƃ�ꂽ�B���̑[�u�ɕ�������lj����������ꂽ���A�悤����ɁA�u�����|���R�v�̓��}���̋��z�ƁA�u�����|�����v�u�����|���R�v�Ƃœ��}�����čw���������z�Ƃ̍��z�����ꂽ�Ƃ������ƁB�u�lj������v�ƋL�������A�ŏ����痷�s�㗝�X������ȍw���̎d�������Ă���A�������z��������킯�ł���A�ǒ����Ƃ������i�ł͂Ȃ��B�������s���ꂽ�̂́A���Ȏw��̐V��������������R���O�ł������B�s�E�����猔�����A����Ȃ���K�i���삯�オ��A�z�[���ɂ��ǂ蒅�����Ƃ��ɂ͂��łɐV�����̓z�[����O�ɗ��Ă����B
�@���āA���̎��ɐ����Ήw�̐V�����������D��ʂ�Ƃ��Ɏ�ɂ��������R���ł������B�i�P�j�u����������|���R�v�̏�Ԍ��A�i�Q�j�u�����|���R�v�̐V�����w��Ȍ��A�i�R�j�u�����|���R�v�̐V�������}���B�i�P�j�Ɓi�Q�j�͗��s�㗝�X����z�������B�i�R�j�͐����Ήw�����s�������ł���B���R�w�Łi�R�j�̌��͉��D�@�B�̒��ɏ����Ă��܂����̂ł͂�����Ƃ͊o���Ă��Ȃ����A�u�w�茔����v�ƋL����Ă����悤�ɋL�����Ă���B�ʏ�́A�i�Q�j�Ɓi�R�j�͈ꖇ�̌��ɓ�������Ă���̂ł���B
�@��A��s�͗[�H�̂��ƁA��A�O����ւƂ���o�����B�������A���ʂĂ��s�E���͓�I���ƂƂ��Ƀz�e���ւƏ����čs�����B�s�c����ǐE���͂��̓��A�Q�s���ł������B�O��10���ɏ��ɏA���A�ߑO�S���ɖڂ��o�߂��B��x�Q������ƐQ�V����̂ł͂Ȃ����Ƃ̋��|����A�ނ͌ߑO�S���ɖڂ��o�߂Ĉȍ~�A�e���r������Ȃǂ��ďo�Ύ��Ԃ�҂̂ł���B�������ނ́A�c��@�ɋc����ǐӔC�҂Ƃ��ē��s����̂��A�킸���Q�x�ځB�P�x�ڂ̎��@�c�����l���������A�����邳���c��������̎��@�c�ɂ͂�����Ă���B�����ցA����̏o�����ł���B�������ނ̕����ŁA��������蔲���邱�Ƃ��ł����B�ނ͈ꐶ�A����̏o������Y��Ȃ��ł��낤�B�����ɁA���s�㗝�X�ɑ��ẮA���܂ł��S�Ɏv�����̂��c��ł��낤�B�@�@�@���ʐ^�́A��蔭�˂̒n�u�����Ήw�v
�g�b�v�_�E���̎O��o�C�N���[�X
 �@�Ό��s�m�����O��̕����C�x���g�Ƃ��đł��グ���u�O��I�[�g�o�C���[�X�v��16�A17���ɊJ����A�}�X���f�B�A�����X�Ɠ��ɉ����Ă���B������s�͂��̃C�x���g�ɍ��킹�āu�ϐ�c�A�[�v���v��B�������\���30����傫�������Q���̉��債���Ȃ��A�s�����Q���������鎖�ԂɁB �@�Ό��s�m�����O��̕����C�x���g�Ƃ��đł��グ���u�O��I�[�g�o�C���[�X�v��16�A17���ɊJ����A�}�X���f�B�A�����X�Ɠ��ɉ����Ă���B������s�͂��̃C�x���g�ɍ��킹�āu�ϐ�c�A�[�v���v��B�������\���30����傫�������Q���̉��債���Ȃ��A�s�����Q���������鎖�ԂɁB
�@���S���������o�C�N���[�X�ɑ��ẮA�����o�C�N���[�J�[�����͂����ށB���[�X����ǂ���\�肾�����u���{���[�^�[�T�C�N���X�|�[�c����v�����͂��Ȃ����Ƃ����߂�ȂǁA�Ό��m�����g�b�v�_�E���Ō��߂��C�x���g�́A�o�������甪���ӂ�����̏�Ԃł���B
�@���ɂ́A���������e���A����������҂��������ł̃o�C�N���[�X�Ƃ������z���ǂ����Ă������ł��Ȃ��B�o�C�N�̍������苿���A���������Ɣߖ������邩�炾�B�g�b�v�_�E���Ō��߂�ꂽ�C�x���g�́A�O����J���̊O�ɒu����Ă���B���̎�̐������āA�ǂ����u�x���v�ƌ����邾�낤���B
�i�u����Ԃ���v2007�N11��18���t���j
�M�B�E�ؑ�
�@�u���쌧�̐ؑ��ɍs�����v�ƗU���A�m�l�Ƀv���������ׂĔC���Đ��ʗp��Ɖ����ނ��l�ߍ������̃o�b�O�Ў�ɓd�Ԃɔ�я�������̓��̒��ɂ́A�u�ؑ��v���ǂ�ȂƂ���Ȃ̂��̒m���͂܂����������Ă͂��Ȃ������B�u�H�̒��쌧�ɍs���v�Ƃ������ꂾ���ŁA�ꔑ����̏����s�͏[���Ɏ����y���܂���ɑ�����̂ł���̂�����B���R�ɁA�ؑ������O�ɒ��ׂĂ������Ƃ��A���쌧�̂ǂ̂�����Ɉʒu����̂��������A��A���t���Ă͂��Ȃ������B�V�����̎ԑ��ɉf��i�F�߂Ȃ���A����ɂЂ��т��ɏo�����銽�тŋ��͂����ς��ł������B
 �@10��23��(��)�ߑO10��50���A�D�V�̏�c�w�ɉ��藧������X�U�l���o�}���Ă��ꂽ�̂́A�ؑ��ݏZ�őO�ؑ��c��c���̖x������v�ȁB��X�̈�l�����m�̊ԕ��Ƃ������ƂŁA���O�ɘA������荇���Ă������̂ł���B�x������̎Ԃɏ�Ԃ��A�x��������̓��ē��Ő�Ȑ쉈���𑖂�Ȃ���A�ŏ��Ɍ��������̂͊C��h�B�p���t���b�g�ɂ��Ɓu1625�N�ɖk���X���̏h�w�Ƃ��ĊJ�݂���A�W���͒����ɂ����铌�M�Z����̍����E�C�쎁�̏鉺���ł��������v�B��650���̊X���̗��e�ɉƕ��݂������A�X���̐^�ɗp��������Ă���B1986�N�Ɂu���{�̓��S�I�v�̂ЂƂɑI��A1987�N�ɂ́u�d�v�`���I�������Q�ۑ��n��v�̑I����Ă��邾���ɁA�X���݂͂����킸�������Ă��܂��قǁB���������ƂɁA���̊C��h�̒����т��Ă���X���������Ԃ����邱�Ƃ��ł���̂ł���B���H�̈ē��ɉ����ĎԂ𑖂点�Ă�����A�C��h�̒��ɎԂ��Ɠ����Ă����Ƃ�����B�C��h�ŐH�ׂ����鋼���́A���ɔ����ł������B �@10��23��(��)�ߑO10��50���A�D�V�̏�c�w�ɉ��藧������X�U�l���o�}���Ă��ꂽ�̂́A�ؑ��ݏZ�őO�ؑ��c��c���̖x������v�ȁB��X�̈�l�����m�̊ԕ��Ƃ������ƂŁA���O�ɘA������荇���Ă������̂ł���B�x������̎Ԃɏ�Ԃ��A�x��������̓��ē��Ő�Ȑ쉈���𑖂�Ȃ���A�ŏ��Ɍ��������̂͊C��h�B�p���t���b�g�ɂ��Ɓu1625�N�ɖk���X���̏h�w�Ƃ��ĊJ�݂���A�W���͒����ɂ����铌�M�Z����̍����E�C�쎁�̏鉺���ł��������v�B��650���̊X���̗��e�ɉƕ��݂������A�X���̐^�ɗp��������Ă���B1986�N�Ɂu���{�̓��S�I�v�̂ЂƂɑI��A1987�N�ɂ́u�d�v�`���I�������Q�ۑ��n��v�̑I����Ă��邾���ɁA�X���݂͂����킸�������Ă��܂��قǁB���������ƂɁA���̊C��h�̒����т��Ă���X���������Ԃ����邱�Ƃ��ł���̂ł���B���H�̈ē��ɉ����ĎԂ𑖂点�Ă�����A�C��h�̒��ɎԂ��Ɠ����Ă����Ƃ�����B�C��h�ŐH�ׂ����鋼���́A���ɔ����ł������B
����̏����s�ł����Ƃ��S���������̂́u�����فv�B���݂͒m���Ă������̂́A����܂łɖK��邱�Ƃ��Ȃ��A�u���Ј�x�͌��Ă����ق���������v�Ǝ��͂��猾���Ă��������ɁA�����ق̑O�ɗ������Ƃ��ɂ͌��Ƃ���Ԃł������B
 �@�����ق́A�����m�푈�Ő�v������w���̈��������E�W������{�݂ŁA1997�N�ɃI�[�v���B�u�w�����فx�Ƃ������O�ɂ́A�G���������Ɂw�����x�ł��邾���ł͂Ȃ��A�������̂ق�����w�������̊G�ɂނ����āw�����x�ł���Ƃ����Ӗ����܂܂�Ă���v�Ɛݗ��҂̌E������Y���͖{�ɋL���Ă��邪�A���ɂ́g��D���ȊG�����܂ł����������Ă������̂ɁA���ŏe�������炴��Ȃ����ꂽ�w�������́A���t�ɔ����邱�Ƃ̂ł��Ȃ��������v�������߂�ꂽ�ꏊ�h�Ƃ����v�����Ђ��Ђ��Ɗ������B�����ɂ�������炸�A�����قɂ͂�������̐l�X���K��Ă����B �@�����ق́A�����m�푈�Ő�v������w���̈��������E�W������{�݂ŁA1997�N�ɃI�[�v���B�u�w�����فx�Ƃ������O�ɂ́A�G���������Ɂw�����x�ł��邾���ł͂Ȃ��A�������̂ق�����w�������̊G�ɂނ����āw�����x�ł���Ƃ����Ӗ����܂܂�Ă���v�Ɛݗ��҂̌E������Y���͖{�ɋL���Ă��邪�A���ɂ́g��D���ȊG�����܂ł����������Ă������̂ɁA���ŏe�������炴��Ȃ����ꂽ�w�������́A���t�ɔ����邱�Ƃ̂ł��Ȃ��������v�������߂�ꂽ�ꏊ�h�Ƃ����v�����Ђ��Ђ��Ɗ������B�����ɂ�������炸�A�����قɂ͂�������̐l�X���K��Ă����B
�@�����ق���Ԃŏ����������Ƃ���Ɂu�O�R���v�Ƃ�����������B�u�����ɂ́g�������̊������h�ƌĂ��O�d�̓�������܂���v�Ɩx��������B���ɑ������Ă��Ȃ�����g�������h�炵���̂����A���ɂ͗��h�Ȋ������Ɋ�����ꂽ�B�H���Ƃ����̂ɁA�c�c�W���炢�Ă����̂ɂ͋������B�O�R���̎R�剡�ɂ́u�M�Z�f�b�T���فv����������ł������A�s�����Ԃɗ]�T���Ȃ����߂ɁA�������������Ɍ��Ȃ��玛�����Ƃɂ����B
 �@���̒n�̊����鉷��́u�ʏ�����v�B����̒n�������܂�m��Ȃ����ł������A���̖��͒m���Ă���̂�����A���{���ɂ��̖����Ƃǂ납���Ă���ɂ������Ȃ��B���̉���n�̒��ɎR�{�鎡�̐Δ肪����Ƃ����B�R�{�鎡�͐�O�̘J���_���}�̏O�@�c���ŁA�����ێ��@�̉����ɔ����Ē鍑�c��ŌnjR�������A1923�N�R���A�E���̃e���ɓ|���ꂽ�B�Δ�͑z�����đ傫���A�R��w�ɂ��ęz�R�ƍ\���Ă����B�ƁA�����܂ŋL���Ă������A�܂��{��̐ؑ��ɂ͎Ԃ͓��B���Ă��Ȃ��B���z�̓������X�ɎR�A�ɔ��낤�Ƃ��Ă���B��s�͈ē��������Ă����������ؑ��̖x��������������܂��邱�ƂƂȂ����B �@���̒n�̊����鉷��́u�ʏ�����v�B����̒n�������܂�m��Ȃ����ł������A���̖��͒m���Ă���̂�����A���{���ɂ��̖����Ƃǂ납���Ă���ɂ������Ȃ��B���̉���n�̒��ɎR�{�鎡�̐Δ肪����Ƃ����B�R�{�鎡�͐�O�̘J���_���}�̏O�@�c���ŁA�����ێ��@�̉����ɔ����Ē鍑�c��ŌnjR�������A1923�N�R���A�E���̃e���ɓ|���ꂽ�B�Δ�͑z�����đ傫���A�R��w�ɂ��ęz�R�ƍ\���Ă����B�ƁA�����܂ŋL���Ă������A�܂��{��̐ؑ��ɂ͎Ԃ͓��B���Ă��Ȃ��B���z�̓������X�ɎR�A�ɔ��낤�Ƃ��Ă���B��s�͈ē��������Ă����������ؑ��̖x��������������܂��邱�ƂƂȂ����B
�@�x�������͌Ó��u���R���v�̊X�������ɂ���A�]�ˎ���͂��㊯�l���Z��ł����ꏊ���Ƃ����B����͂Q�K���ĂŁA�����ɂ͑��z�����d�̃\�[���[�p�l�������t�����Ă���B����̑��ɔ��ǂ̑�������A������A���܂ɂ����������Ȗؑ��̔_��Ɨp�̌������������B����̒��ɓ���ƁA���Ԃ̃h�^�Ƀf���ƃX�g�[�u���u����Ă����B�d�X�g�[�u�̂悤�Ɏv����B���Ԃ̈�l���u����̓��R�[�h�v���[���[�ł����H�v�ƌ������̂ŁA�ꓯ�́g���̐l�����ɁA�����܂ł������h�Ɣނ̓��߂Ȃ��爣����A���������Ύ��̎��Ƃɂ��́A���̂悤�ȃ��R�[�h�v���[���[���������ȂƁA�v���N�������B��K�̓V�䂪�Ⴂ�B�u�́A���J�C�R������Ă�����ł����H�v�ƁA���Ԃ̈�l���w�E�B�������Ă��Ȃ��@�����ɑ��𓊂��o���Ȃ���A�J�C�R�̘b��A���̒n��̋�J�b�ȂǂŘb�͐s�����B�z�[���X�e�B�̎�����n�߂��Ƃ����̂ŁA�h���ꏊ�ƂȂ��Ă���Q�K�������Ă�������B
�@���āA�x������ɂ��܂ł��Â��Ă��Ă͂����Ȃ��B��s�́A�x������̃��S���Ԃ���āA���ē��Ȃ��ŏh���n�̓c��Ɍ��������ƂƂȂ����B�c��͐ؑ��̂Ȃ��ɂ���A���āA���蓡�������������˂ďh�����Ă����Ƃ������ƂŒm���Ă���炵���E�E�E�E�B���ē��Ȃ��B�^�]��͎��B�^�]�Ɏ��M�͂��邪�A�i�r�Q�[�^�[�Ɏ��M�͂Ȃ��B�n�}�����Ȃ���A�܂��̓X�^�[�g�B���炭�����āu�������t����Ȃ��́H�v�ƌ��������B����Ȃ�Ƃt�^�[���B�ŁA���炭�����āu�ǂ����Ⴄ�悤�ȁE�E�E�E�v�̐����B�ŁA�܂��t�^�[���B�Ȃ�₩���ŁA�Ȃ�Ƃ��c��ɓ������A�u�x�m���z�e���v�ɓ������B
 �@�ؑ��́A�]�ˎ���ɕS���Ꝅ���T����N���Ă���n���Ƃ����B�u�T��v�Ƃ����̂������̂����Ȃ��̂��̔��f�͎��ɂ͂��Ȃ����A�u�]�ˎ���̕S���Ꝅ���A�S���I�ȓ��v�����Ō���ƁA���ʂ̑��ʂ͐M�Z�ŁA�M�Z�̒��Ŕ˕ʑ��ʂ͏�c�˂ł���B���̏�c�˂̗̒n�̒��ŁA���ɕS���Ꝅ�������N�������Ƃ���Ƃ��Ē��ڂ����̂��A���݂̐ؑ��ɓ����Ă��鑺�X�Ȃ̂ł���v�Ɛؑ�����ψ���̃p���t���b�g�͏Љ�Ă���B�����āA���̐ؑ��̒��ɁA�`�����܂����K(�ق���)������Ƃ����̂��B�u�`���v�Ƃ͉����H�B�p���t���b�g�ł͎��̂悤�ɋL���Ă���B�u�i�Ꝅ�́j�ŏ��̉����Ƃ�ƂȂ�����A�����l�ƂȂ邱�Ƃ́A�傫�ȋ]�������Ƃł������B����������o��̏�ŁA�����l���������A�����������v�����ʂ������Ƃł��A�l�g�䋟�̌`�ŏ��Y���ꂽ�̂��`���ɂق��Ȃ�Ȃ��v�B�܂�A�命���̑��l�̗��v��������邽�߂ɁA����͈Ꝅ�̎�d�҂Ƃ��Đl�g�䋟(�ЂƂ݂�����)�ɂȂ�]���ɂȂ��Ă������l���A���l�������߂܂����̂��u�`�����K�v�ƂȂ��č����܂Ŏc����Ă���̂ł���B���̐ؑ��ōŏ��́u�S���`���T�~�b�g�v���J����A��N�̏H�ɂ͐ߖڂƂȂ�10��ڂ̃T�~�b�g���J����Ă���B �@�ؑ��́A�]�ˎ���ɕS���Ꝅ���T����N���Ă���n���Ƃ����B�u�T��v�Ƃ����̂������̂����Ȃ��̂��̔��f�͎��ɂ͂��Ȃ����A�u�]�ˎ���̕S���Ꝅ���A�S���I�ȓ��v�����Ō���ƁA���ʂ̑��ʂ͐M�Z�ŁA�M�Z�̒��Ŕ˕ʑ��ʂ͏�c�˂ł���B���̏�c�˂̗̒n�̒��ŁA���ɕS���Ꝅ�������N�������Ƃ���Ƃ��Ē��ڂ����̂��A���݂̐ؑ��ɓ����Ă��鑺�X�Ȃ̂ł���v�Ɛؑ�����ψ���̃p���t���b�g�͏Љ�Ă���B�����āA���̐ؑ��̒��ɁA�`�����܂����K(�ق���)������Ƃ����̂��B�u�`���v�Ƃ͉����H�B�p���t���b�g�ł͎��̂悤�ɋL���Ă���B�u�i�Ꝅ�́j�ŏ��̉����Ƃ�ƂȂ�����A�����l�ƂȂ邱�Ƃ́A�傫�ȋ]�������Ƃł������B����������o��̏�ŁA�����l���������A�����������v�����ʂ������Ƃł��A�l�g�䋟�̌`�ŏ��Y���ꂽ�̂��`���ɂق��Ȃ�Ȃ��v�B�܂�A�命���̑��l�̗��v��������邽�߂ɁA����͈Ꝅ�̎�d�҂Ƃ��Đl�g�䋟(�ЂƂ݂�����)�ɂȂ�]���ɂȂ��Ă������l���A���l�������߂܂����̂��u�`�����K�v�ƂȂ��č����܂Ŏc����Ă���̂ł���B���̐ؑ��ōŏ��́u�S���`���T�~�b�g�v���J����A��N�̏H�ɂ͐ߖڂƂȂ�10��ڂ̃T�~�b�g���J����Ă���B
�@���̐ؑ��B10���̉��{�Ƃ��Ȃ�ƁA���ӂ̗₦�邱�ƁB�z�e���ł͂��łɒg�[��������A�Q��Ƃ����g�[��t�����܂ܕz�c�ɂ�����B�ł��A�x�m���z�e���̖�̘I�V���C�͍ō��ł������B�_�ЂƂȂ����ɂ܂�ۂ̌����P���A�d�����Ñ�����d�b�������܂ł͒ǂ��Ă͗��Ȃ��B�j���w�S�l�͖�̂X��30���ɑS���A�n���ɓ������B
�@��24��(��)���A�z�e�����猩�鑺�͎R�ɃK�X���������Ă��āA�����ɂ��������B���X���A�x�����}���ɂ����B�x������̒��ԂŁA�ȑO�A���{���Y�}�̑��c��c���߂Ă����Ƃ������V�̐l�ƕx�m���z�e�����ō����B���̏��V�̐l�A�z�e���̑ҍ����Ō���������Ў�ɁA�z�e���̏]�ƈ��̌��������X�Ɍv���Ă����B�������͂��̏��V�̐l���u�f�Ï��̐l���o���ł���Ă��āA�����Őf�@���s�Ȃ��Ă���v�Ə���ɐ����B�R�[�q�[�Ў�ɂ������Ō��Ȃ���A�g�ǂ��炪����҂��킩��Ȃ��ˁh�ƁA���V�̐l�����҂���ɁA�]�ƈ�������҂���ɒu�������Ē��߂Ă����B������A�x������Љ�ꂽ�Ƃ��ɂ͐����A�������B���V�̐l�͌��݁A��Ð����̎d�������Ă���Ƃ����B
 �@�x������̈ē��ő��̋���ψ���֏o�����A�`�������W���������w��A�`�����K��Δ�E��Ȃǂ����ĉ�����B���̂���ɂ͋�͈�Ăɐ���n��A�㒅������Ȃ����炢�̗z�C�ɁB�`���W�̎j�Ղ���������Ƃ́A�x�������̑O��ŁA��̏��V�̐l����`���̗��j�̍u�`����u�B���H���R�ŐH�ׂ�Ƃ����̂ŁA���C����ĎԂŎR���������B�Ȃ�ƁA�x������͎��g�����L����R�������Ă���B���̎R�ɓ����āA���H�O�ɂ��̂����܂ő̌����Ă��܂����B �@�x������̈ē��ő��̋���ψ���֏o�����A�`�������W���������w��A�`�����K��Δ�E��Ȃǂ����ĉ�����B���̂���ɂ͋�͈�Ăɐ���n��A�㒅������Ȃ����炢�̗z�C�ɁB�`���W�̎j�Ղ���������Ƃ́A�x�������̑O��ŁA��̏��V�̐l����`���̗��j�̍u�`����u�B���H���R�ŐH�ׂ�Ƃ����̂ŁA���C����ĎԂŎR���������B�Ȃ�ƁA�x������͎��g�����L����R�������Ă���B���̎R�ɓ����āA���H�O�ɂ��̂����܂ő̌����Ă��܂����B
�@�x������̖{�E�͔_�ƁB�ǂꂭ�炢�_�n��R�т������Ă��邩�͒m��Ȃ����A20�H���炢�̌{�������A�R�Ɍ��������n�ɂ͗r�Q������������ɂ��Ă���B�Ƃ̗����ɂ͏����Ȑ��c���J�A���@����̕������яオ�点��������点�Ă���B���ɂ����c�┞�c�������Ă���A�v�w�Ɩ�����̂R�l�Ŕ_�Ƃɐ����o���Ă���B�u���̈�l���ꏏ�ɔ_�Ƃ�����Ă���Ă���v�Əq�ׂ鉜����̊�͂ƂĂ����ꂵ�����B���̖�������R�̒��H�ɂ������Ă��ꂽ�B
 �@�ؑ��̂����܂��ɁA����̑�@���O�d�������w�����B���q���㖖���̌����ŁA���쌧�Ɏc��O�d���ł͍ł��Â��A�ޗǂ⋞�s�̎O�d���ɂ��C�G���閼���Ə̂����B�g���Ԃ�̓��h�Ƃ��Ă�A���R�����������l�����x���U��Ԃ��Ė��c��ɂ��Ƃ����B �@�ؑ��̂����܂��ɁA����̑�@���O�d�������w�����B���q���㖖���̌����ŁA���쌧�Ɏc��O�d���ł͍ł��Â��A�ޗǂ⋞�s�̎O�d���ɂ��C�G���閼���Ə̂����B�g���Ԃ�̓��h�Ƃ��Ă�A���R�����������l�����x���U��Ԃ��Ė��c��ɂ��Ƃ����B
�@�x������Ɍ������A��c�w�̍\���ɏ������������́A�ꔑ����̍D�V�̐ؑ��ɑ喞���B�[��������������Ԃ�U��Ԃ�Ȃ���A��{�w�܂ł̈ꎞ�Ԃ������B
102�Ŏ��m�l�̗��j
�@�X�����߁A�ޏ��͉Ƒ��Ɉ͂܂�Ȃ��炻�̐��U�ɖ������낵���B���N102�A���Ɉꐢ�I���������B�ޏ��Ƃ̕t��������15�N�O����B�����s�c��c���I���ɏ����킷�邽�߂ɖK��Ă���̂��ƁB15�N�O�Ƃ͂����Ă��A���łɔޏ��͂��̎��_��87�ɂȂ��Ă����B
�@15�N�O�̔ޏ��͍��͋Ȃ����Ă������A������Ȃ���X������A���ɏo��ƃj�R�b�Ə��Ȃ��猾�t�������Ă��ꂽ�B�ޏ��̎�͊G��B���G�����������ʉ悾�������͖Y�ꂽ���A�A���f�p���_���W�ɏo�W���A������ƈꏏ�ɌW�Ȃǂ��J���Ă����B�ޏ��̊G�ň�ۂɎc���Ă�����̂ɁA�ޏ��̃_���i���܂�`�������̂��������B���ւŖj������Ȃ���l���������Ă���p�𐳖ʂ���Ƃ炦���G�ł���B
�@�ޏ��̃_���i���܂́A�����ޏ��ƒm�荇�������ɂ͂��łɂ��̐��̐l�ł͂Ȃ��A�݂肵���̎p�͎ʐ^�ł������ڂɂ����������Ƃ͂Ȃ��B���̃_���i���܂́A1944�N�́u���l�����v�Ō�������A1945�N�W���Ɏߕ������܂ō��������𑗂��Ă���B
�@��O�A���̕v�w�́A�����ȕ��M�ƁE�����Ґl�i����͂炱��ЂƁj������̂Q�K�ɂ����܂������Ƃ��������B�����Ґl�̊肢������A�������̉��E�w�Ɛ����E�w�̒��ԂɈʒu����Q�K���Ă̑傫�ȉƂ�ނ������܂����߂Ɏ�A���������͂P�K�ɏZ�݁A�Q�K��ނɂ��Ă������B�����Ґl�����̉Ƃɂ��낪�肱�̂�1929�N12�����{�B���N�V���P���ɑ����Ґl��������E�o����܂ŁA���̉Ƃ͑����Ґl�́u������Ɓv�ƂȂ����B
�@�����Ґl���Q�K�ɏZ��ł������N�ԁA���̂Q�K�ɂ͂����Ȑl���K�ꂽ�B�u���N�O���\�ܓ��v�u�}�����ҁv�u�I�H�D�v�̍�҂ł��鏬�ё��������̈�l�ł���B�u�����͍����R�̒����𒅂Ă��āA�ƂĂ����킢���V�����ł������v�ƁA�ޏ������Ɍ���Ă��ꂽ���Ƃ�����B�����x�@�ɘA�s����A���̓��̂����ɂ�����ʐl�ƂȂ������ё����O�A����ɏ������ꂽ���Ƃ̂���l�����A�ǂ�قǂ����ł��낤���B���͔ޏ��ɁA�u���̎��̂��Ƃ������L���Ă����Ăق����v�Ɨ����Ƃ����邪�A���̖ڂ������ɑ��E�������Ƃ͐S�c��ł���B
�@�����Ґl���Q�K�ɂ����܂��Ă������ԁA���̉Ƃɂ͂�����l�A�Z�l�������B���̕v�w�̂Q�ɂȂ閺�ł���B���̖��́A���낪�肱�����Ґl�ɂƂĂ��Ȃ����炵���A�ނ�ǂ������āA��������イ�Q�K�ւƏオ���Ă������B���̍��̃G�s�\�[�h���A�_���i���܂��������{�Ɏ��̂悤�ɋL����Ă���B�u�L�[�����͖l�������C�ɂ͂���ƕ��C��̑O�ɍ����Ă����ƌ��Ă����B�ƂĂ��G�b�`�ȐԂ�������B����܂肶���ƌ��Ă���̂ł������������Ă��܂��v�B����͂����܂ł��Ȃ��A�����Ґl�̌��t�ł���B�u�L�[�����v�ƌĂ��G�b�`�Ȗ��́A�ޏ���102�ł��̐�������܂ŋ��ɐ����𑗂�A�ޏ����߂����Ă����ƂɁA���݂����C�ŕ�炵�Ă���B
�@�ޏ���100���}�������A���͓}�̒��ԂƂƂ��ɔޏ��̎����K�₵�A100�̒a�������j�����B���̍��̔ޏ��͊O�֏o�������Ƃ��Ȃ��A����̃x�b�h�ʼn߂������X�𑗂��Ă������߁A�K��҂��قƂ�ǂȂ��A�n���̋��Y�}�̎s�c��c�������ꂾ������������L�����玸����ƂȂ��Ă����B������A���⎄�̒��Ԃ��K�₷��i�ɂȂ��āA���́u�L�[�����v�͔ޏ��ɁA�����ǂ������l���ł���A�ǂ�ȕ��̂Ȃ̂�����������ƌ��A�ޏ����s������Ȃ��悤�ɓw�߂��B�����Ă��悢��A�Ђ����Ԃ�̂��ΖʁB�ޏ��͏��߂Ď�������Ƃ��������ł��������A�ޏ��̊J����Ԃ��������낢�B�u��`�A����Ȃɂ����j���Ƃ͎v��Ȃ������v�B���̃z�[���y�[�W��ǂ܂�Ă���݂Ȃ���B�����ł��B
�@100�̂��j���ŖK�₵�Ĉȍ~�A�ޏ��Ƃ͂��ɉ���Ƃ͂Ȃ������B100�ł���Ȃ��猾�t���������]���������肵�A�q�ǂ��̂悤�Ȃ��킢���Ί�ƁA���킢�����Ō}���Ă��ꂽ���̎p�́A���̎��ɎB�e�����L�O�ʐ^�Ō���ق��͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B��O�̋�Y�̎������ޏ�����A�����Ƃ����Șb�������Ă�����Ǝv�����̍��ł���B
�����}���ّI��
�@�ߏ��̃K�\�����X�^���h����u�X�̂��m�点�v���������B�K�\���������łȂ��A�����Ԃ�o�C�N�̓_���E�C���A���]�Ԃ̃p���N�����܂Ŏ肪���A�����ԁA���ꂽ�X�ł������B
�@�u�n���̃^���N���V�������A���܂Ȃ��̔�p���o����̂Łv�ƌ������A�K���ɘa�ɂ�閳�l�K�\�����X�^���h�̐i�o���A�o�c���������Ă��邱�Ƃ͔ۂ߂Ȃ��B
�@�}�X�R�~�ł́A�����}���ّI����A�����A���҂̌��������ׂ��ɒm�点��B����ǂ��A�ނ炪���ɂ��錾�t�ɂ͐����͂��������Ȃ����肩�A�ǂ��Ɍ������Č��t���Ă���̂������A�킩��Ȃ��B
�@�K�\�����X�^���h�́A�x�݂Ȃ��X���J����悤�ɂȂ����B�������u�\�����v�v�u�K���ɘa�v�����Ԍ��҂̖ڂɂ́A���̐l�����̎p�͂������ē���͂��Ȃ��B��ƌ����A���}�������ŘJ������炵�Ă��邩�炾�B�����s�݂̐��������I�T���o���B
�i�u����Ԃ���v2007�N�X��23���t���j
�䕗�c�f�Ǝs����ψ���̑Ή�
�@����25���ȏ�̖\��������������āA�䕗�X�����V��(��)�����A�֓��n�����c�f�����B�䕗�����ŏ�����s�ł��A�������������������|����Q�����܂�A�����w�Z������ق̉J�R�肪���������B�䂪�Ƃ͖ڂɌ������Q�͂Ȃ��������A�O��(�U��)���������肩��́A�������ʼnƑS�̂��h���n���B�J�˂��Ȃ��Z��Ȃ̂ŁA���K���X�ɕ����������Ċ���͂��Ȃ����ƁA���������Ȃ������B
�@���i�͋C�ɂ��Ƃ߂Ȃ��C�ۏ��ɁA�q�ǂ������͎��������Ă��B�V�����o�Z�ɂȂ�̂��x�Z�ɂȂ�̂����C�ɂȂ邩�炾�B�������A�q�ǂ��͈�v���āu�x�Z�v������Ă���B�������A���̌��_�͂V�����̋�͗l��҂��˂Ȃ�Ȃ��B�u�䕗��A�����ƕ��݂�x���v�ƁA�q�ǂ������͊肢�z�c�ɂ��������B
�@�V�����A�O�͕��J�Ƃ��ɋ����B�������w�Z����̎w���́u�ߑO�V�����߂��Ă������n���܂��͑����k���̖\���x��������Ȃ��ꍇ�͗Վ��x�Z�Ƃ���v�Ƃ������́B���V���A�Ƒ��S���Ńj���[�X������B�C�ۏ��́u����23��ɖ\���x��v�̕B�����ʼn䂪�Ƃ́g�n�e�H�h�ƂȂ����B�u����23��v�Ƃ����ꍇ�A����͊w�Z�̎w�������ł����u�����n���v�ɍ��v����̂��H�B
�@�J�~����͂܂��A������s�����ɓd�b�����B���̎��Ԃɉ�����͎̂s�����{���ɂP�K�̎{�݊Ǘ�����B����ψ���ɂȂ��ł��炨���Ƃ������A���̎��ԑт͂܂�����ψ���͗��Ă��Ȃ��Ƃ̂��ƂŁA�Ȃ��ł��炦�Ȃ������B���̎��ԑт̎s���������ł���͂��̎{�݊Ǘ�����́A����ψ���牽�̎w�����������Ă͂��Ȃ��l�q�ł������B���ɃJ�~����͓쒆�w�Z�ɓd�b�����B�d�b�̌Ăяo���R�[������葱������A�d�b�ɏo���l�́A�u�w�����k���܂��͓����n���x�����f��Ȃ̂ŁA�w����23��x�͊Y�����Ȃ��v�Ƃ̐����B����āu�o�Z�v���m�F���ꂽ�B�قǂȂ����āA�����ʂ���l���w�Z�̘A���Ԃ�����A�u�o�Z�v���w�����ꂽ�B
�@�w�Z�ɂ���āA�ی�҂ւ̎w�����e�͈قȂ��Ă����B�u�����̎q�ǂ��̊w�Z�́w���A�A���Ԃ��āA�o�Z���x�Z���̂��m�点���s�Ȃ��x�Ƃ����w�����e�������v�Ɠ����c���̌��t�B����A��ꏬ�w�Z�́u�Q���ԌJ�艺���āA���ƊJ�n�v�ł������B�u�ߑO�V�����߂��Ă������n���܂��͑����k���̖\���x��������Ȃ��ꍇ�͗Վ��x�Z�Ƃ���v�́A������s����ψ���e�w�Z�ɏo�����w�������ł��邪�A�ŏI���ʂ�d�b�A���ԂœO�ꂷ��w�Z������A���ƊJ�n���Q���ԌJ�艺����w�Z�����܂�A�܂��A�쒆�w�Z�̂悤�ɁA����̃e���r�ȂǂŊe�ƒ낪�o�Z�Ȃ̂��x�Z�Ȃ̂����u���Ȕ��f����v�Ƃ����Ƃ�������܂ꂽ�B
�@�Q�Ă��̂̓J�~����B�Ȃɂ����l���w�Z�̖��͂��̓��A�Љ�Ȍ��w�����Ƃɑg�ݍ��܂�Ă���A�u�ٓ����Q�v���`���t�����Ă������炾�B�������ő䏊�ɗ����A�ٓ������ɒǂ�ꂽ�B
�@���̓��A�쒆�w�Z�ł́A�ȑO����v�悳��Ă����ی�҉�J���ꂽ�B�u�ی�҉�ł́A����̓쒆�w�Z�̎w���̂�����ɋ���������ꂽ�v�ƁA�J�~����̌��t�B����A�쒆�w�Z�̑��q�̃N���X�ł́u�Q�l�قǁA�x��Ċw�Z�ɗ����v�Ƃ̂��ƁB������s����ψ���̊e�w�Z�ւ̎w���̂�����ɖ�肪����Ɗ�����̂́A���������H�B
�����́u�ҏ��v
 �@���̉āA�ϑ��j��ō��́u40.9�x�v����ʌ��Ŋϑ����ꂽ�B�L�^������ꂽ16���A�u�̉���荂���C���ȂǑz���ł��Ȃ��v�ƌ��ɂ��Ȃ���A���͋����E����ʼnċx�݂��߂����Ă����B �@���̉āA�ϑ��j��ō��́u40.9�x�v����ʌ��Ŋϑ����ꂽ�B�L�^������ꂽ16���A�u�̉���荂���C���ȂǑz���ł��Ȃ��v�ƌ��ɂ��Ȃ���A���͋����E����ʼnċx�݂��߂����Ă����B
�@���x�̌����Ă�����ނ��Ƃ̂ł��Ȃ������̉Ă��瓦��悤�ƁA�ق�̐����̋����ł��������A���̋����ł������A���A35�x�O��Ɍ�����ꂽ�B�������A���{�C���̉Ă͎��C�����������͂邩�ɏ��Ȃ��A�u���N�͏����v�Ƃ̕�e�̌��t�ł͂��������A�߂����₷�������𑗂邱�Ƃ��ł����B
�@�A���̖ҏ��ł͂��邪�A������͏H���}����B�}�����Ƃ���ɖҏ��������Ă��������ނ̂�����A�s���̂悢���̂ł���B���̏H���}����O�ɁA�����Ă̒��߂�����Ɏs�c�O�����h�ł́A37��ڂƂȂ镽�a�~�x�肪�ԊJ�����B���a���@����������鍡���A���a���Ăт�������g�݂́A����Ȃ鉊�����߂���B���̉��͓~�ɂȂ��Ă��������Đ����邱�Ƃ��Ȃ��قǂɁB
�i�u����Ԃ���v2007�N�W��26���t���j
�~�J����
 �@�挎14���ɔ~�J���肵���֓��n���́A��J���]���߂��������ł��A������C�z�������Ă͂��Ȃ��B�ߋ�30�N�̕��ϔ~�J�������V��20���O��Ƃ�������A��T�ԗ]�A�x��Ă���B �@�挎14���ɔ~�J���肵���֓��n���́A��J���]���߂��������ł��A������C�z�������Ă͂��Ȃ��B�ߋ�30�N�̕��ϔ~�J�������V��20���O��Ƃ�������A��T�ԗ]�A�x��Ă���B
�@��N�̔~�J�����͂V��30���������B��N�Ɠ����ł���A��������̌��ʂ�����������Əd�Ȃ�A�\�����������̔~�J���������҂ł���B
�@�~�J�����ɂ́A�����m���C���̕��N���������Ȃ��B�~�J�O������C�ɉ����グ�A�������肵�����V��������������������̂��B�����⍑���ł́A�ǂ̐��͂������m���C���ɂȂ肤��̂��A�������茩��߂邱�Ƃ����߂���B�O���������グ��͂��̐��͂��A�C��������O���Ɠ����������ʂ����A�����ɕ��J��^���邱�Ƃ����肤�邩�炾�B
�@������̔~�J�����C�ɐ��炷�����́A�Ȃ�Ƃ����Ă��u�������Ȗ�}�v�B���ꂽ�����q���t���̋�����؎�炸�ɁA���炵�����߂����Ă��邩�炾�B�V��15���A���̓}��85���}�����B
�i�u����Ԃ���v2007�N�V��29���t���j
�p�b�`�M�I
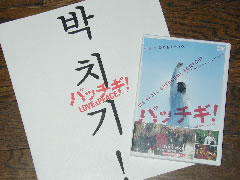 �@�䓛�a�K�ḗu�p�b�`�M�I�v���e���r�ŕ��f����A����ő��e�����J���ꂽ�B����������{�ɏZ�ޒ��N�̐l�����̋�Y�ƌ����ɂ��炷�������܂��e�[�}�ƂȂ�A�ϏI����������Ƃ肱�ɂ��Ă���B �@�䓛�a�K�ḗu�p�b�`�M�I�v���e���r�ŕ��f����A����ő��e�����J���ꂽ�B����������{�ɏZ�ޒ��N�̐l�����̋�Y�ƌ����ɂ��炷�������܂��e�[�}�ƂȂ�A�ϏI����������Ƃ肱�ɂ��Ă���B
�@�V�c�����{�͐펞���A���N�⒆������70���l�ȏ�������A�s���A�ш�k���̗��R�Z�p�����������H����e�n�̍H��A�Y�z�Ȃǂœ�������ƂƂ��ɁA�����͐�n�ɑ����A�]�R�Ԉ��w���������ꂽ�B�ĉ��@�ψ�����{���{�Ɍ����Ӎ߂����߂錈�c���̑��������A���{���t�������ɔے肵�悤�Ƃ��A���j�̐^������ڂ����ނ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@������s�ɂ͊O���l��2,300�l�ȏ�A�Z��ł���B��ԑ����̂͒����̐l(1,007�l)�A��Ԗڂ����N�E�؍��̐l(429�l)�B��ԋ߂����ł���Ȃ���A���̐ӔC�҂����j��c�߂�ԓx���Ƃ��Ă��邽�߂ɁA���N�����̓�k���f�̂悤�ɁA�����ɂ��u�C���W���́v������Ă���B
�i�u����Ԃ���v2007�N�V���P���t���j
���@���
�@�����q�ǂ��̍��́A���q�������ɏo�����邱�ƂȂǍl�����Ȃ������B�Ƃ��낪16�N�O�̘p�ݐ푈�ő|�C�����y���V���p�ɏo�q�����A���N�ɂ̓J���{�W�A�Ɏ��q����h���B���ꂩ��11�N���2003�N�ɂ́A���̃C���N�ɕ�����g���ďo�����Ă������B�������u��팠�̔۔F�v�L�������@������A����̎g�p���~�߂����Ă���B
�@����}���{��c�̌���F�߂����߂ɍ������[�@���������A�R�N�ォ��͌��@���肪�\�ȏɂȂ�B���̖���}�́A����ψ����p�~����Ǝ咣�B���ɒ��ځA����ɉ�������A�q�ǂ������Ɂu�����S�v���������߂Ƃł������̂��낤���B
�@����A���@�~���[�W�J���u�L�W���i�[�v���ς��B�F�R�ł���͂��̓��{�R�������ɏe�������A���������v�B���̗��j�́A�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ����P�ł���B�u���@������Ȃ�Ƃ��Ă����ʂ��˂v�B���ӐV���Ɍ�������Ƃɂ����B
�i�u����Ԃ���v2007�N�U���R���t���j
�}�@��
�@�����E�����������A������Ō��@��ς��邽�߂̎葱���@�Ă𐬗������悤�Ƃ��Ă���Ȃ��A�S��30���̖�A�s���̗���s�Łu�s�[�X�i�C���R���T�[�g in ����v�Ƒ肵���W�����J���ꂽ�B�u�i�C���v�Ƃ͌��@�X���̂��ƁB�u���@�X���̉����������Ȃ��v���Ƃ��A�̂�ʂ��ăA�s�[������Ƃ������g�݂ł���B
 �@��ꕔ�́A�O�����̂i�q������������Ŋ������Ă��鉹�y�D���̎s���c�̂��A���a���ނƂ����I���W�i���Ȃ��I����Ƃ������́B�o���c�̂́u���ɂ������y��y���v�u�^�v��(�܁[����)�v�u�܂��̂������S����v�u���炵����������v�u�킽���̋�����̂���v�u�������q���v�ȂǁB�u�킽���̋�����̂���v�ɂ͒m�l���Q�����Ă���A�m�l���쎍�����u�킽���̋���v�Ɍ� ���ꌀ��̉��c���q���Ȃ����A�����A��I���ꂽ(�ʐ^�Q��)�B �@��ꕔ�́A�O�����̂i�q������������Ŋ������Ă��鉹�y�D���̎s���c�̂��A���a���ނƂ����I���W�i���Ȃ��I����Ƃ������́B�o���c�̂́u���ɂ������y��y���v�u�^�v��(�܁[����)�v�u�܂��̂������S����v�u���炵����������v�u�킽���̋�����̂���v�u�������q���v�ȂǁB�u�킽���̋�����̂���v�ɂ͒m�l���Q�����Ă���A�m�l���쎍�����u�킽���̋���v�Ɍ� ���ꌀ��̉��c���q���Ȃ����A�����A��I���ꂽ(�ʐ^�Q��)�B
�@��ꕔ�̏o���҂̂Ȃ��ň�ۂ����������̂́A�u�^�v��(�܁[����)�v�B�z��ꂽ�p���t���b�g�ɂ��A�����s�ݏZ�̃A�}�`���A�t�H�[�N�V���K�[�ŁA���C�u�n�E�X�ʼn��t�����𑱂��Ă���Ƃ����B�M�^�[�̉��t�͂��悭�A�������̏��͂��Q���Ă���B���ꂵ����������A�����ق��ɂ����S����^���錩�����ł������B���̐l�̃X�e�[�W�͍ēx�A�����Ă݂����Ǝv�����e�ł������B
�@��́A�u�}�ؓ��ƎG�ԏm�v�B�u�}�ؓ��v�͒m��l���m��u�t�B�[���h�t�H�[�N�v�̐��ҁB1970�N�ォ��80�N��ɂ����ċ��s�𒆐S�Ɋ������Ă����u�U�E�i�^�[�V���[�E�Z�u���v�ɉ̂���Ă����l�ŁA��\�ȂɁu���̎q�ǂ������ցv�u�킪��n�̂����v�u���Ȃ����閾��������q�ǂ������v�u���ɐl���Ƃ�������̂�����Ȃ�v�ȂǁB
�@�}�ؓ������߂Ēm�����̂́A25�N�قǑO�B�����������Ă����J�g�N�w�l���̃L�����v�������R�s�ōs�Ȃ��A�L�����v�̎����C�x���g�Ɋ}�ؓ���������A�ނ̃M�^�[�e������ڂ̑O�ŕ������̂��ŏ��B�ǂ�ȉ̂��̂����̂��͑S���o���Ă��Ȃ����A�Ƃɂ������[���A�����Ղ�̂��b���Ɖ̂������Ƃ������Ƃ����͋L���ɂ���B
�@���ɂ��ڂɂ��������̂́A20�N�قǑO�B������s���ɖ{���n���\���Ă������ꌀ��̒n�����K��ŁA���݂̏�������h���̓��ׂ�̃r���̒n���ł�����(���݂́A���̃r���Ɂu�ӂ邳�ƃL�����o���v�����������\���Ă���)�B���̍��̊}�ؓ��́u�t�H�[�N�X�v�Ƃ����o���h��g��ł���A���̋L���ł́A�u�U�E�i�^�[�V���[�E�Z�u���v�̃����o�[�ł��������Ȍ�Ə�c�������o�[�ɓ����Ă����悤�Ɏv���B�����A�߂Ă����E��̐l����U���ăR���T�[�g�ɏo�����Ă��������́B���������̂́u�U�E�i�^�[�V���[�E�Z�u���v�̋Ȃ����S�������悤�Ɏv���B�Ƃ͌����Ă��A�}�ؓ����Ȃ������Ă����̂����B�Ƃɂ����A���̎��̃X�e�[�W�͑f���炵�������B������s�̊X���̃r���̈ꎺ�Œ����Ă���̂ɁA���̓��̒��͌̋��̕���̓c�ɂŒ����Ă�����o�Ɋׂ��Ă��܂����̂�����B�u�t�H�[�N�X�v�͒����������A1991�N����ނ̓\�������ɓ������B
�@���āA�S��30���̖�B�}�ؓ��ƎG�ԏm�́A���b���Ɖ̂������Ȃ�����ɂP����30�����y���܂��Ă��ꂽ�B�̂����Ȃ́u�킪��n�̂����v�u���̓��̎��Ɓv�u���Ȃ����閾��������q�ǂ������v�u�z�E�Z���ԁv�u���ҁv�u�N�������ɐ�����q�ǂ��Ȃ�v�u�s�[�X�E�i�C���v�B���ɂ��̂����Ǝv�����A�o���Ă���͈̂ȏ�V�ȁB�}�ؓ��͋Ȃ̍��Ԃ����܂Ɍ��@����̏d�v���Ɨ��j���q�ׁA�����̌��@�����̓����ɑ��Čx����炵�������B
 �@�u�z�E�Z���ԁv�����߂Ē������B���e�͏]�R�Ԉ��w�̖��B�G�ԏm�����o�[�̃M�^�[�e�����̔M���ŁA�ׂŒ����Ă����Ȃ͗܂���ł����B�u���̓��̎��Ɓv�͕���Ɂu�V�������@�̂͂Ȃ��v�Ƃ���悤�ɁA���A���a���@���ł����Ƃ��ɓ����̕����Ȃ�1947�N�ɔ��s�����u�����炵�����@�̂͂Ȃ��v�Ƃ������q����ɁA�搶�����ƂŎq�ǂ������ɐV���@�̂͂Ȃ������Ă���l�q���̂������́B���łɂb�c�ł��̉̂͒m���Ă������A�i�}�̊}�ؓ��̖쑾�����́A���������͂ł������B�}�ؓ��͍��N70�B�K���K�����͂ЂƂ��킾���A�s�N����̐L�т₩���͐������l�q�B�}�ؓ�������悤�ȉ̂𑼂ɂ����l����������Ȃ��Ȃ��ŁA�ނɂ͂��܂ł����C�Ŋ��Ăق����Ɗ肤�B �@�u�z�E�Z���ԁv�����߂Ē������B���e�͏]�R�Ԉ��w�̖��B�G�ԏm�����o�[�̃M�^�[�e�����̔M���ŁA�ׂŒ����Ă����Ȃ͗܂���ł����B�u���̓��̎��Ɓv�͕���Ɂu�V�������@�̂͂Ȃ��v�Ƃ���悤�ɁA���A���a���@���ł����Ƃ��ɓ����̕����Ȃ�1947�N�ɔ��s�����u�����炵�����@�̂͂Ȃ��v�Ƃ������q����ɁA�搶�����ƂŎq�ǂ������ɐV���@�̂͂Ȃ������Ă���l�q���̂������́B���łɂb�c�ł��̉̂͒m���Ă������A�i�}�̊}�ؓ��̖쑾�����́A���������͂ł������B�}�ؓ��͍��N70�B�K���K�����͂ЂƂ��킾���A�s�N����̐L�т₩���͐������l�q�B�}�ؓ�������悤�ȉ̂𑼂ɂ����l����������Ȃ��Ȃ��ŁA�ނɂ͂��܂ł����C�Ŋ��Ăق����Ɗ肤�B
�@���̓��̃`�P�b�g�͂Q��~�B�Ƒ��S�l�ŎQ�������̂łW��~�ƂȂ������A�\���ɖ����ł���X�e�[�W�ł������B�X�e�[�W�I����A���r�[�Ŕނ̂b�c�Ə��Ђ̃T�C����������B�Ȃ͑����Ɋ��������̂ł��낤�B�b�c�Ə��ЁA�̏W���w���B���������T�C����������Ă����B�u�ʐ^���B���Ă���낵���ł��傤���H�v�Ɛq�˂�ƁA�}�ؓ��́u�ǂ����v�Ɖ����n�j�B�ȂƉ���猾�t�����킵�Ȃ���A�Ȃ��w���������Ђ�̏W�ɃT�C�������Ă����i�ʐ^�Q�Ɓj�B
�S���w�̓e�X�g
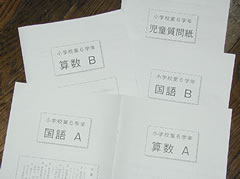 �@24���A���w�Z�ł�43�N�Ԃ�A���w�Z�ł͏��߂Ă̑S���w�̓e�X�g�����{���ꂽ�B���w�U�N�̖��̐����ɂ��ƁA���O�̗��ɂ͉����L�ڂ����ɁA���O�̃t���K�i���������ɑg�Əo�Ȕԍ�����Ȃ鐔�����L�ڂ����Ƃ����B�P���Ԗڂ͎Z���`�ƍ���`�A�Q���Ԗڂ͍���a�A�R���Ԗڂ͎Z���a�A�S���Ԗڂ̓A���P�[�g���s�Ȃ��A�����A�����A���P�[�g�p��������ƁA99���ڂ��̎��₪����ł����B �@24���A���w�Z�ł�43�N�Ԃ�A���w�Z�ł͏��߂Ă̑S���w�̓e�X�g�����{���ꂽ�B���w�U�N�̖��̐����ɂ��ƁA���O�̗��ɂ͉����L�ڂ����ɁA���O�̃t���K�i���������ɑg�Əo�Ȕԍ�����Ȃ鐔�����L�ڂ����Ƃ����B�P���Ԗڂ͎Z���`�ƍ���`�A�Q���Ԗڂ͍���a�A�R���Ԗڂ͎Z���a�A�S���Ԗڂ̓A���P�[�g���s�Ȃ��A�����A�����A���P�[�g�p��������ƁA99���ڂ��̎��₪����ł����B
�@���O�����͍̂���A�w�Z�ʂ̐��ь��\��ы��������ɂȂ����Ă����̂ł͂Ȃ����Ƃ������ƁB�w�Ԃ��߂̊w�Z���A�������邽�߂̏�Ƃ���Ă��܂��A�w�Z�͊y�����Ȃ��ꏊ�ɕς���Ă��܂��B
�@�S�����I���ɋ߂Â��A���F�����S�J�o�[�̃����h�Z����w�������V��N�����V�������Ɋ���Ă����l�q�B�F�����Ƃ���ꍇ���Ȃ���s�������p�ɁA�̂т̂тƈ���Ăق����ƐS����v���B
�i�u����Ԃ���v2007�N�S��29���t���j
�����s�̍���ҕ���
�@���̂W�N�̊ԂɁA�����s�̍���ҕ����͑啝�ɐ�̂Ă�ꂽ�B1999�N�����A�����̃V���o�[�p�X���Ă���������s����6,122�l�B�����ł͑S�����L���ɂ���Ă��܂����B�}�����ƌĂ���Ô���͓����A10,767�l�����Ă������A���N�U���Ő��x�͔p�~�����B�܂��A65����x������A70����͌��z�T���T��~�x������Ă����Q������蓖�i�V�l�����蓖�j�͓����A1,099�l�����炦�Ă������A�����ł͂��łɔp�~����Ă���B�������s���̕�炵���L���ɂȂ����킯�ł͂Ȃ��B
�@�V�N�O����P�����ȕ��S�̉��ی����x����������A������t�̂��Ƃň�Ð��x����������ꂽ�B���ł������s�ł��u�������ґ�v�Ƃ���A�����玟�ւƐ�̂Ă��Ă������ƂŁA�������炵�̑��ɗ������邱�Ƃ͑҂����Ȃ��ɂȂ��Ă���B���܂���������ς��铬���̎����B
�i�u����Ԃ���v2007�N�S���P���t���j
��t�s���́w�s���Q���x�̓���
�@�u�s���̎���͎s���v�������Ɍf���A�u�s���̖]�ނƂ�����s���ɐϋɓI�ɂ������Ă����v�Ƃ��������s���Q����Ⴊ�{�s����ĂR�N�B���̏��ɂ��ƂÂ��A�s�̏d�v����ƂȂ�u�q�ǂ��̌������v�f�Ă���N�R���A�s���Q���̍���ψ����s���ɒ�o���ꂽ�B
�@�Ƃ��낪�s���́u���e�����̈ӂɂ�����Ȃ��v����ƁA�c��ւ̏���o�����܂��ɍs�Ȃ����Ƃ͂��Ă��Ȃ��B�u�q�ǂ��̌���������������A���ȐӔC�ɂ��Ă͕s�\���v�Ƃ����̂����̗��R�B
�@���̎s���A�P�J����̔R�₷�S�~�̎�����������s�ȊO�͊m�肵�Ă��Ȃ����Ԃ��A�ǂ��l���Ă���̂��B�s���Q�����������Ȃ��玖�Ԃ𖾂炩�ɂ����A�s���s�݂Ō��n�Ă����������ɁA�s���̎��ȐӔC���̂��̂�����Ă���B
�@�u�s���Q���v��{���ɂ��邽�߂ɂ��A�s���]�����K�v�B���̂R�����u�M���t�v�ɐ�ւ��āB
�i�u����Ԃ���v2007�N�R���S���t���j
�g�~
 �@�אg�̎��ł������A���̓~�͒g�~���Ɗ�����B��N�͂P�����{�ɂ͐ϐႪ����A���̑O�̔N�͑�A���Ƀh�J�Ⴊ�~�����B���������N�͍���20���ɐႪ�`�������ȊO�́A������Ă��Ȃ��B������肩�A�X�̒�������ʂ����������ǂ����B�e���r�ł͑��X�L�[���Ȃ���̃Q�����f���f���A�y�̏�ŊJ�Â�҂�܂�����Љ�Ă���B �@�אg�̎��ł������A���̓~�͒g�~���Ɗ�����B��N�͂P�����{�ɂ͐ϐႪ����A���̑O�̔N�͑�A���Ƀh�J�Ⴊ�~�����B���������N�͍���20���ɐႪ�`�������ȊO�́A������Ă��Ȃ��B������肩�A�X�̒�������ʂ����������ǂ����B�e���r�ł͑��X�L�[���Ȃ���̃Q�����f���f���A�y�̏�ŊJ�Â�҂�܂�����Љ�Ă���B
�@�u�n�����g���v�������ċv�����B�C�����R���㏸����^���̋��ꂪ���債�A�C�ʂ�65�p�㏸����A���{�S���̍��l�C�݂̂W�����N�H����Ƃ����B�Ɠd���i�𑵂���A���ꂾ���œ�_���Y�f�傳����Ƃ����̂�����A�������߉䂪�Ƃ͓�_���Y�f�̂Ȃ��ɏZ��ł���悤�Ȃ��́B
�@�אg�̎��ɂ͒g�~�͂��肪�����B�������A�m���ɉԂ��炩���邽�߂ɂ́A�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂��͓s���B���ɂ́u�g�c���O�v�����ʔ��Q���B���ʐ^�͍�N12�����{�́u�ш�_�Ёv�B
�i2007�N�P��28���t�u����Ԃ���v���j
��N
�@�N�̐��̉₩���������ĉ��N�ɂȂ낤���B �u�����Ȃ��i�C�����v �Ƃ������A �W���O���x�����Ζ��唄�o�����A �Q����l�X�̎p�͉ߋ��̏o�����B ��N�܂ł̓T���^�ւ̗v�������f�����䂪�q���A ���ɍ��N�͓\�肾������߂��B �q�ǂ��S�ɁA �T���^�ɖ����͌����Ȃ��ƌ�������̂��B �������C�u�̖�A ���ɑ��ėv������˂������B
�@�V�N�̓C�m�V�V�N�B ���x�̂Ȃ��ōŌ�ɓo�ꂷ�铮�������A ����܂ł�11�̓����̂ӂ����Ȃ����R�U�炷�悤�ɁA ���˖Ґi�A ������i���Љ�𐁂�����Ă��炢�����B �����ɁA���̊J�Ԃ̍��ɂ́A �����s���ɖ��̑������炩�������B
�@������s�c��24�l�̒��ŁA �C�m�V�V�N�͂Q�l�B ���Ďs�c��싅���Ńo�b�e���[��g���m�����A ��t�s���ɑ���X�^���X�͐�������ށB �V�t�A �s���̃}�E���h�ɗ��������撷���C�m�V�V�j�B �������������ߋ����B
�i2006�N12��31���t�u����Ԃ���v���j
���V�o��
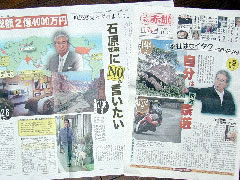 �@�Ό��m���̍��؊C�O�o�������炩�ɂ��ꂽ�B�P�l�P��26���~�̃z�e���ɕv�w�����ŏh���B�������s���̐ŋ��B�m���A�C�ȗ�19��̊C�O�o�����s�Ȃ��Ă��邪�A�u�s�c�I�̉������ʓ|����������v�Əo�������P�[�X���B �@�Ό��m���̍��؊C�O�o�������炩�ɂ��ꂽ�B�P�l�P��26���~�̃z�e���ɕv�w�����ŏh���B�������s���̐ŋ��B�m���A�C�ȗ�19��̊C�O�o�����s�Ȃ��Ă��邪�A�u�s�c�I�̉������ʓ|����������v�Əo�������P�[�X���B
�@������s�c���������g�����o���͂���B��C�ψ���̏ꍇ�A�N�P��P���Q���ŁA�h����p�́u�P�l�P���T��~�ȓ��i�H��݁j�v�B�s����ꏊ�́u�\�Z�z�͈̔́v�ƂȂ邽�߁A���͊����ʁA�k�͓��k�܂łƌ��肳���B���R�ɊC�O�Ȃǂ��肦�Ȃ����A�v�w�����Ȃǂ����Ă̂ق��B�s�ł��[�Ă�̂�����A���ʂ͊m���Ɏs���ɔ��f������B
�@�����i�����L����Ȃ��A������s�ł��A�w�������鐶�k��12���A�����ی쐢�т͂T�N�ԂłQ�{�߂��ɂ̂ڂ��Ă���B���V�Ŏg���u�P��26���~�v�ȉ��̌����ő����̓s������炵�Ă��邱�Ƃ��A�����ɂ��ċ��т����B
�i�u����Ԃ���v2006�N12���R���t���j
�؍��l�X
 �@14�N�O�܂Ŏ��́A������(�Z��)�Ƒ�X��(�E��)�̉������J��Ԃ��Ă����B���܂ɐV�h�Ȃǂ֏o�����邱�Ƃ͂��������A����ȏꏊ������Ȃ�đS���m��Ȃ������B�������̏ꏊ���A�����قǂɏW��Ă������͋^��Ȃ̂ŁA�����͂���قǂɒ��ڂ��W�߂���̂ł͂Ȃ����������m��Ȃ����E�E�E�E�B �@14�N�O�܂Ŏ��́A������(�Z��)�Ƒ�X��(�E��)�̉������J��Ԃ��Ă����B���܂ɐV�h�Ȃǂ֏o�����邱�Ƃ͂��������A����ȏꏊ������Ȃ�đS���m��Ȃ������B�������̏ꏊ���A�����قǂɏW��Ă������͋^��Ȃ̂ŁA�����͂���قǂɒ��ڂ��W�߂���̂ł͂Ȃ����������m��Ȃ����E�E�E�E�B
�@11��19��(��)���A���l���̗F�l�ƂƂ��ɁA�i�q�V��v�ۉw�߂��ɂ���u�؍��l�X�v��K�ꂽ�B�u�E���ʂ�v������т̂��̏ꏊ�́A�؍��������X���ɂ��ӂ�A�؍����������ԓX��ł͊؍���Ǝv���錾�t�œX�����Љ��l�����ނ낷��B���肵���O��A�m�g�j�́u�`�����O���̐����v���ŏI�����f��������B�������ԓX��ɂ́u�`�����O���̐����v�̓o��l���̃|�X�^�[�Ȃǂ�����߂��炳��A�T�C���������{���ꂽ���ƂȂǂ����Ă���B
�@��X��s�́u�}�j�g�v�Ƃ����؍��������ɓ������B�H�ׂ������̖��̂͊o���Ă��Ȃ����A�����炵��������̗����ɂ��g���A�قǂ悢�h�������Ɏc�����B���X�̐l�͂S�l�B�X�����Ƃ���40���炢�̒j���́u���͓��{�l�v���Əq�ׂĂ��邪�A�b���Ă�����{��͖��ɃA�`�����ɂ������Ȃ��B�X�����킭�u���͍�������̊��l�B�Q�N�O�ɂ����ɂ��ēX���ɂȂ������A���{�̕W����œX���̊؍��l�ƑΉ����Ă��邤���Ɋ؍��̌��t�����������A���{�̕W������������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����v�B�u�X�𗣂��Ɗ��قɖ߂�v�ƌ������X���́A���̊��قŘb���͂��߂Ă����B�ƁA���̎��A�X����������b�������Ă�����A�����Ȃ���ق��؍���ɕϐg�����B
�@���̈�тɂ�120���炢�̊؍��X������Ƃ����B���N�O�̓��؋��Ẫ��[���h�J�b�v�T�b�J�[�ȗ��A�l�C���o�n�߁A�u�ؗ��u�[���v�ɏ���Ĉ��A�r�����W�߂��l�q�B�u�悤�₭�A���̈�тŁA���{�l�X���Ƃ��Ď���Ă��炦��悤�ɂȂ����v�ƓX���B����܂ł́A���{�l�Ƃ��������ŁA�����ڂŌ����Ă����Ƃ̂��ƁB�u�Ό��m���́A���̍��ݓ�������т����w�r���X�ɂ��悤�ƍl���Ă��邪�A�X�̐l�C���オ���Ă��܂������߂ɁA�肪����ꂸ�ɂ���v�Əq�ׂ�p����́A���̊X������Ȃ������Ă��銴�����Ђ��Ђ��Ɠ`����Ă���B�u�܂����Ă��������B�������낢�b�������ς�����܂�����v�B�d���̂��߂ɁA�H�����I��������͈ꑫ��ɏ�����ցB�c������s�́A�߂��́u���픎���فv�֏o������
�i2006�N11��20���t�j
�����ی�v��
 �@�w�ڂɂ͖ڂ��x�w���ɂ͎����x�B�\�͒c�܂����̋c�_���A���{���ɉ��s���Ă���B�j�����ő�����Њd���u�����ƂȂ�������Ԃ��v���̍s����ɂ́A�ǂ�Ȑ��̒����҂��Ă���̂��낤���B �@�w�ڂɂ͖ڂ��x�w���ɂ͎����x�B�\�͒c�܂����̋c�_���A���{���ɉ��s���Ă���B�j�����ő�����Њd���u�����ƂȂ�������Ԃ��v���̍s����ɂ́A�ǂ�Ȑ��̒����҂��Ă���̂��낤���B
�@���̂��Ƃ��������̂��A������s�����\���������ی�v��B�m(�j)�a(����)�b(���w)����ɂ��U���ɂ��������S�\�����������A���w�h�앞�A���ː����葕�u�A�����g���h�~���邽�߂̏������Ȃǂ���~����Ƃ��Ă���B
�@�w���������̂́u��ЏZ���ɑ���~���v�B�����E�Α��̕�������ь����A�u���̎��e���̊J�݁A���̂̔����A���e�y�я��������s�Ȃ��v�Ɩ��L�B�u���̂̐��E�D���E���Łv�ȂǁA���̂̏������@�܂ŋL����Ă���B
�@�U���ɂ����ɑΏ����邩�����A����Ȑ��E�ɂȂ�Ȃ��悤�ɕ��a�O���𐭕{�ɋ��߂�v�悱���A�^����ɂ������ׂ��ł͂Ȃ����낤���B���܂������@����������f���āB
�i�u����Ԃ���v2006�N11���T���t�j
�i�q�R�c��
 �@10�����{�A�s�c������ψ���̍s�����@�ŁA��茧�̋{�Îs��K�ꂽ�B�{�Îs�͗����C�݂ɖʂ��Ă���A���`�Ƃ��Ă��A�܂��Ôg���e���r�ʼnf���o�����l�̃e���r�J�������ݒu����Ă���ꏊ�Ƃ��Ă��A�m���Ă���B�ꏊ�I�ɂ́A��茧�����[�̒��S�Ɉʒu���Ă���B �@10�����{�A�s�c������ψ���̍s�����@�ŁA��茧�̋{�Îs��K�ꂽ�B�{�Îs�͗����C�݂ɖʂ��Ă���A���`�Ƃ��Ă��A�܂��Ôg���e���r�ʼnf���o�����l�̃e���r�J�������ݒu����Ă���ꏊ�Ƃ��Ă��A�m���Ă���B�ꏊ�I�ɂ́A��茧�����[�̒��S�Ɉʒu���Ă���B
�@���k�V�����u�͂�āv���w�ʼn��Ԃ�����s�i�c���W�l�A�E���R�l�j�́A�{�Éw�s���̂i�q�R�c���̂Q���Ґ��f�B�[�[���Ԃɏ�Ԃ����B��͐��B�e�w��Ԃɓ������قǂɑ����̉w�Ɏ~�܂�ԗ����R���ɓ���ɂ�A���ӂ̖X�̗t�͌����ȐF�Â��ɕς���Ă����B�֍s���Ȃ�������H�̉����Ɋ��Y���ė����k�J�̐����ʂɂ́A�����t��������������ł����B
�@�����͋�E(��������)���B���ӂ̖X�͌����ȍg�t�B���F��Ԃ��ɂ��قǂɖڂɔ�э���ł���B�k���ɂ��т����_�R(1103��)�����ꍛ�ꂷ��قǁB�ł�����Ȃ�A�����ł��炭��Ԃ��Ăق������炢���B�J���������Q���Ă��Ȃ���A����قǂ܂ł̌i�F���ꖇ���L�^���Ȃ��������Ƃ��S�c��B�������ԗ��́A�͂��݂������悤�ɐ��H�������Ă����B���킹�āA���H�����ɗ����k�J�̐��ʂ́A���x�͎ԗ�����������Ɠ��������ɗ����ς����B
�@�{�Îs�͐l���U���P��l�B�s���ʐς�696.82㎡�B�L��ȏꏊ�ɏ�����s�̐l���̖��Ƃ��Ȃ�A�w�O�͓��R�ɊՎU�Ƃ��Ă���B�s�����͋{�Øp��������Ƃ���ɂ���A���ɂ̒�����p�����ቺ�Ɍ��邱�Ƃ��ł���B���@�̓��e�͕ʍ��ɂ䂸��Ƃ��āA�s�����E���̘b�����t���A�e���r�ł悭���ɂ������a��ł��������Ƃ��A�I���͍��A���ɂ���I�Ǝ����������B
�@���@���I������s�͌ߌ�R��49�����̎ԗ��ɏ�邽�߂ɋ{�Éw�ɕ����߂�A�z�[���ŐÂ��ɂ�������ł��鐷���s���̎ԗ��ɑ��߂ɏ�荞�����ƁA���D���O�ɂ���Ă����B�Ƃ��낪���D���ɉw�������炸�A�������i���֎~�̊Ŕ��u����Ă���B�ǂ����A�o���ԍۂłȂ��Ɖ��D���J���Ȃ��炵���B�������Ȃ��A�w��������̂����܂����܂��Ƒ҂����B���Ĕ���10���O�B����������ɗ��Ăق����ƃC���C�����͂��߂��Ƃ���ցA���D���̋߂��ʼnw�������c��ł��鏗��������Ă��āu���D���͂�����ł���v�Ǝw�������B�����ꂽ��͑ҍ����̒��B���ߐ�ꂽ�ҍ����̈�p���K���X�˂ɂȂ��Ă��āA���̌˂����ɊJ�����A�������\���ɓ�����D���ɂȂ��Ă����B��X������ł������D���͍\������w�O�ɏo�邽�߂̉��D���ł���A�����ł́A�����Əo���̉��D���͕ʁX�ɂȂ��Ă����̂��B���������������Ă���Ȃ������犮�S�ɏ��x��Ă������A�i���ɏ��Ȃ�������������Ȃ��B
�@�A�H�̂i�q�R�c���͂P���݂̂̃f�B�[�[���ԁB�\��ǂ���ߌ�R��49���A�o���B�z�͂����ԂɌX���A�s�H�Ŏʐ^�B�e�ł��Ȃ�������E���t�߂́A�ʂ肷���鍠�ɂ́A�����炭�͎B�e�ł��閾�邳�ł͂Ȃ����낤�B�ӂ����сA�e�w��Ԃ��Ƌ^���قǂɑ����̉w�Ɏ~�܂�Ȃ���A�ԗ��͐����w�ւƐi��ł����B�r���A�u�Ђ��߁v�Ƃ����w�ɒ������B���̒n���ɂ͓��ʂ̎v��������B�Ȃ��Ȃ�A��N�V���ɔ]���o���̂��߂ɑ��E�����t�H�[�N�O���[�v�u�m�r�o�v�̓V�� �� ���ƂƂ��ɂm�r�o�̈���Ƃ��Ċ������Ă��������o�[�̈�l���A���́u�Ђ��߁v�o�g�����炾�B�m�r�o�͊�茧��֎s�𒆐S�Ɋ������A���̎茳�ɂ́A�m�r�o�̑啔���̃��R�[�h�E�b�c���u����Ă���B
�@���āA�ԗ��͋�E���߂����ēo���Ă����B�O�͂����Ԃ�Â��Ȃ�A���J���~���Ă����B�ԗ��͋ꂵ�����ɂ������ł���B�ƁA���̎��A�ԓ��A�i�E���X�����ꂽ�B�u�J�Ɨ����t�̂��ߐ��H�����ׂ�A�X�s�[�h���o���Ȃ��ƂȂ��Ă��܂��B���������������v�B��E�w���O�́u�܂����w�v�Ɍ����đ����Ă���Œ��̌ߌ�T���߂��̃A�i�E���X�B�O������ƁA���N��肪�����悤�ȃX�s�[�h�ŁA�������ɉJ�Ŏԗւ����ׂ��Ă���悤�ȐU�����B�r�����x���~�܂肻���ɂȂ�قǂ̏ɂ��Ȃ����B���̂��J�Ƃ͊W�̂Ȃ��g���l�����ł������A���̏͑������B���̂����C�̂������A�G���W�����Ă���悤�ȏL��������B
�@���R�A�ԓ��͂���߂��������B�����w�ŐV�����ɏ�芷����l�́A�V�������w��Ȃł��邪���߂ɁA�C���C�łȂ��B�ԗ��͂킸���ɂP���B��q��30�l�O��B���̂����W�l�́A����������₩�܂����s�c��c���B���Ƃ����邪�����s�h���ł����Ă��A�ԗ��̑���������Ă���Ƒ����������Ȃ�B�Ⴂ�j���ԏ�����ʑ����ɂȂ�Ȃ���A�ԗ��̑O������x���s�������B�䂪�s�c��c�������̏�q���A�ԏ��Ɂu�ǂ��Ȃ��Ă���I�v�Ɛ��������߂͂��߂�B�������ԏ��́A�ԓ��A�i�E���X�̂Ƃ���ɓ�����̂݁B�g�ѓd�b�́u���O�v�������B
�@�ߌ�T��35���A�悤�₭�u�܂����w�v���B�����Ŏ��Ȃ�A�i�E���X�������B�u���ׂ�~�߂̍���ςݍ��ނ��߂ɁA���炭��Ԃ��܂��v�B�ցI�H ���̕�[�H�E�E�E�E�B���Ȃ��炸��q���z�[���ɍ~�藧�����B�^�o�R���z���l�A�ԗ��̑O�ʂɍs���āA���m���߂�l�B�~�藧�����̂��A�ق�̂킸���B�ԏ��ɂ���Ďԓ��ɖ߂��ꂽ�B�����ď����ԗ���i�s�����ɓ������āA�܂���ԁB�u�������܂���A���̕⋋�̂��߂ɒ�Ԃ������܂��v�B�ߌ�T��44���A�u��ϒ��炭���҂������܂����B���̕�[���I���܂����̂ŁA�^�]���ĊJ�������܂��v�B�ԗ��͓����������B�����ăA�i�E���X�A�u�܂����w��38���x��ẴX�^�[�g�ł��B�������܂���A��Ԍ��̔q���ɂ��������܂��v�B
�@�u��Ԍ��̔q���ɂ��������܂��v�̃A�i�E���X�Ɏ��́A�^�C�~���O�������I�ƁA�O�̐Ȃɍ����Ă���n�ӑ�O�c���Ɍ��������A���̎����g�́A�ŏ��̃A�i�E���X�����ꂽ�ߌ�T���߂������肩��A���̎��Ԃ��y�������Ă����B����Ȍo���͂߂����ɂȂ����A��s�@��D�ƈ���āA�ė����鋰����Ȃ��B�������ɓn�Ӌc���������悤�ɁA�ԗ������̂ł͂Ȃ����Ƃ̎v���͂��������A���̎��͂��̎��Ƃ�������ƍl���Ă����B����ɂ��Ă��A���J�̒��̓��Ɍ������o���ł͂����Ă��A�킸���ȃ��[�����̏�ɉ��X�Ɨ����t�������Ă���킯�ł��Ȃ����A�Ȃ��A�ԗւ�����Ȃ��Ƃł��ׂ�ɂȂ�Ƃ����̂��낤���B���̂��Ƃ́A�����炭��q�̒N�����������^��ł������낤�B�������A�u�����[�����v�ԗ��́A�܂����w�ȍ~�̓X�s�[�h�����߂��A���Ⴆ�鑖����������B���̑���́A���̂i�q���m�R���̒E�����̂��ق��ӂ�����قǂɁB
�@�ߌ�U��38���A�\����38���x��āA�I�_�̐����w�ɓ��������B�u�������ɁA���̈З͂͂������i�v�ƁA�䂪�s�c��c���̉�b�B�������A�N�����A�����T���Ȃ��瑖���Ă����Ƃ͎v���Ă͂��Ȃ������B����ςނƂ���������҂͂��Ȃ����A���̒��x�̏��J�Ɨ����t�Ŏԗւ����ׂ�̂ł���A���̋G�߂ɂ́A���̂悤�Ȏ��Ԃ͖��x�A�N���邱�ƂɂȂ�B���A���[����ɗ����t�ȂǂقƂ�ǒ����Ă��Ȃ����Ƃ��u�܂����w�v�Ŋm�F���Ă���ʁX�́A����̂킯�̂킩��Ȃ��o�����ɁA���܂��܂Ȑ����𗧂Ă�̂݁B�Ƃɂ������ɂ��A�s�v�c�Ȃi�q�R�c���́A��X�܂Ō��p����čs�����ƂɂȂ邾�낤�B
�i2006�N10��19���t�j
�S�~��펖�Ԑ錾
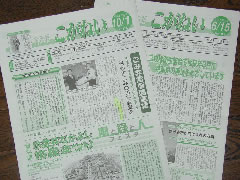 �@�P���t�́u�s��v�Łu���ݔ�펖�Ԑ錾�v�����L���ꂽ�B���N�R���œ��ċp�ꂪ�S�ʒ�~���邽�߁B�����āA�R�₷���ݎs����l���������u50�����ʂ��v�ƌĂт����Ă���B �@�P���t�́u�s��v�Łu���ݔ�펖�Ԑ錾�v�����L���ꂽ�B���N�R���œ��ċp�ꂪ�S�ʒ�~���邽�߁B�����āA�R�₷���ݎs����l���������u50�����ʂ��v�ƌĂт����Ă���B
�@���łɁu�s��v�͂U��15���t�ŁA���ċp�ꂪ���N�R���Ŕp�~����邱�Ƃ��q�ׂĂ���A�u���́A���ɂȂ��āH�v�̊����ʂ����Ȃ��B�������u50�����ʁv�͍����ɂȂ��đł��o�������́B�W���ƂX�����ł́u���݂̌��ʁE���ʂ������ɐi��ł��܂��v�Əq�ׁA��l����킸���u�P���̌��ʁv�������߂Ă͂��Ȃ������B�V��15���t�܂ł́u51���̌��ʁv���Ăт����Ă����ɂ�������炸�B
�@�����ɂ́A�����ɂȂ��Ď��Ԃ̐[�����ɋC�Â���@�ӎ��̌��@����������Ă���B�w�O�J���ɔM�����邠�܂�A�U���c��ł̉䂪�}�́u�S�ʏ�������v�̎w�E�ɁA�@�q�ɑΉ����銴�o���������Ă������炾�B�s���̐ӔC�͏d��ł���B
�i�u����Ԃ���v2006�N10��8���t���j
�h�V�j���
 �@�s�̌h�V�17���ɍs�Ȃ���B�ĊJ���̂��߂Ɏ��ꂽ����ɑ����Ď��{����钆����w�������Z�ł̍Â��ɂ́A68�Έȏ�̍����16,173�l�Ɉē������t���ꂽ�B �@�s�̌h�V�17���ɍs�Ȃ���B�ĊJ���̂��߂Ɏ��ꂽ����ɑ����Ď��{����钆����w�������Z�ł̍Â��ɂ́A68�Έȏ�̍����16,173�l�Ɉē������t���ꂽ�B
�@���킹�ď�����s�́A����i799�l�j�E�Ď��i244�l�j�E�����i17�l�j�E�S�Έȏ�i23�l�j��1,083�l�ɍ������A�L�O�i�̃M�t�g���𑗕t�B���̂����S�̂T�l�ɑ��ẮA�s�������ږK�₵�ċL�O�i����n���Ƃ����B
�@���̎s�������\�����u�s�v��j�v�ł͗��N�x�A�O�q�̍���ҋL�O�i�x�����Ƃ��������Ƃ��Ă���B�u�������S���v�̖��Łu���Ƃ̖������I�����v�Ƃ̔��f����B�s���͕S�̕��X��O�ɁA�u�L�O�i�͂���ł����܂��ł��B�����͏I���܂����v�Ƃł������̂��낤���B
�@10���W���A�ш�≺�̎�����A����͖��N�P��̌h�V�j�����J���B�N�X������Q���҂ł͂����Ă��A�s�v�͍l�����A�S����̌h�ӂ�\���āB
�i�u����Ԃ���v2006�N�X��10���t���j
���c����Ô�����A�w�O�܂�
�@�u2005�N�̏o�����P.25�v���g����Ă�ł���B�l�������邾���łȂ��A�Y�Ƃ��x����J���͂�Љ�ۏᐧ�x�̊�Ղ������h�邪�����˂Ȃ����炾�B�����Â����A2003�N�̏�����s�̏o�����͂P.08�A�����s�͂O.9987�B������s���܂��Ȃ��P.0����Ă��܂��̂ł͂Ȃ����낤���B�v
�@���̎����������Ȃ���A�ߓ��̎s�c��Łu�q��Đ���̌o�ϓI���S���y�����邽�߂ɂ��A���c����Ô�̖��������A�w�O�܂Ŋg�傹��v�Ɣ������B�s���͏]���́u���S�\�͂ɉ����ĕ��S���Ă��������v��ύX���A�u�N���v��𗧂ĂāA�����߂Ă��������v�Əq�ׂ�ɂ��������B�w�i�ɂ́A�O�����łV�s�������ƂȂ�A�������s�����N�x�ɂ͖����ɓ��ݐ邩�炾�B
�@���{���Y�}�͂R���c��ɏ����T�{�A���c��ɂ́u���c����Ô�̏A�w�O�܂ł̖��������v�����������B�s���̐����ق��铖�R�̖����Ƃ��āB
�i�u����Ԃ���v2006�N�U��18���t���B�Ȃ��A�֘A���鎑�����o�c�e�t�@�C���Ōf�ڂ��܂��j
���c����Ô�����A�w�O�܂�PDF�i127KB�j
�O�
 �@�O�����A������s�c��̈���Ƃ��ĖK�₵���B�S�N���Ԃ�̓����A������P�N�R�J�����o�����́A�ό�����̐����}�s�b�`�ł����߂��Ă�����̂́A���̏��Ղ͐��X�����c���Ă���B�u�K�X�}�X�N�̏펞�g�т��`���Â����Ă��܂��v�Ƃ̂��Ƃł��������A���ɑ��ݓ���Ă݂�ƏL���͂��قǂł��Ȃ��A�N��l�Ƃ��ăK�X�}�X�N�͕t���Ă��Ȃ������B �@�O�����A������s�c��̈���Ƃ��ĖK�₵���B�S�N���Ԃ�̓����A������P�N�R�J�����o�����́A�ό�����̐����}�s�b�`�ł����߂��Ă�����̂́A���̏��Ղ͐��X�����c���Ă���B�u�K�X�}�X�N�̏펞�g�т��`���Â����Ă��܂��v�Ƃ̂��Ƃł��������A���ɑ��ݓ���Ă݂�ƏL���͂��قǂł��Ȃ��A�N��l�Ƃ��ăK�X�}�X�N�͕t���Ă��Ȃ������B
�@�����⑺�c����́A�����̍���ɑ��錜�O�����X�Ɍ��ꂽ�B�O��̍�����͎O���E�܁��ɂ��̂ڂ�A���h�̎{�݂͂����Ă��A����ʼnc�Ƃ��ĊJ���悤�Ƃ��Ȃ��l�������B����ł��܌��̘A�x���ɂ́A��БO�̎����ɂ܂Ŋό��q�����A�ނ���O�����łɂ�������Ƃ̂��ƁB
�@�ό��Ə̂��āA���𑖂���o�C�N���Z���咣����l�����邪�A���R���ӂ�铇�Ɉ�l�A�܂���l�ƖK��A���̗ւ��L���čs���Ă����A�{���̊ό��ɂȂ���̂ł͂Ȃ����낤���B���͂��܁A�ނ�̕�ɂł���B
�i�u����Ԃ���v2006�N�T��21���t���j
�쒆�w�Z���w��
 �@����������s�ɏZ�ݒ������N�̂S���A�s���쒆�w�Z���n�����ꂽ�B���̓쒆�����N�A�n��30���N���}����B��ԗ��j�̂����ꏬ�w�Z���R�N�O�ɑn��130���N���}�����Ƃ�������A���ɕS�N�ȏ���̍��B����ł����̊ԁA3,950�l�̐��k��쒆�w�Z�͑���o���Ă���B �@����������s�ɏZ�ݒ������N�̂S���A�s���쒆�w�Z���n�����ꂽ�B���̓쒆�����N�A�n��30���N���}����B��ԗ��j�̂����ꏬ�w�Z���R�N�O�ɑn��130���N���}�����Ƃ�������A���ɕS�N�ȏ���̍��B����ł����̊ԁA3,950�l�̐��k��쒆�w�Z�͑���o���Ă���B
�@�S���V���A���w�����s�Ȃ��A134�l�̐V�������쒆�w�Z�̖�����������B�J�Z�����̐V������163�l�Ƃ�������A�����̒��w�Z��I���k�����邱�Ƃ��l����ƁA30�N�̊Ԃ̐��k���ɑ卷�͂Ȃ��Ƃ�������B���Ǝ��O��ɍ炫�n�߂����͓��w���܂ł�������}�ɂ��炢���A���捠�܂ŏ��w���������A���ǂ��Ȃ��̎c��V�������������}������Ă���B
�@���̓쒆�֍��N�A���q��������������B���@�Ƌ����{�@�̉�������ɂ̂ڂ�Ȃ��A���a�̂�����������蔲���Ȃ���ƁA���炽�߂Ďv���B
�i�u����Ԃ���v2006�N�S��16���t���j
���Ǝ�
 �@�u���͓��w���̍��v���ʐ��������悤�Ɏv���B����ǂ��A�ŋ߂͑��Ǝ��̍��ɃV�[�Y�����}���邱�Ƃ������A�u���~�̂ق����������đ����炭�v�Əq�ׂ�҂�����B�Ƃ͂����Ă��A���t�͓���A���Ǝ�������Ƃ����킯�ɂ͂����܂��B���̑��Ǝ����\�����͎s�����w�Z�ŁA��l���ɂ͏��w�Z�Ō}����B �@�u���͓��w���̍��v���ʐ��������悤�Ɏv���B����ǂ��A�ŋ߂͑��Ǝ��̍��ɃV�[�Y�����}���邱�Ƃ������A�u���~�̂ق����������đ����炭�v�Əq�ׂ�҂�����B�Ƃ͂����Ă��A���t�͓���A���Ǝ�������Ƃ����킯�ɂ͂����܂��B���̑��Ǝ����\�����͎s�����w�Z�ŁA��l���ɂ͏��w�Z�Ō}����B
�@���X�ɁA�n��̒��w�Z����ē����͂����B�u���Ə؏����^���̂��ē��v�B��������ɂ��āA�n�e�H�ƂȂ����B�Ȃ��u���Ǝ��v�ł͂Ȃ��̂��낤���B�^����Ӗ��ł́u���^�v�ƁA��o�Ƃ��Ắu���Ɓv�ł́A�������������Ă��܂��ł͂Ȃ����B���Ǝ����ɂ���܂ł͔F�߂��Ă����q�ǂ������̓W�������A���N�́u���^���v�ł͓P�������w�Z���o�Ă���Ƃ̂��Ƃł���B
�@��l���A�䂪�q�����w�Z�𑃗����Ă����B�Z�N�O�̓��w���́A���ǂ��Ȃ��݂͂�����Ȃ��B�S�����Ŗ��J�ɂ��āB
�i�u����Ԃ���v2006�N�R��19���t���j
�S�R����Y���̖ڐ�
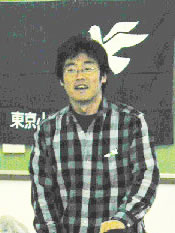 �@�ߓ��A�t�H�g�W���[�i���X�g�̌S�R����Y���̍u�������B�V���b�^�[���Ƃ����āA���̍��̎p�M���Â���ނ́A04�N�S���ɂQ�l�̎�҂ƂƂ��ɃC���N�ŗU�����ꂽ���A�Ȍ�������̑������X��K��A�N����ԁA�]���ɂȂ��Ă��邩�������������Ă���B �@�ߓ��A�t�H�g�W���[�i���X�g�̌S�R����Y���̍u�������B�V���b�^�[���Ƃ����āA���̍��̎p�M���Â���ނ́A04�N�S���ɂQ�l�̎�҂ƂƂ��ɃC���N�ŗU�����ꂽ���A�Ȍ�������̑������X��K��A�N����ԁA�]���ɂȂ��Ă��邩�������������Ă���B
�@�ނ��ł�����ɂ߂Ă���̂́A���܂Ȃ����Â��C���N��A�t�K�j�X�^���̐l�X�B�̉��łǂꂾ���̖����]���ɂȂ�A�����c�����l�X���ǂ̂悤�Ȑ������������Ă���̂��́A�܂����������Ă͂��Ȃ��B�u�����猻��Ō��邱�Ƃ���Ȃ�ł��v�Ɣނ͌����B�C���N�U�����J�n����Ă��łɂR�N�B�R���l����C���N�s�����]���ɂȂ��Ă���B
�@�C���N�U�����n�܂����R���́A�������P�̌��ł�����B�W���T��l�����ɁA�S���l�]����������61�N�O�̑��P�B���̖�̓����������̃C���N���A���s�Ȃ��̂̓A�����J�ł���B�̉��ł͑����̎�҂��A��������D���Ă���B
�i�u����Ԃ���v2006�N�Q��19���t���j
���������Ă͂Ȃ�Ȃ�
 �@�s�c�O�����h�k���̌����������B�펞���ɗ��R�Z�p�������̖{�����Ƃ��Č��Ă��A���͏������w�Z�Ƃ��Ďg�p�B���̌�A�s�c���Z��̊Ǘ����Ƃ��Ċ��p����Ă����B�V�����Ƃ͂����A���j�f���������������Ă����͎̂c�O�ł���B �@�s�c�O�����h�k���̌����������B�펞���ɗ��R�Z�p�������̖{�����Ƃ��Č��Ă��A���͏������w�Z�Ƃ��Ďg�p�B���̌�A�s�c���Z��̊Ǘ����Ƃ��Ċ��p����Ă����B�V�����Ƃ͂����A���j�f���������������Ă����͎̂c�O�ł���B
�@���̏�����s���s�Ȃ����u�s���]���v�ł́A���@�L�O���ƂƔ�j���a���i���Ƃ��u�p�~�v�u�k���v�Ɩ��������B�܂������N�͌��@����60�N�A��N�͔픚60�N�ł���B���E�A�M���a�s�s�錾���j���a�s�s�錾���s�Ȃ���������s���A���̂悤�ȕ]�����s�Ȃ����Ǝ��́A�����������B�푈��Ղ͏����Ă��A�߂����x�ƌJ��Ԃ����Ȃ����g�݂͔R�₵�����悤�B
�@������s�͌��݁A�s��50���N�̓�N��Ɍ����āA�L�O�����s�̏����������߂Ă���B���܂܂ł܂Ƃ߂���Ȃ�������O�E�풆�������Ȃ���B���������Ȃ����߂ɁB
�i�u����Ԃ���v2006�N�P��22���t���j
�ϐk�
 �@������s�ɐg��u���Ă���28�N�]���o�߂����B�Z�݂͂��߂����͐A�ؔ���_�n���L����A�Â��Ȃ������܂����݂��Ă����X�������܂ł͂Q���Q��U�S���̌����łЂ��߂������Ă���B �@������s�ɐg��u���Ă���28�N�]���o�߂����B�Z�݂͂��߂����͐A�ؔ���_�n���L����A�Â��Ȃ������܂����݂��Ă����X�������܂ł͂Q���Q��U�S���̌����łЂ��߂������Ă���B
�@24�N�O�Ɍ��z��@�����肳��A����ȑO�Ɍ��Ă�ꂽ�����́A�V�������肳�ꂽ�ϐk��ɍ��v���邩�ǂ����������悤�ɂȂ����B�䂪�Ƃ��܂߂āA�s��������25�������z��@����ȑO�Ɍ��Ă��Ă���̂ŁA�n�k�̎��ɂ͂��������h��Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�Ƃ���ŋߍ��́A�ߔN���Ă�ꂽ�}���V�����ł��h�ꂪ�������ƕ����B�ꍇ�ɂ���ẮA�I���{���䂪�Ƃ�����ɓ|�邱�Ƃ����邻���ȁB�o����ؑ��́A�Ƃ�ł��Ȃ����蕨��N�̐��ɂ悱�����B
�@���Ƃ킸���ŃN���X�}�X�B�䂪�q�͍��N���A�T���^�ւ̔j�i�̗v������\�肾�����Ƃ��Ă���B�t�g�R���͕��O���B
�i�u����Ԃ���v2005�N12��18���t���j
�Z�̂ɍ��܂ꂽ�肢
�@21���I�͂X�E11�e������ɁA�A�t�K�j�X�^���A�C���N�ւƐ�Ђ��L����A�e�����p������悤�ɂȂ����B�푈�Ŗ�����ꂽ20���I��̌��������E������A���܂̎����J�����͍��܂����B�����������ゾ���ɁA���a����蔲�����߂̎��g�݂͌������Ȃ��B���@�X�������A��x�Ɛ푈�ɉ����Ȃ����Â���������߂Ă������Ƃ�����B
�@����A�{�����w�Z�̊J�Z40���N�L�O���T�ɎQ���B���̊w�Z�̍Z�̂ɂ́u���a�v�̉̎�������A�q�ǂ������ɕ��a�̑�����`���Ă������Ƃ̍쎌�҂̊肢���݂ĂƂ��B���ׂĂ݂�ƁA�s�������w�Z14�Z�̂����A�Z�̂Ɂu���a�v�����܂�Ă���̂͏��w�Z�łS�Z(�{�����w�Z�A��ꏬ�w�Z�A�O�����w�Z�A��O���w�Z)�A���w�Z�łQ�Z(�����w�Z�A�Β��w�Z)�ƂȂ��Ă���B
�@���60�N�A�푈��m��Ȃ������Ƃ����@����𐺍��ɋ��ԂȂ��A���҂̂Â����̎��ɁA�傫�ȏd�݂�������B
�i�u����Ԃ���v2005�N10��23���t���j
�h�V��
�@���{�l�̕��ώ����͍����A������85.6�Ő��E��A�j����78.7�œ�ԖڂƂȂ��Ă���B���̂��Ƃ��ے�����悤�ɁA�ߏ��ł��V�l��⎩�����80���z���Ă������Ŋ���鍂��҂������A�����̌o����m����n��ɖ𗧂Ă�d���ɏA���Ă���B
�@�s�ɂ��ƁA������s��90�Έȏ��825�l�A����������75�����߁A�ߓ����{���ꂽ�s�̌h�V��ł������̎Q�����ڗ������B
�@�����͏j���������̂ł���B����ǂ����{�Љ�̌���͒������������قnj��g�̋����v�����������A������t�͏��q����Љ�ɑΉ����邽�߂Ƃ̌������ŁA��Â�N���A���̉��������ŋ��s�����B
�@�ߓ��̌h�V��ł́A���i��ł��Ȃ��݂̋ʒu�G�����o���B�u��T�ԂԂ�̂��Ԃ����ł����v�Ŏn�܂����ނ̃g�[�N�́A���N�̌o���E�m���𑶕��ɔ�������f���炵�����̂ł������B���C����������Q���҂́u�P�N�Ԃ�v�ɉ�闈�N�߂����āA���V�̏H��̉��A�A�H�ɂ����B
�i�u����Ԃ���v2005�N�X��25���t���j
���w�Z�̉^����
 �@��T�̓��j���A�䂪�q���ʂ����w�Z�̉^��������w�����B�O�邩��ْ̋����߂��ʉ䂪�q���A�e�̊��҂���g�ɎȂ���삯�����ɒ��킵���s�ނ���p�ɁA�g�x���̂̓I�����肩�h�ƍ��N�����ߑ��B �@��T�̓��j���A�䂪�q���ʂ����w�Z�̉^��������w�����B�O�邩��ْ̋����߂��ʉ䂪�q���A�e�̊��҂���g�ɎȂ���삯�����ɒ��킵���s�ނ���p�ɁA�g�x���̂̓I�����肩�h�ƍ��N�����ߑ��B
�@�����q�ǂ��̂���́A�^����͏H�ɍs�Ȃ��Ă����B�������u�H�͕����s���ȂǂŃX�P�W���[�����Ƃ��邽�߁A�t�ɉ^������s�Ȃ��Ƃ��낪�����Ă��Ă���v�Ƃ͎s����ψ���B�w�Z�����Ɋ���Ȃ������ɑ傫�ȍs���ɒ��ʂ�����Ȃ��V��N���ɂ����ẮA�Ƃ܂ǂ���ʂ�����Ƃ����B
�@�u�I�����q�ǂ��̂���́A�^����ǂ���ł͂Ȃ������v�ƁA�ߏ��̏��V�͌����B�푈�����ɂ͏�����ł��ČR�̐퓬�@��a29���}�������˖C���Ƃǂ낫�A�_�H��߂����ĕČR�͍ڋ@���@�e�|�˂��͂Ȃ��Ă�������ł���B�^����������s�����S����y���߂鐢�̒��B�������蔲���Ă����̂����a���@���B
�i�u����Ԃ���v2005�N�U���T���t���j
���{�ҋ@��360�l
�@�u���ʗ{��V�l�z�[���̓�����҂l��360�l������B����Ŗʓ|�����悤�Ǝv���Ă��A�Q�������Ԃł͉����œ|��Ă��܂��B���A�����Ȃ���ΐH�ׂĂ����Ȃ��B�ǂ�������ǂ��̂��v�B���̊ԁA�������@��]�V�Ȃ�����Ă���Ƒ��������l�̐؎��ȑi�����������Ŋ���B
�@65�Έȏ�̐l�����@����ƁA�R�J���őމ@�𔗂���B��ނ��]�@���邱�ƂɂȂ邪�A�������܂��R�J���őł�����B�{�ݓ���������×{���ł��Ȃ��Ȃ��ŁA���@��p�����͂ǂ�ǂ��݁A�u�ڂ̑O�̂��Ƃ��l����Ɛ^���ÂɂȂ�v�ƁA�ߒɂȕ\��B
�@����ȂȂ�������s�́A2005�N�x�����ł�17���T�疜�~���s�����S�������ĊJ���ɓ˂��i�ށB�u���܍s�Ȃ�Ȃ���A�w�O�J���͓�x�Ƃł��Ȃ��B100�N�̊X�Â���v������ɁB�������s�������͕S�N�ǂ��납�A�ꐡ����ŁB���炵�ɂ����ŋ����B
�i�u����Ԃ���v2005�N�P��30���t���j
�S�̉J
�@�����m�푈���A���{�����ŗB��n��킪�s�Ȃ�ꂽ����ł́A�����̂S�l�ɂP�l������ł���B�Ȃ��ł������̎��҂��o�����ČR�ɂ��͖C�ˌ��́A�X��ʂ�R�e���Ռ`�Ȃ��ł��ӂ���A�u�S�̉J�v�ƂȂ��ďZ�����P�����B
�@���̕ČR�����x�́A�C���N�����̓s�s�t�@���[�W���ւ̑��U�����s�Ȃ��Ă���B�l��30���̑�s�s���P������l�̕ČR����͂��A�ꕔ�̃e�����X�g��ׂ����߂ɑ命���̖��Ԑl�̓���ցB
�@���̃A�����J�ɑ��ē��{���{�́A����A�o�����ւ���������������B�u�e����̂��߁v���A���̗��R�B�������A����͐l���E�����߂̓���B�t�@���[�W���ŌJ��Ԃ����ČR�ɂ�閳���ʍU�����A�u�e����v�����R�B�߂��Ȃ��Z���̓���ɓS�̉J���~�点��E�C�ɁA���{�̕��킪�g���邱�ƂɂȂ�̂��낤���B
�@�����ł͖C�������R�J���ȏ㑱���A���폤�l�͏݂��ׂ��B
�i�u����Ԃ���v2004�N11��28���t���j
�A��
 �@���N�͑䕗�̓�����N�ƂȂ��Ă���B��̑䕗�����������Ǝv���Ă���ƁA�V���ȑ䕗�ڋ߂̕���э��ށB�����m���C�����������Ƃ����R�Ƃ���邪�A�n�����g���̉e�����B������Ȃ��B �@���N�͑䕗�̓�����N�ƂȂ��Ă���B��̑䕗�����������Ǝv���Ă���ƁA�V���ȑ䕗�ڋ߂̕���э��ށB�����m���C�����������Ƃ����R�Ƃ���邪�A�n�����g���̉e�����B������Ȃ��B
�@�䕗10���̔�Q�Ɍ�����ꂽ�̋��E����́A�A�Ȃ����~�̍��ɂ͓��������ꂽ��Ō}���Ă��ꂽ�B����ł��A�y�����������ꏊ�ɂ͏������c��A�召�̐���ɕ���ꂽ�����A������Ƃ���Ɍ���ꂽ�B
�u�钆�Ƀp�[���Ƃ����傫�ȗ��̉��������A��������̂������J�ƂȂ����B�삪�y���Ŗ��܂�A�܂������܂ɓ�����ƂȂ����v�B�Ƒ���ߏ��̐l�̘b�́A�S�N�Ɉ�x�Ƃ������J�̕|�����������Ă���B
�@��T�̓��j���́A�s�̖h�ЌP���̓��������B�������锼����̉J�ɂ����̃O�����h�s�ǂ𗝗R�ɁA�P���͒��~�ƂȂ����B�V��ō��E�����P���ŁA�ǂ��̂��낤���B
�i�u����Ԃ���v2004�N�X���T���t���j
�M�\��
 �@�u�M�\���v�ƌĂ��A�ł���ꂽ����������������B�����̓�����R���Ƃ���M���̈�ŁA�]�ˎ���ɐ���ɑ���ꂽ�Ƃ����B�s���ɂ�10���N�O�܂ł�17�J���c���Ă����Ƃ������A�����ł͓s�s���̂Ȃ��Ŕ������Ă���B �@�u�M�\���v�ƌĂ��A�ł���ꂽ����������������B�����̓�����R���Ƃ���M���̈�ŁA�]�ˎ���ɐ���ɑ���ꂽ�Ƃ����B�s���ɂ�10���N�O�܂ł�17�J���c���Ă����Ƃ������A�����ł͓s�s���̂Ȃ��Ŕ������Ă���B
�@�ш�쒬�́A�J���炵�ɂȂ��Ă���M�\���ɂ́u��ӂ��イ�v�u�������Ԃv�u�k���ˁv�̕��������܂�A�s���l�◷�l�̓��ē������Ă������Ƃ��킩��B����͉߂��Ă��A�����Ɠ����ꏊ�Ő��m�ȕ��p�������Â��Ă���B
�@�Ƃ���ō��A���̍��̎w���҂����͓��̐^�ɗ����āA������푈�̕��p�ɓ��ē����Â��Ă���B�}�X�R�~������̑������A���̕��p�����Ȃ����̂悤�ɕ��������킹�āB�������A���ē��͗��j�̎����ɑς������̂������A���̔C���ɂȂ���B�����Ă���200�N�]�̊ш�쒬�̍M�\���ɂ͋y���Ƃ��A���{���Y�}��82�N�̗��j�́A����́u�M�\���v���B�Q���A�u����Ԃ�Ԋ��v�͑n��76���N���}�����B
�i�u����Ԃ���v2004�N�Q��15���t���j
�N���X�}�X �v���[���g
 �@���܉䂪�Ƃɂ́A�q�ǂ��������g�ݗ��Ă������ȃN���X�}�X�c���[������B�Z���͂��������A�T���^����ւ̂��˂�����L���A�C�u������̂��y���݂ɑ҂��Ă���B �@���܉䂪�Ƃɂ́A�q�ǂ��������g�ݗ��Ă������ȃN���X�}�X�c���[������B�Z���͂��������A�T���^����ւ̂��˂�����L���A�C�u������̂��y���݂ɑ҂��Ă���B
�@���͂܂��A�N���T���^�Ȃ̂���m��Ȃ��B�T���^���N�Ȃ̂���m���Ă���Z�́A���̂������߂��u�肢���Ɓv�����āA�u����Ȃ̂��炦��킯�Ȃ����v�ƈ�R�B�T��̐e�́A�L���ꂽ���e�ƍ��z�̒��g������ׂ�B����A�Z�̋L�������ɂ́A���́u�肢���Ɓv�������Ă���B�g���ꂪ�_����������A����g�ƁB�T���^�ւ́u�肢���Ɓv�Ȃ�ʁA�e�ւ́u�v�����v���̂��́B
�@������t�͐�㏉�߂āA���q���Ƃ������̌R����푈�p���n�E�C���N�ɑ���o�����Ƃ��Ă���B�C���N�����ւ̃v���[���g�ł͂Ȃ��A�A�����J�ɒ����𐾂����߂́A�u�b�V�������ւ̃v���[���g�Ƃ��āB������A�C���N�����ɂ́u�푈�g��v�̎S�Ђ��҂��\����B�C�u���I���A���S���ĐV�N���}�����鐢�E�ցB�h���ɂ͒f�Ŕ��I�B
�i�u����Ԃ���v2003�N12��14���t���j
�J�C�R
 �@���w�S�N�̑��q�́u�ċx�ݎ��R�����v�̂��߂ɁA�Ȃ��J�C�R���������B�Ƃ͂����Ă��A�������ȂNJF�ڂ킩��Ȃ��B�}�ӂ��Ђ��ς肾���ØV�ɋ����Ȃǂ��āA�ǂ��ɂ������ł��A�H���������̂��o�Ă����B �@���w�S�N�̑��q�́u�ċx�ݎ��R�����v�̂��߂ɁA�Ȃ��J�C�R���������B�Ƃ͂����Ă��A�������ȂNJF�ڂ킩��Ȃ��B�}�ӂ��Ђ��ς肾���ØV�ɋ����Ȃǂ��āA�ǂ��ɂ������ł��A�H���������̂��o�Ă����B
�@������n��͖�������吳�ɂ����āA�{�\�̑S�������}���Ă���B���̂V�����{�\�_�ƁA�����͔����q�`���l���[�g�ŃA�����J�ɗA�o���ꂽ�B
�@�J�C�R���������߂ɂ͌K�̗t���K�v�ƂȂ�B������͂��āA���ʐς̂R�����K������߁A�䂪�Ƃ̏ꏊ���ȑO�͌K���ł������Ƃ����̂ɁA�����K�̗t�T���ƂȂ�ƁA�e�Ղł͂Ȃ������B
�@�u���R�����v�́A�����̊G���L�ւ̋L�����ۂ�����B���̂��߁A���~�̎��ƂցA�ӂ��̂Ȃ����ɕ��ׂ�ꂽ�J�C�R�����Ȃ��邱�ƂɂȂ�A�������E�V�����E�k�����ƁA�J�C�R���l�X�̏O�ڂ��W�߂邱�ƂƂȂ����B
�@�W�������{�ɓ���A���R�����͖�����悤�Ƃ��Ă���B�������A�J�C�R�͐����𑱂��A����̏��u�Ɏ���₢�Ă���B
�i�u����Ԃ���v2003�N�W��24���t���j
�u20�N��ɂȂɂ��Ă�H�v
�@�u20�N��ɂȂɂ��Ă�H�v�ƕ����ꂽ��A���Ȃ��́A�ǂ�ȉ����܂����B�����ъw���ۈ珊�R�N���̑��q�i��n�j���ƂɎ����A�����A�w���̑������W�ɍڂ���A�w���R�N���̈�l�ЂƂ�̃A���P�[�g�p���ɋL����Ă������⍀�ځB
�@���w�Z�R�N���̍��A���͉̎���Ă��܂����B���w�Z�̎��̎��́A���̎q���畉���́u�{�[�C�Y�\�v���m�v�B�e���r���痬���̎�̉̂��o���A�_�Ђ̋����ŁA�V�їF�B��O�ɂ��āA���ӋC�ɉ̂��Ă������́B�s���L�[�ƃL���[�Y�́u���̋G�߁v��A����������݂́u�u���[���C�g�E���R�n�}�v�ȂǁB�Ƃ��낪�A���w�Q�N���̎��́u���ς��v�����ɉ̂������������āA�C��������A�u���Ђ�݁v�̐����u�X�i��v�ɂȂ��Ă��܂����B�����A�u���Ђ�݁v�̂܂܂�������A�����͈Ⴄ���E�ɂ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@���āA�䂪���q�A�A���P�[�g�ɋL���ꂽ�́u������Ɓv�B20�N��Ƃ����A29�B���̎��ɍs�Ȃ��Ă��邱�Ƃ��u������Ɓv�ł́A���͋����Ă���������Ȃ����B���Ȃ݂ɁA���q���ۈ牀�̑������ɉ����A�u�傫���Ȃ����牽�ɂȂ肽���H�v�̓����́A�u�R�[�v�Ƃ����傤�œ��������v�B�ނ�29�̎��ɂ́A�R�[�v�Ƃ����傤�ŃA���o�C�g���Ă���̂ł��傤���B
���̎q�ǂ��͌����f���āA�������ĂȂ��̂��A����Ƃ����ꂪ����t�̖��Ȃ̂��A�͂��܂��A�e���e������A����ȉȂ̂��E�E�B�l���������鑧�q�̉ł����B
�i�u���Ђ��܃��[�����e��i�v2003�N�Q��13���t����j
�T���^�N���[�X
�@�q�ǂ��̍��A�T���^�N���[�X���A�ǂ����炩�䂪�Ƃɂ���Ă��āA�v���[���g���^��ł���Ă���ƐM���ċ^��Ȃ������B�v���[���g�������̋��߂Ă������ƈ���Ă��Ă��A���A�ڂ��o�߂��Ƃ��ɖ����ɒu����Ă����Ƃ��́A���̊����́A���܂ł��n�b�L���Ƃ��ڂ��Ă���B���Ƃ����ꂪ�A�Z��S���A�����u���C�ɓ��������َq�v�������Ƃ����s���͂������ɂ��Ă��B�u�T���^����͂ˁA�݂�Ȃ��Q�Ă���v���[���g�������Ă����v�B�����̂��A�䂪�Ƃł͓�����b�����킳��Ă���B
�@������t�́A�����ɂƂĂ��Ȃ��g�v���[���g�h���^�ڂ��Ƃ��Ă���B�u�s�Ǎ������v�u��O���Łv�u��Ô�S���v�E�E�B����ȃv���[���g�́A�����ɒu���Ăق����͂Ȃ��B�T���^��ウ���Ƃ��K�v���B
�@�C�u�̖�A�䂪�q�͂ɂ킩�ɃT���^�ւ́A���肢���Ƃ������͂��߂��B������Ƒ҂āB���܂��珑����Ă������Ă��܂��B�T���^�͂��łɗ��Ă���̂�����B
�i�u����Ԃ���v2002�N12��29���t����j
��Ղ߂���c�A�[
 �@����A�s���̐푈��Ղ߂���c�A�[���T�l�ōs�Ȃ����B�܂�����ꏊ�͋����R�Z�p�������W��12�J���B �@����A�s���̐푈��Ղ߂���c�A�[���T�l�ōs�Ȃ����B�܂�����ꏊ�͋����R�Z�p�������W��12�J���B
�ŏ��ɖK�ꂽ�w�|��ł́A�_�Ɖ��~�Ղ��L�����u���₫�̔�v�Ə㗤�p�M���̓n�͎����������{�����u�v�[���Ձv�����w�B�T���W�I�ʂ�́u�������v�ł́A�s�C���ȗl���ɂ������فB�s�c�O�����h�k���́u�Ǘ����v�͌����������������茩�āA�ۑ��̕K�v�����ĔF���B�u���R�v���������E�́A��{���Ƃ낤�Ƙa���̏ォ�牔�M�łȂ��������A�Ύ��̂��ʉ����Ă������߂Ɏ��s�B
�@�ő�̓�ւ́u�k��Ձv�B���R�Z�p�������̖k�������ǂ̂����肩�A�悭�킩��Ȃ��B�����ŁA�y�n�̌Ðl�ɕ������ƂɁB���̌��ʁA�k��̂������ꏊ����іk���̋������������B
�@�펞���A�_�Ƃ̓y�n��D������ꂽ�A�L��ȗ��R�Z�p�������B�푈��Ղ��㐢�Ɏc�����g�݂͂͂��܂�������B
���u�����R�Z�p�������v�Ɋւ���푈��Ղɂ��ẮA���z�[���y�[�W���u�s���v���u�s���̐�Օۑ��̎��g�݂Ɍ����āv���Q�Ƃ��Ă��������B
�i�u����Ԃ���v2002�N12���P���t����j
�L���@���_�c�̂Ȃ���
�@�f��u�����A�킾�݂̐��v���r�f�I�Ŋς��B���50�N�L�O��i�Ƃ��đS����f����A�D�c�T��⏏�`���l�ȂǁA���o�D�������o�ꂵ�Ă���B�^�C�g���ɂȂ����u�����킾�݂̂����v�́A�����m�푈���̐�v�w���̓��L���L�����^�����{�̑薼�ŁA1949�N�ɓ��勦���g���o�ŕ����甭�s�B�����A�x�X�g�Z���[�ƂȂ��Ă���B
�@�w�������ɑ�����悤�ɂȂ����̂́A1943�N10���Q���́u�݊w���W�����Վ����߁v�B�܂�A�w���̒����P�\��S�ʓI�Ɏ������[�u�ɂ��B���̂��߁A��13���l�̊w�������E�C�R�ɓ��c�E���������B
�f��u�����A�킾�݂̐��v�ł́A���Ŏ��X�ƒ��Ԃ��|��Ă����Ȃ��ŁA�D�c�T��ӂ鏭�т���]�̒��ŋ��ԁB�u����Ȑ푈�A�N���n�߂��I�v�B
�@�U���������푈�ɂȂ��Ă��� ����Ȃ��ƂɂȂ�Ȃ��悤�ɁA���������͐����グ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���a�����߂�҂Ƃ��āA�����āA�q�����e�Ƃ��āB
�i�u����Ԃ���v2002�N�T���P���t����j

|