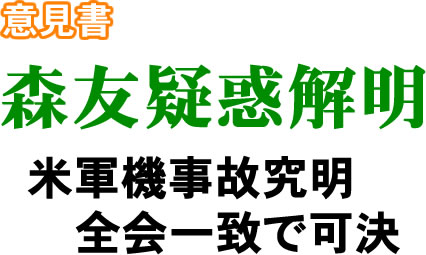
 3月28日閉会した3月市議会は、最終日に党市議団提案の「森友学園疑惑の徹底解明を求める意見書」と「米軍機の事故等の原因究明を求める意見書」等を全会一致で可決。 3月28日閉会した3月市議会は、最終日に党市議団提案の「森友学園疑惑の徹底解明を求める意見書」と「米軍機の事故等の原因究明を求める意見書」等を全会一致で可決。
国民の注目を集めた「森友学園疑惑」では証人喚問でも疑惑解明にはほど遠いなかで「国民の共有財産である国有地の利用や国の権限、税金支出などが首相とその周辺によって歪められた」という厳しい指摘を含んだものです。この意見書が、自民党議員も含めて可決した意義は大きく、毎日・朝日新聞、テレ朝ニュースでも紹介されました。
また沖縄県の米海兵隊普天間基地所属の海兵隊機による事故やトラブルが相次ぐなか、米軍横田基地を抱える首都圏にとっても他人事ではないとして事故原因の徹底究明を求めた意見書の可決も、画期的なことであり、安倍政権に対する市民の怒りの反映とも言えます。
新電力会社出資金
削除修正案僅差で否決
再生可能エネルギーによる地域電力会社への出資金510万円を、一般会計予算案から削除する修正案は、賛成が共産、リベラル所沢など15票、反対は自民、公明など17票の僅差で否決されました。
再生可能エネルギーの積極活用では異議のないものの、会社設立には運営リスクの大きさや、電源仕入れ先を市外の企業に8割近くも委ねることは地産地消とは言えない等の批判が出されていました。
予算特別委員会では6対5で可決していました。
党市議団一般会計予算組替え動議提出
【組替え動議項目】
○重度障害者福祉タクシー使用料金補助金削減、重度心身障害者福祉手当引下げしない事○グループホーム等利用者家賃補助、難病患者見舞金制度を元に戻す事○公立保育園給食民間委託と、育休退園の中止○放課後児童待機児解消の抜本的整備計画を○東西クリーンセンター長期包括運営業務委託関連の再検討など、大きくは7項目になりました。
予算特別委員会を終えて
今議会の予算特別委員会では、新電力株式会社・旧コンポストセンター跡地活用事業などの議案に質疑が集中しました。
議会最終日の採決では、一般会計予算に対し、賛成22票・反対10票でした。
無料法律生活相談会
4月28日(土)(要予約)
午前9:30〜11:30
中央公民館1階学習室3号
小林亮淳弁護士
担当議員 荒川 広
090−2660−5883
主催 日本共産党所沢市議団 |
城下のり子の議会報告

入学式を迎える新年度、子どもたちの笑顔が溢れる時期でもあります。
昨年議会から「子どもの貧困対策に関する提言」を受け、新年度予算編成で貧困対策をどのように検討したのか質問しました。
市長は「施政方針では、市政運営について述べた。私は事細かに指示しない」と答弁。市民憲章には「子どもは市の宝」と掲げています。その子ども達の貧困実態を把握するのは市の責務です。新年度の施政方針には、子どもの貧困という文字はひとつもありませんでした。市長の認識の無さが顕著に表れた議会でもありました。
保育園や学童保育に入れなかった子ども達を抱える家庭にとっては辛い春です。政治の転換を早急に進めなくてはいけません。 |
�公共施設は市民との共有財産
国は人口減少や老朽化した公共施設の修繕に費用がかかるとして、すべての自治体に公共施設等総合管理計画の策定を求めており、これを機に施設の統廃合や集約化を狙っています。公共施設は地域コミュニティの拠点でもあり、住民との共有財産です。
地方自治法第244条「公の施設」では、地方公共団体は住民の福祉の増進のために施設を設ける事。正当な理由なく住民の公の施設利用を拒んではならない事。また、不当な差別的扱いをしてはならないと明記しています。
今後のあり方は広範囲な市民参加で議論を
小学校が身近なところにあるかどうかは子育て世代が自治体を選択する際のキーワードにもなります。人口減少を理由に統廃合などを進めれば子育て世代が居住地として選択せず、より一層の人口減少につながる事も指摘されています。地域住民が主体的に地域の公共施設をどうするか、しっかりとした議論をすることが重要です。
その際、議論を深めるため十分な情報提供や市民参加のあり方では、飯田市やさいたま市など先進市も調査するよう求めました。
経営企画部長は「公共施設のあり方は検討段階から市民意見を聞く事は重要。市民参加についても先進自治体も参考にしたい」と前向きな答弁をしました。
学校の余裕教室を活用して
余裕教室の活用については、すでに若松小学校で余裕教室を活用した高齢者の集会所「わかば」が設置されています。ここでは異世代交流や子どもの見守りなど、防犯面や住民のコミュニティ形成にも大きく貢献しています。
人口減少による労働力確保により保育園や学童保育の需要は高まっており、高齢者の居場所づくりという視点からも2006年に教育福祉常任委員会から提言した余裕教室の活用に対する見解を求めました。
経営企画部長は「施設機能の複合化は重要な視点と認識しており、今後も教育委員会と協議を進めたい」と答弁しました。
貧困の連鎖を断ち切るためにも安心して学べる環境を
生活保護受給世帯のうち、子どもが大学等に進学の場合は世帯分離をしなくてはならないため、世帯の保護費が減額され本人は国保に加入し保険料の支払いなどをしなくてはなりません。
貧困の連鎖を断ち切るためにも子ども達が卒業まで、生活保護受給対象とするよう国に意見を上げるよう求めました。
福祉部長は「国も社会保障審議会でも支援重要としているが、様々な意見もあり国の動向を注視したい」との答弁でした。
また、子ども達は学業とアルバイトを掛け持ちしながら国保料などの支払いをしています。所得の少ない子ども達が安心して学べるよう国保の窓口3割負担の軽減など、あらゆる支援につなげるよう求めました。
福祉部長は「必要な支援につなげるよう、寄り添い型の支援をしていきたい」と答弁しました。 | 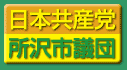
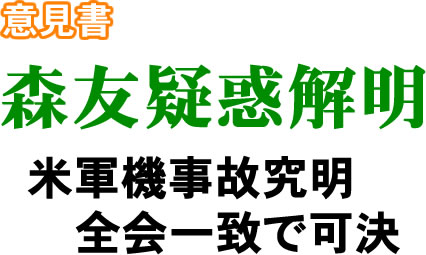
 3月28日閉会した3月市議会は、最終日に党市議団提案の「森友学園疑惑の徹底解明を求める意見書」と「米軍機の事故等の原因究明を求める意見書」等を全会一致で可決。
3月28日閉会した3月市議会は、最終日に党市議団提案の「森友学園疑惑の徹底解明を求める意見書」と「米軍機の事故等の原因究明を求める意見書」等を全会一致で可決。