
 10月8日午後国保運営協議会が開催され、小林議員が傍聴しました。 10月8日午後国保運営協議会が開催され、小林議員が傍聴しました。
この日は、税率改定の4ケースが提示され、それぞれモデル世帯別影響額の資料も提出されました。
改定モデルケース案
現行、所得割率6.5%、資産割率30%、均等割額9千円、平等割額1万7千円を基準に4ケースで試算しています。
(1)所得割率 7.2%
均等割額1万5百円(2)所得割率 7.2%
資産割率27%
均等割額1万5百円 平等割額1万6千円(3)所得割率 7.3%
均等割額1万5百円(4)所得割率 7.3%
資産割率27%、
均等割額1万5百円 平等割額1万6千円に、それぞれ改定する案が審議されました。 この改定で各ケース、
(1)5億5千万円
(2)4億8千万円
(3)6億円
(4)5億1千万円
の増収です。
なお、4ケースのうち、現行の賦課限度額(医療給付費分50万円、後期高齢者支援金分12万円、介護納付金分9万円)を、医療給付費分51万円、後期高齢者支援金分16万円、介護納付金分14万円にそれぞれ引き上げるのは共通しています。
新国民健康保険法は第1条の目的で「社会保障及び国民保健の向上に寄与する」と明記しています。
国の責任は明確化されており、まして社会保障であるならば安易な被保険者への負担転嫁は問題です。
広聴・広報委員会 四日市市へ視察
広聴広報委員会は10月6、7日、議会改革度調査で全国第1位となっている愛知県四日市市を視察、矢作議員が参加しました。
議会報告会は、毎議会、委員会ごとに市内4か所で同時開催され、委員会審議も活発になり、市民の要望で手話通訳も依頼するように改善されました。
6日夜の市立小学校を会場にした報告会は、議員8名市民14名の参加で、8月定例議会の報告、所管部分の意見交換です。関心ある市民が参加し、議案に対する質疑応答・動画共有サービスで委員会・協議会を視聴した意見等、活発な意見交換の場という印象を受けました。
翌日は、四日市市役所で、市議会議長・市職員から「議会報告会・議会モニター」の説明を受けました。
議案に対する意見募集や、常任委員会・協議会のインターネット配信の実施、議員政策研究会など多くの取り組みがされています。
市議会モニターは現在50人、議会傍聴・アンケート・意見交換会等が行われています。
議会報告会の参加者の減少は当市でも課題ですが、四日市市の委員会ごとの開催やテーマの設定のなどは、参考になりました。
第5回国民健康保険運営協議会
市役所全員協議会室(低層棟3階)
10月29日(水)
1時30分からです
ぜひ傍聴して下さい |
無料法律生活相談会
10月25日(土)
午後1時30分〜4時
中央公民館 学習室3号1階
必ずご予約をお願いします
担当・城下のり子
090‐8450−4360 |
小林すみ子の議会報告
9月末で終わったNHK連続テレビ小説『花子とアン』。私には翌日が待ち遠しいドラマでした。
戦時中英語は敵性語とされた中、『赤毛のアン』は花子が命がけで本を守り、翻訳したおかげで戦後日の目を見ることができました。
腹心の友、蓮子のモデル柳原白蓮は、息子の戦死から平和運動の道へ。脚本を書いた中園ミホさんは対談で、今の日本があの戦争前にそっくりという発言がありました。秘密保護法や集団的自衛権行使容認は戦前そのもの。平和を守るがんばり時です。
土砂災害等への対策と緑地保全について
昨今の異常気象で集中豪雨が多発し、土砂災害等がいつどこで起こるか不安です。
市内に急傾斜地崩壊危険箇所が50カ所あります。
1危険箇所の周辺住民への周知について
2急傾斜地崩壊危険箇所の改善、支援について
3国や県への財政支援要請をすること
4災害防止のために、開発規制を強化して、緑地保全の必要性
5土砂災害警戒(特別警戒)区域の指定で、固定資産税の引き下げの検討 等を求めました。
担当部長は、土砂災害警戒区域に該当する地域の説明会が県により順次開催予定。指定急傾斜地の下の住宅移転等は融資等が受けられる。被害を受けた場合、国は被災者生活再建支援法による支援金(適用条件は同一市内10世帯以上)が、県では今年度から全壊10世帯未満でも被害規模に応じて(上限あり)の支給があることと、緑地の保全は認識しているとの答弁でした。
警戒区域指定地の固定資産税の引き下げは、減価要因になるので近隣他市を調査して対処したいとの答弁でした。
子どもの貧困対策
所沢の児童・生徒の六人に一人が就学援助の対象ですが、子どもの貧困化が社会問題化しており、今年一月子どもの貧困対策法が施行されました。
市に対しスクールソーシャルワーカーの充実や育英奨学金・遺児奨学金の額の引き上げ、政府に、世界では当たり前の返済不要の「給付型奨学金」導入、一人親家庭への児童扶養手当の対象年齢引き上げ(額は今年度から引き下げた)などを求めるよう質しました。
担当部長は、市の制度の充実も政府へ意見を挙げることも消極的でした。
教職員の多忙化問題
公立学校の教職員の多忙化が社会問題化し、経済協力開発機構の教員に関する調査でも日本の中学校の教員の勤務時間が突出して長いことが、明らかになりました。教職員は通常の授業や教材研究・授業の準備、いじめや体罰など、学校で子どもを守るための取り組みが、切実に求められています。
教育長は、多忙感があることは認識していると答弁しました。
しかし、超過勤務時間が月80時間を超える教職員数の実態把握はなく、小中学校の開閉庁時間の実態調査等も求めました。
また、教育委員会内に「負担軽減検討委員会」を設け、現場教職員の実態や意見を反映した多忙化解消の具体化を図ることについては、現場校長に改善を求める趣旨の担当部長答弁でした。
市役所窓口委託
足立区の戸籍住民課の窓口の民間委託に、東京法務局からは見直しを東京労働局からは偽装請負の是正指導を受けたことから、当市の窓口委託事業についても質しました。
特別養護老人ホーム入所基準
介護保険制度の改正で来年4月から特養の新規入所基準を「要介護1」から、原則「要介護3」以上になることから、入所判定や責任の所在について質しました。 |
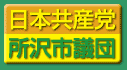
 10月8日午後国保運営協議会が開催され、小林議員が傍聴しました。
10月8日午後国保運営協議会が開催され、小林議員が傍聴しました。