|
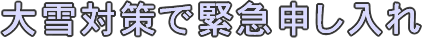
 2月17日、所沢市議団は、市長に大雪で市民生活に支障が出ていることから市としての次のような緊急対策を求めました。 2月17日、所沢市議団は、市長に大雪で市民生活に支障が出ていることから市としての次のような緊急対策を求めました。
交通機関ではバスやトラック運行など流通機能に支障が出て、スーパーから商品が無くなる事態です。またいちご等を栽培している農家ではビニルーハウスが積雪で倒れ大変な被害で、「何か保障する制度はないのか」等の声も出ています。
今回は土日だったこともあり、サラリーマン家庭では男性が家にいて除雪が助かったという状況もありました。しかし、高齢者世帯の多い地域では除雪も困難であり、地域的な格差もあります。
 |
| 雪でつぶれたビニールハウス(中富) |
市が現状把握をし、ホイールローダ等の除雪機材の所有者の協力を得ながらネットワークの中心になること、また埼玉土建所沢支部や所沢市建設産業連合会などが災害協定を提案していることもあり、建設労働者とも、どういう対応ができるか話し合う場を作ることなどを求めました。
対応した副市長は「自治会での連携がこういう時こそ必要だ、その機能をまちづくりセンターに担って欲しい」などと答えました。
議員団は、ネットワークの要は市が責任を持つことを重ねて要求しました。
米軍基地が駅前一等地に 相模補給廠視察
2月7日、基地対策協議会は、神奈川県相模原市の相模総合補給廠の返還についての経過や基地跡地の街づくりについて視察しました。党市議団からは基地対策副委員長の平井明美議員が参加しました。
相模総合補給廠は、相模原駅前にありながら、約214ヘクタールもの広大な土地が市民利用できないまま経過してきました。
相模原駅のすぐ前にある米軍基地は、旧日本陸軍相模陸軍造兵廠として使用され、米軍接収後は朝鮮戦争やベトナム戦争の時、在日米軍の主要な補給基地として位置付られていました。今でも800名もの日本人が倉庫などで働き、100人の米軍人がおります。基地内には米軍らの家族が住む邸宅や保育所、スーパーなども完備されています
返還の経過は、平成18年5月に行われた日米安全保障協議委員会(2プラス2)で在日米軍再編の最終報告によるものです。
日米強化の目的で在日米軍司令部の改編として第一軍団司令部は30名で発足しましたが、90名に強化されました。朝霞駐屯基地は移転し座間駐屯基地へ開設されるなどの合意が成立したものです。
平成20年6月には日米合同委員会において17ヘクタールの一部返還され、その後、24年6月には35ヘクタールも米軍の共同使用の合意がされています。
こうした経過で相模総合補給廠の一部が返還されたものです。
基地周辺は駅前の一等地でもあり、その中心に占める米軍基地が相模原市の街づくりを進めていく上で、いかに大きな障害になっていたのか実感した視察でした。
2014年3月議会日程
|
曜日 |
開会時刻 |
議 事 内 容 |
| 2月24日 |
月 |
午前10時 |
施政方針及び提案理由の説明・議案説明(先議) |
| 25日 |
火 |
午前10時 |
議案質疑(先議) |
| 26日 |
水 |
午前 9時 |
四常任委員会並行審査(先議) |
| 27日 |
木 |
午前10時 |
常任委員長報告・質疑・討論・採決(先議)
常任委員長報告(特定事件)・質疑 |
| 28日 |
金 |
午前10時 |
議 案 説 明 |
| 3月5日 |
水 |
午前10時 |
議 案 質 疑 |
| 6日 |
木 |
午前10時
本会議散会後 |
議 案 質 疑 ・予算特別委員会の設置
予算特別委員会審査 |
| 7日 |
金 |
午前9時 |
四常任委員会並行審査
予算特別委員会審査(四分科会並行審査) |
| 10日 |
月 |
午前9時 |
四常任委員会並行審査
予算特別委員会審査(四分科会並行審査) |
| 12日 |
水 |
午前9時30分 |
一般質問(石本・浜野・浅野・越阪部・平井・秋田・松崎) |
| 13日 |
木 |
午前9時30分 |
一般質問(石井・吉村・脇・西沢・亀山・末吉・城下) |
| 17日 |
月 |
午前9時30分 |
一般質問(小林・やさく・荻野・松本・荒川・谷口・桑畠) |
| 18日 |
火 |
午前9時 |
常任委員会審査(予備日) |
| 25日 |
火 |
午前9時 |
予算特別委員会審査 |
| 27日 |
木 |
午前10時 |
常任委員長報告・特別委員長報告・質疑 |
| 28日 |
金 |
午前10時 |
討論・採決 |
*今議会は予算特別委員会が設置されます。一般質問は45分です。
新規障害者 65歳以上重度医療対象外へ
埼玉県は、重度心身障害者の医療費の自己負担分を助成する制度(重度医療)について、65歳以上の障害者手帳新規取得者と年間所得360万円以上の障害者を来年1月から対象外とする方針を明らかにしました。県は制度見直しについて「高齢化の急速な進行と受給対象者や助成額が増加しており、制度の維持が難しい」としています。所沢市での受給者数は6700人、そのうち65歳以上は3800人です。障害者が必要な医療を受けられるように公的な保障を行う事は当然であり、制度維持を理由に年齢や所得で制限を設けることは社会保障の理念にも反するものです。
|