|
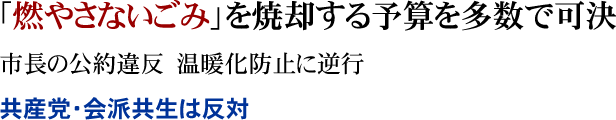
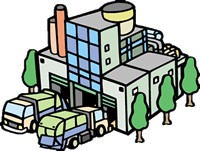 所沢市はこれまでダイオキシンや有害物質を発生させる塩化ビニール等(履物やカバン・おもちゃなど)を「燃やさないごみ」として埋め立ててきました。これを十月から「燃やす」と方針転換をしました。当市はダイオキシンの教訓から、脱焼却・脱埋め立てを掲げ、全国初の「ダイオキシンを少なくし所沢にきれいな空気を取り戻す条例」をつくり国を動かしてきました。 所沢市はこれまでダイオキシンや有害物質を発生させる塩化ビニール等(履物やカバン・おもちゃなど)を「燃やさないごみ」として埋め立ててきました。これを十月から「燃やす」と方針転換をしました。当市はダイオキシンの教訓から、脱焼却・脱埋め立てを掲げ、全国初の「ダイオキシンを少なくし所沢にきれいな空気を取り戻す条例」をつくり国を動かしてきました。
市は国の方針転換を焼却の理由に示していますが、国は排出抑制・減量資源化が最優先としています。また、廃プラスチックを焼却すればスラグ(灰を固形化したもの)は増え、今年度も約6500t埋め立てなければなりません。これを改善するためには、焼却量を減らすための減量・資源化に一層取り組むべきであり、自区内処理のために最終処分場の早期建設に着手すべきではないでしょうか。市長は、選挙時のアンケートに「廃プラ焼却は反対」と回答していながら、議会では「市政の継続性から、廃プラ焼却は課題のひとつで、どこかの時点で市民の意見を聞き結論を出す」としています。しかし、東部クリーン・センター周辺住民などの同意は不必要で、説明のみで理解を求めるとしています。市長の公約のあり方も問われています。

市民からの要求もないのに唐突な条例提案に違和感を感じます。条例の内容には市民の平穏な日常活動を拘束するかのような条項があります。また条項には市民に対し、地域安全活動の義務づけや知り得た情報の提供義務などが盛り込まれています。さらに今度の条例は、一部特定団体の意見だけで提案された印象は拭いきれず、民主的手順を踏んでいません。防犯まちづくりの推進における市民の役割は、強制ではなくあくまで自主性にまかせるべきでしょう。
この条例に対し日本共産党、共生、会派「翔」が反対しました。
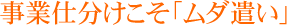
国の事業仕分け同様、外部からの視点で事業を検証するとして、全事務事業の2%に当たる40事業41項目を「事業仕分け」しました。「専門チーム」に事業を委託しその結果、判定は不要4、民間実施3、市(民間委託拡充)5、市(要改善)25、市(継続)4、と結論を出しました。市はこの結果をあくまで参考に、方向性を定めるとしています。
主に民間と公の人件費比較などを中心に、「安くて財政効率の高い」民間に誘導する狙いがあります。例えば「民間委託拡充」と判された「保育園の給食」では、「小学校給食が委託できて、なぜ保育園はできないのか」などの乱暴な議論で、わずか30分で結論をだすのです。乳幼児は児童とは違い、ミルクや離乳食など子どもの成長に合わせた対策が求められています。
しかし、そこには目もくれず、職員の人件費のみに集中するなど、市民の命を守る自治体の仕事を効率のみで仕分けすることに憤りを覚えました。
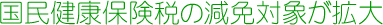
長引く不況の中で、国の税制改正により、7割・5割・2割の減免制度も設けられ対象が広がりました。(従来は6割・4割減免)
さらに、所沢市では減免条件が改善されました。例えば、失業などで前年の半分まで所得が激減した場合、年間所得六百万円以下の世帯が対象になり、大幅に広がりました。(改正前は3百万円まで)
前年度の二分の一以下に所得が減った方は申請してください。担当は国保年金課。
(電話2998‐9131)
|
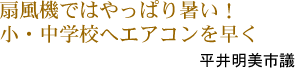
 暑い夏、小・中学校の教室の温度は38度まで上がり、「子ども達はぐたっりして思考が止まり授業できる状況ではない」と訴える先生の声もあります。防音地域(飛行機騒音)では防衛省予算でエアコン設置が可能で、三ヶ島地域の宮前小はすでに設置ずみです。 暑い夏、小・中学校の教室の温度は38度まで上がり、「子ども達はぐたっりして思考が止まり授業できる状況ではない」と訴える先生の声もあります。防音地域(飛行機騒音)では防衛省予算でエアコン設置が可能で、三ヶ島地域の宮前小はすでに設置ずみです。
狭山ヶ丘中は25年までに設置予定ですが、10年前、暖房を入れた若狭小学校はエアコン設置の計画がありません。
部長は「市内29校の防音校舎には平成18年より順次設置する予定、防音予算は一度使うと15年後になり、今後は航空機騒音の影響や学校の老朽化なども考えて防衛省と協議する」など答弁しました。
|
|
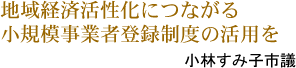
未曾有の建設業不況で、倒産・廃業の中小業者が後をたちません。そういう中、小規模公共工事に光をあて地域経済活性化に繋がる小規模事業者登録制度を活かす必要があります。所沢市は制度発足10年経過しましたが、平成21年度は発注件数379件、発注額は1663万8165円と近隣他市と比べても低い実績です。限度額50万円枠の引き上げと、小規模修繕の発注対象は、登録業者にすること等を求めました。
部長は「限度額引き上げは近隣市の実績を調査する、小規模修繕は登録簿に登録された業者に発注するよう3ヵ月毎に各部署に促す」と前向きに答えました。
|
|

所沢保健所の廃止後、保健センターを利用する団体の方から「保健センターでは手狭のため、検便などの対応が約半数しか対応できない」など、要望が寄せらています。さらに県議会で、柳下県議の質問に「所沢市が保健所を設置する時は、県として最大限支援する」という知事答弁を紹介し、どの部署がどのように検証・検討していくのかと質しました。市長は、「保健所を設置には中核市もしくは保健所政令市になる必要がある。現在、中核市移行に関して検討する組織を設置し、調査研究を進めており、報告を待って今後の方向性を定めたい」と答弁しました。
また、西所沢の弘法の井戸付近の行政道路の水たまり問題では、担当部長から「県に対応を求めたい」との答弁がありその後、緊急工事が行われ改善しました。
|
|
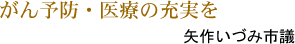
 当市のがん検診は、保健センターまたは健診車・医療機関(乳がん・子宮頸がん)で実施されています。しかし、人数に限りがあるため、受診率が5%〜12%台で、国が目指す50%と大きくかけ離れています。他の自治体のように、地域の病院で健康診査と一緒にがん検診が受けられるよう改善を求めました。また、子宮頸がんワクチン助成も質問。 当市のがん検診は、保健センターまたは健診車・医療機関(乳がん・子宮頸がん)で実施されています。しかし、人数に限りがあるため、受診率が5%〜12%台で、国が目指す50%と大きくかけ離れています。他の自治体のように、地域の病院で健康診査と一緒にがん検診が受けられるよう改善を求めました。また、子宮頸がんワクチン助成も質問。
これに対し部長は、「がん検診は検査方法など条件整備も必要なため、今後も医師会と協議していく。子宮頸がんワクチンは、国の審議会など動向を注視したい」と答弁。
この他、国民健康保険加入者の6割弱が所得2百万円以下の低所得世帯との実態を、今年の審議会に反映するよう情報提供も求めました。
|
|

所沢駅周辺のまちづくりは、議会特別委員会からの提言があり、市も協議会を立ち上げ「基本構想」を策定。3つのエリアのうち所沢駅東口と駅舎改造は西武鉄道頼み、西武車両工場跡地周辺の西口まちづくりは地権者の反対により、基本構想の具体的な進展はありません。日東地区のうち根岸交差点付近のエリアでの共同化事業がほとんどの地権者の合意がとれ、設計図までできています。高齢者住宅や地元商店を中心にした商業棟、住宅棟などとともに、公園・広場などが配置されています。議会の提言に沿ったまちづくりの第一歩となる共同化事業への支援を求めました。
市長は「関係者の意向を聞きながら、この地区にふさわしいまちづくりを推進したい」と答弁。今後の対応が注目されます。
|
|

当摩市政がスタートして三年目、市長は常々「市民との双方向の市政運営」を掲げながら、この間、市長は当事者の声も聞かないまま福祉タクシー券の削減や国民健康保険税の大幅値上げ。更に廃プラスチック類の本格焼却については、近隣住民や市民の同意は不必要としてトップダウンで強行しようとしています。こうした市政運営に市民からは「説明が不十分、応答が遅い」などきびしい指摘の声が寄せられています。これは市としての説明責任が十分に果たされていないことや意見や要望等に対する「応答」が非常に弱いからです。「市民との双方向の市政運営」になっていない現状をどのようにとらえているのか市長に質問しました。 市長は「市民との双方向の施政運営は、車の両輪のように大事」。さらに「市民からの指摘については、真摯に受け止め市政運営に努めたい」などと答弁しました。
|
|