
労働総研ニュースNo.193号 2006年4月

労働総研ニュースNo.193号 2006年4月
| 目 次 |
・戦後日本財政の流れと「小さな政府」論 |
|
戦後日本財政の流れと「小さな政府」論 安藤 実 |
|
はじめに 小泉内閣のもと、「小さな政府」が流行語になっている。これを「大きな政府の改革」、とりわけ「膨大な財政赤字の改革」と受け取っている人が少なくないかもしれない。しかし、それは善意の誤解である。「小さな政府」は、現代資本主義国家の一つの政策体系であり、国際的現象でもある。そのイデオロギー的側面と政治的意義については、『労働総研ニュース』(06年新年号)で、大木一訓論文が詳細に解明している。 ここでは、「小さな政府」を別の観点から取り上げる。現実の日本政府が、どういう政府か、それを歴史的に取り扱う。そのなかで「小さな政府」論が、どのように登場したか、それが目指しているのはなにかを分析する。いずれにせよ政府を問題にする場合、政府の量(大か、小か)ではなく、政府の性質、誰のための、どういう政治内容なのか、が大事である。 1 戦後日本財政の原点 ポツダム宣言と新憲法が、新しい日本の「政府」のあり方を規定した。日本の降伏条件を示したポツダム宣言(1945.7.26)は、「日本軍国主義権力の除去」(6項)「戦争犯罪人の処罰、民主主義の育成、言論・思想の自由、基本的人権の尊重」(10項)、「民主的・平和的政府の樹立」(11項)を掲げ、それらの実行を迫るため、日本を占領するとした。これを理念的にいえば、軍国主義・天皇制絶対主義・帝国主義から、自由主義・民主主義・平和主義への転換であり、新憲法にそれらの条項が盛り込まれ、新生日本のスタ−トとなった。 しかし新憲法制定までの経過が明らかにしているように、当時の日本政府当局者は、旧憲法的観念から抜け切れず、この理念の転換に対し、執拗な「抵抗」を試みていた。だから憲法こそ新しくなったものの、日本政府の旧い体質は残った。実際のところ、旧日本帝国の政府機構のうち、陸海軍など軍事機構は解体されたが、占領軍の方針もあり、天皇制は「象徴」として残され、中央官僚機構もほぼ温存された。ある意味で、戦後日本の歴史は、こういう政府の民主化を求める国民のさまざまなたたかいの歴史といえる。 そういう政府のもと、財政面では、「均衡財政」方針が取られた。その具体化が、ドッジライン、シャウプ税制勧告、そして財政法である。ドッジラインは、インフレ収束のため、財政収支の均衡を厳格に指示した。シャウプ勧告も、インフレ抑止作用をもち、税意識を刺激する所得税(累進税制)を中核とする租税制度のほか、中央集権的官僚支配を改革し、地方自治の育成を目指し、行政事務の再配分、補助金制度や地方税制の改革、また平衡交付金制度を提案した。財政法は、第4条および第5条に国債発行制限規定をおき、インフレを防ぎ、憲法第9条を財政面で担保するはずだった。 2 再軍備 アメリカの対日政策の転換により、まだ占領下の1950年、朝鮮戦争を機に、GHQが警察予備隊の創設を指令し、解体した軍事機構の再建、すなわち再軍備がスタートする。これはポツダム宣言や新憲法に違反する上、当時の国民感情から見て、許し難いことだった。だからマッカーサー元帥は、警察予備隊7万5千人の予算措置について、国会で審議・議決するのを許さなかった。財政法の「移用」規定を変更するという非常手段を用いた。隊員の訓練も装備も、いわばアメリカお仕着せの「軍隊」が誕生した。 1951年、講和条約と同時に日米安全保障条約が結ばれ、在日米軍に基地を提供し、日本は軍備増強を約束する。その後、日米安保体制の下で、警察予備隊は保安隊、そして自衛隊へ成長していく。歴代の自民党政府は、この対米従属的な軍事機構の再建・強化を、なかば非公然ながら、最重要の課題とする。 1952年、「占領政策是正」の流れのなか、地方自治に対する中央支配体制の復活が始まる。自治庁が発足し、自治体警察の廃止が相次ぐ。同じ流れのなかで、シャウプ税制も「修正」されていく。富裕税や付加価値税が廃止され、資本蓄積の促進を至上命題に、投資や貯蓄が税制上優遇されていく。財政法では、「継続費」規定が復活する。表向きは公共事業のためとされたが、実際のところ軍事費増加の仕組みに利用される。 3 高度成長期の財政 1950年代後半から始まる高度成長期には、「均衡財政」の枠内で、国民所得の増加を上回る財政規模の拡大が続く。それは、インフレ的財政運営と特徴づけることができる。その内容は、素材型・組立型重化学工業の競争力強化のための財政出動であり、公共投資中心の経費構造ができあがる。輸銀、開銀など政策金融も動員された。 このインフレ的財政運営の手法を可能にしたのは、広汎な大衆負担だった。… (1) 年度内に生じる税の「自然増収」を財源に、補正予算を組み、財政規模を膨張させた。税制構造が、この「自然増収」を可能にした。まず、(1)個人所得税の独特な累進構造が上げられる。税率の刻みが、中堅所得以下の階層で細かくなっており、急激に累進する。本来、高額所得層をとらえる累進税率が、大衆所得の僅かな上昇もとらえ、大幅な税収増となった。また、(2)重化学工業を中心に高利潤が実現し、法人税収の急増をもたらした。そして、(3)家庭電化や自動車の普及という消費生活の変化を反映し、間接税収入も増えた。1954年度以降、揮発油税が道路事業の特定財源となり、公共投資膨張のテコとなる。 (2) 財政投融資が、信用財源動員の機構として強力な役割を演じる。借入れが許される特別会計や政府関係機関(公庫・公団等。その多くは、公共事業の実施機関)の新増設ラッシュ。1960年代には、社会保障積立金が郵便貯金と並ぶ有力な財投資金源になる。厚生年金保険は、急増する若年労働者を保険料拠出義務者に組み入れていく。年齢構成が若く、年金給付比率もまだ低いため、積立金が累増し、財投資金として効果的に機能した。国民年金保険も加わった。… この経済成長、そして財政膨張と平行しながら、軍事機構の再建・強化は着々と進む。1954年、自衛隊に組織がえ。55年、「保守合同」により、「憲法改正」を党是に掲げた自民党発足。今日に及ぶ長期の政権党である。57年、国防の基本方針のなかに、「国力・国情」論が据えられ、経済の発展と国民の意識「改革」が、軍備強化の前提条件として明確に位置付けられる。経済発展計画に対応した形で、長期防衛計画の策定が始まる。60年、国民的大闘争が展開されたなか、新安保条約が「自然成立」する。在日基地が攻撃された場合、「日米共同作戦」(第5条)が規定される。 4 国債発行政策 増加率の高い積極予算方式を続けた結果、1960年代前半に、「均衡財政」形式は限界に達した。1964年度補正予算は、税の自然増収が減り、歳入不足となる。続く65年度には、不況の影響で、税収が異常に落ち込み、補正予算で国債発行に追い込まれた。 1966年、本格的な国債発行が開始される。「財政新時代」の呼び声のもと、「建設国債」主義(財政法第4条但し書)を掲げ、主力重化学工業部門の合理化・量産化の態勢に対応する公共投資を拡大していく。公共投資の経済波及効果が喧伝され、「建設国債」は「良い国債」、のイメ−ジがふりまかれる。 国債政策は不況期だけでなく、景気のすべての局面で、財政に組み込まれ、財政規模拡大を裏打ちした。その意味では、ケインズ主義的財政政策の一面的利用といえる。しかも「建設国債」は、公共事業財源として発行されたから、いわば特定財源の性格をもった。こういう財源に恵まれ、各種の公共事業が、何次にも及ぶ長期計画として継続され、拡大された。その結果、公共投資関連の巨大企業は、財政と深く結びつき、「政官財癒着」が完成する。天下りと談合が横行する、典型的な浪費構造である。 その一方で、本格国債の発行を機に、財政当局者から「財政硬直化論」が高唱される。経費を、「投資的経費」(公共事業関係費)と「消費的経費」(経常費)に分け、「投資的経費」は、政策判断で「弾力的」に増減できるが、「消費的経費」は、法律や制度に基づいているため、「硬直化」(自然増)しやすいと主張。これは、公共事業費優先、「消費的経費」(公務員給与や社会保障関係費)抑制の論拠とされる。 1967年、第三次防衛計画のなかで、兵器国産の方針が打ち出され、三菱重工業を筆頭に軍需生産が本格化していく。沖縄返還交渉が転機となり、日米安保条約の「変質」が現実化する。日米首脳会談時の佐藤首相の発言、「韓国と台湾の防衛に関心をもつ」に対し、これまで「安保条約と米軍基地は、ただ日本防衛のため」としてきた日本が、「自国以外の地域の防衛に関心を示した」として、アメリカ側から歓迎される。このあと日本国内では、政府や財界が「国を守る気概」の鼓吹に乗り出す。 同じく1960年代後半、韓国とインドネシアを皮切りに、アジア各国に対する経済協力が始まる。韓国援助は、アメリカの肩代わりであり、インドネシア援助は、スハルトの反共クーデターが契機になった。1966年、日本はアメリカと協力しながら、アジア開発銀行設立に主導的役割を果たす。また、円借款の機関として海外経済協力基金を設立し、経済大国化を背景に、アジア地域への進出・経済協力を本格化していく。 5 「歳入欠陥」と「赤字国債」 1975年度の「歳入欠陥」は、かつてない巨額(3.8兆円)となった。オイル・ショックを契機とする戦後最大の不況、それによる法人税と所得税の減収のためであった。法人所得は景気の変動に強く影響を受けるが、法人税の特別措置による、利益の過小計算の仕組みが、税収の低下幅を一層拡大した。 「建設国債」を発行対象経費の限度一杯に発行しても、「これだけ巨額の歳入不足は、補填しきれず」(大蔵省)、75年度補正予算において、財政法では許されない「赤字国債」(「財政法特例法による国債」)の発行に追い込まれた。「特例国債は、75年度かぎりの特例措置」のはずが、その後もけじめなく発行が続き、「建設国債」ともども借金の山を築く。 自民党政府は何度か「財政再建」=「赤字国債の発行ゼロ」を宣言するが、容易に成功しない。しかも、こういう考え方だと、たとえ「財政再建」ができたとしても、「建設国債」の方は手つかずだから、公共事業に偏ったインフレ的財政運営は変わらない。つまり国債の累積傾向は続くことになる。… 1976年、三木内閣は軍事費のGNP比1%枠を設定。当時の軍事費の水準からすれば、それは軍事費抑制というより、逆に増加目標となった。70年代、ベトナム戦争に介入し、敗北したアメリカは、アジア戦略の立て直しをはかるなか、日本の軍事的役割を見直す。78年、日米防衛協力のための指針(ガイドライン)が、その具体化である。そこでは、「日本有事」、「極東有事」などの戦争を想定し、一連の日米共同作戦計画がつくられ、実動演習も実施。それにより作戦、情報、通信、後方支援、装備が点検される。こののなかで、日本の法体制が作戦行動の障害になることが認識され、「憲法改正」への動機となる。自衛隊は、世界最強の米軍と同じ作戦構想をもち、同じ装備、同じ情報・補給システムを整備・運用することになるわけだから、当然高くつく。 駐留米軍経費のうち、負担義務のない基地労務者給与の一部などを負担し始める、いわゆる「思いやり予算」。日本は、世界で10位以内に入る、軍事費大国へ。 6 第二臨調路線と「小さな政府」論 「小さな政府」論が、「民間活力」論と並んで登場するのは、「増税なき財政再建」を掲げた1980年代の第二臨調路線においてである。 第二次臨時行政調査会の土光敏夫会長は、かねてグル−プ1984年による「日本の自殺」(『文芸春秋』、1975年2月号に掲載)を読んで感動し、その抜き刷りを自費で10万部つくらせ、各方面に配布したという。 かれは臨調会長としての行革哲学を、この「日本の自殺」に負っていると公言して憚らなかった。それは一種の福祉亡国論で、「国民が自らのことは自らの力で解決するという自立の精神と気概を失うとき、その国家は滅亡するほかはない。福祉の代償の恐ろしさは、まさにこの点にある」というもの。 また、日本モンペルラン協会会長として、ハイエクの影響を強く受け、日本的新自由主義の提唱者として知られる木内信胤は、臨調専門委員に加わり、その理念を、『行革を考へる』(1981年)という著作で展開している。それは、「小さな政府」論を援用した行財政改革論である。 このなかで木内信胤は、政府の仕事を、(1)是非やらねばならないもの、(2)条件つきでやってよいもの、(3)やってはならないもの、というふうに分ける。 そして、(1)の「是非やらねばならないもの」は、国防や治安の分野であり、これら以外の仕事に手を出す場合は、きわめて限られている、という思想に立つのが、「小さな政府」論であると言う。この場合、たとえば社会福祉は、(2)「条件つきでやってよいもの」に入れられる。(3)は、経済活動に対する政府規制ということになる。 こういう考え方に指導された第二臨調の答申(1981年)は、「真に救済を必要とする者」を除き、国民に「自助・自立・自己責任」を求め、社会福祉に関係する「行政の縮減・効率化」を提案した。その具体化が、毎年のように行われる社会福祉関係費の自然増分の一部カットであり、受益者負担の拡大である。 この「福祉見直し」論=「小さな政府」論は、「国際貢献」論と裏腹の関係にあった。土光敏夫、細川隆元、加藤寛の対談記録、『土光さん、やろう』(1982年)によれば、第二臨調の目標は二つ、「活力ある福祉社会の建設」と「国際社会に対する積極的貢献」。そして「活力ある福祉社会」とは、「政府に頼るな。自分のことは自分でやれ」であり、「国際貢献」とは、「日本の経済力・財政力を国内で無駄に使わず、外へ向け…名誉ある国際的地位」を得ることだという。 したがって臨調路線では、「国際貢献の経費」、つまり軍事費や経済協力費を優遇することになるのである。このように「小さな政府」論は、「国際貢献」論とワン・セットで登場したことで、憲法理念に対する挑戦という意味をもった。木内信胤も、「将来の国の在り方」として、「無責任な平和主義」を「何とかしなければ、取り返しのつかないことになる」、「憲法問題…早く割り切ったらどうでしょう」(p.93)と主張していた。… 臨調路線が展開された1980年代、日本のODA(政府開発援助)は急増し、90年代を通し、世界一となる。その主要な援助対象国の選定が、アメリカの世界戦略に対応し、アメリカ当局者との協議を経ていること、また円借款の援助案件が、日本企業の対外投資にも役立つ産業基盤づくりに重点がおかれ、いわば国際的な公共投資という性格をもつことが特徴である。 1984年、中曽根首相は軍事費のGNP比1%枠撤廃を、米特使に約束する。「国際国家日本が責任逃れをしていないことを示すため、私の手で、この枠をはずす。」… 7 竹下税制改革 1989年、竹下内閣が消費税の導入に成功する。竹下税制改革の骨格は、直接税(所得税や法人税)の減税と、間接税の改革(物品税廃止と消費税の導入)である。 竹下税制改革は、税負担公平原則の転換を伴っていた。政府税調は、新しい租税理念として、「薄く」、「広く」、「活力」などを唱えているが、それは、応能負担(累進税制)を公平理念としてきた、シャウプ税制からの離脱を意味した。すなわち、「薄く」とは、金持ち減税=所得税の累進税率のフラット化を指し、「広く」とは、庶民増税=消費税導入と課税最低限引下げ(人的控除の縮小・廃止)を指す。そして「活力」とは、「小さな政府」の意味で、福祉国家の夢を捨てることである。 竹下税制改革は、バブルの時期(1990〜93年)にぶつかり、大幅減税にもかかわらず税収が増え、特例公債発行ゼロ、すなわち自民党政府のいう「財政再建」を達成した。しかし94年度以降、再び特例公債に依存するようになり、95年の公債発行総額は、20兆円台にふくらんだ。97年度に、消費税の税率を5%に引上げた影響で、不況におちいったあと、景気対策として、99年度から法人税率下げ、所得税の最高税率引下げ、定率減税など、大減税の代わり財源の名目で、98年度から公債発行額30兆円台、過去最高レベルへふくらんだ。… 特例公債発行ゼロを達成した1990年に、アメリカから湾岸戦争の戦費分担(1兆円)要求があり、さっそく特例公債を発行して、それをまかなった。自民党政府の対米従属性を示す一例。96年、日米安保共同宣言(駐留米軍10万人に対し財政支援。その行動範囲を日本と極東から、地球的規模へ広げる)。以後、急ピッチで日米共同作戦の態勢づくりが進み、憲法改正も日程に上がってきそうな動きである。97年、新ガイドラインの策定。日本が攻撃されなくても、「周辺地域における事態」に米軍を後方支援(輸送や補給)する。これを受けて99年、周辺事態法成立。 また、国旗・国歌法。そして2000年、衆参両院で憲法調査会の設置。 8 小泉改革(21世紀初頭) その発足当初、公債発行額30兆円以下を実現し、財政構造改革へつなげると公約した小泉内閣。しかし第一年目につまずき、結局、その在任中の2002年度から05年度までの間、公債発行額は、34兆円〜36兆円と過去最高額を続け、公債依存率も、42%〜44%と、これも過去最高の依存率が続いている。あの塩川財務相の言葉を借りれば、「めちゃくちゃな予算」を続けてきたことになる。その結果、公債残高は、2001年度末389兆円から、05年度末538兆円へ、約150兆円増やした。故小渕首相をしのぐ「借金王」というところ。これが小泉改革の財政的成果である。そして小泉後の財政課題といえば、消費税の増税であり、その上げ幅と時期だけが問題であるかのごとき状況になっている。… 小泉首相は、多くの日本国民の平和への願いを逆なでし、中国や韓国の国民感情を傷つけるのを意に介せず、毎年の靖国参拝。また、自衛隊のイラク派遣(03年度予備費から350億円)を強行。軍備強化は惜しまず、大型の輸送機・輸送艦・ヘリ空母、空中給油機など、これまでのタブ−を破り、高価な攻撃的兵器のオンパレード。そして宇宙の軍事利用へ道を開く、情報収集衛星。費用は膨大、効果は不明のミサイル防衛システム導入。イラク復興支援(03年度、無償資金協力1000億円)。06年度、「思いやり予算」特別協定を延長。さらに、米軍再編の移転費用負担を押し付けられている。 国内では、「防衛省」へ昇格の問題や武器輸出禁止三原則を緩和する動き。 これまでの流れをまとめると、「小さな政府」とは、経済大国、援助大国、借金大国、軍事大国、消費税大国は許せるが、「福祉大国」だけにはしたくない、の意味であることが分かる。 9 フリードマンの「小さな政府」論によせて フリ−ドマンは、『選択の自由』(西山千明訳、1980年、日本経済新聞社)のなかで、政府(公僕という階級)に「隷従」(ハイエク)するのではなく、「政府に対して厳しい制限を設け、自由な個人の自発的協力に依存する」という選択(p.9)を提唱している。かれは基本的原則として、「私益追求が見えざる手に導かれて(強制なしに)人々を協力させる。」(A・スミスの経済原則)と「人は自分の価値観を追求する権利をもつ。」(T・ジェファ−ソンの政治原則)を上げる。(p166)…これはいわば、法的規制からの自由宣言というおもむきである。 政府の役割も、アダム・スミスにならっている。…(1)他の社会の暴力に対し社会を防衛、(2)他の構成員による不正や強制から保護する任務、(3)ある種の公共事業と公共施設。 このうち、(1)と(2)は、「単純明快」で、「このような保護がなければ、どんな選択の自由もない。」(p47)これに対し、「第3の任務は、濫用される危険がある。」(p54) だが、「濫用」というなら、(1)の「防衛」でも、(2)の「警察」でも同じではないか。あるいは、一層大きな「危険」があるのではないか? しかし「単純明快」に割り切るフリ−ドマンに、そういう問題意識は出てこない。こういう自己流解釈を、そのまま現代のアメリカに適用する。だから国家経費のなかで、軍事費と警察・司法費は、それがどれほど巨額であり、どれほど危険で無駄であっても、まるで問題にしない。「聖域」扱いである。もっぱら社会福祉費や教育費が問題であり、圧縮の対象としている。 10 「小さな政府」論とマルクスの見方 (1)資本主義社会における法的規制について 『資本論』の序文のなかで、マルクスは、工場法を「対錘」と呼んでいる。工場法は労働時間に対する法的規制であるが、それなしには資本主義的生産が正常に機能しないという意味で、この「対錘」という名を与えている。つまり法的規制がないのが、自由な資本主義ではなく、法的規制あっての自由な資本主義なのである。それというのも、自由な資本主義が、法的規制を呼び出すのだからである。 マルクスは、資本主義社会における法的規制の例として、イギリスの工場立法の歴史を、第8章「労働日」のなかで、詳しく叙述しているが、その理由を次のように述べる。「こんにちの支配階級は、より高尚な動機は別として、まさに彼ら自身の利害関係によって、労働者階級の発達をさまたげるいっさいの、法律によって処理できる諸障害を取り除くことを命じられている」と。 とはいえ工場法は、資本家階級の好意から生まれたわけではなく、労働者階級の長期にわたる闘争の成果であった。「労働日の限界は、商品交換そのものの性質からは出てこない」(『資本論』p400)。労働力という商品の場合も、買い手の権利と売り手の権利は同等である。そして「同等な権利と権利とのあいだでは、強力がことを決する」以上、しかも労働者階級にとって、まさに生命と生活がかかっている以上、必死の闘争とならざるを得ない。工場法の歴史がものがたるように、「資本は、社会によって強制されるのでなければ、労働者の健康と寿命にたいし、なんらの顧慮も払わない。」(p463) (2)軍事費の独特な性質について マルクスは、『剰余価値学説史』のなかで、軍事費について、その目的が「国の安全」という「非物質的生産物」(一種の状態)であるため、目的の達成にどれだけの経費が必要か、はっきりしないという性質をもっている、と述べている。その意味からすれば、フリ−ドマン流に「単純明快」と割り切れる経費ではなく、あいまいで危険な経費というべきであろう。 あいまいといえば、1980年代以降の日本を振り返っても、軍事費増加には、いつも「脅威」論が、ついてまわっている。代表例は、「ソ連脅威」だったが、ソ連の崩壊後は、国際テロやら、北朝鮮やら、中国やらが、「脅威」に仕立てられてきている。『核時代の国防経済学』の著者ヒッチは、国民世論を動かせば、「軍事費には限度がない」と主張したが、それは軍事費のこの独特な性質を、かれなりに把握していたといえる。 しかし私たちは、このヒッチの主張を逆用すべきだろう。日本国民の歴史的経験に学び、それにもとづいて、国民世論を動かさねばならない。たとえば、その経費が大きいほど、それだけ国民は「安全」かといえば、戦前の日本の場合、予算の大半を軍事費に費やしてきた結果、アジアの近隣諸国民に深甚な損害を与え、自国民も大きな犠牲を払うことになった。安保条約を廃棄し、平和憲法を守ることが、もっとも安上がりの「安全」確保である。 (小論は、2006年3月29日、労働総研政治経済動向研究部会公開研究会での報告に、当日の質問などをふまえて加筆したものである) (あんどう みのる・会員・静岡大学名誉教授) |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
労働総研2005年度プロジェクト・研究部会代表者会議は、3月31日午後1時より5時まで、平和と労働センター・全労連会館3階会議室において、唐鎌直義常任理事の司会で開催された。 冒頭、牧野富夫代表理事は以下のような基調的あいさつをおこなった。労働総研の研究活動のあり方について1年近く検討してきた。それは労働総研設立15周年事業で全労連と共同で実施した「労働組合の実態と課題と展望」調査やシンポジウム「労働政策の新自由主義的展開に対するわれわれの対抗軸を考える」を成功させることと結合して、実践的に深められてきた。本日の会議の討議を踏まえ、次回の常任理事会で次年度の方針案として提案する。そうした角度からの積極的な討議を期待する。 プロジェクト・研究部会代表者会議の討議に先立ち、ナショナル・ミニマムプロジェクトの研究の到達点とナショナル・ミニマム大綱案について、浜岡政好常任理事から以下のような報告がおこなわれた。 ナショナル・ミニマム大綱案 (1)ナショナル・ミニマム確立は急務 (2)日本におけるナショナル・ミニマムをめぐる歴史的検討 1)戦前:恩恵的・慈恵的救済施策も戦争政策で破壊された、2)戦後:健康で文化的な生存権を確立するための闘争、3) ナショナル・ミニマムはたたかいによって獲得され、発展・実態化していく―朝日訴訟闘争の意義=プログラム規定から実態的・具体的規定へ (3)国民生活の最低限を規定する生計費 (4)小泉「構造改革」攻撃への対抗軸としてのナショナル・ミニマムの柱 1) ナショナル・ミニマムの構成要素、2)ナショナル・ミニマムの水準、3)財政保障、4)運営、5)ナショナル・ミニマムを確立する運動課題 報告をめぐって議論がおこなわれた。議論で出された意見をも考慮し、大綱案を深めることになった。ナショナル・ミニマムプロジェクト報告は、『労働総研クォータリー』2006年春季号+夏季号合併号で発表される予定である。 次いで、大木一訓代表理事が以下のような研究所活動あり方検討委員会の報告をおこなった。 報告の基本は2004年度プロジェクト・研究部会代表者会議で提案され、2005年度定例総会で確認され、研究所活動あり方検討委員会で数次にわたり議論し、常任理事会に提案され練り上げられてきたものである。研究所の研究活動は、限られた財政のもとで、より実践的で効率的な成果をあげられるよう、労働総研の研究活動のあり方を次の3類型とする。第1の類型は常任理事会が計画したプロジェクトである。第2類型は全労連など運動団体の要請にもとづいて常任理事会が計画したプロジェクトである。第3類型は常任理事会に2年間の研究計画と研究会メンバーを提出し、常任理事会の承認のもとにおこなわれる研究部会活動である。 大木提案にもとづき討論がおこなわれ、承認された。 大須眞治事務局長が以下のようなまとめのあいさつをおこなった。今日の会議で出された積極的な意見を次回の常任理事会にも反映し、労働総研設立15周年記念行事を成功させた実績を土台に、当研究所の調査研究活動をさらに発展する2006年度方針案を確定するために努力したい。 |
|||||||||||||||||||||||
|
労働総研中小企業問題研究部会 公開研究会のお知らせ
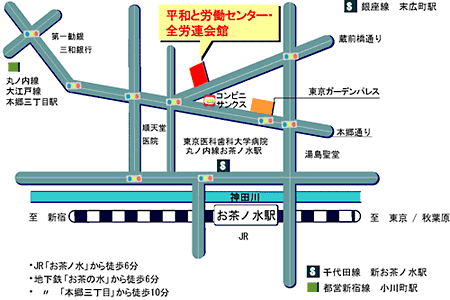 |