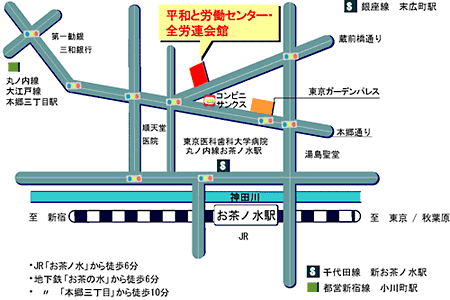|
マンション耐震強度偽装事件、ライブドア事件、米国産牛肉輸入問題に防衛施設庁談合事件と、小泉「改革」のデタラメぶりが次々と明らかになっています。小泉改革の「総仕上げ」どころか、まさに「総崩れ」といった有り様です。しかし、これは小泉政権と経団連がアメリカと一体で進めてきた「構造改革」の当然の結果に過ぎません。そこで今日は「検証:アメリカ型日本改造計画の顛末」と題して、小泉「改革」の背景と特徴を明らかにしながら、その行き着く先について考えてみたいと思います。
本論に入る前に、昨年の総選挙前に起きた不思議な現象についてお話したいと思います。ZAKZAK(2005/09/16)にこんな記事が出ていました。以下はその引用です。
ナゼ読めない…「アマゾン」で1年超も品切れの本──米が日本に提出する「年次要望書」の存在を暴く
日本最大の書籍販売サイト『アマゾン・ドット・コム』で、ある本の品切れ状態が続いている。絶版本や希少本ではない。昨年4月に発売され、今年6月にも9刷となったロングセラーで、版元も大手の『文藝春秋』。ただ、郵政民営化を含めた小泉政権の規制緩和政策が、なぜ、“米国追従”なのかを種明かしする内容だけに、憶測が飛んでいる。
この本『拒否できない日本』(関岡英之著、文春新書)=写真=は、米国政府が毎年10月に日本に提出する「年次改革要望書」の存在を暴く内容。10年来、日本の規制緩和政策が、独占禁止法や郵政民営化、先に成立した会社法など、すべて「要望書」通り実現していく様を描いている。もっとも、「要望書」自体は、米国大使館のサイトで日本語訳が読め、同書は《数年後の日本になにが起きるか知りたいときには必読の文献である》と指摘する。
一方で、その要望実現過程では“内政干渉”もどきの手法もあるようで、日本政府としてはあまり国民に知られてほしくない代物らしい。実際、竹中平蔵郵政民営化担当相は平成16年10月19日の衆院予算委で「存じ上げております」と答弁しながら、郵政法案の審議が大詰めを迎えた8月2日の参院郵政特別委で「見たこともありません」と一転させた。
同書は、「3万8000部売れています。昨年は社内ベスト10に入っています」(担当者)ながら、巨大サイトのアマゾンで買えないのだ。
一体、なぜか。文藝春秋の担当者は、アマゾンでこんな状態になっていることを知らなかった。取次ぎを通じて調べてもらったところ、「アマゾンからの注文が来ていないようです。理由は分かりません」という。ネット上では、「米IT企業の代表格として日本に進出したアマゾンは小泉改革を推し進めたい。先の総選挙では、小泉陣営の邪魔になるから売らないのだ」との憶測が飛び交っている。(一部省略)
昨年の総選挙は、大掛かりなマスコミ誘導が行われたといわれますが、ここまで徹底した言論統制が行われていたとすると恐ろしくなります。背後に小泉自民党を勝利させ、「構造改革」路線を継続させようとする大きな力の存在を感じるからです。
特異な小泉政権
この『拒否できない日本』には、『年次改革要望書』をテコに、アメリカが日本をアメリカ型の社会に「改造」していく過程が明らかにされています。とりわけ小泉政権になってからは、イラクへの自衛隊派兵、郵政民営化法案の成立、牛肉輸入再開とアメリカ政府の要求がそのまま日本政府の政策となって実現しています。なぜ、こうした状態になってしまったのでしょうか。
まず考えられるのは小泉首相と彼の政権の特異性です。慶大同級生として、誰よりも小泉首相の素顔を知るといわれる栗本慎一郎東京農大教授は、「パンツをはいた純一郎」(『週刊現代』2005/12/24号)のなかで小泉首相の人間像についてこんな風に語っています。
「(小泉は)あまり大学にも来なかったし、社会性がなくて友達もいない。(略)しかも、みんなから浮いているのではなくて、沈んでいるんです。友人から無視されるような存在でした。おそらく、高校時代も同じでしょう。その社会性の欠如とそこから来る孤独感が彼の奇矯な政治行動の原点だと思います」
「小泉は通常の意味で、とにかく頭が悪かった。本当は頭がいいんだけど、成績が悪いといったパターンがありますが、彼の場合、ただわかんないだけ。理解カゼロなんです。彼がいかに頭が悪いか。私が'95年に衆議院議員として自民党に入党したときに、一時期彼の『押し掛け家庭教師』をやったことがあります。『金融市場をどうするのか』『戦後の日本経済のなかで、現在はどういう位置にあるのか』、そういったことについて、すでに名の知れた若手リーダーなのにあまりにとんちんかんなので、教えてやろうということになったわけです。それで、最初は私がやったのですが、あまりにダメなので、懇意にしている別の有名教授に応援を頼んだ。…某教授も小泉がそんなバカとは知らないので、日本のためにと、やってきた。(略)後で某教授に『どうですか』と聞いたら、彼がこう断じたのです。『これがわからないとか、あれがわからないということじゃなくて、問題がわかっていない』。小泉は採点のしようがないぐらいバカだというのが正しい評価です。前首相の森喜朗さんも頭が悪そうですが、彼は、自分がわかっていないことがわかるようだ。だから森のほうが少し上です。」
「小泉は前妻と離婚していますが、あれは離婚じゃなくて離縁という表現が正しい。(略) 離縁の理由は、彼の弟が代弁して言うには、前妻の一家が創価学会の会員で、それがいやだった、と。小泉が創価学会が大嫌いであることは間違いないでしょう。(略)ところが、小泉は政権を維持するためにその創価学会と手を組んだ。それは、権力欲、地位欲が強いからです。逆に言えば地位のためなら何でもできるのが小泉という男なのです」
靖国参拝についても、栗本教授は興味深いコメントをしています。
「靖国神社参拝問題で、小泉は中国、韓国の怒りを買っていますが、靖国神社に対して、彼は何も考えていないですよ。私はかつて国会議員として『靖国神社に参拝する会』に入っていた。そこで、小泉に『一緒に行こうぜ』と誘ったのですが、彼は来ない。もちろん、靖国参拝に反対というわけでもない。ではなぜ行かないのかといえば『面倒くさいから』だったのです。ところが、総理になったら突然参拝した。きっと誰かが、『靖国に行って、個人の資格で行ったと言い張ればウケるぞ』と吹き込んだのでしょう。で、ウケた。少なくとも彼はそう思った」──。
栗本教授によれば、小泉首相という人は、社会性が無く、頭が悪く、特別な信念があるわけでなく、しかし権力欲が強く、地位のためなら何でもできる──そういう人間のようです。
間違って首相になってしまった男
何故このような無能で特異な人間が一国の首相になってしまったのでしょうか。答えは簡単です。他に人材がいなかったのです。自民党は小渕政権で終わっていました。もう少し遡れば、社会党と連立政権をつくった時に事実上終わっていたのです。それなのに無理やり延命をさせた。それ以降の政権はいわば徒花に過ぎない。自民党は政策も人材も完全に枯渇していた。そこで自民党は仕方なく「奇矯な政治家」に託したのです。
しかし、小泉総裁は誕生したものの、党内基盤は極めて弱く、しかも彼は自民党を否定(少なくとも表向きは)していましたから、最初から党に頼ることはできませんでした。そこで、彼が拠り所としたのが官僚(財務省)とアメリカ(ブッシュ政権)だったのです。小泉首相の総裁選公約をまとめたのが財務官僚だったことはよく知られていますし、対米盲従は周知の事実です。つまり、小泉政権は与党自民党ではなく、アメリカと官僚に依存することによってのみ存続し得る、歴代自民党政権のなかでも極めて特異な政権だったのです。歴代の首相は、アメリカから難題を押し付けられると、与党の抵抗や反発を理由にアメリカの要求をある程度拒否することができました。しかし、小泉政権は最初からアメリカの要求を全面的に受け入れることによって政権を維持しようとしたのです。アメリカとしても、これは大変好都合でした。しかも相手が頭が悪く、物事の本質を理解する能力をまったく持たず、自己顕示欲と権力欲の固まりのような人間となれば、ブッシュ政権や外資が放っておくはずはありません。
小泉「構造改革」の振付師
ブッシュ政権の経済外交戦略は“Campaign 2000:A Republican Foreign Policy”(『フォーリン・アフェアーズ』誌(2000年1−2月号)に述べられています。これをまとめたのはロバート・ゼーリック(Robert
Zoellick)という人物です。現在、彼は国務副長官ですが、レーガン、ブッシュ(父)政権時代から共和党外交エリートの一人でした。ブッシュ(父)政権下ではメキシコとの自由貿易協定(NAFTA)の締結に尽力し、アジア太平洋経済協力会議(APEC)の発足でも重要な役割を果たしました。ブッシュ(息子)政権では01年から05年までUSTR(通商代表)として、日本との通商政策や規制緩和交渉の先頭に立ってきました。小泉政権が誕生したのが01年ですから、まさにゼーリックこそ小泉「構造改革」の振付師と言ってよいと思います。彼は自分の政策スタッフに、永年、日本に滞在して日本の政治経済分析を行っていた優秀なブレーンを抱えており、日本の「構造問題」には精通しているといわれます。
ところで、ゼーリックはネオコンの代表的シンクタンクProject for the New American Century(PNAC)のメンバーで、ブッシュ政権のインナーサークルの一人です。ラムズフェルド国防長官やウォルフォイッツ国防副長官(現在は世銀総裁)らほどの超タカ派ではありませんが、タカ派であることに変わりはありません。ネオコンが軍事・政治問題に偏っているなかで、彼は経済、軍事の両方に精通した数少ない人物といわれます。彼はウォール街とアメリカ財界でも高く評価されています。それは彼が金融業界や多国籍企業の政府代表であるにとどまらず、これらの業界や企業の幹部として直接、関わってきたからです。例えば彼はゴールドマンサックスやアライアンス・キャピタルの役員をしていたことがありますし、通商代表に就任する前は、後でお話するエンロンの顧問も務めていました。要するに彼は「アメリカ株式会社」の利益代表なのです。
彼は前述の“Campaign 2000:A Republican Foreign Policy”のなかでクリントン前政権の外交政策を酷評しています。クリントン政権が経済政策を限定的に捉え、社会問題や環境問題に偏り過ぎてアメリカが本来追求すべき外交目標を見失ったというのです。そこで彼は、共和党の新しい外交政策は、アメリカの圧倒的な軍事力を基本に据えるべきだと主張しました。つまり、アメリカは強大な軍事力を背景にしてアメリカ企業の利益を追求すべきだというわけです。彼が過去にNAFTAやAPEC、さらにWTOなどの多国間協議に関わってきたために、彼を現実主義的な自由貿易主義者とみる人もいますが、実際には彼はAPECやWTOをアメリカの国益を実現するための手段としか考えていません。事実、USTR時代の彼は多国間の枠組みを無視して、途上国と二国間協議を進め、強引にアメリカの輸出や投資に対する障壁を撤廃させました。彼の目標は、アメリカの企業のための「グローバライゼーション」を実現することです。彼はかつてグルーバル化についてこう語ったことがあります。「葬儀業界もいまではグローバル化が進み、ヒューストンの葬儀会社は世界20ヵ国で墓地を販売している」と。
ネオコンについて、もう少し説明しておきたいと思います。アメリカの識者の間で、ヒトラーの『我が闘争』と同じように位置付けられているものがあります。先ほどお話したネオコンのシンクタンクPNACの基本的政策文書“Rebuilding
America's Defenses”がそれです。これは、アメリカの世界支配のための軍事力強化の必要性を説いたものですが、あまり注目されませんでした。その意味で、戦争が終わるまでほとんど注目されなかった『我が闘争』と似ているというわけです。このなかには、サイバースペース(インターネット)のコントロールとか、ロボットの兵隊とか、未来の戦争について恐ろしいことがたくさん書かれています。日本では走ったり、お茶を運んだりするロボットがニュースで紹介されていますが、おそらく日本のロボットに最も強い関心を抱いているのはアメリカのネオコンと軍部ではないでしょうか。ロボットが戦争するようになれば、アメリカの大統領も世論に縛られずに、自由に戦争を遂行できるようになるでしょう。
少し話がそれてしまいましたが、このなかで示されているネオコンの考え方は次のように要約されます。まず、アメリカは世界唯一の超大国であり、これは神の恩恵によってもたらされたものである。世界の秩序を維持できるのは神によって選ばれたアメリカのみである。アメリカはこの絶対優位を永続化する必要がある。そのために、新たな挑戦国の台頭を阻止する、あるいは地域的な勢力に成長させないようにしなければならない。潜在的挑戦国にはアメリカの庇護を約束し、大国への野望を放棄させる必要がある。他方で、アメリカの利益を守り、アメリカ的価値、即ちアメリカ型民主主義とアメリカ型市場経済を世界に広めなければならない。日本などの先進国には、現行の政治経済秩序=アメリカ型市場経済=を擁護させる、としています。
これが、アメリカの「日本改造計画」の背景です。ゼーリックにとって、日本の条件は極めて好都合でした。なぜなら、アメリカ型の構造改革を推進すると宣言した小泉政権が誕生したからです。ゼーリックの任務は、小泉=竹中チームを支援し、彼らの「改革」がアメリカ企業の利益に合致するように監視することでした。
「日本改造計画」の系譜
ところで、最近注目されるようになった『年次改革要望書』は、小泉政権が誕生するずっと前の94年から毎年、発表されているものです。それ以前の日米関係は、貿易収支の悪化に伴って、個別分野で貿易摩擦が発生すると、日本側が輸出自主規制などによって対応する、というのが一般的でした。ところが、89年9月、当時の宇野首相とブッシュ(父)大統領の間で行われた「日米構造協議」、93年7月の宮沢首相とクリントン大統領の「日米経済包括協議」を経て、アメリカの対日要求は次第に日本の伝統や慣習を含め、制度全体を変えようとする方向に傾いていきました。この背景にはいわゆるリヴィジョニストらの「日本異質論」の台頭がありました。そうしたなか、宮沢首相とクリントン大統領は93年の首脳会談で、お互いに相手国政府に対して改革の要求を出し合おうということになり、94年10月、第1回の『米国政府の日本政府に対する年次改革要望書』が発表されたのです(注)。さらにその後、97年6月には「強化されたイニシアチブ」(日米規制緩和対話)が加わり、01年3月、森政権下で「総合規制改革会議」が設置されました。
(注)『要望書』はアメリカに関心のある6つの産業分野と5つの「分野横断的テーマ」を網羅していました。6つの産業分野とは通信、IT、エネルギー、医療・医薬、金融、流通で、5つの分野横断的テーマは「競争政策」「透明性及びその他の政府慣行」「民営化」「法務制度改革」「商法」です。
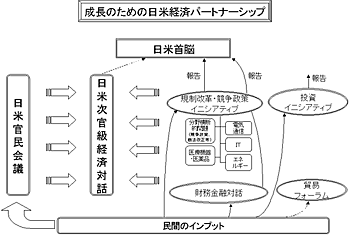 小泉政権になって、対日要求の制度化はさらに進みます。01年6月、キャンプデーヴィッドで開かれた日米首脳会談において、小泉首相は日本の「企業債務及び不良債権に効果的に対処することを含め、日本経済の再生のための構造改革及び規制改革を精力的かつ包括的に実施する」との決意を表明し、ブッシュ大統領との間で「成長のための日米経済パートナーシップ」で合意しました(図参照)。この合意に基づいて設けられたのが「日米規制改革イニシアチブ」と「日米投資イニシアチブ」です。アメリカの規制改革要求は引き続き『年次改革要望書』に、投資に関する要望は「対日投資促進プログラム」に反映され、その達成度合いが十分でない場合は毎年春、USTRが『外国貿易障壁報告書』で米議会に報告し、日本に圧力をかけるという仕組みです。こうしたなかで小泉政権は04年4月、「規制改革・民間開放推進会議」を設置し、民営化の道をひた走ることになるのです。 小泉政権になって、対日要求の制度化はさらに進みます。01年6月、キャンプデーヴィッドで開かれた日米首脳会談において、小泉首相は日本の「企業債務及び不良債権に効果的に対処することを含め、日本経済の再生のための構造改革及び規制改革を精力的かつ包括的に実施する」との決意を表明し、ブッシュ大統領との間で「成長のための日米経済パートナーシップ」で合意しました(図参照)。この合意に基づいて設けられたのが「日米規制改革イニシアチブ」と「日米投資イニシアチブ」です。アメリカの規制改革要求は引き続き『年次改革要望書』に、投資に関する要望は「対日投資促進プログラム」に反映され、その達成度合いが十分でない場合は毎年春、USTRが『外国貿易障壁報告書』で米議会に報告し、日本に圧力をかけるという仕組みです。こうしたなかで小泉政権は04年4月、「規制改革・民間開放推進会議」を設置し、民営化の道をひた走ることになるのです。
『年次改革要望書』はお互いに要求を出し合うわけですから、当然、日本側もアメリカに出しています。出してはいるのですが、日本の要求は包括的なものが多く、また日本側の腰が引けているため、ほとんど成果は上がっていません。それに対してアメリカ側の要求は戦略的且つ具体的で、確実に成果を上げています。これまで法制化された主なものを挙げてみると、持ち株会社解禁(97年)、NTT分割(97年)、建築基準法改正(98年)、株式交換制度の導入(99年)、有価証券の時価会計の導入(00年)、大規模小売店舗法の廃止(00年)、確定拠出年金制度(01年)、法科大学院の設置(04年)、裁判員法成立(04年)、郵政民営化法成立(05年)、外国株対価によるM&A(凍結中)などです。これらはほとんどすべてアメリカの要求に基づいて日本政府が決定したものです。こうした法改正の結果外資による日本支配が急速に進みました。小泉政権になってから邦銀の90%、製造業の70%、東京の主だったホテルのほとんどが米国資本傘下に置かれています。しかし、小泉首相は外資の支配を「悪いこととは思わない」と平然と語っています。
大きい在日アメリカ商工会議所の役割
|
対日要求実現の流れ
|
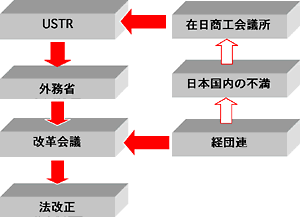 |
それにしても、主だった国内の抵抗もなく、なぜこうも簡単に、アメリカの要求が次々と実現していくのでしょうか。
そのカギは、在日アメリカ商工会議所の役割にあります。アメリカ企業の要望を取りまとめるのは在日商工会議所です。商工会議所はそれぞれの分野の専門家を招いて頻繁に情報収集のための勉強会を開いています。ここでは、在日アメリカ企業の不満だけでなく、日本のジャーナリストや、アナリスト、ビジネスマンや消費者などからも意見を聞きます。そうすることによって、日本人が自国の制度に対してどういう不満を抱いているかを知るのです。その中からアメリカ企業のインタレストに合致するものを要求としてまとめて、USTRに報告する。USTRはそれを『対日要望書』に書き込む。いったん文書になりますと、それが正式な約束のようになり、日本政府に対するプレッシャーになります。アメリカは毎年、毎年、実現するまで要求を繰り返します。
ここで重要なことは、アメリカは戦略的に、日本の世論について、十分な調査・研究を行っているということです。日本の業界や消費者の不満を知ったうえで、日本政府に要求を突きつけてくるわけです。だから、日本の世論がアメリカの要求を支持する場合が多いのです。たとえば、談合に対しては世論の批判があることを彼らは良く知っています。彼らはそうした世論の批判を取り入れながら、独禁法の強化や国際競争入札の導入(例えば関西空港プロジェクト)を要求してくるのです。病院や医療サービスに対する不満が強いことも知っています。昨年11月に内閣府が実施した特別世論調査によれば、63%が規制改革・民間開放について「さらに進めるべき」と答え、規制改革を推進すべき分野として最も多い58.9%が「医療分野」を挙げています。アメリカは日本のシステムの弱点、これはまさに自民党政治がもたらした弊害でもあるのですが、そこを巧みに突いてくるのです。
郵政民営化の場合は、彼らは日本の銀行・保険会社の「民業圧迫」という不満を利用しました。また、郵貯や簡保資金が財政投融資を通じて無駄な公共事業に使われ、財政赤字や不正・癒着の元凶になっているという国内世論も彼らにとって追い風になりました。小泉首相は、「アメリカに言われて郵政民営化をやったのではない」と主張しています。その根拠として、「アメリカよりも先に郵政民営化を提唱した」と自慢しています。たしかに記録によれば、小泉首相が郵政民営化を最初に提唱したのは92年、宮澤内閣の郵政大臣時代のことです。それから2年後の94年に彼は『郵政省解体論』を発表しています。実は、小泉首相が郵便局に反感を持つようになったのはそれよりかなり前の69年、彼が総選挙に初出馬して負けた時からだ、という説もあります。この時、小泉首相のあるスキャンダルを理由に地元の選挙区の特定郵便局長が彼を支持しなかったことが敗因となり、小泉氏はそれ以来、郵便局を恨むようになった、というのですが、真偽のほどはわかりません。
しかし注目すべきは、小泉氏が『郵政省解体論』を発表した翌年に、アメリカが早速、『要望書』のなかで郵政民営化を取り上げていることです。95年の『要望書』には「郵政省のような政府機関が、民間保険会社と直接競合する保険業務に関わることを禁止する」
と書かれています。翌96年の『要望書』では、「郵政省のような政府機関が、民間保険会社と直接競合する保険業務に関わることを禁止する」「政府系企業への外国保険会社の参入が構成、透明、被差別的かつ競争的な環境の下で行えるようにする」よう求めています。そして、99年の『規制改革要望書』では「米国は日本に対し、民間保険会社が提供している商品と競合する簡易保険(簡保)を含む政府及び準公共保険制度を拡大する考えをすべて中止し、現存の制度を削減または廃止すべきかどうかを検討することを強く求める」と要求はどんどんエスカレートしていきます。
アメリカは、自分たちの利益に合致する人物、あるいは利益を代弁してくれる人間を探し出し、育て、彼らを通じて自分たちの目的を達成してきました。小泉首相はアメリカに利用されただけなのです。竹中大臣も同じです。「トロイの馬」は日本でつくられたのです。
郵政民営化は医療制度破壊に通ず
アメリカの対日戦略は、郵政民営化で終わるわけではありません。次の狙いは医療・医療保険です。それは、すでに99年の『規制改革要望書』のなかにはっきり書かれています。彼らの狙いは、「民間保険会社が提供している商品と競合する簡易保険(簡保)を含む政府及び準公共保険制度を拡大する考えをすべて中止し、現存の制度を削減または廃止」することにあります。
米国政府は94年以来一貫して、医療機器・医薬品を『年次改革要望書』の重点項目に位置付けてきました。また、『投資イニシアチブ』では医療サービス市場への米国企業の参加を要求してきました。彼らの狙いは日本の医療制度に市場原理を導入し、公的医療保険を「民」すなわち米国の製薬業界、医療関連業界、そして保険業界に対して市場開放することにあります。この問題では宮内義彦・オリックス会長(規制改革・民間開放推進会議議長)が「トロイの馬」です。
最近、医療保険の適用を受けられず、病院に担ぎ込まれた時はすでに手遅れで、命を落とす人が増えています。小泉政権は医療費抑制のためとして公的保険の給付範囲を縮小し、保険外診療(自由診療)を拡大させようとしています。そうなると民間医療サービス業者が自由に価格や報酬を決定でき、保険外診療分野をカバーする民間医療保険へのニーズが拡大します。アメリカでは4,400万人が無保険者といわれます。それぐらい無保険者がいないと、民営化は成り立たないのです。それが「医療制度改革」の狙いです。アメリカは、お金のある人は高度な医療サービスを受けられますが、お金の無い人は最低限の医療も受けられないという極めて悲惨な社会です。このまま小泉「改革」が進めば日本もあっという間にアメリカのようになってしまうでしょう。
「トロイの馬」をつくったのは
先ほど「トロイの馬」は日本でつくられた、そして小泉首相や竹中大臣や宮内会長がその「トロイの馬」であると言いました。しかし、アメリカだけで「トロイの馬」をつくったのではありません。そこには協力者がいました。日本経団連です。
バブル崩壊で日本の経営者は日本的経営に対する自信を喪失しました。長期の景気低迷に対し、海外からも自民党政府・財界の対応能力に公然と疑問が呈されるようになりました。そうしたなかで自民党と財界は、景気対策(公共事業の追加)によって日本の景気を支えるという従来の手法から、アメリカ型の構造改革(サプライサイド改革)にシフトしていきました。アメリカ主導の「グローバリズム」に翻弄され、「競争力喪失」という妄想に取り憑かれたのです。増大する財政赤字が増税や金利の上昇につながり、それが企業負担を増大させ、国際競争力を低下させるというのが財界の論理でした。エコノミストも、日本の財政赤字が国家を破綻させるという非科学的な論理を展開し、危機感を煽りました。余談ですが、同じ論法は郵政民営化でも使われました。「郵政の赤字を放っておくと旧国鉄の二の舞になる」と。これはアメリカのネオコンが世論操作に使う常套句です。彼らはいつも危機を誇張し、世論を煽動します。たとえばイラク問題では、「イラクの大量破壊兵器をこのまま放っておくとたいへんなことになる」と世論を脅し、武力行使に踏み切りました。しかし、いくら探しても大量破壊兵器は見つかりませんでした。「郵政を民営化すれば財政赤字がなくなる」などというのも絵空事に過ぎません。反対に国民負担が増大する恐れがあります。
経団連が推進する「構造破壊」路線
財界が規制緩和を本格的に主張し始めたのは94年です。同年11月、経団連は「規制緩和の経済効果に関する分析と雇用対策」を発表、そのなかで、「規制緩和が断行されない場合には、・・・円高が進展し、産業の空洞化が不可避となることから、失業が増加するおそれが強い。この結果、日本経済は成長しつつある世界の市場から脱落し、縮小均衡と生活水準の悪化、経済活力の低下という斜陽化の道を辿る危険性が高い。従って、このような事態を回避するためには、規制緩和は避けては通れない道である」と主張しました。そして、規制緩和によって、規制産業において生産性が向上する効果と、内外価格差が縮小する効果を合わせると、95年度〜2000年度の累計では、実質GDPが177兆円増加し、雇用者数は74万人増加するとの経団連の試算も紹介しています。
これ以後、経団連は頻繁に規制緩和・撤廃に関する要望書を政府に提出するようになります。そして98年(小泉政権が誕生する3年前)、経団連は今井新会長の下で、「構造改革路線」に大きく舵を切ります。その年の5月に開かれた第60回総会で採択された決議(「21世紀に向け新たな発展の基盤を確立する」)は、取り組むべき課題の第一番に「構造改革」を掲げ、具体的に以下の点を強調しています。
| (1) |
規制の撤廃・緩和により、高コスト構造を是正する。 |
| (2) |
直間比率の見直しを踏まえ、所得税の累進税率構造および法人実効税率を国際水準に合わせることによって、個人や企業の意欲と能力を引き出す。 |
| (3) |
当面の対策として、不良債権を早期に処理し、金融システム改革を迅速に進めて金融機能の回復を図る。 |
翌99年5月の第61回総会で、経団連は一段と構造改革路線に傾斜していきます。総会決議「産業競争力の強化と経済の活性化のために」は、「景気の本格回復を達成」するためには「供給構造を改革する」しかない、と訴えました。こうした経団連の支援を受けて、01年4月、「聖域なき構造改革」を掲げた小泉政権が誕生するわけです。つまり、経団連の構造改革路線が小泉政権を誕生させたのであって、その逆ではありません。小泉=竹中チームは、経団連が描いたシナリオを演じたに過ぎません。さらに経団連が描いたシナリオもアメリカ版のコピーに過ぎません。それを小泉「改革」などと囃し、あたかも小泉政権の独自政策のように国民を錯覚させたのは新聞やテレビです。小泉=竹中は財界とアメリカのたんなる御用聞きに過ぎないのです。
02年5月、経団連と日経連が合同し、日本経団連が発足すると、経団連の規制緩和・民間開放を求める声は一段と強まり、これに政治資金を絡めるという手法が取られるようになりました。奥田新会長の下でまとめられた「日本経団連新ビジョン」(活力と魅力溢れる日本をめざして)は、「民主導型」の経済社会を実現するため、「与野党の政策と実績を評価した上で、企業・団体が資金協力する際の参考となるガイドラインを作成する。・・・経済界の考えに共鳴し行動する政治家を支援する」と述べています。「政治資金が欲しければ、経団連の言うことを聞け」といわんばかりです。小泉政権は、政権維持のために、こうした財界の意向を受けてがむしゃらに民営化路線を突き進んだのです。最近は奥田会長が「構造改革の加速」といえば、小泉首相も「改革の加速」と言い、まるで「双子」のようです。
このように、構造改革路線の真の推進者は日本の経団連だったのです。追い詰められた日本の財界がアメリカの手法を日本に導入したのです。しかし、それは日本の社会・伝統とはまったく異質の制度を持ち込むことを意味します。当然、日本社会は拒絶反応を起こし、自殺者が急増し、奇妙な犯罪が頻発するようになりました。
「構造改革」のもたらすものは
財界の構造改革(サプライサイド)路線は、最初から破綻する運命にありました。第一の理由は、処方箋が間違っていたことです。サプライサイドは経済が完全雇用状態にあるとき(ボトルネックが生じているような状態)には効果を発揮します。しかし、日本の経済は元々、供給が需要を上回っていました。問題は供給サイドではなく需要サイドにあったのです。そうした状態でいくら規制緩和をしても、景気はよくなりません。むしろ、デフレ圧力を強め、景気を悪化させます。実際、構造改革路線が強まると、日本経済のデフレ圧力は一段と強まり、不況を長期化させました。最近になって、ようやく日本経済も回復しつつあるかにみえますが、これは「改革」の結果などではなく、海外市場の拡大のおかげです。もし、サプライサイド政策を取っていなければ、日本経済の落ち込みはもっと小さく、もっと早く立ち直っていたはずです。
第二の理由は、サプライサイド経済学そのものの限界です。サプライサイドの始まりは80年代のレーガノミクスです。減税や規制緩和により企業の負担を減らせば、企業は投資を拡大し、経済は活性化する、つまり供給を増やせば需要が増えるという倒錯した論理に基づくものです。このサプライサイドがもたらしたのは、株価の上昇を至上命題とする世界でも特異なアメリカの企業文化でした。ところがITバブルが崩壊すると、その矛盾が一気に噴出しました。エンロンとワールドコムの巨大粉飾事件がそれです。経営者が不正をしただけでなく、彼らを監視する会計事務所やアナリストもまったく機能していなかったのです。これが「グローバル・スタンダード」といわれるものの実体でした。アメリカ流の企業会計もコーポレート・ガバナンス(企業統治)も、実際はみせかけに過ぎなかったのです。
ところが、すでに述べたように、バブル崩壊で自信を喪失した経団連は、こうしたアメリカ・モデルを日本に持ち込み、日本を改造しようとしてきました。小泉「改革」の下、強引に規制を壊し、不正を助長する土壌をつくりました。そして、日本でもライブドアの堀江社長が逮捕され、「改革の旗手」が、実は株式分割と粉飾決算を繰り返す「金融詐欺師」に過ぎなかったことが明らかになりました。驚くのは、ライブドアの手法がワールドコムの手法と酷似していることです。ワールドコムは20年間で75件もの合併を繰り返し、業界大手にのし上がりました。小泉「構造改革」こそ、ライブドア事件の元凶なのです。ところが、小泉首相は規制緩和や民営化の「方向」は間違っていない、必要なのは「監視体制」の強化だ、などと嘯いています。アメリカの監視制度は日本の制度より遥かに厳しいものでした。それでも事件は繰り返し発生しました。市場(民間)に任せれば何でもうまく行くという経団連と小泉政権の考え方そのものが問われているのです。
製造業を壊滅させたサプライサイド
アメリカのサプライサイド改革は所得格差の途方も無い拡大をもたらしました。80年代に平均的な労働者賃金の40倍だった CEO(最高経営責任者)の収入が、03年には実に185倍にまで拡大しています。貧困層も増加しています。04年の調査では、貧困層(「貧困ライン」=家族3人で年収1万4,680ドル=以下で生活している人)は前年より100万人増えて3,700万人に達しています。サプライサイド改革は一握りの「勝ち組み」と多数の「負け組み」をつくります。中産階級が没落し、貧困層が拡大しているのです。皮肉にも、サプライサイド改革はアメリカの製造業をほとんど壊滅させてしまいました。60年代にはアメリカの雇用に占める製造業の比率は30%程度でした。それが現在は10%以下に低下しています。GMまでが苦境に立たされています。この事実をみても、製造業を強みとする日本に、アメリカ・モデルを当てはめようとするのは無理があることがわかります。
日本は、アメリカ・モデルではなく、日本の伝統と強さを活かした日本・モデルを開発すべきです。アメリカ型グローバリズムは日本経済だけでなく世界を破壊に導きます。外資はお金を求めて世界を移動します。日本でうまみがなくなれば、彼らは日本を捨てて次の場所に移って行きます。すでに多くの外資系金融機関がアジアの拠点を東京から香港・シンガポールに移しています。しかし、わたしたちは日本を据てるわけにはいきません。アメリカや外資のためではない、私たち日本人の生活を豊かにする改革が求められています。
(ひらかわ ひろかず・評論家)
|