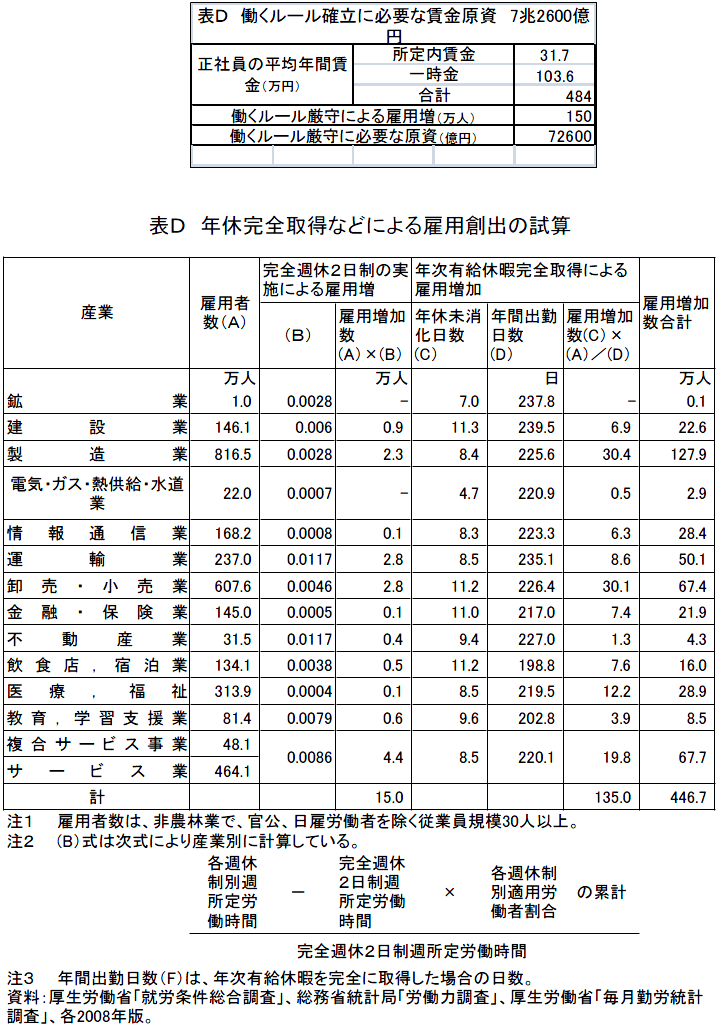経済危機打開のための緊急提言
内部留保を労働者と社会に還元し、内需の拡大を!(概要)
労働運動総合研究所(労働総研)
代表理事 牧野富夫
労働総研は、この度、「日本経済の危機打開のための緊急提言」をまとめた。
日本経済はいま深刻な危機に直面している。この危機を打開するためには、日本経済の仕組みを外需・輸出依存型から内需・国民生活充実型に転換させることが急務である。提言では、企業が膨大にため込んでいる内部留保を労働者と社会に還元することが、現下の日本経済の危機を打開するうえで、待ったなしの課題となっていることを明らかにした。
われわれは、今回の提言にあたって、この10年間にため込んだ内部留保218.7兆円を、労働者と社会に配分した場合の経済効果について、(1)最低賃金の引き上げ、(2)非正規雇用者の正規化と働くルールの確立、(3)税、NGO等への寄付などによる社会還元、(4)生産、環境設備などへの投資、(5)全労働者の賃上げ等による労働条件の改善という5つのケースを想定し、産業連関分析の手法を用いて分析した。
【試算結果】
国内需要が263.0兆円拡大し、それによって国内生産が435.5兆円、付加価値(≒GDP)が238.8兆円誘発され、それに伴って、国税・地方税合わせて42.4兆円の増収となる。その具体的内容は以下の通り。
(1)最低賃金の引き上げ 最低賃金を「時給1000円」に引き上げることによって、国内需要が5.8兆円拡大し、それによって、国内生産が13.4兆円、付加価値(≒GDP)が7.3兆円誘発される。それに伴い、国税および地方税が、合わせて1.3兆円の増収となる。
(2)非正規雇用者の正規化と働くルールの確立 働くルールの確立(サービス残業根絶、有給休暇の完全取得および週休2日制の完全実施)によって、266.5万人の新規雇用が必要になる。その雇用増によって、家計消費需要が13.4兆円拡大し、国内生産が21.8兆円、付加価値(≒GDP)が11.1兆円誘発され、税金が、国・地方合わせて2.0兆円の増収となる。そのために必要な資金は、12.9兆円である。
非正規の正規化では、派遣53.4万人、有期契約310万人を正規化するために、7.7兆円の資金が必要である。その賃上げ効果によって、国内需要が8.7兆円拡大し、国内生産が14.3兆円、付加価値(≒GDP)が7.0兆円誘発され、税金が、国・地方合わせて1.24兆円の増収となる。
(3)税、NGO等への寄付などによる社会還元 国内需要が32.2兆円拡大し、国内生産が55.5兆円、付加価値(≒GDP)が29.4兆円誘発され、国税、地方税合わせて5.2兆円の増収となることが分かった。
(4)生産、環境設備などへの投資 内部留保増分の30%である65.6兆円の投資によって、2次的な消費需要を加えて93.5兆円の国内需要が発生し、国内生産が149.4兆円、付加価値(≒GDP)が79.2兆円誘発され、国税・地方税合わせて14.1兆円の増収となる。
(5)全労働者の賃上げ等による労働条件の改善 この10年間に低下した「現金給与総額」は、月、1人あたり3万5151円になる。これを元の水準に戻すことを前提に試算すると、33.0兆円/年が必要になる。その実施によって国内需要が35.0兆円拡大し、国内生産は53.7兆円、付加価値(≒GDP)は30.7兆円誘発され、国・地方税合わせて5.5兆円の増収となる。
【労働総研の主張】
今回の提言にあたって、われわれは、財務省「法人企業統計」にもとづいて、内部留保の歴史的分析をおこなった。そのなかで、昨年来の深刻な不況にもかかわらず、日本企業が内部留保を増やしていること、また、内部留保の急膨張が始まったのは1999年度以降のことであることが明らかになった。それまで209.9兆円だった内部留保は、その後の10年間で倍以上の428.7兆円にも急膨張している。1999年度以降積み上がった218.7兆円は、賃金の切り下げや非正規労働者の解雇など労働者の犠牲と、下請単価切り下げなどによる中小企業への犠牲転嫁の上に、国内需要に転化することなく積みあがったものであり、到底正当化できるものではない。こうした内部留保の過剰なため込みが、国際的にみても著しく落ち込みが激しい日本経済の危機の原因となっている。内部留保を労働者と社会に還元し、内需を拡大することは急務となっている。労働組合がこのたたかいの先頭に立つことが期待される。
経済危機打開のための緊急提言
内部留保を労働者と社会に還元し、内需の拡大を!
2009年11月18日
労働運動総合研究所
代表理事 牧野富夫
研究員 木地孝之
常任理事 藤田 宏
はじめに――経済危機下でも増大した内部留保の異常
2008年9月、米証券4位リーマン・ブラザーズの経営破綻を機に世界経済は恐慌状態に陥り、先進資本主義国の経済成長率が軒並みマイナスに転化した(表1)。日本のGDP(国内総生産)も、前年同期に比べて、2008年10~12月期▲3.9%、2009年1~3月期▲7.4%、4~6月期▲6.9%と大幅に低下した。
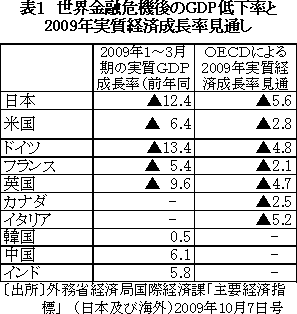
ところが、財務省「法人企業統計」によると、同時期の法人企業(277万4434社、全産業、全規模、金融・保険業を除く)の売上高も、▲11.6%、▲20.4%、▲17.0%とGDP以上に低下し、経常利益にいたっては、▲64.1%、▲69.0%、▲53.0%と半分以下に激減しているにもかかわらず、内部留保は、+1.7%、▲0.6%、+1.4%と、増加が続いているのである(表2)。
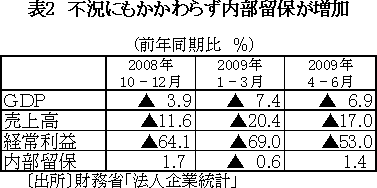
| 「法人企業統計」・・・資本金10億円以上の企業は全数調査。資本金10億円未満の企業は層化抽出調査し、サンプル理論に基づいて全企業を推計。 |
内部留保は、企業の生産活動によって新たに付け加えられた価値(「付加価値」≒GDP)の一部が、企業内部に滞留することを意味し、過度の増加は、国内需要の不足をひき起こして経済を不況に陥れることになる。
| 内部留保・・・利益のうち,配当や役員賞与などで流出せずに,企業内部に留保した部分の累計額。貸借対照表では利益準備金,任意積立金および未処分利益の合計額(有斐閣「経済辞典」)であるが、倒産引当金、退職給与引当金、資本準備金なども、生産された価値が企業内部に滞留する点では同じなので、本分析は、それらを加えた広義の内部留保により行っている。 |
今回の経済危機について、自民党や財界の幹部は、「アメリカ発の世界同時不況」と、あたかも天災ででもあるかのような言い方をしているが、自公政権の「新自由主義的」経済政策と大企業の近視眼的な利益追求主義の経営によって、内需が縮小し、外需に対する依存度が高まっていたことが根本的な原因の一つである。だからこそ、他の国以上に日本経済の落ち込みが大きく、回復も遅れているのである。
それを表すのが、今回の分析で明らかになった内部留保の異常な増加である。昨年来、経済危機の下にもかかわらず積み増しされてきた内部留保は、「派遣切り」「非正規切り」、さらには、正社員に対する希望退職などの、首切り・リストラをおこなうなかでため込んだものであり、そのような経営が、日本経済を、雇用の減少→賃金低下→内需縮小→国内生産縮小→雇用の減少という“負の悪循環”に追い込み、経済の落ち込みを加速している。
日本経済の“負の悪循環”を打開し、内需拡大→国内生産増加→雇用の増加→賃金収入の増加→内需拡大という“プラスの循環”に変えるためには、内部留保の過度のため込みをやめ、利益を労働者と社会に還元して、需要と供給のバランスを回復しなければならない。
いま、そのための適切な政策と、大企業にたいして、その実現を迫る強力な労働組合の運動が求められている。
1 日本経済の急激な落ち込みと内部留保
今回の大不況以後、今までに最も落ち込みが大きかった2009年1~3月期について、各国の実質成長率(前年同期比)を比較すると、日本は▲12.4%で、ドイツと並んで、落ち込みの大きさが際立っている。さらに、OECD(経済協力開発機構)の2009年実質経済成長率見通しによると、日本は▲5.6%で、先進7ヵ国中最も低い。(前掲した表1)
なぜ、日本経済の落ち込みがこれほどまでに大きいのか。私たちは、その原因は、大きくいって3つあると考えている。
第1は、1996年の橋本内閣による「日本版ビッグ・バン」(金融の市場開放)に始まり、2001~2005年の小泉内閣で頂点に達した「市場原理主義」的な経済政策の下で、政治・経済の両面においてアメリカの影響力が強まり、日本の金融機関や大企業がアメリカのヘッジファンドや銀行と連携し、国内外で積極的に投機活動に乗り出すようになった。アメリカ金融危機が日本にとりわけひどい激震をもたらすようになったのは当然であった。
第2は、第1とも関係するが、日本経済の体質が、アメリカを中心とした外需依存型の構造になっていることである。日本の直接的な対米輸出比率は、2000年の29.7%から2008年には17.5%まで低下しているが、ASEANや中国に進出した現地企業も対米輸出比率が高く、それらの関連産業の生産も加えると、日本の対米依存度は、むしろ上昇している。そのため、米国発世界同時不況の直撃に加えて、進出先の国々からの“副震”を大きく受けることになったのである。
第3は、日本企業が、異常な内部留保の増大に示される、近視眼的な経営を行ってきたことである。経済は、生産活動によって新たに付加された価値が、賃金、株主配当、税金などに配分され、それが家計消費、政府消費、設備投資などの国内需要に転化して、再び国内生産を誘発することにより、循環していく。ところが、1998年から2008年の間に、企業の内部留保として218.7兆円も溜め込まれ、それが、国内需要に十分転化されていないのである。その結果、わが国経済は、大幅な需要不足が慢性化し、成長できないどころか、正常な循環すら困難になっている(2008年の国内総支出は507.6兆円であり、この間の内部留保増加額は、実にその41.4%に相当する)。他の先進資本主義国と比較してより深刻な日本の不況は、このような日本企業の行動が自ら招いたものということが出来る。
最近の大企業経営者は、コップの中(自社の経営)だけを見て、それがおかれた状態(経済全体)を見ている人が少ない。一方、大企業の労働組合は、企業の率先した派遣労働者切りに目をつむり、リストラがあっても賃下げになってもたたかおうとしない。そればかりか、「労働者派遣法」の改正に企業と一緒になって反対している労組もある。このような状況の下で、とりわけ雇用者への価値の再配分(付加価値全体の53.9%を占める)が十分に行われず、内需の鍵である家計消費需要の拡大(国内最終需要全体の54.7%を占める)が出来ていないのである。
2 99年度以降、急膨張した内部留保
私たちは、内部留保を、直ちに「悪い」と言っているのではない。企業経営上、また、経済社会の安定のために資本準備金や貸倒引当金などは当然必要であるし、企業が安定的経営や拡大再生産のために積立金を確保しようとするのも十分理解できる。しかし、1999年度以降積み上がった218.7兆円は、賃金の切り下げや非正規労働者の解雇など労働者の犠牲と、下請単価切り下げなどによる中小企業への犠牲転嫁の上に、国内需要に転化することなく積みあがったものであり、到底正当化できるものではない。
今回、我々は、このような内部留保の急速な蓄積がいつごろから始まったのかを調べ、もし“適正な内部留保の水準”があるとしたら、過去の経験からどのくらいと言えるか、また、もし、この間、大企業が、利益を適切に労働者や社会に還元・配分していたら、何が可能だったのかを分析してみた。
内部留保が急増したのは1999年度以降であり、奇しくも「労働者派遣法」が改悪された時期と一致する(図1)。それ以前も、内部留保の増加率は、売上高より高かったが、従業員給与も上昇していた。しかし、1999年度以降は、売上高も従業員給与も低下する中で、内部留保のみが急増しているのであり、到底、妥当な経営の姿とは言えない。
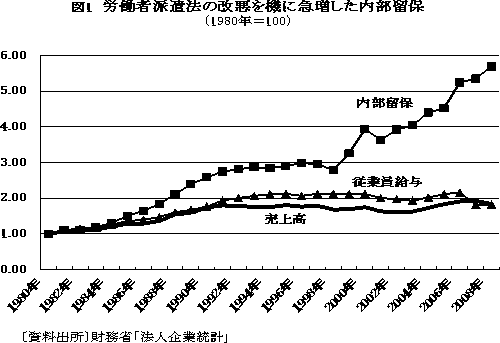
それでは、“妥当な内部留保”とは何だろうか。もし、内部留保に“妥当な水準”があるとしたら、それは、どのくらいだろうか。財務省「法人企業統計」から計算した、企業の売上高に対する内部留保の水準をメルク・マールとして探ってみた。
「法人企業統計」によると、売上高に対する内部留保の水準は、1970年頃の高度経済成長期には5%前後であったが、日本経済の不安定化に伴って徐々に上昇し、第2次石油危機から円高へと続いた1980~86年度には、平均10.1%になった。その後のバブル景気(1987~90年度)の時期は13.1%、バブル後の長期不況“失われた10年”(1991~2001年度)の時期は、平均16.1%であった。それが、いざなみ景気(正式名称は未定。2002~2007年)の時期に、23.7%に急上昇したのである。(表3)
年次別に見ると、内部留保が急増したのは1999年度以降である。その後、2008年度までの10年間に、209.9兆円から428.6兆円へ、218.7兆円増と、2倍以上に膨張した。売上高に対する水準も、15.2%から28.4%へ、13.2ポイントも上昇している。
内部留保を種類別に見ると、この間の増加額が大きかったのは、「繰越利益剰余金」、「積立金」、「資本準備金」および「その他資本剰余金」の順であり、“狭義の内部留保”が全体の68.0%を占める。(表4)
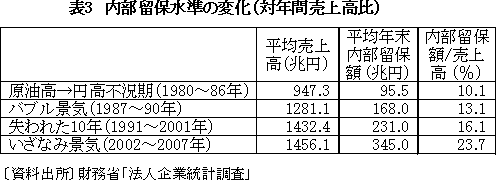
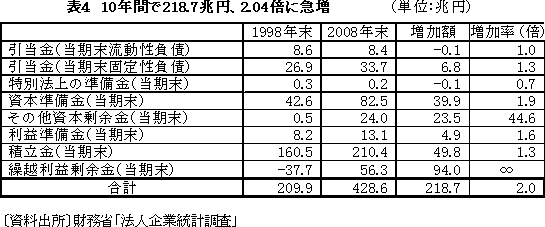
長期不況期に、“倒産や経営危機に備えるため”といって、内部留保をため込んだ大企業は、その後、バブル期を上回る収益を上げてもそれをやめようとせず、逆に、さらに労働者や下請中小企業に犠牲転嫁を強いて、内部留保を拡大してきたのである。
本分析では、かなり甘いかも知れないが、急増前の水準である1998年度の対売上高比、15.2%、209.92 兆円を内部留保の“妥当な範囲”と仮定し、それを基準に以下の分析を進めることにした。
3 労働者と社会に還元し、内需の拡大を
(1) 内部留保の還元に関する一考察
私たちは、もし、1999年度以降、溜めすぎた内部留保を、労働者と社会に配分した場合の経済効果について、
(1) 最低賃金の引き上げ
(2) 非正規雇用者の正規化と働くルールの確立
(3) 税、NGO等への寄付などによる社会還元
(4) 生産、環境設備などへの投資
(5) 全労働者の賃上げ等による労働条件の改善
という5つのケースを想定し、産業連関分析の手法を用いて分析した。(表5)
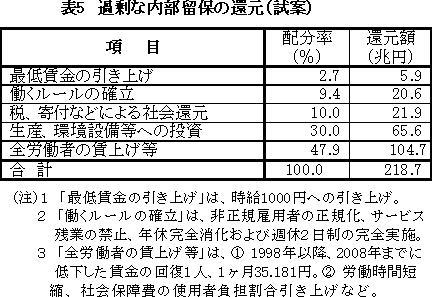
(1)最低賃金の「時給1000円」への引き上げ
日本の最低賃金は47都道府県ごとに決定され、全国平均額は713円である。世界の多くの国では、全国一律の制度として設定されており、フランスやイギリスなどは1100~1300円という水準である。最低賃金を1000円に引き上げることは、ワーキング・プアなど、働く貧困を解消するための急務であり、直ちに実施すべきである。そのために必要な資金は5.9兆円で、1998~2008年度の間に増加した内部留保、218.7兆円の2.7%にすぎない。
(2)非正規雇用者の正規化と働くルールの確立
《非正規の正規化》
昨年来の「派遣切り」、「非正規切り」によって職場を追われ、職を失った労働者は、厚生労働省の控えめな推計によっても24.4万人にものぼる。「派遣切り」、「非正規切り」の実態は、派遣労働者や有期契約労働者が、無権利で低賃金の「使い捨て労働者」として企業に活用されている実態を浮き彫りにするものとなった。「非正規切り」の先頭に立ってきた自動車メーカーでは、生産調整が終わり、増産体制に入ると、再び、短期の「使い捨て」を前提にした非正規雇用の再開の動きが広がっている。こうした企業の都合次第で「使い捨て」にできる雇用をやめさせ、「安定した雇用」を実現することは広範な労働者の切実な要求となっている。「雇用は正社員が当たり前」という社会を実現する必要がある。そのために必要な資金は7.7兆円であり、内部留保増加分の3.5%に過ぎない。
《働くルールの確立》
| i) | サービス残業の根絶・・・労働基準法違反の犯罪行為であるサービス・不払い残業が大手を振ってまかり通っている。不況のもとで、操業短縮や一時帰休などの生産調整が進んだにもかかわらず、サービス残業は依然として根絶されていない。2008年度の労働基準監督署の監督指導による割増賃金の是正状況(100万円以上)をみると、是正指導を受けた企業は1553社に及び、是正支払金額は196億円に及んでいる。サービス残業の根絶は急務になっている。 そのために必要な資金は5.6兆円であり、内部留保増加分の2.6%にすぎない。 |
| ii) | 完全週休2日制の実施と年次有給休暇の完全取得・・・年次有給休暇の完全取得について、異論をはさむ人はいないだろう。あまりにも当たり前の要求である。日本の年次有給休暇の取得状況をみると、取得日数8.8日、取得率48.1%という低い水準であるが、フランスの取得日数は36日、ドイツは21日である。日本の年休取得はフランスの24%、ドイツの42%という低水準である。日本の低い年休取得の水準をEU諸国に近づけるためには、年休の完全取得を義務化することが必要である。完全週休2日制の実施と年次有給休暇の完全取得に必要な原資は7.3兆円であり、内部留保増加分の3.3%にすぎない。 |
(3)税・NGO等への寄付などによる社会還元
企業に対する税金(ここでは、「法人企業税(国税)」は、1989年頃約40%であったが、消費税増税をよそに、1999年以降30.0%に低下した。それだけ企業の社会的貢献が小さくなったのであり、これを元に戻す必要がある。また、他の先進国の企業に比べて貧しすぎるNGOやNPOへの寄付を大幅に増やし、企業の社会的責任を果たさせる必要がある。そのために、ここでは、内部留保増加分の10%、21.9兆円を用意する。
(4)生産および環境設備投資
内需が拡大し、需給が回復すれば、当然、新たな設備投資が必要になる。また、地球温暖化等に対応するためには、もっと環境投資を拡大しなければならない。そのための資金として、内部留保増加分の30%、65.6兆円を用意する。
(5)全労働者の賃上げ等
以上、4つのケースに必要な資金は、114兆円であり、内部留保増分の52.1%、約2分の1にすぎない。残りの104.7兆円を全労働者の賃上げなどに振り向けるなら、次のことが可能になる。
まず、賃上げである。厚生労働省「毎月勤労統計調査」によれば、労働者の賃金総額は、1998年の36万6481円から、2008年の33万1300円へと、10年間に、3万5181円も減少している。これをとりあえず1998年水準にもどすことは、内部留保急増が示す日本経済の不均衡を正すことであり、国内需要、とりわけ家計消費需要の回復のために決定的に重要である。そのために必要な資金は、33兆円であり、内部留保増分の15.1%と見込まれる。
さらに、残りの71.7兆円分を労働者に配分すれば、労働時間短縮、長期休暇制度、社会保障費の使用者負担引き上げなどにより、ワーク・ライフ・バランスを欧米先進国水準に近づけることも可能になる。
(2) 内部留保を労働者と社会に還元した場合の経済効果
我々の試算では、1998年度~2008年度の間に積み上がった内部留保を労働者と社会に還元すれば、トータルとして、国内需要が264.8兆円拡大し、それによって国内生産が424.7兆円、付加価値(≒GDP)が231.3兆円誘発され、それに伴って、国税・地方税合わせて41.1兆円の増収となる。
つまり、この間、目先の利益を追って内部留保の拡大に走るのではなく、表5のような内容で利益を労働者・社会に適正に配分していれば、これだけの経済効果が発生し、現在のような不況には陥らなかったと思われる(表6)
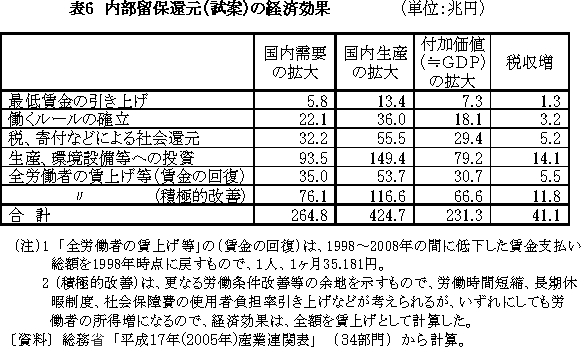
なお、ここでは、総務省公表の「平成17年(2005年)産業連関表」(34部門表)、および、経済産業省作成の「平成18年延長産業連関表」(当研究所が家計消費分析用に組み替えた45部門表)を利用した産業連関分析を行っている。各項目の試算内容等については、別記「【参考】試算の具体的内容」を参照されたい。
|
産業連関分析・・・ある製品に対する需要増は、まず、その製品を生産している企業の生産を拡大するが、それだけにとどまるのではない。例えば、自動車に対する需要増は、まず、自動車産業の生産を拡大するが、次の段階では、その生産に必要な原材料やサービスの購入を通じて、様々な企業の生産を拡大する(自動車の生産→タイヤの生産→合成ゴムの生産→エチレンの生産→ナフサの生産→原油の輸入といった具合である)。 |
|
産業連関分析は、ある需要(例えば、収入増に伴う消費需要)の増加が、究極的に見て、国内のどの産業の生産を、どれだけ拡大するかを計測するものである。 |
*最低賃金引き上げの経済効果
最低賃金を「時給1000円」に引き上げることによって、国内需要が5.8兆円拡大し、それによって、国内生産が13.4兆円、付加価値(≒GDP)が7.3兆円誘発される。それに伴い、国税および地方税が、合わせて1.3兆円の増収となる。(表6)
労働総研と全労連、首都圏の労働組合が行った「首都圏最低生計費試算報告」によれば、必要な最低生計費は年間280万円である。最低賃金を時給1000円に引き上げても、現在それを下回っている労働者の賃金が、一般労働者で年間249万円、パート労働者の場合は、年間114万円になるだけであり、一般労働者でも自分一人のギリギリの生活が保障されるだけである。パートの場合には、「最低の生計費」に遠く及ばない。(表7)
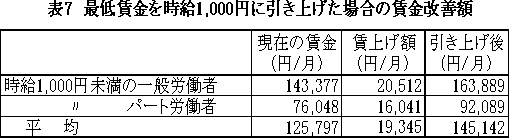
最低賃金引き上げの対象となる労働者は、総務省「家計調査」の「年間収入十分位階級別1世帯当たり1か月間の収入と支出」で最も低い「第1分位」(年収250万円以下)に該当する。
この階層では、可処分所得の89.9%が消費されるので、同じ1万円の賃上げでも、他の階層より内需拡大効果が大きい。(ちなみに、年収900万円以上の第X分位は、64.9%である。)
また、産業連関分析により、最低賃金引き上げに伴う消費増が、どのような商品・サービスの生産を多く誘発するか調べてみると、娯楽、理美容等の「対個人サービス」、「食料・飲料・たばこ」、「運輸・通信」、紙や繊維製品等の「軽工業品」など、中小企業が多い分野の商品・サービスを誘発する。したがって、最低賃金の引き上げは、中小企業の経営に良い影響を及ぼすと考えられる。(表8)
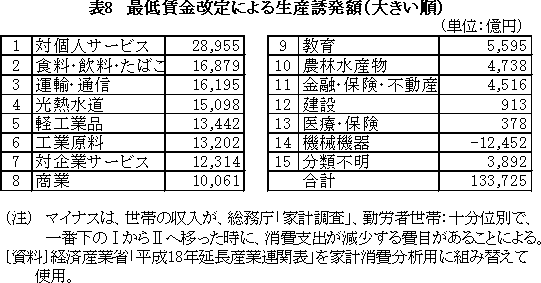
*働くルール確立の経済効果
働くルールの確立(サービス残業根絶、有給休暇の完全取得および週休2日制の完全実施)によって、266.5万人の新規雇用が必要になる。その雇用増によって、家計消費需要が13.4兆円拡大し、国内生産が21.8兆円、付加価値(≒GDP)が11.1兆円誘発され、税金が、国・地方合わせて2.0兆円の増収となる。そのために必要な資金は、12.9兆円である。
非正規の正規化では、派遣53.4万人、有期契約310万人を正規化するために、7.7兆円の資金が必要である。その賃上げ効果によって、国内需要が8.7兆円拡大し、国内生産が14.3兆円、付加価値(≒GDP)が7.0兆円誘発され、税金が、国・地方合わせて1.24兆円の増収となる。
*税・寄付など社会還元の経済効果
まず、消費税を引き上げる一方で、1989年の40%から2008年の30%まで引き下げられた法人税(国税分)を元に戻し、加えて、NGOやNPO、学術研究機関等に対する寄付を非課税として、企業に欧米並みの社会貢献を促すことを求めたい。
ここでは、NGO等の活動は政府の活動に似ていると仮定し、全体を、2005年産業連関表の政府消費と公共投資の比率である79.3%対20.7%に分けて、それぞれの生産誘発効果を計測した。その結果、国内需要が32.2兆円拡大し、国内生産が55.5兆円、付加価値(≒GDP)が29.4兆円誘発され、国税、地方税合わせて5.2兆円の増収となることが分かった。
ただし、この計算には、法人税引き上げによる直接的な増収が含まれていない。2009年度補正予算の法人税は10.54兆円だから、現行の法人税30%を40%に引き上げたとすると、3.5兆円の増収となり、税の増収額は、合計8.7兆円になる。
*生産設備および環境投資の経済効果
設備投資は、1単位の需要によって誘発される国内生産額が、国内最終需要の中で最も大きい。したがって、本格的な景気回復には欠かせない需要項目であるが、生産設備に対する投資は、将来の需要拡大が見込まれない限り行われない。これに対して、技術革新や環境のための投資は、いつ行っても良い投資である。これらの投資が行われれば、国内需要が拡大し、国内生産を誘発するから、自立的な景気回復の大きな力になる。そして、次の段階では、生産の拡大を伴う新たな設備投資も必要になるはずである。
今回の試算から投資の生産誘発力を観測すると、内部留保増分の30%である65.6兆円の投資によって、2次的な消費需要を加えて93.5兆円の国内需要が発生し、国内生産が149.4兆円、付加価値(≒GDP)が79.2兆円誘発され、国税・地方税合わせて14.1兆円の増収となる。
*全労働者の賃上げ等の経済効果
まず、内部留保の急増が始まった1998年度から2008年度までの10年間に低下した「現金給与総額」を、元の水準に戻さなければならない。その額は、従業員5人以上の事業所、一般・パート合計でみて、1998年が36万6481円、2008年は33万1330円だから、月、1人あたり3万5151円になる。5524万人の雇用者全員では、ボーナスを年間5ヶ月分として、33.0兆円/年が必要になる。その実施によって国内需要が35.0兆円拡大し、国内生産は53.7兆円、付加価値(≒GDP)は30.7兆円誘発され、国・地方税合わせて5.5兆円の増収となる。
以上に必要な資金は147兆円であり、全てを実行しても、1998~2008年度に積み上がった内部留保の増加分が、まだ71.7兆円も残っている。もし、それを、全労働者の賃上げや労働時間短縮、長期休暇制度、社会保障費の使用者負担率引き上げ等、欧米先進国並を目指す積極的な労働条件改善に使用するなら、国内需要が、さらに76.1兆円拡大し。国内生産が116.6兆円、付加価値(≒GDP)が66.6兆円誘発され、国税、地方税合わせて11.8兆円の増収となる。
なお、「税・寄付などによる社会還元」以降の生産誘発効果は、総務庁「平成17年(2005年)産業連関表」(34部門表)から数学的処理によって導き出された、「生産誘発係数」(ある需要が1単位増加したとき、各産業の国内生産額はどれだけ誘発されるかを表す係数により、計算している。
4 まとめ――一刻の猶予も許されない、待ったなしの課題
(1) 我々は、内部留保の蓄積自体を“悪”と言っているのではない。また、蓄積された内部留保を直ちに全て取り崩せと言っているのでもない。1999年度以降の内部留保急増は異常であり、妥当性を欠き、国内経済の需給バランスを崩しており、それが、今回不況を他の国以上に深刻なものにしているのだから、極力、その改善に努め、また、これまでの経営を改めて、利益を労働者と社会に的確に還元・配分し、内需の拡大を図るべきであると主張しているのである。
(2) 現実に崩れてしまっている国内需給のバランスを回復するには、急増した内部留保に見合った内需の拡大が必要であり、当面、以下の事項程度は、直ちに実施すべきである。
最低賃金を時給1000円に引き上げ、非正規雇用を正規雇用に代えることは、労働者に健康で文化的な最低限の生活を保障することである。また、サービス残業の禁止、週休2日制の完全実施、年次有給休暇の完全取得は、先進国の常識であり、当然、既に実現されていなければならない事項である。これらを実施しても、必要資金は26.5兆円であり、1998~2008年度の内部留保増分218.7兆円の12.1%にすぎない。
次に、労働者の賃金を、少なくとも1998年度時点に戻すべきである。ボーナスを年間5か月分として、労働者1人あたり、1月3万5151円の賃上げが必要であり、そのための資金は、33.0兆円、内部留保増分の15.1%である。
(3) 今回の試算は、もし、我々が提案したような経営が行われていれば、景気だけではなく国の財政も、現在のように深刻な状況にはならなかったことを、実証的に示したものである。
試算で示した、国内需要263.0兆円の拡大効果は、今回の分析で使用した経済産業省の「平成18年(2006年)延長産業連関表」をベースに計算すると、国内需要総額505.7兆円の、52.0%に相当する。
それによって誘発される付加価値(≒GDP)238.8兆円は、同産業連関表の付加価値505.2兆円の47.3%に相当する。これを1年あたりに直すと23.9兆円になり、1998年のGDPは504.9兆円だから、毎年約3.7%の経済成長率が上積みされることになる。
税収は、国、地方合わせて42.4兆円の増収であるが、これに、「税・寄付など社会還元の経済効果」で説明した法人税の増税分3.5兆円を加えると45.9兆円になり、2009年度補正予算の公債発行額44.1兆円を全額賄ってもおつりが来る。
(4) ただし、今回の試算で仮定した5項目を今後も継続するとすれば、生産コストの増大による一定の物価上昇は避けられない。その率は、毎年2%程度と予想される。
その分賃金が上昇すれば労働者の生活に影響はないが、経団連・財界は、それをもって「国際競争力の低下」を主張するかもしれない。しかし、現在の最も一般的な経済学の教科書によれば、A国とB国の物価上昇率の差は、為替レートによって調整されるのであり、国全体としてみれば、競争力は変らない。ただ、平均以上に価格が上昇した品目は輸出が困難になり、輸入品に取って代わられる一方、平均より価格上昇率が小さかった品目は、それまでより輸出が容易になる。
(5) また、「大企業はとにかく中小企業は無理」との主張が予想されるが、内部留保を溜め込んだのは大企業であり、1998年度~2008年度の増加分の69.3%は、1億円以上の企業に滞留している。中小企業の経営が苦しいのは、大企業の買い叩き、無慈悲なプライス・ダウン要求を受け、経営者自身、生活できる収入を確保できていないからであり、労働者と力を合わせて、大企業に経営の転換を迫るべきである。
また、「内部留保は過去の利益の蓄積であり、設備等に変っているから取り崩すことは出来ない」という主張がある。しかし、ここでは“適正な内部留保の水準”という考え方を示し、対象を1999年度以後急増した内部留保に限定し、しかも、「それを直ちに全部取り崩せ」とは言っていない。決して不可能ではないはずであるである。
なお、「法人企業統計」によって企業の保有資産を見ると、2008年度末の時点で、現金・預金だけで143.1兆円もあり、公社債や利殖目的の有価証券、ゴルフ会員権なども抱えている。
(6) 最近の大企業は、本業より利益の“運用”に力を注いでいるように見える。その一部が、証券会社等を通じてアメリカの投資会社やヘッジ・ファンドに流れているとしたら、日本経済を困難に陥れている円高や原油価格上昇の原因を、自ら作っていることになる。
(7) 企業とは、(1)生産を拡大し、(2)利益を上げて、(3)雇用者を増やし、(4)労働者には十分な賃金を、株主には十分な配当を支払って一国経済の基礎単位である家計を維持・拡大し、さらに、(5)税金を支払って国家財政を支え、(6)地域・社会等にも利益を還元するという、社会的責任を持った存在である。
ソニーの会長だった故・盛田昭夫氏は、「競争」と「効率」に走る「日本的経営」のあり方を批判し、少ない従業員への配分、低い株主配当、一方的下請単価切り下げなど取り引き先にたいする横暴、地域社会や環境への配慮の欠如などの問題点を指摘し、その変革の重要性を強調した。そして、「日本企業の経営理念の根本的な変革は、一部の企業のみの対応で解決される問題ではなく、日本の経済・社会のシステム全体を変えていくことによって、初めてその実現が可能になる」(『文藝春秋』1992年2月号「『日本型経営』が危ない」)と述べた。
私たちは、今が「競争」と「効率」に走り、労働者や中小企業にすべての犠牲を押しつける「日本型経営」の「根本的変革」にのりだす時期であり、企業がみずからの社会的責任を果たす「経済・社会のシステム」をつくりあげることがとりわけ重要になっていると考える。景気が悪いからと言って先延ばしは許されない。景気が悪いからこそ、速やかに実行すべきである。
(8) 労働組合は、組合員の生活向上が第1の目的であるが、生産活動によって生み出された価値を適正に配分させ、内需に転化して拡大再生産につなげる社会的任務を持っている。さらに、現在の情勢の下では、自らが所属する企業の派遣切りや下請けいじめ、生産コストに見合わない安売りや安易な海外移転などを監視することが重要となっている。今春闘が、そのたたかいの第1歩となることを期待したい。
【参考】試算の具体的内容
*最低賃金の「時給1000円」への引き上げ(表A)
《試算方法》
(1)時間当たり賃金の分布データは、厚労省 「平成19年版賃金構造基本統計調査報告」によって、10円刻みの「時給」と「該当人数」の表から、1000円未満の人数をカウントした。
(2)「時給1000円」未満労働者は、一般労働者、パート労働者それぞれについて計算した。調査された一般1051.4万人(内、時給1000円未満313.8万人)、パート602.1万人(同437.5万人)を、「毎勤統計」の5人以上の一般・パート比率を利用して全労働者(5524万人)に換算した。
《試算結果》
最低賃金を時給1000円に引き上げることによって、一般の労働者(そのうち時給1000円未満の労働者)の賃金は、平均12万9797円/月から14万9142円/月に、1万9345円/月引き上げられる。なお、厚生労働省の「毎勤統計」(2008年)にもとづき、1月の出勤日数20.4日、1日の労働時間8時間18分、年間労働時間2031.6時間、ボーナス年間3.2ヶ月分として月額を計算した。
パート労働者(そのうち時給1000円未満の労働者)の場合は、賃金が、平均7万6048円/月から9万2089円/月へ1万6041円/月引き上げられる。なお、同じ厚生労働省の「毎勤統計」(2008年)にもとづき、出勤日数16.2日、1日の労働時間5時間42分、年間労働時間1111.2時間、ボーナスは、年間0.38ヶ月分として計算した。
(2)最賃を1000円に引き上げた場合の生産波及効果は、1次、2次あわせて国内生産を13兆3700億円拡大させることになる。これに必要な原資は5.87兆円である。
最低賃金に該当する人は、時給1000円になっても、総務省の「家計調査」、「年間収入十分位階級別1世帯当たり1か月間の収入と支出」の第1分位「世帯主の収入258万円未満」から抜け出せない。この分位では、収入の98.8%が家計消費に回り、(消費支出/世帯主の収入。消費支出/可処分所得では89.9%)賃金引上げによる内需拡大効果が大きい。
そして、「家計調査」から、収入増の結果どのような費目に対する支出が増えるかを調べ、次に、産業連関分析によって、究極的な各産業に対する生産誘発額を計算してみると、対個人サービス、食料・飲料・たばこ、運輸・通信、光熱水道、軽工業品など、比較的中小企業の多い分野の生産活動をよく誘発する。したがって、最低賃金の引き上げは、中小企業の経営にプラスの効果がある。
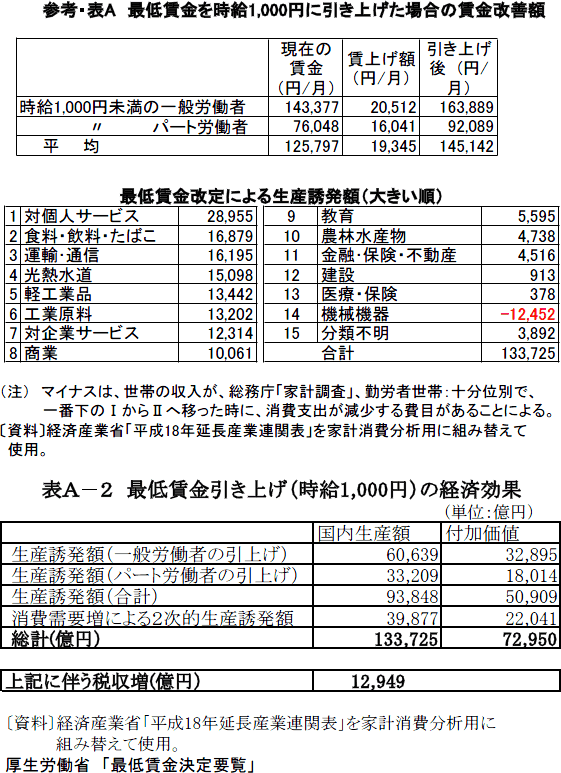
*サービス残業の根絶(表B)
《試算方法》
(1)サービス残業時間の算出については、事業所調査である厚生労働省「毎月勤労統計調査」と世帯対象の個人調査である総務省「労働力調査」との差を根拠にした。「毎勤統計」によれば、一般労働者の年間総労働時間は2017時間だが、「労働力調査」では2133時間となっており。その差115時間が労働者一人当たりの年間サービス残業時間となる。
(2)労働者一人当たりサービス労働時間を労働者数に乗じてサービス残業総労働時間を計算し、これを一般労働者の年間労働時間で除して雇用者増加数を算出した。その際、労働者数については、「毎勤統計」の事業所規模30人以上に働く2035.9万人に限定して計算し、雇用者増加数の計算に当たっても、30人以上に働く一般労働者の年間労働時間数を用いた。
《試算結果》
非常に控えめな試算だが、それでも新たに116.5万人の雇用が創出されることになる。そのために必要な賃金原資は5兆6000億円である。
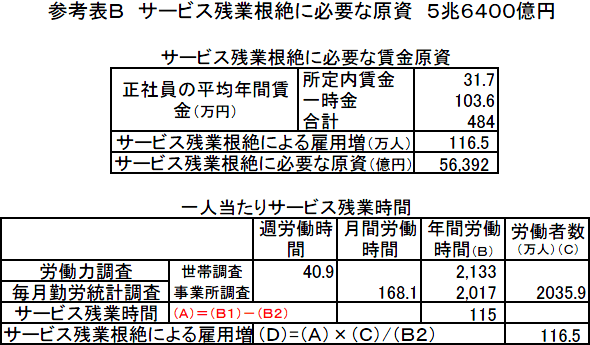
*非正規雇用者全員の正規雇用化(表C)
《試算方法》
(1)非正規の正社員化については、派遣労働者と有期契約労働者の2つに分けて対象人数を決めた。派遣労働者は、総務省「就業構造基本調査」(2007年)にもとづき160.7万人とし、そのうち33.2%を正規社員化する対象とした。厚生労働省「労働力需給についてのアンケート調査」によれば、「派遣労働者が派遣という働き方を選択する理由」として、「正社員として働きたいが、就職先が見つからなかったため」派遣労働者が32.2%にのぼっているからである。
有期契約労働者の正規化の人数は310万人とした。厚生労働省「有期契約労働者の雇用管理の改善に関する研究会報告」(2008年7月)で、「1週間の所定内労働時間が通常の労働者と同一な有期契約労働者が310万人に上る」としていることから、そのデータを採用することにした。
(2)賃金増加分については、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」にもとづいて、「正社員・正職員計」(年間賃金万円)と「正社員・正職員以外計」(同万円)の賃金の差額分を賃金増加分とした。その際、派遣労働者については、相対的に青年労働者が多いことを考慮して、25~29歳の年齢階級別賃金(「正社員・正職員計」(年間賃金万円)と「正社員・正職員以外計」(同万円))を用い、それぞれの賃金増加額に非正規から正規化した人数を乗じて賃金増加額を求めた。
(3)正規化される前と非正規のときの平均賃金を総務省「家計調査」の「年間10分位階級別」にあてはめ、消費パターンの違いからくる限界消費性向を計算し、賃金増加分がどのような消費にどれくらい支出されるかを算出。
(4)最後に、これらの消費支出の増加が日本経済にどのような波及効果をもたらすかについて「産業連関表」を用いて算出した。
《試算結果》
非正規の正規化で派遣53.4万人、有期契約310万人を正規化するために必要な原資は20.6兆円。それによって国内需要が20.4兆円拡大。国内生産を46.9兆円誘発。GDPを約25.6兆円増やす。それに伴って、国税、地方税合わせて4.5兆円の増収となる。
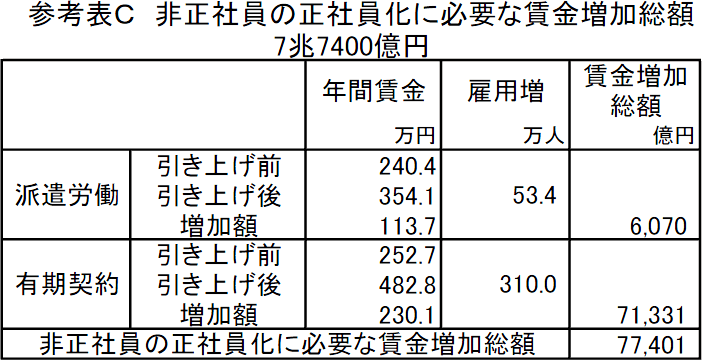
*完全週休2日制・有給休暇の完全取得(表D)
《試算方法》
(1)完全週休2日制については、厚生労働省「就労条件総合調査」にもとづき、産業別に「各週休制別週所定労働時間」から「完全週休2日制週所定労働時間」を差し引き、これに各週休制別適用労働者割合を乗じて算出しその累計を完全週休2日制週所定労働時間で除して算出。雇用増加数は15万人となる。
(2)年休の完全取得は、産業別に「就労条件総合調査」にもとづき産業別の年休未消化日数を算出し、それを「毎勤調査」による年間出勤日数で除して、年休完全取得による雇用増加数を算出した。